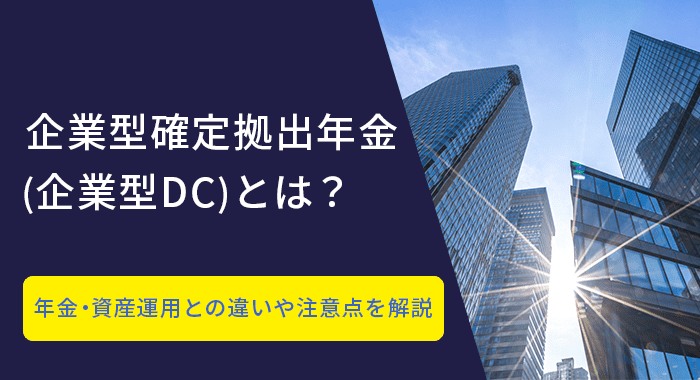企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、企業が従業員の年金口座に掛金を拠出し、従業員が運用する福利厚生と資産運用の両面を持つ制度です。
しかし、名前からどのような内容なのか想像しにくく、制度をよく理解できていない方もいるでしょう。
- 企業型確定拠出年金とは
- iDecoや厚生年金、NISAとの違い
- 企業型確定拠出年金のデメリット
企業型確定拠出年金について分かりやすく解説し、メリットや他の年金制度との違いも説明しています。
デメリットの内容や、対処方法についても確認して制度をうまく活用しましょう。
企業型確定拠出年金(企業型DC)とは福利厚生で年金を用意する制度
企業型確定拠出年金とは、企業が従業員の年金口座に掛金を拠出し、従業員が運用する福利厚生と資産運用の両面を持つ年金を用意する制度です。
あらかじめ決めておいた掛金を拠出して運用していくことで、退職金代わりとなる企業独自の年金を用意します。
企業型DCとは、確定拠出年金の英語訳「Defined Contribution Plan」をDCに略した名称です。
制度の内容は、企業型確定拠出年金と同じです。
- 企業型確定拠出年金の仕組み
- マッチング拠出制度の特徴
- 運用商品は元本保証型と元本変動型の2種類
- 企業によっては自動加入ではなく選択制のところもある
- 企業型確定拠出年金の節税効果
企業型確定拠出年金とはどのような制度なのか、マッチング拠出制度も含めて仕組みを分かりやすく解説します。
運用商品の選び方次第では、元本保証や大きな利益が得られるなど運用結果に大きな差が生まれます。
企業型確定拠出年金の最大のメリットともいえる、節税効果についても知っておきましょう。
企業型確定拠出年金は企業が掛金を払って従業員が運用
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、一定の掛金を企業が支払い(拠出)、従業員それぞれが運用する年金制度です。
運用商品は、企業が選んだ運営管理機関が取り扱う投資信託や保険商品から従業員が自分で選びます。
掛金と選んだ運用商品の運用成績により将来の年金額が決まるため、勤続年数や給与条件が同じ方でも受取金額は異なります。
掛金が支払われる期間は企業ごとに異なり、60歳から70歳までと法令で定められていることが特徴です。
掛金の運用で拠出した資産は、60歳以降に年金または一時金として受け取ることもできます。
毎月一定の金額を受け取る方法のほか、一時金としてまとめて受け取れる方法の種類があります。
企業の福利厚生を利用して、計画的に老後のための資産形成ができる点です。
マッチング拠出制度の活用で自分の給与から追加で掛金を上乗せできる
企業型確定拠出年金では、企業によっては掛金を上乗せするマッチング拠出制度が利用できるケースもあります。
マッチング拠出制度のルールは以下の2点です。
- 企業の掛金は超えられない
- 企業の掛金とマッチング拠出の合計がひと月55,000円以
※会社が企業型確定給付年金(企業型DB)も実施しているなら27,500円の範囲内
参照元:厚生労働省
制度上、企業型確定拠出年金の拠出限度額は1ヶ月55,000円を超えないことです。
限度額の範囲内、かつ企業の掛金を超えない金額の範囲内でマッチング拠出が利用できます。
マッチング拠出を行うメリットは所得控除と年金原資が増えること
マッチング拠出で掛金を上乗せすると、現在の手取り収入は減るもののメリットもあります。
- マッチング拠出分の掛金は従業員負担分は全額所得控除の対象となる
- 年金原資が増えるため運用資産を着実に増やし将来に備えられる
マッチング拠出で給与から差し引かれた分は、全額所得控除の対象です。
所得控除分は所得税や住民税の計算から除外されるので、納める税金を少なくできます。
マッチング拠出は自動的に給与から差し引かれる状態となるので、老後のための運用資産を着実に増やせる点も魅力的です。
給与天引き分の負担が重いなら、解約や返金はできないもののマッチング拠出を停止できます。
マッチング拠出が利用できるかどうかは企業により異なるため、気になる方は勤務先の担当部署に問い合わせましょう。
運用商品は元本保証型と利益を狙う元本変動型の2種類
企業型確定拠出年金の運用商品は、元本保証型と元本変動型の2種類から選択できます。
元本保証型とは、運用している元本分の金額が保証される方法です。
元本割れしないのでマイナスにはならないものの、大きな利益は得にくい傾向にあります。
元本変動型は、元本割れするリスクはありますが利益を得やすい方法です。
| タイプ | 商品の特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 元本保証型 |
|
|
| 元本変動型 |
|
|
元本保証型の特徴
元本保証型の商品は、主に1年~20年の定期預金や保険会社の積立保険が該当します。
投資に関する知識の必要性はなく、受取額が掛金より少なくなることはありません。
しかし、リスクが低い分リターンも小さいのが元本保証型の特徴です。
世の中の物価変動の影響を受けないので、受け取り時にインフレが進んでいると金額が少ないと感じる場合もあります。
元本変動型の特徴
元本変動型の代表的な運用商品は、NISAでもおなじみの投資信託です。
株式や債券など様々な金融商品がパッケージ化されており、日々価格が変動します。
元本変動型の運用商品で利益が出る仕組みは以下の通りです。
- 選んだ投資信託の運用が好調で購入時よりも基準価格が上昇する
- 運用中に発生した分配金が再投資され、運用資産が増加する
購入時よりも基準価格が上がれば、解約時に差額分の利益を上乗せして受け取れます。
例えば、10万円で買ったものを11万円で売却すれば1万円の利益が出るのと同じ仕組みです。
分配金の有無は投資信託の種類により異なり、保有数によって分配金額は異なります。
企業型確定拠出年金の投資信託で発生する分配金は、再投資にまわるのが基本です。
基準価格は必ずしも上昇するとは限らないため、様々な要因で価格が大きく下落する可能性もあります。
利益は狙えるものの、受け取る年金が掛金を下回るリスクもあり、投資の勉強や運用商品の見直しが必要です。
企業によっては自動加入と選択制の2種類ある
企業型確定拠出年金は、大きく分けると自動加入となる企業と選択できる企業の2種類に分かれます。
自動加入なら、従業員は企業型確定拠出年金に加入する選択肢しかありません。
企業からの説明や運用商品一覧の配布があるなど、指示に従って手続きを行いましょう。
選択制は、給与の一部を掛金に置き換える形であり、加入しなかった方よりも給与は減少します。
給与として今受け取るか、将来に向けて企業型確定拠出年金として拠出していくかを選びます。
給与として受け取るなら、企業が退職金を月々分割して従業員へ前払いで支払っている状態です。
資産運用の方法は企業型確定拠出年金のみではなく、前払いされた退職金をiDecoやNISAで運用する選択肢もあります。
入社した企業が選択制を導入していたら、どのように資産形成をしていくかよく考えた上で決定しましょう。
企業型確定拠出年金のメリットは3つの節税効果
企業型確定拠出年金の大きなメリットとして、3つの節税効果が挙げられます。
- 運用益が非課税
- 所得税控除、または非課税
- 受け取り時、公的年金等控除または退職所得控除が適用できる
運用益が非課税になるとはどういうこと?
資産運用の主な目的の1つに、投資した金額以上の利益=運用益を得ることがあります。
企業型確定拠出年金では、運用益に対して税金が発生しません。
証券会社や銀行の一般口座で資産を運用すれば、運用益から税金を支払う必要があります。
税額は、所得税15.315%と住民税5%の合わせて20.315%を掛けた金額です。
例えば株式投資で10万円の利益が出ると、20,315円の税金を納めなければなりません。
企業型確定拠出年金で同じく10万円の利益が出ても納税義務はなく、20,315円の節税効果があると言えます。
掛金は所得の扱いにならず所得税は非課税
企業型確定拠出年金の掛金は所得の扱いにならず、所得税は非課税です。
自動加入と選択制、企業がどちらの制度を導入していても従業員が自己負担した掛金分の所得税は発生しません。
マッチング拠出分についても全額所得控除の扱いになり、所得税を節税できます。
一方、選択制で企業型確定拠出年金に加入しない方は、退職金の先払い分だけ給与が増加するので社会保険料や所得税額が加入者より多くなります。
受け取るときも控除がある
年金は税制上雑所得として扱われるので、所得税が発生します。
しかし、年金には公的年金控除が適用され、年齢や収入に応じて算出された金額分だけ所得税の課税対象額を少なくできます。
分割ではなく一時金として一括で受け取るときは退職所得控除の対象となり、勤続年数が長いほど控除額が大きくなるため、節税効果が上がるでしょう。
他の年金制度や資産運用との違いは3つ
企業型確定拠出年金は他の年金制度や資産運用と異なる点は以下の3つです。
- iDeCoとの違いや併用の可否
- NISAとの違いはどこにある?
- 厚生年金への影響はある?
iDeCoと企業型確定拠出年金のどちらを選択するべきなのか、併用ができるのかを気にする方は多くいます。
資産運用の観点から、選択制でNISAにするべきかを迷うケースも少なくありません。
企業型確定拠出年金と厚生年金は別物なのか、加入による影響があるかどうかも気になります。
iDeCoとNISA、企業型確定拠出年金、厚生年金の制度を把握せず申し込み後悔しないよう、事前に比較しておきましょう。
個人型確定拠出年金のiDecoとはお金の出どころが違う
iDeCo(イデコ)は個人型確定拠出年金の略称で、掛金を加入者自身で全額支払う仕組みです。
企業型確定拠出年金では勤務先が掛金を支払うので、似ていても異なる制度です。
60歳まで原則解約できない点と、個人が負担した掛金が所得控除の対象となる点は共通しています。
しかし、限度額や選択できる運用商品は異なるので、企業型確定拠出年金が選択制の方はよく検討する必要があります。
| 比較項目 | 企業型確定拠出年金(企業型DC) | iDeCo |
|---|---|---|
| 限度額 | 制度上は1ヶ月最大55,000円まで ※企業の規定により異なる |
厚生年金保険の被保険者で企業型 DC未加入:1ヶ月最大23,000円 |
| 運用商品 | 企業が選定した金融機関の、企業型DC向け運用商品から選択 | 自分が良いと思った証券会社や銀行を選び、運用商品を選択 |
厚生年金に加入・企業型DCには未加入の方は、iDeCoの限度額は1ヶ月23,000円までです。
一般的に企業型確定拠出年金の限度額は、制度上は55,000円ですが役職や年収により掛金が決まります。
iDeCoのメリットは、運用する金融機関から自分で選択できる点にあります。
口座開設キャンペーンや運用サポートなど、自分に合うサービスを選択できるのはiDeCoならではと言えるでしょう。
企業型確定拠出年金とiDecoの併用は条件付きで可能
2022年の制度改正により、企業型確定拠出年金に加入している方でも条件付きでiDeCoにも加入できるようになりました。
iDecoと企業型確定拠出年金の併用条件
- マッチング拠出を利用していない
- 1ヶ月の限度額は20,000円
- 企業型DCの企業の掛金+iDeCoの掛金が55,000円以内
参照元:厚生労働省
企業型確定拠出年金でマッチング拠出を利用している方は、iDeCoとの併用はできません。
1ヶ月の掛金は全体で55,000円まで、iDeCo単体での掛金は20,000円が上限です。
例えば企業型確定拠出年金が1ヶ月1万円の方は、iDeCoでは上限いっぱいの20,000円まで拠出できます。
企業型確定拠出年金が1ヶ月35,000円未満の方は、マッチング拠出の方が掛金を限度額最大まで利用できる計算です。
限度額よりも運用商品の選択肢を多く持つことを優先したい方は、iDeCoの併用を検討しましょう。
運用益非課税のNISAは投資した元本は所得控除の対象外
NISAでの資産運用は、運用益が非課税なのは共通ですが掛金は所得控除の適用外です。
例えば、課税対象所得が300万円の方が年間20万円を資産運用したと仮定しましょう。
20万円を全額NISAで運用するケースと、選択制企業型確定拠出年金の掛金にするケースで税金を比較したものが以下の表です。
| 資産運用方法 | 所得税(税率10%) | 住民税(所得割・税率10%) |
|---|---|---|
| 企業型確定拠出年金 | 28万円 | 28万円 |
| NISA | 30万円 | 30万円 |
※住民税の所得割とは、住民税のうち収入に応じて納税額が変わる部分のこと
上記の例では、企業型確定拠出年金を選択することで合計4万円の節税が実現しています。
20万円の資産運用で、1年間で4万円の利益を得るのは簡単ではありません。
所得控除による節税効果も運用益と見なせば、企業型確定拠出年金のメリットは大きいと言えます。
自分のタイミングで解約できるかどうかがポイント
企業型確定拠出年金は60歳まで解約できないため、臨機応変に使える資産ではありません。
NISAは自分のタイミングで解約して現金にできるので、老後資産よりも優先してお金を貯める目的に向いています。
NISAと企業型確定拠出年金の併用に制限はないので、無理のない範囲でバランスをとりながら資産を運用しましょう。
厚生年金制度は勤務年数と収入に応じて将来の支給額が変わる
企業の社会保険加入で給付を受けられる厚生年金は、勤務年数と収入から計算されます。
厚生年金の一部が企業型確定拠出年金に置き換わるのではなく、全く別の年金制度だと考えておきましょう。
現在の年金制度は、3階建て構造として考えると分かりやすくなります。
国民年金と厚生年金に、企業型確定拠出年金も加えることで老後の生活にゆとりができます。
自動加入の企業型確定拠出年金では、給与金額により変動する厚生年金の支給額にも影響がでません。
企業型確定拠出年金への加入は4つのデメリットがある
企業型確定拠出年金は、場合によってメリットだけでなく以下4つのデメリットがあります。
- 選択制で加入を選択すると厚生年金の支給額が減少する
- 原則60歳まで引き出し不可
- 運用商品の選択肢は少ない
- 商品の選び方によっては元本割れリスクがある
厚生年金の支給額は給与金額に応じて変わるので、選択制で給与が目減りすると影響を受けてしまいます。
原則60歳まで引き出せないので、あらかじめライフイベントごとにどう資金計画を立てるか考えておくことも重要です。
運用商品のラインナップはNISAやiDeCoより少ないケースもあり、元本割れリスクも考慮しておく必要があります。
企業が選択制DCのとき厚生年金の支給額が減る可能性がある
企業型確定拠出年金(企業型DC)が選択制の企業では、加入することで厚生年金の支給額が減る可能性があります。
選択制DCでは、退職金を給与として上乗せするか企業型DCに拠出するかを選択するので、後者を選択すると給与が減る仕組みです。
毎月給与から天引きされている厚生年金保険料は給与金額に比例し、将来の受取額も払い込んだ保険料に応じて変動します。
厚生年金保険料が少なければ、天引きされる金額も少なく済みますが将来受け取る年金も少なくなります。
選択制DCに加入しないと、厚生年金保険料は退職金上乗せ分だけ高くなり、将来受け取る厚生年金の額も増加するでしょう。
企業が選択制DCを導入している方は、自分にとって以下のどちらにメリットがあるのかよく検討する必要があります。
- 現在の手取りと支払う社会保険料は少なく、将来は基礎年金+やや少ない厚生年金+企業型DCを受け取る
- 現在の手取りと支払う社会保険料を多く、将来は基礎年金+やや多めの厚生年金を受け取る
企業型確定拠出年金に自動加入の方や、マッチング拠出で掛金を増やしている方は厚生年金に影響はありません。
原則60歳までお金を引き出せないためお金の使い方に柔軟性はない
企業型確定拠出年金で拠出しているお金は、原則60歳まで引き出せず柔軟な使い方ができません。
途中で脱退(解約)し、拠出したお金を一時金として引き出す条件を満たすことは非常に難しいと言えます。
一時金として企業型DCの資産を引き出す条件
資産が15,000円以下の場合、以下2つのどちらも満たしている
- 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者ではない
- 最後に企業型DC加入者の資格を喪失してから6ヶ月経過していない
資産が15,000円を超える場合に満たすべき7つの要件
- 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者ではない
- 最後に企業型DC加入者の資格を喪失してから6ヶ月経過していない
- 60歳未満である
- iDeCoに加入できない
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)ではない
- 障害給付金の受給権者ではない
- 企業型DC加入者及びiDeCo加入者として掛金を拠出した期間が5年以下、または個人別管理資産額が25万円以下
参照元:厚生労働省
「貯まった200万円を住宅購入の頭金に使いたい」「子どもの大学進学費用が足りないから100万円引き出したい」といったケースでは原則認められません。
就職してから60歳を迎えるまで、まとまったお金が必要になるライフイベントはいくつか考えられます。
余剰資金をすべて企業型DCにまわすと、他のライフイベントへの備えができません。
老後までに発生するライフイベントに備えるには
- いつでも解約できるNISAで資産運用
- 子どもの学費は学資保険で積み立て
- 住宅や車の購入費用として定期預金を利用
NISAは運用益が非課税なので、利益はまるごと自分の資産にできます。
学資保険は学費の積立貯蓄ともしもの時の備えができ、生命保険料控除で節税対策が可能です。
住宅や車など、費用が高額で元本確保しておきたいお金なら、定期預金を利用する手段もあります。
確定拠出年金にこだわることなく、広い視野で金融商品を選びましょう。
退職しても転職先の企業型DCかiDecoのどちらかに移管できる
企業型確定拠出年金は、今の会社を退職しても転職先の企業型DCか個人型であるiDecoのどちらかに移管する選択肢があります。
退職=解約して返金にはならず、退職後は自分で移管手続きを行わなければなりません。
転職先の企業でも企業型DCを導入しているなら、担当部署に確認して指示を受けましょう。
転職前と運営管理機関が異なると、運用商品の買い替えが必要です。
転職先に企業型DCがない方、個人事業主や専業主婦(夫)になる方はiDeCoに移管します。
引き続き掛金を拠出し続けるか、今まで拠出した掛金のみで運用するかを選択できます。
いずれも6ヶ月以内に手続きが必要なので、加入者資格喪失の書類が揃ったら早めに行動しましょう。
iDecoやNISAと比べて運用商品の選択肢が少ない
企業型確定拠出年金は、企業があらかじめ運営管理機関を決定しているため運用商品の選択肢は少ないといえます。
確定拠出年金では、企業型・個人型(iDeCo)とも金融機関が提示できるのが最大35本までと制限が設けられています。
より積極的に資産運用したい方や多くの運用商品から選びたい方は、NISAを検討しましょう。
NISAではつみたて投資枠(旧つみたてNISA)の対象だけでも200本以上あり、成長投資枠なら株式投資もできます。
積極的な運用は元本割れリスクも高くなりがちなため、投資に関する勉強や情報収集も欠かさず行いましょう。
元本変動型の選択には元本割れリスクがある
企業型確定拠出年金で元本変動型の運用商品を選択すると、元本割れのリスクがあります。
払い込んだ保険料に応じて受取金額が確定する厚生年金とは異なり、将来受け取れる金額は現時点で誰も分かりません。
ただし、元本割れリスクは、NISAやiDeCoについても同様です。
どうしても払い込んだ掛金だけは確保したい方は、ローリターンではあるものの元本保証型の運用商品を選択しましょう。
企業型確定拠出年金以外で元本保証の資産運用を選択するなら、個人向け国債もあります。
資産運用に関する情報は日々新しくなるので、どんどん情報を仕入れて資産を有効活用しましょう。