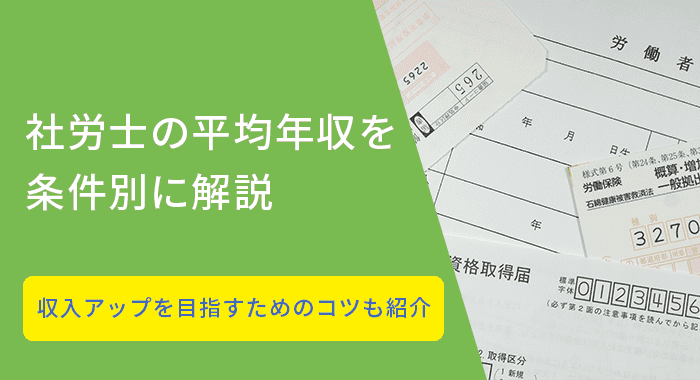社労士(社会保険労務士)とは、社労士資格を取得している国家資格者で、社会保険や労働関係の法律に精通しています。
企業の人材に関わる専門家で、社会保険や労務管理に関わる業務を行えるスペシャリストです。
社労士にしかできない仕事も多く、資格取得を目指す人も多い一方で、業務内容に見合うだけの年収を得られるか疑問に思う人も少なくありません。
本記事では社労士の平均年収を条件別に解説。
社労士を目指す人に向けて、社労士が年収アップを目指すためのコツや社労士の資格を取得する方法も紹介するので、資格を取得するか決める参考にしてください。
社労士(社会保険労務士)の平均年収は500万円前後
厚生労働省が実施している賃金構造基本統計調査によると、社労士(社会保険労務士)の平均年収は500万円前後です。
令和5年現在の賃金構造基本統計調査では、社労士単独での調査は実施されていません。
社労士単独の年収が分かる令和元年の調査結果は、以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| きまって支給する現金給与額 | 4,018,800円 ※月額334,900✕12ヶ月 |
| 年間賞与その他特別給与額 | 841,400円 |
| 年収 | 4,860,200円 |
令和元年の社労士の平均年収は486万円程度との結果が出ています。
年による変動もあるため、社労士の年収は500万円前後を1つの目安と考えましょう。
令和5年社労士の平均年収の目安もチェック
令和2年からの変更により、社労士は「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」に含まれています。
令和5年の社労士も含めた「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」の平均年収の目安は950万円程度です。
| 年 | 社労士も含むその他の経営・金融・保険専門職業従事者の年収 |
|---|---|
| 令和5年 | 9,476,000円 |
| 令和4年 | 7,808,600円 |
| 令和3年 | 10,295,200 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者に含まれる職業は、以下の通りです。
- 公認会計士
- 会計士補
- 税理士
- 社会保険労務士
- 経営コンサルタント
年による変動も大きいため、社労士も含めた専門職の年収の目安として参考にしましょう。
社労士の平均年収を条件別にチェック
社労士の平均年収は、性別や勤務形態によっても大きく異なります。
社労士の性別による平均年収の差は、以下の通りです。
| 性別 | 令和元年 | 令和5年 ※その他の経営・金融・保険専門職業従事者の年収 |
|---|---|---|
| 男性 | 5,147,500円 | 10,489,000円 |
| 女性 | 4,340,300円 | 7,284,100円 |
男性と女性で社労士の年収を比較すると、男性の方が高めの傾向にあります。
とはいえ女性の年収は全体として男性より低い傾向のため、女性の社労士は年収が低いとは言えません。
| 性別 | 社労士の月額賃金 | 正社員の月額賃金 |
|---|---|---|
| 男性 | 336,800円 | 351,5000円 |
| 女性 | 271,400円 | 269,4000円 |
賃金で比較すると、社労士の平均的な年収は男女共に他の職業とあまり変わらないと分かります。
社労士の年収は年齢に大きく影響されるわけではない
社労士の年収は年齢に大きく影響されるわけではありません。
| 年齢 | 令和元年 | 令和5年 ※その他の経営・金融・保険専門職業従事者の年収 |
|
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| 20歳~24歳 | ― | ― | 4,211,400円 |
| 25歳~29歳 | ― | ― | 7,221,300円 |
| 30歳~34歳 | 5,573,200円 | 2,183,405円 | 8,834,200円 |
| 35歳~39歳 | 4,466,800円 | 4,534,000円 | 9,761,300円 |
| 40歳~44歳 | 4,933,800円 | 4,366,300円 | 9,037,700円 |
| 45歳~49歳 | 5,409,900円 | 4,018,300円 | 15,800,200円 |
| 50歳~54歳 | ― | 4,970,800円 | 9,240,600円 |
| 55歳~59歳 | ― | 5,433,200円 | 11,256,400円 |
調査結果によると、年齢が上がるにつれ年収も高まるとは言えません。
雇われている社労士なら、勤続年数が長くなることで給与が増える可能性があります。
とはいえ一般的な仕事と同じで昇給の幅は大きくないので、「40歳以上になったら一気に収入が増える」といった変化は期待できません。
社労士の企業規模別平均年収
社労士の希望規模別平均年収は以下の通りです。
| 企業規模 | 令和元年 | 令和5年 ※その他の経営・金融・保険専門職業従事者の年収 |
|---|---|---|
| 1,000人以上 | 6,311,500円 | 8,950,900円 |
| 100人~999人 | 3,968,200円 | 12,542,300円 |
| 10人~99人 | 4,956,600円 | 7,233,100円 |
社労士として働くには、1,000人以上の従業員がいる企業での勤務が最も収入を上げられます。
大企業の方が年収を上げやすいのは、一般職も同じです。
できるだけ高収入を目指すなら、規模が大きい企業への就職を目指しましょう。
しかし、社労士として働きたい人材は多く、採用されるかは実力や経歴によります。
まずは中小企業で経験を積んで評価を得たり、新卒での入社を目指しましょう。
社労士の収入を左右するのは業務内容
調査の結果から、社労士の年収は業務内容に左右されると推測できます。
年齢や企業規模による年収の違いはあまり見られず、関連性があるのは性別のみです。
社労士の担当業務は幅広いため、年収を高めたい人は担当できる業務を増やし、年収が高めな勤務先に採用されるよう意識しましょう。
社労士の年収は高いのか一般会社員と比較
社労士の年収は一般社員と比較してほとんど変わりません。
社労士の平均年収と全体の平均年収を比較した結果は、以下の通りです。
| 時期 | 令和元年 |
|---|---|
| 社労士の平均年収 | 4,860,200円 |
| 全職業の正社員の平均年収 | 5,034,000円 |
出典:賃金基本統計調査│厚生労働省
出典:民間給与実態統計調査│国税庁
社労士の年収は、資格が必須な専門家であるにも関わらず、高額とは言えないのが現状です。
国税庁が調査した民間給与実態統計調査によると、給与取得者の平均年収は503万円。
社労士の年収と約30万円しか変わらないので、「苦労して資格を取ったのに割に合わない」と感じる人も少なくありません。
社労士の資格を持っている人は年々増えており、仕事が少なくなっているため、資格を持っているだけで稼げる状態ではないと分かります。
社労士の収入は担当する業務によって幅広い傾向にあります。
社労士になれば高い収入を得られるわけではなく、業務内容で差が出るため、高い年収を目指すなら担当できる業務が増やせるよう知識をつけましょう。
社労士が年収をアップさせるコツ3つ
社労士が年収をアップさせるコツは、以下の3点です。
- 営業スキルを磨き人脈も広げる
- コンサルティング業務も担当できるよう学ぶ
- ダブルライセンスを目指す
- 独立して起業する
社労士の年収が年齢や企業規模に大きく影響されないのは、担当できる業務の幅によって収入が決まるためです。
営業スキルを磨き人脈も広げれば、より多くの企業から仕事をもらえる可能性があります。
コンサルティング業務も担当できる社労士は、高い収入を期待できる傾向です。
ダブルライセンスを目指せば、担当できる業務が増え収入アップに繋げられます。
社労士としての経験を積み、ある程度クライアントとの繋がりができたら、独立するのも1つの手です。
仕事が安定するまでは収入も増減しますが、安定すれば起業した社労士が最も稼ぎやすい傾向にあります。
3つのコツから自分に向いたものを選び、収入アップを目指しましょう。
営業スキルや人脈を生かして仕事を獲得する
社労士が年収アップを目指すなら、以下の方法で仕事を獲得しましょう。
| 方法 | 詳細 |
|---|---|
| 営業スキルを磨く | 顧客を獲得できなければ仕事自体がない |
| 人脈を広げる | 知り合いが多いと集客に繋がる可能性もある |
社労士は企業に勤務する働き方と独立開業する方法があります。
企業に勤めていると自分で業務を探す必要がない代わりに、大きな年収アップは目指せません。
収入アップを目指すなら独立開業して自分で仕事を見つけるのが近道です。
業務をこなす力はあっても営業スキルがなければ、自分の良さをアピールできず仕事の獲得に繋げられません。
最初は書類作成や給与計算の依頼を受けながら信用を積み重ねながら、強みをアピールして幅広い業務を任せてもらう必要があります。
依頼された業務をこなしながら自分なりの提案もできると、新たな仕事を任せてもらえる可能性も。
自分の中で得意分野を決めて、他の人と差別化するのも有効です。
幅広い人脈があると仕事を任せてくれる人も見つけやすいので、将来的に独立を目指すなら、早い段階から人脈作りを始めましょう。
コンサルティング業務が担当できると年収アップに繋がりやすい
社労士は幅広い業務を担当できますが、中でもコンサルティング業務が担当できると年収アップに繋がりやすいです。
社労士は主に書類作成や帳簿作成を行いますが、知識を活かして労務関係のコンサルティング業務も担当できます。
コンサルティング業務の内容は多岐にわたり、企業の抱える悩みに合わせて対応を実施。
- 就業規則に関する相談
- 評価制度の構築
- 労働環境の整備
- 福利厚生の充実
- 採用業務に関する相談
コンサルティング業務は社労士専門の仕事ではなく、他の人でも可能です。
しかし、人材に関する専門家である社労士ならではの視点からアドバイスを送れるため、企業が抱える問題の解決に繋げられる可能性があります。
社労士が年収アップを目指すなら、コンサルティング業務を担当できるよう、幅広い知識を身につけましょう。
ダブルライセンスで担当できる業務を増やす
社労士が他の資格も合わせて取得すると、ダブルライセンスにより担当できる業務を増やせます。
社労士と相性の良い資格の例は以下の通りです。
| 社労士と相性の良い資格 | 理由 |
|---|---|
| 行政書士 | ・社労士として健康保険、雇用保険、年金関連の書類が作成できる ・行政書士の資格を取れば会社設立に関する書類作成にも関われる |
| 司法書士 | 法律的な問題にも対応できる |
| 中小企業診断士 | コンサルティングに関する知識を高められる |
| 税理士 | 税務関連の業務も担当できる |
| ファイナンシャルプランナー | 社労士としての保険や年金関連の知識を活かせる |
| 年金アドバイザー | 社労士としての年金関連の知識を活かせる |
行政書士は事業届や開業届を作成できるので、会社設立に関わった後で社労士の資格を活かして人事関連書類の担当もすれば長く1社と関わりが持てます。
司法書士の資格を取れば、法律関連と人事関連の問題を両方サポート可能です。
中小企業診断士の資格があれば、コンサルティング業務を担当しやすくなります。
税理士の資格を取得すると税務関連の業務も担当でき、ファイナンシャルプランナーや年金アドバイザーは社労士として得た知識の活用が可能な資格です。
社労士として得た知識を活かしつつ業務の幅を広げられるよう、得意な分野や興味のある資格を合わせて取得しましょう。
社労士の業務内容と資格を取得する方法
社労士の業務内容は主に3種類に分かれています。
| 社労士の業務の種類 | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1号業務 | 事務手続きの代行 | ・労働保険や社会保険の手続き ・健康保険の手当金の申請手続き ・助成金申請手続き |
| 2号業務 | 書類や帳簿作成 | ・就業規則の作成や改定 ・帳簿作成 ・労働者名簿作成 |
| 3号業務 | コンサルティング業務 | 人事関連の相談や指導 |
1号業務は主に事務手続きの代行で、労働保険や社会保険の加入また脱退の手続き、助成金申請といった専門的な内容です。
2号業務は労働社会保険諸法令に基づいて、必要な書類や帳簿の作成を実施します。
3号業務は人事関連の幅広い相談に乗る業務で、社労士以外の人も担当できる内容です。
社労士は人材に関する専門家という位置付けで、事業の健全な発達と労働者等の福祉向上を目指して業務を行います。
社労士になるには国家資格を取得する必要があるため、計画的に学習を進めましょう。
社労士の資格を取るには長期的な計画が必要
社労士の資格を取るのに必要な勉強時間は1,000時間が目安と言われるため、長期的な学習計画を立てて取り組まなければいけません。
受験を控えて仕事をしていない人が1日6時間勉強するなら、170日程度準備期間が必要です。
仕事をしながら受験を目指す人が1日2時間勉強すると、500日かかります。
受験日が近づいてから勉強しても間に合わないので、ある程度まとめて時間を取って勉強を進めましょう。
社会保険労務士試験は、社会保険労務士試験連合会が年1回、厚生労働大臣の委託を受けて実施しています。
社労士の受験資格は学歴や実務経験によって異なるため、まずは受験資格について社会保険労務士試験オフィシャルサイトの「受験資格及び受験資格証明書」で確かめましょう。
受験資格を満たしている人は、原則Webで受験を申し込みましょう。
2024年6月現在は、郵送による申し込みも受け付けています。
社労士の合格率は6%前後と低い
社会保険労務士試験の合格率は6%前後と低いです。
| 年 | 合格率 |
|---|---|
| 2023年 | 6.4% |
| 2022年 | 5.3% |
2023年の申込者は42,741人で、合格者は2,720人 です。
簡単に取得できる資格ではないため、少なくとも1,000時間の勉強時間を確保できるよう計画的に学習を進めましょう。
社労士の年収に関してよくある質問
社労士の年収に関してよくある質問は、以下の通りです。
- 社労士は独立開業すると年収1,000万円を目指せますか?
- 社会保険労務士になっても仕事がないと言われるのは本当ですか?
- 社労士は20代や女性だと収入が低めになりますか?
社労士の年収は高いと感じる人もいれば、「仕事がないのでは」「年収が低いのでは」と不安に思っている人もいます。
社労士の年収は実際どうなのか知っていれば、資格取得を目指すか判断しやすいです。
資格取得の勉強を始める前に疑問を解消して、勉強を始めるか決めましょう。
社労士は独立開業すると年収1,000万円も目指せる?
社労士は独立開業すると年収1,000万円も目指せますが、開業するだけで収入を得られるわけではありません。
独立すると自分で営業を行って仕事を獲得しなければいけないため、営業スキルを磨き、人脈を駆使してより多くの仕事を任せてもらう必要があります。
自分の得意分野を決めて営業すると、特定の業務を必要とする企業とマッチしやすいです。
独立すれば自分の頑張り次第で年収を上げられるので、得意分野を磨いて顧客を獲得しましょう。
社会保険労務士になっても仕事がないって本当?
「社会保険労務士になっても仕事がない」との声もありますが、仕事がないと心配する必要はありません。
社労士は人事関係のスペシャリストで、企業には必要な存在です。
仕事を獲得できない可能性があるのは、独立しても顧客を獲得できなかったとき。
営業スキルに自信がなければ、企業に所属して働くと仕事を得られない心配はいりません。
社労士の資格試験は合格率が6%程度と低く、そもそも受かるのが難しいです。
資格取得の難しさから「やめた方がいい」との意見はありますが、国家資格なので取らなければよかったと後悔する可能性は低いと言えます。
社労士の資格を取るには長期的な学習が必要なので、計画を立てて進めましょう。
社労士は20代や女性だと収入が低い?
社労士は20代や女性だと多少収入が低くなる傾向はありますが、大幅に低いわけではありません。
女性はもともと男性と比較して年収が低いため、男性と比較しなければ平均的な収入を得られます。
社労士の収入は年齢や性別よりも、業務内容に左右される傾向です。
年収をアップするならコンサルティング業務も含め、幅広い業務に対応できなければいけません。
幅広い知識を得るのが苦手なら、自分の得意分野を明確にして深く掘り下げる方法もあります。
企業から信頼を得られるよう、自分の強みを明確にして業務に取り組みましょう。