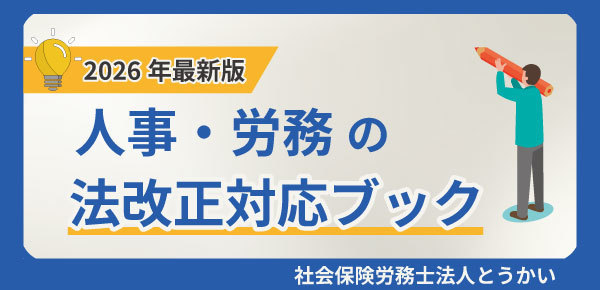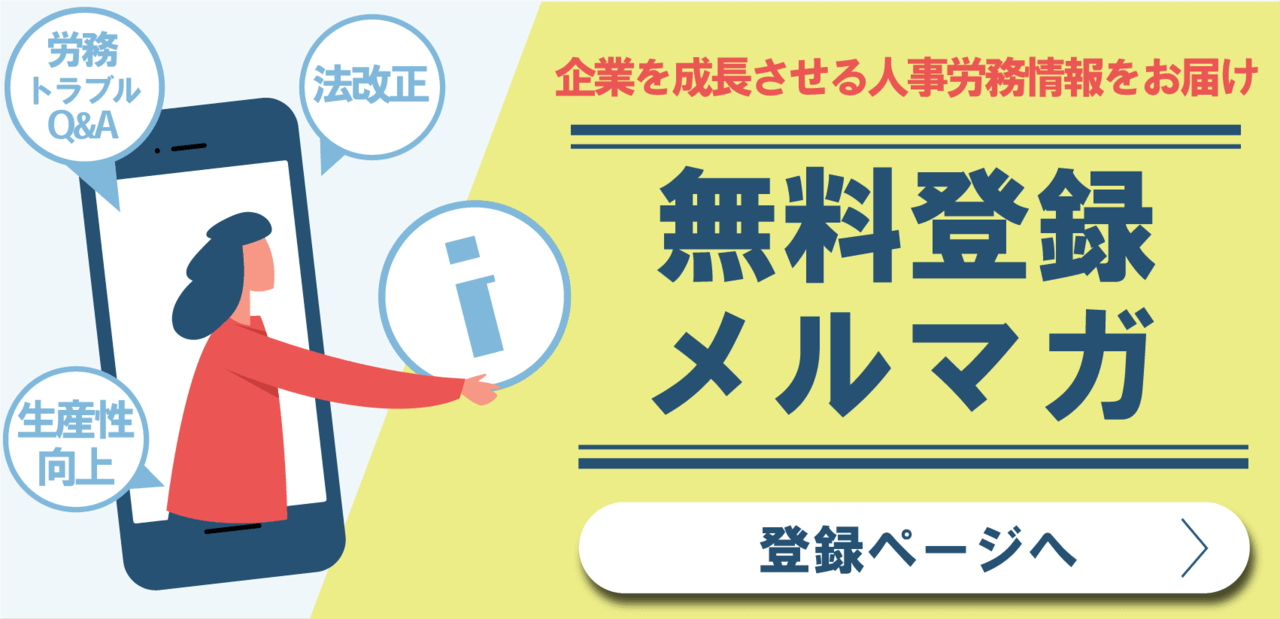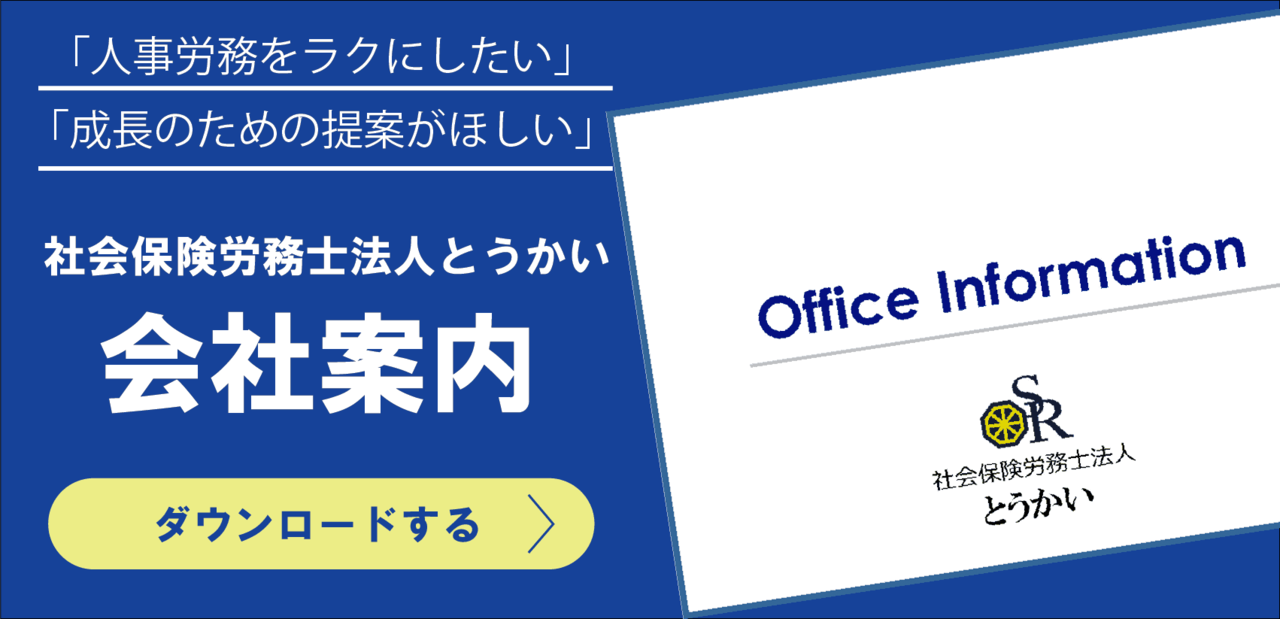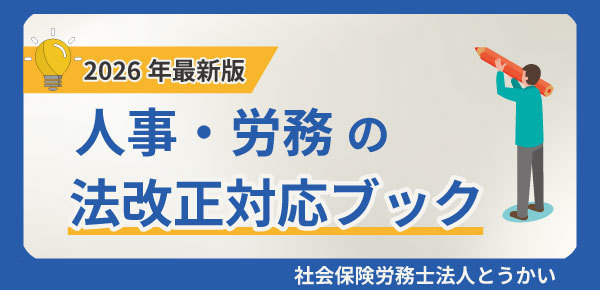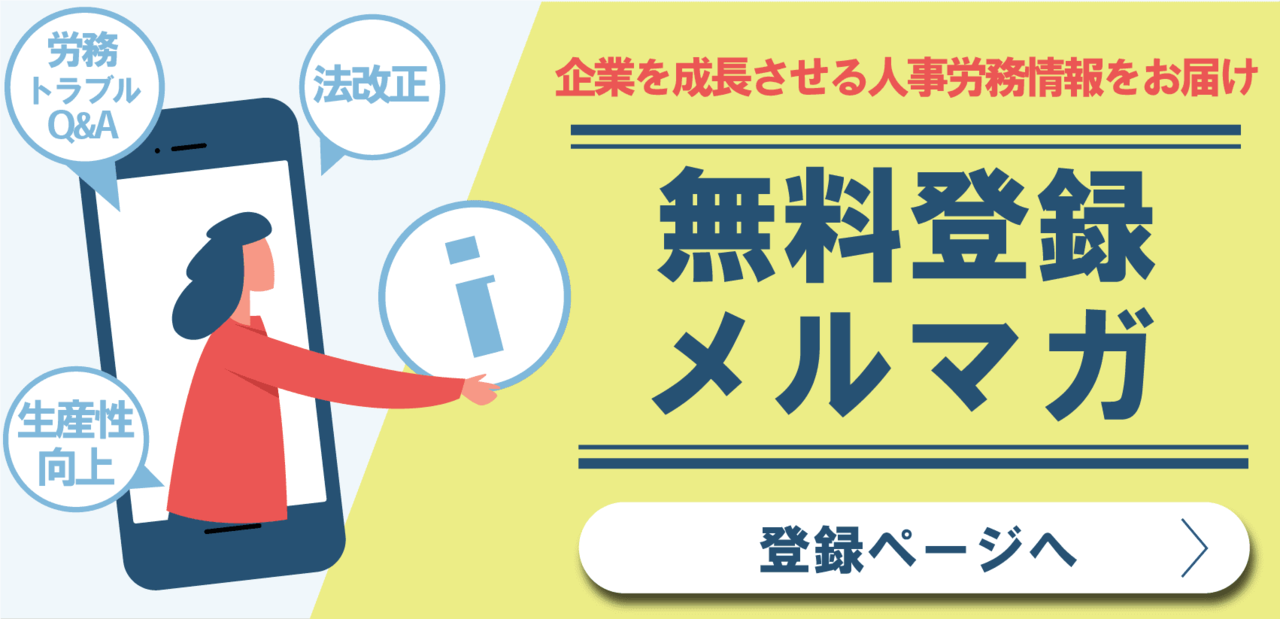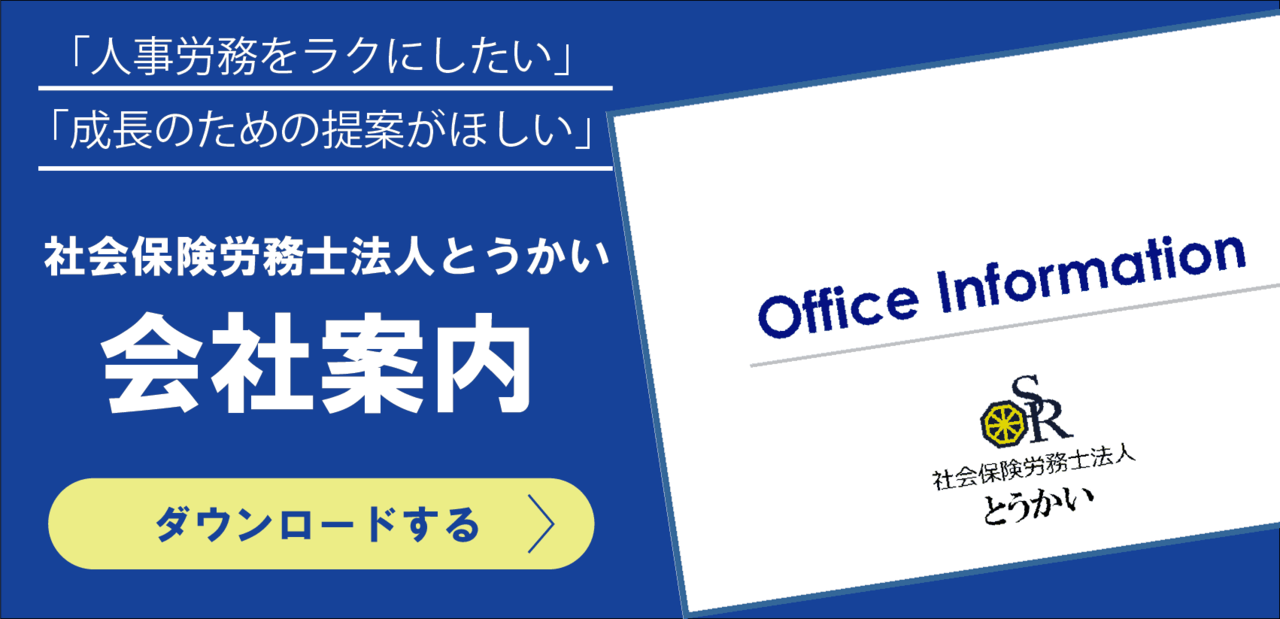10名・50名・100名 従業員数で変わる人事労務管理。
担当者が押さえておきたいポイントとは?
社会保険労務士が解説します。

企業の経営資源は、「ヒト・モノ・カネ」、最近では「情報」も加わり、重要な資源だと言われてきました。どれが欠けても成り立たない重要な経営資源です。中でも「ヒト」は、唯一、感情が伴うものであり、一旦トラブルが発生すれば、大きな問題となるばかりか、トラブルが長引けば、事業の停滞も引き起こしかねません。企業が売上・利益を拡大し、安定的に維持するうえで、「ヒト」への関わりは、非常に重要なものといえるでしょう。
その「ヒト」への問題には、状況に応じた対応を行ったり、コンプライアンスに沿ったルールのもとマネジメントを行うなど、適切な人事労務管理が必須です。
人事労務管理は、会社の状況、従業員の規模に応じて対応しなければならない事項が多くあります。
今回は、従業員規模別に押さえておきたい人事労務管理のポイントについて、ご紹介します。
目次
- 人事労務管理とは?
- 従業員1〜10人未満の会社の場合
- 従業員10〜50人未満の会社の場合
- 必要な手続き・届出や管理、その他の対応
- 従業員50〜100人未満の会社の場合
- 必要な手続き・届出や管理、その他の対応
- 従業員100人を超える会社の場合
- まとめ
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

企業の経営資源はヒト。人事労務の役割は非常に重要です。
人事労務管理の仕事の範囲は、会社によって多少異なる部分はありますが、一般的には大きく「人事」と「労務」の側面を持ちます。
「人事」については、会社の経営方針や経営戦略によって「人材採用」を行ったり、組織に適切な「人材配置」を行います。さらに、ポジションに適したスキルや能力のための「人材育成」や、従業員が持っている力を発揮してもらうための「人事評価」もあるでしょう。
一方、「労務」については、従業員が働きやすい環境をつくるための「職場環境の充実」や「ルールや仕組みづくりと運用管理」の側面を持ちます。
ヒトに関わることであれば、すべて人事労務管理の業務の範疇とも言えるでしょう。どんなに小さな会社であっても、1人でも従業員を雇用すれば、人事労務管理が必要です。会社の経営方針や戦略、従業員規模によっても、体制や環境づくりもさまざまに対応していかなくてはならない仕事です。とくに、労務の領域については、従業員規模によって対応する法律が異なる場合も多いので、しっかりと確認しておきましょう。

小規模企業は、まずは労働関連法規をきちんと守れているか確認を。
従業員が少人数であったり、起業したばかりの会社の場合、人事労務業務の専任担当者がいるケースは少ないでしょう。社長が自分自身で対応していたり、1人の担当者が人事労務、経理、総務もといった具合にバックオフィスすべてを担っている場合も少なくありません。
押さえなくてはいけない基本的な労働関連法の届出や手続きが漏れていたり、誤った認識のまま業務を行なっているケース、給与の計算方法が誤っているといったことが、往々にしてあります。とくに労基法などに関する部分は、従業員数が少ないからといって曖昧にしていると、後々、大ごとにもなりかねませんので、今のうちから仕組みを整備したり、手続きや届出に漏れがないか確認しておきます。
小さな会社の場合、経営者は業績や資金繰り、将来計画に注力していることのほうが多いでしょうが、会社の地盤づくりも重要です。外部のサポートなども頼りつつ、今のうちから体制づくりを整備していきましょう。
従業員を1人でも雇用すれば、雇用するうえでのさまざまな手続きや届出が必要です。
絶対に必要。労働条件通知書や雇用契約書作成
従業員を雇用する際には、必ず労働条件通知書や雇用契約書といった書面で、労働期間や時間、賃金、就業場所、時間外労働の有無など、絶対に明示しなくてはならない事項があります。
忘れると罰則も。労働保険(労災・雇用)手続き
従業員が1人であっても、原則、労働保険の適用がされるため、労働保険関係成立届を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署、ハローワークに届出なくてはなりません。
従業員が入社・退社すれば、その都度、雇用保険の資格・喪失の手続きも必要になりますので、忘れず行います。従業員がいるにもかかわらず、手続きや届出を行なっていない場合には、罰則もあります。過去に遡って未納保険料や追徴金が発生しますし、未加入期間に発生した労災事故に関しては、保険給付額の一部もしくは全部を徴収されるということになります。故意だとみなされば、厳しい措置となりますので、くれぐれも手続き・届出をお忘れなく。
パート・アルバイトも対象。社会保険(健康・厚生年金)手続き
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に、初めて加入する場合には、新規適用の届出が必要となります。代表者1人であっても、その大半の法人が強制適用事業所となります。従業員を雇用すれば、資格取得の届が必要です。
従業員がパート・アルバイトであっても、労働時間や労働日数が所定の割合以上であれば、社会保険の加入対象となりますので、注意しましょう。労働保険同様、こちらも未加入などがあれば年金事務所の指導や立ち入り検査が実施されるケースもあります。遡及納付や罰金も発生することもあります。
【強制加入対象者】
法人代表者/役員/正社員(試用期間中含む)/パート・アルバイト
【パート・アルバイトの加入条件】
●1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行なっている正社員など一般社員の3/4以上
●上記に該当しない場合は、次の要件に該当する場合で労使の合意があるとき
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が1年以上もしくは見込みがある
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生以外
注意)2022年10月から短時間労働者(パート・アルバイト)に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます
残業させるには必須。36協定の締結
非常に重要なのが36協定の締結です。
小さい会社の場合で人事労務に知識がない場合には、そもそも“36協定って何”という状態の会社もあるかもしれません。「36協定」とは、1日8時間、週に40時間の法定労働時間を超えて働く従業員が1人でもいる会社は、すべて対象となります。残業時間についての取り決めを労使で行い、36協定として締結します。
36協定を締結していなくても、この法定労働時間を超えて働かせることがなければ特に問題はないのですが、一方でこの36協定を結ばずに残業をさせた場合には、罰則の対象となるのです。この従業員は、正社員はもちろん、契約社員やパート・アルバイトであっても同様です。残業が発生するということがあるのであれば、しっかりと36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出を行いましょう。
勤怠管理で労働時間管理の徹底を
小さな会社で従業員の労働時間の管理まで、手が回らないという声も聞きますが、小規模だからこそ、今のうちから管理のしくみや方法を整えておくことをおすすめします。
そもそも適切な労働時間を管理・把握していないと、その後の給与計算が正しく行えませんし、36協定で締結した残業時間の限度を超えそうなのか、超えてしまっているのかの判断もつきません。過重労働になれば、従業員の健康問題も生じます。後々の大きなトラブル予防という意味でも、しっかりと行ない、記録として保存しておきましょう。
勤怠管理を行うには、タイムカードやエクセルに入力といった方法もあります。とはいえ、タイムカードやエクセル表を集計するのは、少人数とはいえ手間もかかります。最近では低額で導入できる勤怠システム等も多いので、効率よく低コストで導入も可能なものを選択するのもよいでしょう。
意外といろいろな法律が関係する給与計算
少人数の会社の場合、多様な労働時間制を用いているケースは少ないので、給与計算なんて簡単ではと思いきや、そうとは限りません。給与計算は、さまざまな法律に則って計算しなくてはなりません。所得税、住民税、社会保険、雇用保険、労基法に基づいた残業代の計算、各種の法律が関わっています。適切に勤怠管理がされていることが大前提にもなります。
所得税や保険料の計算を間違えてしまうと、後々まで影響が及ぶということもあるので、非常に慎重さを有する業務です。とくに社会保険料などは、給与の昇給・降給などに連動して、社会保険の随時改定が必要だったり、年に1回は定時改定された保険料を、反映させなくてはなりません。また、残業代を計算するにあたっても、労基法を理解していないと、計算結果の端数処理を誤ったり、割増率を誤るといったミスも引き起こしかねません。どれか1つでも間違えると正しく計算することができません。ミスが発生すれば、遡及計算や未払いがあれば精算しなくてはならないなど、手間がかかるばかりか、従業員からの信用を下げることにもつながります。
これらは給与計算に関わる法律はたびたび改正されることもあるので、最新の情報をタイミングよくキャッチアップできていないと、大きな給与計算ミスにもつながるのです。
その点で、人事労務担当者の責任は大きく、専任担当者でない場合などは、“果たして自身のおこなった計算結果が合っているのか不安”という方も多いのではないでしょうか?
会社規模が小さくとも、正しく給与計算を行う体制を整えたり、給与計算の担当者の育成が難しいようであれば、適宜、外部のサポートなどを受けながら、ミスなく運営できるような仕組みづくりを構築することをお勧めします。
スタッフが1人でも有給休暇は必要
従業員を雇用すれば、有給休暇は発生します。一定の要件を満たせば、法律上、当然に権利が発生するものなので、しっかりと確認しておきましょう。週に1回のアルバイトであっても、要件を満たせば、有給休暇が発生します。
少人数で運営している会社は、スタッフが休みを取ると回らないので困るという経営者の方もいるかもしれませんが、従業員にも気持ちよく働いてもらえればこそ、会社の業績につながるというものです。きちんと有給休暇を取得できる体制づくりも併せて考えていきましょう。
【有給休暇の付与要件】
- 6か月間継続して雇用されている
- 全労働日の8割以上出勤している
| 勤続期間 | 6か月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
※短時間労働者(パート・アルバイト)の場合は、別途付与要件が異なります。
| 所定労働日(週) | 所定労働日(年) | 6か月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 6日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
少数精鋭は健康が資本。健康診断実施は会社の義務、必ず実施を
従業員の健康診断も実施の必要があります。通常は、雇入時と定期的に年1回の実施とされています。正社員はもちろん、パート・アルバイトであっても、1年以上の雇用継続が見込まれている場合や、週の労働時間が正社員の3/4以上であれば、実施の必要があります。
少人数の会社は、スタッフ1人でも病気になれば、事業運営に影響がでることも。予防のためにも定期的な健康診断実施を行いましょう。従業員規模が50人以上になると健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告・届出なければなりません。50人未満の企業は、届出の義務がないだけで、健診実施は義務となりますので、注意が必要です。

労務トラブルの芽が育たぬうちに。早めに対応を。
会社が成長し、従業員数が増えてくると、さまざまな人事面での問題や課題が出てくるようになります。人材採用を活発に行なっていくことで企業文化や価値観が広がり、人事評価をどのように行っていくか、人材配置をどうするかといった経営方針や戦略にも関わる問題・課題が見えてくるでしょう。人材が多様化するよい側面の裏返しで、労務トラブルも発生しやすくなってくる面もあります。従業員規模が大きくなってきたときの手続きや届出などの基本的な対応はもちろんですが、組織運営としての人事労務課題・問題への対応が必要になってくるでしょう。
必要な手続き・届出や管理、その他の対応
従業員が10〜50人規模になってくると、法律に関わる手続きや届出以外に、さまざまな対応が必要になってきます。
就業規則の作成、届出
従業員を10人以上雇用する際には、必ず就業規則を作成し、事業所ごとに設置・周知する必要が生じます。企業が大きくなっていけば、従業員の価値観も多様になってきます。企業文化や風土を反映できるような働き方の見直しや、福利厚生などをどのようにルール化するか、トラブルや問題が発生したときにはどのような対応や処分を行うのか、休職者が発生したらどうするのか、その他考えておかなければならないことが非常に多くなります。それには、就業規則として一定のルールを明示し、従業員と共有認識を持っておく必要があるでしょう。
この就業規則は、作成したら、所轄の労働基準監督署に届出を行わなければなりません。もちろん従業員が10人以下であっても、就業規則を作成するのが望ましいですが、届出は従業員10人以上の場合に必要となります。
すでに就業規則は整備されているものの、従業員が増えていく中、実態に即していなかったり、改正が進む各種法令に則した内容になっていない場合には、見直しが必要になります。
活躍する人材を適切に評価できる仕組みを。人事評価制度の構築や人材育成
法律的に必要な対応というわけではありませんが、就業規則同様、注力して臨みたい課題です。企業文化や風土の土台とも言える人事評価制度は、従業員のモチベーションに大きく影響する制度です。人材不足の中、せっかく人材採用をしても、離職されては意味がありません。評価の一貫性や評価結果を適切な人材配置につなげるために、実態に則した評価制度、運用継続を行うことが重要になってきます。
人が増えれば、トラブルも増える。労務トラブルへの対応
従業員が増えれば増えるほど、それに応じて起きやすくなってくるのが労務トラブル。仕事のほとんどは相手がいることですから、人間関係のトラブルも増えてきます。大きなトラブルに発展すれば、事業活動にも影響が及びますので、トラブルの芽は早め摘むことが肝要です。よくあるケースは残業代未払いやハラスメントの問題。これらが発生すると、場合によっては裁判に発展するなど、問題が長期に渡ることもありますので、適切な対応がされているのか、見直しをしておくことをおすすめします。
メンタルヘルス不調者への対応は早めに。
うつ病などに起因するメンタルヘルスの問題も発生するかもしれません。長時間労働が発生していないか、ハラスメントなどの訴えはないか、発生しないような予防策としての対応は重要ですが、もしも発生した場合の対応についても、検討しておかなければなりません。早めの対応が、症状を長引かせることなく、復調することにつながります。フォローアップ体制や医師への連携、休職者が発生した場合の復職タイミングや人材配置など、一定の仕組みや体制を整えておきましょう。

外部のリソースも活用しながら、人事労務体制の構築を。
従業員が50人を超えてくると、さまざまなコミュニケーションの問題やマネジメントの問題も発生しがちです。人事評価制度や各種規定類なども、バージョンアップが必要になってくるでしょう。従業員数50人以上ともなると、ある程度、人事労務業務の基盤はあるものの、担当者が兼務で行っているような場合には、対応が難しくなってくる頃です。外部のサポートも適宜受けながら、人事労務業務の体制を整えておかないと、目が行き届かないことが多くなりがちです。この先の会社の人員計画なども想定しながら体制構築を整えていく段階でしょう。
従業員50人を超えると、組織的な管理や体制などが必要な場面が増えてきます。従業員の健康管理や職場環境に関する事項について、法律で求められる手続きや届出も増えますので、50人に達することが見込まれる前から、準備が必要になってきます。
衛生管理者の設置や産業医の選任が義務に
従業員が常時50人以上の事業所では、その事業所専属の衛生管理者の設置が義務づけられます。製造業や建設業では安全管理者の設置も必要です。専属の衛生管理者ということになるので、従業員が衛生管理者になるわけですが、衛生管理者になるには、資格の取得をしなければなりません。資格取得までには一定期間の勉強も必要になるので、従業員が50人に達するのが計画される段階には、準備しておく必要があるでしょう。
また産業医の選任も行わなくてはなりません。産業医は、従業員が快適な職場環境で仕事が行えるよう、医学的立場から指導・助言を行う医師です。従業員の健康診断結果に対する就業判定や、メンタル不調の社員へのアドバイス、休職者の復職判断等、専門的知見を持ってサポートしてくれる医師の選定が必要になります。こちらも、早めに選定しておかないと、従業員が50人に達してから動き出しても、適任が見つからないなど慌てることになりかねません。しかも50人を超えた事業所は、衛生管理者の設置も、産業医の選任も14日以内に選任し、労働基準監督署へ報告しなければなりません。
さらに、常時50人以上の事業所では、衛生委員会の設置も義務となります。(製造業や建設業では安全委員会の設置も義務)従業員の健康障害の防止や健康の保持増進に関する取り組みなどの重要な事項について、労使一体となって調査審議を行います。原則、月1回以上の衛生委員会を開催し、議事録を保管しておきます。委員会のメンバーの選出や運営計画なども準備していく必要があります。
健康診断結果やストレスチェックの実施を報告
衛生管理者の設置や産業医の選任とあわせて、従業員が50人以上の場合には、年1回の健康診断結果、年1回のストレスチェック実施を所轄労働基準監督署に報告する義務が課されます。
経営者の中には、『100人の壁』を意識される方も多いのではないでしょうか。100人の壁とは、グレイナーの“5段階企業成長モデル”の第2段階のこと。“5段階企業成長モデル”とは、会社の成長段階にあった人材を登用することが会社の発展につながるとして、それぞれの段階を定義しています。その中で、ちょうど第2段階の終わり頃である従業員100人前後の規模について述べられていることによれば、組織的にさまざまなトラブルが現れる段階とされています。従業員100人前後は、ある程度、組織や階層に厚みができる頃であり、人事労務についても、人事採用や労務管理といった専任の担当者が担うようになってきます。一方で、指示系統が確立してきた分、自主性が失われる面が現れます。いわゆる指示待ちのスタッフが増えるというのです。こうした人材を増やさないためのチームビルディング、人事施策やマネジメントへの対応が必要になってくるでしょう。
さらに、法律で求められる組織としての対応は増えますので、100人の壁を乗り越えるには、相応のエネルギーを持って臨む必要がありそうです。

人事労務のお悩み事・ご相談に幅広くサポートします。
従業員規模によって、対応していかなければならない事項は多岐にわたります。だた、共通して言えるのは、人事労務管理の役割は重大でコンプライアンスを徹底しつつ、経営方針や経営戦略に則した対応が必要になるということです。とはいえ、これらは非常に慎重さが必要な反面、大ごとに発展しないよう、スピード感を持って対処しなければならない面もあります。常に法律知識・情報をキャッチアップしておかなければならないといった難しさもあります。
しかしながら、現実はルーティン業務をこなすだけで精一杯という状態という人事労務担当者も多いのではないでしょうか。
ここで一旦、先を見据え、人事労務全般において、業務の整理・体制を整理してみてはいかがでしょうか。人事労務担当者がコア業務に集中できるよう、外部委託や社会保険労務士の活用も視野に検討をお勧めしています。経験豊富なスタッフがサポートしていきますので、お気軽にご相談ください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」