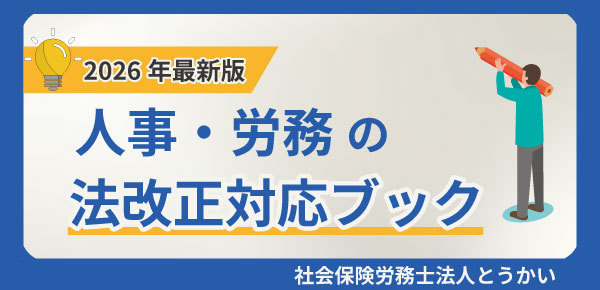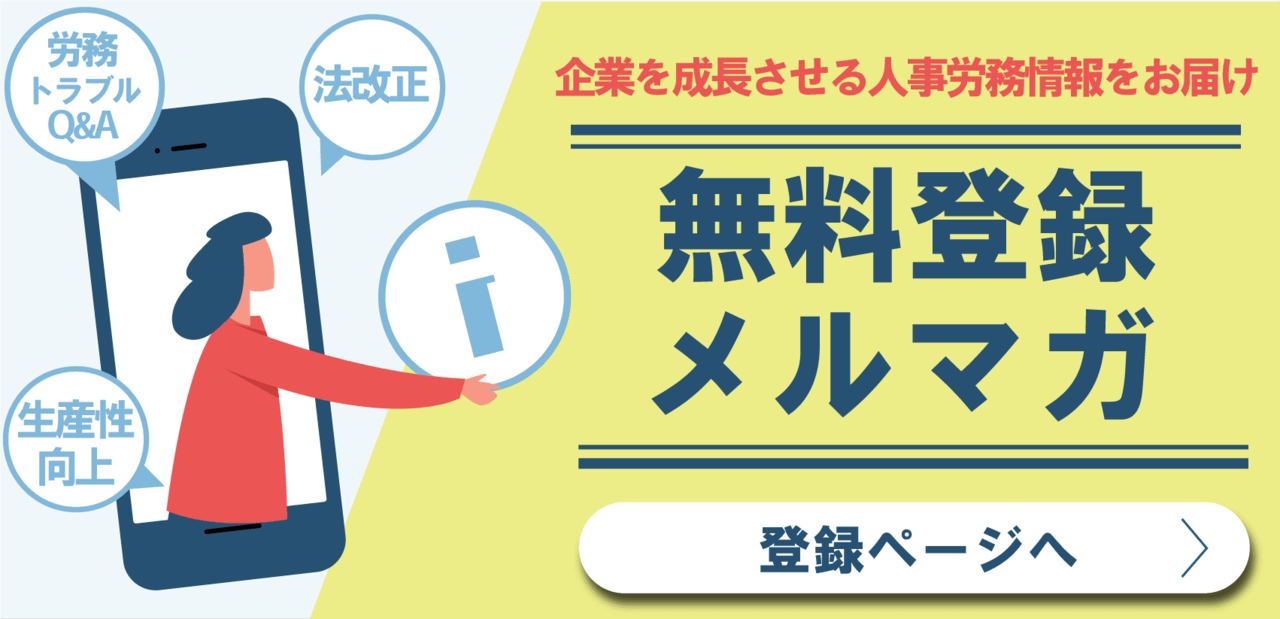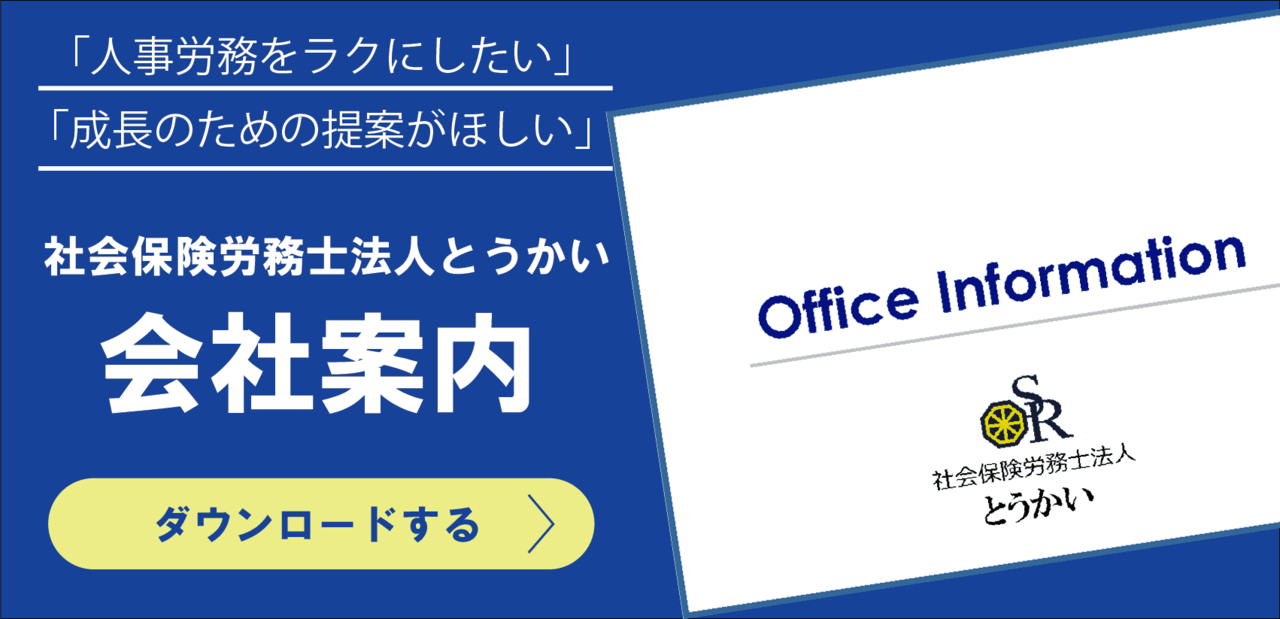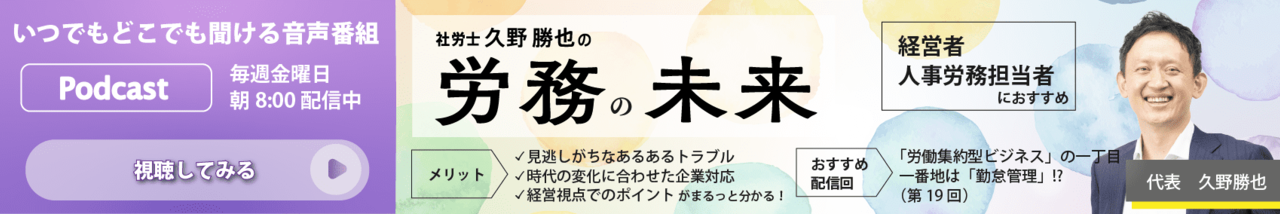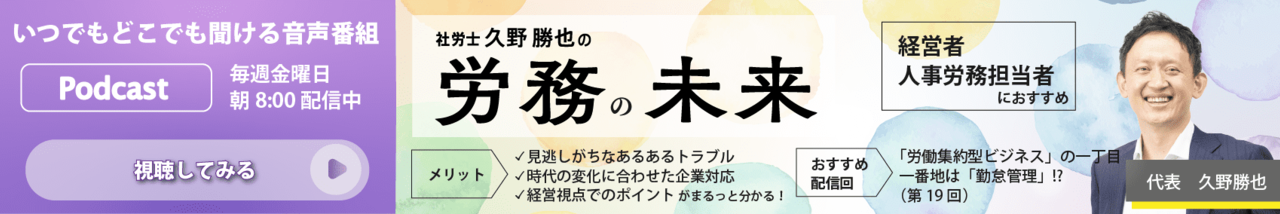<2025年最新版>中小企業のパワハラ防止対策、
義務化のポイントと実践すべき対策を社労士が解説します

2025年においても、パワハラ防止対策は企業にとって重要な課題です。特に中小企業では、2022年4月からパワハラ防止措置が義務化されており、適切な対策が講じられているか改めて確認が必要です。
この義務化の背景には、依然として増加傾向にあるハラスメント相談件数があります。企業は、ただ法を遵守するだけでなく、より実効性のある対策を講じることで、従業員が安心して働ける職場環境を整備し、企業の健全な成長を促すことが求められています。
本記事では、2025年におけるパワハラ防止対策の最新動向と、中小企業が実践すべき具体的な対策について解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

相談件数は年々増加。企業のハラスメント対策を強化しましょう。
パワハラ(パワーハラスメント)にあたる行為として、労働施策総合推進法では以下の3つの基準を定義しています。
優越的な関係に基づいて行われること
職務上の地位が上位であったり、優位な立場である上司や先輩の言動や行動がこれにあたります。優越的という点では、上司・先輩だけではなく、同僚や部下・後輩も含まれます。例えば、業務上必要な知識や経験を有している同僚や部下・後輩の協力を得なければ、円滑に仕事を行うことが困難である場合、その同僚や部下・後輩は優位性があるといえるでしょう。さらに、同僚や部下・後輩らの集団的による行為で、抵抗や拒絶することが困難であるケースも該当します。
業務上必要、かつ相当な範囲を超えて行われること
社会通念に照らして、明らかに業務上の必要性がない、業務の目的から逸脱した言動や行為です。業種や職種、業務内容、言動の頻度や継続性など、総合的に社会通念上に照らして判断されます。職場内では、業務を進めるために指示をしたり、指導が行われるものです。指示や指導を不満に思い、パワハラであると申し出る者もいるかもしれませんが、当然ながら、その指示や指導が適正であれば、パワハラではありません。
身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること
就業をするうえで支障が生じるような言動、行為、嫌がらせ行為やいじめが該当します。暴力や人格・名誉を傷つけるような言動により、通常の仕事が行えない状況です。同様の言動や行為を受けた場合、社会一般の労働者が就業するうえで支障があると感じる行動や言動かという点が判断基準となります。たとえば、社員が精神的苦痛によって休職するなど、就業できない状態に置かれる場合をいいます。
無料相談・お問い合わせ
初回無料相談実施中!お気軽にお問い合わせください

パワハラ行為者の多くは無自覚。教育を通して理解を深めましょう。
パワハラであるかどうかは、3つの基準に当てはまるかどうかによって判断されます。職場内だけでなく、客先なども該当します。ただ、総じてパワハラについては、双方の主張が分かれることもあります。代表的なパワハラ行為とされたケースを確認しておきましょう。
パワハラであるかどうかは、3つの基準に当てはまるかどうかによって判断されます。職場内だけでなく、客先なども該当します。ただ、総じてパワハラについては、双方の主張が分かれることもあります。代表的なパワハラ行為とされたケースを確認しておきましょう。
身体的な攻撃
上司が部下に対して、殴る、蹴る、突き飛ばすなどの暴行・傷害行為。業務上関係のない単に同じ会社の社員同士が喧嘩した場合には、パワハラ行為には該当しません。
精神的な攻撃
上司が部下に対して、人格を否定するような発言や、業務上であっても必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を行うなど。服務規律違反などに対し再三の注意によっても改善されない場合に上司が強く注意する、といった場合には、パワハラ行為に該当しないケースがあります。
人間関係からの切り離し
特定の社員を仕事から外し、長期にわたって別室に隔離したり、自宅研修させたりする。新入社員育成のため、短期集中的に個室で研修教育を実施するといったケースは、パワハラには該当しません
過大な要求
業務上明らかに不要なことや推敲が不可能なことを強制する。社員育成のために現状より少し高いレベルの業務にチャレンジさせるようなケースは、該当しません。
過小な要求
業務上の能力や経験とかけ離れた誰でも推敲可能な業務を行わせるといったケース。経営上の理由によって一時的に簡易な業務を担わせることは該当しません。
個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること。思想・信条を詮索したり、個人情報を許可なく他者へ暴露したりすること。社員への配慮を目的に家族状況等についてヒアリングを行うことは該当しません。

セクハラとパワハラの違いについて解説します。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)も、パワハラと並んで企業が取り組むべき重要な課題です。
セクハラは「労働者の意に反する性的な言動」に起因するものであり、パワハラの背景にある「優越的な関係」とは定義上の起点が異なります。
しかし、上司がその地位を利用して部下に性的な言動を行うなど、パワハラとセクハラが複合して発生するケースも少なくありません。
セクハラは、大きく「対価型」と「環境型」の2つに分類され、企業はどちらの類型についても防止措置を講じる義務があります。
対価型セクシュアルハラスメント
労働者の意に反する性的な言動に対して、その労働者が拒否・抵抗したことを理由として、解雇、降格、減給、契約更新の拒否、不利益な配置転換など、労働条件上で不利益を与える行為を指します。
例えば、上司が部下との性的な関係を要求し、それを拒絶されたことへの報復として、その部下を閑職に追いやったり、不当に低い人事評価をつけたりするケースがこれにあたります。
「対価」という名称の通り、性的な要求への対応が、労働者にとっての利益・不利益と直接的に結びつけられるのが特徴です。地位や権限を利用して行われることが多く、パワハラ的な要素を併せ持つ典型的なハラスメントです。
環境型セクシュアルハラスメント
労働者の意に反する性的な言動によって、職場の環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮に重大な悪影響が生じるなど、就業する上で見過ごせない程度の支障が生じる行為を指します。
具体的には、職場で性的な内容の会話や噂話を執拗に繰り返す、業務に不要なヌードポスターなどを掲示する、必要なく身体に触れる、食事やデートにしつこく誘うといった行為が該当します。
この類型では、直接的な労働条件上の不利益は伴いませんが、被害者が精神的な苦痛を感じ、仕事への集中力が削がれるなど、職場環境そのものが悪化します。
行為者の意図に関わらず、相手が不快に感じればセクハラと見なされる可能性があります。

労務トラブルの芽が育たぬうちに。早めに対応を。
「パワハラ(パワーハラスメント)」という言葉が浸透し、誰もがパワハラは行ってはいけない行為であることは認識しているはずです。それにも関わらず、残念なことにパワハラの相談件数は増加しているのが現状です。さまざまな仕事への価値観の変化、働き方をはじめとした就業上の変化もあるでしょう。しかし経営層の認識・理解不足や、上司などのハラスメント認識・理解不足も、その要因になっているといえます。こうした状況を受け、法規制を強化し、企業に対策を講じることを義務化したのです。
厚生労働省:令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況
民事上の個別労働紛争|相談内容別の件数
厚生労働省が毎年公表している「個別労働紛争解決制度の施行状況」を見ると、企業のハラスメントの現状が浮き彫りになります。
全国の総合労働相談コーナーに寄せられる相談のうち、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は、2012年度以降、一貫してトップを占め続けています。近年のデータでもその件数は年間8万件を超えており、全相談件数の中でも突出して高い割合を占めています。
この数字は、氷山の一角に過ぎない可能性も指摘されており、社内で声を上げられずにいる潜在的な被害者も多数存在すると考えられます。労働者が外部の公的機関に相談せざるを得ない状況が、これだけ多く発生している現実を企業は重く受け止める必要があります。
民事上の個別労働紛争|主な相談内容別の件数推移(10年間)
2020年6月、労働施策総合推進法施行により、大企業の職場におけるパワハラに関する個別労働紛争は同法に基づき対応することとなったため、計上されていません。
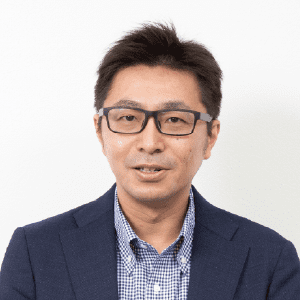
コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
ハラスメントは、しばしば当たり前の基準によって引き起こされます。年齢や性別、立場によって当たり前が違います。それによってお互いが善意だとしても起こるのがハラスメントです。もちろんそのハラスメントの定義も人によって変わってきます。ハラスメント撲滅の第一歩は、当たり前の基準や意識の統一だと心得ましょう。

2025年最新の法改正について見ていきましょう。
職場におけるハラスメント対策は、パワハラ防止法への対応だけで完結するものではありません。
社会情勢の変化に伴い、企業に求められる責任の範囲は広がり続けています。
2025年現在、特に注目すべきは、顧客などからの著しい迷惑行為である「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策強化や、就活生やフリーランスなど、直接雇用関係にない人々へのハラスメント対策です。
これらの動向は、企業が目を向けるべき範囲が社内から社外へ、そして従業員から関係者全体へと拡大していることを示しています。
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の強化
顧客や取引先からの暴言、威嚇、不当な要求といった著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)から従業員を守ることも、企業の重要な責務です。
2025年時点では、カスハラ対策を直接的に義務付ける法律はありませんが、厚生労働省が企業向けの対策マニュアルを公表するなど、国として企業の自主的な取り組みを強く推奨しています。
企業は労働契約法上の安全配慮義務に基づき、従業員の心身の健康を守る義務を負っており、カスハラを放置することはこの義務に違反すると判断される可能性があります。
具体的な対策としては、対応方針の明確化と社内周知、従業員向けの研修実施、相談窓口の設置、悪質なケースに対応するための組織体制の整備などが求められます。
就活生などに対するハラスメント対策の義務化
従来のハラスメント防止法は、主に企業と直接雇用関係にある労働者を保護の対象としていました。
しかし、法改正により、その対象範囲は拡大しています。
現在、事業主は、自社が雇用する労働者だけでなく、就職活動中の学生やインターンシップ生、さらにはフリーランスなどの個人事業主といった人々に対するハラスメントに関しても、相談に応じ、適切に対応するための体制を整備することが望ましいとされています。
採用選考の過程における面接官の不適切な言動(就活セクハラなど)も、企業の責任問題に発展しかねません。
採用担当者への教育を徹底し、万が一の際に相談できる窓口をこれらの関係者にも周知しておくことが重要です。

ハラスメントを放置したらどんなリスクがあるのでしょうか。
ハラスメント防止対策は、単なる法令遵守や福利厚生の一環ではありません。これは企業の存続に関わる重要なリスクマネジメントです。
職場で発生したハラスメントを一件の問題として軽視し、適切な対応を怠った場合、企業は法的な責任追及を受けるだけでなく、事業の継続を困難にするほどの多岐にわたる深刻なリスクに直面します。
ここでは、ハラスメントを放置した際に企業が被る具体的なリスクを、「損害賠償責任」「企業イメージの低下」「生産性の低下」という3つの側面から解説します。
損害賠償責任の発生
職場でハラスメントが発生した場合、被害を受けた従業員から損害賠償を請求される法的なリスクがあります。
加害者本人が不法行為責任(民法709条)を負うのはもちろんのこと、企業も「使用者責任(民法715条)」や「安全配慮義務違反(労働契約法5条)」を問われる可能性があります。
使用者責任とは、従業員が業務に関連して他者に与えた損害について、企業も連帯して賠償責任を負うというものです。
また、安全配慮義務とは、企業が従業員の生命や健康を危険から守るように配慮すべき義務のことで、ハラスメントの発生を予見できたにもかかわらず放置した場合は、この義務に違反したと判断されます。
裁判に発展した場合、高額な賠償金の支払いを命じられるケースも少なくありません。
企業イメージの低下と人材流出
ハラスメントの事実が外部に漏れた場合、企業の社会的信用やブランドイメージは著しく損なわれます。
特に現代では、SNSや口コミサイトによって情報は瞬時に拡散されるため、「ブラック企業」という評判が一度立つと、その払拭は容易ではありません。
企業イメージの低下は、製品やサービスの不買運動、取引先からの契約打ち切りなど、直接的な業績悪化につながります。
さらに深刻なのが、人材の流出と採用難です。
ハラスメントが横行する職場環境に嫌気がさし、優秀な人材が次々と離職していく一方で、悪い評判が原因で新たな人材の確保も困難になります。
結果として、組織全体の活力が失われていきます。
職場環境の悪化による生産性の低下
ハラスメントは、被害者個人の問題に留まらず、職場全体の環境を悪化させ、生産性を著しく低下させます。
被害者は精神的な苦痛から本来の能力を発揮できなくなり、休職や退職に至ることもあります。それだけでなく、ハラスメントを日常的に見聞きしている周囲の従業員も、強いストレスを感じ、会社に対する不信感を募らせます。
職場全体の士気が下がり、従業員間のコミュニケーションが希薄になることで、円滑な業務連携が阻害され、チームワークは崩壊します。自由闊達な意見交換が行われなくなり、新たなアイデアやイノベーションも生まれにくくなるなど、組織の成長が停滞する大きな原因となります。

企業の講ずべき措置について、解説していきます。
パワハラ防止法には、3つのパワハラに関する定義はあるものの、職場のトラブルは個別の状況・事情が複雑に絡み合っているものです。「上司に大声で叱責された。パワハラだ!」というわけにはいきません。中立的な第三者が相談者、行為者の双方から丁寧に事実確認していくことが必要です。そのためには、企業としてパワハラを防止するための視点、もしもパワハラが発生してしまった時の対応の視点、両面から対策を講じることが重要です。ハラスメントのない職場づくりのために、企業が講ずべき措置はどのようなものでしょうか。
パワハラ防止に関するトップメッセージ
企業のトップがパワハラ防止についての重要性を発信します。パワハラを許さないという企業姿勢を示すことになります。また、メッセージは機会あるごと、定期的に行うことも必要です。
社内方針の明確化
企業としてパワハラをはじめとしたハラスメントにどのような姿勢で臨むのか方針を明確にし、社員へ周知しなくてはなりません。まずはパワハラの定義やどういう言動や行為がパワハラに該当するのか、社員に理解してもらう必要があるでしょう。教育研修などで正しく理解してもらい、周知していきます。パワハラを行った社員に対する処罰の内容も、就業規則等に明記すべきでしょう。それには、企業側・社員側双方がどのような取り組みを進めていくのか、具体的な内容をしっかりと協議していくことが大切です。就業規則等に明記する場合には、労働者代表の意見聴取も必要です。また、就業規則等に明記する場合には、全社員へしっかりとアナウンスしていくことも重要です。
社内体制・苦情相談窓口などの設置
パワハラ被害を受けた社員が安心して相談できる窓口を設け、広く周知しましょう。そのための社内体制も必要です。パワハラ被害者に対するケア、プライバシー保護に関する対応も重要です。被害を訴えたことで不利益な取り扱いがされないようにしなければなりません。
ハラスメント状況の社内実態把握
パワハラ被害の訴えがあった場合には、中立的な立場の人が、双方の視点から丁寧に実態を調査することが重要です。また、パワハラ被害の訴えはなくても、職場の実態としてハラスメント被害が発生していないか把握することも必要です。
例えば、アンケートなどを実施し実態把握に努めます。記名でも匿名でも構いませんが、実態把握の場合は、匿名のほうが本音が聞きやすい場合もあるでしょう。
社員教育の実施
定期的に行うべきは、ハラスメント予防研修の実施です。管理職、一般社員等によって、研修内容は異なってくるでしょう。ハラスメント事例などを盛り込みながら、理解・認識をより深めてもらう機会としましょう。
再発防止策の実施
残念ながら、パワハラ被害が発生してしまったら、再発防止のための対策が重要です。パワハラ被害は、安易に考えていると大きな問題にも発展しますし、人材の流出にもつながりかねません。ハラスメント被害が発生していたにも関わらず、適切な対応や再発防止策を実施しなければ、場合によっては安全配慮義務違反として責任を問われたり、損害賠償請求などにもなりかねません。
今回、パワハラ防止対策が義務化された労働施策総合推進法では、厚生労働大臣が必要と判断した場合、企業に助言・指導、勧告を行うことができるとしています。それに反いた場合には、内容が公表されることになります。また、虚偽の報告などを行った場合には罰金を科すことも定められています。
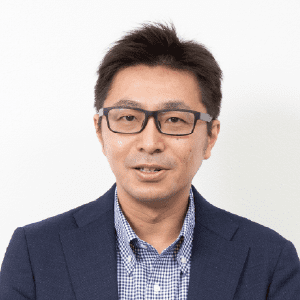
コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
万が一、ハラスメントの通報を受けた場合の、初動は「調査」です。初動で同意をしてしまうと、後日事実誤認であった場合に、解決が非常に難しくなります。調査をする前から通報者の訴えを鵜呑みにしないように気を付けましょう。

ハラスメントが発生した際、企業がとるべき対応を見ていきましょう。
どれほど万全な予防策を講じていても、ハラスメントの発生を100%防ぐことは困難です。
そのため、実際に相談が寄せられた際に、パニックに陥ることなく、迅速かつ適切に対応できる体制と手順をあらかじめ定めておくことが極めて重要です。
初期対応のまずさは、問題をより複雑化させ、企業が負うリスクを増大させかねません。
ここでは、相談受付から再発防止措置の実施まで、企業が取るべき一連の対応フローを時系列で具体的に解説します。
このフローを社内で共有しておくことが、有事の際の冷静な対応を可能にします。
事実関係の迅速かつ正確な確認
相談窓口にハラスメントの申し出があった場合、まず最初に行うべきは、予断や先入観を排した中立的な立場での事実確認です。
担当者は、相談者のプライバシー保護に最大限配慮しながら、いつ、どこで、誰から、どのような言動があったのかを具体的にヒアリングします。
次に、相談者の了解を得た上で、行為者とされる人物からも事情を聴取します。
この際、どちらか一方の主張を鵜呑みにせず、双方から客観的な事実を聞き出すことに徹します。
必要に応じて、周囲で状況を見ていた可能性のある第三者からも話を聞くなど、慎重に調査を進めます。
メールのやり取りや録音データなどの客観的な証拠があれば、それらも確認します。
迅速さと正確性の両立が求められます。
被害者・行為者への適切な措置
事実確認の結果、ハラスメント行為があったと客観的に認められた場合、速やかに被害者と行為者のそれぞれに対して適切な措置を講じます。
被害者に対しては、まず会社として謝罪するとともに、精神的なケアが必要であれば産業医やカウンセラーとの面談をセッティングします。
また、行為者と顔を合わせることなく安心して就業できるよう、席の移動や配置転換といった環境改善措置を検討します。
一方、行為者に対しては、就業規則の懲戒規定に基づき、行為の悪質性や被害の程度に応じて、けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇といった処分を公平に下します。
処分内容は、事案とのバランスを欠かないよう慎重に決定する必要があります。
再発防止措置の実施
個別の事案に対する措置が完了したら、必ず組織全体としての再発防止策を実施します。
これは、同様の問題が二度と発生しないようにするための最も重要なプロセスです。
具体的には、全社に向けて改めてハラスメント防止の方針を周知徹底し、経営トップからメッセージを発信します。
また、今回の事案から得られた教訓を反映させた研修を、管理職を含む全従業員を対象に実施します。
その際、プライバシーに配慮し、個人が特定されない形で情報を共有します。
さらに、今回の対応プロセスを振り返り、相談窓口の機能や調査手順に改善すべき点がなかったかを検証し、必要に応じて運用を見直します。
根本的な職場環境の改善に取り組む姿勢が不可欠です。

人事労務のお悩み事・ご相談に幅広くサポートします。
ハラスメントは受け取り方次第、という声もあります。「業務上で必要な指導を行ったにも関わらず、部下にパワハラだと訴えられるから、注意できない」といったケースも、よくある話です。ですが、本来の業務上の指導であれば、問題ないのです。企業は、この指導が業務上必要であり、社会一般に照らしても相当であると説明できればよいのです。逆に、説明がつかないようであれば、ハラスメントの可能性があるということになるわけです。
パワハラをはじめとしたハラスメントは、被害者、行為者双方が社員であるというケースがほとんどです。被害者を発生させないことはもちろん、ハラスメントの無理解から行為者を発生させないためにも、適切な社員教育や周知、対応策を実施していきましょう。ただし、ハラスメントの定義づけは広く、それぞれの業種、職種、業務内容、個人の環境などによっても一概に判断できない部分も多くあります。感情がこじれてしまうケースも多いでしょう。小規模の会社では、社内だけでの対応では事態が悪化することもあるかもしれません。ときには、社会保険労務士など専門家のアドバイスも取り入れながら、予防策・対応策を検討してみることをおすすめします。
弊社でも、ハラスメントの対策のアドバイスやハラスメント研修を実施しています。
お困りの際は、ご相談ください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」