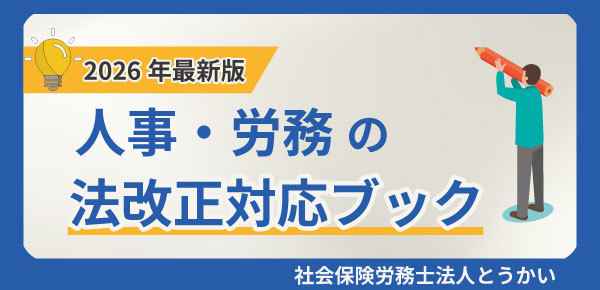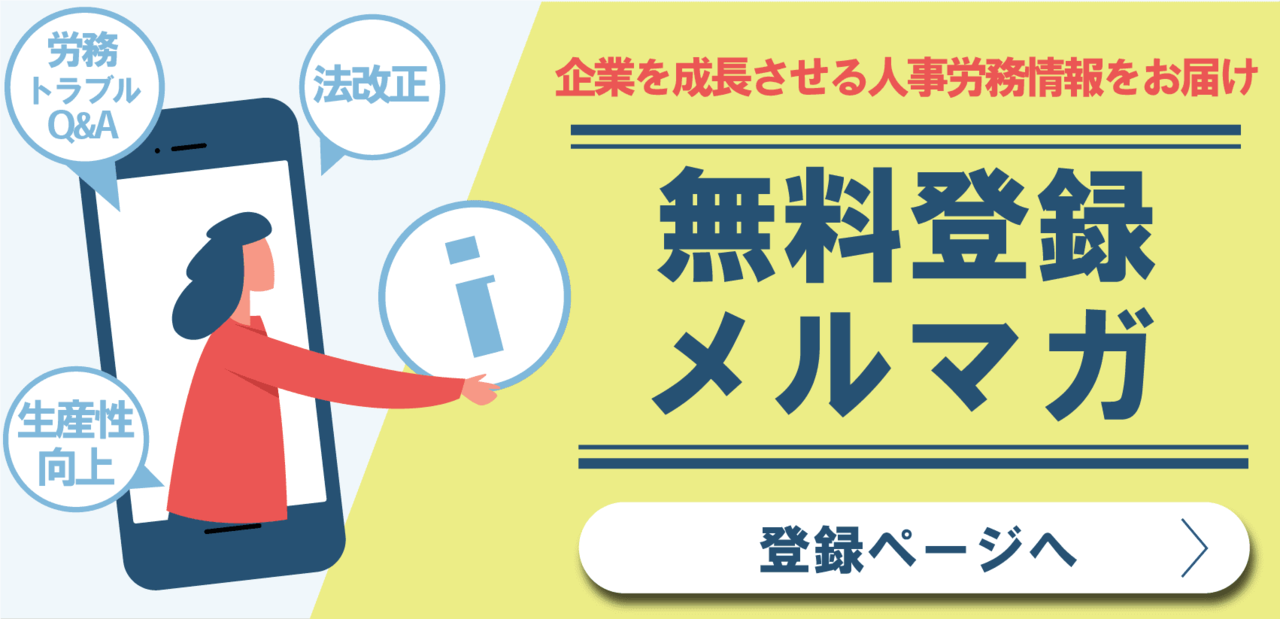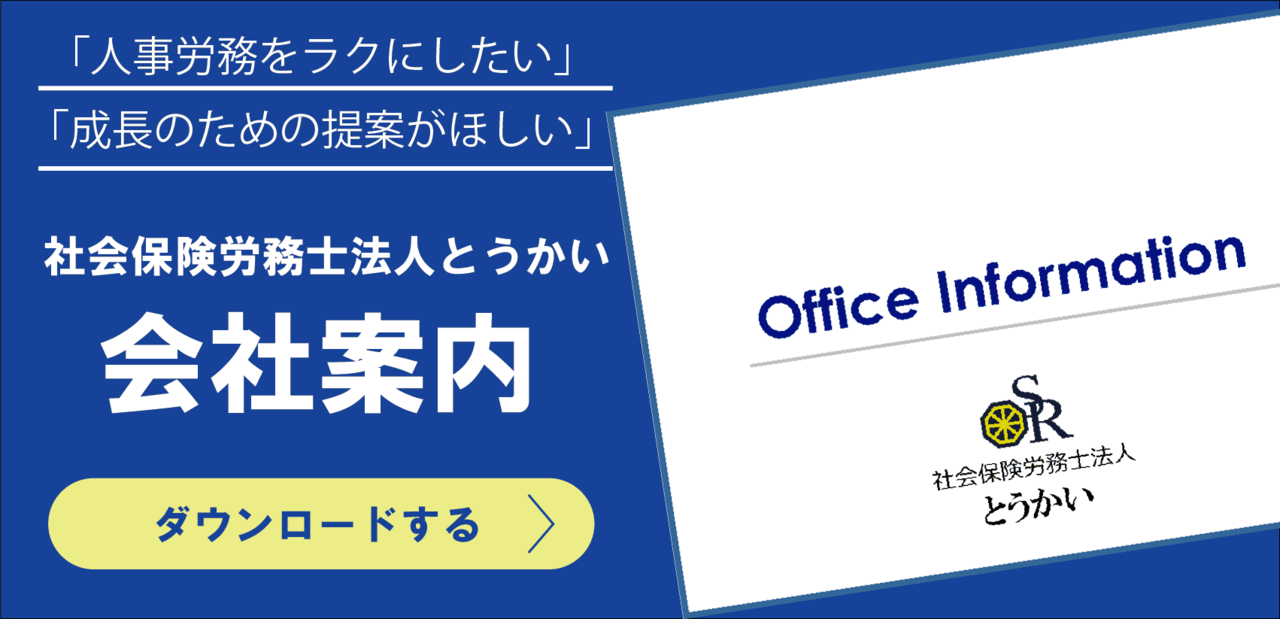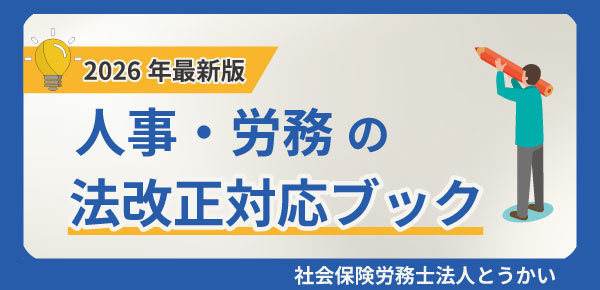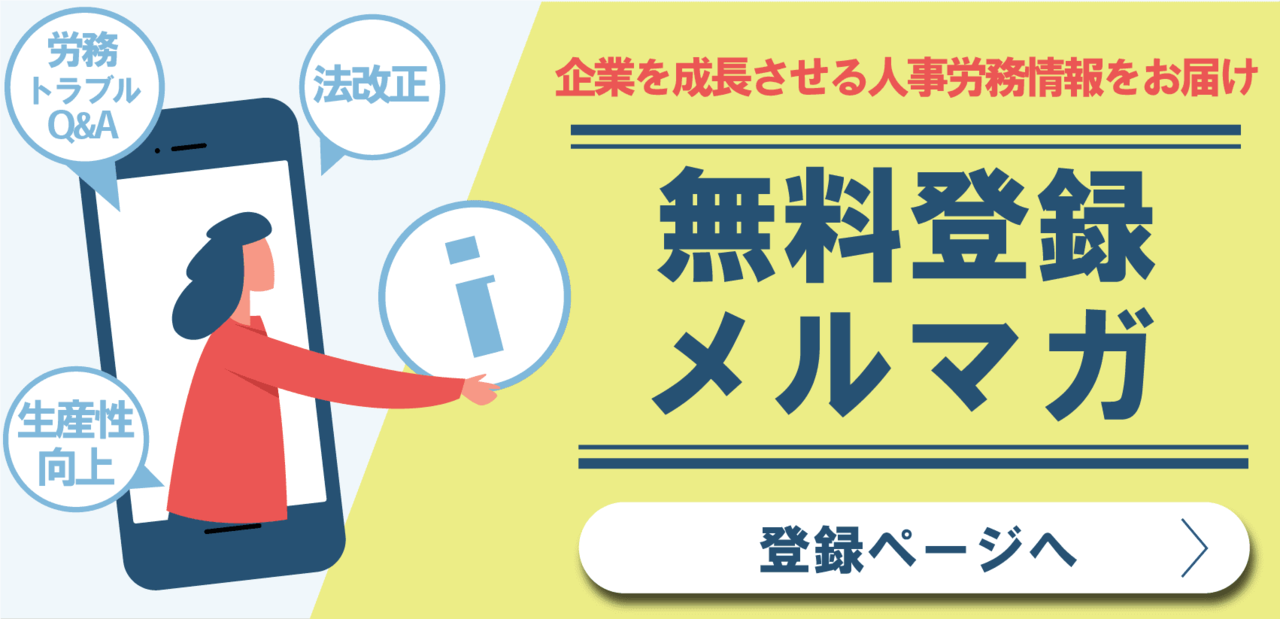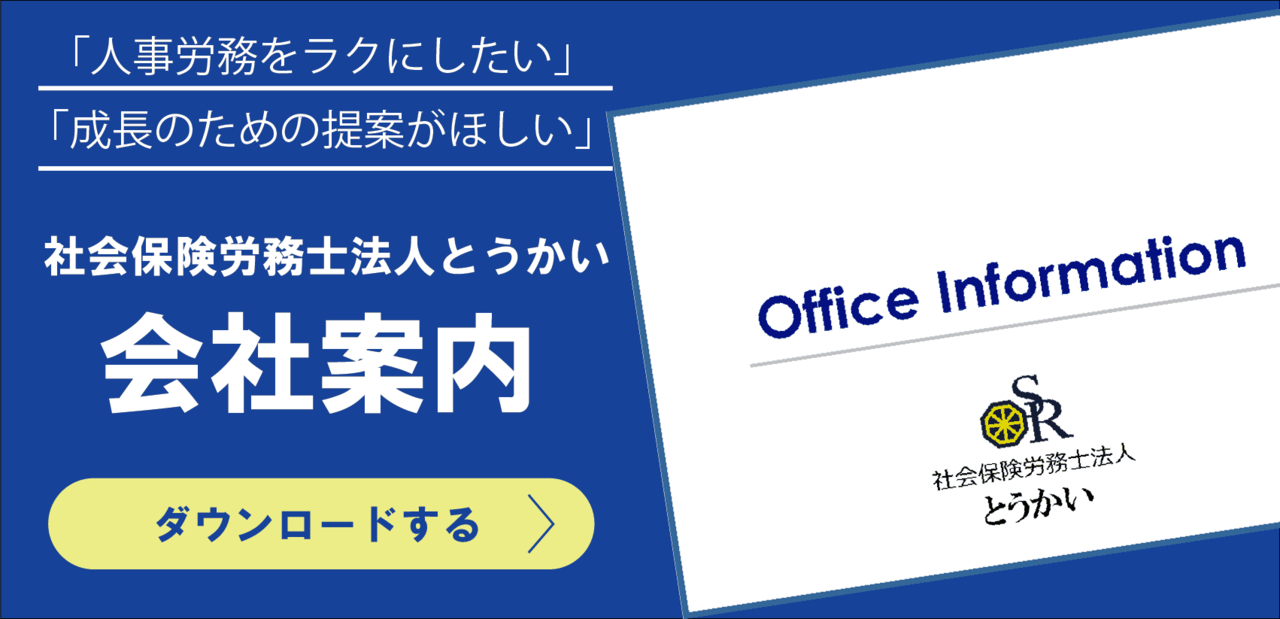教育訓練休暇給付金(10月開始)のための休暇制度規程|対象者や要件を解説

2025年10月1日から、労働者の主体的な学び直しを支援する「教育訓練休暇給付金」制度が始まります。
この制度は、従来の教育訓練給付金とは異なり、在職中に長期の休暇を取得して教育訓練を受ける労働者が対象です。
企業は、この給付金の活用を可能にするため、就業規則等で休暇制度を整備する必要があります。
本記事では、制度の概要から対象者の要件、企業が規程に定めるべきポイント、申請手続きまでを詳しく解説します。
▼わかりやすく解説した動画はこちらから▼
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

教育訓練休暇給付金について知っていますか?
教育訓練休暇給付金は、労働者が自発的に教育訓練を受けるために30日以上の長期休暇を取得した場合に、その間の所得を保障するために新設される雇用保険の給付金です。
この制度は、労働者の主体的なキャリア形成やスキルアップを促進し、雇用の安定を図ることを目的としています。
企業が就業規則や労働協約に基づき教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその制度を利用して休暇を取得・教育訓練を受講することが給付の前提となります。
企業にとっては、従業員のスキル向上を後押しすることで、生産性の向上や組織全体の成長につなげる機会となり得ます。

給付金の対象となるのは、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者で、被保険者期間が5年以上ある方です。
ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その支給決定日から5年以上経過している必要があります。
また、この制度は労働者の自発的な意思に基づく休暇取得が前提であり、事業主の命令による教育訓練は対象外です。
年齢の上限は設けられていませんが、65歳以上の高年齢被保険者も対象に含まれます。
これらの要件を満たす労働者が、会社の就業規則に定められた教育訓練休暇制度を利用して、指定された教育訓練を受ける場合に給付金の対象者となります。

支給額は、原則として休暇開始前の6か月間に支払われた賃金から算出した「賃金日額」に相当する額が、休暇日数分支払われます。
この賃金日額には上限と下限が設定されています。
給付を受けられる日数は、実際に取得した教育訓練休暇の日数に応じて決まり、被保険者期間が5年以上10年未満の場合は最大90日、10年以上の場合は最大120日が上限です。
これは、教育訓練休暇を取得して訓練を受けている期間の生活を支えるためのものであり、労働者は経済的な不安を軽減しながらスキルアップに集中することが可能になります。
具体的な金額は個々の賃金によって変動するため、ハローワークで確認することが推奨されます。

整備すべき規程について見ていきましょう。
この給付金の対象となる教育訓練休暇は、企業が就業規則等で制度として定めている必要があります。
育児休業などと同様に、法律で定められた休暇ではなく、企業が任意で設ける法定外の休暇制度です。
そのため、制度を導入する企業は、給付金の要件を満たす形で休暇制度の内容を明確に規程として整備しなければなりません。
ここでは、企業が休暇制度を設ける際に、就業規則等に定めるべき4つの重要なポイントについて解説します。
教育訓練休暇給付金制度の根幹は、労働者の主体的なキャリア形成を支援することにあります。
そのため、休暇の取得は、労働者本人からの自発的な申し出によって開始される必要があります。
企業側からの一方的な指示や命令による教育訓練は、この給付金の対象とはなりません。
就業規則には、労働者が所定の手続きに則って休暇を申請し、それに対して事業主が業務の状況などを考慮した上で承認するというプロセスを明記することが重要です。
この手続きを定めることで、制度の趣旨に沿った適切な運用を確保し、労使双方の認識の齟齬を防ぎます。
給付金の対象となる教育訓練休暇は、30日以上の連続した期間であることが要件です。
これは、短期的な講習ではなく、一定期間を要する本格的な教育訓練への参加を想定しているためです。
分割して取得することは認められておらず、1回の申し出でまとまった日数の休暇を取得する必要があります。
したがって、企業は就業規則において、休暇の取得単位が30日以上であることを明確に規定しなければなりません。
この要件は、労働者が腰を据えて学習に専念できる環境を保障するための重要な定めとなります。
教育訓練休暇は、その都度の労使間の合意や、事業主の温情的な措置として与えられるものではなく、就業規則や労働協約によって制度として確立されている必要があります。
つまり、休暇の取得要件、期間、手続き、賃金の取り扱いなどが、全従業員に適用されるルールとして文書化されていなければなりません。
これにより、従業員は誰でも公平に制度を利用する権利を持つことが保障されます。
企業は、既存の就業規則に「教育訓練休暇」に関する章や条項を新たに追加し、その内容を具体的に定めることで、給付金の要件を満たす制度を構築することになります。
休暇の目的は、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講することに限定されます。
具体的には、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練などが対象となります。
趣味や教養目的の講座は対象外です。
企業は就業規則において、休暇の取得目的をこれらの指定された教育訓練の受講に限定する旨を明記する必要があります。
労働者がどのような訓練を受ける場合にこの休暇制度を利用できるのかを明確にすることで、制度の不正利用を防ぎ、本来の趣旨であるキャリアアップ支援に資する運用を徹底することが求められます。

2025年10月の制度開始に向けて、企業の人事・労務担当者は計画的な準備を進める必要があります。
単に就業規則を改定するだけでなく、従業員が制度を円滑に利用できるような環境を整えることが重要です。
具体的な準備としては、就業規則の整備、従業員への周知、そして休暇取得者が出た際の業務体制の検討などが挙げられます。
これらの準備を事前に進めておくことで、制度開始後のスムーズな導入と運用が可能になります。
教育訓練休暇給付金の活用には、就業規則に教育訓練休暇制度を設けることが不可欠です。
具体的には、休暇の目的、対象となる従業員の範囲、休暇期間、取得手続き、休暇中の賃金の取り扱い(無給とするのが一般的)などを明確に規程として追加する必要があります。
特に、給付金の要件である「労働者の自発的な申し出」や「30日以上の連続した休暇」といった点を盛り込むことが重要です。
就業規則の変更後は、労働基準監督署への届出も忘れずに行わなければなりません。
法的な要件を満たした規程を整備することが、制度導入の第一歩となります。
教育訓練休暇制度を導入後は、その内容を全従業員に広く周知することが重要です。
社内ポータルサイトへの掲載、説明会の開催、資料の配布など、様々な方法を通じて制度の目的や利用方法、利用できる教育訓練の種類などを丁寧に説明します。
従業員が制度の存在を知り、内容を正しく理解することで、キャリアアップを目指す従業員の積極的な活用が期待できます。
相談窓口を設けるなど、従業員が気軽に質問できる体制を整えることも、制度の定着には効果的です。
従業員が30日以上の長期休暇を取得する場合、その間の業務をどうカバーするかは企業にとって重要な課題です。
休暇取得者が出ることを想定し、代替要員の確保や、チーム内での業務分担の見直し、引き継ぎのマニュアル化など、業務が停滞しないための体制を事前に構築しておく必要があります。
特に専門性の高い業務の場合は、代替要員の育成に時間がかかる可能性も考慮しなければなりません。
休暇取得を希望する従業員が安心してスキルアップに臨めるよう、職場全体でサポートする体制を整えることが、制度を形骸化させないために不可欠です。

教育訓練休暇給付金は雇用保険制度の一部であるため、他の給付金との併給は基本的にできません。
例えば、離職後に支給される基本手当(失業手当)や、育児休業中に支給される育児休業給付金、介護休業中に支給される介護休業給付金などとは同時に受給することは不可能です。
教育訓練休暇の期間中は在職している状態ですが、万が一、休暇中に離職するなどの状況変化があった場合は、どの給付を優先するか慎重に検討する必要があります。
労働者が不利益を被らないよう、企業の人事担当者は、これらの制度間の関係性を理解し、必要に応じて従業員に情報提供できる準備をしておくことが望ましいです。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」