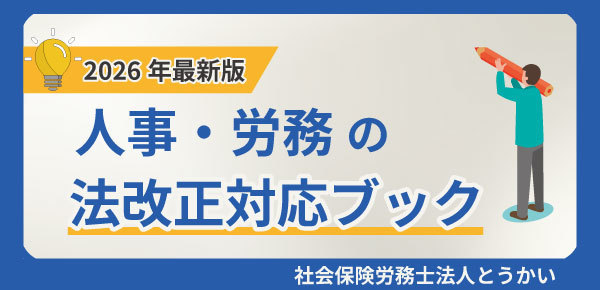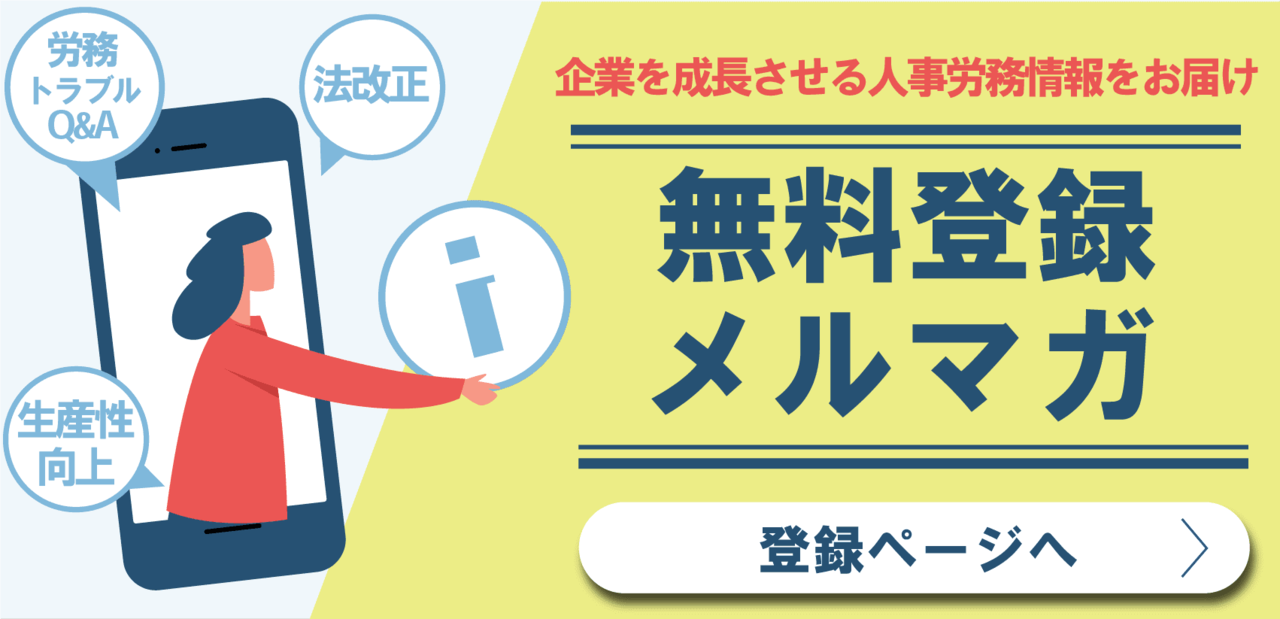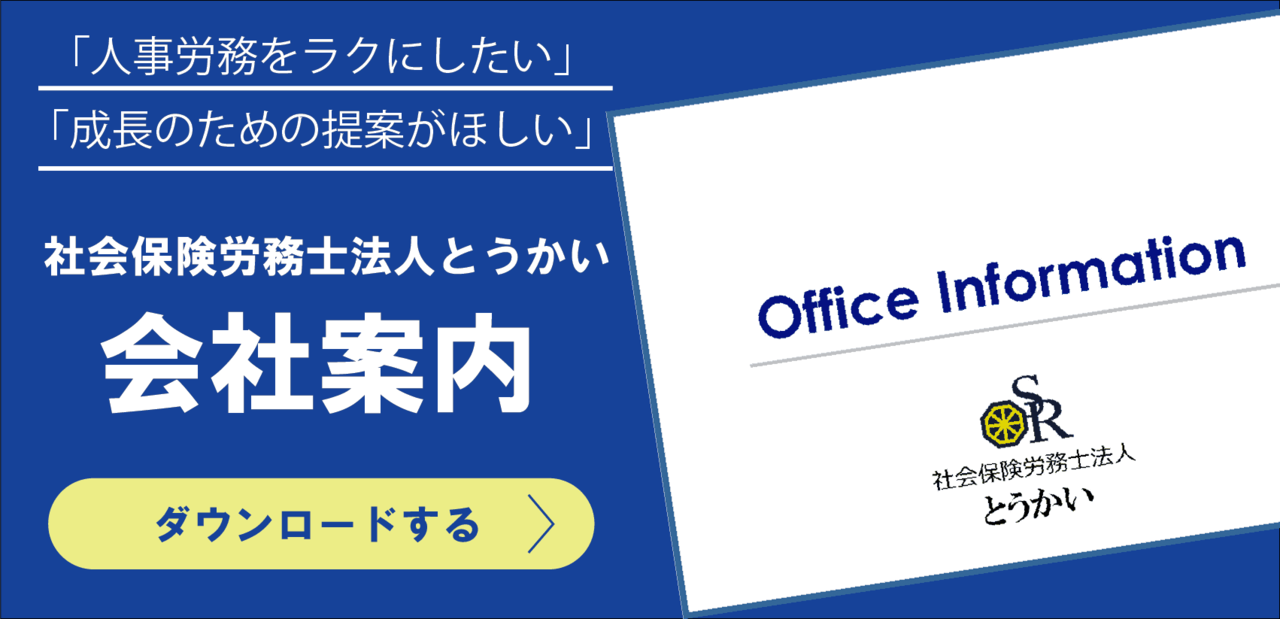給与所得控除とは?給与所得の計算方法や所得控除との違いについて社労士が解説します。


給与所得控除がどのようなものか、計算方法や他の所得控除との違いについて詳しく解説します。
給与所得控除とは、給与に関わる所得税の計算に用いる控除です。
所得税の計算には、給与所得控除以外にも、扶養控除や住宅ローン控除などがあります。これらの控除は個々の生活状況や支出の内容に応じて適用されるため、自分にどの控除が適用可能かを理解することが重要です。この控除により、実際に課税される所得額が減り、結果的に支払う所得税も少なくなります。
今回は給与所得控除がどのようなものか、計算方法や他の所得控除との違いについて詳しく解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

給与所得控除について詳しく解説します。
給与所得控除は、給与に関わる所得税の計算に用いる控除する制度です。給与所得者の給与総収入から一定額を控除し、課税対象となる所得金額を算出します。給与所得控除することで、課税所得が減り、結果的に支払う所得税が軽減されます。給与所得控除は他の所得控除と異なり、給与収入にのみ適用される特別な控除です。この制度により、労働者は公平な所得税計算が行われます。
給与所得控除の目的は、給与所得者の税負担を軽減し、納税の公平を図るために設けられています。この制度によって、同じ収入レベルの給与所得者の税負担の公平性が保たれます。
具体的には、給与所得控除が適用されると、全ての給与受取人がほぼ同額の控除を受けることで、異なる収入源を持つ者との間の不公平感を無くすことができます。生活費や社会参加に必要な最低限の手取り収入を保障し、経済的安定を支援します。この控除により必要な支出をまかないやすくなるため、消費活動の活発化と経済全体の発展に寄与する効果も期待されています。
給与所得控除は、税金の軽減だけでなく、給与所得者の生活を支え、経済活動を促進する重要な役割を果たしています。そのため、給与所得者はこの制度を理解し、適切な申告を行う必要があります。
給与所得控除は給与収入のみに適用されます。
給与所得控除は、正社員や契約社員をはじめアルバイトやパートを含むさまざまな雇用形態のすべての労働者に適用される減税措置で、給与収入がある場合にのみ利用できます。自営業者やフリーランスなどの事業所得やその他の所得を得ている人には、この控除は適用されません。自営業者等が所得税を計算する際には、総収入から必要経費を差し引き課税所得を算出することになります。給与所得控除は、この必要経費と同様の意味合いを持ちます。
給与収入のある方は、この給与所得控除を通じて、より多くの給与を手元に残せます。この制度を適切に理解し活用することで、効果的に所得税負担を軽減できるため、自身の給与明細や年末調整の際にこの点を確認することが重要です。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
各種所得控除を適切に理解し活用することで節税が可能です。
給与計算や年末調整を行う担当者はもちろん、給与を受け取る従業員自身についても、所得税に関する知識は理解しておきたいものです。

給与所得控除、所得控除の違いと、節税のポイントを解説します。
給与所得控除と所得控除の違いとの違いについても、それぞれの特徴を具体的に理解して税負担を効果的に軽減しましょう。給与所得控除は給与総収入から一定の額が控除されます。この控除額は年収に応じて変動します。
一方、給与所得控除と名前が似ているもので所得控除があります。所得控除はもう少し広い範囲で適用されます。これは個人の事情に応じた控除制度であり、基礎控除、配偶者控除、医療費控除、社会保険料控除など具体的な支出に基づく15種類の控除が該当します。たとえば基礎控除は全納税者に適用される固定額の控除で、所得税を計算する際に自動的に所得から差し引かれます。配偶者控除は配偶者の収入が一定額以下の場合に適用され、家計への経済的負担を軽減します。また、社会保険料控除は健康保険や国民年金などの保険料を支払った際に、その金額を所得から控除できるもので、実際に支払った保険料に応じて控除額が決まります。
これらの控除を適切に理解し、自分の状況に合わせて最大限活用することで、より多くの税金を節約することが可能です。給与所得者は自分が受けられる全控除をしっかりと確認して、無駄なく税金を納めることが重要です。

所得税の算定の手順・控除タイミングなど、わかりやすく説明します。
給与所得者が年間の所得税を計算する際、理解しておくべき重要な要素が給与所得控除や所得控除です。これらの控除は、所得税の算定の手順・控除タイミングの理解が必要です。
給与所得者の所得税計算には、以下の3ステップに従って算出することになります。
① 給与総収入 ― 給与所得控除 = 「給与所得」
② 給与所得 ― 所得控除 = 「課税所得」
③ 課税所得 × 税率 ― 控除額 = 『所得税額』
給与所得控除額は、給与の収入に応じて定められています。例えば、年収が660万円超850万円以下であれば、給与所得控除額は、収入金額×10%+110万円となりますし、年収が162.5万円以下であれば、55万円の控除が適用されることになります。
【給与所得控除額】
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
「給与所得」を算出したら、続いて該当する所得控除を差し引くことになります。所得控除のうち、基本は基礎控除です。基礎控除額は合計所得金額が2500万円以下の人に48万円が適用されます。また、個人の事情によって、配偶者がいれば配偶者控除を、生命保険料などの支払いがあれば生命保険料控除などが適用になります。
例えば、年収が500万円の場合、
500万円×20%+44万円=144万円
給与所得控除額は144万円です。これは、収入に応じて計算される金額で、全国の給与所得者に同じルールが適用されます。給与所得控除後の課税対象所得は、500万円から144万円を控除した356万円です。この356万円が給与所得となります。この給与所得から所得控除を差し引き、課税所得が計算されます。所得控除が基礎控除のみであれば、
356万円―48万円=308万円
課税所得が308万円となります。
この308万円が所得税計算の基礎となり、所得税率を乗じることになります。
【所得税率】
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
308万円×10%=30.8万円
所得税が30.8万円となります。
所得税の基本をよく理解しておくことは、自分の経済状況を把握し、適切な経済決定をする上で非常に重要です。
給与所得者の皆さんは、自分の年収と給与所得控除額を把握し、効率的な税金管理を行うためにこの情報を活用してください。また、年収が変動した場合には、控除額の再計算が必要になるため注意が必要です。

高谷の経営視点のアドバイス
昨今の給与計算システムであれば、各種の控除額の判定や所得税計算がスムーズに行えます。年末調整業務などで担当者の負荷が大きい場合などは、給与計算システムの利用などを検討することをおすすめします。

給与所得者に認められている「特定支出控除」について説明します。
給与所得者が所得税計算時に利用できるものに、特定支出控除があります。特定支出控除とは、職務上必要不可欠な支出があった場合、判定基準額を超えた分について控除する制度です。例えば、研修費や資格取得に関わる支出が該当します。この制度を活用すると、給与所得者は実際に支払う所得税額を効果的に減少できます。
特定支出控除の正確な計算方法を理解することが、給与所得者にとって非常に重要です。この控除を利用すると、仕事関連の実際の費用を確定申告で控除でき、結果として納税額が抑えることができます。具体的には、営業職の方が支払う交通費や外回り時の飲食代など、職務遂行に直接関連する支出が対象となります。その年の特定支出の合計額が給与所得控除額の1/2相当額が判定基準額となります。
例えば年収500万円で給与所得控除額が144万円の場合には、72万円を超える特定支出分について控除が可能です。
これらの費用は年間を通じて集計し、その総額を確定申告書に記載する必要があります。申告では、各種支出を証明するレシートや領収書の保存が必須です。これらの文書は税務調査を受けた際にも、支出の正当性を示す決定的な証拠となるため、適切な管理をしてください。
特定支出控除を正しく申請することで、給与所得者は自身の経済的負担を軽減し、法令に沿った税務処理を行うことができます。確定申告時には、これらの項目を適切に記載し、適正な控除を受けることが重要です。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」