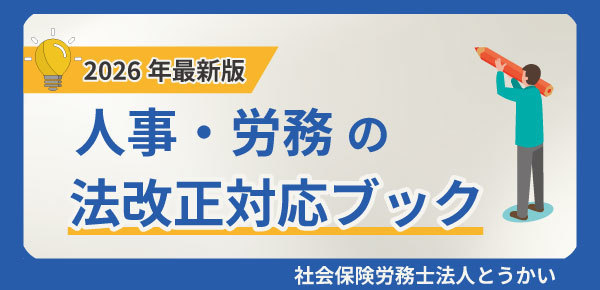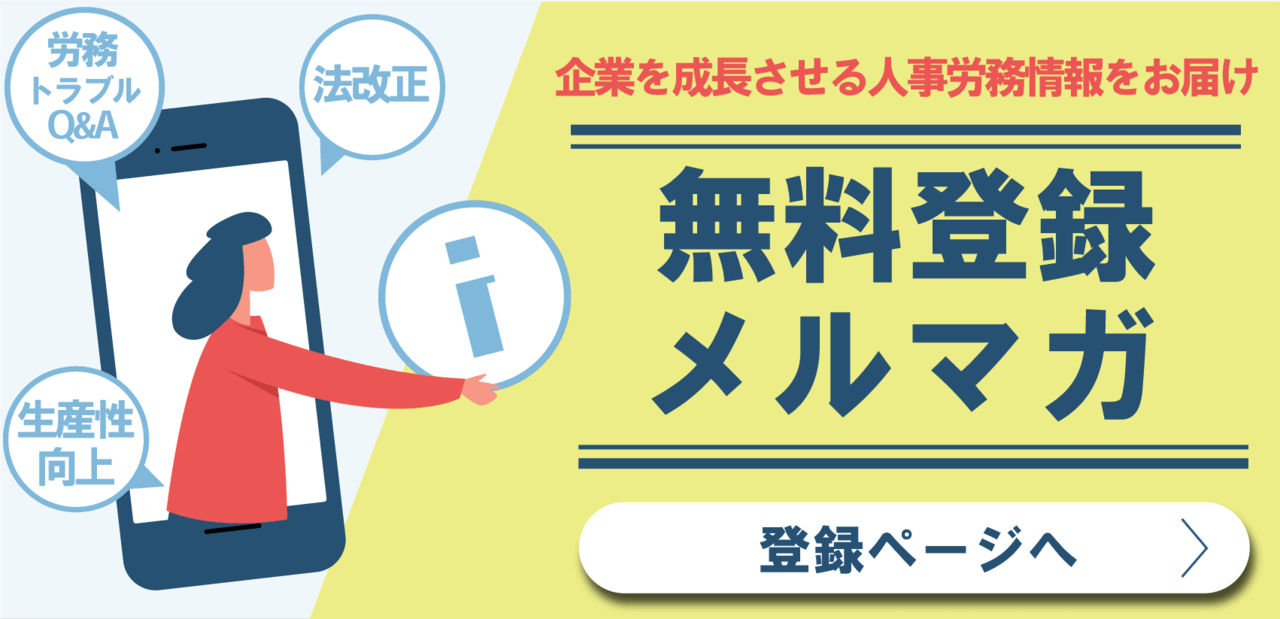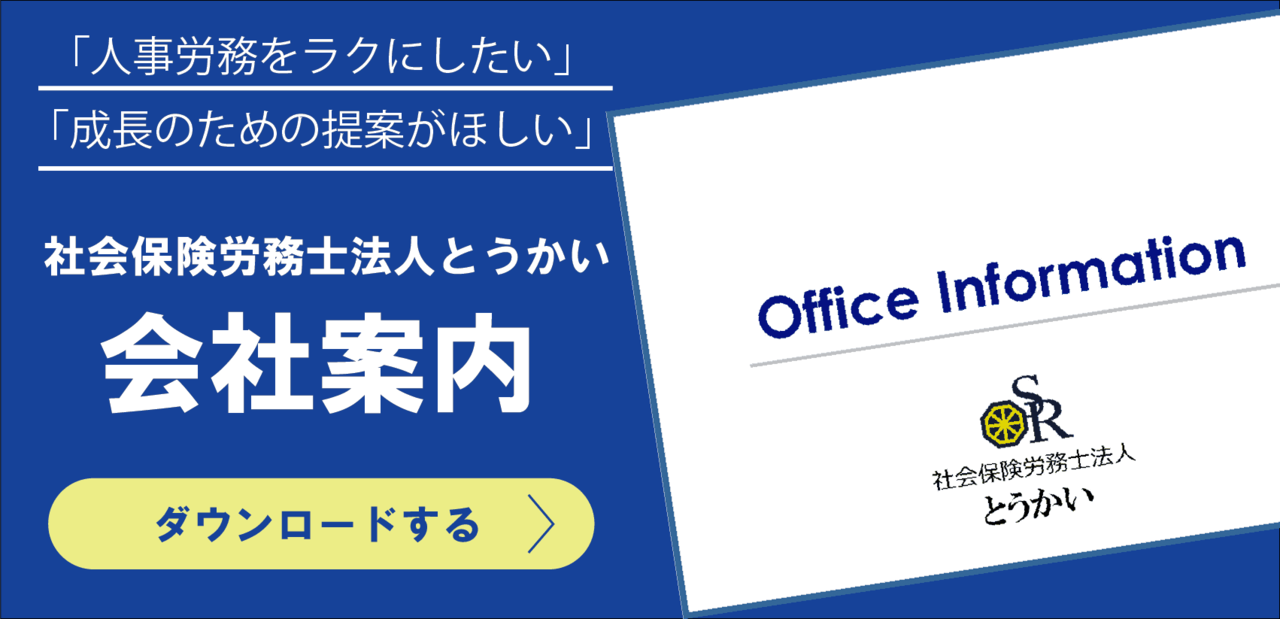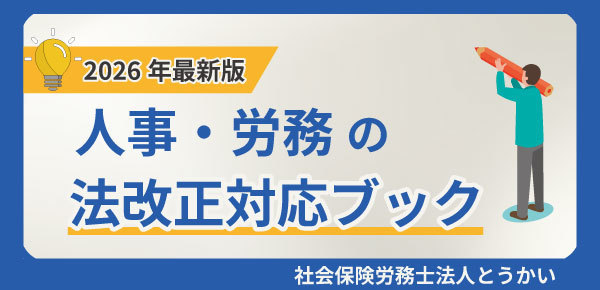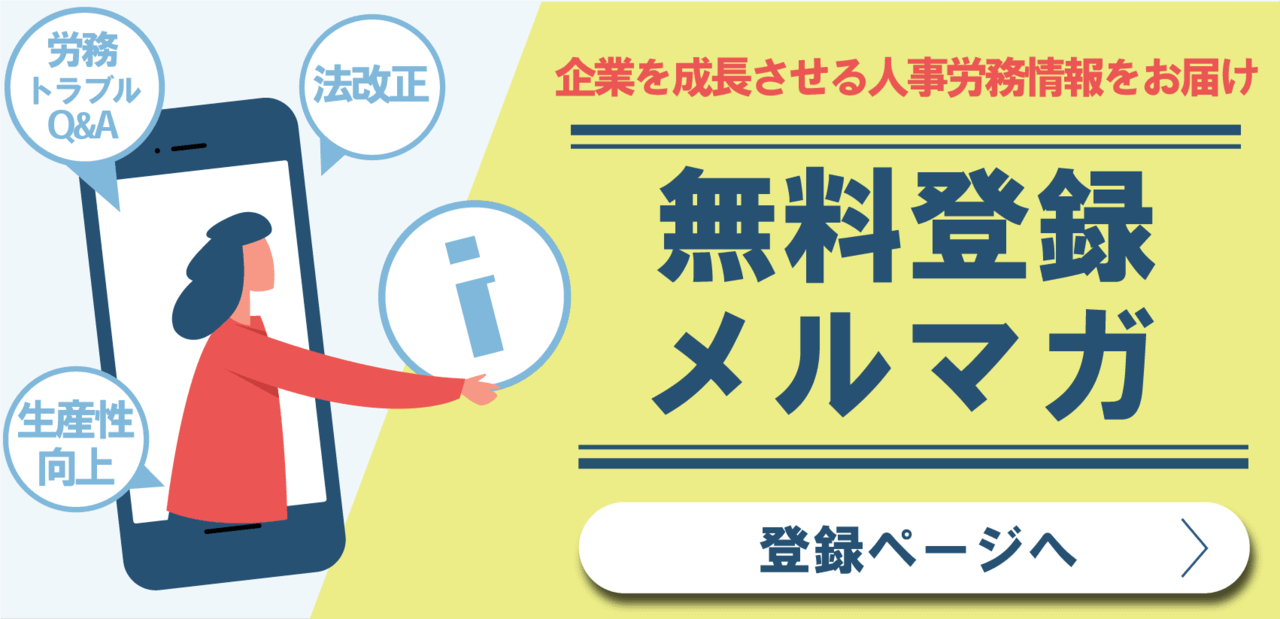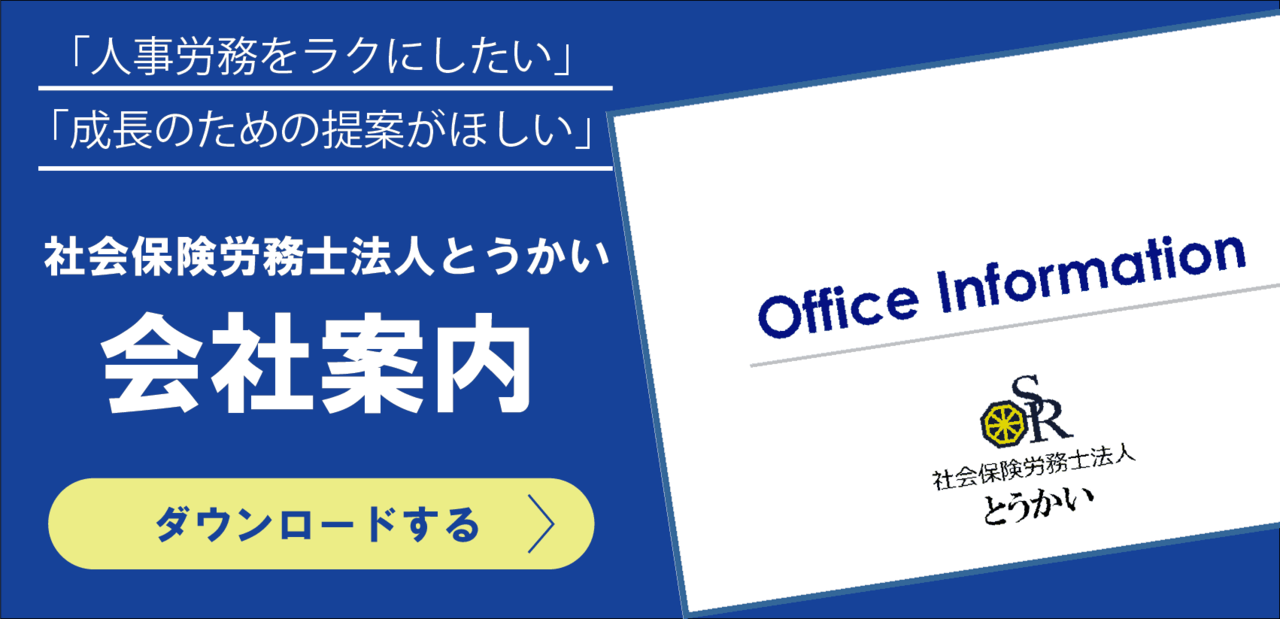企業の成長を支える上で、従業員の貢献意欲を引き出し、組織の目標達成を促進する人事制度の役割は極めて重要です。しかし、事業環境の変化や組織の拡大に伴い、既存の制度が機能しなくなるケースは少なくありません。そうした課題解決のため、専門的な知見を持つ人事制度設計のコンサルティング会社活用を検討する企業が増えています。
この記事では、コンサルティングの基礎知識から会社の選び方、導入プロセス、成功のポイントまでを網羅的に解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

人事制度設計・運用コンサルティングについてご存じですか?
人事制度設計・運用コンサルティングとは、企業の経営戦略やビジョンと連動した人事制度構築を外部の専門家が支援するサービスです。
等級、評価、報酬といった制度の設計から、導入後の運用定着、改善までをトータルでサポートします。
専門家の客観的な視点と豊富な知見を活用することで、自社だけでは気づきにくい課題を可視化し、従業員のエンゲージメントと組織の生産性を高める、実効性のある仕組みづくりを目指します。
人事制度コンサルティングで依頼できる業務は、制度の企画・設計といった上流工程から、導入後の運用・定着支援まで多岐にわたります。
企業の根幹となる等級・評価・報酬制度の新規設計や見直しはもちろん、策定した制度を現場で正しく運用するための評価プロセスの策定も支援範囲です。
また、新制度を円滑に浸透させるための管理職や従業員向けの研修、導入後の効果測定や改善提案といった継続的なサポートも提供されます。
企業の課題やフェーズに応じて、これらのサービスから必要なものを選択、あるいは一気通貫で依頼することが可能です。
人事制度の中核をなすのは、従業員の役割や貢献度を定める「等級制度」、その貢献度を測る「評価制度」、評価結果を処遇に反映させる「報酬制度」です。
コンサルティングでは、企業の経営戦略や事業計画と連動させ、これら3つの制度に一貫性を持たせた設計を行います。
従業員に求める行動や成果を明確にし、それが公正に評価され、報酬として報われる仕組みを構築することで、モチベーション向上と組織目標の達成を促します。
また、事業環境の変化や組織の成長に合わせて既存制度が機能しなくなった場合には、現状分析に基づいた最適な形への見直しも行います。
優れた評価制度を設計しても、それが現場で適切に運用されなければ意味がありません。
コンサルティングでは、目標設定の方法から、期中での進捗確認、期末の評価面談、フィードバックの仕方まで、一連の評価プロセスを具体的に策定し、現場への定着を支援します。
評価者である管理職と被評価者である部下の間で、評価基準の認識齟齬が生まれないよう、評価シートや面談マニュアルなどのツール作成もサポートします。
これにより、評価の客観性と納得感を高め、従業員の成長を促すための運用を実現します。
新しい人事制度を導入する際には、従業員の理解と協力を得ることが不可欠です。
特に、評価者となる管理職には、制度の目的を深く理解し、部下を適切に評価・育成するスキルが求められます。
コンサルティング会社は、管理職を対象とした評価者研修や、部下との1on1ミーティング、フィードバック面談のスキル向上トレーニングなどを実施します。
また、全従業員向けに新制度の概要や目的を伝える説明会やセミナーを開催し、制度変更に対する不安を払拭し、スムーズな移行をサポート。
これにより、制度の形骸化を防ぎ、実効性を高めます。
人事制度は一度導入したら終わりではなく、社会情勢や事業フェーズの変化に応じて、常に最適化していく必要があります。
そのため、多くのコンサルティング会社では、制度導入後の継続的な運用サポートも提供しています。
例えば、導入から一定期間後に従業員意識調査などを実施して効果測定を行い、運用上の課題を抽出します。
その結果を基に、制度の微調整や改善案を提案したり、人事部門からの運用に関する相談に対応したりします。
法改正への対応や新たな人事課題に対するアドバイスなど、長期的なパートナーとして企業の成長を支えます。

人事制度コンサルティングを活用するメリットを解説します。
人事制度の見直しや再構築は、専門的な知識と多くの工数を要する一大プロジェクトです。
これを社内リソースだけで完結させようとすると、様々な壁に直面することがあります。
外部のコンサルティング会社を活用することで、専門家の知見を取り入れた最適な制度構築、客観的な視点による課題発見、そしてプロジェクトに要する時間と手間の削減といった、大きなメリットを享受することが可能になります。
人事制度コンサルタントは、多種多様な業界や企業規模における制度構築の経験と、労働法規や最新の人事トレンドに関する専門知識を有しています。
他社の成功事例や失敗事例、様々なフレームワークに関する知見も深いため、自社の経営戦略や組織文化、従業員の特性といった個別事情を踏まえた上で、実効性の高い最適な制度を設計することが可能です。
社内にはない専門的なノウハウや客観的なデータに基づいた提案を受けることで、属人的な判断を排し、説得力のある制度を構築できます。
長年同じ組織にいると、既存の慣習や社内の人間関係にとらわれてしまい、組織が抱える本質的な課題が見えにくくなることがあります。
コンサルタントという外部の第三者が介入することで、社内のしがらみに影響されることなく、客観的かつ中立的な立場で組織や人事制度の問題点を分析できます。
従業員へのヒアリングや各種データ分析を通じて、経営層や人事担当者自身が気づいていなかった潜在的な課題を浮き彫りにすることが可能です。
この客観的な現状把握が、的確な解決策を導き出すための重要な第一歩となります。
人事制度の設計は、現状分析から課題抽出、方針策定、制度の具体設計、規程整備、導入準備と、多くの工程を要する複雑なプロジェクトです。
人事担当者が通常業務と並行してこれらすべてを担うのは、時間的にも労力的にも大きな負担となります。
コンサルティング会社に依頼することで、確立された手法やノウハウを活用してプロジェクトを効率的に推進してくれるため、制度構築にかかる時間を大幅に短縮できます。
これにより、人事担当者は制度の運用準備や社内コミュニケーションといった、より重要な業務に集中できます。

続いて、デメリットを見ていきましょう。
人事制度コンサルティングは多くのメリットをもたらしますが、一方で活用にあたっては注意すべき点も存在します。
外部の専門家に依頼するため、当然ながらコンサルティング費用が発生します。
また、自社の実情が正確に伝わらなければ、理論上は優れていても現場に合わない制度になるリスクも抱えています。
コンサルタントに依存しすぎると、自社にノウハウが蓄積されにくいという側面も理解しておく必要があります。
人事制度コンサルティングの活用には、外部への委託費用がかかります。
費用は、依頼する業務の範囲、プロジェクトの期間、コンサルティング会社の規模やブランド力などによって大きく変動し、数十万円から数千万円に及ぶこともあります。
限られた予算の中で最大の効果を得るためには、なぜコンサルティングが必要なのか、その投資によってどのようなリターンを期待するのかを明確にすることが不可欠です。
複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と費用の妥当性を慎重に比較検討するプロセスが重要になります。
コンサルタントは人事制度設計のプロフェッショナルですが、依頼企業の事業内容や組織風土、現場で働く従業員の価値観までを最初から熟知しているわけではありません。
企業側が自社の経営課題や組織の実態、現場が抱える問題点などを包み隠さず正確に提供しなければ、一般的な理論に基づいただけで実態にそぐわない制度が設計されてしまう恐れがあります。
コンサルタントをパートナーとして信頼し、密なコミュニケーションを通じて自社の情報を積極的に開示する姿勢が、プロジェクト成功の鍵を握ります。
制度の設計から導入までをコンサルティング会社に任せきりにしてしまうと、プロジェクトが終了した後に、なぜその制度が作られたのかという設計思想や、運用上の細かな注意点などが社内に十分に共有されず、ノウハウが蓄積されないという事態に陥りがちです。
その結果、導入後に問題が発生した際に自社で対応できなかったり、将来的な制度改定を再び外部に依存せざるを得なくなったりする可能性があります。
プロジェクトには自社の担当者も主体的に関与し、コンサルタントから知識やスキルを積極的に吸収する意識を持つことが大切です。

人事制度コンサルティング会社はどのように選べばいいのでしょうか。
人事制度コンサルティングを成功させるためには、自社の課題や目的に最適なパートナーを選ぶことが何よりも重要です。
世の中には数多くのコンサルティング会社が存在するため、どこに依頼すればよいか迷うことも少なくありません。
選定を誤らないためには、依頼したい業務範囲の明確化、自社と類似した実績の確認、運用支援体制の充実度、そして費用体系の透明性という4つのポイントを総合的に評価し、判断することが求められます。
コンサルティング会社によって得意とする領域や提供するサービス範囲は異なります。
現状分析から戦略立案といった上流工程に強みを持つ会社もあれば、具体的な制度設計や研修の実施といった実行支援を得意とする会社もあります。
まずは自社が抱える課題を整理し、「制度のコンセプト設計から手伝ってほしいのか」「評価制度の見直しだけをピンポイントで依頼したいのか」「導入後の運用定着まで長期的に伴走してほしいのか」など、コンサルティング会社に何をどこまで依頼したいのかを具体的にすることが重要。
これにより、提供サービスとのミスマッチを防ぎ、効率的な支援を受けることが可能になります。
最適な人事制度は企業の規模、成長ステージ、業種、従業員構成などによって大きく異なります。
例えば創業期のベンチャー企業と成熟期にある大企業とでは制度に求められる役割や設計思想が全く違います。
そのためコンサルティング会社を選ぶ際には自社と類似した企業規模や業種での支援実績が豊富かどうかを必ず確認するべきです。
過去の具体的な支援事例を聞くことでその会社が持つノウハウや知見が自社の課題解決に活かせるかどうかを判断する重要な材料になります。
ウェブサイトなどで公開されている実績情報を参考にし商談の場でより詳しくヒアリングすると良い。
人事制度は、精巧なものを設計しても、それが現場で適切に運用されなければ価値を発揮しません。
制度導入後こそ、様々な課題や疑問が生じるものです。
そのため、コンサルティング会社を選ぶ際には、制度設計後の運用支援体制がどの程度充実しているかを事前に見極めることが重要です。
評価者研修の実施、運用マニュアルの作成支援、導入後のモニタリングと改善提案、人事担当者からの相談に応じるヘルプデスク機能など、制度を現場に根付かせるための具体的なサポートメニューが用意されているかを確認します。
長期的な視点で伴走してくれるパートナーを選ぶことが成功の鍵です。
コンサルティングにかかる費用は、プロジェクトの難易度や期間、依頼範囲によって大きく変動するため、あらかじめ自社で確保できる予算を明確にしておくことが大切です。
その上で、複数の候補企業から提案と見積もりを取得し、サービス内容と費用のバランスを比較検討します。
その際、単に総額の安さだけで判断するのではなく、費用の内訳が明確に提示されているかを確認することが重要です。「コンサルタントの人件費」「成果物作成費」「研修実施費」など、何にどれくらいのコストがかかるのかが透明である会社は信頼性が高いと言えます。
契約形態も確認し、自社のニーズに合った会社を選びます。

人事制度設計・運用コンサルティング会社をタイプ別に見ていきましょう。
人事制度設計・運用を支援するコンサルティング会社は、その規模や専門性によっていくつかのタイプに分類できます。
グローバルな知見と豊富な実績を持つ大手ファーム、特定の業界や課題に深い知見を持つ専門会社、クライアントに寄り添った柔軟な対応が魅力の中小・ベンチャー系、そして必要なスキルをピンポイントで活用できるマッチングサービスなどがあります。
それぞれの特徴を理解し、自社の状況に最も適したタイプの会社を選ぶことが重要です。
大手コンサルティングファームは、国内外における多様な業種・規模の企業へのコンサルティング実績が豊富であり、組織人事に関する包括的な知見と確立された方法論を有しているのが特徴です。
人事制度設計に留まらず、経営戦略との連動や組織全体の変革といった、より大きな視点からの支援を期待できます。
例えば、リクルートグループのように人材サービスで培った膨大なデータや知見を基にした提案が可能なコンサルティングファームもこのタイプに含まれます。
大規模な組織改革やグローバルな人事制度の導入を検討している企業に適していますが、費用は高額になる傾向があります。
IT、医療、金融、製造業といった特定の業界や、「M&Aに伴う人事制度統合」「海外拠点の人事制度構築」「ベンチャー企業の成長支援」といった特定のテーマに特化した専門コンサルティング会社も存在します。
これらの会社は、その領域における深い専門知識と経験を有しているため、業界特有の商慣習や法規制、課題などを踏まえた、より具体的で実践的なコンサルティングが期待できます。
自社が抱える課題が明確で、高度な専門性が求められる場合に有力な選択肢となります。
総合力では大手に及ばない場合もありますが、専門分野での知見は非常に深いものがあります。
中小・ベンチャー系のコンサルティング会社は、大手ファームと比較して、顧客企業一社一社に対してより柔軟できめ細やかな対応を期待できる点が大きな特徴です。
パッケージ化されたサービスではなく、経営者の想いや企業の文化を深く理解した上で、完全にオーダーメイドの制度設計を行う傾向があります。
担当コンサルタントがプロジェクトの最初から最後まで密接に伴走してくれるケースが多く、経営層との壁打ち相手としても機能します。
費用面でも大手より比較的抑えられる場合が多く、自社の実情に寄り添った手厚いサポートを求める企業に適しています。
近年、企業とフリーランスのコンサルタントや人事の専門家(プロ人材)をつなぐマッチングサービスが注目されています。
大手コンサルティングファーム出身者や、事業会社で豊富な人事経験を持つ個人に対し、プロジェクト単位で業務を依頼できるのが特徴です。
「評価制度の設計だけを依頼したい」「評価者研修の講師を頼みたい」といった特定のニーズに対して、必要なスキルを持つ専門家をピンポイントで、かつ比較的リーズナブルに活用できます。
コンサルティング会社に包括的に依頼するほどの規模ではないが、専門家の知見を借りたいという場合に有効な選択肢です。

人事制度コンサルティング導入の基本的な流れを解説します。
人事制度コンサルティングを導入し、プロジェクトを進める際には、一般的に標準的なプロセスが存在します。
まず、自社の現状を客観的に分析することから始まり、新しい制度が目指すべき方向性を定め、具体的な制度内容を設計します。
そして、設計した制度を従業員に説明し導入、その後は運用状況をモニタリングしながら改善を続けていくという流れです。
この一連のステップを理解しておくことで、コンサルティング会社との協業をスムーズに進めることができます。
プロジェクトの最初のステップは、現状の人事制度や組織が抱える課題を正確に把握することです。
コンサルタントは、経営層や人事担当者へのヒアリングを通じて、経営方針や事業戦略、人事に関する問題意識を共有します。
さらに、管理職や一般社員へのインタビュー、従業員意識調査などを実施し、現場が感じている課題や制度への要望を多角的に収集します。
また、離職率や人件費、評価分布といった定量データも分析し、客観的な事実に基づいた課題の特定を行います。
この現状分析の精度が、後の制度設計の質を大きく左右します。
現状分析によって明らかになった課題を踏まえ、新しい人事制度が何を目的とし、どのような方向性を目指すのかという基本方針(コンセプト)を策定します。
この方針は、企業の経営理念やビジョン、中期経営計画などと整合性が取れている必要があります。
「年功序列から成果主義へ移行する」「挑戦する人材を積極的に登用する」「専門性を評価しキャリアパスを複線化する」といった、企業が従業員に何を求め、どう報いるのかという根幹の考え方を明確にします。
この基本方針が、以降の具体的な制度設計における判断の拠り所となります。
策定した基本方針に基づき、人事制度の3つの柱である「等級制度」「評価制度」「報酬制度」を具体的に設計します。
まず、従業員の役割や責任の大きさに応じた等級を定義し、各等級に求められる能力や行動を明文化します。
次に、それらを公正に評価するための評価項目や基準、評価手法を定めます。
最後に、評価結果を昇給・賞与・昇格といった処遇に結びつけるための報酬テーブルやルールを設計します。
これら3つの制度が相互に矛盾なく、一貫したメッセージを発するように連動させることが極めて重要です。
新しい人事制度を設計しても、それが従業員に理解・受容されなければ円滑に運用できません。
そのため、制度の導入に先立ち、全従業員を対象とした説明会を実施し、新制度の目的や概要、自分たちへの影響などを丁寧に説明します。
特に、評価者となる管理職に対しては、新しい評価基準を正しく理解し、適切な評価やフィードバックができるようになるための評価者研修が不可欠です。
こうしたコミュニケーションを通じて、新制度に対する不安や疑問を解消し、納得感を醸成した上で、就業規則の改定などの手続きを経て正式に導入します。
人事制度は導入がゴールではありません。
実際に運用を開始した後、制度が当初意図した通りに機能しているか、予期せぬ問題は起きていないかを検証するプロセスが不可欠です。
導入から半年後や1年後といったタイミングで、従業員満足度調査やエンゲージメントサーベイを実施したり、評価結果の分布や昇格者数の推移などを分析したりして効果測定を行います。
そこで得られたデータや従業員からの意見を基に、必要に応じて制度の微修正やルールの見直しを実施します。
このPDCAサイクルを回し続けることで、制度の実効性を維持・向上させます。

人事制度を形骸化させないためには、注意点があります。
時間とコストをかけて作り上げた人事制度も、運用がおろそかになれば、従業員のモチベーションを下げ、組織の成長を阻害する要因になりかねません。
制度を形骸化させず、本来の目的を達成するためには、運用段階で特に注意すべきポイントがあります。
経営層からの継続的なメッセージ発信、管理職の評価スキル向上、そして従業員からのフィードバックを活かした改善サイクルを確立することが、制度に魂を吹き込む鍵となります。
人事制度は企業が従業員に何を期待しどのように報いるかを示す経営からの最も重要なメッセージの一つです。
そのため制度導入時だけでなく運用が開始された後も経営層が主体となりあらゆる機会を通じて制度に込められた想いや目的を発信し続けることが不可欠です。
経営トップ自らが制度の重要性を語りその運用にコミットする姿勢を示すことで従業員の制度に対する理解と信頼が深まります。
経営の関与が薄れると制度は単なる事務作業に成り下がり形骸化への道をたどる危険性が高まります。
人事制度の運用の成否は評価者である管理職の肩にかかっていると言っても過言ではありません。
部下の目標設定を支援し日々の行動を観察し公正な評価を行い成長を促すフィードバックをする、といった一連の役割を適切に果たせるかどうかで制度の実効性は大きく変わります。
これらの評価スキルは一朝一夕に身につくものではないため導入時だけでなく定期的に評価者研修を実施しスキルの維持・向上を図る必要があります。
評価者同士で目線合わせを行ったり面談のロールプレイングを行ったりすることで評価のばらつきを防ぎ制度の信頼性を担保します。
実際に制度の適用を受ける従業員は、その制度の長所や短所を最もよく知る存在です。
制度をより良いものにしていくためには、従業員からのフィードバックを積極的に収集し、改善に活かす仕組みが欠かせません。
定期的なアンケート調査や、人事部門との面談、目安箱の設置など、従業員が安心して意見を表明できるチャネルを複数用意することが望ましいです。
寄せられた意見は真摯に受け止め、分析し、改善可能な点については迅速に対応します。
従業員が制度作りに参加しているという当事者意識を持つことで、制度への納得感が高まり、より良い運用が実現します。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」