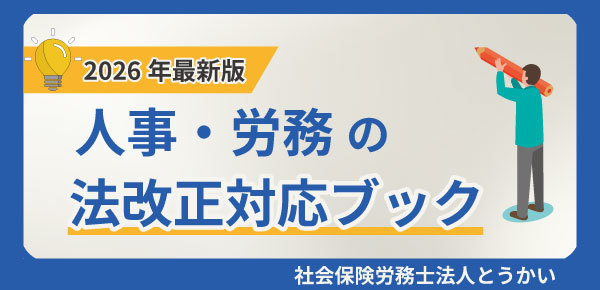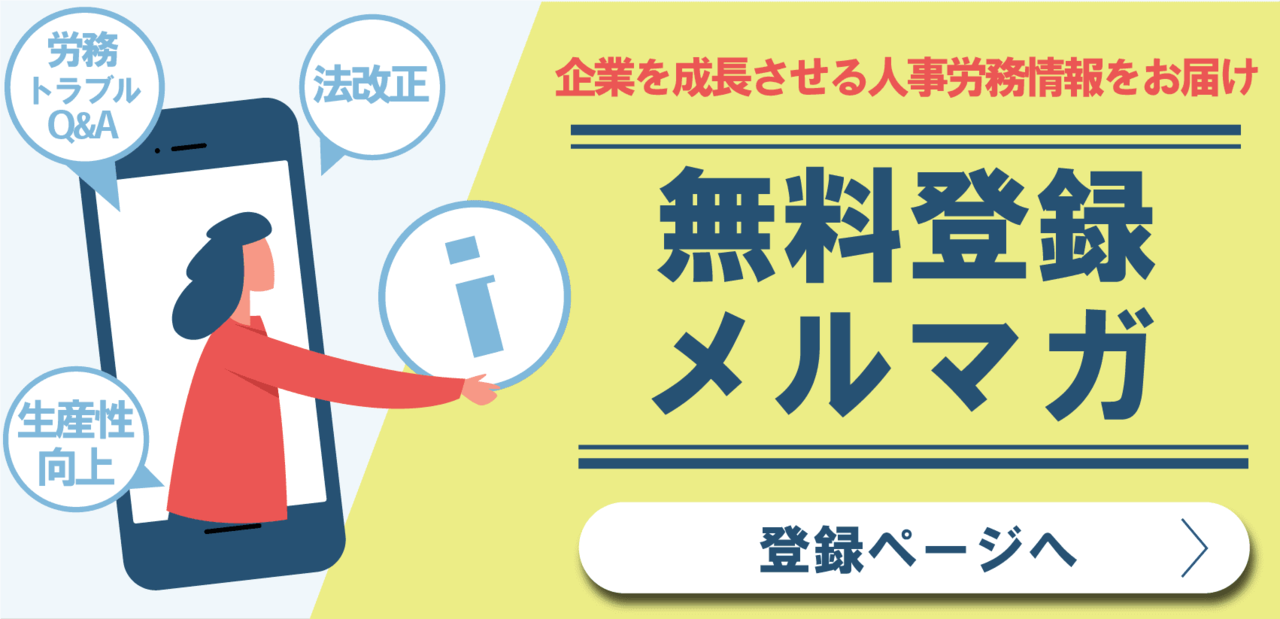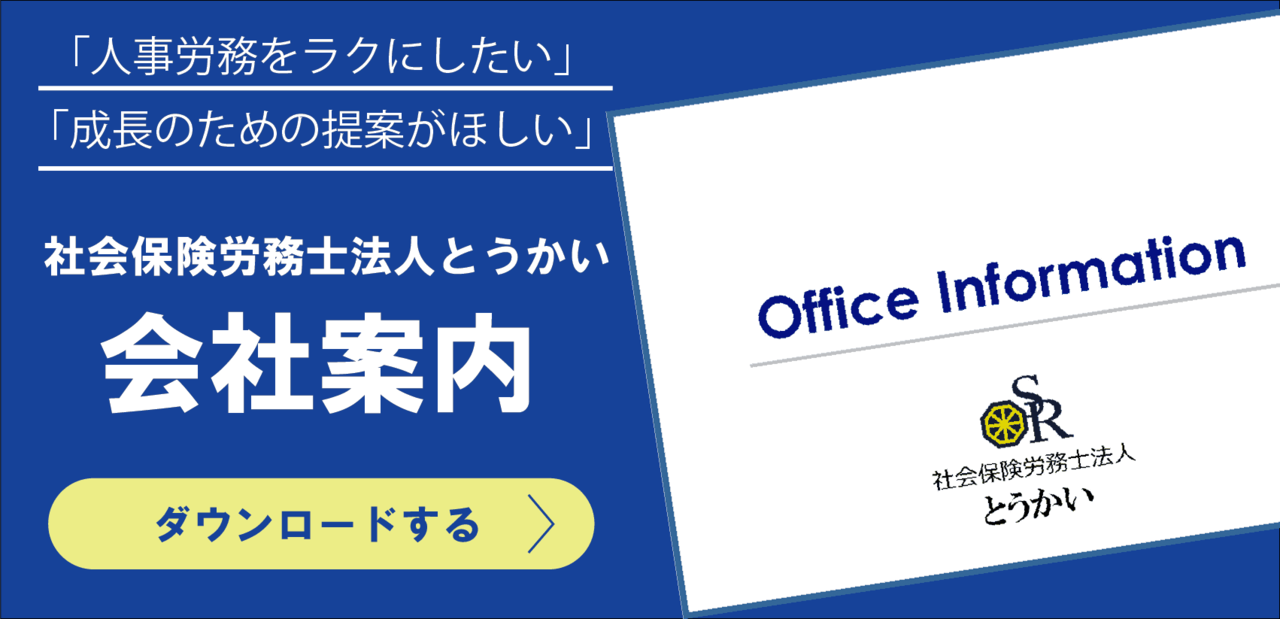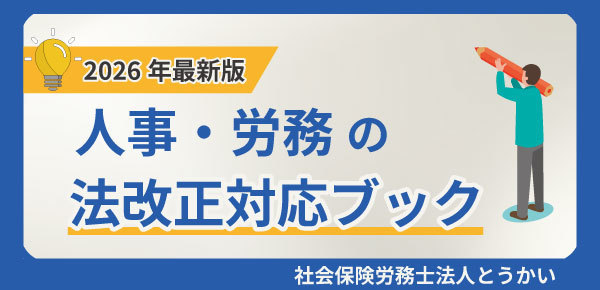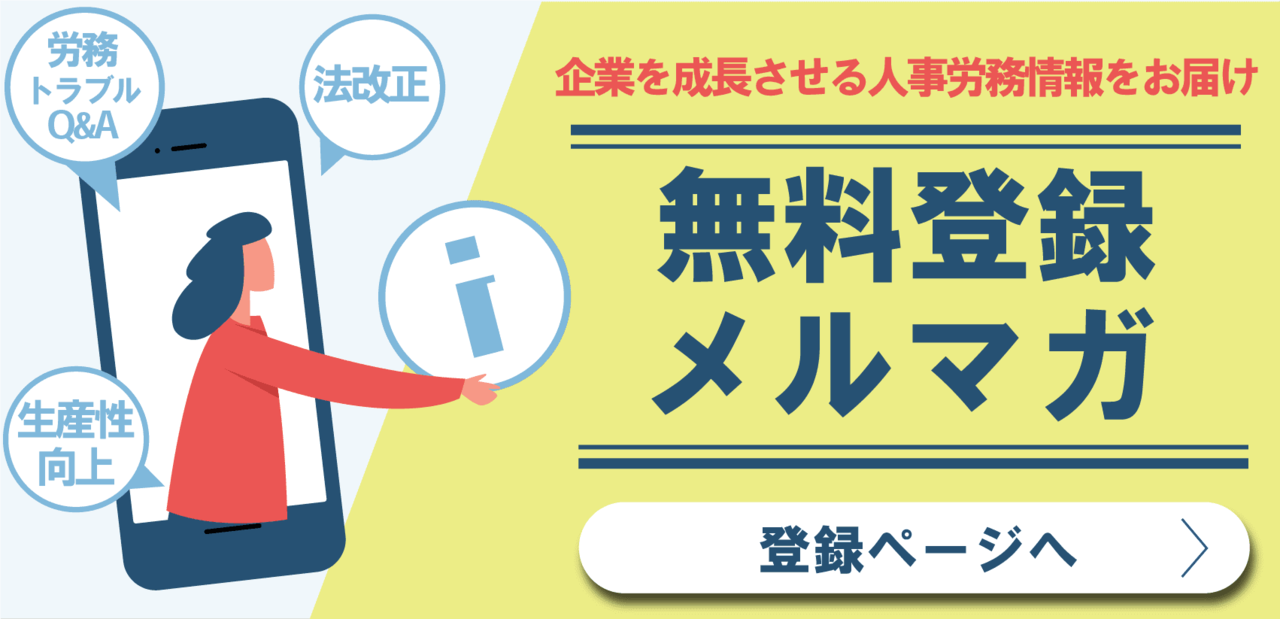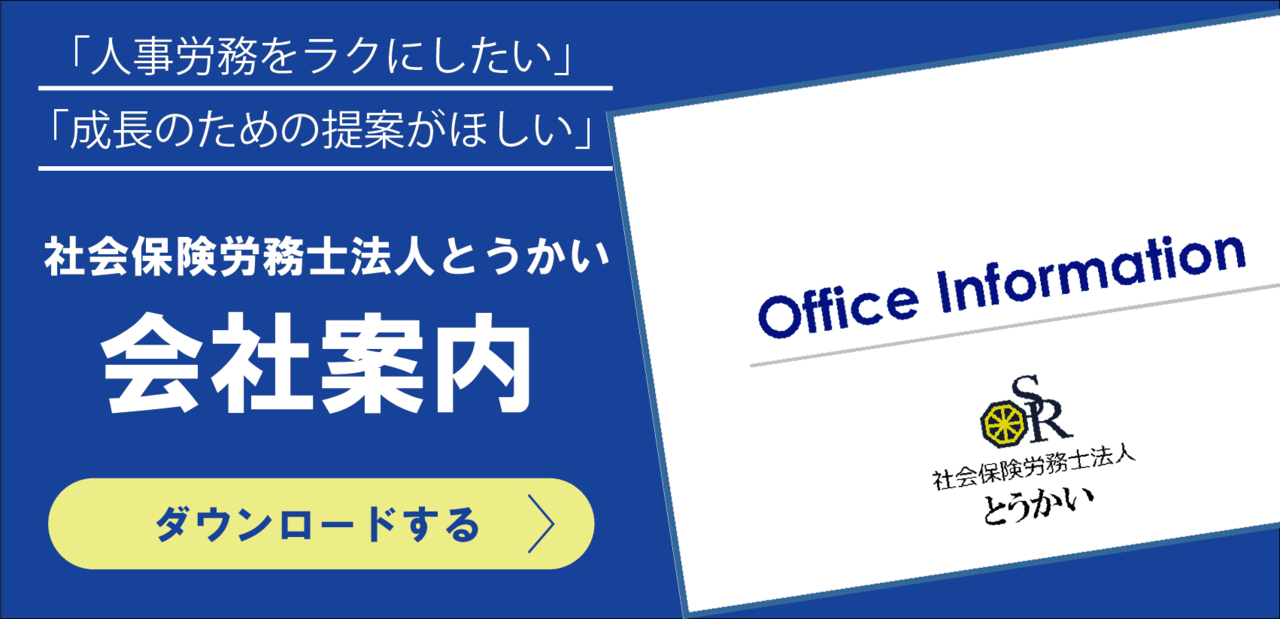労務業務の属人化を解消する方法とは?原因別の対策とシステム活用術

労務業務が特定の担当者に依存する「属人化」は多くの企業で課題となっています。
この状態を放置すると、担当者の不在時に業務が滞るだけでなく、品質の低下や不正のリスクも高まります。
業務の属人化を解消するためには、その原因を正しく理解し、計画的に対策を進めることが不可欠です。
本記事では、労務業務が属人化する原因を掘り下げ、具体的な属人化を解消する方法として、業務の標準化手順やシステムの活用術を解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

労務業務が属人化する原因について見ていきましょう。
労務業務の属人化は、単一の原因ではなく複数の要因が絡み合って発生します。
業務そのものが持つ専門性の高さに加え、組織の体制や文化も大きく影響します。
例えば、多忙さから情報共有が後回しにされたり、標準化された業務フローが会社に存在しなかったりするケースが挙げられます。
ここでは、労務業務がなぜ属人化しやすいのか、その背景にある代表的な4つの原因について掘り下げていきます。
労務業務には、労働基準法や社会保険制度といった専門的な知識が不可欠です。
頻繁な法改正に対応する必要があり、給与計算や年末調整、社会保険の手続きは複雑なルールに基づいています。
そのため、知識と経験を積んだ担当者が一手に引き受ける構図が生まれやすくなります。
特に、総務や事務の担当者が少ない中小企業では、一人の従業員がこれらの業務をすべて担うことが多く、専門性が高いがゆえに他の人が代替しにくく、結果として業務がその個人に固定化されてしまうのです。
労務担当者は、給与計算や入退社手続き、勤怠管理といった月次・日次の定型業務に常に追われています。
これらの業務は期限が厳格に定められているものが多く、目の前のタスクをこなすことで手一杯になりがちです。
その結果、業務マニュアルの作成や後任者への引き継ぎといった、緊急度は低いものの重要な情報共有の作業が後回しにされてしまいます。
このような状況が続くと、担当者の負担が増大し、長時間労働の原因にもなり、情報共有の時間を確保できなくなるという悪循環に陥ります。
業務の手順やルールが明確に文書化されておらず、担当者がこれまでの経験や独自の判断で作業を進めている場合、属人化は進行します。
例えば、書類の管理方法やデータの入力形式、関係各所との連携手順などが個人の裁量に委ねられているケースです。
このような状態では、同じ業務であっても担当者が変わると進め方が異なり、品質にばらつきが生じます。
また、他の従業員がその作業を代行しようとしても、独自のルールが障壁となり、簡単には手を出せない状況が生まれてしまいます。
一部のケースでは、担当者が意図的に情報を共有せず、知識を独占することで組織内での自身の立場を有利にしようとすることがあります。
「自分がいなければこの業務は回らない」という状況を作り出すことで、評価や待遇面での優位性を確保しようとする心理が働くのです。
このような行動は、個人の問題だけでなく、個人のスキルに過度に依存する評価制度や、情報共有を促す文化が組織にないことも背景にあります。
この状態は、他の従業員にとって業務を進める上でのストレスとなり、チームワークを阻害する要因にもなります。

労務業務の属人化がもたらすデメリットをご説明します。
労務業務の属人化を放置すると、組織にとってさまざまな不利益が生じます。
担当者の急な休職や退職といった不測の事態が発生した際に、業務が滞るリスクは特に深刻です。
過去の事例を見ても、給与支払いの遅延や行政手続きの漏れなど、事業の根幹を揺るがす問題に発展しかねません。
ここでは、属人化が引き起こす具体的なデメリットを3つの側面に分けて解説し、その危険性を明らかにします。
属人化の最も直接的なデメリットは、担当者の不在による業務の停滞です。
給与計算や社会保険の手続き、年末調整といった業務は、対応すべき時期が決まっており、遅延が許されません。
しかし、担当者が急な病気や事故で休んだり、突然退職してしまったりした場合、他の誰も業務内容を把握していないため、対応が不可能になります。
これにより、従業員への給与支払いが遅れる、行政への届出が期限に間に合わないといった事態が発生し、従業員からの信頼失墜や法令違反のリスクに直結します。
業務プロセスが標準化されていないため、担当者のスキルや経験、その日の体調などによって、業務の品質にばらつきが生じます。
ベテラン担当者が処理すれば問題なく完了する業務も、経験の浅い担当者が行えばミスが発生する可能性が高まります。
また、業務がブラックボックス化していると、第三者によるチェック機能が働きにくくなります。
担当者自身も自分のやり方が正しいと思い込み、間違いに気づかないまま業務を進めてしまうことがあり、潜在的なミスが見過ごされやすい状態を生み出します。
業務の全容を一人しか把握していない状況は、不正行為の温床となり得ます。
例えば、架空の残業代を計上したり、経費を不正に請求したりといった行為も、チェック体制がなければ見過ごされる可能性が高まります。
また、意図的な不正だけでなく、担当者の知識不足や誤った解釈によって、労働関連法規に違反した処理が行われ続けるリスクも存在します。
コンプライアンス遵守という会社の目標達成を妨げるこれらの問題は、外部からの指摘で初めて発覚することも多く、企業の信用を大きく損なうことになりかねません。

労務業務の属人化を解消するためのステップを見ていきましょう。
労務業務の属人化を解消するには、場当たり的な対応ではなく、体系的なアプローチが求められます。
まずは現状の業務を正確に把握し、課題を特定することから始める必要があります。
その上で、誰が担当しても同じ品質で業務を遂行できるような仕組みを構築していくことが重要です。
ここでは、属人化解消に向けて踏むべき具体的な5つのステップを順を追って解説し、実践的なプロセスを示します。
最初のステップは、現状を正確に把握することです。
どの担当者が、どのような業務を、どのくらいの頻度と時間で行っているのかをすべて洗い出します。
担当者へのヒアリングや業務日誌などを活用し、「誰が」「何を」「いつ」「どのように」行っているかを具体的にリストアップしていきます。
このとき、給与計算のような主要な業務だけでなく、電話対応や書類整理といった付随的な作業も漏らさずに記録することが重要です。
この作業を通じて、これまで見えていなかった業務や、特定の個人に負担が集中している状況が明らかになります。
リストアップした各業務について、開始から完了までの一連の流れをフローチャートなどを用いて図式化します。
これにより、個々の作業のつながりや、部署間の連携、必要な書類、判断基準などが明確になります。
例えば、「入社手続き」という業務であれば、内定者からの書類回収、社会保険の加入手続き、社内システムへの登録といった各工程を時系列で整理します。
業務の全体像が可視化されることで、非効率な部分や重複しているプロセス、判断が担当者任せになっている箇所といった、属人化の原因となっている問題点を発見しやすくなります。
業務の可視化によって明らかになった課題をもとに、業務プロセスを見直し、標準化を進めます。
このステップの目的は、特定個人のスキルや経験に依存せず、誰が担当しても一定の品質を保てる状態を作り出すことです。
具体的には、複雑な手順を簡素化したり、不要な承認プロセスをなくしたり、判断基準を明確に定めたりします。
業務を標準化することで、担当者ごとのやり方の違いがなくなり、品質が安定します。
また、業務内容をシンプルにすることで、定期的なジョブローテーションも実施しやすくなり、複数人が対応できる体制の構築が可能になります。
平準化した業務プロセスを、誰が見ても理解できるマニュアルとして文書化します。
マニュアルには、具体的な作業手順だけでなく、その仕事の目的や背景、注意点、トラブル発生時の対処法なども記載することが望ましいです。
専門用語は避け、図やスクリーンショットを多用することで、視覚的に分かりやすくする工夫も有効です。
完成したマニュアルは、ファイルサーバーやクラウドストレージなど、関係者がいつでも簡単にアクセスできる場所に保管し、新入社員の教育や業務の引き継ぎ時に活用できる体制を整えます。
マニュアルを作成して終わりではなく、それを実際に運用しながら継続的に改善していくことが不可欠です。
法改正や社内規定の変更、より効率的な業務手順の発見など、業務環境は常に変化します。
そのため、少なくとも年に一度など定期的にマニュアルや業務フローの内容を見直す機会を設けるべきです。
現場の担当者からフィードバックを収集し、実態に合わなくなった箇所を修正することで、マニュアルの陳腐化を防ぎ、常に最新かつ最適な状態を維持する仕組みを構築します。

属人化の解消に役立つ労務管理システムはどう選べばいいのでしょうか?
業務プロセスの標準化と並行して、労務管理システムを導入することは、属人化解消を効果的に進める上で非常に有効です。
システムを活用することで、手作業によるミスを減らし、業務の透明性を高めることができます。
しかし、多種多様なシステムが存在するため、自社の課題や目的に合致したものを選ぶことが重要になります。
ここでは、労務業務の属人化解消という観点から、システム選定時に着目すべき3つのポイントを解説します。
労務管理システムを選定する際、定型的な業務をどれだけ自動化できるかは重要な判断基準です。
給与計算や勤怠データの集計、社会保険に関する書類作成など、これまで手作業で行っていた時間を要する業務を自動化できる機能を持つシステムを導入すべきです。
業務自動化のメリットは、担当者の作業負担を大幅に軽減し、入力ミスや計算ミスといったヒューマンエラーを削減できる点にあります。
これにより、担当者はマニュアルの整備や業務改善といった、より創造的な業務に時間を使えるようになります。
属人化の解消には、情報の一元管理と共有が不可欠です。
従業員情報や勤怠データ、給与明細といった情報をシステム上で一元的に管理し、権限を持つ複数の担当者がいつでもアクセスできる環境を構築することが重要です。
そのため、誰にとっても直感的で分かりやすいインターフェースを備えているか、操作性は必ず確認するべきポイントです。
特に総務部門のように複数人で業務を分担する場合、操作が複雑だと結局特定の担当者しか使わなくなり、システム内での属人化を招く可能性があるため注意が必要です。
労務関連の法律や保険料率は頻繁に改正されるため、システムがこれらの法改正に迅速かつ自動で対応できるかは極めて重要な要素です。
クラウド型の労務管理システムの多くは、法改正があるとシステム側で自動的にアップデートが行われます。
これにより、担当者が自ら法改正の情報を収集し、手作業で設定を変更する必要がなくなります。
この機能は、担当者の負担を軽減するだけでなく、会社として常に最新の法令を遵守した労務管理を行うことにつながり、コンプライアンスリスクを低減させます。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」