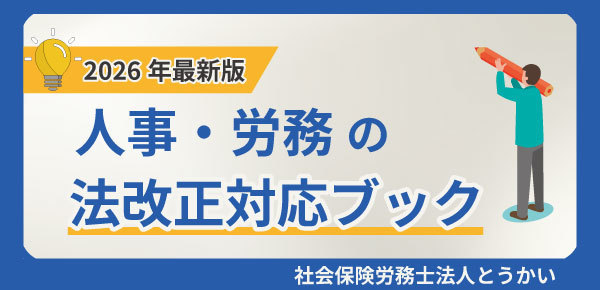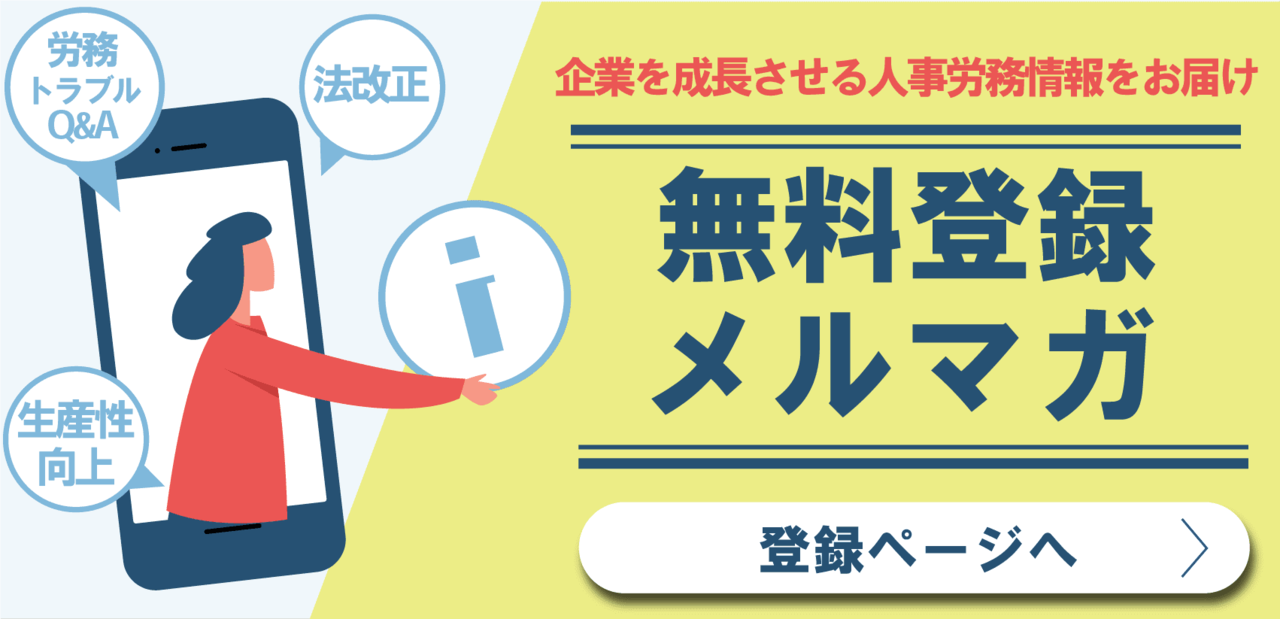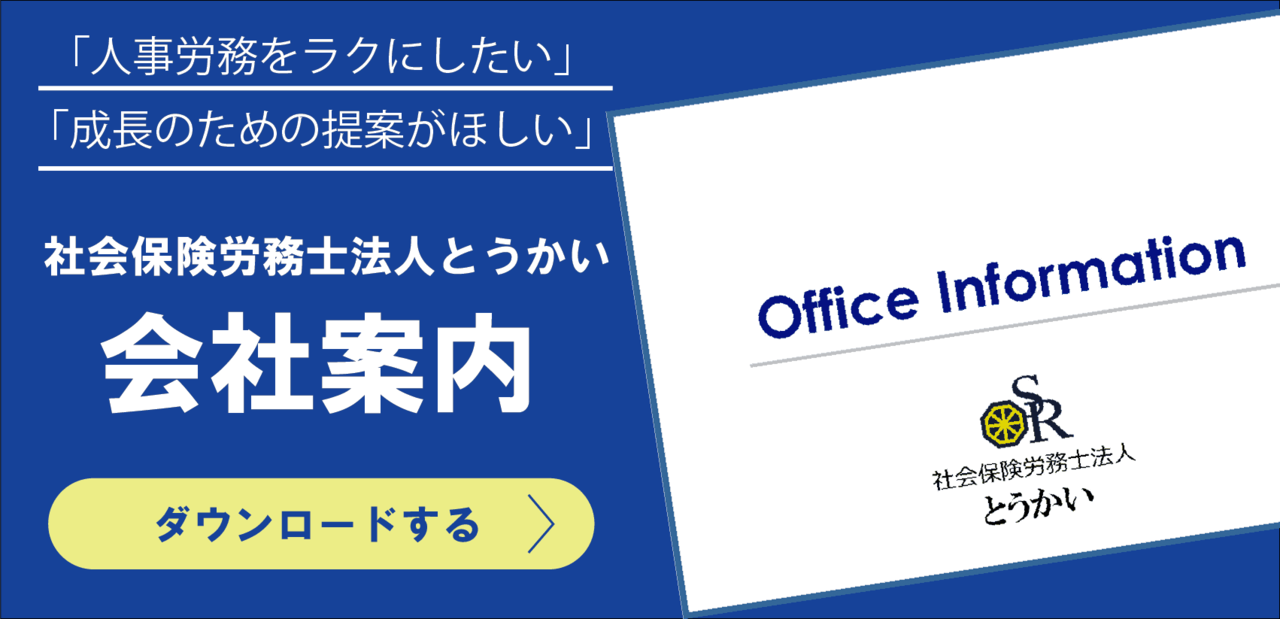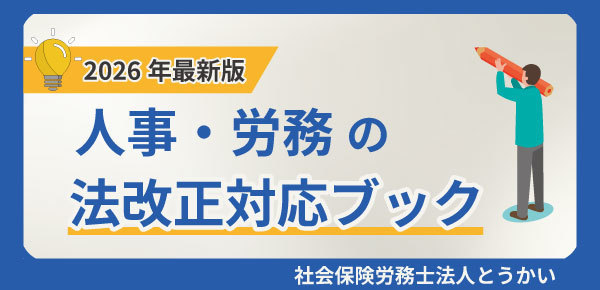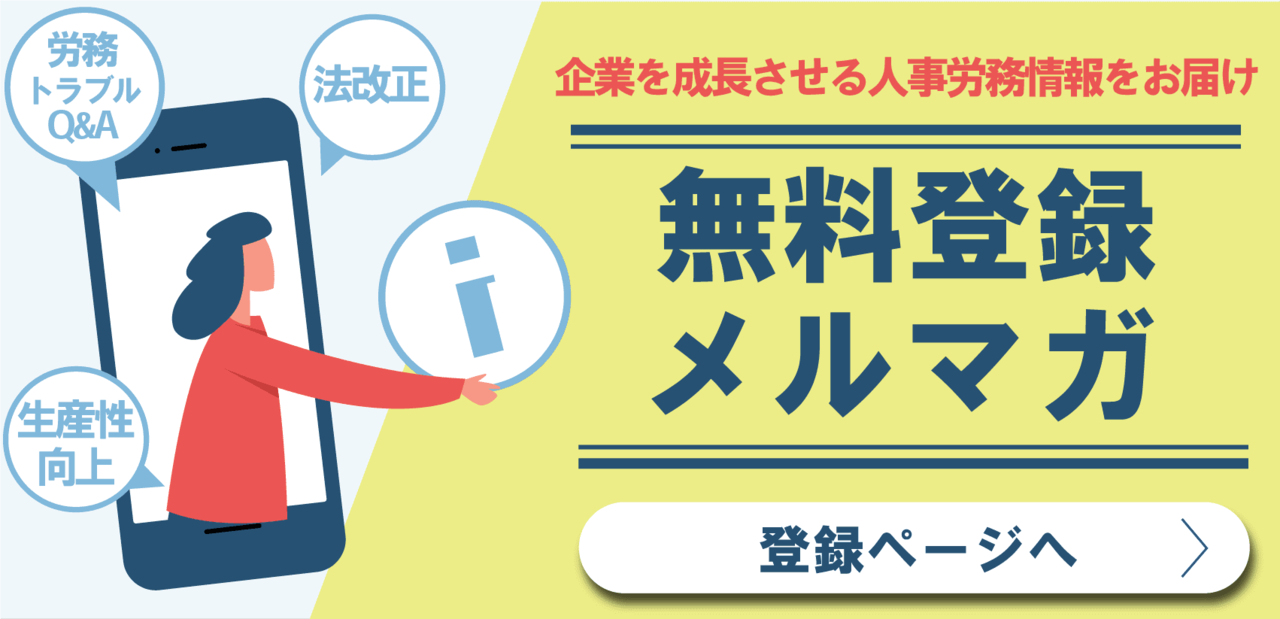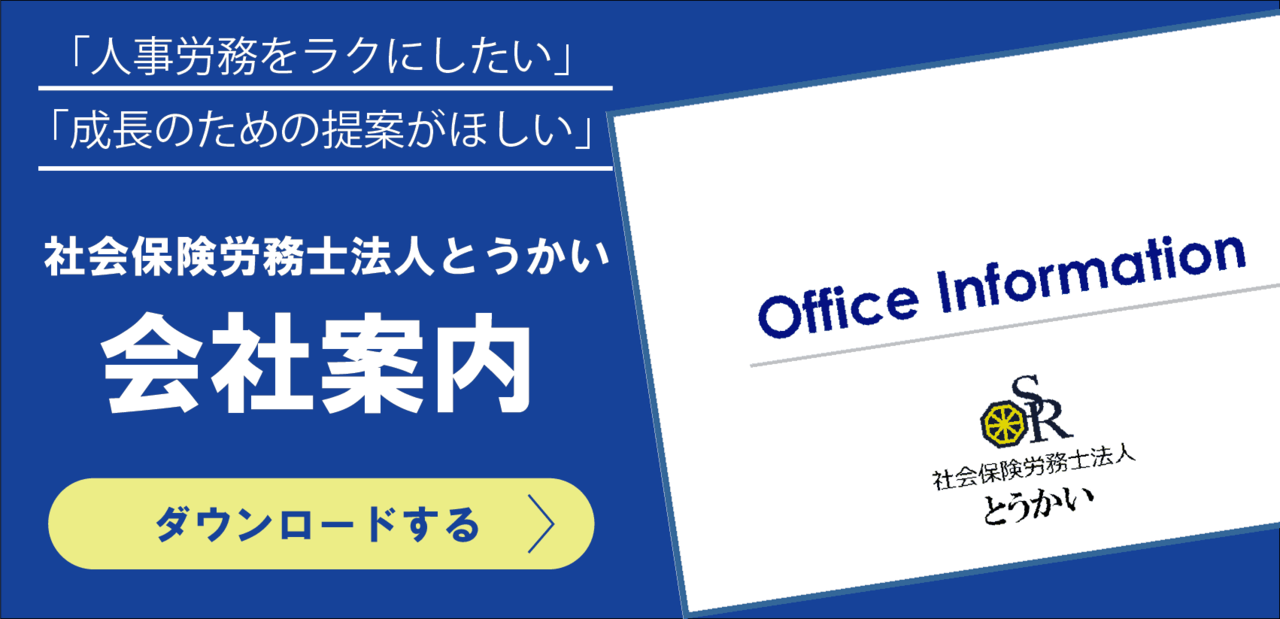法改正に未対応だとどうなる?罰則や事業へのリスクを徹底解説

近年の法改正、特に電子帳簿保存法への対応は、すべての事業者にとって重要な課題です。
もし未対応のまま放置した場合、罰則が科されるだけでなく、事業運営そのものに深刻な影響を及ぼすリスクがあります。
この記事では、法改正に未対応の場合に具体的にどのような事態が起こりうるのか、罰則の内容から事業上のデメリット、そして今からでも間に合う対応策までを詳しく解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

法改正に未対応だと、どんな罰則があるのでしょうか?
電子帳簿保存法などの法改正に適切に対応しない場合、いくつかの罰則が科される可能性があります。
これらは企業の税務や法務に直接的な影響を与えるため、未対応のリスクは決して軽視できません。
具体的には、税制上の優遇措置が受けられなくなる、追加の税金が課される、あるいは会社法に基づく過料が発生するなどのケースが考えられます。
これらの罰則について、以下で詳しく見ていきましょう。
電子帳簿保存法の要件を満たさずに電子取引データを保存していた場合、青色申告の承認が取り消されるリスクが生じます。青色申告が取り消されると、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除といった税制上の大きな優遇措置が受けられなくなります。
これにより、納税額が大幅に増加し、企業の資金繰りに直接的な打撃を与える可能性があります。
帳簿書類の保存は青色申告の承認要件の一つであり、電子データ保存の義務化に伴い、その適切な運用がより一層厳しく問われることになります。
電子取引データの保存義務に違反し、その内容が申告漏れにつながった場合、追徴課税が課されるリスクがあります。
通常の申告漏れであれば過少申告加算税が課されますが、意図的なデータの改ざんや隠蔽など、悪質なケースと判断されると、より税率の高い重加算税の対象となります。
さらに、電子データに関連する不正に対しては、重加算税が10%加重される厳しい措置が設けられています。
このような追徴課税は、本来納めるべき税額に加えてペナルティとして課されるため、企業経営にとって大きな負担となります。
電子帳簿保存法だけでなく、会社法においても会計帳簿や事業に関する重要資料の保存が義務付けられています。
これらの帳簿書類を適切に保存していない場合、会社法第976条の規定に基づき、代表者個人に対して100万円以下の過料が科されるリスクが存在します。
電子取引データも事業に関する重要資料に含まれるため、電子帳簿保存法の要件を満たさない保存方法は、同時に会社法違反と見なされる可能性があります。
税法上の罰則とは別に、このような法的な制裁を受けることも念頭に置く必要があります。

法改正の未対応が引き起こすデメリットについて見ていきましょう。
法改正への未対応がもたらす影響は、法的な罰則に限りません。
日常的な業務運営においても、さまざまなデメリットが生じるリスクがあります。
紙媒体での書類管理を続けることによるコストの増大や業務の非効率化は、企業の競争力を少しずつ蝕んでいきます。
また、取引先とのやり取りにおいて電子化の潮流から取り残されることは、企業としての信頼性に関わる問題に発展しかねません。
法改正に対応せず、従来通り紙の書類を主体で管理し続ける場合、企業は多くのコストと手間を負担し続けることになります。
具体的には、書類を保管するためのファイルキャビネットや倉庫のスペース代、印刷に必要な紙代やインク代、プリンターのリース費用、そして取引先への郵送費などが継続的に発生します。
また、膨大な量の紙書類から目的のものを探し出す作業や、ファイリングといった整理業務にも多くの時間と人件費が割かれます。
これらの目に見えるコストと見えにくい手間は、企業の利益を圧迫する要因となります。
紙ベースの業務プロセスは、企業の生産性を著しく低下させる要因となります。
例えば、請求書の承認を得るために、担当者が書類を持って上司の席を回る、あるいは遠隔地の拠点へ郵送するといったプロセスは時間と手間がかかります。
また、過去の取引内容を確認したい場合、オフィスに戻って膨大なファイルの中から目的の書類を探し出す必要があり、迅速な意思決定の妨げになります。
このような非効率な業務フローは、従業員の負担を増やすだけでなく、企業全体の成長スピードを鈍化させることにつながります。
近年、多くの企業が業務効率化やコスト削減のために請求書や契約書の電子化を進めています。
そのような状況下で自社だけが紙でのやり取りに固執していると、取引先に手間をかけさせてしまい、敬遠される原因になりかねません。
例えば、「請求書は電子データで送付してほしい」という要望に応えられない場合、取引の継続が難しくなるリスクがあります。
また、法改正に適切に対応していない企業と見なされることで、コンプライアンス意識が低いという印象を与え、企業としての信頼性を損なう恐れもあります。

電子帳簿保存法について解説します。
ここで言う法改正とは、主に「電子帳簿保存法」を指します。
この法律は、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存することを認めるものですが、特に2022年1月の改正で大きな変更がありました。
中でも重要なのは、電子メールやクラウドサービスで受け取った請求書などの電子取引データを、紙に出力して保存することが原則として認められなくなった点です。
2023年末で宥恕措置が終了し、すべての事業者に対応が義務付けられました。
電子帳簿保存法の中でも、法人や個人事業主を問わず、すべての事業者が対応必須となるのが「電子取引データ保存」です。
これは、電子メールで受け取った請求書のPDFファイルや、ネット通販サイトからダウンロードした領収書など、電子的に授受した取引情報をデータのまま保存する義務を定めたものです。
2024年1月からは、これらの電子データを単にパソコン内に保存するだけでなく、「真実性の確保」と「可視性の確保」という二つの要件を満たした形で保存しなければなりません。
紙に印刷しての保存は認められないため、注意が必要です。
電子帳簿等保存は、自社が会計ソフトなどを使用して最初から一貫して電子的に作成した国税関係帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)や書類(決算関係書類など)を、データのまま保存することを認める制度です。
これは義務ではなく、事業者の任意で選択できます。
一定の要件を満たすことで、優良な電子帳簿として認められ、申告漏れがあった際の過少申告加算税が軽減されるといったメリットもあります。
多くの企業では既に会計ソフトを導入しているため、比較的取り組みやすい区分と言えます。
「スキャナ保存」は、取引先から受け取った紙の請求書や領収書、自社で作成した書類の写しなどを、スキャナやスマートフォンで読み取って電子データとして保存することを認める制度です。
これも「電子帳簿等保存」と同様に、対応は任意です。
この制度を活用することで、紙の原本を破棄できるようになり、保管スペースや管理コストの大幅な削減が可能になります。
ただし、タイムスタンプの付与や解像度の確保など、一定の要件を満たす必要があり、導入を検討する企業は保存ルールを正確に理解することが求められます。

法改正に対応するための具体的な手順を見ていきましょう。
まだ何も準備できていないと焦りを感じている事業者もいるかもしれませんが、適切な手順を踏めば、今からでも法改正への対応は可能です。
重要なのは、対応を先延ばしにせず、自社の状況を正確に把握することから始めることです。
どのタイミングで何から手をつけるべきか、具体的なステップを理解し、計画的に進めることで、混乱なくスムーズに対応を完了させることができます。
法改正への対応における最初のステップは、自社でどのような電子取引が行われているかを正確に把握することです。
請求書、領収書、見積書、納品書といった書類の種類ごとに、どのような方法で受け取りや送付を行っているかを確認します。
例えば、取引先からメール添付で送られてくるPDFの請求書、ウェブサイトからダウンロードする領収書、EDIシステムを利用した取引データなどが該当します。
この洗い出し作業を通じて、保存が必要な電子データがどれくらいあるのか、その範囲を明確にすることが、後のルール作りやシステム選定の基礎となります。
電子取引の範囲を特定したら、次にそれらのデータをどのように保存するかの具体的な社内ルールを定めます。
法改正への対応では、「真実性の確保」と「可視性の確保」という二つの要件を満たす必要があります。
これらを踏まえ、例えば「取引年月日_取引先名_金額」といったファイル名の命名規則を統一したり、データを保存するサーバー内のフォルダ構成を決めたりします。
また、誰がいつデータを保存し、どのように管理するのかといった運用フローを明確に文書化し、社内全体で共有することが重要です。
これにより、属人化を防ぎ、一貫性のあるデータ管理を実現します。
手作業でのファイル管理やルール運用に限界を感じる場合、法改正に対応した会計システムや文書管理システムの導入が有効な解決策となります。
多くのシステムは、電子帳簿保存法の保存要件である「真実性の確保」と「可視性の確保」を自動で満たす機能を備えています。
例えば、受け取った請求書データをアップロードするだけで、検索要件を満たす情報を自動で読み取ったり、訂正・削除の履歴が残る仕組みになっていたりします。
JIIMA認証(電子帳簿ソフト法的要件認証)を取得しているシステムを選ぶと、より安心して導入を進めることができます。

法改正への対応でどんなメリットが得られるのでしょうか。
法改正への対応は、罰則を回避するための守りの施策と捉えられがちですが、実際には企業経営に多くのプラスの効果をもたらす攻めの取り組みでもあります。
業務プロセスを見直し、デジタル化を推進する絶好の機会となり、コスト削減や生産性向上といった直接的なメリットが期待できます。
さらに、従業員の働き方にも良い影響を与え、企業の持続的な成長を支える基盤を構築することにつながります。
法改正をきっかけに書類の電子化を進めることで、企業は大幅なコスト削減を実現できます。
具体的には、これまでかかっていた紙代、プリンターのインク代やリース費用、書類を郵送するための通信費、そして保管用のキャビネットや倉庫の賃料などが不要になります。
特に、書類の保管義務期間は長いため、物理的な保管スペースにかかるコストは決して小さくありません。
ペーパーレス化によってオフィススペースに余裕が生まれ、そのスペースをより生産的な活動に活用することも可能になります。
書類を電子データで一元管理することにより、業務効率は飛躍的に向上します。
紙の書類の場合、キャビネットや倉庫から目的の一枚を探し出すのには多くの時間がかかりますが、電子化されていれば話は別です。
電子帳簿保存法に対応したシステムを導入すれば、取引年月日、取引先名、金額といった条件で瞬時に検索できます。
これにより、経理担当者が問い合わせに迅速に対応できたり、監査や税務調査の際にも必要な資料をすぐに提出できたりと、業務全体のスピードアップが図れます。
請求書や領収書などの経理書類が電子化されると、場所に縛られない働き方が可能になります。
従来は、請求書の処理や押印のために出社が必要でしたが、システム上で申請から承認までのワークフローを完結できれば、経理担当者もテレワークがしやすくなります。
ネット環境さえあれば、自宅やサテライトオフィスからでも業務を遂行できるため、従業員のワークライフバランス向上に寄与します。
これは、優秀な人材の確保や定着といった面でも、企業にとって大きなメリットとなります。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」