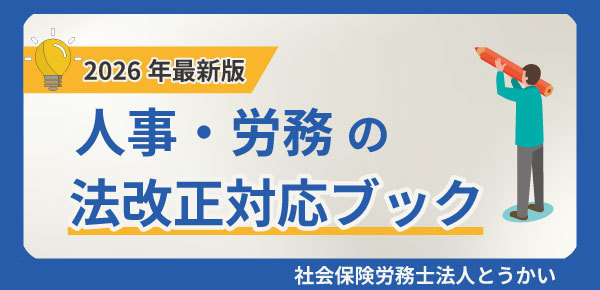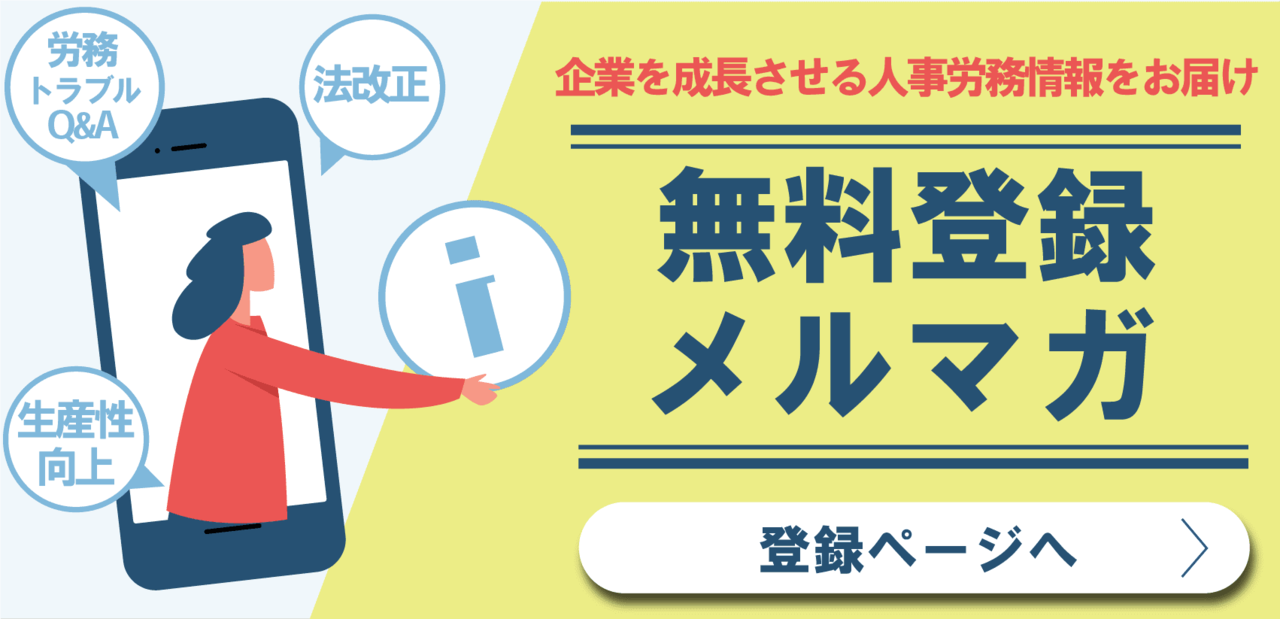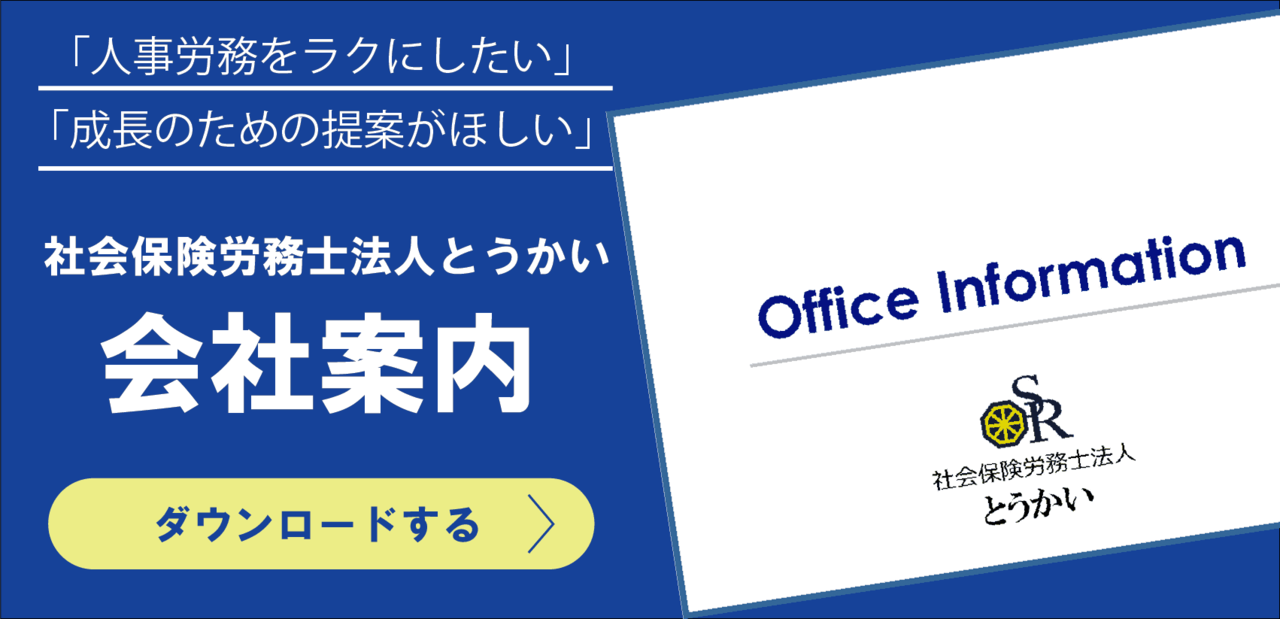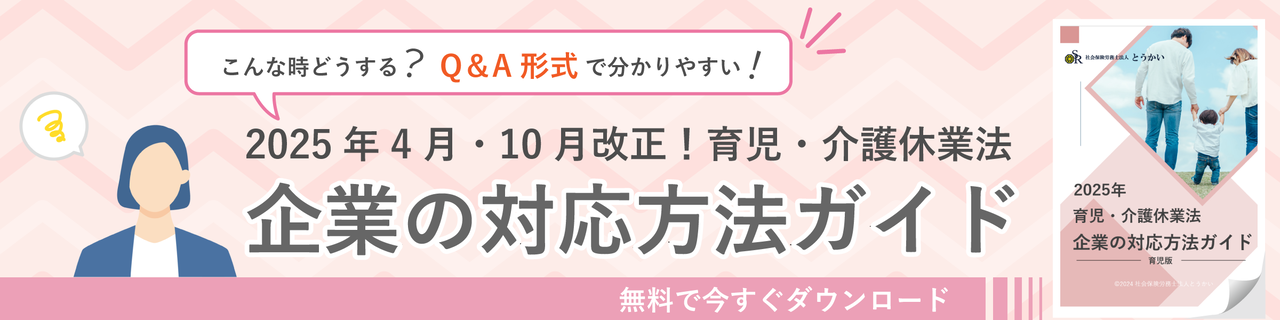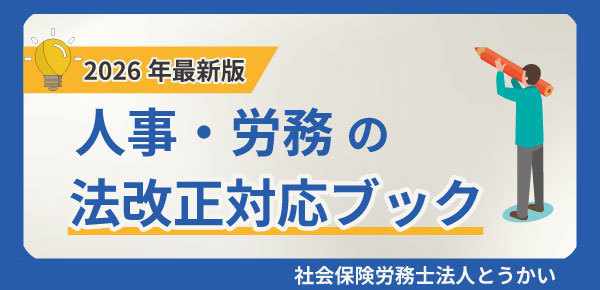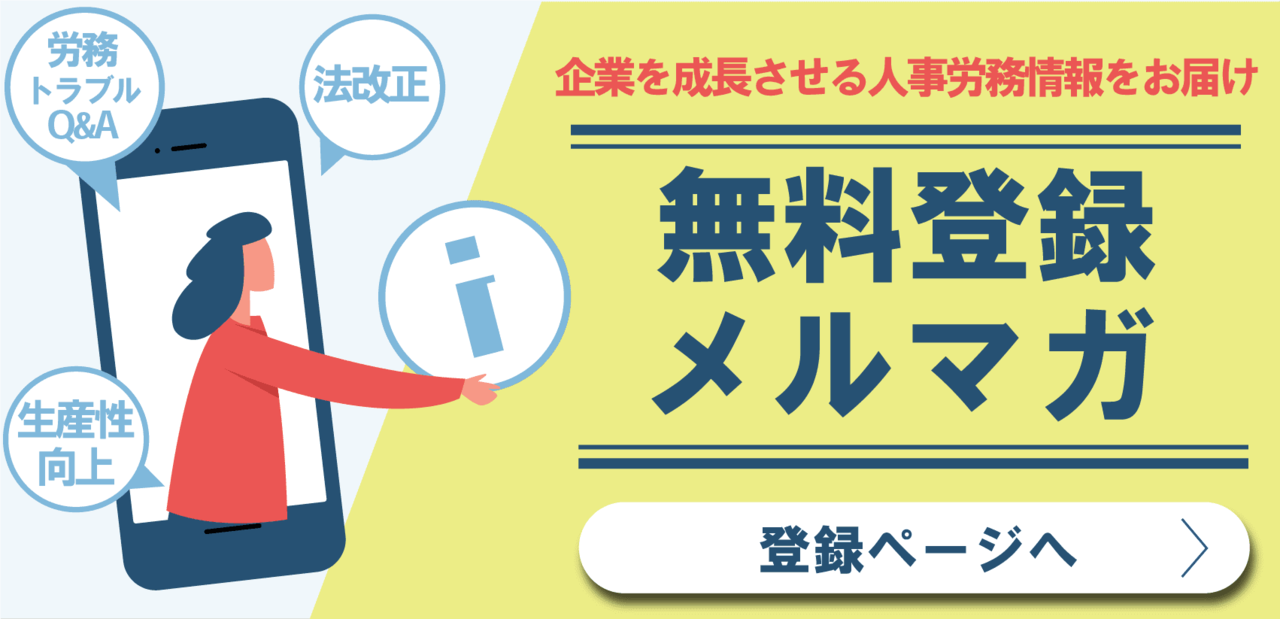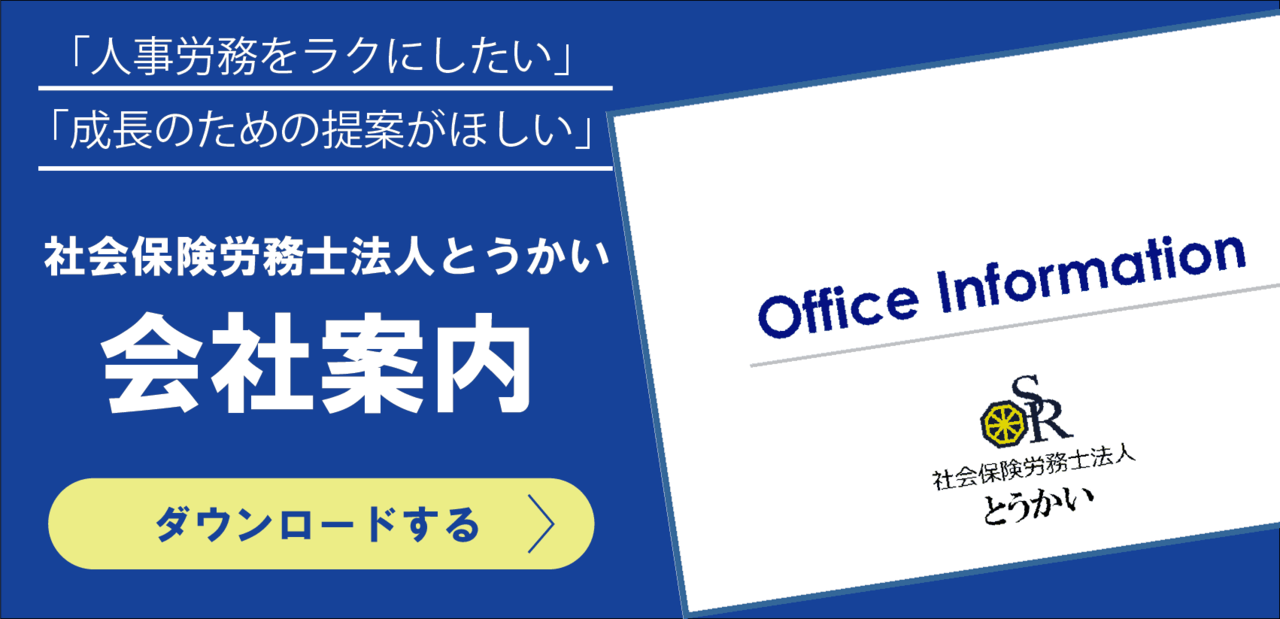2025年から高額療養費の限度額が引き上げ?
社会保険の観点から仕組みや申請方法について解説

高額療養費制度は、高額な医療費が発生した際の自己負担額を軽減するために設けられた制度です。病気になったとき、けがをしたときに、高い医療費になるのではと不安になることもあるのではないでしょうか? そんなときにサポートしてくれるのが高額療養費制度です。医療機関でかかった治療費などに対して、自己負担限度額を超える分は返金される仕組みとなっています。今回は、高額療養費制度のしくみ、事前の手続きや申請方法、計算方法など、詳しく解説していきます。高額療養費制度の利用方法を理解しておくことが、家族やご自身の医療費負担を軽減する手助けとなります。適切に活用し、安心して医療を受けられる環境を整えましょう。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

高額療養費制度の基本を詳しく解説します。
高額療養費制度は、病気やけがなどで高額な医療費がかかった場合に、自己負担を一定額以下に抑えてくれる制度です。病院や診療所での医療サービスを受けた際、入院及び外来の医療を問わず適用されるため、多くの人々が必要な医療を受けやすくする役割を果たしています。
高額療養費制度は、医療費負担を軽減するために設けられた公的保険制度であり、病気やけがなどで医療費が高額になった場合に適用されます。日本においては、国民皆保険であるため、国民全員何らかの健康保険に入っていますので、適用対象は会社員などであれば健康保険や自営業者などは国民健康保険の加入者です。通常、受ける医療の内容や入院の有無に応じて、自己負担の上限は異なります。この制度により、多くの人々が高額な医療費の負担を軽減し、必要な治療を適切に受けやすくなる環境が整えられています。
自己負担限度額は、被保険者の年齢や所得状況によって異なります。この限度額は、健康保険加入者であれば標準報酬月額によって異なり、所得が高いほど限度額も上がる傾向があります。具体的な計算方法は、自己負担限度額が適用される金額を基準として、実際に支払った医療費の総額からその限度額を引くことで求められます。その結果、高額な医療費の一部が補助され、患者の負担が軽減される仕組みとなっています。この制度を活用することで、経済的な負担を抑えつつ、必要な医療を受けることが可能となります。
高額療養費制度が適用されるのは、医療費がいくらからかという点も重要です。被保険者の年齢や所得区分に応じて自己負担限度額が設定されており、この金額を超えた場合に高額療養費が適用されます。たとえば、年収550万円位の人の場合、おおよそ医療費が8万円を超えてくると、その超過分が高額療養費として返金される仕組みです。このため、予想外に医療費が高額になった場合でも、自己負担限度額に基づく助成が受けられるため、安心して医療を受けることができます。

鶴見の経営視点のアドバイス
一定の医療費を超えるとその負担をカバーしてくれる高額療養費ですが、医療費であればすべて該当するわけでもありません。入院中の差額ベッドや自由診療、先進医療などは対象外になります。ただ、対象外になる医療費については、所得税の申告の際に医療費控除の対象となる場合もありますので、しっかり理解しておくことが重要なのです。

高額療養費制度の詳しい区分と適用条件についてご説明します。
高額療養費制度は、医療費の負担を軽減するための重要な制度です。被保険者の年齢や所得区分に応じて細かく分かれています。この仕組みにより、予期せぬ高額な医療費が発生した際でも、必要な医療を受けやすくなり、多くの方が安心して治療を受けることができます。
自己負担限度額は、年齢や年収によって異なります。年齢区分に応じ、年収が高いほど自己負担限度額は高くなり、調整が行われます。70歳以上の高齢者の場合は、自己負担限度額が軽減されるしくみになっています。とくに医療費がかさむ高齢者にとっては大きな助けとなるでしょう。逆に、若年層や所得が多い方は高めの自己負担限度額が設定されている点も留意しておくべきです。
1か月の自己負担限度額(69歳以下)
|
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
| ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:所得901万円超 | 252,600円+(医療費−42,000円)×1% |
| イ | 年収約770万円~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万円~79万円 国保:所得600万~901万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
| ウ | 年収約370万円~約770万円 健保:標準報酬月額28万円~50万円 国保:所得210万~600万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| エ | 年収156万円~約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:所得210万円以下 | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
1か月の自己負担限度額(70歳以上)
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | うち外来(個人ごと) |
| 現役並み所得者 年収約1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
|
| 現役並み所得者 年収約770万円~約1,160万円 標準報酬月額53万円~79万円 課税所得380万円~690万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
|
| 現役並み所得者 年収約370万円~約770万円 標準報酬月額28万円~50万円 課税所得145万円~380万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
|
| 年収156万円~約370万円 標準報酬月額26万円以下 課税所得145万円未満等 | 57,600円 | 18,000円 [年144,000円] |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円 | 8,000円 |
| 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | 15,000円 | 8,000円 |
高額療養費の計算は、自己負担額が一定の限度を超えた場合に適用されます。計算の際は、医療費全体の請求額から自己負担限度額を引くことで、払い戻しの対象となる金額が算出されます。これにより、必要な医療を受けた後の実際の負担を明確に把握することができるようになります。限度額の設定は所得に基づいて決定されるため、年収や標準報酬月額など支給に関する情報をしっかり把握しておくことが重要です。

高額医療費の自己負担上限額についてお話しします。
2025年8月から高額医療費の自己負担上限額を引き上げる方針が固まりました。具体的には、3段階で引き上げ、2027年8月に平均所得層(年収約370万円〜770万円)で最大5万8500円を引き上げる見直し案となっています。自己負担限度額は年齢や所得に応じて異なっており、引き上げの範囲もそれぞれの条件によって異なります。例えば、現在の自己負担上限が月額で約8万円の患者もいれば、高齢者の収入が一定以下の場合には6万円程度に設定されていることもあります。新たな改定によって、段階的に引き上げられることになります。とくに高額な治療を受けなければならない患者にとっては、経済的な負担が増すリスクも否めませんが、低所得層の上げ幅を抑えるなどの対策も提案されています。
また、政府はこの改定に対し、必要な医療を受ける権利を保障することを目的としており、患者が安心して治療に専念できる環境の整備を続けるとのことです。実際に、医療機関による高額療養費制度の利用促進が期待されており、具体的には高額医療費貸付制度との連携も強化される見込みです。
とはいえ、引き上げに伴う新たな負担がどの程度の影響をもたらすのか、また、どのように制度を活用していくべきかについては、利用者がしっかりと理解しなければならない重要なポイントとなります。今後、これらの改定内容に関する情報が普及し、患者やその家族が適切に対応できるような環境が整備されることが望まれます。

高額療養費制度を利用するための申請方法を見ていきましょう。
高額療養費制度の利用には、適切な申請方法が重要です。医療費が高額になりそうな場合、事前に申請することが望ましいです。この制度を利用することで、医療費負担が軽減されます。申請方法には、事前に限度額適用認定を行う方法と、医療サービスを受けた後に高額療養費として申請する事後申請があります。自身の状況や医療の種類に応じた最適な申請方法を選択することが求められます。適切な手続きを行うことで、安心して医療を受けることができる環境が整います。
事前申請と事後申請は、高額療養費制度を利用する際に重要な2つの手続きです。事前申請は、医療サービスを受ける前に行うもので、限度額適用認定を受けることができます。この場合、医療機関で自己負担限度額を適用してもらえるため、窓口で支払う金額が軽減されます。対して、事後申請は医療サービスを受けた後に行う申請方法で、事後的に高額療養費を請求します。この申請方法では、自己負担限度額を超えた分が後日返金されますが、初めに全額を負担する必要があります。それぞれの状況に応じて、どちらの申請が適しているのか判断することが一つのポイントです。
会社で社会保険に加入している場合、高額療養費の申請手続きはやや異なります。まず、勤務先の健康保険組合または協会けんぽに、「高額療養費支給申請書」を提出する、もしくは「限度額適用認定証」を発行してもらうかのいずれかが基本でした。ただ、健康保険証新規発行廃止に伴い、マイナ保険証を利用すれば、事前に手続きなく、窓口が自己負担限度額まで軽減されて精算することができます。

高谷の経営視点のアドバイス
人工透析など長期にわたって治療を受ける場合などは、特定疾病療養受領証の手続きを行うことで、医療費を抑える制度や、同一世帯内で医療と介護の自己負担が高額になったときに利用できる制度もあります。正しく制度を理解しておくことで、負担を軽減できる制度もあります。

高額療養費制度の活用ポイントを知っておきましょう。
高額療養費制度には、医療費の負担を軽減するためのさまざまな活用ポイントがあります。例えば、家族全体の医療費を合算する、高額療養費の該当が複数回に渡る場合の仕組みも整備されています。これらの活用ポイントを把握し、事前に対策を講じることで、安心して医療を受ける環境が整います。
世帯合算とは、同じ世帯に属する家族全員が1年間に支払った医療費を合算し、その合計額に基づいて高額療養費を計算する制度です。例えば、夫婦それぞれの医療費がその月の自己負担限度額に達しなくても、合算することで高額療養費の対象となり負担額が軽減されることがあります。家族が共に医療を受ける機会が多い場合には、世帯合算を活用することが非常に有効な方法となります。ただし、世帯合算を利用する場合には、同じ公的医療保険に加入している必要があります。
高額療養費制度では、複数回自己負担限度額を超える医療費が発生した場合に「多数該当」の仕組みが適用されます。過去1年間に3回以上自己負担限度額を超え高額療養費を使用する場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がる設定となるため、経済的な負担が軽くなります。例えば、自己負担限度額が8万円程度の人が、3回以上自己負担限度額を超えている場合は、4回目以降の自己負担限度額は44,400円に引き下がり、その後の負担が大幅に軽減されるのです。この仕組みを活用することで、治療が長引くなどして高額な医療を受ける必要がある場合でも、経済的な負担を軽減しながら安心して治療を続けることが可能です。
高額医療費貸付制度は、高額な医療サービスを受ける際に事前に資金を借りることができる制度です。医療費が高額となったとき、支払う医療費の一部を無理しで借りることができます。高額療養費の限度額適用認定証など、事前に対応できる制度がありますので、あまり利用するケースは少ないかもしれませんが、急な医療費の負担に備えることが可能になります。これにより、安心して医療サービスを受ける環境が整うのは大きな利点です。

突然の病気やけがに対する備えとして高額療養費制度は覚えておきましょう。
高額療養費制度を利用することで、医療費の負担を大きく軽減することができます。突然の病気やけがに対する備えとして非常に重要な役割を果たしています。具体的には、自己負担限度額を設定することで、負担が過度に増えることを防ぐことが可能です。とはいえ、高額療養費制度だけではすべての医療費をカバーできるわけではありません。万一のために、貯蓄や保険を合わせて活用することが必要です。
高額療養費制度では全ての医療関連費用がカバーされるわけではありません。たとえば、治療に伴う雑費やオプションサービス、差額ベッド代などは自己負担となります。これらの費用が発生することを考慮し、事前に対策を立てておくことが大切です。民間の医療保険の活用や貯蓄も念頭に置き、補填できる範囲を確認するとよいでしょう。民間の医療保険の保険料は各年度の保険料控除の対象ともなるため、税金の軽減にもつながります。万が一の医療費の負担を抑えながら、経済的なメリットも享受できるというメリットがあります。医療保険の内容や高額療養費制度の自己負担限度額も理解した上で、適切な保険を選択することが求められます。事前の準備が、万一の出費に対する不安を軽減する手助けになります。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」