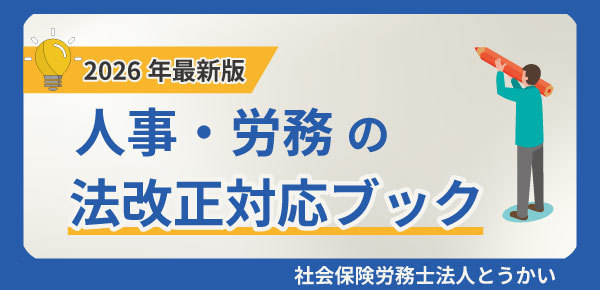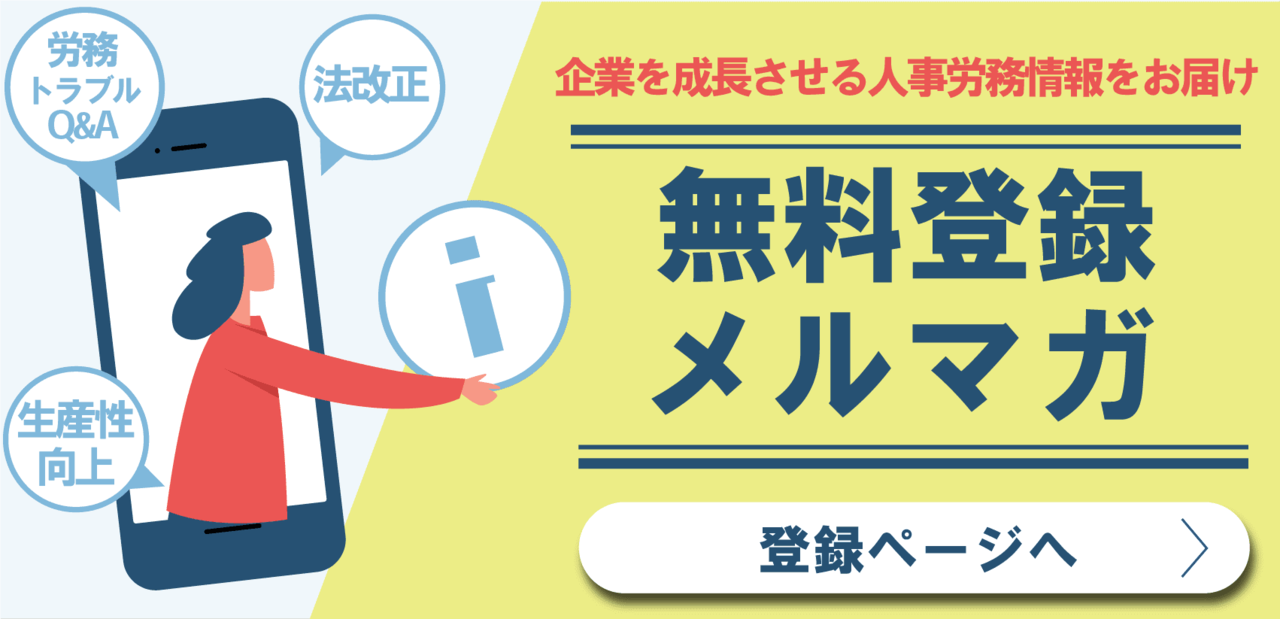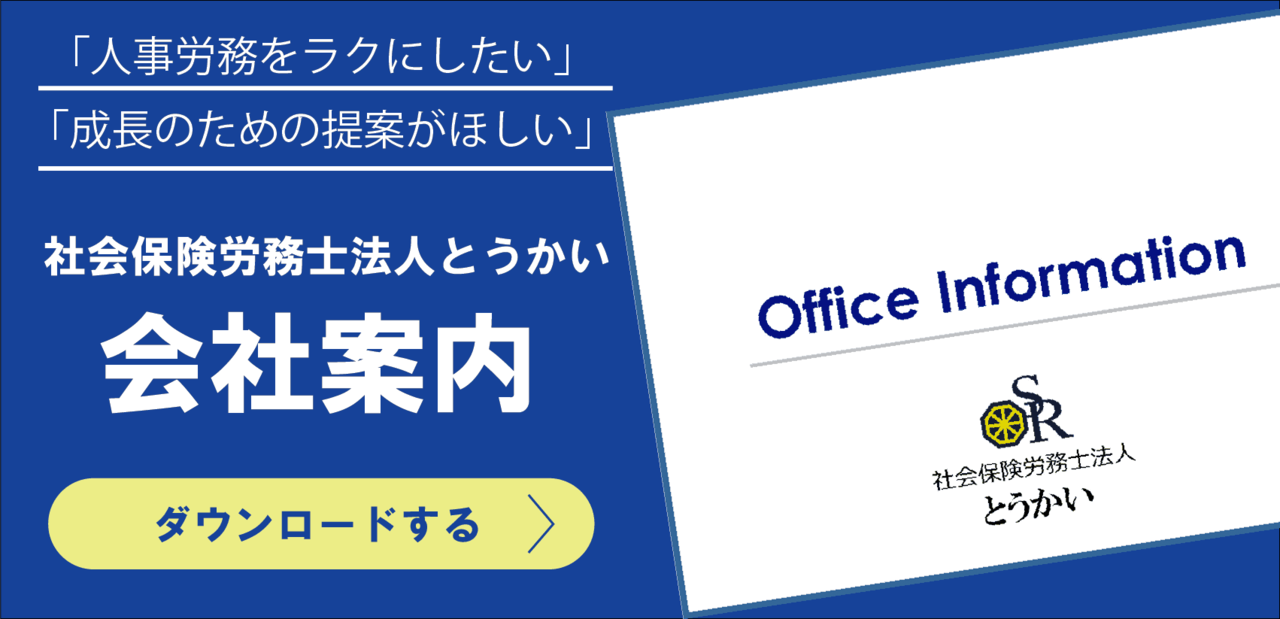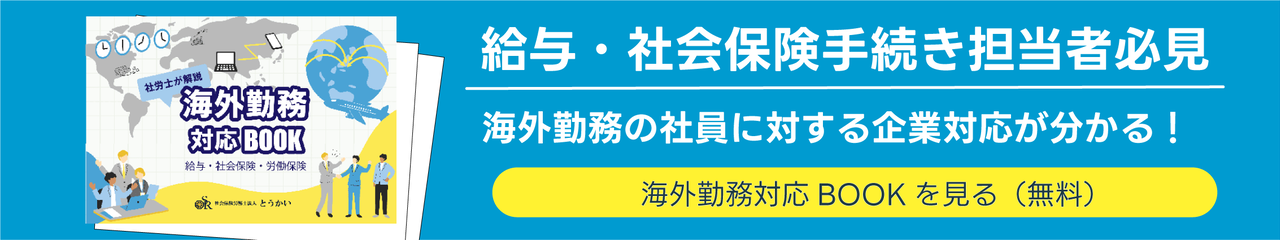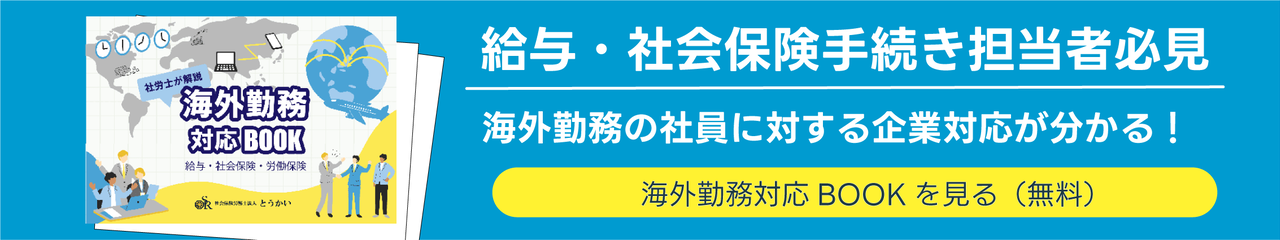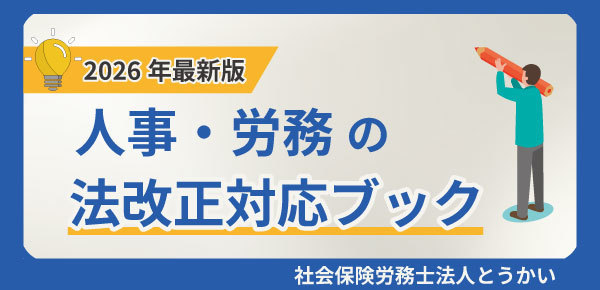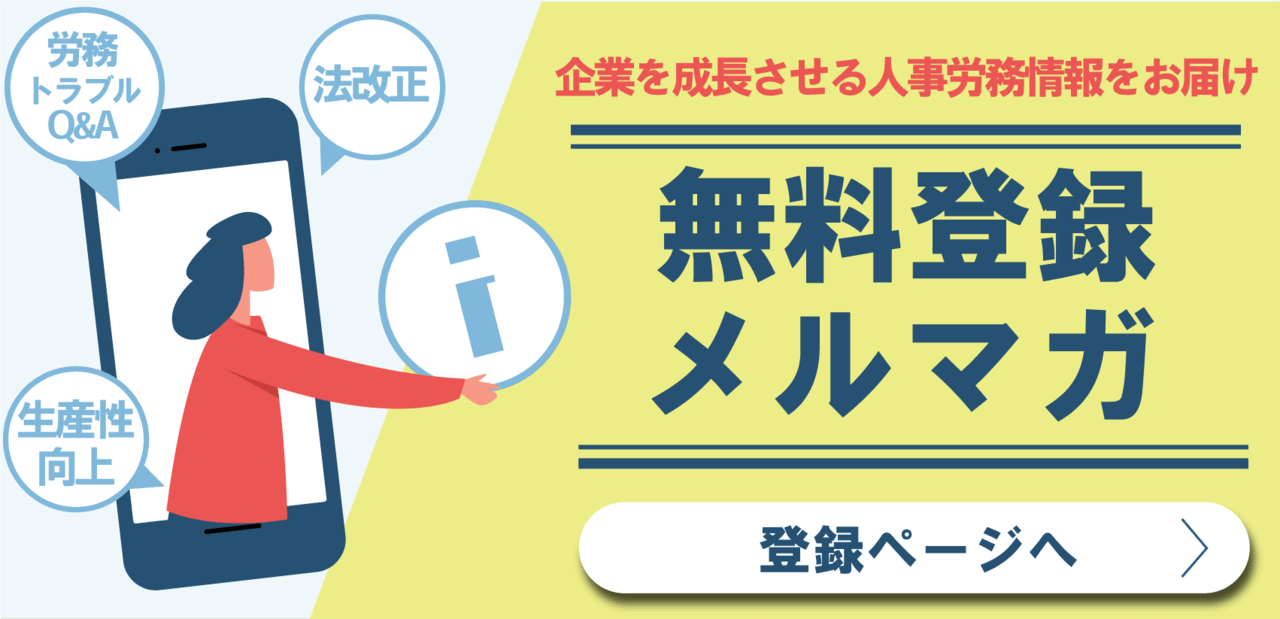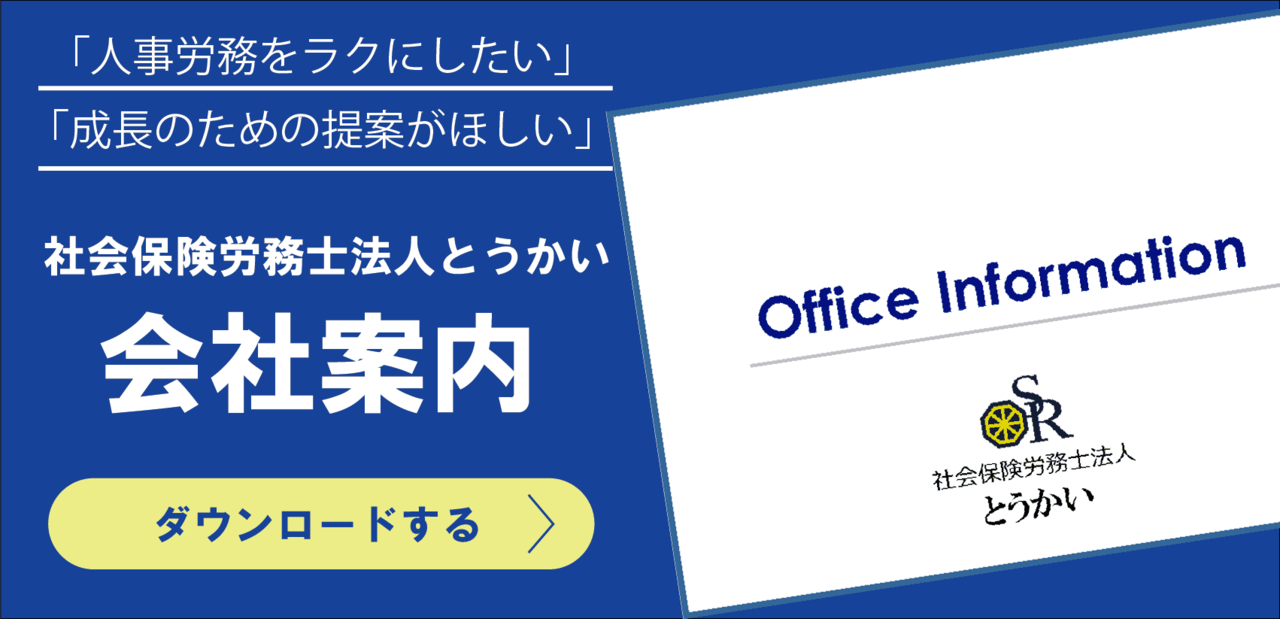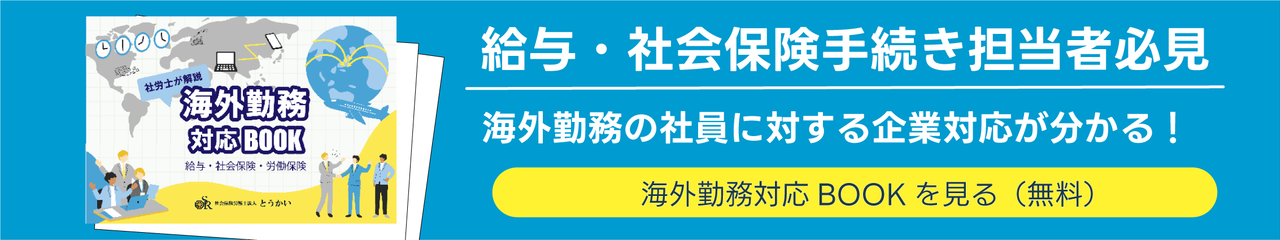海外赴任者など非居住者の年末調整や源泉徴収はどうなる?

グローバル展開をしている企業などは従業員を海外赴任させたり、外国人の従業員を雇用するケースも多いのではないでしょうか。従業員が海外赴任など日本国内の非居住者となる場合は、その期間や出国・帰国のタイミングによっては年末調整や源泉徴収の対象が変わります。間違えてしまうと二重課税になってしまうので注意が必要です。年末調整に備え、判断基準や企業がとるべき対応について解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

年末調整の基本的な概要について詳しく解説します。
年末調整とは、会社が従業員の給与・賞与から差し引かれる源泉所得税の過不足を、年末に納める年税額と精算調整するための手続きです。毎月の給与や賞与から差し引かれる源泉所得税は、概算で計算された金額です。正確な源泉所得税額は、1年間(1月1日~12月31日)に支払われた給与や賞与をもととして、再度計算します。さらに配偶者控除や生命保険料控除等といった控除額などを反映し、その年の所得税額が確定することになります。
確定した所得税の計算結果と、概算で控除してきた金額を比べ、払い過ぎであったならば差額が還付され、不足があれば不足分を徴収するといった手続きを行うことになるのです。
本来、従業員一人ひとりが行う確定申告の手続きを、会社で年末調整という手続きで行えるということになります。
年末調整の対象となる人は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人で、年末まで勤務している従業員です。ただし、年収が2000万円を超える場合や、医療費控除を適用する人、雑所得などがある、2か所以上から給与をもらっていて、他の勤務先で年末調整を受ける人など場合には、年末調整の対象外で確定申告の必要が生じます。加えて、年の途中で退職した人や、海外に転勤になって、非居住者である場合にも同様です。
年末調整とは?手続きのデジタル化について詳しくはこちら
年末調整とはtokai-sr.jp/year_end_adjustment/year-end-adjustment
所得税法上では、納税義務の判断を日本での「住所または居所」の有無で区分します。ここでの「住所」とは生活の本拠を指し、一方の「居所」は生活の本拠とまではいえないが相当期間にわたって継続居住している場所のことをいいます。
所得税法上では、「居住者」とは、国内に住所を有し、また現在まで引き続き1年以上居所を有する人のことを言います。この居住者以外の人を「非居住者」と規定しています。
そこで、海外赴任者が居住者なのか、非居住者なのか判断するには、海外への出張期間が1年未満であるか、超えるのかを判断します。1年未満の場合は日本の居住者に該当します。1年以上の予定で日本を離れる場合は「非居住者」に該当します。居住者と非居住者では課税される所得の範囲が大きく異なるため、どちらに該当するかの判断が重要になります。
図1 所得税による居住者・非居住者の区分
| 定義 | 国内源泉所得 | 国外源泉所得 | ||
|---|---|---|---|---|
| 居 住 者 | 非永住者以外の居住者 | 次のうちいずれかに該当する個人のうち非永住者以外の者 ・日本国内に住所を有する者 ・日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者 | 課税 | 課税 |
| 非永住者 | 居住者のうち、次のいずれにも該当する者 ・日本国籍を有していない者 ・過去10年以内において、日本国内に住所又は居所を有していた期限の合計が5年以内である者 | 課税 | 国内で支払われたもの及び国内に送金されたもののみ課税 | |
| 非居住者 | 居住者以外の個人(1年以上の予定で日本を離れる者人は非居住者に該当) | 課税 | 非課税 | |
藤井恵(2023) 海外出張・海外赴任の税務と社会保険の実務ポイント 税務研究会出版局

海外赴任者の出国時年末調整についての詳細を見ていきましょう。
年末調整の対象者は、日本国内の居住者ですので、非居住者は対象外です。非居住者の定義を正しく理解していなければ間違って年末調整をおこなってしまう恐れがあります。そのため居住者と非居住者の違いについて正しく理解する必要があります。
自社の従業員が海外赴任する場合、すでに海外赴任している場合について、取り扱いを正しく理解しておきましょう。
まずは海外での勤務期間が1年未満の場合は、日本国内の「居住者」に該当し、年末調整の対象者になります。また、年の途中で海外赴任をおこなう従業員も年末調整の対象者になる場合があります。年の途中で海外赴任する場合は、出国する日までに確定した収入に対して、出国する日までに年末調整をおこなう必要があります。これを「出国時年末調整」といいます。
出国時年末調整は以下の両方に当てはまる場合に必要となります。
・年の途中で1年以上の海外赴任のため出国する
・年末調整の対象となるその時の確定した給与が2,000万円以下
たとえば、3月31日に3年の任期で出国した従業員への年末調整の扱いは次のようになります。
・1月1日~3月31日の期間の給与→出国時年末調整で精算する
・4月1日以降の給与→原則、国外源泉所得として年末調整・源泉徴収の必要なし
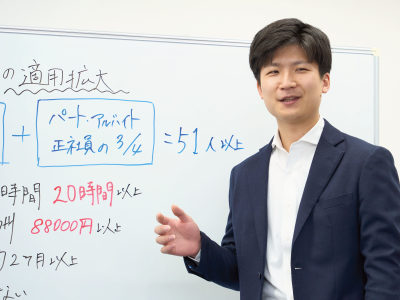
非居住者の課税所得と年末調整について解説します。
所得税法上の非居住者である場合、日本の居住者ではないため日本における所得税の課税はありません。ただし、この場合であっても、海外赴任者が出張で日本に一時帰国し、日本国内で役務を提供した場合には、当該役務の提供に係る対価は国内発生したと考えられるため、国内源泉所得に該当することになり、日本において所得税が課されます。
住者のうち非永住者と判定された場合、国内源泉所得についての扱いは変わりませんが、国内源泉所得のうち日本国内において支払いを受ける、または海外からの送金を受けた場合のみ日本の所得税が課税されることになります。
非永住者が国外で役務を提供し、給与にその対価が含まれており国内で支払いを受ける等の場合は、日本で所得税が課されます。国外源泉所得のうち、日本で課税となる所得については二重課税に注意する必要があります。
不動産の賃貸収入などは自己都合により発生する国内源泉所得であるため、二重課税や複数の国での納税を避けたい場合は資産を手放すことによりなくすことができます。
しかし、海外赴任の際に発生する所得の中には個人の都合ではなく、会社の都合で発生してしまう税金もあります。例えば、日本と租税条約を締結していない国へ赴任することになり、不必要に二重課税がなされ納税額が増加した場合です。
会社都合で発生したものであっても、これらの税金を会社が負担してしまうと当該社員への給与とみなされ、個人の所得が増加し、税額はさらに増えてしまいます。
租税条約を締結している国はこちら 財務省公式HPhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html

配偶者控除・扶養控除の適用条件を詳しく解説します。
配偶者控除・扶養控除が受けられるかどうかの判定要点として「生計を一にしているか」「控除の対象とできる所得水準であるかどうか」等がありますが、出国時の状況によって判断するということになっています。
出国をした年の所得控除のうち、配偶者控除や扶養控除については納税管理人の有無によって控除の基準が異なります。
海外勤務として非居住者の方が、日本国内で発生した一定の所得について確定申告する場合に、納税管理人の選任しているケースがあります。納税管理人とは、確定申告を提出すべき納税者(この場合は海外赴任者)に代わって、納税の手続きを行う人や法人となります。
納税管理人を選定・届出していた場合は、非居住者となった年の翌年の申告期限までに納税管理人が納税手続きをすることになります。この場合、扶養控除の対象は12月31日の時点の状況で決まります。
例えば、海外赴任後に子どもが16歳を迎えて扶養対象者が増えた場合は扶養控除を受けることができます。
一方、納税管理人を選定・届出していない場合は、出国の前日までに年末調整と確定申告を行うことによりその年の課税の対応を完了させる必要があるため、出国後に扶養控除の適用対象者が増えたとしてもその分の控除は受けることができません。
出国前に納税管理人を届け出るか否かによって扶養控除対象の人数が変わる可能性はありますが、納税管理人の有無で控除の金額が変わることはありません。年の途中で納税管理人を選定・届出せずに非居住者となったとしてもその年に受けることのできる基礎控除額は38万円で変わらず、非居住者になった期間について月数按分等により減額されることもありません。
図2 納税管理人の有無による扶養控除の取扱いの違い
| 納税管理人あり | 納税管理人なし | |
|---|---|---|
| 確定申告の期限 | 翌年の3月15日 | 出国の日の前まで |
| 扶養控除の期限日 | その年の12月31日を基準とする →出発後に扶養控除の対象が増えた場合、扶養控除の計算に含めることができる | 出国時の状況を基準とする →出発後に扶養控除の計算に含めることはできない |
| 扶養親族の判定 | その年の所得が38万円以下か、生計を一にしているか等について、12月31日の状況で判定する | その出国の日の現況により判定 |
| 扶養控除の額 | 各扶養親族の区分に応じた控除額 |
佐藤広一 檜田和毅(2014) 海外赴任海外出張の労務と税務早わかりガイド アニモ出版

社会保険料と生命保険料の控除は、居住者がその年に支払ったものが対象です。
社会保険料と生命保険料の控除は、居住者がその年に支払ったものが控除の対象となります。出国時年末調整を行う場合には、その年の1月1日から出国日までに支払った社会保険料が控除対象になります。非居住者であった期間内の給与から控除した社会保険料は、社会保険料控除の対象にはなりません。
生命保険料に関しても同様で、保険料が居住者期間内に支払われたものなのか、非居住者期間中に支払われたものなのかにより判断されます。年払いで支払っている場合はその時点で居住者であれば全額が生命保険料控除の対象となります。
年末調整において、配偶者控除、基礎控除、保険料控除および所得金額調整控除の適用を受けようとする場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」、「給与所得者の基礎控除申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」および「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。

海外出張者や海外赴任者は少しずつ増えてきているものの、様々なリスクや労務管理の難しさにより現時点でもまだ少ない状況です。しかし、コロナ禍を経て海外からもリモートで働くことができるという証明もされ、今後は増えてくると予測されます。またいずれは物理的に人を海外に送り出さなければならない業務がある企業もいらっしゃると思います。グローバル化が進む今、海外赴任者に求められる役割も大きくなっているでしょう。それに伴って、海外で活躍する従業員をサポートするための人事担当者の負担も大きくなることが予想されます。今回ご紹介した年末調整といった税金のことから、社会保険をはじめとした取り扱いも要件によって、手続きが変わってきます。また、海外赴任時の労災事故などの対応や、労務管理はわかりにくいことも多いのです。
社会保険労務士法人とうかいでは、必要な手続きや就業規則作成などを承っております。これから海外赴任を検討している、海外赴任者の社会保険手続きなどにお困りであれば、お気軽にご相談ください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」