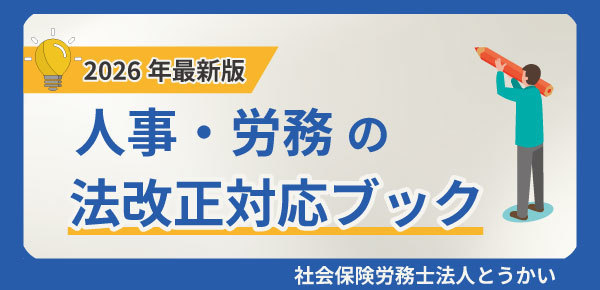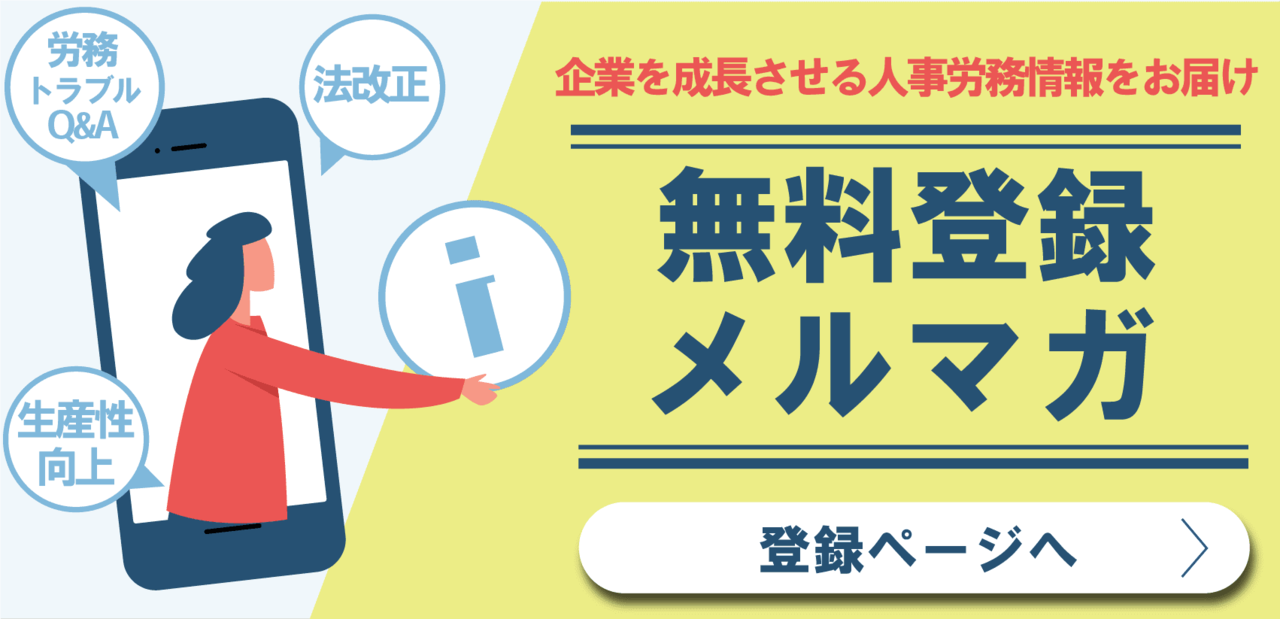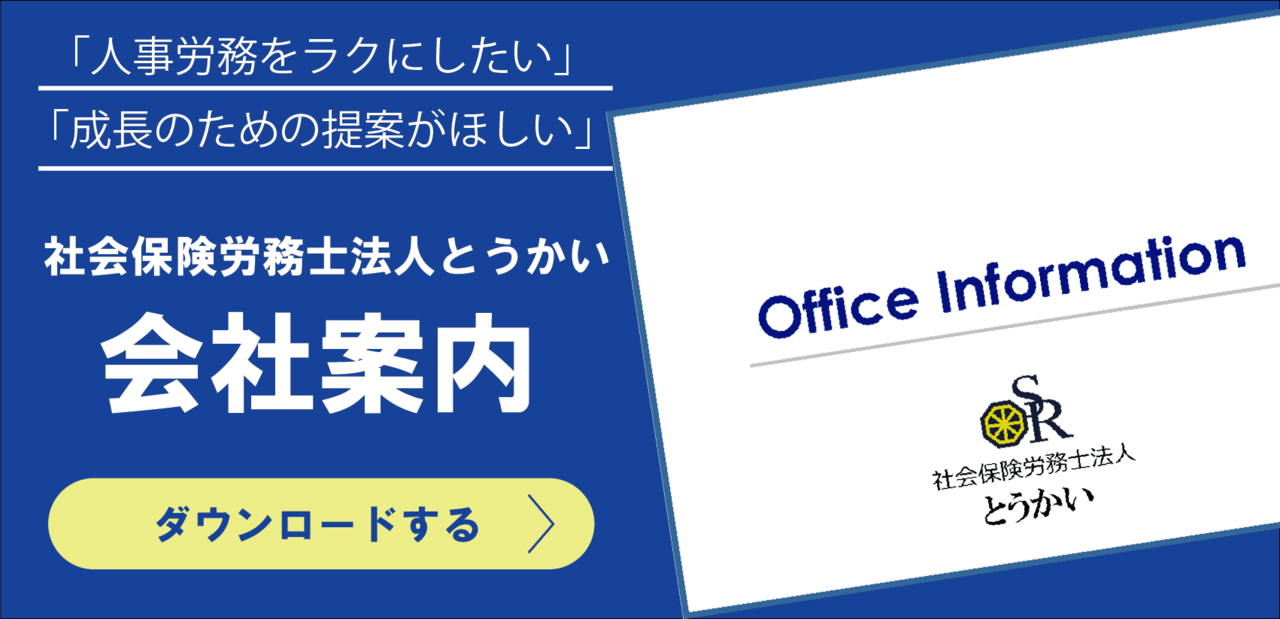【テンプレート付き】一斉休憩適用除外の労使協定書の作り方

原則として、従業員には休憩を一斉に付与しなければなりません。ただし、もともと一斉休憩が適用除外の業種や、労使協定を締結した事業所においては、休憩の一斉付与の適用が除外されます。
事業運営上、従業員に交代で休憩を取得させたい場合は、一斉休憩適用除外の労使協定書を作成しましょう。適用除外の業種に該当せず、また労使協定書を作成せずに休憩を一斉取得させなかった場合、労働基準法違反となります。
事業運営をスムーズにしつつ、従業員が快適に働ける環境を作るためにも、一斉休憩適用除外の労使協定書をきちんと作成しましょう。
本記事では、無料でご利用いただけるテンプレートも用意しておりますので、ぜひご活用ください。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから


一斉休憩適用除外の基礎知識について解説します。
一斉休憩とは、すべての従業員が同時に休憩を取ることです。労働基準法では、原則的なルールとして、休憩の一斉付与が事業主に義務づけられています。
ただし、以下に該当する業種に関しては、休憩時間の一斉付与が適用除外となります。
● 運輸交通業
● 商業
● 金融広告業
● 映画・演劇業
● 通信業
● 保健衛生業
● 接客娯楽業
● 官公署
これらの業種は、従業員が休憩を一斉に取得すると、サービスを提供する体制を維持できません。そのため、すべての従業員に休憩時間を一斉付与する必要はありません。
他にも、企業の業務形態によっては、全ての従業員が一斉に休憩を取ることが困難な場合もあるでしょう。このような場合、労使間において「一斉休憩の適用除外に関する労使協定」を締結することにより、一斉休憩の適用除外が認められます。

高谷の経営視点のアドバイス
なお、休憩時間中は、従業員が自由に過ごせる状況である必要があります。休憩時間でも、電話や来客の対応が必要な「手待ち時間」は、自由利用の原則に反しており、休憩とはみなされません。

一斉休憩適用除外に関する労使協定の作成方法を解説します。
「一斉休憩の適用除外に関する労使協定」では、業務の特性や労働条件を考慮したうえで、どのような方法で休憩の取り方を運用するか具体的に定めます。
企業の実情にあわせて、柔軟に休憩時間を運用することで、業務の効率化や従業員のエンゲージメント向上などを実現できます。以下で、具体的な労使協定の作成方法を解説します。
まずは企業内での労働条件や業務内容を正確に把握したうえで、一斉休憩適用除外を必要とする理由を明確に定義しましょう。具体的かつ合理的な説明を加えることにより、実効性のある労使協定を作成できます。
一斉休憩適用除外の対象となる従業員は誰なのか、また休憩はどのように取得するのかを明記しましょう。例えば、企業内で特定の部署だけ一斉休憩適用除外としたい場合は、「製造部門について、一斉付与の原則を除外する」といった旨を記載します。
休憩時間の取得方法については、班別・チーム別に交代制とするのか、何時から何時までを休憩時間とするのかを定めましょう。このように、実施方法や時間帯などに関する具体的な情報を記載することで、従業員が不安なく業務に取り組めます。

大矢の経営視点のアドバイス
労使協定を作成したあとは、労働環境の変化に応じて、定期的に見直す必要があります。休憩は従業員の安全に欠かせないため、細部にわたる配慮を加えて、生産性を向上させていきましょう。

フレックスタイム制における一斉休憩の適用除外についてです。
フレックスタイム制を導入している企業においても、一斉休憩の適用除外を導入するためには、労使協定書の作成が欠かせません。
フレックスタイム制とは、従業員が自身の裁量で勤務時間を調整できる制度です。そのため、全従業員が同じタイミングで一斉に休憩を取ることは現実的ではありません。
以下で、フレックスタイム制度を導入している企業が、一斉休憩の適用除外の労使協定を締結する際の注意点を解説します。
コアタイムが設定されているフレックスタイム制においては、休憩時間をコアタイム内に設定します。一斉休憩を適用しないためには、「一斉休憩の適用除外に関する労使協定書」を締結しましょう。
協定内で、コアタイム中に与える休憩の長さや具体的に取得する時間帯を定めましょう。
コアタイムがないフレックスタイム制を採用している企業において、一斉休憩の適用除外を受けるためには、労使協定の締結が必要です。各従業員は自身の働き方に合わせて、定められた時間内において、自由に休憩を取得できます。
ただし、業務を円滑に回すためには、休憩時間が業務へ与える影響を最小限に抑える必要があります。柔軟な選択肢を提供しつつも、業務への支障が出ないような休憩時間を設定しましょう。

よくある質問と回答例を紹介します。
最後に、一斉休憩の適用除外に関する労使協定に関するよくある質問を紹介します。
一斉休憩適用除外の労使協定書は、労働基準監督署への届出は不要です。協定を締結したあと、従業員がいつでも確認できるように備えておきましょう。
休憩時間に関する事項は、就業規則の「絶対的必要記載事項」に含まれます。そのため、労使協定を締結したあとは、就業規則の内容も変更しましょう。
一斉休憩の適用除外に関する労使協定の有効期間は、最長3年まで定められます。しかし、実務上は有効期限を1年間として、毎年必要に応じて内容を修正するのが一般的です。

従業員の休憩時間に幅を持たせ、交替制にしたい場合は「一斉休憩適用除外の労使協定書」を作成する必要があります。労使間で適用除外の理由やその条件を明確にし、どのように休憩時間を取得すればよいのかを明確にしましょう。
企業内の業務運営体制を整備しつつ、従業員が心身を休める時間をきちんと確保することで、生産性を維持できます。また、締結した労使協定書はしっかりと書面・デジタル上に残し、就業規則にも反映させましょう。
労使協定の作成や就業規則の改訂などでお悩みの方は、社会保険労務士法人とうかいへお問い合わせください。企業を成長させるためには、労使間で信頼関係を築くことが欠かせません。労使間で信頼関係を築き、安心して働ける環境を整備するために欠かせないのが、労使協定と就業規則です。

鶴見の経営視点のアドバイス
弊社では、事業主様の思いや事業の実態を踏まえて、オーダーメイドで協定や規程を作成しております。人事労務の専門家として、事業の成長をサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。


最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」