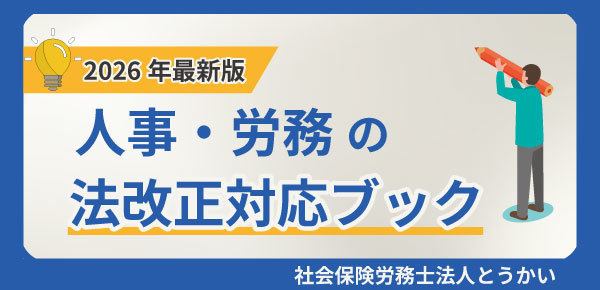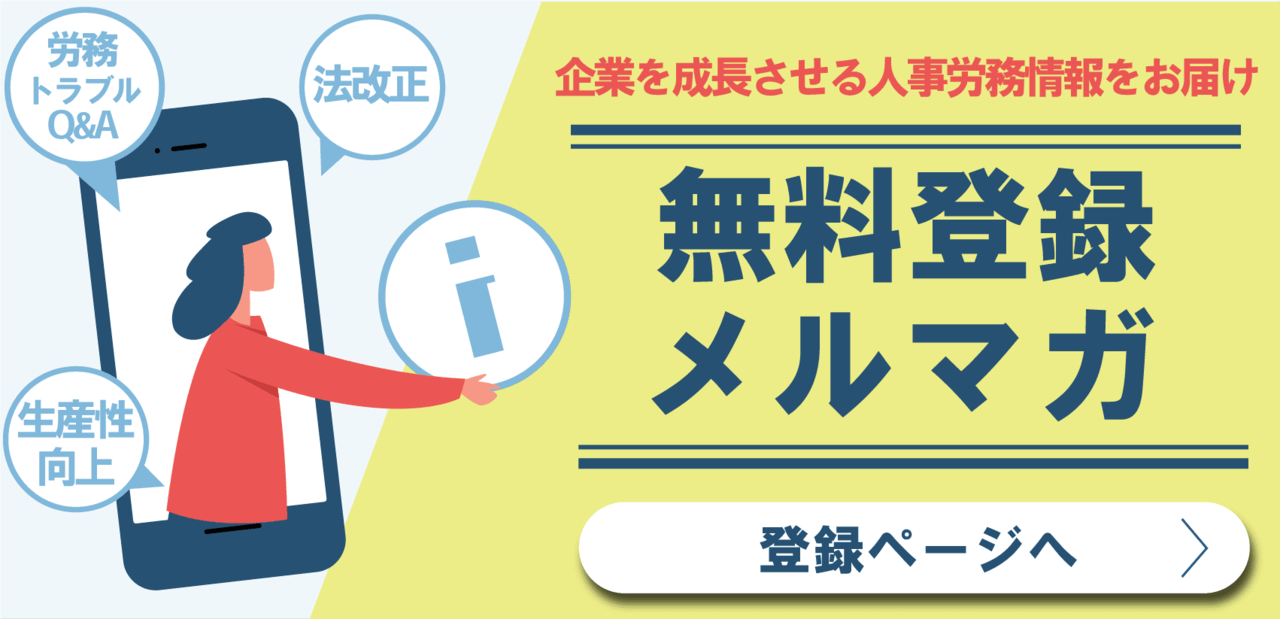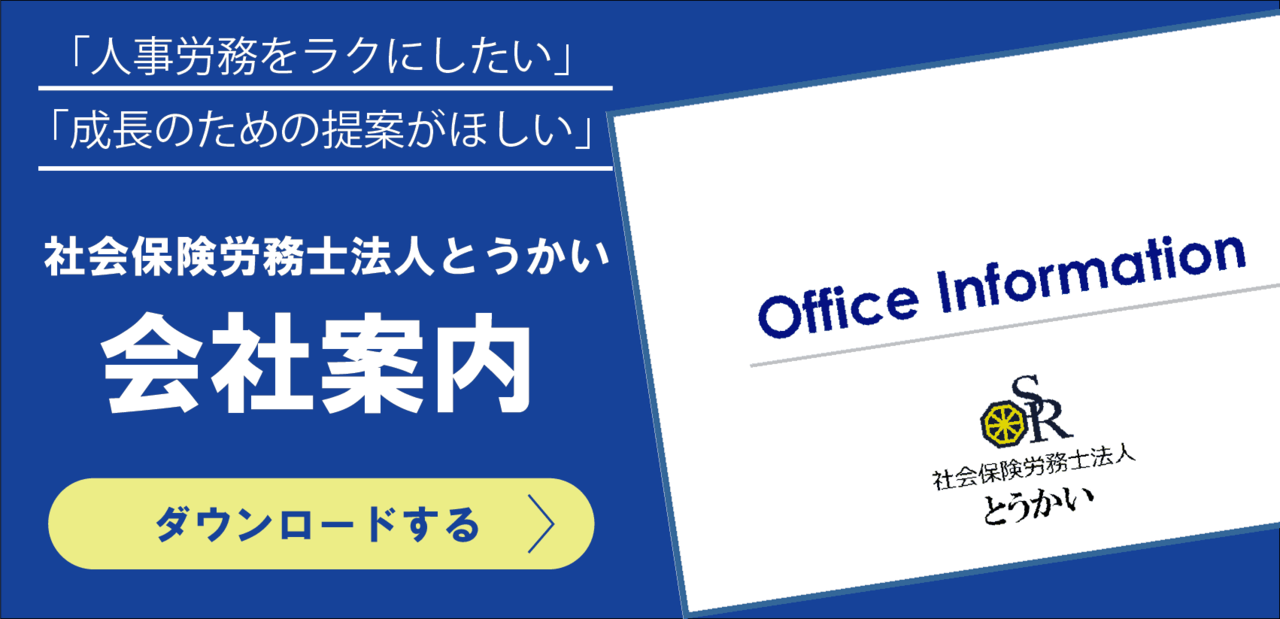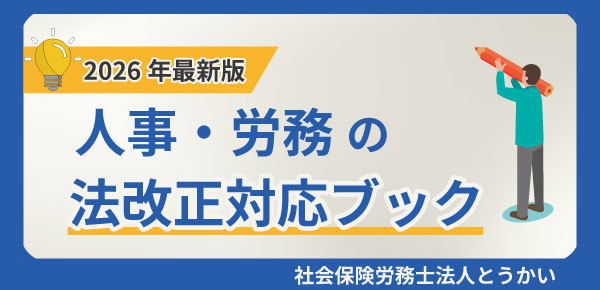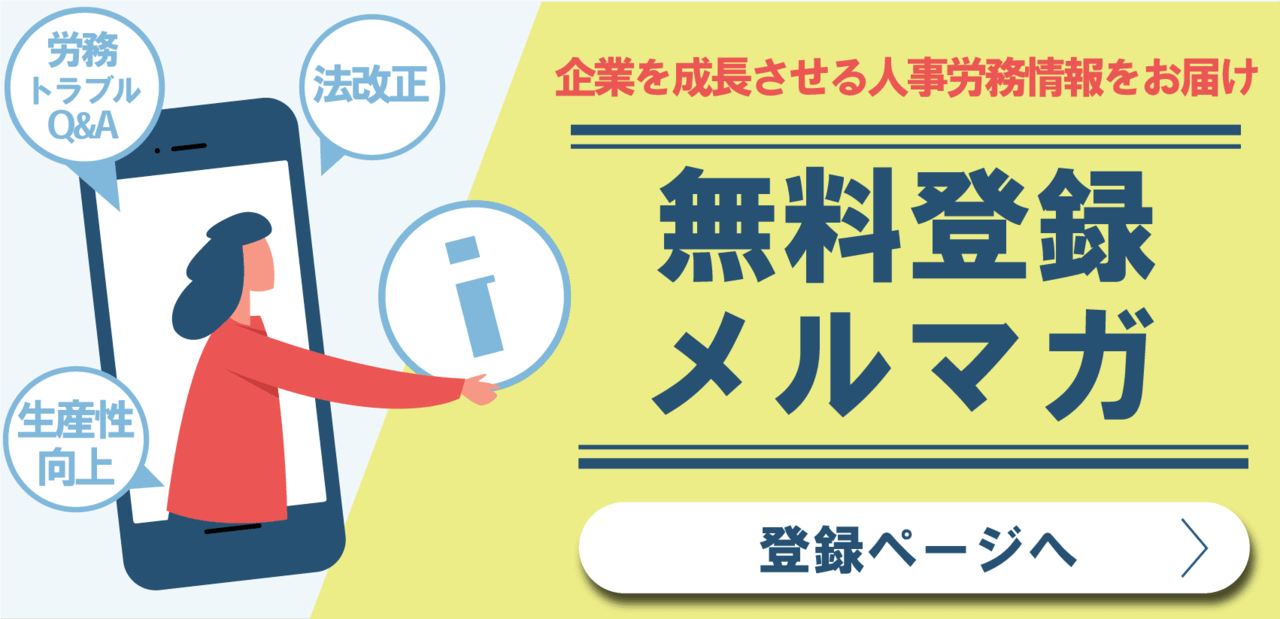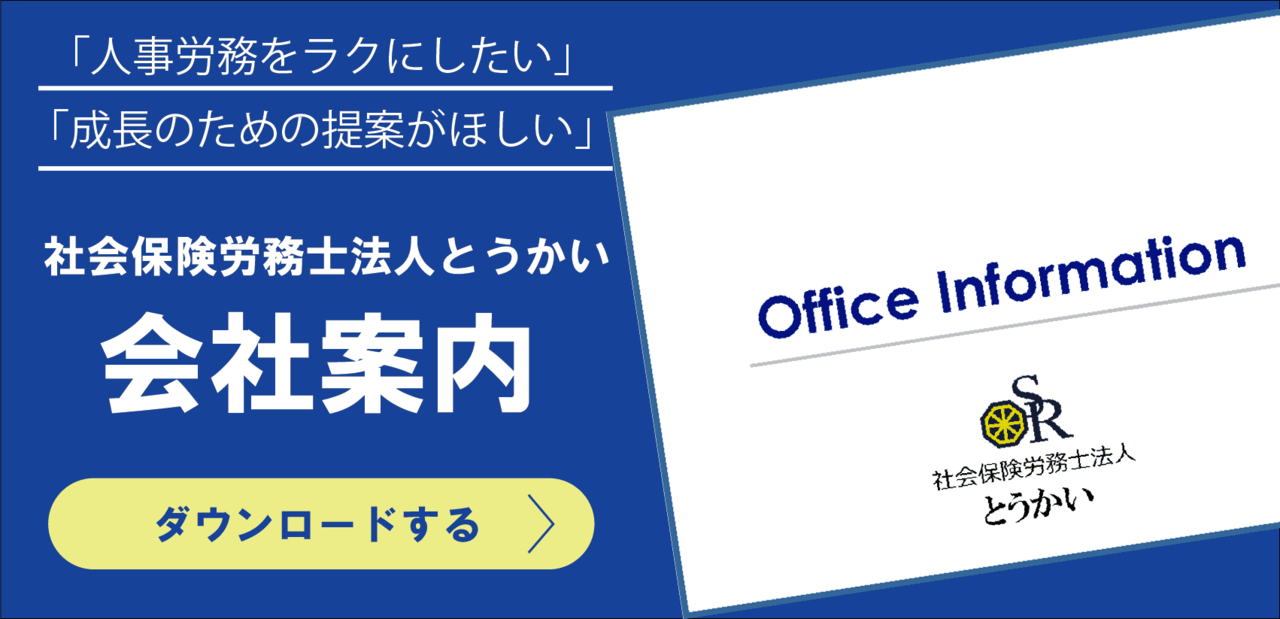2026年改正女性活躍推進法、従業員101人以上の情報開示義務を解説

2026年に施行が予定されている改正女性活躍推進法により、これまで努力義務とされてきた従業員数101人以上300人以下の企業においても、女性活躍に関する情報公表が義務化される見通しです。
この法改正は、企業の規模にかかわらず、男女間の格差是正と女性の社会での活躍を一層推進することを目的としています。
新たに対象となる企業は、男女間の賃金格差や女性管理職比率といった自社の状況を把握し、外部へ開示する義務を負うことになります。
本記事では、この法改正の背景と具体的な内容、企業が取るべき対応について解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

2026年の法改正の内容、把握していますか?
2026年に予定されている女性活躍推進法の改正は、情報公表義務の対象企業を大幅に拡大する点が最も重要なポイントです。
これまで、この義務は常時雇用する労働者が301人以上の大企業に限られていましたが、改正後はその範囲が101人以上の企業にまで広がります。
これにより、新たに対象となる中小企業は、自社の女性活躍に関する状況を数値で把握し、指定された項目の中から選択して公表することが求められます。
具体的には、「男女の賃金の差異」や「女性管理職比率」などが公表項目に含まれており、企業の透明性を高め、自主的な取り組みを促すことが狙いです。

改正のポイントを押さえて、早めの対応を。
今回の法改正で、情報公表の義務化対象が拡大されます。
従来、この義務は常時雇用する労働者数が301人以上の大企業に課されていました。
しかし、2022年7月の改正で男女の賃金差異の公表が義務付けられた流れを受け、2026年からは、新たに従業員数101人以上300人以下の企業も対象に含まれる見込みです。
これまで努力義務とされていた規模の企業が、法的義務を負うことになります。
一方で、従業員数が100人以下の企業については、引き続き努力義務とされています。
この変更により、より多くの中小企業が女性の活躍状況に関する情報を開示する必要が生じ、社会全体で女性活躍を推進する体制が強化されることになります。

2026年の法改正により、従業員数101人以上の企業に義務付けられる情報公表は、大きく分けて2つのカテゴリーから構成されます。
まず、全ての対象企業が必ず公表しなければならない必須項目があります。
これに加えて、企業が自社の状況に応じて選択して開示する項目群が設けられています。
これにより、各企業は自社の課題や強みを踏まえた情報開示が可能です。
公表は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社のウェブサイトなど、求職者や一般の人が容易に閲覧できる方法で行う必要があります。
適切な項目を選択し、正確な情報を開示することが求められます。
情報公表項目の中でも特に重要なのが、男女間の賃金格差の状況です。
具体的には、「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の3つの区分それぞれについて、男性の賃金の中央値に対する女性の賃金の中央値の割合を算出し、パーセンテージで公表する必要があります。
この計算には、基本給だけでなく、賞与や各種手当などを含めた年間の総賃金が用いられます。
賃金格差の背景には、雇用形態の違いや勤続年数の差、役職の偏りなど様々な要因が考えられるため、企業は算出された数値を公表するだけでなく、その差異がなぜ生じているのかを分析し、任意で補足説明を記載することも可能です。
これにより、企業は自社の課題を客観的に把握し、格差是正に向けた具体的な取り組みを検討するきっかけとなります。
女性管理職の割合の公表は、企業の意思決定層におけるジェンダーバランスを示す重要な指標です。
この項目では、「管理職に占める女性労働者の割合」を計算し、開示することが求められます。
ここでの「管理職」とは、一般的に「課長級」以上の役職にある者を指し、企業の組織体系に応じて定義されます。
この数値を算出・公表することにより、企業は管理職登用における男女間の機会均等が進んでいるか否かを客観的に評価できます。
割合が低い場合には、女性従業員のキャリアパス支援や育成プログラムの見直し、評価制度の公平性の確保といった課題が浮き彫りになる可能性があります。
自社の現状を正確に把握し、将来的な改善目標を設定するための基礎情報として活用することが期待されます。
必須項目である「男女の賃金差異」に加え、企業は指定された選択項目の中から自社の状況に応じて一定数の情報を公表する必要があります。
この選択項目は「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の2つの区分に大別され、合計で10数項目の選択肢が用意されています。
例えば、男女別の採用における競争倍率、男女別の平均継続勤務年数の差異、有給休暇取得率、育児休業取得率、月平均の残業時間といった項目が含まれます。
企業はこれらの項目の中から、自社の課題解決や取り組みのアピールにつながるものを戦略的に選び、公表することが可能です。
どの項目を選択し開示するかが、企業の女性活躍推進に対する姿勢を示すことにもなります。

さまざまな業界の中小企業が、女性活躍推進に取り組んでいます。今回の改正女性活躍推進法の義務化対象は101人以上の企業ではありますが、100人未満の企業であっても、積極的に取り組んでいることがわかります。
どのような取り組みを行なっているか事例を紹介します。
厚生労働省:女性活躍・両立支援に積極的に取り組む企業の事例より
法改正への対応は、まず自社の状況を客観的な数値で把握することから始まります。
具体的には、採用した労働者に占める女性の割合、男女の平均継続勤務年数の差異、月間の平均残業時間、管理職に占める女性の割合といった基礎項目について、データを収集・分析する必要があります。
特に、公表が義務付けられる男女間の賃金格差については、正規・非正規といった雇用形態別に正確なデータを算出しなければなりません。
これらのデータを集計し分析することで、自社の強みと課題が明確になります。
例えば、女性の採用比率は高いものの、管理職登用が進んでいないといった実態が明らかになるかもしれません。
この現状把握が、後のステップで実効性のある行動計画を策定するための土台となります。
現状分析によって明らかになった課題に基づき、具体的な行動計画を策定します。
この計画には、達成すべき「目標」、目標達成のための「取組内容」、そして計画を実行する「期間」の3つの要素を盛り込むことが必要です。
例えば、「3年以内に女性管理職比率を15%に引き上げる」といった具体的な数値目標を設定し、そのための施策として「女性社員向けのキャリア研修を実施する」「管理職候補者の育成計画を見直す」といった具体的な取組内容を定めます。
策定した行動計画は、単に書類を作成するだけでなく、社内イントラネットへの掲載や説明会の実施などを通じて、全従業員にその内容を周知徹底させることが重要です。
従業員の理解と協力を得ることで、計画の実効性が高まります。
策定した行動計画は、社内への周知と同時に、社外のステークホルダーに向けて公表する義務があります。
公表の方法としては、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への掲載や、自社の公式ウェブサイトへの掲載が一般的です。
これにより、求職者、取引先、投資家など、外部の関係者が企業の女性活躍推進への取り組みを客観的に評価できるようになります。
特に求職者にとっては、企業選びの重要な判断材料となり、採用活動においても有利に働く可能性があります。
公表する際には、単に計画を掲載するだけでなく、企業のトップメッセージを添えるなど、その取り組みに対する真摯な姿勢を示すことも有効です。
透明性の高い情報開示は、企業の社会的信頼を高めることにつながります。
行動計画を策定し、社内外への公表を終えたら、最後のステップとして管轄の都道府県労働局へ届け出を行います。
この届出は、企業が女性活躍推進法に基づき、適切に行動計画を策定したことを公的に証明する手続きです。
届出には、所定の様式である「一般事業主行動計画策定・変更届」を使用します。
この様式に行動計画の内容や企業の基本情報を記入し、労働局の雇用環境・均等部(室)へ提出します。
提出方法は、窓口への持参、郵送、あるいは電子申請システム「e-Gov」を利用したオンラインでの手続きも可能です。
この届出を完了させることで、法に基づいた一連の対応が完了したことになります。
届出を怠ると、法的な義務を果たしていないと見なされる可能性があるため、忘れずに行うことが肝要です。

現行の女性活躍推進法では、情報公表の義務を怠った企業に対する直接的な罰則規定は設けられていません。
しかし、これは何もしなくて良いという意味ではありません。
厚生労働大臣は、義務を果たさない企業に対して報告を求めたり、助言、指導、勧告を行ったりする権限を持っています。
さらに、勧告に従わない場合には、企業名を公表することができると定められています。
企業名が公表されると、社会的な信用が失墜し、企業のブランドイメージに深刻なダメージを与える可能性があります。
これにより、採用活動において優秀な人材が集まりにくくなったり、取引先や金融機関からの評価が低下したりするなど、事業活動に具体的な悪影響が及ぶリスクがあります。
罰則がないからと軽視せず、法令遵守の観点から誠実な対応が求められます。
法改正への対応は、単なる義務の履行に留まらず、企業経営に多くのメリットをもたらします。
第一に、多様な人材が活躍できる職場環境を整備することで、優秀な人材の確保と定着につながります。
特に、求職者は企業の働きやすさやキャリアパスの透明性を重視する傾向が強まっており、情報公開は採用競争力を高める上で有効です。
第二に、女性従業員の視点や能力が製品開発やサービス向上に活かされることで、新たなイノベーションが生まれ、企業全体の生産性向上に貢献します。
第三に、女性活躍推進に積極的に取り組む企業として社会的な評価が高まり、企業イメージの向上が期待できます。
これは、取引先や金融機関からの信頼獲得、さらにはESG投資を重視する投資家からの評価にもつながる可能性があります。

行動計画の策定や取り組みで迷った際には、ご相談ください。
2026年に施行が予定される改正女性活躍推進法は、従業員数101人以上の企業に情報公表の義務を課すものであり、対象となる中小企業は早期の準備が求められます。
対応の第一歩は、男女間の賃金格差や女性管理職比率など、自社の現状をデータに基づいて正確に把握することです。
その上で、課題解決に向けた具体的な行動計画を策定し、社内外へ公表、そして労働局への届出という一連のプロセスを計画的に進める必要があります。
義務を怠った場合、企業名公表などのリスクがある一方、積極的に取り組むことで、人材確保や企業価値の向上といった多くのメリットが期待できます。
この法改正を、自社の組織体制や働き方を見直す好機と捉え、戦略的に対応していくことが重要です。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
改正女性活躍推進法とはなんですか?
改正女性活躍推進法とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律のことで、男女間の格差是正と女性の社会での活躍を一層推進することを目的としています。
2026年に施行が予定されている改正では、これまで努力義務とされてきた従業員101人以上300人以下の企業に対しても、女性活躍に関する情報公表が義務化されることが主な変更点です。
情報公表の義務化対象となる企業は、従業員何人以上の企業ですか?
2026年の改正女性活躍推進法により、情報公表の義務化対象は、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に拡大されます。
従来は301人以上の企業に義務付けられていましたが、改正後は101人以上300人以下の企業が新たに対象となります。100人以下の企業については、引き続き努力義務とされています。
従業員101人以上の企業に義務付けられる具体的な公表項目は何ですか?
従業員101人以上の企業に義務付けられる公表項目は、主に「男女間の賃金格差の状況」と「女性管理職の割合」の2つのカテゴリーです。
特に「男女間の賃金格差」については、「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の3区分で、男性の賃金中央値に対する女性の賃金中央値の割合を算出して開示することが必須です。
公表が義務付けられる「男女間の賃金格差」は、どのように計算するのですか?
男女間の賃金格差は、「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の3つの区分それぞれについて、男性の賃金の中央値に対する女性の賃金の中央値の割合を算出してパーセンテージで公表します。
この「賃金」には、基本給だけでなく、賞与や各種手当などを含めた間の総賃金が用いられます。
改正法への対応として、企業が策定する「行動計画」には何を含める必要がありますか?
企業が策定する行動計画には、達成すべき「目標」、目標達成のための「取組内容」、そして計画を実行する「期間」の3つの要素を盛り込む必要があります。
これは、自社の現状分析(ステップ1)で明らかになった課題解決に向けた具体的な道筋を示すものです。
企業が女性活躍推進法の改正に対応することで得られる主なメリットは何ですか?
法改正への対応は、単なる義務の履行に留まらず、企業に多くのメリットをもたらします。
主なメリットは、優秀な人材の確保と定着(採用競争力の向上)、女性の視点によるイノベーションの創出と生産性の向上、そして取り組みを積極的に開示することによる企業イメージ・社会的信頼の向上(ESG投資評価への寄与など)です。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」