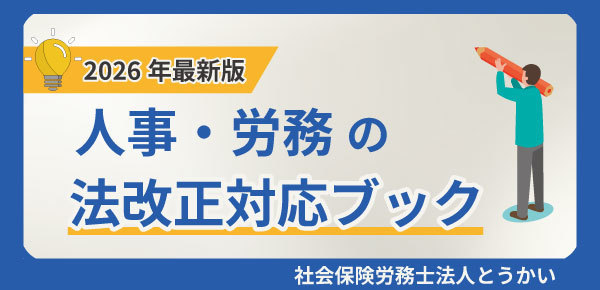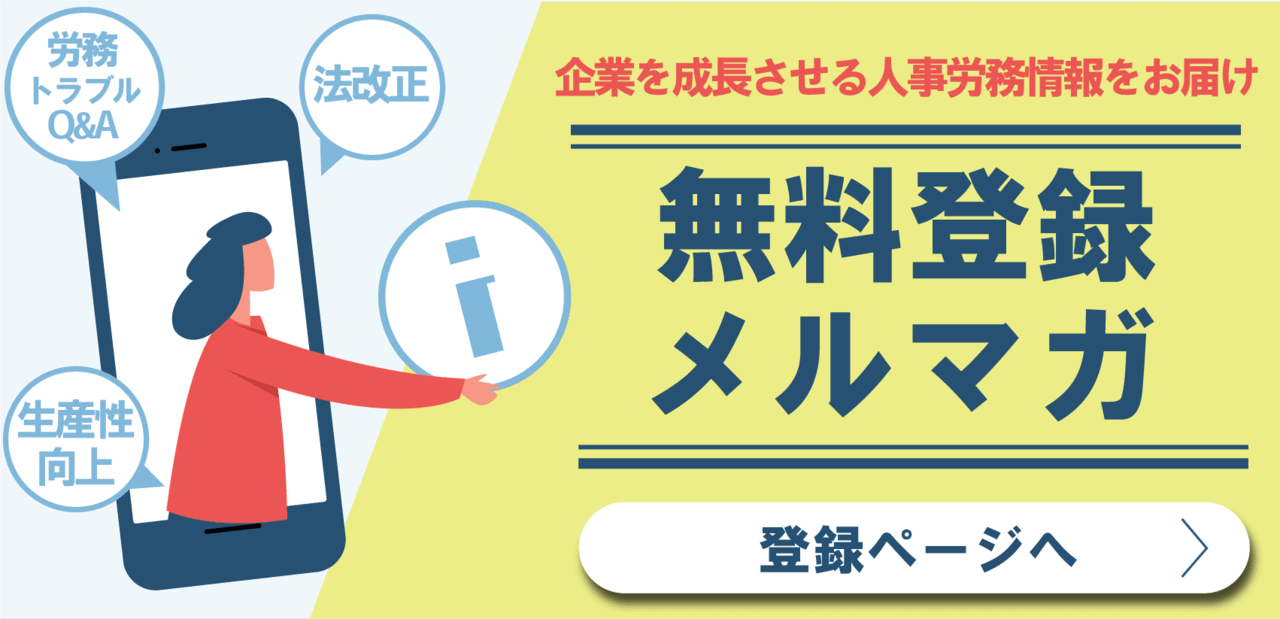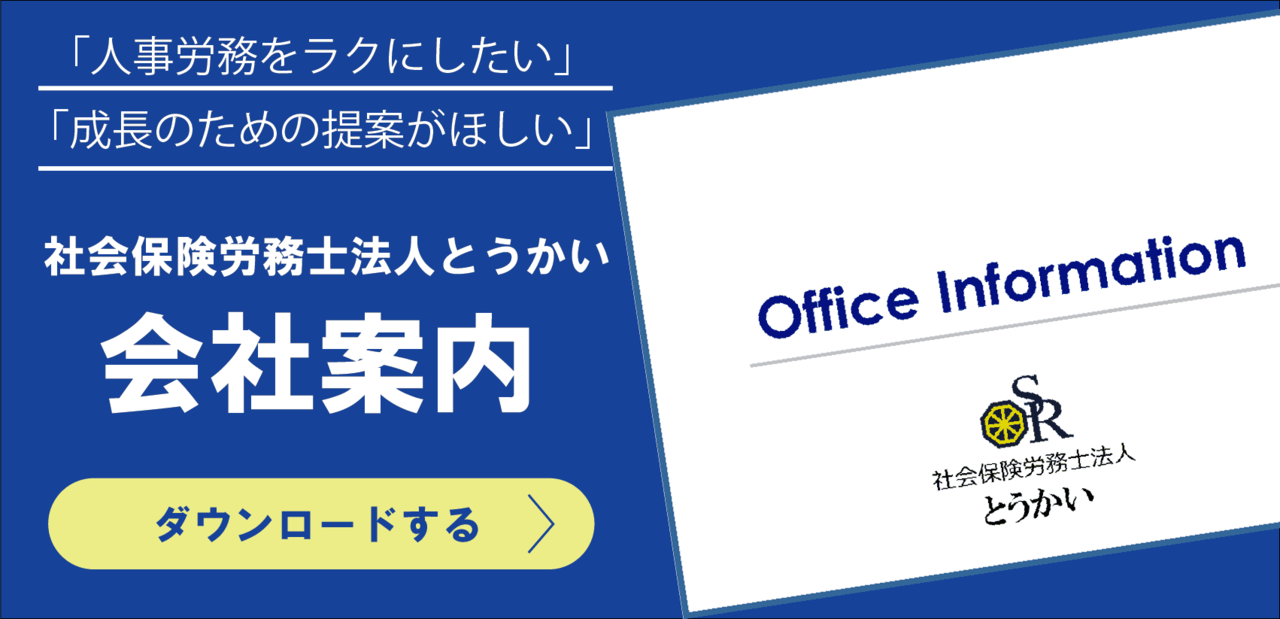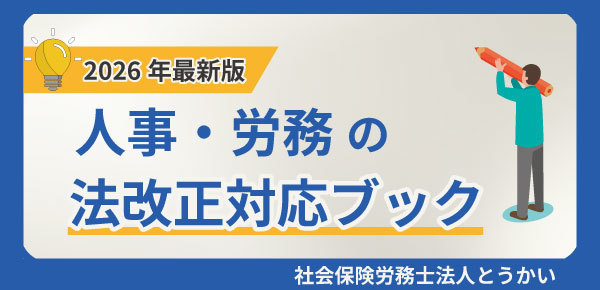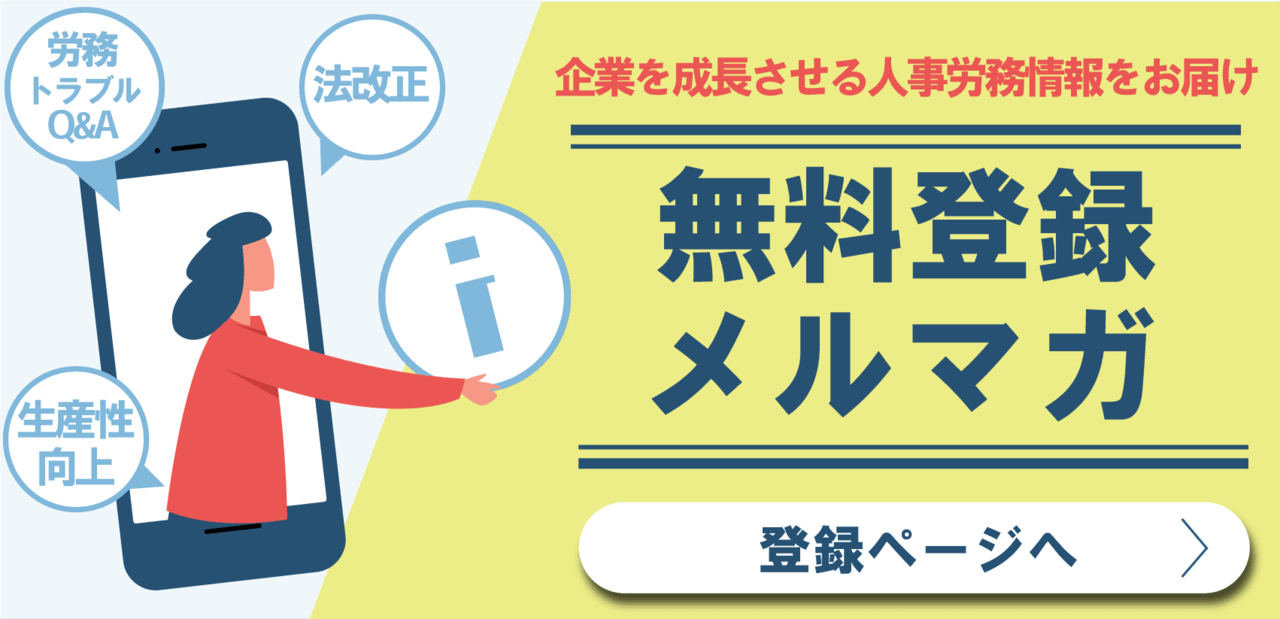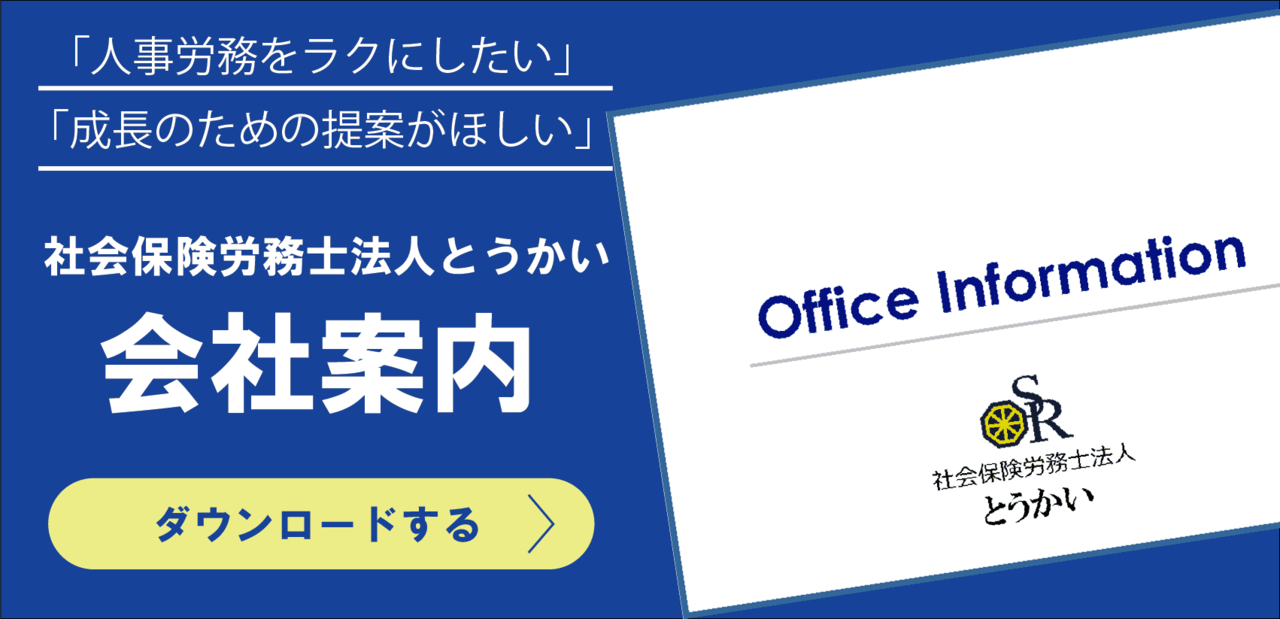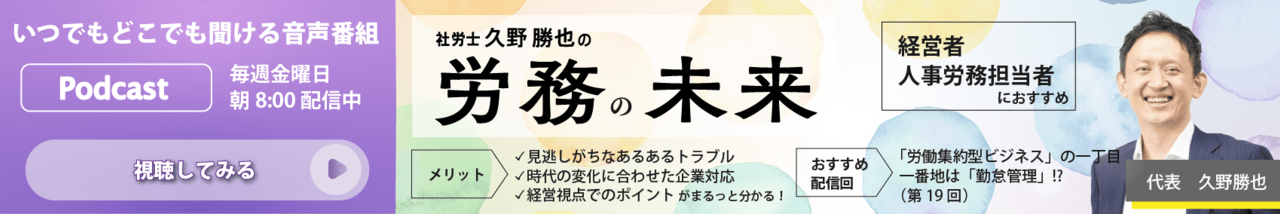備えておきたいBCP(事業継続計画)対策とは?
2024年介護事業所で義務化スタート。


BCP対策のポイントについて
解説していきます。
BCPは、"Business Continuity Planning"の略称で、事業継続計画とも呼ばれるものです。BCP(事業継続計画)は、企業などが災害や緊急事態などの予期しない事態によって、事業活動の中断や混乱の中でも復旧回復し、ビジネスを継続していくための計画です。近年の日本における自然災害、感染症の蔓延を背景に、ますます重要なものであると位置付けられています。
とくに、2024年4月には介護事業所におけるBCP(事業継続計画)対策の義務化がスタートします。すべての介護事業所が対象となるため、まだBCP(事業継続計画)を策定していない介護事業所にとっては、今から策定に取り掛かりたいところです。
今回は、企業のBCP(事業継続計画)に詳しい社労士が、介護事業所がBCP(事業継続計画)を策定するための対策のポイントなどを解説していきます。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから
BCPとは、"Business Continuity Planning"の略です。企業や団体といった組織に、自然災害や大火災、テロ攻撃といった緊急事態が発生した場合に、資産の損害を最小限に留め、早期の復旧を目指し中核となる事業を継続することが重要になります。そのためには平常時に行うべき活動を予め計画や手順として策定し備えておくリスクマネジメントとして、BCP(事業継続計画)の役割は大きいものです。
災害発生時に従業員や取引先などの安全を守るための災害対策である「防災」は、災害発生時の被害を最小限に止めることに主眼が置かれていることに対し、BCP(事業継続計画)は、有事の事後対応に主眼が置かれています。
| ○BCM(事業継続マネジメント) 最近ではBCM(事業継続マネジメント)と表現されるケースも多くあります。BCMとは、“Business Continuty Management”の略です。企業や団体といった組織が災害や緊急事態に、事業継続を行うえで、事業継続計画の策定から、運用・見直しといった継続的改善を含むと定義されています。「防災」や「BCP(事業継続計画)」、それらの改善・運用を総合的に考え、設計することになります。 |
自然災害が多い日本。ここ十数年、大規模な災害に幾度となく見舞われ、小規模な災害も頻発しており、災害慣れしてしまっている状態かもしれません。いざ自分の会社に災害が降りかかったとき、自分自身の身に危険が迫ったとき、どのような対応を取るべきなのか、しっかりと認識しているでしょうか? また、災害を切り抜け、早期に復旧し事業を継続していくための対応策はされているでしょうか? BCP(事業継続計画)は、そのための第一歩です。
| 年 | 災害の発生状況 |
| 2011年 | 東日本大震災 |
| 霧島山噴火<噴火による広域降灰被害> | |
| 長野県北部地震<長野県栄村で家屋倒壊・土砂崩れ> | |
| 2013年 | 台風26号<伊豆での大雨による土石流> |
| 2014年 | 豪雪<首都圏でスリップ事故が相次ぐ、岐阜・山梨・長野で孤立集落が発生> |
| 台風12号<紀伊半島での大雨被害> | |
| 御嶽山噴火 | |
| 広島市北部土砂災害 | |
| 2015年 | 関東・東北豪雨<鬼怒川流域の浸水被害> |
| 2016年 | 熊本地震<阿蘇大橋地区の大規模土砂災害> |
| 台風10号<小本川氾濫による浸水被害> | |
| 2017年 | 九州北部豪雨<赤谷川の土砂・洪水氾濫、流木被害> |
| 2018年 | 7月豪雨<岡山・小田川の浸水被害> |
| 台風21号<神戸港・関空の浸水被害> | |
| 北海道胆振東部地震<厚真町の大規模土砂災害> | |
| 2019年 | 前線に伴う大雨<佐賀・牛津川の浸水被害> |
| 台風15号<千葉・倒木被害> | |
| 台風19号<千曲川の浸水被害> | |
| 2020年 | 7月豪雨<九州を中心に日本各地での集中豪雨> |
| 新型コロナウイルス蔓延 | |
| 2021年 | 伊豆山土砂災害 |
| 各地での大雨による河川の氾濫、土砂災害、道路崩壊などが多発 |

BCP策定のメリットを理解し、
自社に応じたBCPに取り組む
ことが大切です。
頻発する自然災害に備え、早期復旧・事業を継続していくためにBCP(事業継続計画)の策定は大きな役割を担っています。災害時にBCP(事業継続計画)として事前に対策を行なっていた組織と、何も対策を講じていなかった組織とでは、その復旧期間には約3倍もの期間の開きがあるとも言われています。BCP(事業継続計画)の策定メリットを理解し、自社に応じたBCP(事業継続計画)に取り組む必要があるでしょう。
災害などの緊急事態を想定し、予め備えておくことで、事業の早期復旧に向けて速やかな対応が可能となります。
自社にとっての重要事業、重要タスク、そのためにどのような対策が必要で、コストはどのくらい見込まれるのかなど、明確にすることが可能です。平時からBCP(事業継続計画)に取り組むことで、業務の洗い出しや見直しや効率化の機会にもなるでしょう。
BCP(事業継続計画)に取り組んでいる企業は、対外的にも信頼がおけるといえるでしょう。取引先への影響はもちろん、従業員にとっても、BCPへの取り組みの有無は、信頼性向上に欠かせません。
人材の配置を集中させない、データ保管をデータセンターなどで管理するといった、災害などの緊急事態が発生した際のリスク分散が可能になります。
一定の要件を満たした場合には、自治体によっては補助金や助成金を受給できる可能性もあります。また、税制優遇や金融支援を受けられることもあります。
BCP(事業継続計画)への取り組みは、時間も労力もかかります。そのためのコストの捻出も頭の痛いところかもしれません。ただ、有事の際に、従業員や顧客・取引先などが安全に、そして早期復旧し事業継続するには、BCP(事業継続計画)への取り組みを行うほかありません。今後も首都直下型地震や南海トラフ地震など大災害が予測されるなか、有事への対策は必須でしょう。

介護サービスを提供する事業者は少しでも早くBCPの準備、
策定作業を進めましょう。
企業や団体にとってのリスクマネジメントとして欠かせないBCP(事業継続計画)への取り組み。とくに社会インフラに関わる事業においては、BCP(事業継続計画)への取り組みは欠かせないものです。なかでも、2021年介護報酬改定をきっかけに、介護施設などを運営する介護事業者にもBCP(事業継続計画)策定が重要との認識から、2024年より義務化がすることが決定しました。BCP(事業継続計画)策定の義務化は、介護事業者が災害や緊急事態による業務の中断や支障を最小限に抑え、利用者の安全や福祉を確保するために重要であり、急務です。災害時などの緊急事態において、介護サービスが停止してしまったり、遅延すれば、障害者や高齢者といった介護の必要な利用者が、深刻な影響を及ぼす可能性があります。すべての介護サービスを提供する事業者は、その事態に陥らないよう策定を進めなければなりません2024年まで、あと1年もありません。少しでも早く準備、策定作業に取り掛かる必要があります。BCP(事業継続計画)の策定によって、事前にリスク評価や対応策を考慮し、迅速で効果的な対応ができる体制を整えることが期待されます。
時間も労力もかかるBCP(事業継続計画)の策定ですが、2024年に向けてしっかりと準備を進めなければなりません。策定がされていないことが明らかになった場合には、介護サービス事業者としての介護報酬が減算されることもあります。もちろん、災害が発生した場合に、社会的責任を追及されたりBCP不備による法的責任を問われかねません。人命に関わる被害など訴訟に発展するケースもあるでしょう。
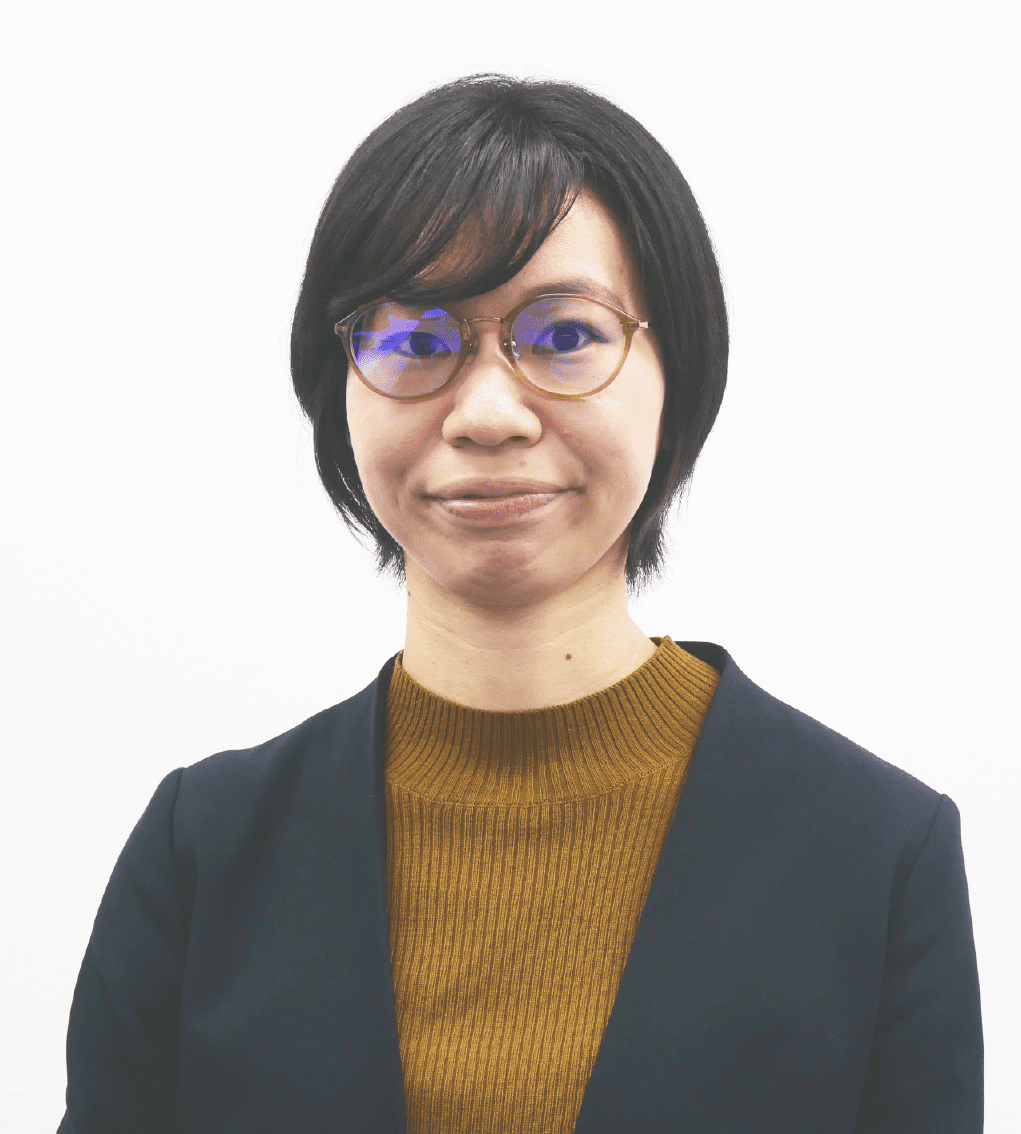
BCP策定の流れと
取り組む具体的なポイント
について解説します。
介護サービスを提供する介護事業者にとって、災害などの緊急事態であってもサービスを継続できるよう体制を整えておくべきなのは、誰もが理解できることでしょう。といって、介護事業者においてBCP(事業継続計画)を策定するための人材も不足しており、「何から手をつけたらよいかわからない」「何を備えればよいのか」といった問題や課題を抱えていることも多いはずです。
介護事業者がBCP(事業継続計画)を策定するために、取り組むいくつかの具体的ポイントを確認してみましょう。
介護サービスの利用者の避難や安全確保のための手順や施策を明確にします。
介護職員の安全確保や適切な役割分担、連絡体制の確立など運営体制を決定します。緊急時の連絡先もすぐに参照できるような工夫も必要です。
介護施設や設備の現況を確認しておきましょう。耐震構造であるのか、そうでない場合にはどのような対策が打てるのか、補修が必要かなど、確認していく作業が必要になります。バックアップ電源の確保などの対策を講じる必要があるでしょう。
介護利用者情報や業務データの保護、バックアップ体制の整備も必要です。
行政機関や他の介護事業者、近隣の医療機関などとの連携体制や情報共有の方法を確立します。
地震・水害などの自然災害であるのか、感染症などあるのか、その事態よっても必要な物資等は異なる部分はありますが、災害を想定し、必要な物資の洗い出し、見直し時期なども検討していく必要があります。
BCPは、自然災害(地震や洪水など)やテロ、情報セキュリティに関わるデータ侵害、感染症のまん延など様々なリスクが想定されます。それに対応するための計画になります。範囲が広すぎて、どこからスタートすればよいかと頭を悩ませてしまうかもしれません。とくに介護事業者は、BCPの策定など専任の担当者を配置できるケースは少なく、さまざまな業務を抱えながら、策定を進めていくことになるでしょう。とはいえ、2024年にはBCP(事業継続計画)策定義務化が迫っています。まずは、策定までの大きなステップを確認し、スケジュールを組み立てることが必要です。
介護サービスを提供する介護事業者にとって、利用者の安全、継続した介護サービスが第一義となります。介護事業者の特徴によって、その目的・方針を明確にしておきます。
介護事業所などを取り巻く災害リスクを認識します。ハザードマップ等を活用しながら地域の災害リスクを把握しましょう。ヒト・モノ・カネ・情報といった観点で、介護事業所・介護サービスにどのような影響が生じるのか確認していきます。
| 災害 | 調査項目 | 発行元 | 項目 | URL |
| 地震 | 主要地震 | 地震本部(政府地震調査研究推進本部) | 長期評価 | |
|
| 内閣府 | 防災情報 | https://www.bousai.go.jp/jishin/ | |
| 地震・ 災害・ 土砂災害 など | 震度分布 | 国土交通省 | わがまちハザードマップ | https://disaportal.gsi.go.jp/index.html |
| 津波浸水深 | 国土交通省 | 重ねるハザードマップ | https://disaportal.gsi.go.jp/index.html |
災害が発生した直後の初動対応を検討します。人命の安全確保、非常時の体制、被害状況の把握や共有といった事項の他に、介護事業所ならではの対応ポイントも洗い出しておきます。
【人命の安全確保】
利用者や従業員の避難のルール、安否確認に方法
【非常時の体制構築】
体制の整備、上位者不在の場合の代行者、周知方法など
【被害状況の把握や共有】
誰が情報収集するのか、緊急時の連絡手段をどうするのかなど
ステップ②で検討した介護事業所・介護サービスへの影響を踏まえ、対策を検討していきます。
BCP(事業継続計画)の策定は、災害などの緊急事態に必要なものだけに、平時の推進体制をどのようにしておくかが、緊急事態の対応の素早さ、早期復旧につながります。介護サービスの中断が最小限に抑えるために、平時の手順やリソースの確保策を検討しておきましょう。
BCP(事業継続計画)の策定は、ステップに沿って、立案していきます。いきなり計画書を作成しようとしても失敗しがちです。まずは入念に準備し、それぞれのステップに沿って検討・整理を進め、計画書にまとめましょう。また、BCPは、定期的に訓練が必要です。その結果に応じて改善も必要になるでしょう。都度計画への反映も実施していきます。

BCP策定に関してのご相談は
とうかいにお任せください。
昨今の自然災害の頻発や新型コロナウイルスまん延の経験から、多くの企業がBCP(事業継続計画)の策定に乗り出しています。2024年には介護サービスを提供する介護事業者のBCP策定が義務化となります。いざというときにサービスを止めず、維持できるよう、入念な準備が必要です。また、BCPは策定がゴールではありません。平時から訓練などを通して、いざというときに備えられる体制も整備しておかなければなりません。適切な対策を講じるために、今から準備を進めていきましょう。当事務所には企業のBCP策定にも詳しい社労士が揃っています。ご不安などがあれば、ご相談を受けさせていただきますので、ぜひお気軽にお問合せください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」