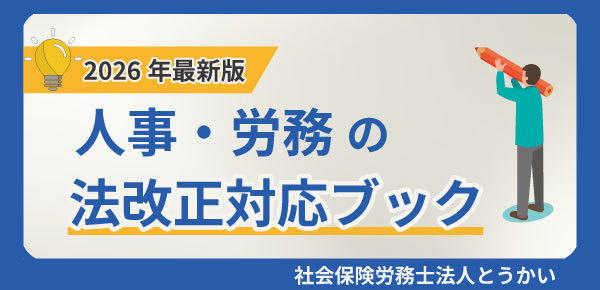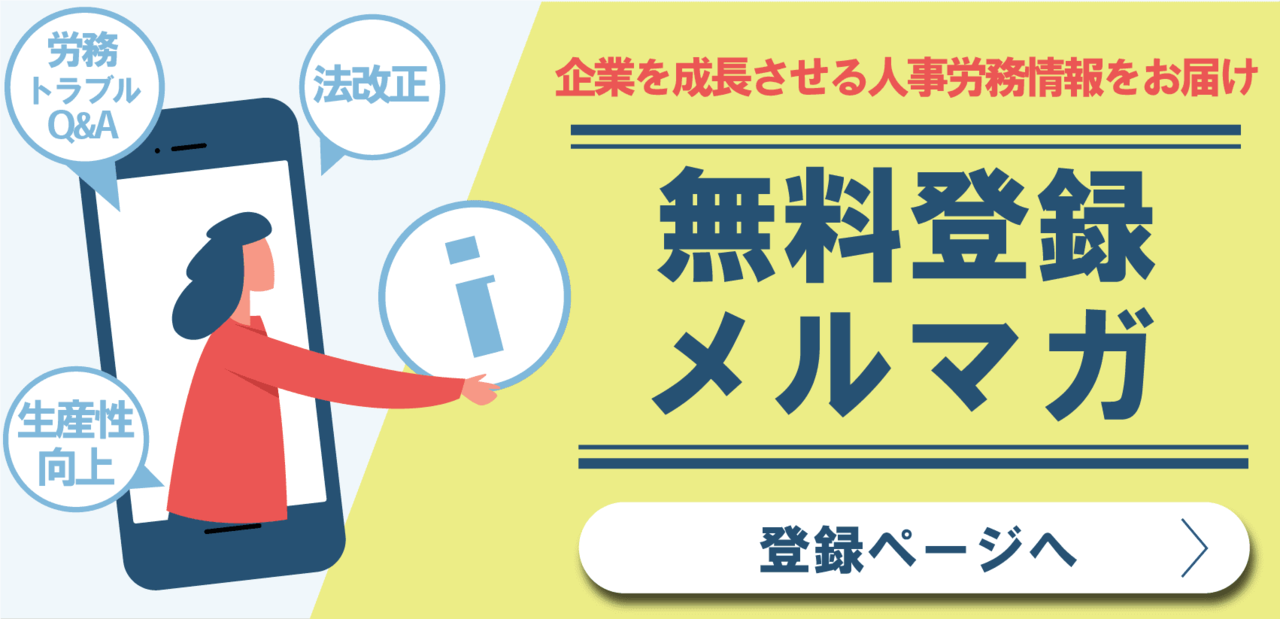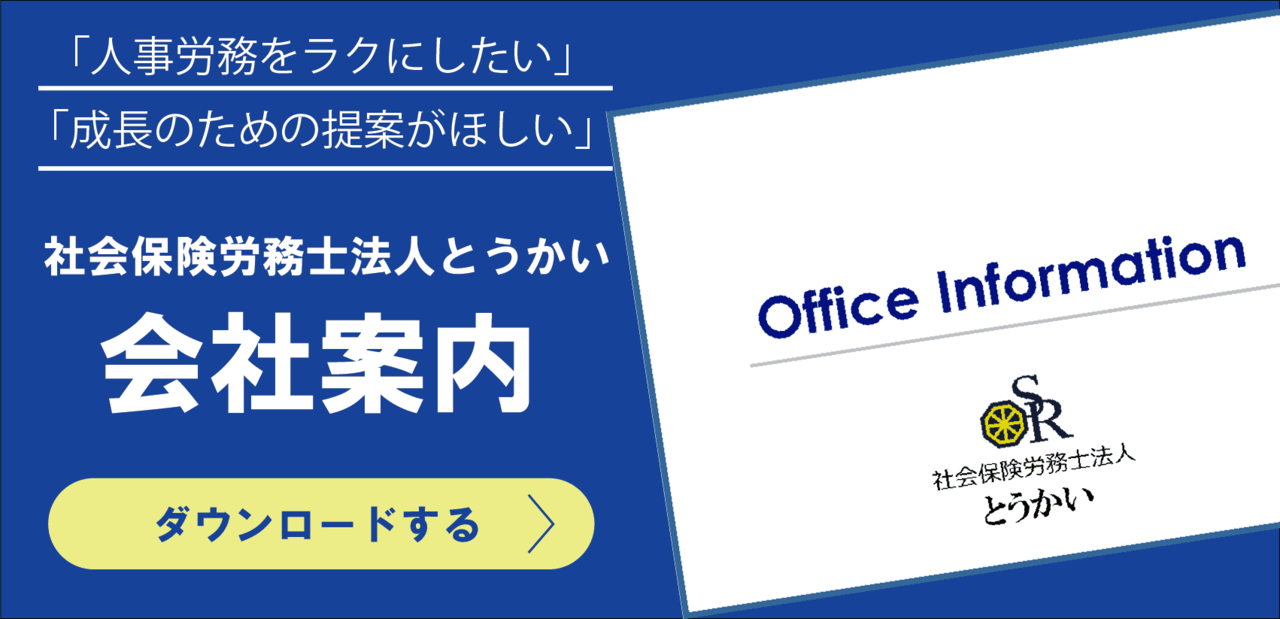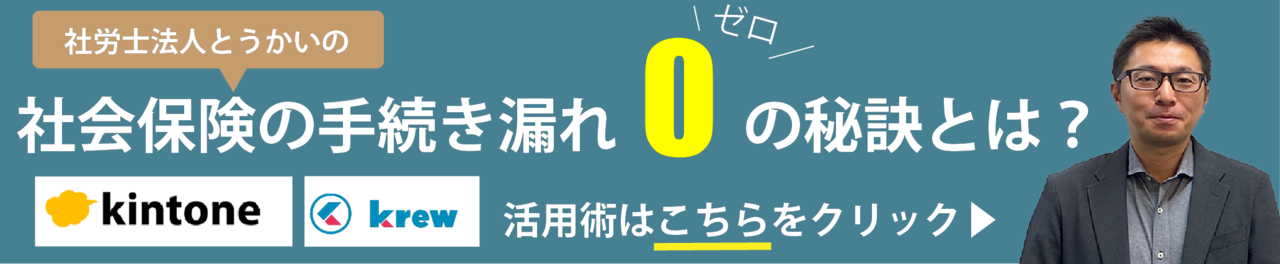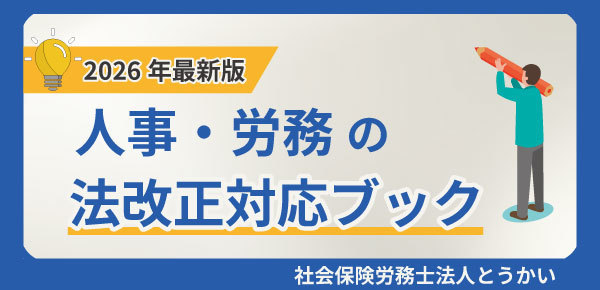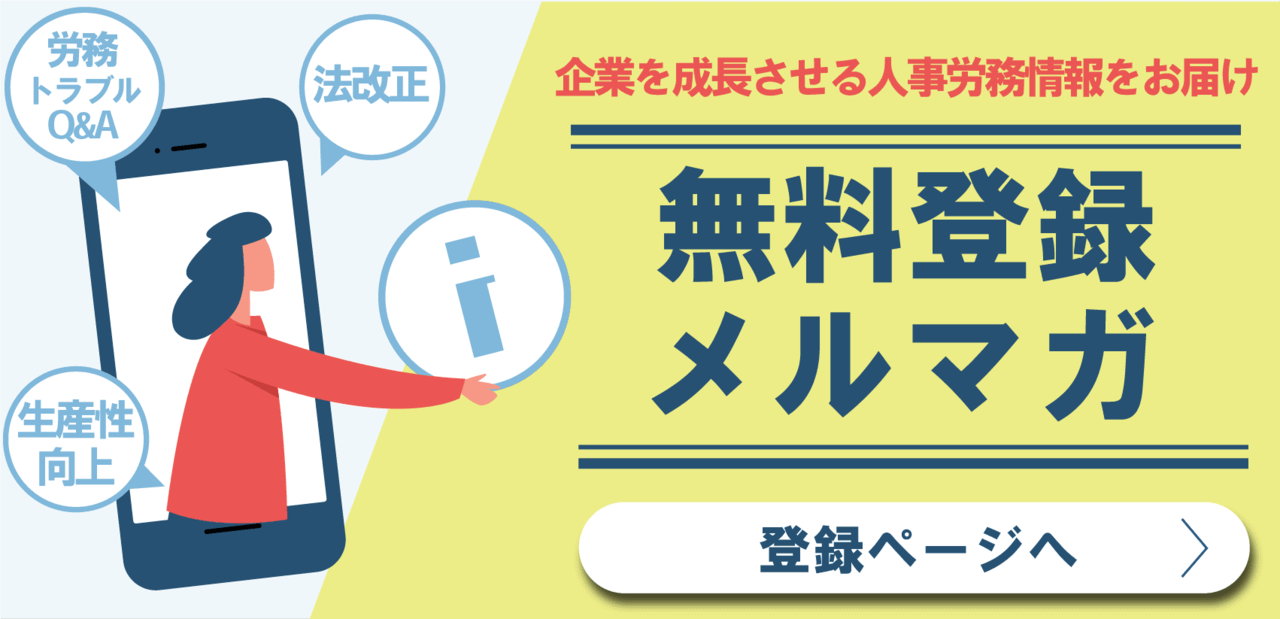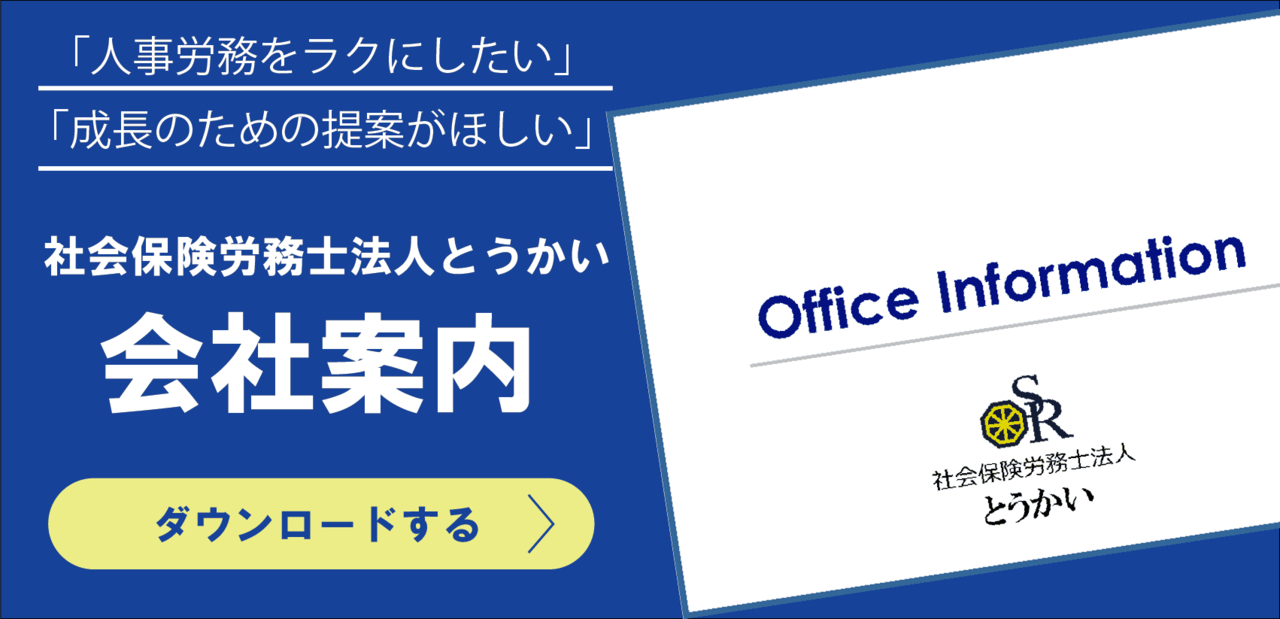丸わかり! 会社設立時の社会保険手続きと労務管理について社労士が解説します!

終身雇用も過去の話となって、いよいよ働き方の多様化が進む中、“自分で事業を行おう”“会社を設立しよう”とお考えの方も多いかもしれません。また、個人事業主から法人化・法人なりを検討しているという方もおられるでしょう。ですが、会社を設立する時、法人化を検討している時期は、事業を軌道に乗せること、業績を上げることに精一杯で、必要な手続きがあることはわかっていても、後回しになりがちです。
今回は、これから会社を設立しようとしている、法人化を検討しているとき、どんな手続きをどのタイミングで行えばいいのかを、社会保険などの手続きを中心に社労士が解説していきます。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
執行役員 社会保険労務士 小栗多喜子
同社、人事戦略グループマネージャーを務め、採用・教育を担当する。商工会議所、銀行、Adeco,マネーフォワードなどセミナーや研修講師も精力的に行っている。労働法のアドバイスだけではなく、どのように法律と向き合い企業を成長させるのかという経営視点でのアドバイスを得意としている。
主な出演メディア
その他、記事の監修や寄稿多数。
取材・寄稿のご相談はこちらから

会社を設立するまでの必要な手続きを詳しく解説します。
会社設立をする時、個人事業主から法人化をする時、経営者は「どうやったら事業を軌道に乗せられるか」「事業を”いけいけどんどん”で拡大したい!」「資金繰りをどうしようか」など、どうしても興味の矛先が事業活動に向きますし、面倒な手続きについてはどうしても後回しにしがちです。ただ、経営者にとって、会社設立・法人化の第一歩には、事業を運営していくためのしっかりとした土台づくりは欠かせません。どのような手続きが必要なのか、どのタイミングで行うのかなどもしっかり確認しておきましょう。まずは、会社を設立するまでの必要な手続きをチェックしておきます。
そもそも会社を設立するというと「株式会社」を想定されることがほとんどでしょう。ただ、会社設立は、株式会社のほか、合同会社は合名会社、合資会社といった会社形態もあります。自社に適した形態を選択する必要があります。
【株式会社とは?】
その名のとおり、株式を発行して資金を出資し設立する会社です。多くがこの形態を選択するでしょう。会社の資本を出資した株主と、経営を行う経営者がいるのが特徴です。所有と経営が分離するというものです。ただ、小規模の会社などでは、経営者が出資しているケースなどは、株主=経営者となっていることが多いかもしれません。各種法律の規制なども多いですが、社会的信用が高いものとなるので、資金調達にもメリットがあります。
【合同会社とは?】
合同会社は、出資者と経営者が同一の形態です。出資したすべての社員が、会社の決定権を持って経営を行うことになります。株式会社に比べて設立費用などが低い、決算公告が不要なのも特徴です。
株式会社設立をするとき、まずは会社設立を行うための基本情報を定めることになります。この基本情報は、株式会社の「定款(ていかん)」に定める事項ともなります。
| ・会社形態(株式会社) ・商号(会社名) ・事業目的(「飲食店の経営」など) 定款に定めていない事業は行うことはできません。 ・本店所在地 ・資本金 ・会社設立日 登記申請を行った日です。 ・会計年度 会計年度(1年間)を定めます。 ・役員/株主構成 1名以上の取締役が必要です。株主名簿の作成も必要です。 株式会社設立をするとき、まずは会社設立を行うための基本情報を定めることになります。この基本情報は、株式会社の「定款(ていかん)」に定める事項ともなります。 |
会社設立時には必須となるのが、定款の作成です。②の会社の基本情報をもとに、定款を作成します。とくに決まった様式はありませんが、商号や事業目的など絶対に記載しなければならない事項がありますので、注意してください。法務局サイトや公証人連合会などのサイトには、定款のサンプルなどもありますので、参考にしてみるのもよいでしょう。
また、定款を作成する際には、会社の実印が必要となりますので、実印の準備も忘れてはなりません。また、実印は法務局に印鑑届を提出して登録する必要があります。会社を運営していくにあたっては、実印のほかにも、認印や銀行印の用意もしておくとよいでしょう。すべて実印で行うことも可能ではありますが、使い分けをしたほうが安全です。
定款の作成が完了したら、本店所在地がある公証役場で認証を受けます。認証を受けるにあたっては、定款はもちろんのこと、手数料やその他必要な書類等もありますので、認証手続きに出向く前に、公証役場へ連絡し、予め定款をチェックしてもらうことがおすすめです。公証役場によっては、認証手続きは予約制となっているので、予約をする前に必要書類を準備するとよいでしょう。
定款の認証が完了したら、資本金の払込を行います。この時点では、会社の法人登記が完了していないため、会社の銀行口座が作成できません。一旦、発起人個人の口座に、資本金を振り込みます。振り込み内容についての書類は、法人登記の際に必要になりますので、保管しておきましょう。
いよいよ会社設立です。本店所在地の法務局において登記申請を行います。ここでもまた、必要になる書類はたくさんあります。不備があると差し戻されたりということもありますので、「会社設立日を絶対この日にしたい」などがある場合には、余裕を持って不備のないよう準備しておくことをおすすめします。
また、法務局に出向いて申請をするほかに、オンライン申請も受け付けています。代表取締役本人のマイナンバーカードを利用して申請が行えます。概ね、申請から1週間から10日ほどで登記が完了します。
法務局(会社設立登記のオンライン申請)

設立登記が完了後、事業を実際に開始するまでにやっておくべき手続きを解説します。
会社の設立準備から登記の完了まで、会社の設立までにはさまざまな手続きが必要です。結構な手間と時間をかけて登記まで完了しても、まだまだ先があります。設立登記が完了後、事業を実際に開始するまでにやっておくべき手続きもチェックしましょう。
会社の設立が完了したら、次には所在地を管轄する税務署への届出が必要となります。顧問税理士に委託する場合には、届出などサポートしてもらえるでしょうが、設立時に委託していない場合などは、経営者本人が行うことになります。ただ、非常に重要な届出になりますので、忘れて放置していたということがないように注意してください。
「法人設立届出書」に定款の写しなど必要書類を添付し、設立から2か月以内に提出します。
【その他必要な申請】
・青色申告承認申請書
法人税を納めるために必要な書類です。設立3か月を経過する日の前日、またじゃ最初の事業年度の末日の前日のうち、いずれか早い方までに提出することになります。
・給与支払事務所等の開設届出書
従業員等に給与を支払うために必要な書類です。会社設立時に従業員がいない場合には必要ありませんが、今後従業員を雇用する場合には提出しておきましょう。
・源泉所得税の納期特例の承認申請書
従業員を雇用する場合、支払う給与から源泉所得税を控除することになります。この従業員からの預かり金は、翌月10日までに税務署に納付する必要があります。毎月、所得税の納付の手続きが必要になるのです。ただ、従業員が常時10人もいない会社においては、事務作業や手続きの負担が大きいため、その負担軽減のためにも、毎月の納付を年2回にまとめて納付できるようにするための申請書となります。
この申請書を提出すると、1〜6月分の源泉所得税を7月10日、7〜12月分の源泉所得税を翌1月20日までに納付することができます。この制度を利用したい場合には、初回の給与支払月前までに申請しておく必要があります。
・棚卸資産評価方法および減価償却資産の償却方法の届出書
商品や製品を販売する事業の場合、在庫資産の評価方法をどのように行うのか届出なくてはなりません。最後に仕入れた物の単価を期末単価とする「最終仕入原価法」や、先に仕入れた物を先に払い出したとして評価する「先入先出法」、取得価格総額を総数量で割った平均価格で評価する「総平均法」など、どのように評価するのか届け出るというものです。棚卸資産の評価は利益と関係しますので、届け出た評価方法で行わなければならないからです、会社側が恣意的に“今年度は先入先出しで”“次年度は平均法で”といったことはできません。
減価償却資産の償却方法についても注意が必要です。通常減価償却資産の償却方法は、資産の種類ごとに「定率法」「定額法」など法定償却方法が定められています。この法定償却方法以外の減価償却を適用する場合には、届出が必要になります。
税務には税務署への届出以外にも、都道府県・市区町村への届出手続きも必要です。法人税などは、税務署への届出・納付となりますが、法人地方税・事業税は、自治体への届出になります。法人設立届書および定款の写し等を所轄の県税事務所などに提出することになります。
続いて、忘れてならないのが社会保険の手続きです。こちらは税務の届出や手続きより、複雑で難しいかもしれません。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
会社設立後は、社会保険の加入手続きを行わなければなりません。従業員がいる場合はもちろん、社長1人の会社であっても役員報酬の支払があれば加入することになります。会社設立から5日以内に会社所在地を管轄する年金事務所に、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を会社の登記簿謄本と合わせて提出することになります。
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届および健康保険被扶養者(異動)届
加えて、被保険者となる役員や従業員の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」も提出します。そして、注意したいのが、被保険者となる役員や従業員に扶養者がいる場合です。その場合には「健康保険被扶養者(異動)届」も一緒に提出しなければなりません。
日本年金機構(健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.html
労働保険の手続きも必要です。労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。会社設立時に従業員を雇用している場合、また事後においても雇用する場合には、必ず手続きが必要となります。
・保険関係成立届
労災保険は、会社設立時に従業員がいる場合には、必ず加入が必要です。会社の所在地を管轄する労働基準監督署に、「保険関係成立届」を提出します。従業員を雇用した日の翌日から10日以内に提出することになりますので、設立日が従業員雇用開始日だとすれば、会社設立日の翌日から10日以内には提出の必要があるということです。会社の登記事項証明書(原本)や、従業員を雇用していることがわかる労働条件通知書、従業員が10人以上いれば就業規則届も必要です。
・労働保険料概算保険料申告書
労災保険料と雇用保険料である労働保険料は、従業員への見込み給与額を元として、保険料率を乗じ保険料を算出し、前払い(概算払い)することになります。そのための申告書を従業員の雇い入れ日(保険関係成立日)の翌日から50日以内に所轄の都道府県労働局に提出します。会社の業種によって、労災保険の保険料率は異なりますし、雇用保険の保険料率も年度によって改正される場合もありますので、必ず最新情報を確認しなければなりません。
・雇用保険適用事務所設置届
従業員を雇用する場合には、雇用した日の翌日から10日以内に所轄のハローワークに届出ます。登記事項証明書のほか、業種によっては営業許可証なども確認することになりますので、準備が必要です。
・雇用保険被保険者資格取得届
従業員を雇用する場合には雇用した月の翌月10日までに所轄のハローワークに提出します。
○各種手続きをオンラインで
各種手続きについては、オンラインでの電子申請が可能なものもあります。まだまだ便利で使いやすいとまではいかないものの、徐々に使いやすく更新されつつあります。適宜e-govの中から、必要な手続きを選択してオンライン申請も可能です。

経営者が最低限知っておきたい社会保険などのポイントを詳しく解説します。
会社設立時において、専門的な知識が必要でハードルが高く面倒と思われるのは、社会保険・労働保険に関することではないでしょうか? また、設立時に従業員を雇用するとなれば、労務管理の義務も発生しますので、社会保険などのほかにも、労務に関する手続きは多くあります。経営者が最低限知っておきたい社会保険などのポイントを押さえておきましょう。
| 健康保険 | 狭義の社会保険 | 広義の社会保険等等 |
| 介護保険 | ||
| 厚生年金保険 | ||
| 労災保険 | 労働保険 | |
| 雇用保険 |
社会保険は、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」を指します。広く捉えると労働保険である「労災保険」「雇用保険」も含まれます。
従業員を雇用する際には、これらの保険の加入が必要です。狭義の社会保険については、設立時に代表が1人で従業員がいなくても加入が義務付けられています。
従業員を1人でも雇用するのであれば、入社に際し「労働条件通知書(雇用契約書)」を書面等により明示することになります。労働条件通知書には、必ず従業員に明示しなければならない事項なども法律で決まっていますので、後々トラブルにならないよう作成し、提示します。
従業員を雇用した場合には、多くの労務上の管理が必要になってきます。従業員の勤怠管理、社会保険の手続き、もちろん給与計算も重要です。給与計算について、割増賃金の計算などは法令で定められていますので、間違いのないよう行うにはある程度の知識と理解も必要です。年末には従業員の年末調整も行います。状況によっては、労務管理システムなどの導入も検討しなくてはなりません。
労働基準法では、一部の例外はあるものの、1日8時間、1週40時間までといった労働時間が決められています。従業員を雇用している場合には、原則これを超えて労働させることはできません。ただ、働いている以上、残業が発生したり、休日に出勤しなくてはならない場合もあるはずです。とくに会社設立時などには時間外勤務が予想されます。会社は従業員に残業や休日出勤をしてもらうには、36協定という時間外労働の協定を従業員と結び、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
従業員が増えれば、一定のルールが必要になってくるでしょう。就業規則として会社のルールを定める必要が生じます。10人以上雇用することになれば、その就業規則について所轄の労働基準監督署に届け出る必要が生じます。

経営者自身に労務知識がない、また設立時に専門の担当者もいないといった場合にはお気軽にご相談ください。
会社設立の手続きは、さまざまな行政機関への申請や届出が必要で、時間もコストもかかり経営者が1人でやり切るには大きな負担です。とはいえ、会社設立はビジネス上のメリットも多くあるので、なんとかハードルを乗り越え、本来の事業活動へ注力できるようにしたいものです。ただ、会社設立後、1人社長であれば、どうにか乗り切れるでしょうが、従業員を抱える場合には、手続き、その後の労務管理をどのように行っていくかは、会社設立前から慎重に検討を進めておきたいとことです。とくに、労務管理に関すること、社会保険などに関することは、複雑で専門知識が必要なことも多く、初めて携わる場合にはかなり労力がかかるのが予想されます。経営者自身に労務知識がない、また設立時に専門の担当者もいないといった場合には、労務の専門家である社労士に委託することをおすすめします。会社設立時に必要な手続き書類の作成や提出代行の委託をはじめ、設立後の労務管理についてもアドバイスやサポートが受けられるでしょう。労務管理を効率的に進めるための各種システム導入などの相談も活用してほしいところです。
自社の状況に応じて、さまざまな労務上の提案をしてもらえる社労士と出会えれば、会社設立時の多忙な経営者やスタッフの大きな助けになるに違いありません。
会社設立時は、やることが多くあり、どのタスクをどこまでやったのか、混乱してしまうこともよくあります。ただ、どの手続きも期限も決まっており、慌ててしまうこともあるでしょう。とくに設立時から従業員を雇うことにでもなれば、やらなければならないことは盛りだくさんです。後回しにして、大きなトラブルに発展しないよう、ぜひ社会保険労務士の活用も検討されてみてください。必ず長期にわたって付き合っていける社労士が見つかるはずです。
当社においても、スタートアップ企業の労務サポートをはじめ、さまざまな企業規模、業種のクライアント様がいらっしゃいます。その知見・経験を活かして、労務の問題・課題へのアドバイス、フォローを行なってまいります。会社設立時の各種手続きや労務管理に不安や心配点があれば、まずはお問合せください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」