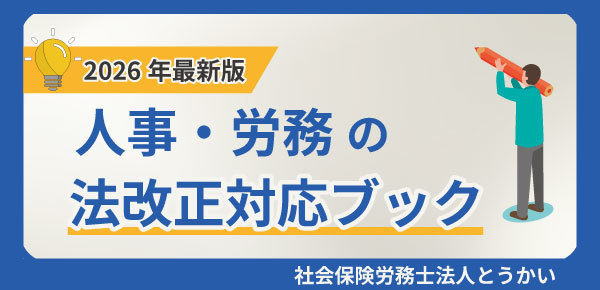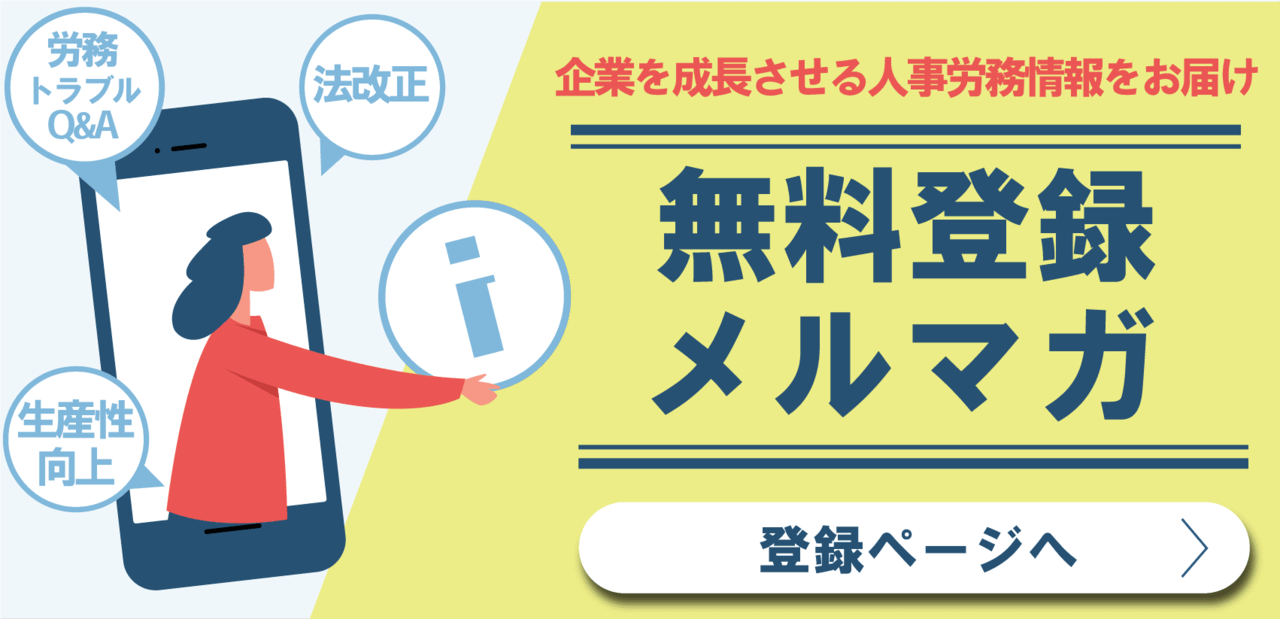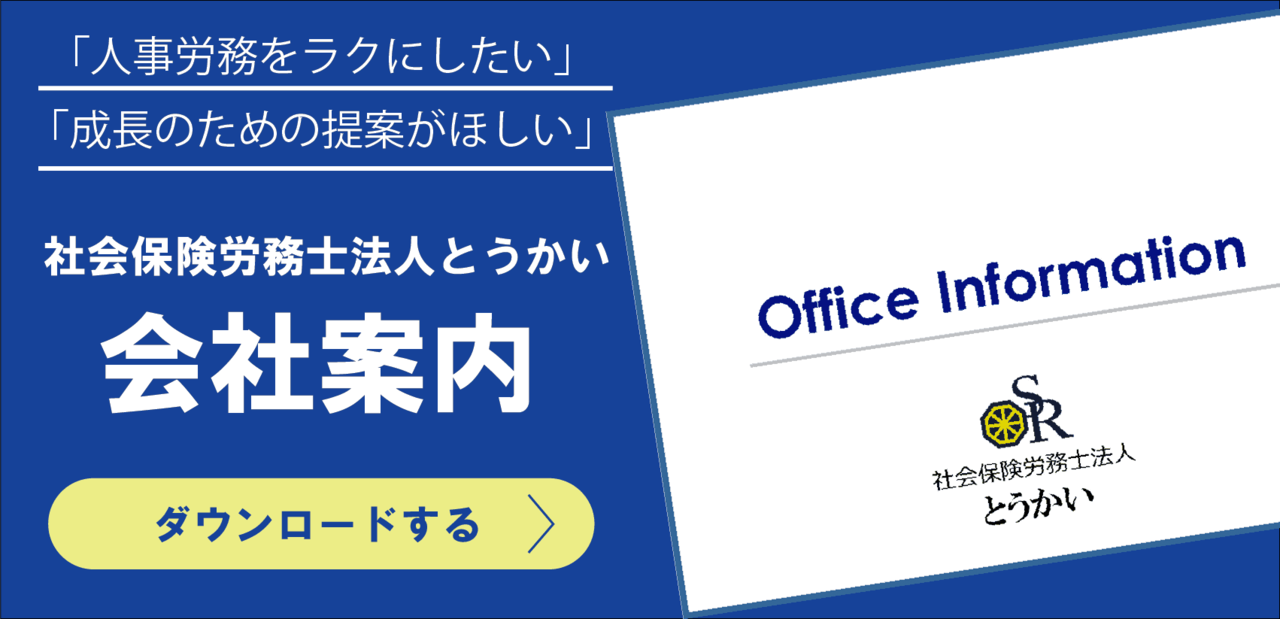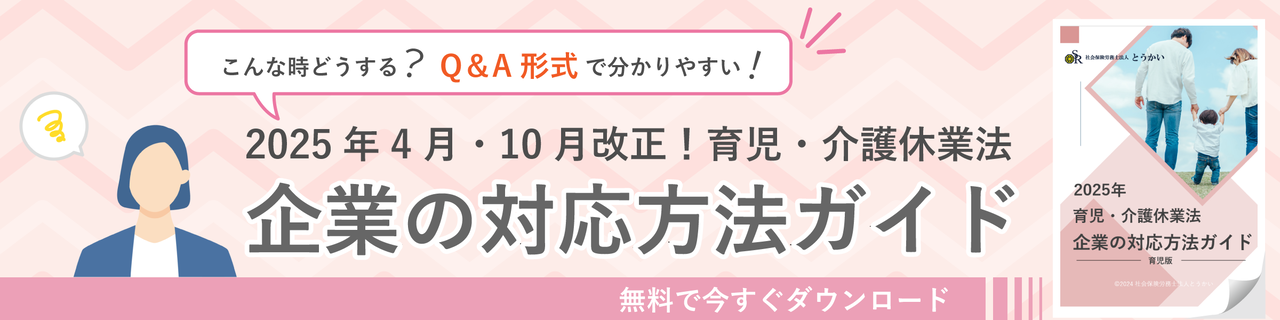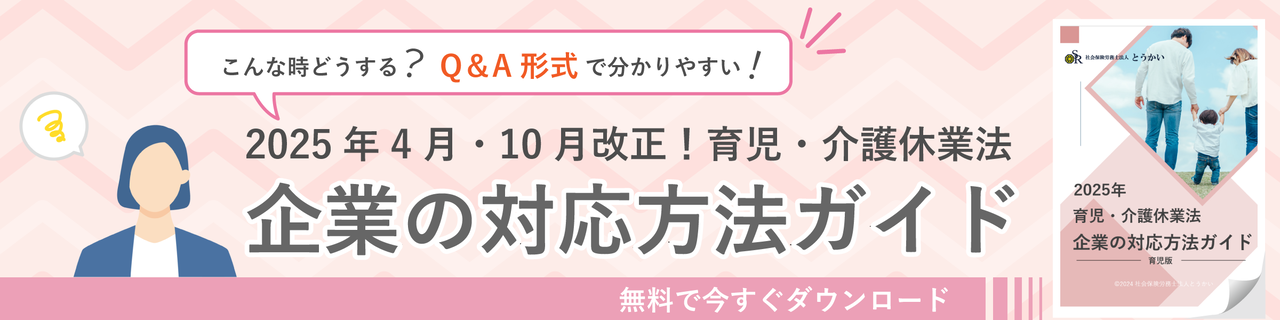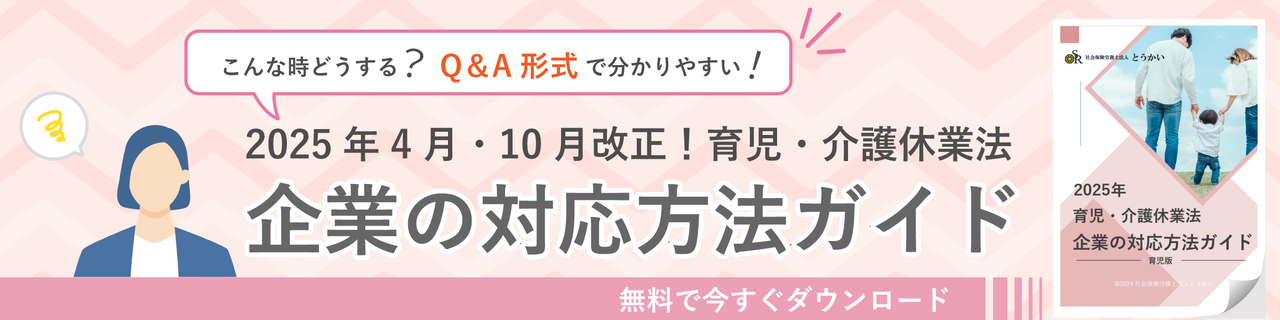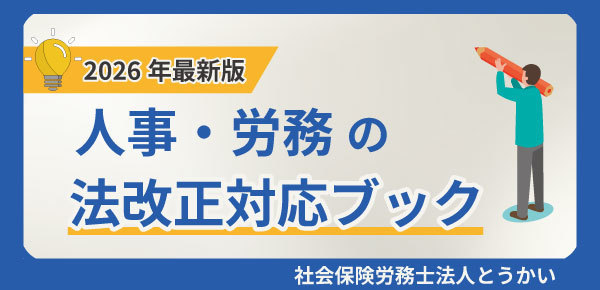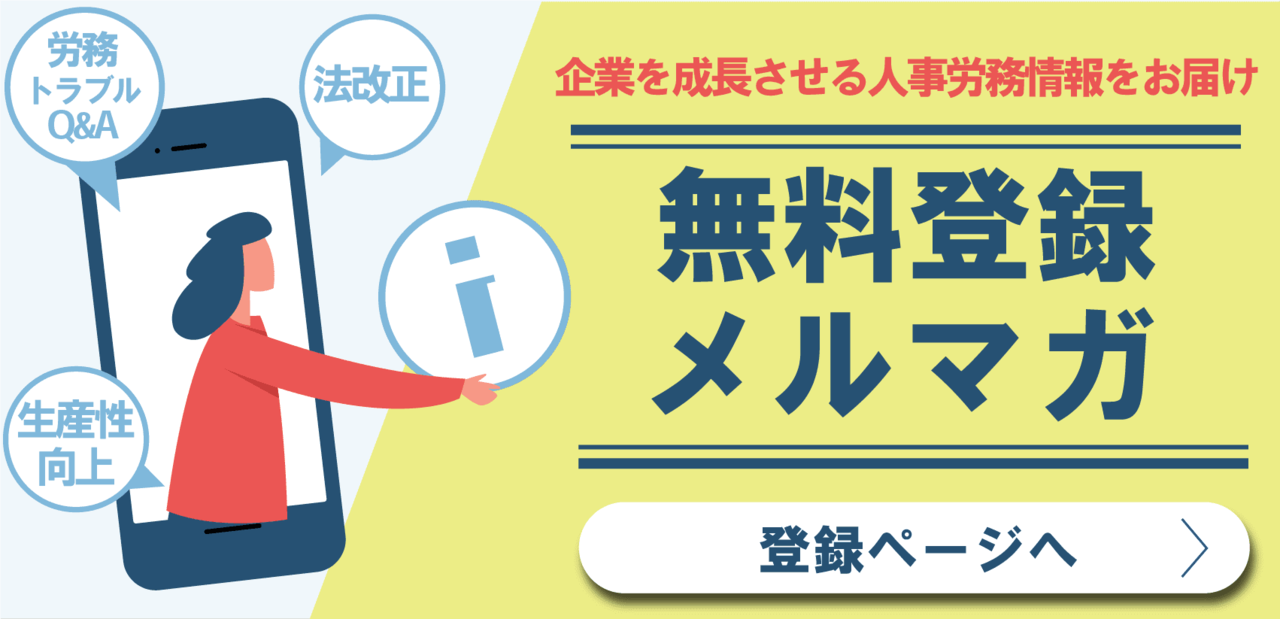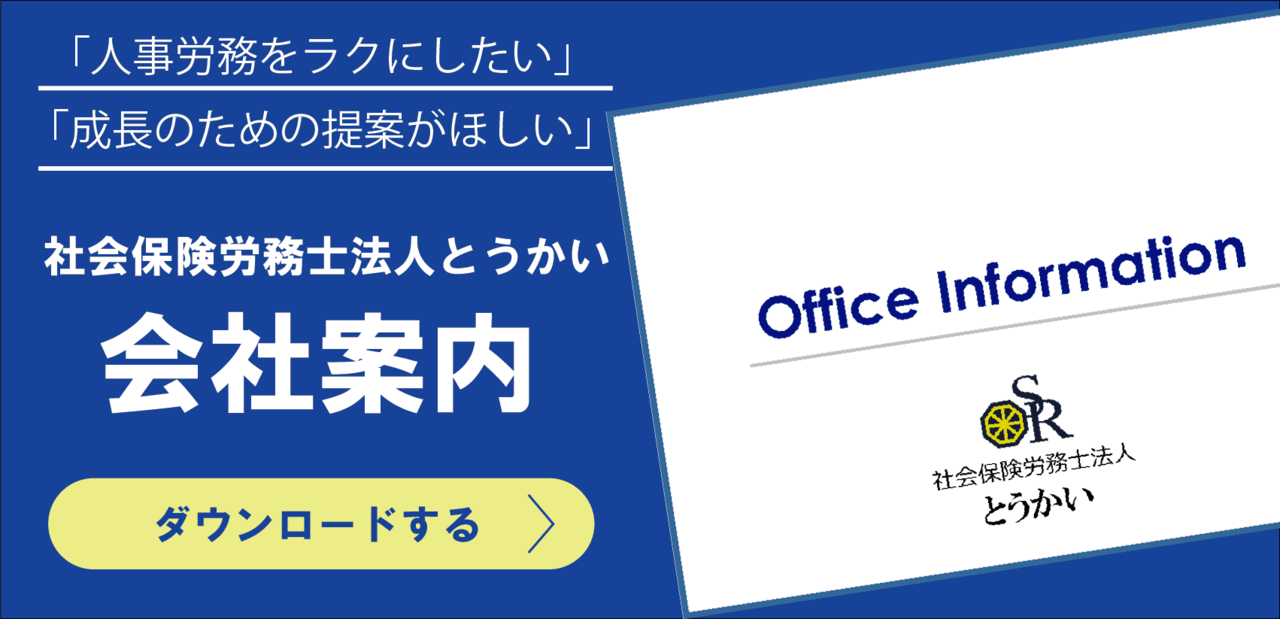育児休業給付金が80%に引き上げ!
時期や受給の条件、税金について気になるポイントをおさえましょう

2025年4月以降、育児休業給付金の拡充が予定されています。育児休業給付金の給付率が80%に引き上げられることで、育児を行う働く人たちにとって、大きな支援となると期待されています。この制度は、子どもが生まれた直後の一定期間に両親が育児休業を取得することを促進し、家計に対する経済的な負担を軽減することを目的としています。新しい制度が施行されることで、現行の給付率67%から80%への引き上げとなり、多くの家庭が子育てに専念できる環境が整いつつあります。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

育児休業給付金の概要と支給対象者について詳しく解説します。
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児のために休業する際に支給される給付金です。育児休業中はほとんどの場合、通常の給与が支払われなくなるため、育児休業給付金により収入減を補う目的があります。育児休業給付金の受給資格は雇用保険への加入が必要であり、特定の条件を満たす必要があります。
育児休業給付金とは、育児のために仕事を休む両親を支援するための制度です。基本的に、育児休業を取得する従業員には給与の支給がされないため、収入減を補うために、育児休業給付金として、通常の給与の約67%程度が給付されます。2025年4月の法改正により、80%に引き上げられる見込みです。ただし、育児休業給付金制度には要件を満たす必要があること、また給付金の上限が定められています。給付金額は育児休業前の給与によって異なります。
育児休業給付金の対象となるのは、大前提として1歳未満の子どもを育てる雇用保険の被保険者です。育児休業を申請する際には一定の条件を満たす必要があります。育児休業給付金といっても、大きく2つにわかれます。まず、男性のみが取得する産後パパ育休(出生時育児休業)に対して支給される育児休業給付金と、男性・女性問わず、育休を取得する際に支給される育児休業給付金があります。
育児休業給付金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
・育児休業開始する前2年間に、11日以上働いた月が12か月以上ある
・育児休業期間中に毎月、休業開始前の1か月あたりの賃金の8割以上が支払われていない
・育児休業期間中の就業日数が支給単位期間(1か月など)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下である
・有期雇用契約の場合、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6か月に達する日までにその雇用契約が満了することが明らかでない

大矢の経営視点のアドバイス
従業員が働きながら子どもを育てるうえで、育児休業制度への理解は非常に重要ですが、「わかりにくい」「結局、いくらもらえるのか」など、疑問や不安の声もよく聞かれます。企業の人事担当者は、制度を正しく理解し、不安を抱える従業員を丁寧にサポートしていきたいものです。

引き上げ時期と詳細をみていきましょう。
育児休業給付金は、育児休業期間中の収入減を補うために通常の給与の約67%程度が給付されます。2025年4月の法改正により、この給付率が80%に引き上げられる見込みです。この新制度が施行されることで、より多くの家庭が育児に専念できる環境が整っていくと期待されています。特に、手取りが上がることで、家計に与える負担も軽減されます。育児休業を取得する労働者にとって、経済的な影響が大きいものですので、新しい制度がどのように適用されるのかを知っておくことは非常に大切です。
育児休業給付金が80%に引き上げられるのは、2025年4月からと予定されています。育児休業を取りやすくすることが求められる中、この引き上げの施行によって、育児休業期間中の経済的な不安を軽減することが目的です。
現時点では詳細は明らかになっていません。新しい育児休業給付金制度の適用は、2025年4月以降に出産した場合に限られるのか、2025年4月以前に生まれた子どもであっても、育休を取得するタイミングが2025年4月以降の場合には、対象になる可能性もあるのか、注視しておくべきでしょう。
改正後の制度の適用に影響を及ぼす要因が多いため、情報収集が重要です。今後の公式な発表やガイドラインを参考にしましょう。

鶴見の経営視点のアドバイス
これまで育休取得が進まない理由の中に、職場で言い出しづらい、人手不足で長期の休業は難しいというほかに、「育休は取りたいが、収入がない状態は生活が厳しくなる」ケースもあったでしょう。今回の改正を皮切りに徐々に、育休を取得すること、生活の不安への解消が進むことを期待したいものです。

受給できる金額の計算をしてみましょう。
育児休業中の生活を支えるための育児休業給付金の金額は、育児休業を取得する人にとって、非常に大きな関心事です。育児休業給付金は、休業前の給与に基づいて計算されるため、給付額は個々の状況によって異なります。2025年4月に予定されている改正では、給付金が8割に引き上げられることになりますが、給付金には上限が設定されており、これを超える場合は、上限内での支給となります。具体的な金額や条件については、最新の制度に基づいて見直されることが必要です。
育児休業給付金の計算方法は、休業開始前の給与を基準にし、休業開始時の賃金日額を算出します。休業開始時の賃金日額は、育休開始前6か月間の賃金を180日で割ります。よって、給与の額によって、賃金日額が変動します。
この休業開始時賃金日額に育休日数と支給率を乗じて計算することになります。
・育休開始から180日まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
・育休開始後181日以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
ただし、2025年4月以降の改正により、出生後の一定期間に両親共に14日以上の育児休業を取得すると最大28日間、給付率が80%となります。
子どもを育てる家庭にとって給付金額を理解することは非常に重要です。なお、給付が行われる期間も重要であり、具体的な給付期間によっても全体の金額は異なります。家庭によって受け取れる金額はさまざまであり、自己の状況に合った情報を得ることが求められます。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
人事担当者にとって、ここ数年の育児休業制度の改正は、複雑でわかりにくい点も多いのではないでしょうか? しかしながら、確実なタイミングで申請・手続きを行なっていかないと、従業員に影響が及んでしまいます。不明点や疑問点があれば、社労士にご相談ください。

受給のための申請方法を見ていきましょう。
育児休業給付金を受け取るためには、いくつかの条件が設けられています。受給資格は雇用保険に加入していることが基本であり、一定の勤務年数や育児休業の取得状況にも影響を受けます。
また、具体的な受給条件には育児休業期間が設定されており、対象となる子どもの年齢や育児休業の開始時期も重要な要素です。これらの条件を確認しておくことで、スムーズに給付金を受け取ることが可能になります。特に、育児と仕事を両立させるためには制度の理解が一層求められます。
育児休業給付金の受給申請手続きには、必要な書類を整えなければなりません。まず、育児休業を取得する旨を会社に伝え、所定の手続きを行うことになります。申請には、育児休業給付金支給申請書や出生を確認できる母子健康手帳や医師の診断書、雇用保険被保険者証などが必要となります。
さらに、育児休業中の給与の支払状況を証明できるものとして賃金台帳や出勤簿なども求められることがあります。給付金には上限が設けられているため、これに基づいて申請を行う際には、正確な情報を記入することが重要です。特に、書類が不備であると、受給手続きが遅れる可能性があるため、準備をしっかりと行っておく必要があります。

小栗の経営視点のアドバイス
2025年以降、育休に関する法改正が予定されています。就業規則や育児休業規程など、早めの準備が大切です。就業規則の作成などでお困りの際には、お気軽にご相談ください。

育児休業給付金の新制度のメリットをあげていきます。
育児休業給付金の新制度の最大の特徴は、給付率が80%に引き上げられることで、育児休業中の家庭の経済的な負担軽減されることです。これまでの67%からの引き上げは、特に出産・育児を控える家庭にとって重要な要素です。育休期間中の収入減を理由に、育休取得に消極的であった家庭も、親が安心して育児に専念できる環境を提供します。経済的な支援が手厚くなることで、子どもを持つことに対するハードルも下がり、より多くの家庭が育児を楽しめるようになるでしょう。
育児休業給付金が80%に引き上げられることで、家庭の家計に対する負担が軽減されます。育児中のママやパパが安心して育児に専念できる環境が整います。例えば、月収30万円のケースでみると、現行の給付率67%の育児休業給付金では、約20万1,000円ですが、新制度の給付率80%では約24万円が支給されることになります。
税金が非課税、社会保険料も免除となりますので、手元に残る金額が増加することになります。生活費や子どもの教育資金への支出をより柔軟に計画しやすくなるでしょう。特に子どもが生まれたばかりの家庭では、育児に必要な物品を購入したり、サービスを利用したりと、支出が増えるため、家計の見直しも重要なポイントです。
新制度による育児休業給付金の引き上げは、金銭的なサポートが手厚くなることで、心理的な抵抗が減少します。この制度が浸透することで、多くの職場で育児休業を取得することがより一般的になり、風土の改善が期待されます。
家族全体が育児に関わる機会が増えることで、夫婦で共に育児を行う際の障害が取り除かれ、協力して子どもを育てることにつながるでしょう。職場の理解が進むことで、育児と仕事を両立しやすい環境が整っていくことが求められます。
育児休業給付金の新制度により、多くの家庭で育児休業取得が進めば、育児環境が改善されていくでしょう。給付金が上限なく手厚く支給されることで、育児に対する経済的な支援が強化され、親が安心して子育てに取り組む基盤が整います。特に、少子化が進む現代において、良好な育児環境を築くことは社会全体の問題です。
また、この制度が普及することで、親たちが育児を共有する風潮が広がり、育児に関する社会全体の意識向上、風土の醸成が見込まれます。各家庭が育児を楽しむための環境整備が進むことで、子どもを育てる喜びを多くの人々が実感できるようになるでしょう。

育児休業給付金の新制度は、出産や育児を行う家庭、これから子どもを迎えたい家庭にとって重要な支援です。給付率の引き上げにより、経済的な負担が軽減されつつ、両親がより安心して育児に携わることができる環境が整うことを期待したいものです。これまで、なかなか取得の進まなかった男性の育児休業取得をはじめ、育児休業中の状況が改善されることで、仕事との両立が容易になり、家計における経済的な余裕を生まれれば、企業にとっても人材活用、働く人のエンゲージメントにもつながります。
この新制度を活用し、育児に対しての不安を軽減しながら、より多くの家庭が子育てを楽しむことができる時代を迎えることに期待が寄せられています。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」