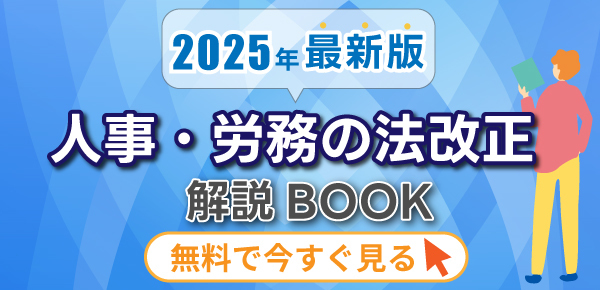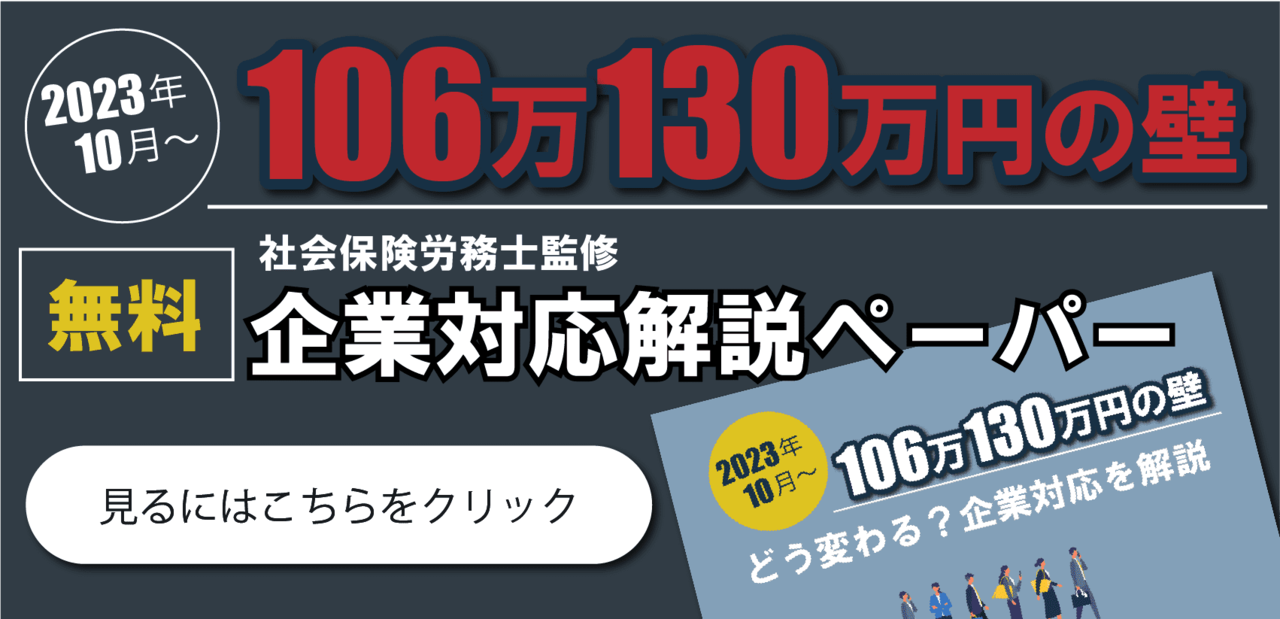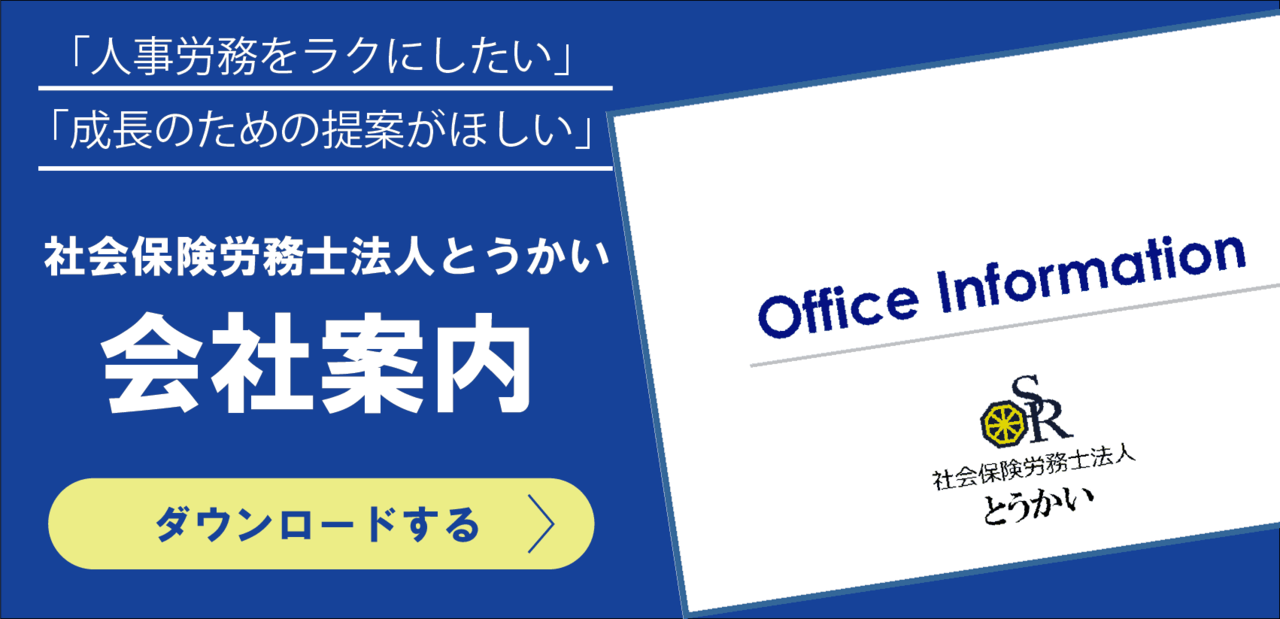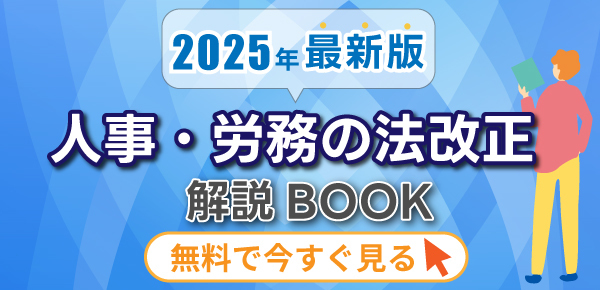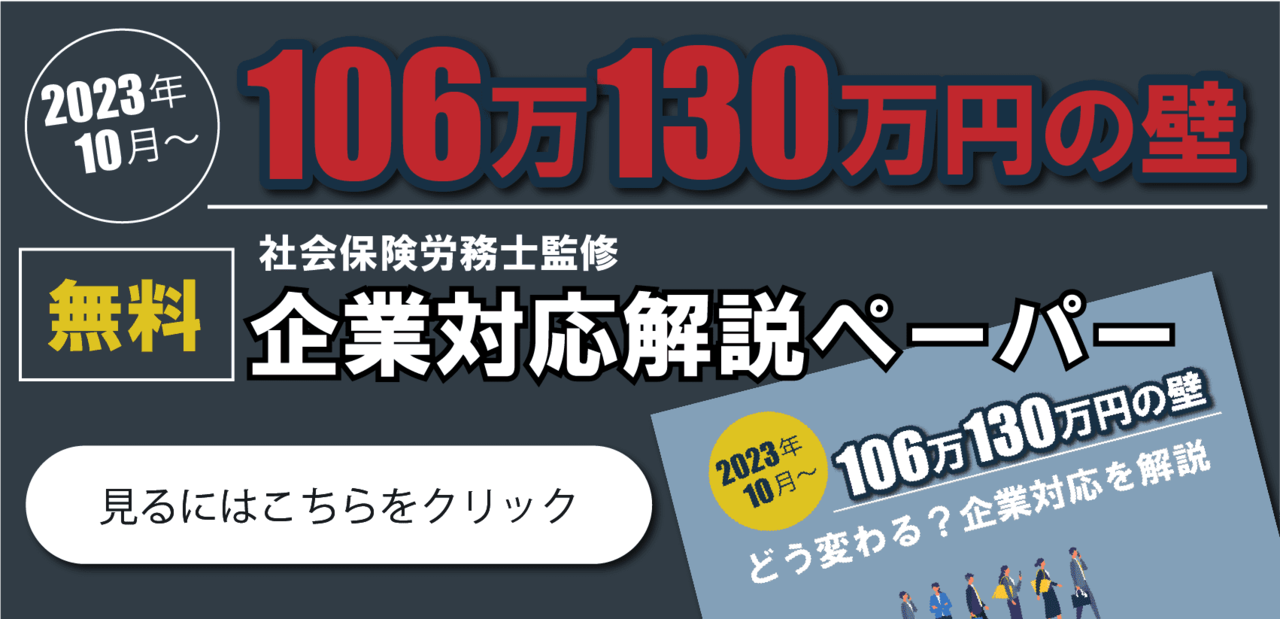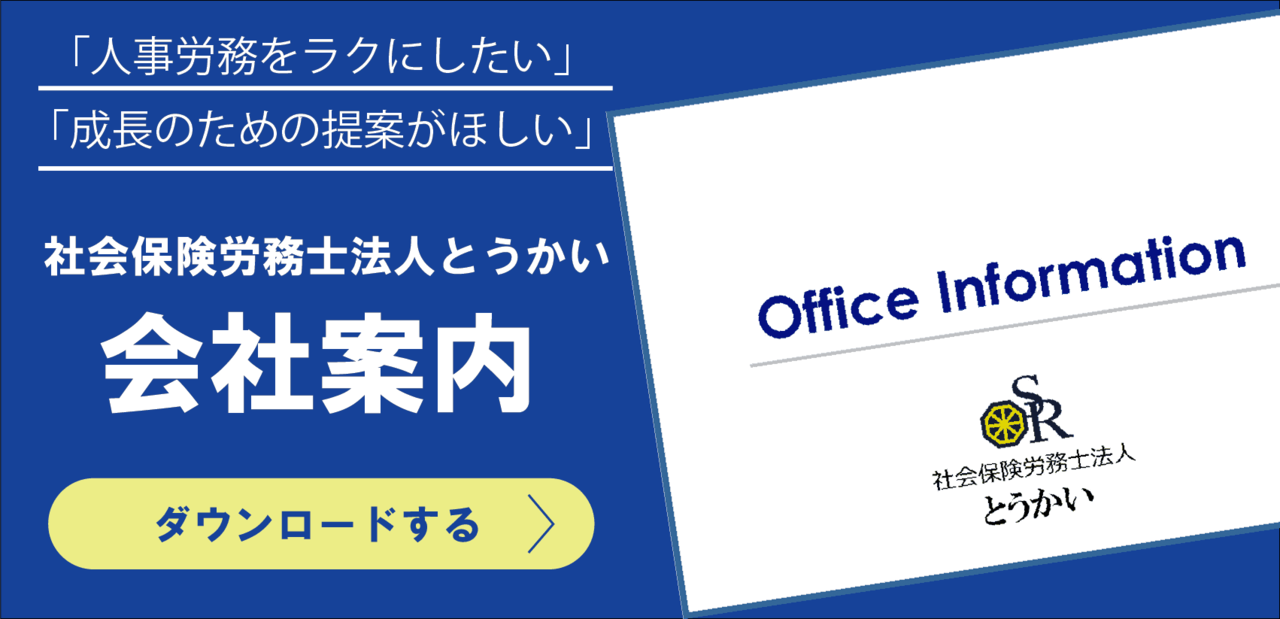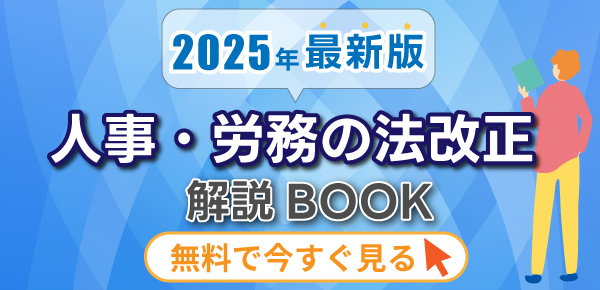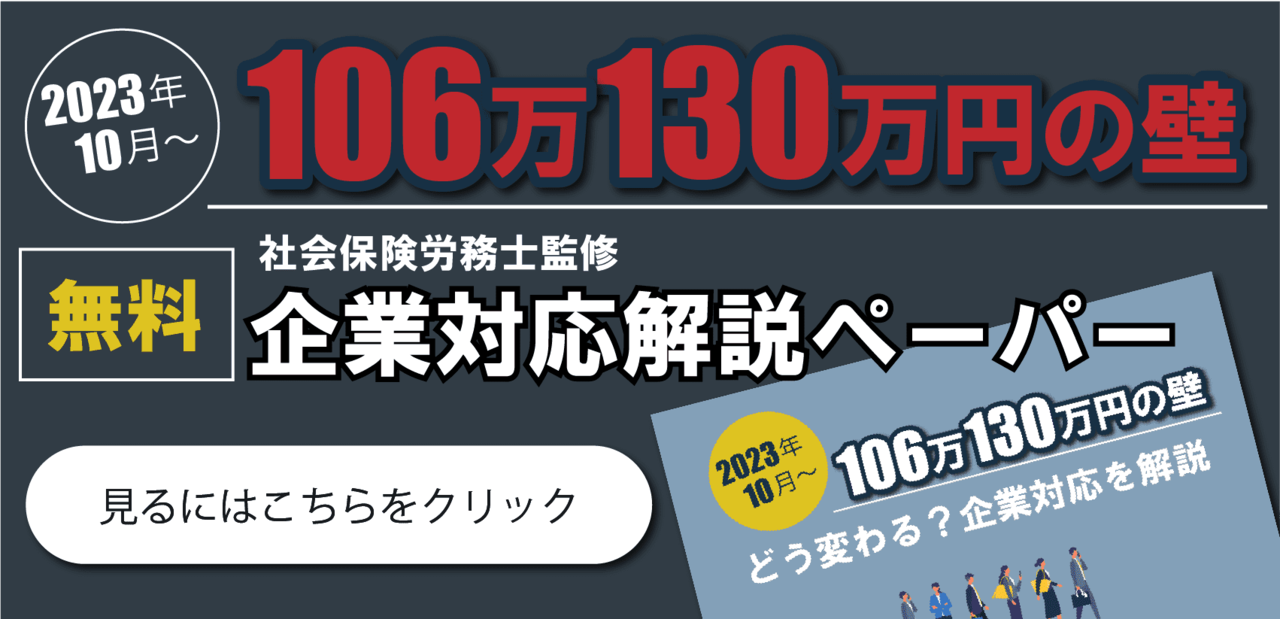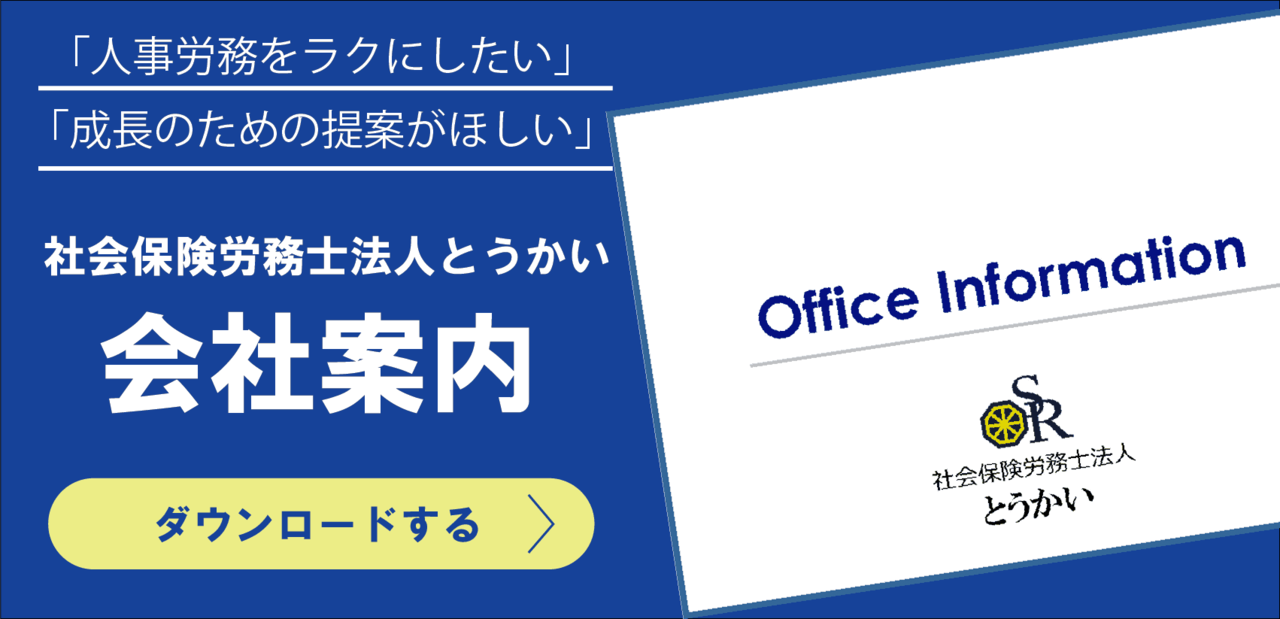賞与(ボーナス)にかかる社会保険料はいくら?
手取り金額の計算方法を分かりやすく解説

賞与(ボーナス)にも、給与と同様、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料といった社会保険料がかかります。賞与(ボーナス)額は、企業によって異なるものの、社会保険の基本的な計算方法を理解すると、事前に手取り額を把握しやすいでしょう。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

賞与(ボーナス)と社会保険料の概要を解説します。
賞与(ボーナス)とは、通常の給与とは別に支給される特別な手当、臨時の給与のことです。一般的には年に1〜3回支給され、会社の業績や従業員の業績、目標達成状況などに基づいて決まります。賞与(ボーナス)支給時にも、毎月の給与と同様で、社会保険料が適用されるため、賞与額から一定の金額が控除されます。この社会保険料は、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険が含まれ、各保険料にはそれぞれの保険料率に基づいて計算され、控除されることになります。賞与にかかる社会保険料の計算方法は、毎月の給与から控除される保険料の仕組みとは少し異なりますので、正確に理解しておくことが大切です。
賞与(ボーナス)は、毎月の給与とは別に会社から支給される一時的、特別な報酬です。賞与(ボーナス)は企業の業績や個人のパフォーマンスに基づいて異なるため、支給時期、支給回数、支給額などは会社ごとに異なりますが、通常、賞与(ボーナス)の支給は年に数回あり、春夏冬のシーズンに行われることが多いでしょう。
賞与(ボーナス)は、特別手当、決算手当、一時金などの名称として呼ばれることもあります。これらの名称は内容に応じて異なりますが、基本的には従業員の会社や業績への貢献を評価するための手段として位置づけられています。
社会保険は、適用を受ける会社で条件を満たす場合には、必ず社会保険に加入することとなります。該当する従業員は、給与や賞与(ボーナス)から社会保険料が徴収されるしくみです。国が定める法律に基づいて徴収される保険料で、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険になります。このしくみは、国民の健康や生活水準を保つために必要な財源を確保するために設けられています。
従業員はそれぞれの保険に対して一定の割合で保険料を負担し、企業側も同様に負担します。賞与(ボーナス)支給時にも、社会保険料を徴収されるため、賞与(ボーナス)が支給される際には、社会保険料がいくら引かれ、手残りがいくらになるのかが重要な関心事となります。

小栗の経営視点のアドバイス
従業員であれば、誰もが楽しみにしているものの一つであるのが賞与(ボーナス)かもしれません。首を長くしてボーナスを待ち侘びていたのに、実際に手にした金額が少なくてビックリ、なんてこともあるかもしれません。従業員にとっては、額面も大事だけど、手取りのほうがもっと重要です。ある程度の税や社会保険の知識があれば、お金の予定も立てやすいというもの。今のうちから、しっかり理解しておきましょう。

賞与(ボーナス)にかかる社会保険料の計算方法を解説します。
賞与(ボーナス)にかかる社会保険料の計算方法は、毎月の給与で徴収される社会保険とは異なる点がありますので、注意が必要です。各保険ごとの計算方法について確認しましょう。
健康保険料(介護保険)の計算は、賞与支給額を基に、標準賞与額を求めます。標準賞与額は賞与支給額を1,000円未満を切り捨てた金額です。標準賞与額に健康保険料率を乗じて、健康保険料を算出します。
健康保険料率は、年ごとに変わる可能性があるものです。また健康保険は都道府県ごとに異なるため、実際に計算する際はその地域の保険料率を確認する必要があります。これにより、より正確な計算が可能になるでしょう。従業員の保険料負担はこの料率によって決まり、企業と従業員の折半で負担する形がとられています。
厚生年金保険料の計算は、健康保険料(介護保険)と同様に、標準賞与額に厚生年金保険料率を乗じる方法が用いられます。ただし、健康保険料と異なる点として、賞与額の上限金額は、1か月あたり150万円です。
雇用保険料の計算には、支給された賞与(ボーナス)額に対して雇用保険料率を掛け算して、雇用保険料を算出します。健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料が、標準賞与額を用いて計算するのに対して、雇用保険料は賞与支給額を用いて計算する点を理解しておきましょう。
雇用保険料率は毎年見直されるため、最新の料率をもとに計算します。通常の給与とは異なる取り扱いが必要です。ボーナスを支給する際には、どの社会保険料が適用されるかを正確に把握し、適切に計算することが重要です。
賞与にかかる社会保険料の計算時には、料率の変更に特に注意が必要です。年度ごとにその料率が変動することが多いため、正しい保険料率で計算しないと、控除額を誤ってしまうことがあります。
また、同一月に複数の賞与が支給される場合、合算して標準賞与額を算出しなければなりません。厚生年金保険料を計算する際にも、標準賞与額には上限が設けられているため、これらのポイントをしっかりと把握することで、正確な計算を行うことができ、後日のトラブルを防ぐことができるでしょう。
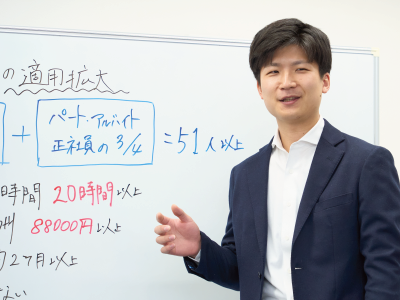
賞与(ボーナス)から引かれる社会保険料の計算例もみていきましょう。
賞与(ボーナス)から引かれる健康保険料(介護保険)や厚生年金保険料、雇用保険料は、それぞれ保険料率を掛けて計算され、最終的な手取り金額を導き出す流れとなります。賞与から引かれる社会保険料の計算例を具体的な数値を用いて確認してみましょう。
賞与の計算を簡単にするためにシミュレーションを活用する方法があります。専用の計算ツールや早見表を利用することで、必要な情報を素早く把握できるという利点が存在します。例えば、賞与額と保険料率を入力すると、シミュレーションの結果が瞬時に得られる仕組みです。この方法によって、個別に計算する手間が省け、より効率的に手取り金額を確認できます。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
具体例として、賞与支給額が500,500円の場合でシミュレーションします。
健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料については、1,000円単位を切り捨てますので、500,000円が標準賞与額となります。
健康保険+介護保険料率(5.79%)、厚生年金保険料率(9.15%)の場合には、
健康保険料(介護保険料) 500,000円×5.79%=28,950円
厚生年金保険料 500,000円×9.15%=45,750円
となります。
さらに、雇用保険料率(0.6%)であれば、賞与支給額に保険料率を乗じますので、
雇用保険料 500,500円×0.6%=3,003円
となります。
会社の従業員であるみなさんが、賞与を受け取った後、手取り金額が「おかしい」と感じる場合、まずはその理由を確認することが重要です。まずは、賞与支給額に対して引かれる社会保険料や税金の割合が正確かどうかを確認する必要があります。
計算ミスや適用された保険料率が間違っていた場合に、手取り金額に影響を及ぼしていることも考えられます。特に、給与と賞与で社会保険料の控除額の計算方法が異なるため、誤解が生じやすいポイントです。
さらに、賞与が支給された月において何らかの変更があった場合も、金額が変化する要因となります。このような状況を踏まえ、必要に応じて人事部門等に確認を行うことで、正確な情報を得ることが可能です。

特定の状況で社会保険料がかからない場合をご紹介します。
賞与(ボーナス)に、社会保険料がかからない場合もあります。具体的には、産前産後休暇、育児休業中や退職にする従業員の場合に該当するケースがありますので、理解しておきましょう。
退職月に賞与(ボーナス)が支給される場合、その退職日に応じて、賞与に対する社会保険料がかかるのか、かからないのかが変わります。まず理解しておきたいのが、社会保険は退職日の翌日が資格喪失日となる点です。賞与を受け取った月に退職する場合、退職日がその月途中であれば、その月の社会保険料はかかりません。一方、賞与を受け取った月の月末に退職する場合には、資格喪失は翌月1日となることから、賞与を受け取った月は、社会保険に加入しているものとして、社会保険料が徴収されます。そのため、退職を控えた従業員にとっては、手取り額が変わる重要なポイントとなります。
産前産後休暇や育児休業中は、社会保険料の支払いが免除されています。よって、この期間に支給される賞与は、社会保険料が免除されます。
この制度により、育児や産休中の従業員が経済的な負担を軽減できるように配慮されているといえます。安心して育児や休暇に専念できる環境が整えるための制度となっています。
社会保険の計算を行う際の標準賞与額に関しては、上限額が設定されており、上限額を超えた部分については社会保険料が控除対象外となります。健康保険や厚生年金の標準賞与額には法律によって上限が異なりますので、注意が必要です。賞与の計算を行う際に、こうした控除対象額や上限について注意を払うことが重要となります。適切な知識を持つことで、正確な手取り額を把握することができるでしょう。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
健康保険の上限は573万円/年となっており、毎年4月1日から翌年3月31日を1年度として、この間の累計額をもとに判断されます。また、厚生年金保険の上限は、150万円/月となっています。賞与月の支給額が150万円を限度としています。例えば、200万円の賞与が支給されたとすると、150万円に対して保険料率を乗じることになるのです。

賞与(ボーナス)の支給頻度と社会保険料についてみていきましょう。
賞与(ボーナス)の支給頻度についても、社会保険料に与える影響は大きくなります。賞与(ボーナス)の支給については、企業ごとに定めることができますので、年1〜2回の支給のケースもあれば、3回、4回といったケースもあります。ただし、社会保険の取扱上では、年3回支給される場合と年4回支給される場合とでは、保険料の計算方法や控除対象の仕組みが異なります。このため、支給頻度によって実際の手取り金額も変わることが多く、従業員にとっては重要なポイントです。
賞与(ボーナス)が年3回支給される場合と年4回支給される場合で、社会保険料の取扱いが変わりますので注意が必要です。賞与(ボーナス)が年3回の場合は、通常の賞与(ボーナス)における社会保険料の計算方法を用いることができます。
しかしながら、年4回以上支給される賞与(ボーナス)の場合は、社会保険での取扱い上は、毎月の給与の社会保険と同様、標準報酬とみなされるのです。
年3回支給の賞与と年4回支給の賞与では、社会保険料が変わってきますので、手取り金額にどのような違いが生じるのかを理解しておくことが重要でしょう。

手取り額アップのために知っておきたいことをチェックしましょう。
賞与(ボーナス)の手取り額を増やすためには、控除に関する理解が不可欠です。特に、賞与から引かれる社会保険料や税金の仕組みがどのように影響しているかを知っておくことが重要です。
賞与(ボーナス)にかかる所得税や社会保険料は、手取り額に大きく影響を与える要因の一つです。賞与支給額が高額なほど、控除額も多くなり、結果的に手取りが減少してしまうことも考えられます。
会社として、従業員の賞与の手取り額へのインパクトを抑えるには、所得税の観点からみるならば、支給タイミングや頻度、金額の調整などの検討も一つでしょう。年末調整などとの組み合わせをうまく使うこともできます。
社会保険料も毎年見直されるため、変更された新しい料率を意識することが必要です。必要な情報を集めておくことで、手取り額を最適化する手段を講じることが可能となります。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」