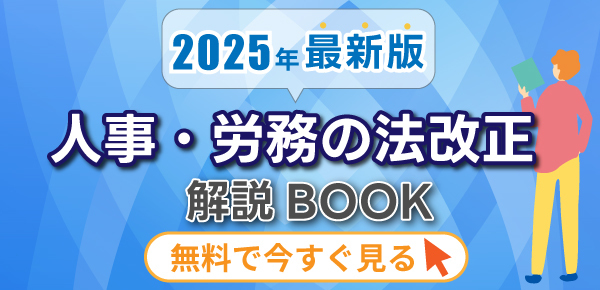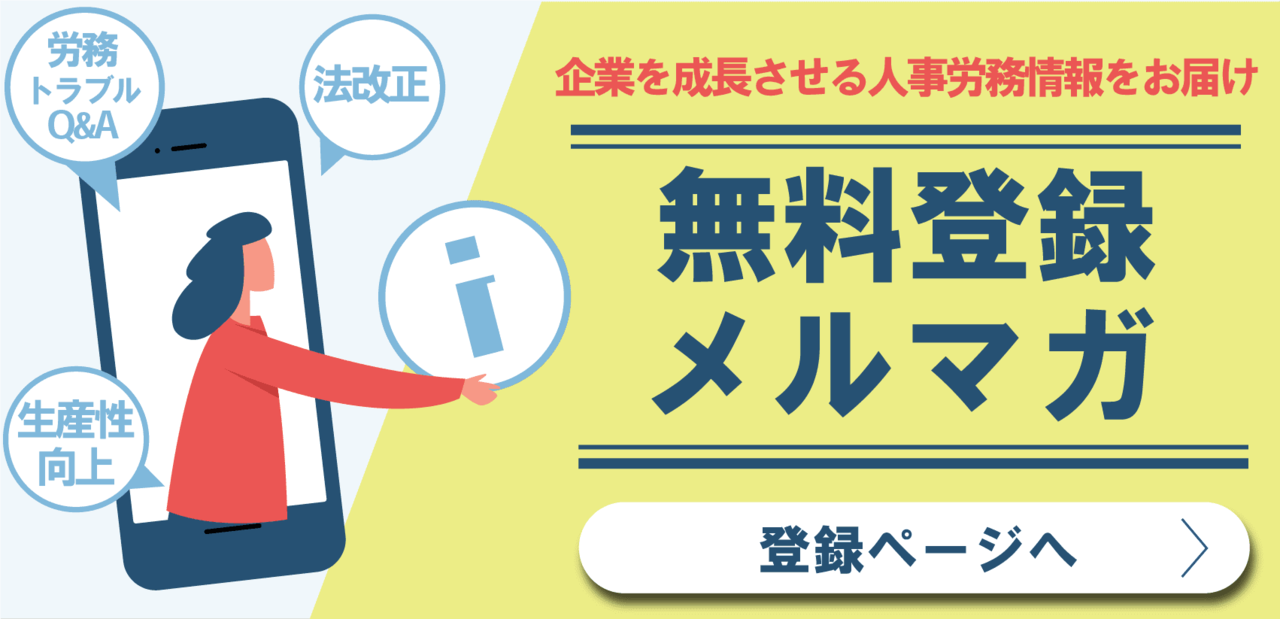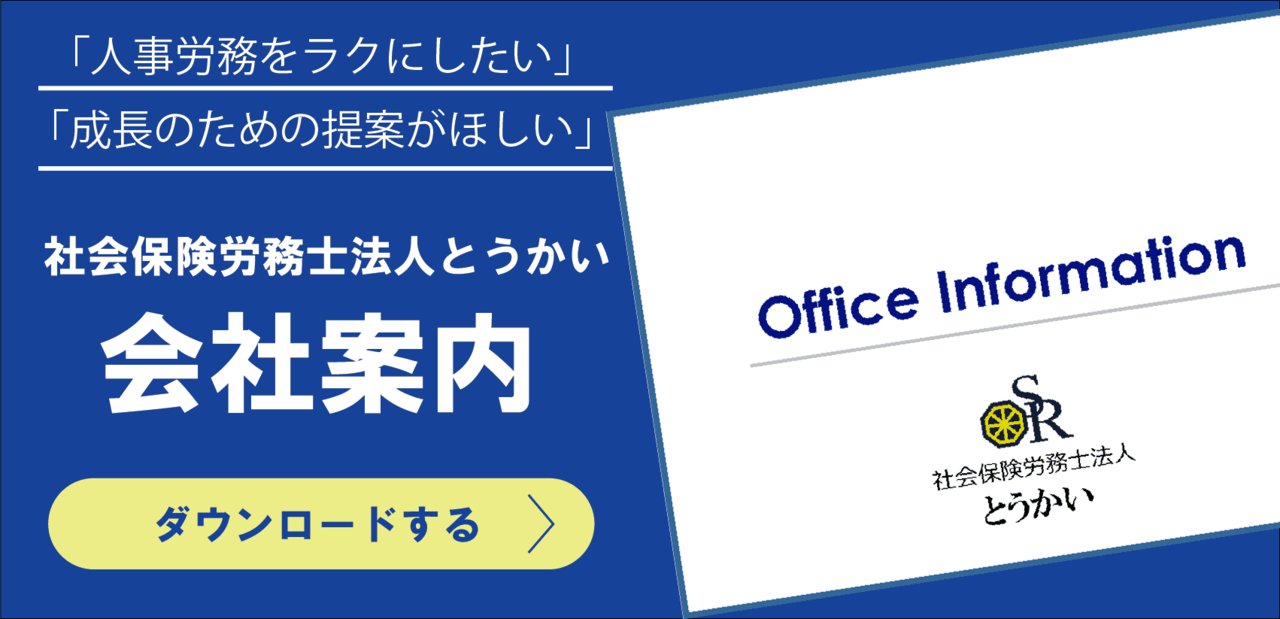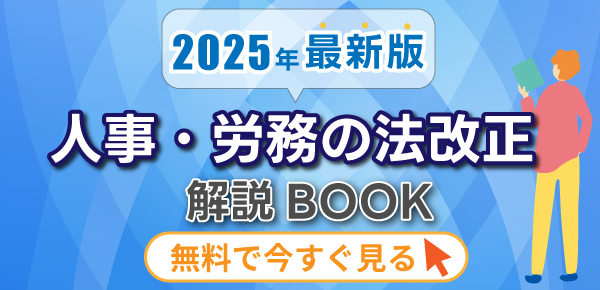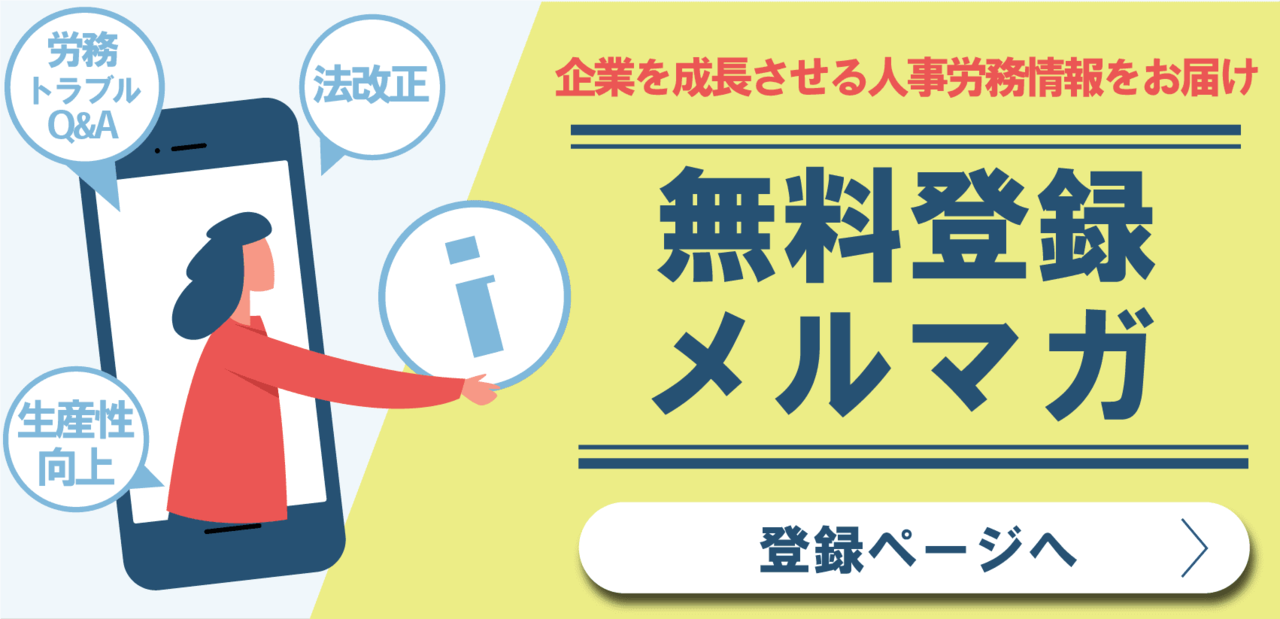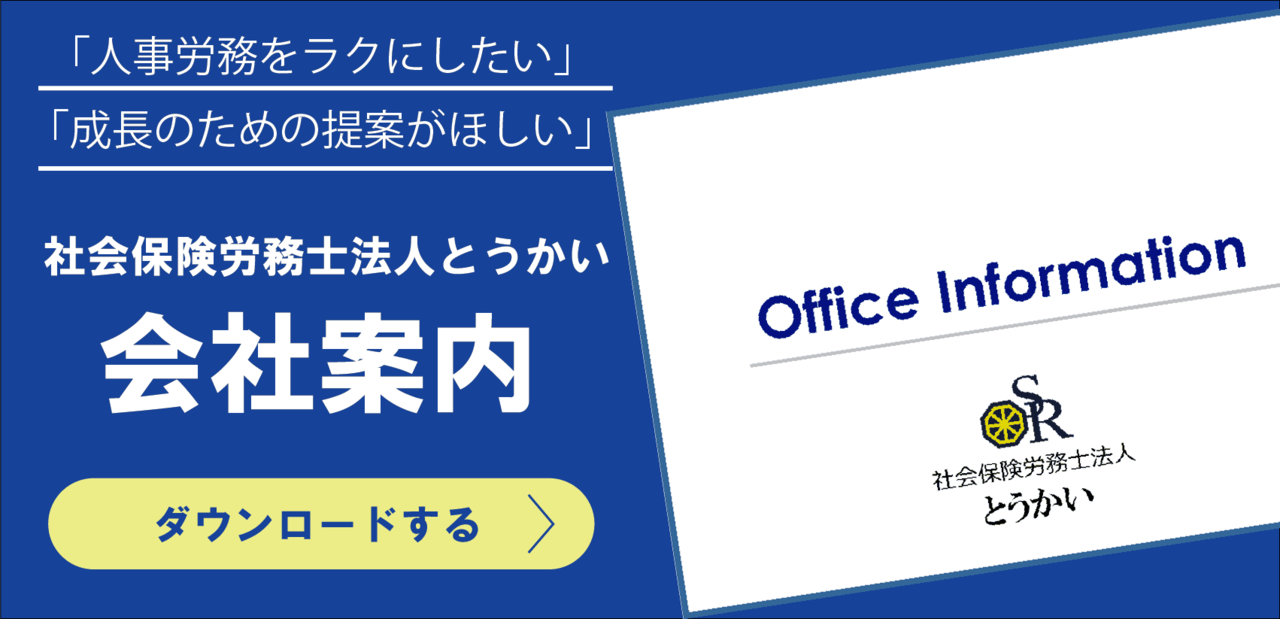子の看護休暇は有給?無給?対象となる子どもや取得の条件を解説

子の看護休暇は、働く親にとって非常に重要な制度であり、子供が病気や怪我をした際に必要な時間を確保できるための仕組みです。2025年4月からは、取得事由の範囲が広がり、名称も「子の看護休暇」から、「子の看護等休暇」に変更される予定です。制度の理解を深めることで、育児と仕事を両立するための一助となります。子どもを育てる従業員にとっては、有給なのか無給なのか、また対象となる子どもの年齢や取得時の注意点などが気になる点が多いでしょう。今回は、重要なポイントを確認していきます。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
執行役員 社会保険労務士 小栗多喜子
同社、人事戦略グループマネージャーを務め、採用・教育を担当する。商工会議所、銀行、Adeco,マネーフォワードなどセミナーや研修講師も精力的に行っている。労働法のアドバイスだけではなく、どのように法律と向き合い企業を成長させるのかという経営視点でのアドバイスを得意としている。
主な出演メディア
その他、記事の監修や寄稿多数。
取材・寄稿のご相談はこちらから

子の看護休暇制度の基本情報を見ていきましょう。
子の看護休暇制度は、小学校に入学前の子どもを育てる労働者のための制度です。この制度の目的は、子供が病気や怪我をした際に必要なケアを行うための時間を確保することです。年次有給休暇とは別に設けられています。具体的には、病院に連れて行ったり、看病をしたりするための休暇を取得することが可能になるものです。この制度は特に、働く親にとって、柔軟な働き方を支援する重要な役割を果たしています。
子の看護休暇は、小学校入学前の子どもを育てる従業員が、子どもが病気や怪我をした際に、看護や世話のため取得できる休暇です。年次有給休暇とは別に法律に基づいて設けられた休暇制度で、従業員が子どもの看護を行う目的でのみ利用できるように設計されています。育児と仕事の両立を図るための重要な手段となっています。親が病院に連れて行く場合や自宅でのケア、予防接種に連れて行く必要がある際などの利用が想定されています。子の看護休暇は、原則として子ども1人につき年間5日(対象となる子どもが2人以上の場合は10日)取得することが可能です。1日単位、半日単位、時間単位での取得ができますので、活用しやすくなっています。
子の看護休暇を利用できる従業員は、小学校就学前の子どもを扶養する親に限られています。日雇い労働者を除くすべての従業員が対象です。正社員やパート・アルバイトなど、従業員の雇用形態は問いません。したがって、子の看護休暇制度は多くの人にとって利用可能な制度であり、さまざまな働き方をする家庭に配慮された形となっています。
ただし、就業規則や労使協定で、「入社後、雇用期間が6か月未満」「1週間の所定労働日数が2日以下」の場合には、除外されているケースもありますので、自社のルールがどのようになっているか確認する必要があるでしょう。
子の看護休暇において対象となる子どもは、小学校就学前の年齢に限定されています。この制度は、子どもが病気や怪我をした際に、親や保護者が看護やケアを行うために設けられています。また、予防接種や定期検診を受ける際にも看護休暇を使用できます。年齢が上がると、この制度の対象から外れるため、早期に制度を利用し、必要なサポートを受けることが重要です。
子の看護休暇と似ていますが、介護休暇は異なる制度です。介護休暇は、介護状態にある家族を介護するためのものです。子の看護休暇は、主に小学校就学前の子どもに焦点を当てています。つまり、看護する対象や取得の目的が異なる点が大きな特徴です。また、取得できる期間や日数についても、それぞれに定めがあります。

厚生労働省が定める法律と改正点について解説します。
子の看護休暇制度は、育児・介護休業法に定められています。育児・介護休業法は、主に育児や介護を行う労働者が、仕事と育児、仕事と介護を両立することを目的としています。
育児・介護休業法は、働く労働者が育児や介護を行う場合であっても、仕事を辞めずに仕事と家庭を両立できるよう、休暇を取得したり、労働時間を短縮して働きやすくできるようにするための法律です。育児休業や介護休業の制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度をはじめ、育児や介護を行う労働者に対する支援措置が規定されています。仕事と家庭生活の両立を支援し、労働者がより柔軟に子育てができる環境を整備し、事業主に対しても配慮ある対応を促す効果が期待されています。
育児・介護休業法は、ここ数年にわたって改正がされてきました。2021年には子の看護休暇に関する制度が充実し、これまで全日単位での取得が一般的であった子の看護休暇が、時間単位でも取得できるようになりました。労働者が必要な時間だけを選択できることにより、より柔軟な働き方が実現できるようになったのです。さらに、対象となる労働者の範囲も広がり、より多くの人々が制度を活用できるようになりました。このような改正は、育児中の家庭にとって大きな支援となり、仕事と家庭の両立の重要性が改めて認識されています。2025年4月からは、名称が「子の看護等休暇」に変更され、対象となる子の範囲や取得事由も拡大される予定です。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
2025年4月からは、対象となる子どもの範囲が広がり、小学校修学前の子どもから、小学校3年生修了までに延長される予定です。また、取得事由についても拡大され、感染症に伴う学級閉鎖や入園式、卒園式、入学式などでも利用できるようになります。さらには労使協定を締結している場合には、雇用期間が6か月未満の労働者は、取得ができませんでしたが、法改正により取得が可能となります。

子の看護休暇はどのような扱いになるのでしょうか。
子の看護休暇について、有給になるのか、無給なのかは、企業の就業規則や労使協定によって異なります。具体的な取り扱いについては、各企業の方針に委ねられていますので、必要に応じて確認することが大切です。
子の看護休暇について、法律で定められているのは、休暇が取得できることのみであり、有給か無給かを定めているわけではありません。企業によっては、看護休暇を有給として認めているところもあれば、無給としている場合もあります。就業規則などに明記することになります。労働者は、必ず自身の勤務先の就業規則等を確認しましょう。
子の看護休暇を取得した場合の給与計算方法も、しっかり確認しておく必要があります。企業によって看護休暇が有給として扱われる場合と、無給として扱われる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。有給である場合には、とくに問題はないでしょうが、無給である場合には、欠勤控除と同様の計算方法が適用されることになるでしょう。就業規則や給与規程で計算方法を確認するとともに、給与明細にどのような扱いがされているかをチェックすることも重要です。

小栗の経営視点のアドバイス
無給の場合、給与計算方法は欠勤と同様の計算方法が適用されるとしても、子の看護休暇は法律で認められているものであり、欠勤とは異なります。会社は従業員が子の看護休暇を取得しても不利益な扱いをしてはなりません。

子の看護休暇に関連する助成金について見ていきましょう。
子の看護休暇には、助成金制度が利用できる場合があります。会社が子の看護休暇について、有給にするなど法定を上回る制度を設けた場合などに、助成金があります。助成金を活用することで、事業主にとっても従業員にとってもメリットのある制度を整備することができます。
助成金制度には、厚生労働省が行う「両立支援等助成金」があります。この制度は、育児や介護と仕事の両立を支援する中小企業が対象で、子の看護休暇について有給などにする場合も対象となります。申請手続きは、各自治体やハローワークを通じて行うことができ、必要な書類や条件を満たすことで助成金を受け取ることができます。
助成金の種類や支給額は、年度によって変動することがあるため、常に最新の情報を確認しておきましょう。助成金を活用したいと考えている企業は、早めに情報収集を行い、申請手続きがスムーズに進むよう準備を整えることが重要です。助成金といった支援制度をうまく利用することで、会社が制度を整えるための経済的な負担を軽減できる可能性があります。

利用時の注意点と職場での配慮についてご説明します。
子の看護休暇制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。従業員にとっては、休暇を取得するにあたり、事前に会社の就業規則等を確認することが重要です。会社ごとに子の看護休暇の申請方法や取得する際の手続きが異なるケースもありますし、急な取得でも対応できるように、予め職場の休暇取得のプロセスなどを確認しておくとよいでしょう。
一方、企業側においても、従業員に子の看護休暇を取得させるにあたっては、注意すべきポイントがあります。
子の看護休暇を利用した場合、労働者が不利益を被ることは法律で禁止されています。この制度を利用したことを理由に、昇進や評価に悪影響が出ることは許されません。従業員は不利益な取り扱いを受けた場合は、労働基準監督署などに相談することができますので、後々トラブルに発展しないよう、企業側もしっかりと認識しておきましょう。
企業側は、子の看護休暇制度を活用しやすい環境を整える責任があります。例えば、子の看護休暇を取得する際に、従業員が申し出やすい雰囲気を作ることが必要です。また、企業は、看護休暇の利用状況を把握し、労働者が気軽に休暇を申請できるような制度運用を行うことが求められます。家庭と仕事の両立がしやすくなり、従業員の満足度向上にもつながるでしょう。
さらに、従業員が看護休暇を取得した場合には、代替要員の配備や業務の調整を適切に行うことで、事業運営への影響を最小限に抑える努力も求められます。企業がこのような配慮を行うことで、従業員が安心して看護休暇を利用できる環境を提供することが可能になります。

子の看護休暇制度は、育児と仕事の両立を支援する重要な仕組みです。制度を利用することで、働く親が子どもが病気になったときや怪我をしたときに、必要なケアを必要なタイミングで行いやすくします。年度ごとに最大5日まで取得できるため、育児中の家庭にとって大きな助けとなるでしょう。ただ、子の看護休暇は、無給で運用しているケースも多いので、従業員にとっては経済的負担により、取得しにくいといった声も聞かれます。企業は制度を有給にすることで、助成金の活用なども可能となりますので、選択肢を広げて検討するのもよいかもしれません。従業員の休暇取得を奨励し、育児と仕事の両立を助けることで、従業員にとって柔軟に仕事を続けながら家庭のニーズに応えるためのサポートとなるでしょう。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」