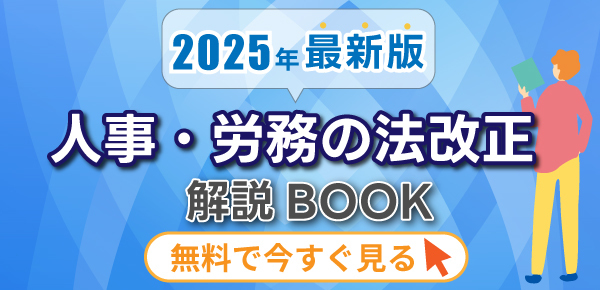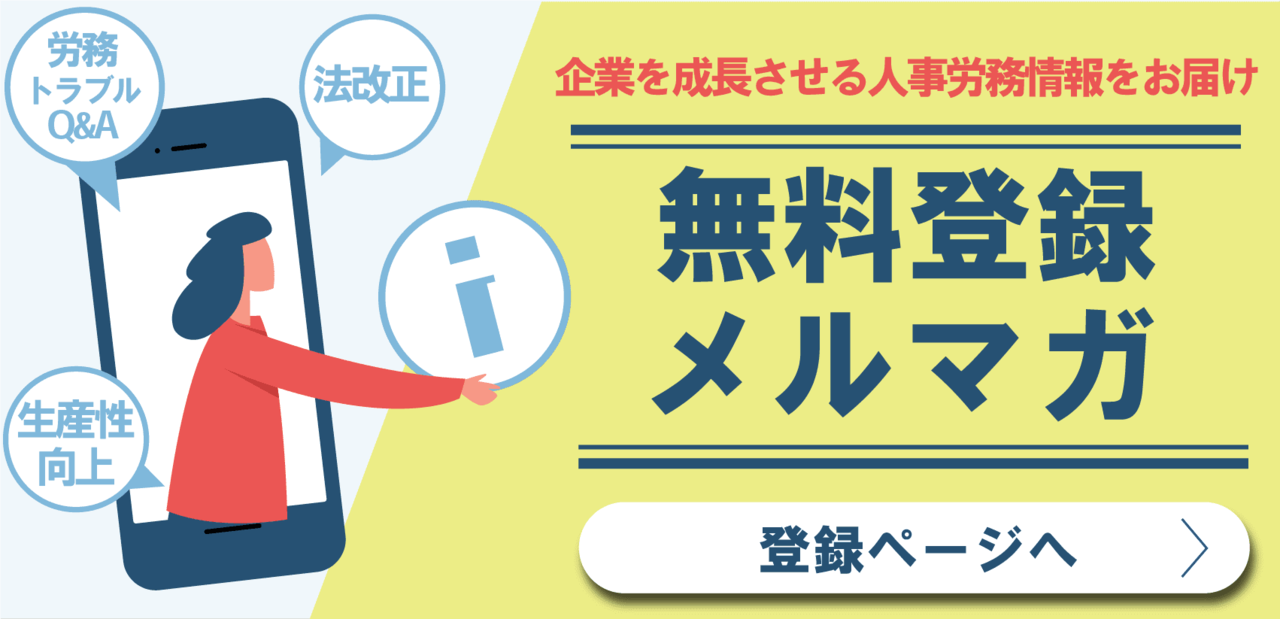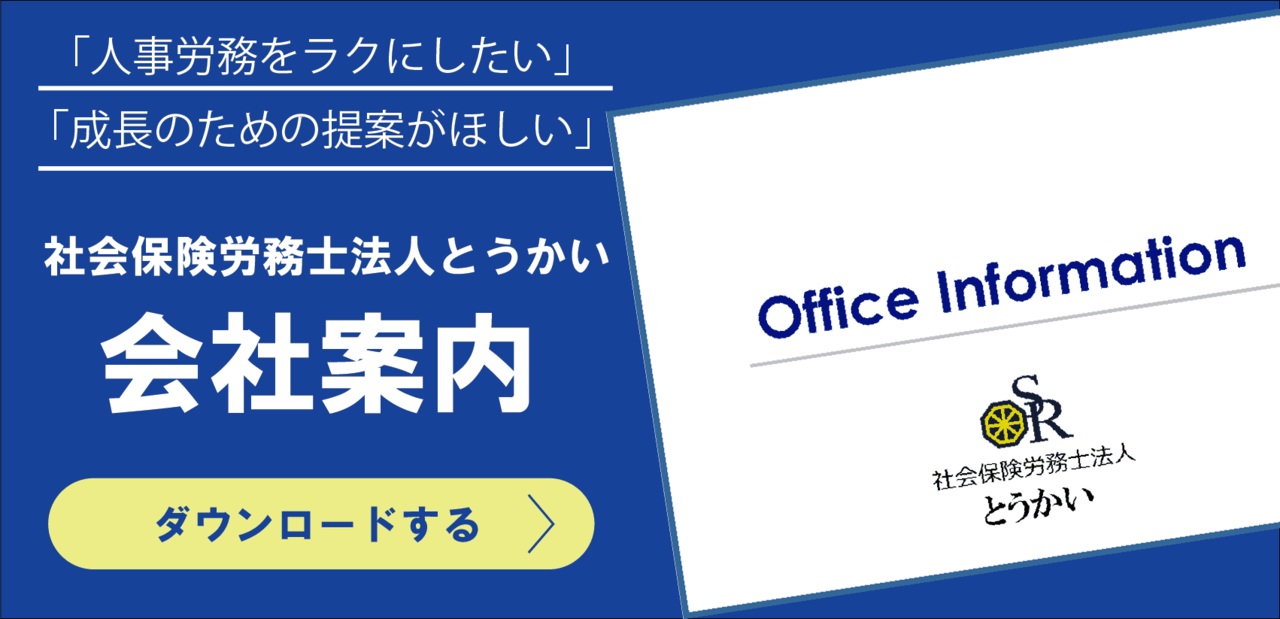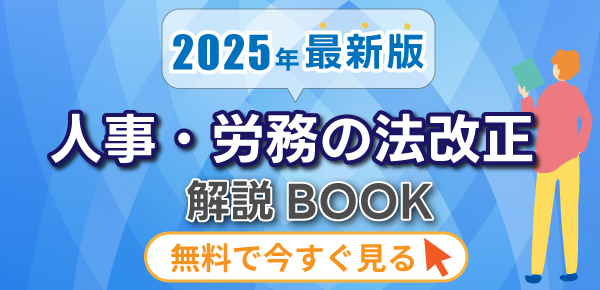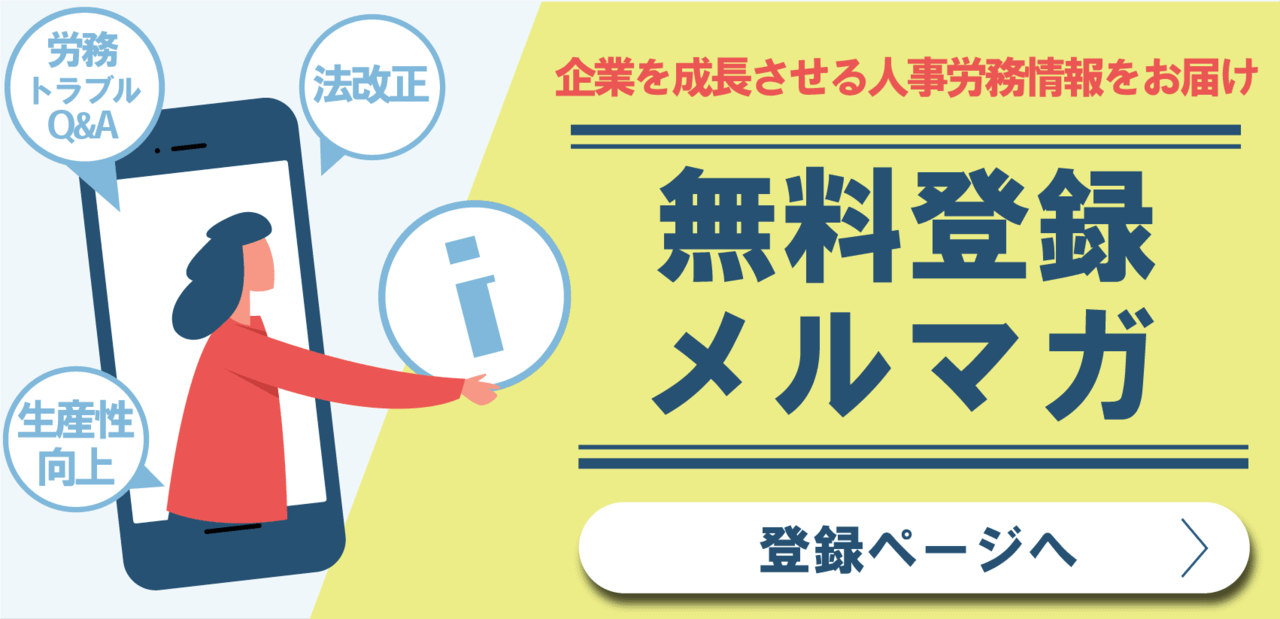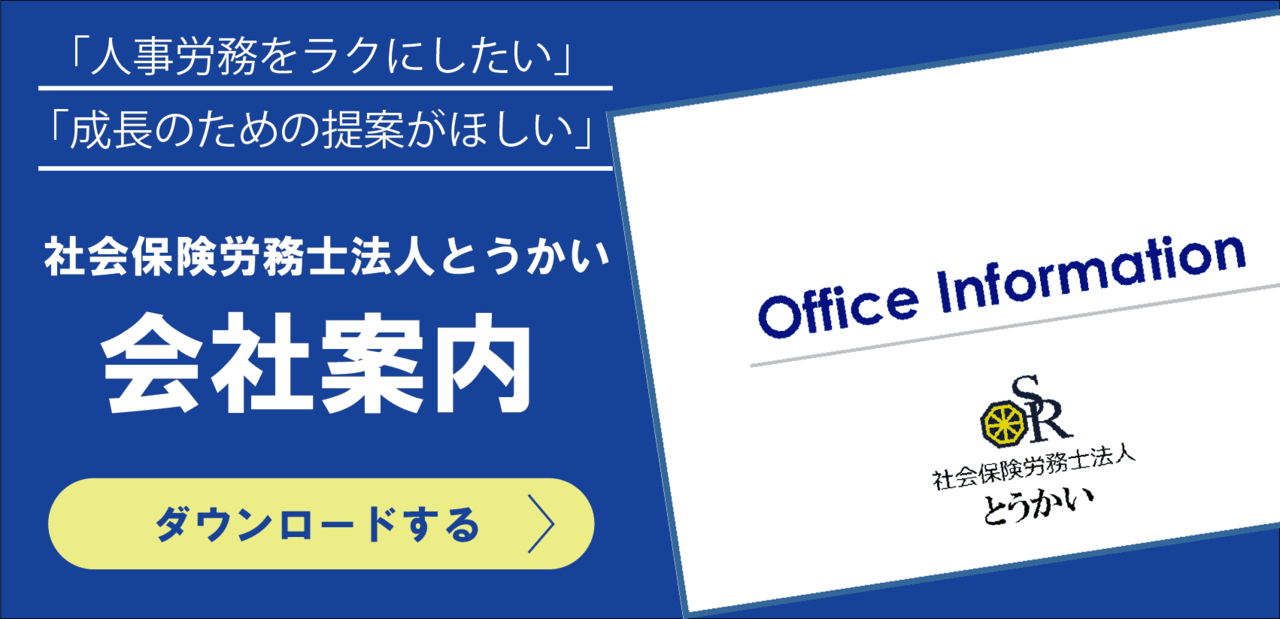間接業務の外注(アウトソーシング)とは?会社の成功事例やメリットを解説

会社の成長に伴い、経理や総務などの間接業務は複雑化し、コア業務を圧迫する一因となります。
この課題を解決する手法が、業務を外部委託するアウトソーシングです。
本記事では、間接業務のアウトソーシングとは何か、そのメリット・デメリット、具体的な業務例から外注先の選び方、成功事例までを網羅的に解説し、会社の生産性向上を支援します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

アウトソーシングとは何か、知っていますか?
間接業務の外注を検討するにあたり、まずは間接業務とアウトソーシングそれぞれの言葉の定義を正確に理解しておくことが重要です。
間接業務が企業活動においてどのような役割を担い、アウトソーシングがどのような仕組みで業務効率化を実現するのか、その基本的な概念を解説します。
間接業務とは、企業の売上や利益に直接的には結びつかないものの、事業活動を円滑に進める上で不可欠なサポート業務全般を指します。
例えば、総務、経理、人事、労務、法務、情報システムなどがこれに該当します。
これらの業務は、営業や製造といった企業の利益を生み出す「コア業務」を支える重要な役割を担っています。
しかし、企業規模の拡大に伴って業務量が増加し、専門性も求められるため、コア業務に従事する従業員の負担増やコストの増大といった課題につながるケースも少なくありません。
アウトソーシングとは、自社の業務プロセスの一部を、専門的な知識やノウハウを持つ外部の企業やサービスに継続的に委託する経営手法です。
「外部(アウト)からの資源調達(ソーシング)」を意味し、単なる業務の外部委託にとどまりません。
専門業者に業務を委託することで、自社のリソースをより重要なコア業務に集中させ、業務効率化や生産性向上を図ることを目的とします。
コスト削減はもちろん、自社にはない専門性を活用できる点も大きな特徴です。
人材を借りる人材派遣とは異なり、業務プロセスそのものを委託する点が異なります。

外注できる間接業務の具体的な種類を見ていきましょう。
間接業務と一口に言っても、その範囲は多岐にわたります。
ここでは、実際にどのような業務がアウトソーシングの対象となるのか、具体的な例を部門ごとに紹介します。
総務や経理、人事といったバックオフィス業務全般において、多くの業務が外注可能です。
自社の課題と照らし合わせながら、どの業務を委託できるか検討する際の参考にしてください。
総務・一般事務は、定型的なルーティンワークが多く、アウトソーシングに適した分野です。
具体的には、代表電話やメールの一次対応、名刺や契約書などのデータ入力、各種書類の作成・ファイリング、備品の発注・在庫管理、郵便物の発送・仕分けといった業務が挙げられます。
また、福利厚生サービスの窓口業務や、社内イベントの企画・運営サポートなども委託可能です。
これらのノンコア業務を外注することで、社員はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、組織全体の生産性向上に貢献します。
経理・財務は専門知識が求められる業務が多く、専門業者にアウトソーシングするメリットが大きい領域です。
日常的な業務としては、伝票起票や会計ソフトへの入力を行う記帳代行、取引先への請求書発行・送付、買掛金の支払管理、従業員の経費精算などが対象となります。
さらに、月次決算や年次決算のサポート、税務申告に関連する書類作成の補助といった、より専門性の高い業務も委託可能です。
法改正への対応や属人化の防止といった観点からも、経理業務の外注は有効な選択肢となります。
人事・労務分野では、専門知識が必要かつ定型的な業務をアウトソーシングできます。
代表的な例として、給与計算や年末調整、従業員の入退社に伴う社会保険・労働保険の手続き、勤怠データの集計・管理などが挙げられます。
また、採用活動における応募者管理、書類選考、面接日程の調整といった採用代行(RPO)も活用されています。
これらの業務は法改正の影響を受けやすく、ミスが許されないため、専門家に委託することで正確性と効率性を両立できます。
個人情報を多く取り扱うため、委託先のセキュリティ体制を確認することが不可欠です。
営業事務や秘書業務をアウトソーシングすることで、営業担当者が顧客対応や商談といったコア業務に専念できる環境を構築できます。
具体的な業務例としては、見積書や請求書、契約書といった各種書類の作成、顧客情報のデータ入力・管理、プレゼンテーション資料の作成補助などが挙げられます。
また、役員のスケジュール調整や会食・出張の手配といった秘書業務も委託可能です。
近年では、見込み客へのアプローチやアポイント獲得を代行するインサイドセールス支援サービスも増えており、営業活動全体の効率化に貢献します。

間接業務を外注する大きなメリットが3つあります。
間接業務の外注は、多くの企業が抱えるリソース不足やコストに関する課題を解決する有効な手段です。
ノンコア業務に潜む時間的・コスト的な無駄を削減し、組織全体の業務プロセスを改善することで、企業成長を加速させます。
ここでは、アウトソーシングによって得られる代表的な3つのメリットについて具体的に解説します。
アウトソーシングを導入する最大のメリットは、社員を間接業務から解放し、企業の売上や成長に直接貢献する「コア業務」にリソースを集中させられる点です。
例えば、営業担当者が請求書作成やデータ入力に費やしていた時間を、新規顧客の開拓や既存顧客との関係構築に使えるようになります。
また、経営層や管理職も、日常的な管理業務から解放され、事業戦略の立案や組織開発といった、より付加価値の高い業務に注力できます。
これにより、従業員一人ひとりの生産性が向上し、企業全体の競争力強化につながります。
間接業務のために正社員を雇用すると、給与や賞与だけでなく、社会保険料、福利厚生費、採用・教育コストなど、多くの付随費用が発生します。
アウトソーシングを活用すれば、これらの固定的な人件費を変動費化し、必要な業務量に応じてコストを最適化できます。
特に、繁忙期と閑散期で業務量が大きく変動する場合や、特定の期間だけ専門スキルが必要な場合に有効です。
新たに人材を採用・育成する必要がないため、採用コストや教育にかかる時間も削減できます。
結果として、トータルでのコスト削減を実現できる可能性が高まります。
アウトソーシングサービスを提供する企業は、特定の業務分野における専門的な知識、スキル、ノウハウを豊富に蓄積しています。
例えば、頻繁に法改正が行われる経理や労務の分野では、専門業者に委託することで、法令を遵守した正確な業務遂行が期待できます。
自社で専門人材を育成するには時間とコストがかかりますが、アウトソーシングなら即戦力となるプロフェッショナルの知見をすぐに活用可能です。
また、長年の経験から培われた効率的な業務フローの提案を受けられることもあり、自社の業務プロセス全体の改善にもつながります。

間接業務を外注する際に注意すべきデメリットを見ていきましょう。
間接業務の外注は多くのメリットがある一方で、導入前に把握しておくべきデメリットも存在します。
これらの注意点を事前に理解し、対策を講じることで、アウトソーシングの失敗リスクを大幅に軽減できます。
ここでは、外注を検討する際に特に注意すべき3つのデメリットと、その対策について解説します。
業務を完全に外部へ委託してしまうと、その業務の進め方や課題解決のノウハウが社内に蓄積されにくくなります。
これにより、将来的に業務を内製化しようとした際に手順が分からなくなったり、委託先との契約が終了した際に業務が滞ったりするリスクが生じます。
また、トラブルが発生した際に、社内に状況を把握している担当者がおらず、迅速な対応が困難になる可能性も考えられます。
このデメリットを回避するためには、委託先に業務プロセスを可視化してもらい、定期的な報告やマニュアルの共有を依頼することが重要です。
間接業務を外注する際には、顧客情報、従業員の個人情報、財務情報といった社内の機密情報を委託先と共有する必要があります。
これにより、自社単独で業務を行う場合に比べて、情報漏洩のリスクが高まることは避けられません。
万が一情報が外部に流出すれば、企業の社会的信用を大きく損なう事態になりかねません。
そのため、委託先を選定する際には、プライバシーマークやISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証の取得状況を確認するなど、セキュリティ対策が万全であるかを厳しくチェックする必要があります。
また、契約時には必ず秘密保持契約(NDA)を締結し、情報の取り扱いに関するルールを明確に定めておくことが不可欠です。
外部の委託先がスムーズに業務を開始できるようにするためには、事前の準備が欠かせません。
現在、社内でどのように業務が行われているのか、そのフローを整理・可視化し、誰が見ても理解できるような詳細なマニュアルを作成する必要があります。
特に、業務が属人化している場合、担当者へのヒアリングや散在する資料の整理に多くの時間と手間がかかることがあります。
この準備工数を甘く見積もっていると、導入がスムーズに進まない原因となります。
この業務の可視化と標準化のプロセスは、結果的に社内の属人化を解消し、業務効率化につながるという側面も持ち合わせています。

間接業務の外注先を選ぶ際に失敗しないためのポイントをお教えします。
間接業務のアウトソーシングを成功させるためには、自社の課題や目的に合った最適なパートナーを選ぶことが極めて重要です。
数多くのサービスの中から、何を基準に比較・検討すればよいのでしょうか。
ここでは、外注先の選定で失敗しないために、必ず確認しておきたい4つの比較ポイントを解説します。
アウトソーシングサービスは、提供会社によって対応できる業務の範囲や得意分野が異なります。
経理業務に特化したサービス、人事労務全般をカバーするサービス、幅広いバックオフィス業務に柔軟に対応できるサービスなど様々です。
まずは、自社がどの業務を、どの程度のレベルまで依頼したいのかを明確にすることが重要です。
その上で、候補となる企業のサービス内容を比較し、自社の要望に過不足なく対応できるかを確認します。
将来的に委託範囲を拡大する可能性がある場合は、拡張性や柔軟性も考慮して選定すると良いでしょう。
機密情報を外部に預ける以上、委託先のセキュリティ体制は最も重要な選定基準の一つです。
情報漏洩などのインシデントが発生すれば、企業の存続に関わる重大な問題に発展しかねません。
具体的な確認ポイントとしては、プライバシーマーク(Pマーク)やISMS(ISO27001)といった第三者認証を取得しているかどうかが一つの指標となります。
また、データの取り扱いルール、アクセス制限、従業員へのセキュリティ教育の実施状況などを具体的にヒアリングし、信頼できる管理体制が構築されているかを確認する必要があります。
契約前の段階で、セキュリティに関する質問に明確に回答してくれる企業を選びましょう。
アウトソーシングの料金体系は、月額固定制、業務量に応じた従量課金制、プロジェクト単位での一括見積もりなど、サービスによって様々です。
コスト削減を目的とする場合、料金の安さだけで選びがちですが、サービス内容と料金が見合っているかを慎重に判断する必要があります。
基本料金に含まれる業務範囲はどこまでで、どのような場合にオプション料金や追加費用が発生するのかを契約前に必ず確認しましょう。
料金体系が不明確な場合、後から想定外の費用を請求されるトラブルにつながる可能性があります。
複数の企業から見積もりを取り、内訳を詳細に比較検討することが失敗しないためのポイントです。
これまでの導入実績や具体的な成功事例は、その企業のサービス品質や信頼性を測る上で重要な指標となります。
特に、自社と同じ業界や事業規模の企業での導入事例があるかどうかを確認しましょう。
同様の課題を抱えていた企業がどのようにアウトソーシングを活用して成果を出したかを知ることで、自社に導入した際の具体的なイメージが湧きやすくなります。
公式サイトに掲載されている導入事例を読み込むだけでなく、可能であれば担当者から直接、類似ケースでの支援実績について詳しく話を聞くことも有効です。
豊富な実績は、様々な状況に対応できるノウハウが蓄積されている証でもあります。

間接業務の外注で生産性を向上させた成功例を見ていきましょう。
間接業務の外注を具体的にイメージするために、ここでは実際にアウトソーシングを導入し、生産性向上を実現した企業の成功事例を3つ紹介します。
経理、採用、営業事務といった異なる分野で、どのような課題を抱え、アウトソーシングによっていかにして解決に至ったのか、具体的な成果とともに見ていきましょう。
ある中小企業では、経理担当者1名が日常業務に追われ、月次決算の資料作成が翌月の中旬以降になるのが常態化していました。
これにより、経営陣が会社の財務状況をタイムリーに把握できず、迅速な意思決定の妨げとなっていました。
そこで、請求書発行や記帳代行、支払管理といった日常的な経理業務を専門のアウトソーシングサービスに委託しました。
その結果、経理担当者は月次決算業務に集中できるようになり、決算報告が5営業日以内に完了するまでに短縮されました。
経営陣は迅速に業績を把握し、的確な経営判断を下せるようになりました。
事業拡大に伴い、採用人数を大幅に増やす必要があったIT企業では、人事担当者が膨大な数の応募者対応や面接の日程調整に追われ、本来注力すべき候補者の見極めや採用戦略の立案に時間を割けないという課題を抱えていました。
そこで、採用代行(RPO)サービスを導入し、母集団形成から応募者との連絡、面接調整までを委託しました。
これにより、人事担当者の事務的な作業負担が大幅に軽減され、候補者との面接や内定者フォロー、採用ブランディングといったコア業務に集中できる環境が整いました。
結果として、採用活動全体の効率と質が向上し、優秀な人材の獲得に成功しました。
営業担当者が顧客リストの作成、見積書や請求書の作成といった事務作業に多くの時間を費やしており、本来の目的である顧客訪問や商談の時間が十分に確保できていないという課題がありました。
そこで、オンラインアシスタントサービスを活用し、これらの営業事務作業を全面的に委託することにしました。
営業担当者は外出先からスマートフォンで依頼するだけで、必要な書類が作成され、顧客データが更新される仕組みを構築しました。
その結果、営業担当者一人ひとりが1日に平均2時間以上、コア業務に使える時間が増加し、顧客との関係構築に集中できるようになったことで、チーム全体の売上が前年比で120%向上しました。

間接業務のアウトソーシングは、ノンコア業務を外部の専門家に委託することで、自社のリソースを売上に直結するコア業務へ集中させるための有効な経営戦略です。
これにより、コスト削減や業務品質の向上といったメリットも期待できます。
ただし、社内にノウハウが蓄積されにくい、情報漏洩のリスクがあるといったデメリットも存在するため、導入には慎重な検討が求められます。
成功のためには、まず自社が抱える課題を明確にし、依頼したい業務範囲を定めた上で、セキュリティ体制や実績などを比較し、信頼できるパートナーを選定することが不可欠です。
本記事で解説したポイントを参考に、自社に合ったアウトソーシングの活用を検討してください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」