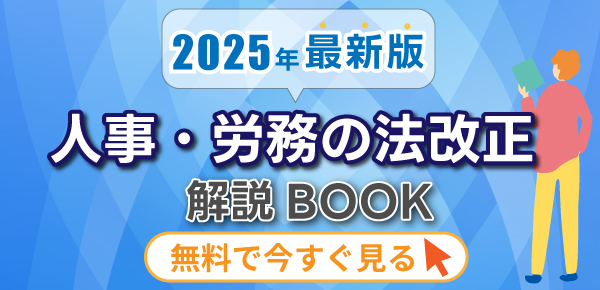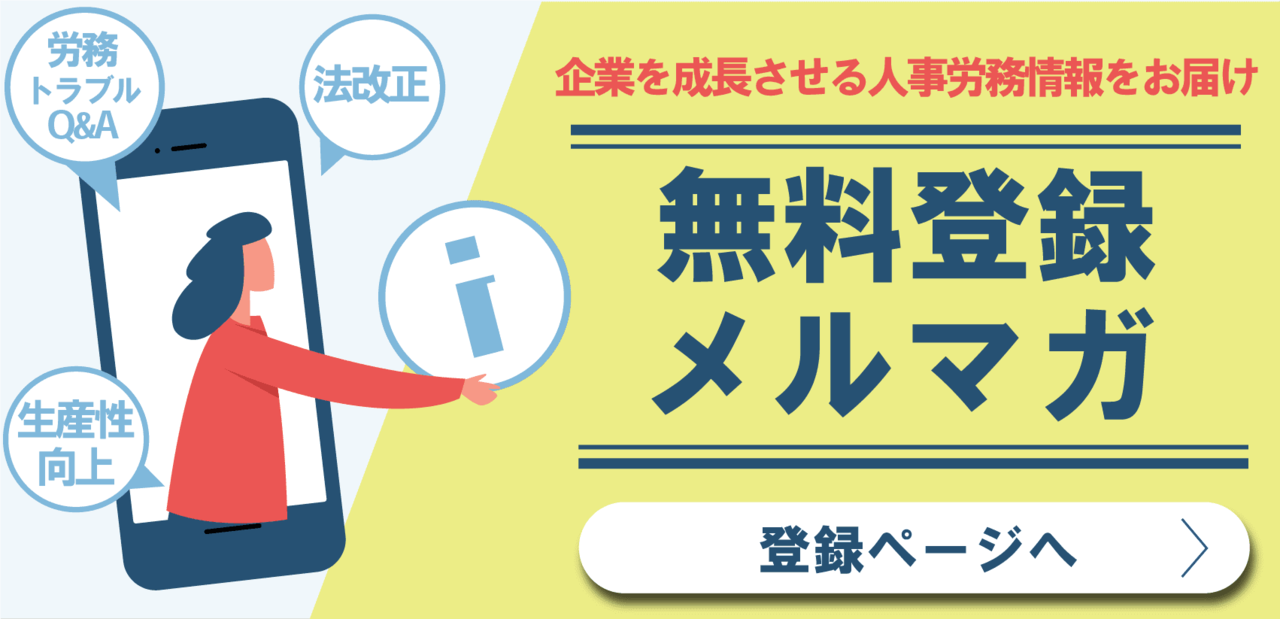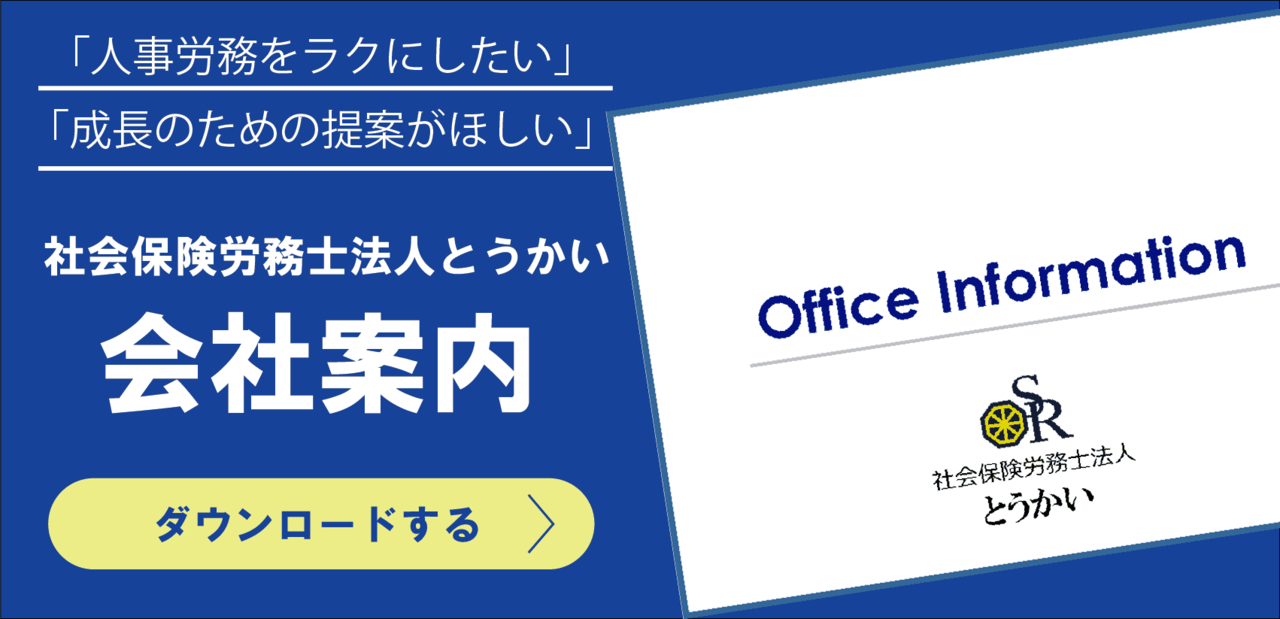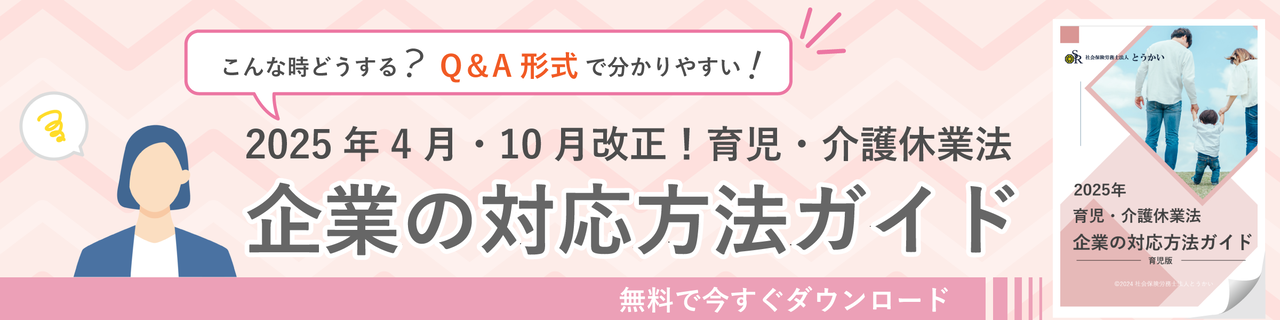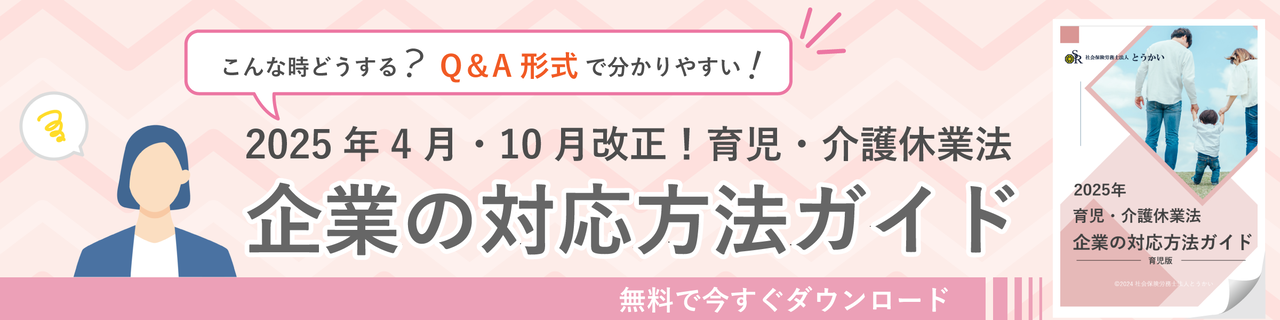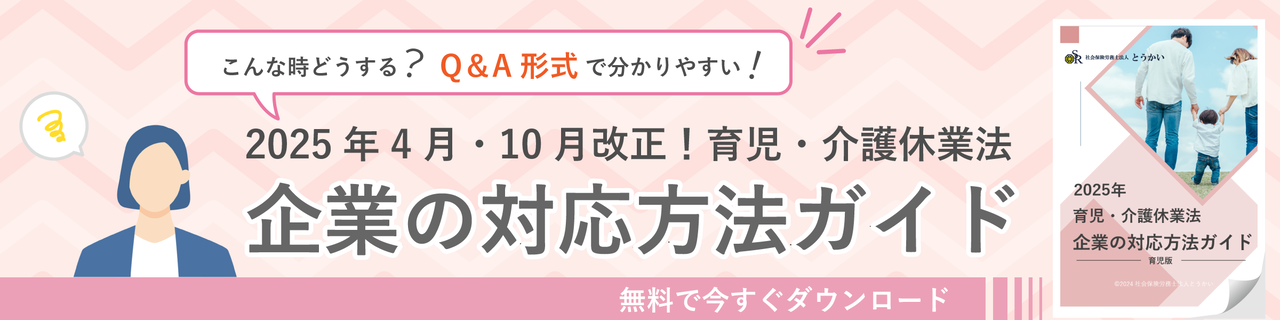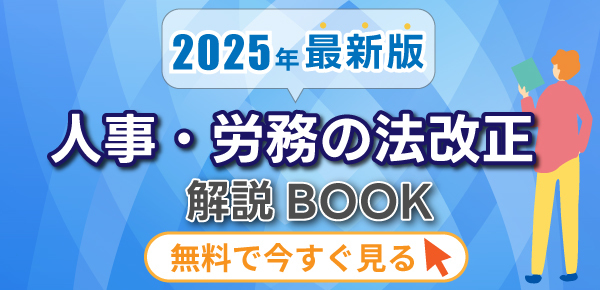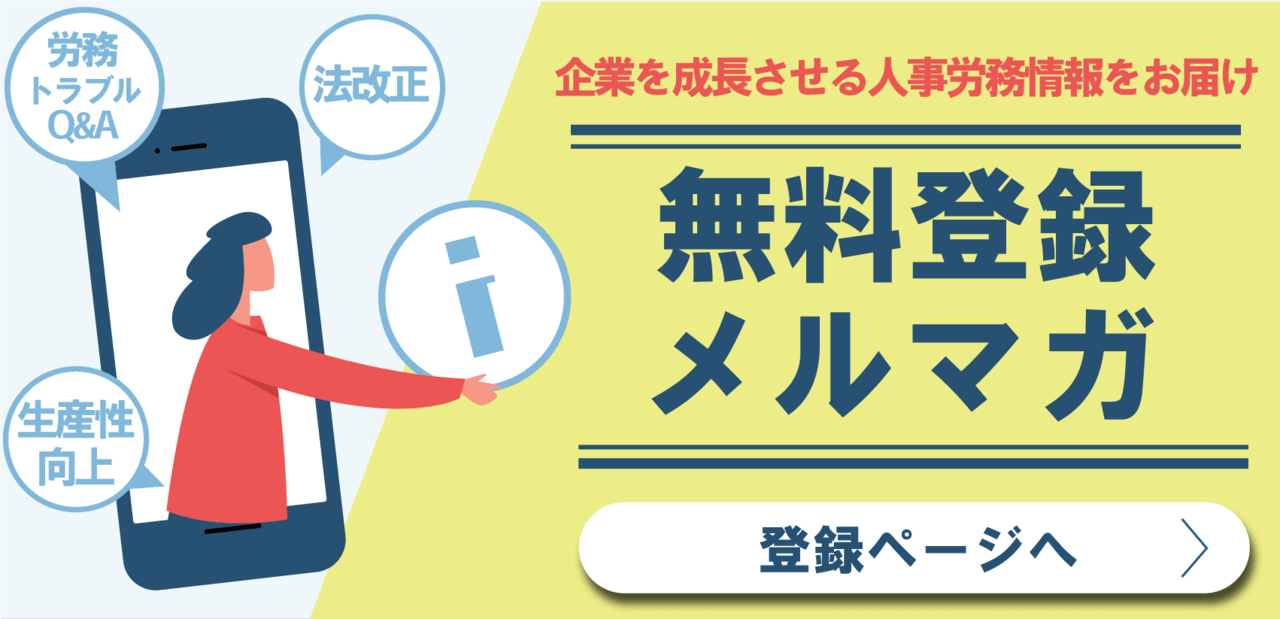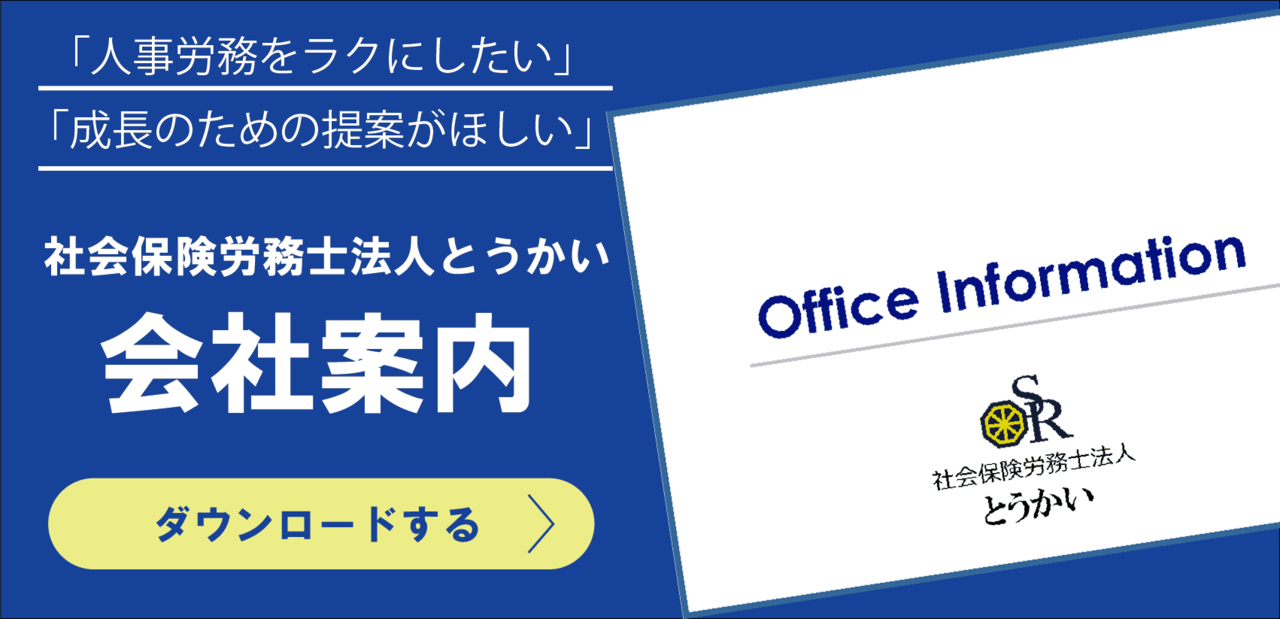「106万円の壁」撤廃…社会保険料負担の要件はどうなる?

「106万円の壁」の廃止に関する議論は、パートやアルバイトをはじめ、働く人々にとって非常に関心の高いテーマです。いわゆる年収の壁と言われるものは、103万円、106万円、130万円と、年収に応じて所得税、社会保険料の取扱いが異なります。今回は、年収106万円の壁にフォーカスします。
これまで、年収が106万円を超えると社会保険料の負担が発生し、結果として手取り収入が減少する可能性があることが課題とされてきました。そのため、多くの人々が「106万円の壁」を意識しながら勤務時間や労働条件を調整してきたのが現状です。
この「106万円の壁」が、2026年10月を目処に撤廃されることになります。ただ、「106万円の壁」の廃止によって、労働環境や収入面での選択肢が広がる可能性がある一方、手取り収入が増加するのか、減少するのか、新たな問題や課題が生まれることも懸念されています。
年収が106万円を超えた場合の手取り収入や社会保険料負担が具体的にどうなるのかについて、今後の制度の動きに、注目しておく必要があるでしょう。
目次
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

改正の背景と目的を詳しく解説します。
「106万円の壁」とは、年収が106万円を超えた場合に、厚生年金保険や健康保険の社会保険料を負担する必要が生じることから表現されています。「106万円の壁」は、特にパートやアルバイト、主婦(主夫)の方々が、一定の収入の範囲内で働くことで、社会保険料の負担をしなくともよいというルールになっています。ただ、短時間で働く人たちにとっては、昨今の最低賃金の上昇、勤務先の人手不足などにより、週20時間程度勤務すると、年収106万円を上回ってしまうケースが多く見られるようになりました。短時間労働で得られる収入が増えても、社会保険料の負担によって手取り額が減少することから働き控えをする人もおり、働く意欲を損ねる側面が課題となっています。
最近ではこの「106万円の壁」を巡る議論が活発化しており、改正の動きも見られます。この仕組みの見直しには、雇用状況や労働環境の変化に対応し、働く人々への負担を軽減しつつ、誰もが公平に社会保障を享受できるようにする目的があります。
「106万円の壁」とは、従業員51人以上の企業で1週間に20時間以上働き、年収が106万円以上となった際に、社会保険の加入義務が発生します。社会保険に加入することになる結果、給与から社会保険料が天引きされるため、手取り額が減少する場合があります。ただし、「106万円の壁」は、一定の収入ラインを超えることで、社会保険料負担が増える一方で、厚生年金への加入で将来的な年金受給額が増える可能性がある点にも忘れてはならないでしょう。そのため、一長一短の側面があり、自身の働き方や年収を選択する際に重要な判断材料となるでしょう。
今回の改正の目的は、主にパートやアルバイトなど短時間労働で働く人の待遇改善を図ることにあります。最低賃金が上昇する中、週20時間以上働く人々は、年収106万円以上となってしまうケースが多く、社会保険料の負担が生じることで、働き控えを引き起こす要因となっています。厚生労働省は、この改正を通じて新たに470万人が厚生年金に加入できる環境を整えることを目標としており、制度の抜本的な見直しを進めています。この取り組みによって、働く意欲の向上や制度利用の増加が期待され、さらに結果として手取り収入が増加する可能性もあります。この改正の目的は、働き手の安心を支え、労働市場の活性化へと繋げることにあります。

高谷の経営視点のアドバイス
年収106万円の壁は撤廃されても、週20時間以上の労働時間の壁については、以前残ったままです。労働時間の壁があるがゆえ、労働時間を増やさずに社会保険への加入を避ける動きには、対応できないままです。これは今後の課題となるでしょう。
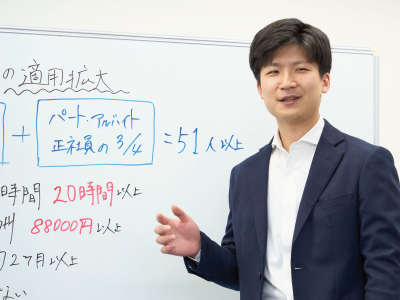
具体的なスケジュールを見ていきましょう。
年収「106万円の壁」の撤廃とあわせて、厚生年金の負担変更についての具体的なスケジュールが明らかになりつつあります。年収「106万円の壁」の撤廃は、2026年10月から想定されています。
社会保険の加入義務は、年収106万円のみならず、勤務先の企業規模(従業員51名以上)、週20時間以上勤務するといった3要件がありますが、2027年10月には、企業規模要件の撤廃も想定されています。したがって、年収や企業規模に関わらず、週に20時間以上勤務すると、厚生年金に加入が義務となるというわけです。この改正は、パートやアルバイトなど非正規雇用の方々にも影響を与える大きな変更となります。この制度改正により、厚生年金の加入条件が見直され、現在よりも幅広い人々が対象となります。これまで厚生年金の対象外であった多くの労働者が新たに加入することが可能となり、その結果として社会保険料の負担が発生します。
したがって、年収や社会保険料によっては、手取り収入が減る人もいるというわけです。一方で、厚生年金に加入することで、将来の年金額が増額されるといったメリットもあります。この改正の目的の一つは、パートやアルバイトといった非正規雇用の方々にも厚生年金加入を促し、将来の生活保障を強化することにあります。しかしながら、当面の手取り額の減少に抵抗感を示す人がいるのも現実です。そこで、現在、企業と従業員で折半することになっている社会保険料の負担割合を変更する特例案もしめされています。
ただし、具体的なスケジュールや「いつから」どのような変更が適用されるのかについては、雇用形態や条件によって異なる部分があるため、詳細については引き続き注目しておく必要があるでしょう。

大矢の経営視点のアドバイス
(現時点での厚生年金加入案)
2026年4月:会社が社会保険料の肩代わりが可能<手取り収入の減少を抑えるため>
2026年10月:年収106万円の壁を撤廃
2027年10月:企業規模要件を撤廃
2029年10月:5人以上の個人事業主も対象に加わる

社会保険料に与える影響をチェックしましょう。
年収に関する「壁」と呼ばれる制度は、今回注目した106万円のほかにも、103万円、130万円など、年収に応じたルールがあり、影響する制度、対象者も異なりますので、理解しておく必要があります。働く人たちの手取り収入や税金負担、社会保険料に大きな影響を与える重要なポイントです。なかでも「103万円の壁」と「130万円の壁」は、働き方を検討する上でぜひ把握しておきましょう。
「103万円」と「130万円」の壁は、同じ「壁」であっても所得税に対する年収の壁、社会保険に対する年収の壁というように、それぞれ目的となる制度が異なります。例えば年収103万円を超えると、配偶者控除や扶養控除といった優遇措置が利用できなくなる可能性があります。そのため世帯の税負担が増加する可能性があります。そのため、特に配偶者の扶養内で収入を保ちながら働きたいと考える人々は、この基準を超えないように勤務時間などを調整していることでしょう。
一方、130万円を超える場合には、社会保険への加入義務が発生します。社会保険への加入義務が生じるのは、106万円のケースも該当します。ただ、年収106万円で社会保険加入義務が発生するのは、企業規模が従業員51人以上の場合です。企業規模が従業員50人以下の勤務先の場合には、年収130万円を超えると加入義務が発生するのです。社会保険料が給与から天引きされ、収入が増えたとしても実際の手取りが減少するケースがあるため注意が必要です。この130万円の壁は、税金に加えて社会保険料の負担も考慮しなければならないため、働き方を考える際の重要な基準となります。
「103万円」と「130万円」の違いや関係性を理解し、それぞれの条件を踏まえた収入計画を立てることが、効率的な家計管理や働き方の見直しに繋がります。
106万円年収の壁の撤廃により、社会保険の加入義務が生じるため、社会保険料負担が新たに発生し、手取り額の減少リスクがあります。アルバイトやパート収入が年収の壁を超えた場合、扶養控除を受けることができなくなる可能性もあります。とくに主婦(主夫)の立場で働く方は、一定の年収を超えると扶養から外れることで、配偶者の税負担が増加するリスクが生じるため、慎重な収入管理が求められます。パートやアルバイトといった非正規雇用で働く人々は、総収入が増えたとしても、社会保険料負担などの増加によって最終的な手取りが減少します。改正内容を正しく理解し、収入の増減が家計全体に与える影響を十分に考慮し、週の勤務時間や月ごとの労働日数など自分の状況に合わせた将来的な収入計画を立てることが重要です。途中に変更が発生した場合には、その影響を正確に理解し、柔軟に働き方を見直す姿勢が必要となります。
扶養の基準が変更されるタイミングについては注意が必要です。一般的に年収が103万円を超えると、扶養から外れることになり、配偶者控除や扶養控除が適用されなくなります。この場合の扶養を判断する基準日は、12月31日時点となります。一方で、社会保険の場合には、12月31日でなくとも、週20時間以上勤務している場合には社会保険に加入されることになります。このような基準の変化が「いつから」適用されるのかを正確に把握し、自分の状況に適した対応を見極めておくことが大切です。
また、今後の法改正によって扶養の基準が見直される場合も考えられるため、最新の情報に常に注意を払うべきでしょう。

小栗の経営視点のアドバイス
年収の壁といっても、103万、106万、130万円と色々と議論されており、混乱してしまうとの声もよく聞かれます。ここ最近は、年収の壁の引き上げ議論も白熱しています。家族を扶養している人、扶養されている人、双方に非常に重要な知識ですので、最新の情報をキャッチしながら、自分と家族にとって、ベストな選択ができるよう、注目していきましょう。

「106万円の壁」撤廃で考慮すべき重要ポイントをみていきましょう。
「106万円の壁」の廃止は、多くのパートやアルバイトで働く方にとって、経済的な選択肢や働き方に新たな影響をもたらす重要な改正です。この制度改正により、年収が106万円を超えた場合でも、厚生年金や健康保険への加入が義務化される対象が拡大され、社会保険に加入できる人々の範囲が広がることになります。その結果、より多くの方が社会保険の恩恵を受けることが可能となり、将来的に受け取れる年金額の増加や医療保障の充実といったメリットが期待できます。
一方で、「106万円の壁」廃止に伴い、厚生年金や健康保険へ加入する際には保険料の負担も発生します。そのため、加入後に想定される手取り収入の減少について注意が必要です。短期的には収入が減少する場合もあるため、現在の生活水準や家計への影響を事前にしっかりと把握し、対応策を検討することが大切です。また、保険加入によって得られる将来的な金銭的利益と現在のコストを比較し、十分な理解を持って判断することが求められます。
このように、「106万円の壁」の廃止は労働者にとって重要な分岐点となり得ます。特に多様な働き方が広がりを見せる現代において、この改正を契機にご自身の働き方や収入の見直しを行い、将来の安定に向けた計画を立てることが必要不可欠です。
厚生労働省は、「106万円の壁」撤廃に伴い、新たな制度の整備を進めています。この取り組みによって、非正規雇用者が厚生年金や健康保険へスムーズに加入できるようになることが期待され、労働環境の改善や雇用の安定化につながるとされています。特に、深刻な人手不足が課題となっている現状において、この制度改革は労働市場へ重要な影響を及ぼすと考えられています。
一方で、制度の導入には慎重な運用が求められます。多くの企業は社会保険料の負担増加に直面する可能性があるため、採用や雇用拡大への意欲低下が懸念されています。そのため、企業が新たな追加負担に適応できるよう支援策を講じることが不可欠です。また、この制度の影響を最大化するためには、企業と労働者の双方が適切に情報を共有し、互いの立場や状況を理解する努力が求められます。そうした相互理解が進むことで、労働市場全体の活性化が期待されます。
厚生労働省が打ち出す新制度は、単なる規制緩和ではなく、働き方の選択肢や生活の安定を広げる重要な施策として社会に広がっていくことでしょう。
今後の社会保険制度に関しては、さまざまな期待と課題の両方があります。特に、106万円の壁が撤廃は、社会保険加入者の増加が予測され、それが社会保険制度の持続可能性を支えるとも言われています。加入者の増加は、制度全体の安定性を高める重要な要素となる一方で、社会保険料の負担増加や給付の質の維持といった新たな課題にも直面することが予想されます。
さらに、年金制度についての将来的な不安も依然として解消できる状況にはありません。持続可能な社会保険制度の構築には、全ての加入者が適正な社会保険料を負担することが必須であり、働き方の選択に対しても、適切な情報を基にした判断が求められます。厚生年金を含む社会保険制度全般の安定を確保するためには、社会全体で負担を分担し、長期的な視点からの議論が欠かせません。
今後は、変化し続ける社会や雇用環境に適応しながら、社会保険制度をより効率的かつ公平に運営するための柔軟な対応が求められるでしょう。引き続き、社会保険に対する理解を深め、その重要性を再認識することで、誰もが安心して生活を送れる制度の実現を目指す必要があります。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
厚生労働省は、「106万円の壁」撤廃の法案について、2025年1月から始まる通常国会に提出する予定です。年収の壁撤廃による社会保険加入者の拡大と併せ、将来の年金財源確保の観点から、収入の多い厚生年金加入者への保険料負担引き上げの方針も示されています。今後の動きに注目しておく必要があるでしょう。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」