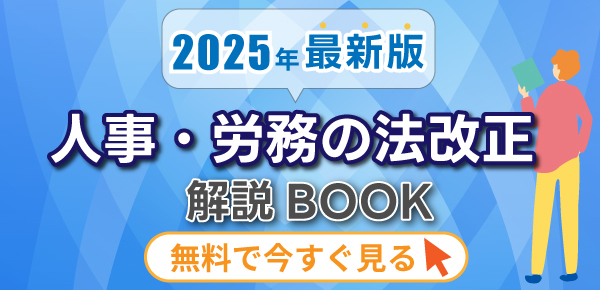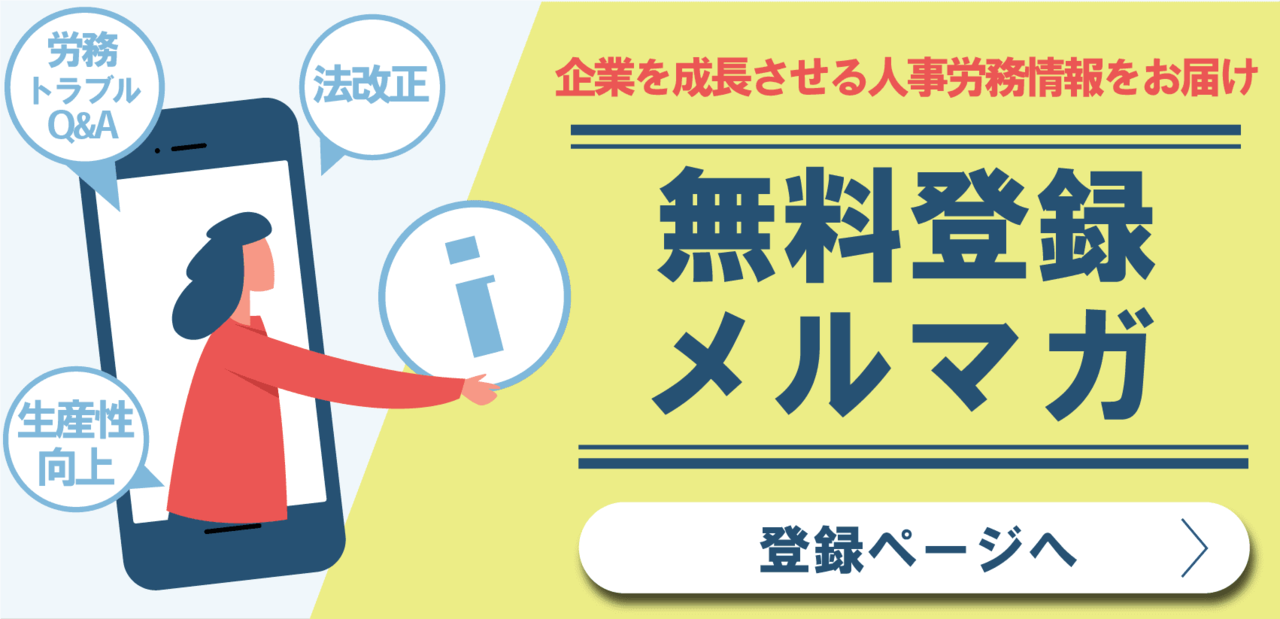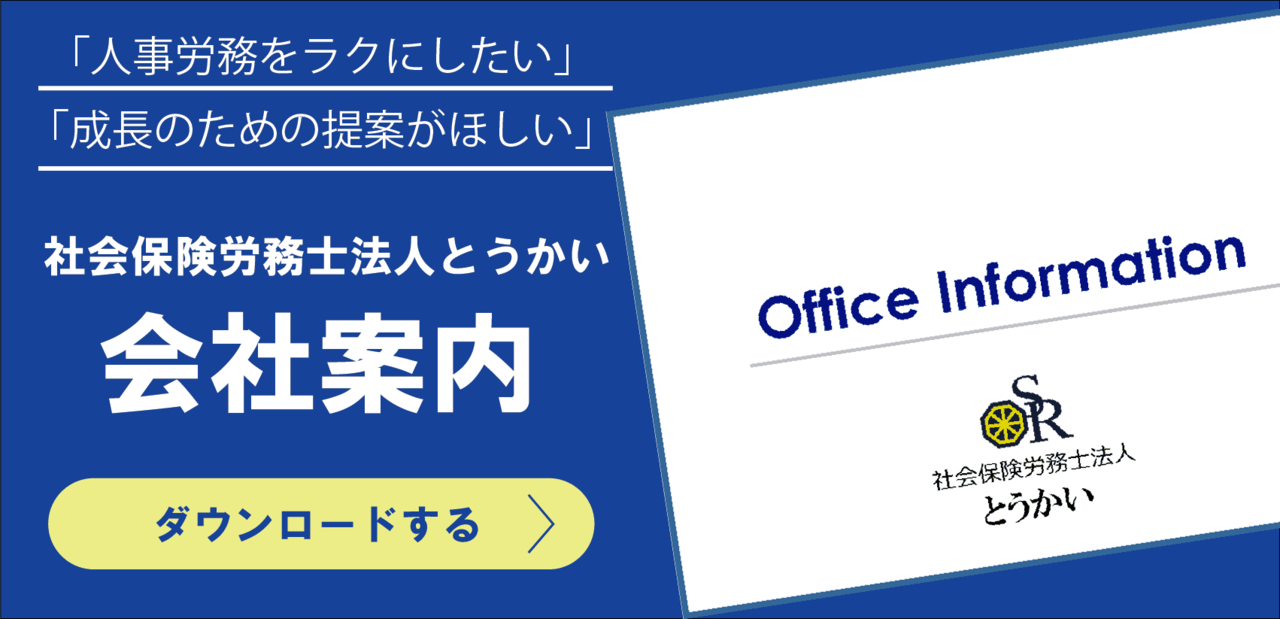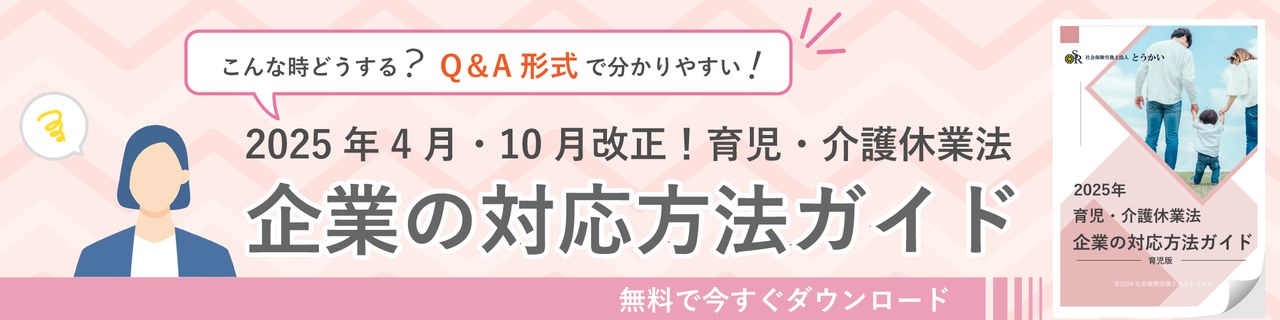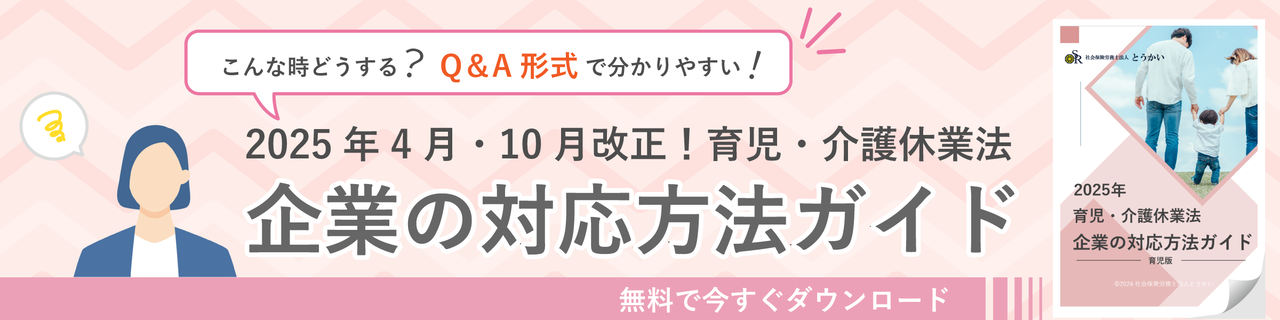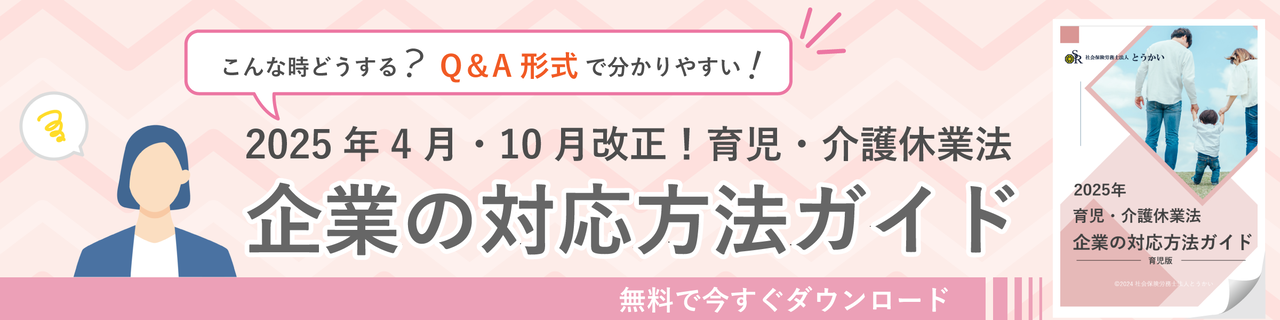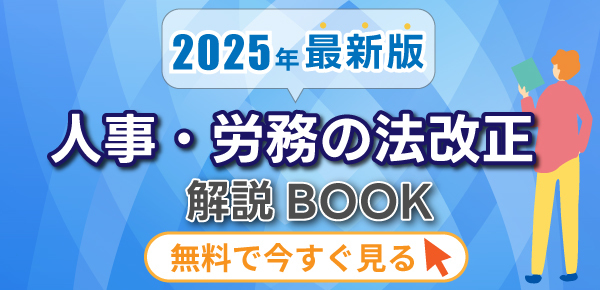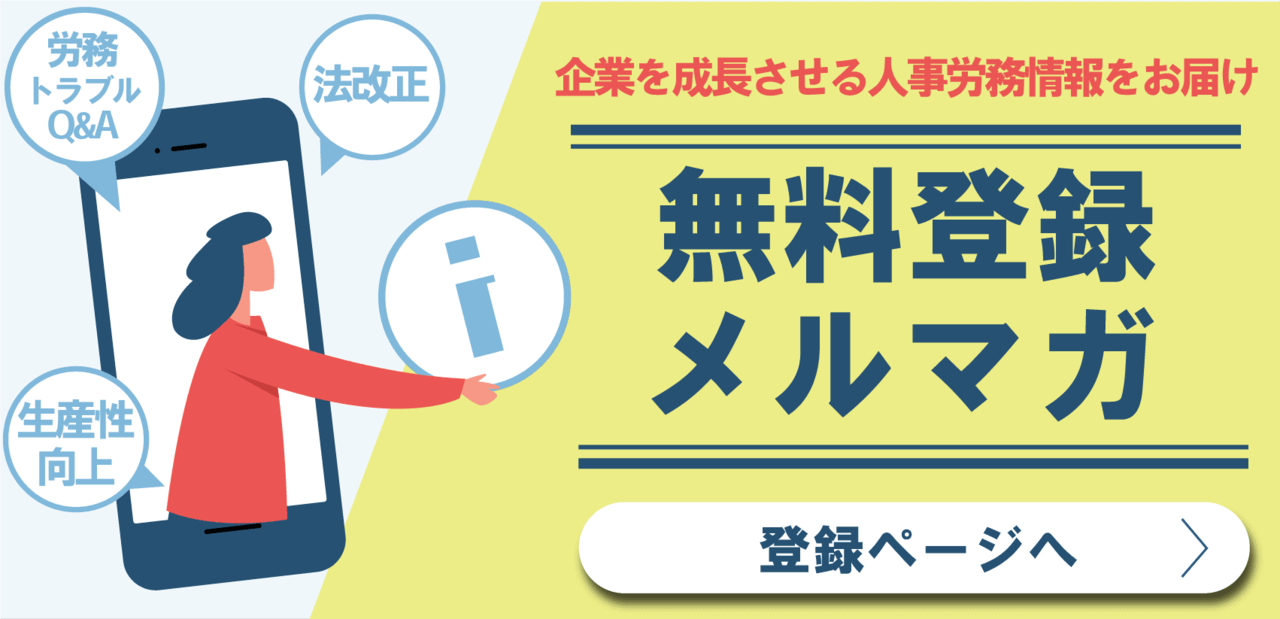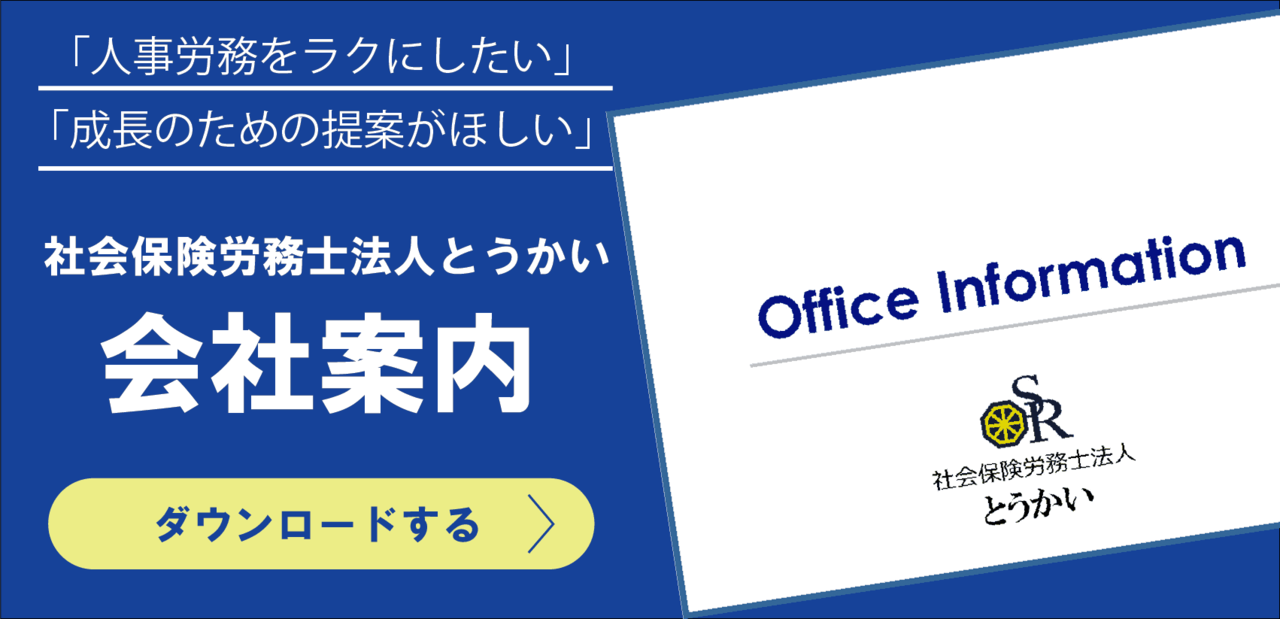解雇規制の緩和で企業にどんな影響が?
現行規制とそのメリット・デメリットを徹底解説

解雇規制の緩和は、企業にどんな影響をもたらすでしょうか。昨年行われた自民党総裁戦では解雇規制緩和、解雇の自由化などの言葉が沸きました。言葉の捉え方によっては、企業が従業員を切り捨てるとも捉えられますが、これまで本質的な議論が進んでこなかったことも事実です。現行の制約の厳しい解雇要件について、時代に合わせた見直し、社会の人材の流動を促すことで、より良い人材戦略を策定できる鍵となり得るかもしれません。
解雇規制の見直しは、企業にとってのメリットとデメリットの両面を理解することで、企業経営者や人事担当者は、規制緩和の影響を的確に捉えた上で、適切な施策を講じることが求められます。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

解雇規制の緩和とは何か?詳しく解説します。
解雇規制の緩和とは、企業が従業員を解雇する際の規制を緩和することを指します。日本では、労働市場の活性化が求められる中で、各企業が迅速に人員を調整し、競争力を維持するための手段として解雇規制の見直しが議論されています。解雇規制緩和により、雇用の流動化、特に経済変動に柔軟に対応できる体制が整うことが期待されています。そのため、現行の厳しい解雇規制を見直し、スタッフのスムーズな入れ替えを可能にし、企業のフレキシビリティを高めることが求められています。
解雇規制を緩和する動きが注目される背景には、さまざまな社会経済的な要因があります。日本の労働市場は高齢化や少子化が進行しており、企業が労働力を確保することが一層難しくなっています。そのため、新しい雇用の流動化を促進する必要が高まっていると言えます。
また、国際競争が激化する中で、日本企業も常に変化する市場に適応するためのアプローチを模索しています。解雇規制を緩和することで、企業は迅速に人員を見直し、必要に応じて新たな才能を迎え入れることが可能になります。これが企業の成長戦略において、極めて重要な局面となるでしょう。
現在の解雇規制には、労働法のもと、整理解雇に関する4要件を定めています。この4要件に該当することで、企業が人員削減を行うことが可能となります。具体的には、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力の有無、③解雇対象者となる人選の合理性、④手続きの妥当性が求められます。
企業はこれに則って解雇を行う必要があります。従業員に対して解雇を通告する際は、少なくとも30日前に解雇の予告し、解雇の予告を行わない場合は、解雇と同時に30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。解雇は従業員の生活に大きな影響を及ぼすものですので、解雇4要件に該当し、相応の手続きをしっかり踏まないと、後々、労務トラブル、訴訟など難しい状況に直面することもあります。特に経営課題や人員整理を行う際、この点をクリアすることが極めて重要です。

整理解雇の4要件とその重要性を見ていきましょう。
整理解雇に際しては、整理解雇法理として4要件があります。これらの要件は、企業が従業員を整理解雇する際に遵守すべきルールであり、企業側の権利と労働者の保護のバランスを保つための基盤です。4要件を遵守することによって、企業側は法律的なリスクを軽減し、労働者とのトラブルを最小限に抑えることになります。したがって、解雇に際してはこの要件が特に注視され、企業が責任を果たす重要性が認識されています。
現在の日本において、経済状況の厳しさや技術革新が進むことで、企業によっては人員削減の必要性を感じているかもしれません。とくに、業績不振や事業の再構築においては、賃金と人員のリバランスが求められます。人員削減は、短期的には痛みを伴うものですが、長期的には企業全体の健全性を保ち、競争力を向上させる措置として必要不可欠です。解雇規制緩和の議論が高まる中で、企業はどのように4要件を満たしながら、事業を運営していくか工夫が求められています。4要件のうちの一つとして、人員削減の必要性を明確に打ち出せるかは重要です。
4要件のうち、2つ目は企業が解雇を行う際に、解雇回避の努力がされていることが必要です。日本においては特に、社会的な責任からも労働者を守る必要があります。解雇は最終手段であるため、例えば、他の部署への異動や他業務への転換が可能かどうかや、賃金カットのような代替案も検討されるべきです。解雇回避の努力は、労働者に対する配慮を示し、企業としての健全な姿でしょう。
企業が整理解雇を行う際には、人員選定に合理性が求められます。合理的な基準に基づいて、賃金や業務能力、勤務態度の評価が行われなければなりません。このプロセスは、整理解雇における公平性を確保するための重要なステップです。適切な基準を設けることで、解雇が不当でないことを証明でき、法的な問題が発生するリスクを低減します。
整理解雇を実施するにあたっては、4要件を踏まえた上で適正に解雇手続きが実施されなくてはなりません。法律に則った対応により、企業と労働者の間での公平性を保ちます。整理解雇の必要性や実施時期、方法など、しっかりと協議していく必要があるでしょう。手続きが整っていない場合、企業は法的なトラブルに直面する危険性が高まるため、十分な注意が必要となります。解雇手続きが適正であれば、従業員も納得しやすくなります。効果的な整理解雇を実現するためには、これらの手続きを円滑に進めることが不可欠です。

大矢の経営視点のアドバイス
2024年の総裁選時に大きな話題となった「解雇規制の緩和」。企業側、従業員側共に、注目すべき政策・争点だったのではないでしょうか? 日本の解雇規制は諸外国よりも厳しいとの意見も多いですが、米国と比べれば厳しいというのが実態で、必ずしも日本が特出して解雇規制が厳しいというわけではありません。
ただ、昨今の日本を取り巻く経営環境が大きく変化してきたなか、雇用・労働環境についても人材の流動をより活性化しなければ、国際社会での競争に勝てないといった見方もあります。そうした背景が解雇規制の緩和の議論にもつながっているのでしょう。

解雇規制緩和のメリットを確認しましょう。
解雇規制の緩和は、雇用の流動化が促進されるなど、企業にさまざまなメリットをもたらすと言われています。企業は人材を注力したい業務に人員を適正な配置したり、新たな人材の獲得なども円滑に行えると期待されています。これらの点から、解雇規制の見直しは企業経営にとって重要な論点です。
解雇規制が緩和されることで、雇用の流動化が進み、人材採用ハードルが低くなると想定されます。人材獲得競争が厳しい企業にとって、大きな柔軟性をもたらすでしょう。新たな人材を採用する際のリスクが軽減されることで、企業はより多くの選択肢を持つことになります。とくに急成長しているスタートアップ企業や新規事業に取り組む企業にとって、適切な人材を迅速に獲得できることは戦略的に重要です。雇用の流動化が進むことで、必要に応じてスピーディに人員を入れ替えたり、育成したりすることが可能となり、業務の迅速な展開が期待されます。
解雇規制を緩和することで、業務の能力や適性、会社のルールなどについて不適合な従業員への対応が容易になります。企業は業績や成果を基に従業員を評価し、適切な賃金を支払うことが求められます。しかしながら、従業員の業績が期待に応えない場合や、組織文化に適さない場合に対する対応が、緩和された規制により円滑に行えるようになります。問題のある従業員ついて適切に退出を促すことが可能になり、チーム全体のパフォーマンス向上が期待されます。企業がフォーカスすべきは、パフォーマンスや業務遂行能力に基づいた合理的な判断です。
解雇規制の緩和は、日本企業の競争力を高め、生産性の向上に寄与すると考えられています。人材の流動性が向上することで、企業においては業務に適した人材を確保しやすくなり、市場のニーズに応じた組織体制へと変化できます。また、企業が必要な人材を獲得しやすい環境は、イノベーションを促進し、より生産的な業務運営に繋がることでしょう。これまで以上にダイナミックな経営環境を実現し、国際市場での競争でも優位に立つ可能性が高まります。

鶴見の経営視点のアドバイス
解雇規制の緩和は、企業にとっては経営の柔軟性をもたらうとして、賛同する経営者も多いでしょう。ただ、緩和されていく方向であっても、やみくもに解雇が可能となるわけではありません。まずは、現行の解雇規制のルールをしっかり理解しておくべきでしょう。労働法に詳しい社労士などにご相談いただければ、適切なアドバイスが受けられるはずです。

解雇規制緩和のデメリットを確認しましょう。
解雇規制の緩和は企業に様々なメリットをもたらすと考えられる一方で、デメリットにも注目しなくてはなりません。とくに、“解雇がしやすい”ということのみが一人歩きすれば、従業員が雇用への不安感を抱くことにもつながります。従業員が将来的に解雇されるリスクを感じることで、長期的な業務へのコミットメントが減少し、生産性が低下する恐れも懸念されています。そのため、企業は解雇制度を見直す際に、透明性のある評価制度や適切な人材育成策を用意することが重要です。
解雇規制の緩和により、従業員が雇用への不安感を抱くこともあるでしょう。従業員が不安を抱えた状況で、業務に集中できず、パフォーマンスの向上が望めないとなれば、生産性低下を招くことになります。これは企業にとって重大なデメリットとなる場合があります。特に、安定した職場環境が重要な業種においては、労働者のメンタルヘルスへの影響が組織全体の生産性に直結します。
解雇のリスクが高まることで、新しいアイデアやイノベーション提案への影響も注意しなければなりません。従業員が解雇を恐れるあまり、リスクを取った発言を避けるようになると、企業としての成長が停滞する要因となりかねません。従業員と企業との信頼関係、エンゲージメントに影響を及ぼすことも否定できません。従業員が抱える不安感は、組織全体の士気に影響を与えることもあるのです。
解雇規制が緩和されると、新たに人材への教育コストが発生する可能性も指摘されています。従業員の雇用が不安定であると、企業は適切なスキルを持つ人材を育成することに対して消極的になりかねません。特に日本の企業文化においては、長期的な教育投資が求められるため、短期的な視点に偏るリスクもあるでしょう。教育や研修に対する投資が不足することで、結果的に即戦力の人材が育ちにくくなり、企業全体の能力が低下することも考えられます。新たなニーズに応じたスキルを持つ人材を補充するために、短期間での再教育や新たな採用を急ぐ必要が出てくるため、これが教育コストを加算する要因になるのです。また、解雇が容易になることで、人材育成に対する企業の関心が薄れる場合があります。
解雇規制の緩和は、派遣労働者へのデメリットにも注目すべきでしょう。派遣労働者は本来、柔軟性を持った働き方ができるため、自由度の高い雇用形態の一環として利用されてきました。しかし、解雇規制の緩和により、派遣労働者にも不安と不安定さが広がることが心配されています。派遣労働者は長く勤めている場合も多く、解雇が容易になることで、彼らのキャリア形成にも影響が出るでしょう。一方で、派遣会社も新たな雇用戦略を求められる中で、より厳しい条件での雇用契約を提示するようになれば、立場が不利になることが考えられます。これにより、派遣労働者の待遇や労働条件が見直されることが求められるかもしれません。

小栗の経営視点のアドバイス
とうかいでは、企業のみなさまの人事労務の問題・課題に適切なサポートを行っております。労務問題は、法律を正確に理解していなかったり、誤解していたりすると、後々大きなトラブルに発展してしまうものです。労務トラブルを事前に防ぐ、もしも発生してしまった場合でも迅速に解決できるよう、アドバイスいたします。

解雇規制の緩和による日本社会の変化も重要です。
解雇規制の緩和は、日本の雇用市場に大きな変化をもたらすことが予想されています。雇用の流動化が進むことで、労働者の職業選択の機会、幅が広がりました。企業は必要な人材を迅速に獲得・調整できるようになり、同時に労働者も自らのキャリア形成を意識しやすくなる傾向があります。転職へのハードルが低く、検討する機会が増加し、仕事へのアプローチや価値観も変化していくでしょう。この流れは、日本の労働市場がよりダイナミックかつ柔軟なものへと進化する強い兆候と言えるかもしれません。
労働市場における雇用の流動化は、長期的な影響を与えていきます。解雇規制が緩和されることで、リストラや人員調整が行いやすくなる一方で、労働者も新しいスキルを身につけたり、自己成長への意識を持つようにシフトしていくでしょう。労働市場全体の活性化が促進されることが期待されています。しかし一方で、同時に経済的不安定さを助長する側面もあります。仕事を失うリスクが高まることで、労働者は心理的なストレスを抱え、長期的なキャリアプランを立てにくい状況に陥ることも懸念されます。このような課題を克服するためには、社会全体での労働者支援や教育制度の充実が求められます。
解雇規制を緩和することによる影響は、中小企業と大企業といった企業規模によっても、大きく異なるでしょう。そもそも大企業では、解雇を行う際の手続きが体系的に整備されていることも多いため、緩和された規制に対しても比較的スムーズに対応が可能です。
一方、中小企業は生産性向上のために柔軟な人員配置や短期間での人材獲得を目指す動きが強まります。しかし、その反面、経営資源が限られているため、解雇に対する不安が高まりやすく、慎重な判断が求められます。このように、企業の規模によって解雇規制の緩和に対する対応が異なり、それぞれの特性が社会における労働市場の変化に影響を与えています。

経営者が知っておくべき施策と対応を確認しましょう。
経営者が解雇規制の緩和に伴うリスクを軽減するためには、さまざまな施策を慎重に講じることが重要です。解雇に関する4要件については、しっかりと理解し、遵守することは当然ながら、企業がクリアすべき解雇に至る正当な理由の確認、解雇回避の努力、合理的な人選、従業員との協議を行っていくことになるでしょう。従業員を解雇する前に、できる限りの配慮や選択肢を講じることで、企業は法的トラブルを避けることができます。これにより、企業の信頼が損なわれるリスクも軽減されるでしょう。
整理解雇に関する4要件を確実に満たすためには、前提として就業規則をはじめ、解雇に関する手続きに関するマニュアルをわかりやすく整備し、従業員全員に周知しておくことが求められます。従業員自身が解雇手続きについて理解し、また何が求められるのか明確にわかるようにしておくのです。さらに、実際に整理解雇を行う際には、外部の専門家である社会保険労務士や弁護士の意見を取り入れることも有効です。このような専門的な視点からのアドバイスは、リスク管理において非常に貴重な情報を提供します。解雇に関連するトラブルを未然に防ぐための環境を構築していくことが大切です。
解雇規制が見直される中で、経営者に求められるのは柔軟な企業運営です。日本においては、企業が適切に人員を調整しなければならない一方で、労働者の権利も尊重する必要があります。解雇に関する法理の理解を深め、迅速に意識を変えていくことが求められます。雇用契約や就業規則の策定も重要な施策です。信頼性を持つ企業としてのイメージを維持するためにも、変化に対する迅速な適応力が必要です。適切な情報共有とコミュニケーションを重視し、企業の成長を阻害しないよう心掛けることが求められます。

解雇規制の緩和は、日本の雇用市場に多くの変化をもたらす重要なテーマです。企業は人員の調整ができる一方で、従業員の雇用に対する不安も増加することが懸念されます。大きなメリット・デメリット両方あるため、慎重に判断していかなければなりません。解雇規制の緩和にシフトしていけば、企業側も生産性の向上や競争力の強化に向けた努力を、両輪で行っていかなければならないでしょう。リスク管理や人材育成も不可欠でしょう。とくに、中小企業においては資源が限られているため、効率的な運用が必要とされるでしょう。
今後の日本においては、労働者と企業間のより良い関係が築かれるよう、しっかりとした制度設計と運営が求められます。この変革の中で、各企業がどのように対応していくかが今後の展開に大きく影響を与えるでしょう。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」