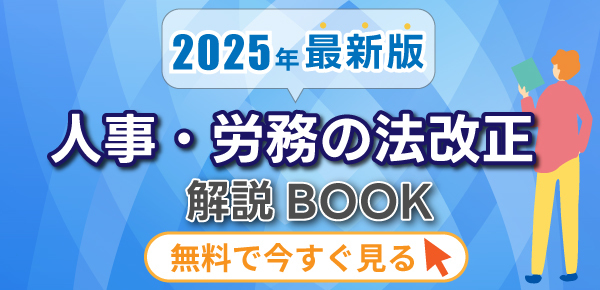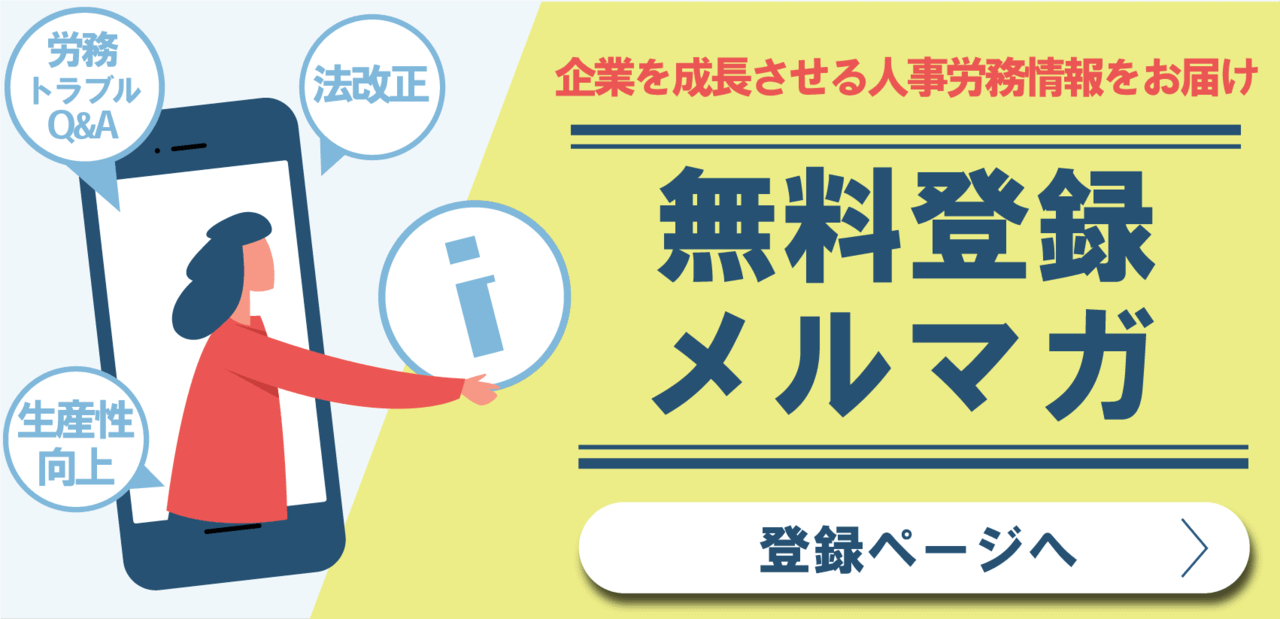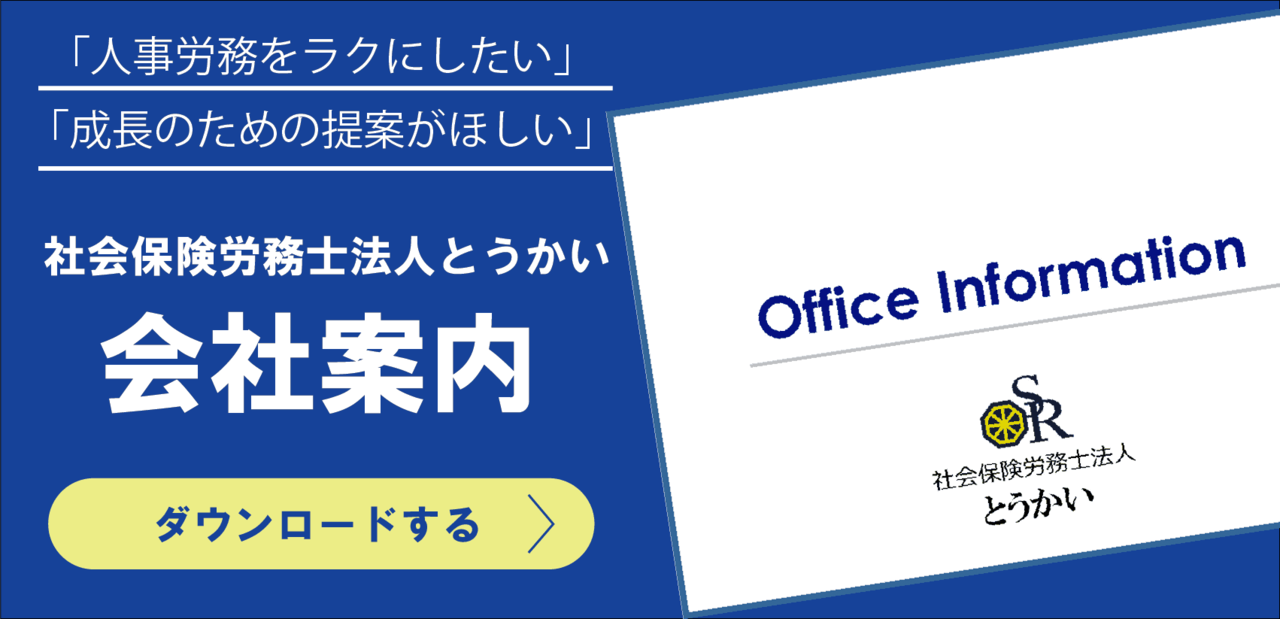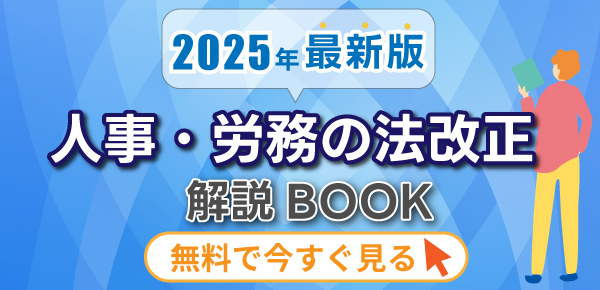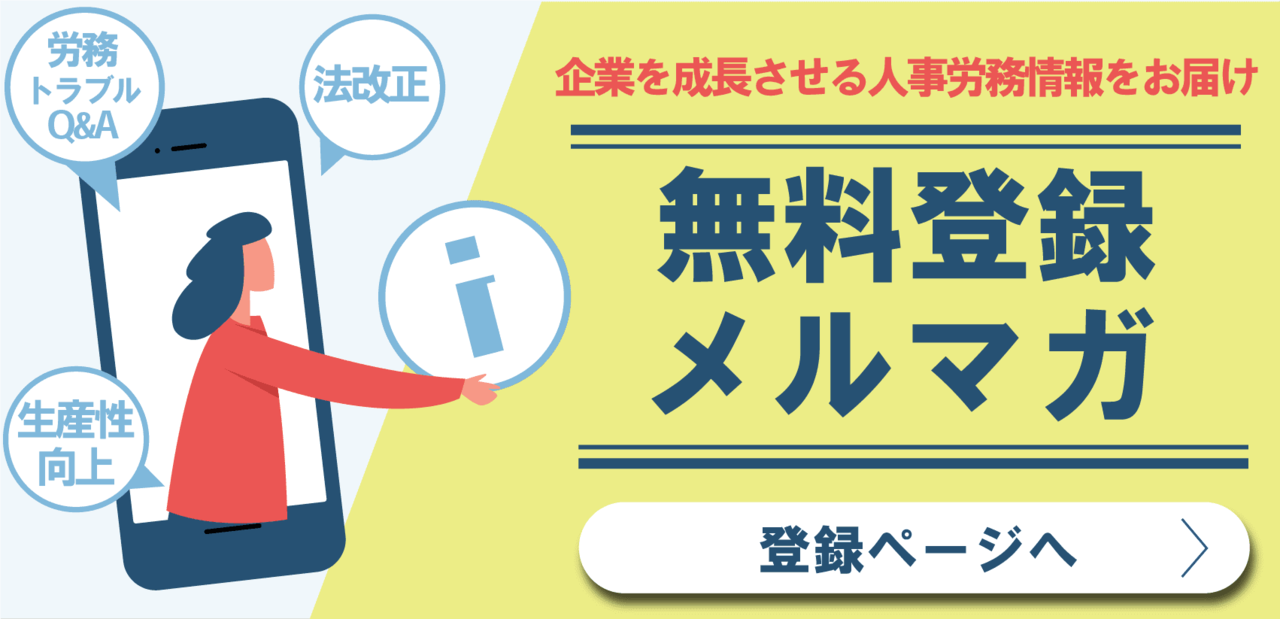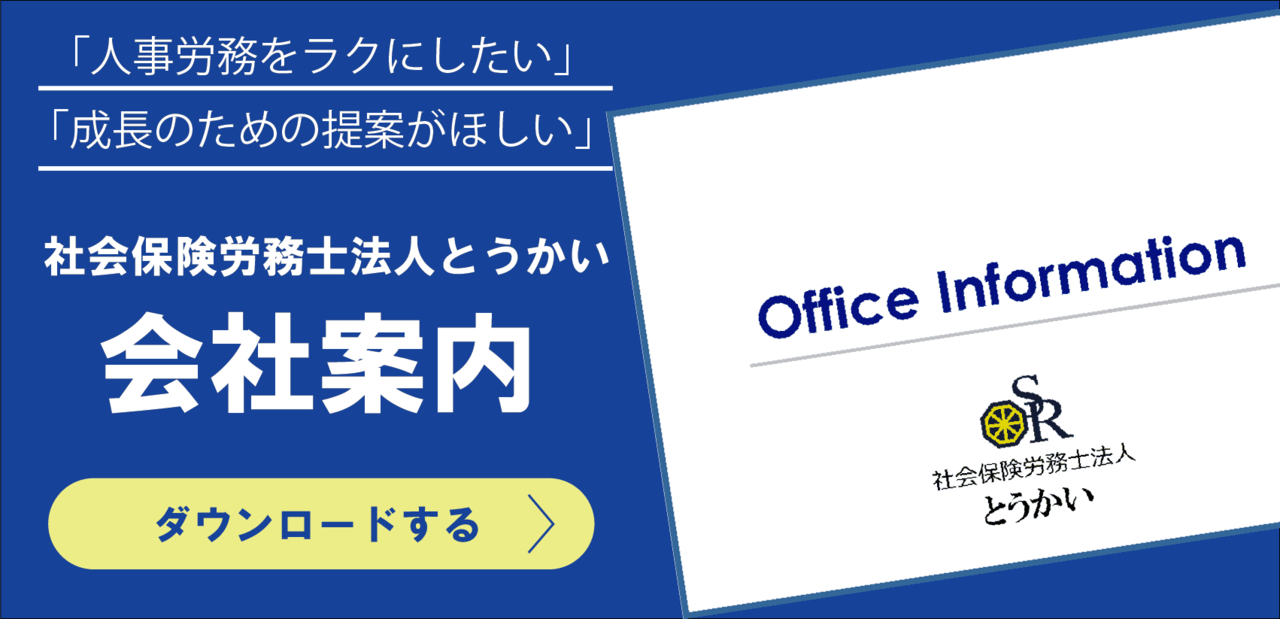【12月より健康保険証の新規発行が廃止】
マイナ保険証の作り方と会社がするべき対応を解説

2023年4月からの医療機関でのマイナ保険証対応によりマイナンバーカードでの保険証利用が可能になりました。さらに2024年12月をもって、現行の健康保険証の新規発行は行われず全面的に終了になります。この変更は、マイナンバーカードと健康保険証の統合を促進するための施策です。企業としても、従業員に大きく関わる変更となるため、適切な情報提供と対応を行うことが求められます。
マイナ保険証の利用が一般化することで、従業員が医療機関での手続きがスムーズに行えるようになり、また企業側がこれまで時間を要していた手続きの簡素化など業務効率の向上が期待されています。
今回は、マイナ保険証の概要や会社が行うべき対応について、詳しく解説していきます。
【更新履歴】 2024年11月26日 マイナ保険証に関するよくある質問を追記
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから
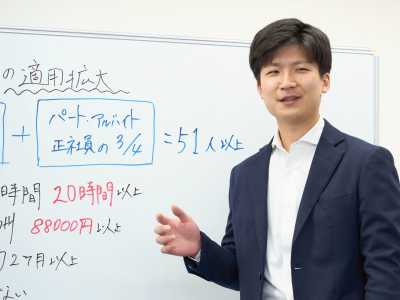
マイナンバーカードと健康保険証の統合について詳しく解説します。
現在、健康保険証とマイナンバーカードの統合が進められています。これにより、従来の健康保険証は廃止され、マイナンバーカード1枚で医療機関の受診から保険手続きまで一括管理が可能になります。この統合によって、データの一元管理が実現し、医療機関や薬局での事務手続きが簡素化されると同時に、個人情報の管理も強化されます。また、紛失や破損による健康保険証の再発行手続きが不要になるため、関連するコストや手間の削減も期待されています。企業としては、この新しい制度に対応するための準備期間を十分に設け、従業員への周知徹底を行うことが重要です。
マイナ保険証は、マイナンバーカードに健康保険証の機能を統合したもので、医療機関や薬局で手続きを行うことができる新たなしくみです。個人の保険情報がそれぞれのマイナンバーカードに集約、一元管理されるため、従来の紙の健康保険証を持ち歩く手間が省けます。また、デジタル化による利便性向上や管理コストの削減といったメリットもあります。本人の資格確認も迅速に行えるため、医療機関での受付や支払い、処方箋受取がスムーズになり、時間や労力が軽減されます。さらに、個人情報の保護が強化されることで、誤情報のリスクが低減されます。また、企業側も従業員の健康保険管理が簡素化され、保険手続きにかかる業務負担が減少します。
現行の健康保険証の新規発行が廃止される背景には、行政の効率化とデジタル化の推進があります。利用者にとっても医療機関や薬局での手続きが簡略化され、利便性が向上します。さらに紛失や破損によるトラブルが減少し、迅速な再発行が可能となるため、従来の紙ベースの健康保険証の管理コストが削減されるだけでなく、個人情報の一元管理とセキュリティ強化も図れます。

小栗の経営視点のアドバイス
マイナンバーカードを保有している人は多いものの、保険証との紐付けを行なっていな人は、まだまだ多いようです。従業員のマイナ保険証移行にあたっては、早めのアナウンスを行いながら、スムーズな移行を目指しましょう

マイナ保険証の概要とメリットを見ていきましょう。
マイナンバーカードと健康保険証の統合は、効率性と利便性の向上を目指す政府の取り組みです。マイナ保険証の導入については、義務化への反対などの声もあるものの、企業としては従業員の健康保険手続き業務が簡素化されるといったメリットもあります。具体的なメリットを確認してみましょう。
マイナ保険証の利点は多岐にわたります。具体的には、健康保険証の更新作業や交付にかかるコストと時間が削減され、事務負担が軽減されます。紛失や破損時の再発行も不要です。次に、転職・結婚・転居など状況が変更になっても、新規に健康保険証の発行を待たずとも、マイナ保険証での医療機関・薬局の利用が可能です。
マイナンバーカードを活用することで、デジタルデータが一元管理され、保険情報の変更や更新がスムーズに行えるため、迅速な保険適用を受けることが可能になるのです。利用者にとっても、医療機関での手続きが迅速になり、受付や会計、薬局での薬の受取りの待ち時間が短縮されます。加えて、健康診断の際にも利用可能です。このように、マイナ保険証は、日常的な医療サービスの利用をより便利で効率的にするための重要なツールとなります。

鶴見の経営視点のアドバイス
2024年末に向かうにしたがって、マイナ保険証がニュースに上がることも多くなっていくでしょう。従業員からの問い合わせにフットワークよく対応できるよう、今から対応方法を検討しておきましょう。

企業が取り組むべき対応策をいくつかご紹介します。
マイナンバーカードと健康保険証の統合が進む中、2024年12月より健康保険証の新規発行廃止が決定されました。この変更の背景には、行政手続きの効率化とセキュリティ強化が挙げられます。現行の健康保険証の廃止は、企業に勤める従業員にとっても、重要なニュースです。企業の人事担当者としては、従業員への迅速かつ正確な情報提供が必要です。マイナ保険証の意義とメリットの説明を通して、不安を軽減し、新しい制度への理解を深めましょう。
マイナ保険証を利用するためには、まずマイナンバーカードに健康保険証の機能を登録する必要があります。利用登録するには、3つの方法があります。まず1つめの手順としては、行政手続きのオンライン窓口であるマイナポータルにログインし、「健康保険証利用登録」を選択して必要な情報を入力します。その後、健康保険組合や協会けんぽからの認証を受けると、紐付けが完了します。続いては、医療機関等の窓口で顔認証付きカードリーダーを利用して登録する方法です。3つ目は、全国にあるセブン銀行のATMにて登録する方法があります。
また、一部の市区町村窓口でも申請が可能で、そこでは係員のサポートを受けながら手続きを進めることができます。登録完了後は、全国の医療機関や薬局でマイナンバーカードを提示するだけで保険を利用することができます。
企業はまず、従業員がマイナンバーカードを取得し、そのカードに健康保険証の機能を登録する手続きを支援することが重要です。企業としては、メールやイントラネット、ポスターなど多様なコミュニケーション手段を活用し、全ての従業員に周知する必要があります。定期的な研修や説明会を通じて最新の情報を提供し、円滑な移行をサポートする体制を整えることが求められます。
さらに具体的な手続きとして、マイナンバーカードの申請方法や利用開始までのステップも明示してはいかがでしょうか。社内通信や説明会を活用することも有効です。特に新制度に対する質問や懸念事項に対しては、Q&A形式の資料を事前に準備し、スムーズな対応ができるようにしましょう。特に新人や中途採用者には、入社時に詳細なガイドを提供することで、スムーズな適応を促進します。
従業員が安心して新制度に移行できるよう、サポート体制を整備し、継続的なフォローアップを行うことが重要です。
マイナ保険証利用の具体的な取り組み例として、大手製造業のA社では、2022年より健康保険証のマイナンバーカードへの統合を開始し、全社員に対して段階的に導入を進めました。社内ポータルサイト上に特設ページを開設し、手続きの流れや必要書類のリストを提供しました。また、定期的にウェビナーを開催し、従業員からの質問にリアルタイムで回答する形式を採用しました。導入の結果、健康保険証の紛失リスクが減少し、保険手続きが効率化されました。さらに、新しいシステムにより従業員の健康情報の管理が一元化され、企業全体の業務効率が向上しました。
マイナンバーカードをまだ持っていない従業員がいる場合、速やかに取得手続きを行う必要があります。まず、マイナンバーカードの申請は、住民票のある市区町村の窓口、または郵便やオンラインで行うことが可能です。申請には個人番号通知カードや住民票の写し、運転免許証などの本人確認書類が必要です。企業としては、従業員に対して申請手続きの詳細な手順や必要書類を周知することが重要です。
マイナンバーカードの作成にあたっては、申請からカード受取までには数週間かかることもあるため、早めの行動が求められます。また、企業が従業員に向けた申請サポートデスクを設けることで、スムーズな申請を支援することができます。
マイナンバーカードを持っていいない、紛失した、マイナ保険証の利用登録していない場合には、保険者が発行する「資格確認書」を利用します。資格確認書は、健康保険証がマイナンバーカードに統合された後も一時的に必要となる場合があります。発行するには、健康保険組合や協会けんぽに申請する必要があります。申請書の記入や必要な本人確認書類を添えて提出し、手続きを進めます。資格確認書の発行には数日かかることが多いため、予め余裕を持って手続きを開始することが望ましいです。ただし、協会けんぽにおいては、2024年9月に全加入者に対し、事業主を経由して、記号・番号を含む被保険者資格等の基本情報が記載された「資格情報のお知らせ」の送付が予定されています。
この書類を適切に管理しておくことで、従業員が医療機関での診療を安心して受けられます。
健康保険証が廃止された後も、自治体から交付される医療証(公費負担医療受給者証・介護保険証・特定疾病療養受領証等)については適切に管理することが重要です。医療証は、特定の医療サービスや補助を受けるための証明書として利用が続きます。企業は、従業員に対して医療証の有効期限や更新手続きについて定期的に通知し、必要な手続きを忘れずに行うようサポートすることが求められます。特に、高齢者や特定疾患を持つ従業員にとって医療証は重要な役割を果たすため、適切な管理が不可欠です。また、医療証の紛失防止や更新時期のリマインダーを定期的に提供することで、従業員が医療サポートを受けやすくなります。

大矢の経営視点のアドバイス
マイナ保険証の利用は、抵抗感を持つ人、とくに問題なく利用をする人など、さまざまです。従業員の中にも、さまざまな考えを持つ人もいるでしょう。マイナンバーカードの作成は義務ではないものの、将来的に医療機関の受診はマイナ保険証のみとなることを予想すると、企業としては従業員の理解を得ながら、マイナンバーカードの作成を推奨していく必要もあるでしょう。

よくある質問にお答えします。
マイナ保険証に関する質問は多くの人にとって関心のあるトピックです。特に、マイナンバーカードやマイナポータルの利用に際して、病歴がバレるのか、医療機関での利用にどのような影響があるのかを心配する声が聞かれます。ここでは、よくある疑問について明確に答えていきます。
マイナ保険証を利用することで過去の病歴がわかるのでしょうか。実際には、現時点ではマイナンバーに紐づく医療データから傷病名を把握することはできません。マイナ保険証によって一元管理されるデータは、診療報酬明細書に基づいているため、病歴が第三者に知られる心配はほとんどありません。従って、安心して利用することが可能です。
マイナンバーカードを紛失した場合、自分の医療情報が流出する危険はないか心配される方も多いでしょう。しかし、マイナンバーカード内の情報はICチップに暗号化されており、無断でアクセスされることはありません。適切に対応すれば、自分の医療情報は保護されるので安心してください。
マイナンバーカードを紛失した場合、再発行の手続きには時間がかかることがありますが、必ずしも医療機関や薬局に受診できなくなるわけではありません。受診に必要な情報を準備しておくことで、スムーズに対応できる場合が多いです。再発行の際も、仮の証明書などを利用することができるため、心配する必要はありません。
自分がマイナ保険証の利用登録をしているか確認する方法は、マイナポータルにアクセスし、ログインして関連情報を探すことでできます。また、利用登録の解除も可能で、同じくマイナポータルを通じて手続きを行うことができます。具体的な手続きについては、マイナポータルのガイドラインを参照してください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」