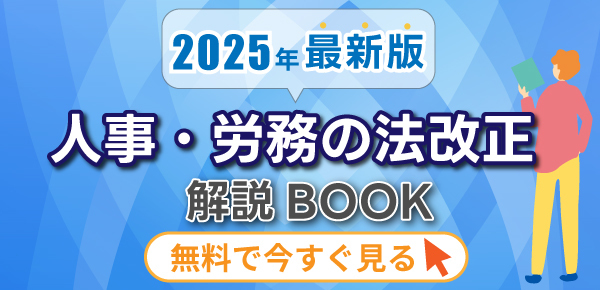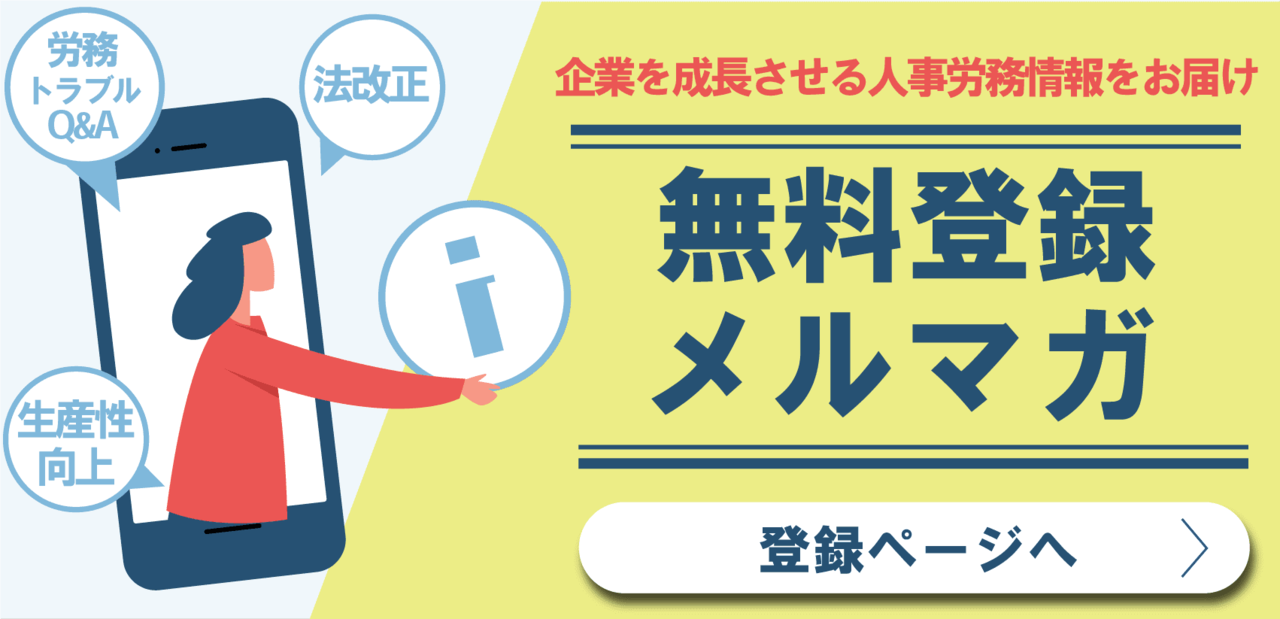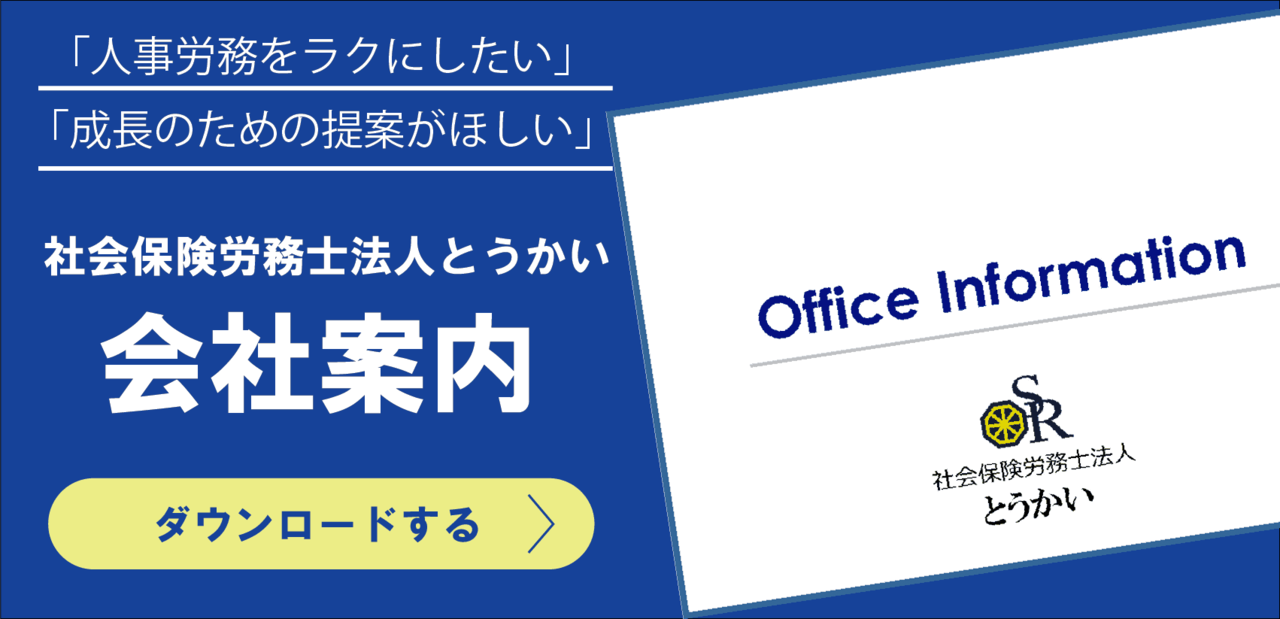退職月の給与計算の方法と注意点は?計算方法の具体例も交えて解説

退職月の給与計算は通常の給与計算とは異なり、注意しなくてはならない点があります。これは、従業員の退職日によっては、社会保険料、税金などの取り扱いが変わってきたり、未消化の有給休暇といった多くの要素が絡むためです。誤った計算が行われると、従業員に対する支払いが不正確になり、後々法的問題に発展する可能性もあります。この記事では、退職月の給与計算の基本や重要な注意点について詳しく解説し、具体的な計算方法についても紹介します。給与担当者や人事部門の担当者が正確かつ効率的に退職者の給与計算を行うためのガイドとして活用してください。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから
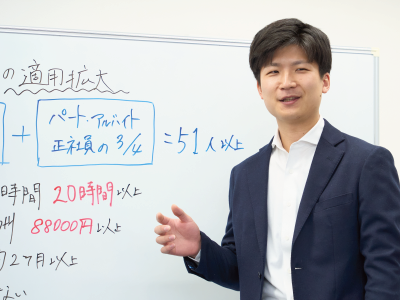
退職月の給与計算の基本を確認していきましょう。
退職月の給与計算の基本は、「従業員が在職していた期間の基本給」を正確に計算することです。これには、基本給の算定方法だけでなく、各種手当や控除項目も考慮する必要があります。特に、退職日が月の中途である場合、給与は日割り計算が必要です。
一般的には以下の3つの方法が用いられます。1つめは暦日で計算する方法、2つめは所定労働日数で計算する方法、3つめは月平均労働日数を使用する方法です。どの方法を選ぶかは、企業が定める就業規則や給与規程、従業員との労働契約によります。給与計算担当者はこれらを予め確認しておくことが重要です。また、未消化の有給休暇の扱いや、退職に伴うその他の手当(退職手当など)についても適切に対応することが求められます。

高谷の経営視点のアドバイス
従業員の退職時の給与計算は、担当者として気をつけておくポイントが多くあります。とくに、頻繁に退職者が発生する会社でない限り、ついうっかりというミスもありがちです。退職時の給与計算の確認事項などのチェックリストを用意し、誤りのない給与計算を目指しましょう。

退職月の給与計算手順を解説します。
退職月の給与計算は通常の給与計算と異なり、基本給の算定方法と、各種手当の計算方法を理解しておくことが重要です。給与計算の手順にはいくつかのステップがあり、従業員が在職していた期間の基本給の算出、次に各種手当や控除項目を適用、最終的な支給額を確定するといった流れです。それぞれのステップについてさらに詳しく見ていきましょう。
基本給を暦日で計算する方法は、退職月の暦日数に基づいて給与を日割り計算する手法です。まず、月の基本給をその月の暦日数で割り、1日あたりの基本給を求めます。そして、在職日数を掛け合わせて、退職者の基本給を算出します。例えば、月の基本給が30万円で、その月の暦日数が30日、在職日数が15日であれば、日割り基本給は1万円となり、在職期間の基本給は15万円となります。この方法は公平さと計算の簡便さから、広く用いられています。
所定労働日数で基本給を計算する方法では、その月の所定労働日数を基に給与を日割り計算します。例えば、月の基本給が30万円で、その月の所定労働日数が20日、在職日数が10日である場合、基本給の日割り計算は15,000円となり、在職期間の基本給は15万円です。この方法は、実際の勤務日数に基づいて計算するため、労働時間の実態を反映しやすいと言えます。ただし、所定労働日数が変動する業務環境では計算が複雑になる傾向があります。
月平均労働日数を基に給与を計算する方法は、年間労働日数を12ヶ月で割った平均労働日数を使用します。例えば、年間の所定労働日数が240日であれば、月平均労働日数は20日となります。この月平均労働日数を基に基本給を日割り計算します。この方法を使うと、特定の月の所定労働日数による変動を抑え、より一貫性のある給与計算が可能となります。ただし、実際の勤務日数との乖離が生じる場合があるため、その点には注意が必要です。
退職月の各種手当の計算では、基本給だけでなく、皆勤手当や残業手当、通勤手当なども適切に計算する必要があります。残業手当については、残業時間に応じて計算しますが、各種手当は基本給と同様に、在職日数に応じて日割り計算されることが一般的です。例えば、月給制の従業員が月中で退職する場合、通勤手当などもその期間に働いた日数に応じて計算されます。未消化の有給休暇の取り扱いについても確認しておく必要があります。基本的に有給休暇の買取は認められていませんが、退職する従業員の未消化分の残日数を買い取ることには特段の決まりはありません。買い取らなければならない義務もありませんので、企業の任意に任せられている部分です。もし未消化分の有給休暇を買い取る場合には、その分の賃金も計算に含める必要があります。これにより、退職者が受け取るべき最終的な給与が正確に算出されます。

小栗の経営視点のアドバイス
退職する従業員には、給与計算のほかにも、社会保険の手続きや退職金の支払、住民税の手続きなど、忘れてはならない事務処理が多くあります。また、自己都合で退職する場合、定年退職の場合など、必要な手続きも変わってきます。労務担当者の経験が浅く、ご不安を抱える企業もあるでしょう。こんなときはどうしたら?といった疑問・質問に、とうかいは丁寧にご説明・解説差し上げます。

社会保険料控除の計算方法を解説します。
退職月の給与計算において、社会保険料の控除も重要な要素となります。社会保険料には健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが含まれます。退職月の社会保険料の控除方法を理解しておくことで、正確な給与計算ができ、退職者が受け取るべき最終的な給与を適切に算出することが可能となります。以下に、退職日の資格喪失日との関係、控除方法、資格喪失手続きの重要性について詳しく説明します。
社会保険料の資格喪失日は退職日の翌日となります。例えば、退職日が3月31日であれば、資格喪失日は4月1日です。健康保険と厚生年金保険では月単位での加入が基本です。そのため、退職日が月末である場合、資格喪失日は翌日となることから、その退職月の保険料は全額控除されることになります。一方、退職日が月初や中旬である場合、その月の社会保険料の控除はありません。雇用保険料については、毎月の給与額に応じて一定の保険料率を掛けて計算しますので、資格喪失日によって、控除する、しないといった処理はありません。
雇用保険を除く社会保険においては、退職日と資格喪失日の関係を把握しておくことが給与計算のポイントです。
社会保険料を給与から控除する方法には「当月控除」と「翌月控除」の2種類があります。「当月控除」は、その月の給与から同月分の社会保険料を控除する方法です。これは例えば、4月分の保険料を4月の給与から控除するケースです。一方、「翌月控除」は、その月の給与から翌月分の社会保険料を控除する方法です。例えば、4月分の保険料を5月の給与から控除します。退職月の給与計算では、どちらの方法を採用しているかを確認し、それに基づいて正確に控除を行う必要があります。
退職後に社会保険の資格喪失手続きを迅速に行うことは非常に重要です。この手続きが遅れると、保険料の二重徴収や保険給付の遅滞など、様々な問題が発生する可能性があります。具体的には、健康保険や厚生年金保険であれば、退職日の翌日から5日以内に、雇用保険であれば退職日の翌日から10日以内に資格喪失の手続きを行うことが求められます。これにより、退職者が受け取るべき手当や保険給付の処理が円滑に進むことになります。企業の給与担当者は、手続きの遅滞を防ぐためのチェックリストを作成し、確実に実行することをおすすめします。

大矢の経営視点のアドバイス
社会保険などの手続きは、手続きの期限が設けられています。手続きが遅れると退職した従業員に迷惑をかけることになりますので、退職日が判明したら予め手続きの準備をしておくことをおすすめします。

退職月における住民税の取り扱いを解説します。
退職月における住民税の取り扱いは、給与計算において重要なポイントの一つです。住民税は前年の所得に基づいて住民税が決定され、6月から翌年の5月までの12ヶ月間にわたって給与から控除し、自治体に納付します。そのため、退職月における住民税の取り扱いを正確に理解し、適切な計算と控除を行うことが必要不可欠です。
年の途中で退職する場合は、その年度の住民税の未払い分を、退職月の給与から一括して控除して納付するケースがあります。また、すでに退職後に転職先が決まっている場合には、転職先の会社で引き続き1か月ずつ住民税を控除するための手続きも可能です。その場合、退職月の給与から控除すべき住民税は、通常の給与と同様です。
一方で、退職者が住民税の年度末(5月末)に退職する場合、その年度の住民税は全額支払済みとなりますので、給与計算上は特別な対応は必要ありません。
退職月における住民税の取り扱いは複雑ですが、適切な対応を行うことで退職者に対する不利益を避け、円滑な給与計算が可能となります。

鶴見の経営視点のアドバイス
退職後の住民税の納付については、従業員が住民税を納付している市区町村へ給与所得者異動届を提出する必要があります。退職の決まった従業員には、予め退職時に一括して納付するのか、転職先などで引き続き納付するのかなど、退職者の同意を得たうえで、正確な金額を計算することが重要です。

退職月における所得税の取り扱いについて解説します。
所得税は源泉徴収制度に基づいて、毎月の給与から控除されるものです。退職する月であっても、通常の給与計算同様に控除します。
ただし、退職金が発生する場合、退職金にも所得税がかかるケースがありますので注意が必要です。退職金の所得税は「退職所得控除」と「退職所得税率」を適用して計算され、他の給与とは別に扱われます。退職金の計算方法は、勤続年数や支給額によって異なるため、正確な算出が必要です。
さらに、退職者が年末まで勤務する場合、その年の年末調整を行う必要があります。しかし、年度途中で退職する場合には、退職月までの給与や賞与を基に源泉徴収票を発行する必要があります。退職者がその後転職しない場合には、確定申告が必要になることがあります。他の会社に転職する場合には、転職先での年末調整に源泉徴収票を利用することになりますので、必要に応じて退職者に案内することが重要です。

退職月の給与計算を効率的に行うためのポイントを紹介します。
退職月の給与計算を効率的に行うためには、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが必要です。退職月の給与計算をスムーズに行うための具体的な方法と注意点を確認しましょう。
まず最初に、従業員が退職する際には、年次有給休暇の取得状況や残日数、残業時間、遅刻や早退がないかといった勤怠に関わる項目、その他の手当を含む全ての給与項目を正確に把握することが重要です。これにより、計算ミスを防ぎ、正確な給与を支給することが可能となります。特に、残りの有給休暇があり、精算をするような場合には、その分の給与を適切に計算し、支給することが求められます。
次に、従業員の退職日に応じて、日割計算が必要な場合には、就業規則や給与規程を確認し、暦日、所定労働日数、月平均労働日数などの方法により、基本給の計算を行います。就業規則や給与規程などに明記した計算方法で処理することで、全従業員に対する公平性を保つことができます。
社会保険料や税金の計算も効率化のための重要なポイントです。退職日が判明すれば、社会保険の資格喪失日が予めわかりますので、「当月控除」か「翌月控除」を適切に選択し、控除の誤りがないよう準備しましょう。住民税や所得税についても、退職月における適切な取り扱いを行い、過不足なく徴収します。特に、一括控除が必要な場合には、退職者とのコミュニケーションを大切にし、同意を得ることが重要です。
最後に、給与計算ソフトウェアやシステムを活用することも、退職月の給与計算を効率化するうえで、重要になります。給与計算ツールは、手作業での計算ミスを防ぎ、時間を大幅に節約することができます。最新の給与計算ツールを導入し、自社のルールに合わせてカスタマイズすることで、精度の高い計算が可能となります。

退職月の給与計算は、通常の給与計算とは異なり、多くの要素を考慮に入れる必要があります。基本給の計算方法一つとっても、暦日、所定労働日数、月平均労働日数など複数の方法が存在します。それぞれの方法で支給する金額も変わってきますので、メリットとデメリットを理解しておく必要もあるでしょう。まずは自社の就業規則や給与規程に明記してあるか確認することが重要です。さらに、各種手当や社会保険料の計算、住民税および所得税の正確な取り扱いも欠かせません。
退職者が次のステップに進む際に給与計算のミスがないように注意を払うことは、企業の信頼性を高める上でも重要です。給与担当者は、最新の制度変更にも常に注意を払い、正確な情報を基に業務を進めることが重要です。
とうかいでは、給与計算を行ううえでの企業のお悩みごとに、丁寧にアドバイスを行なっています。給与計算は小さなことでも処理結果に誤りがあると、後々、トラブルに発展することもあります。リスク防止のためにも、自社の給与計算業務を振り返ってみませんか。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」