採用媒体選び
媒体力が重要

求人媒体を選ぶポイントは媒体力です。媒体力とはどの程度その媒体が見られているかでWEBページであれば単純にPV数です。
媒体を選ぶ際は絶対に名前だけで選んではいけません。媒体を選ぶ側のイメージは固定されてしまっていることが多いため、一昔前に有名だった、名前を知っている媒体を選びがちになります。
媒体を選ぶ際はまずは閲覧数を調べましょう。
例えば世界№1の求人検索サイトと言われるIndeedは月間2000万PV以上あると言われています。これがタウンワークでは1300万PV、バイトルでは600万PVほどになります。
もちろん、それぞれの媒体ごとで閲覧している応募者の層は違いますので、一概には比較できませんが、媒体としての力は想像しやすくなるのではないでしょうか?
傾向としては掲載料が高い媒体ほどアクセス数も多くなる傾向があります。今の時代であればアクセス数は簡単に調べられます。
媒体決定の前に一度比較してみることをおすすめします。
応募者の行動パターン
時代とともに応募者の行動パターンは常に変化しています。今の応募者がどのような行動をしているかは常に注視していく必要があります。
最近の応募者の傾向として下記5つが挙げられます。

スマホで検索
求職者の9割がスマートフォンを使って仕事を探していると言われています。
スマートフォンを使うことはすでに当たり前であり、以前はスマートフォン「も」使って求職活動を行っていましたが、現在はスマートフォン「のみ」で求職活動を行う応募者が増えてきています。
スマートフォンのみで求職活動を終える応募者が増えていることに注意が必要です。

〇〇しながら仕事探し
以前は、仕事から帰って家でパソコンを開き求職活動やわざわざコンビニで求人誌を手に入れなければ求職活動はできませんでした。しかしスマートフォンが普及し、今の応募者はあらたまって仕事を探すことはありません。
上司に怒られたから、休憩時間に仕事をとりあえず探してみる、業務の休憩中にスマホを見ていたら求人広告が目についたので調べてみる。
こういった行動が当たり前なのです。
2017年のアイキューブドシステムズ社の調べによると、55%以上の従業員が今の会社に対し、「辞めたいという気持ちが少しでもある。」と回答しています。
何か仕事で嫌なことがあった後や、特に理由がなくても何気なく仕事を探しを行うのが今の応募者なのです。

情報は多くて当たり前
今は何かわからないことや困ったことがあるとインターネットで検索するのが当たり前の時代です。そういった時代においては検索で表示される情報がすべてになります。
ホームページの雰囲気や口コミが信用されることも、今の応募者の特徴といえるでしょう。

複数社を比較して応募
中途採用の場合、応募者は平均8.4社応募をしていると言われています。
またインターネット上では比較がしやすいため、給与や働き方などの労働条件を比較してから応募する傾向が強まっています。

知名度や安定性重視
知名度や安定性を重視する傾向は年々強まっています。
就職先決定理由の1位は「会社業績、安定性に魅力を感じたから」というアンケートもあります。
人手不足で大手の採用が増えていることも一つの要因ではありますが、名前の知られていない中小企業にとっては厳しい状況が続くと言わざるを得ません。
媒体の種類と変遷
求人媒体は大きく分けると有料・無料、リアル・ウェブで分けることができます。
求人サイト

求人サイトはインターネット上で様々な業種の企業の求人情報を掲載しているサイトです。
特徴としては、登録している人に対してアピールできるため短期間での効果が望まれる、求人の検索がしやすい、等があります。
料金形態は掲載課金型、応募課金型、採用課金型の3つの種類があることになります。
以前は登録型のサイトが主流でしたが、検索型のサイトも少しずつ増えてきました。
媒体の求人広告(求人情報誌・新聞折り込み)
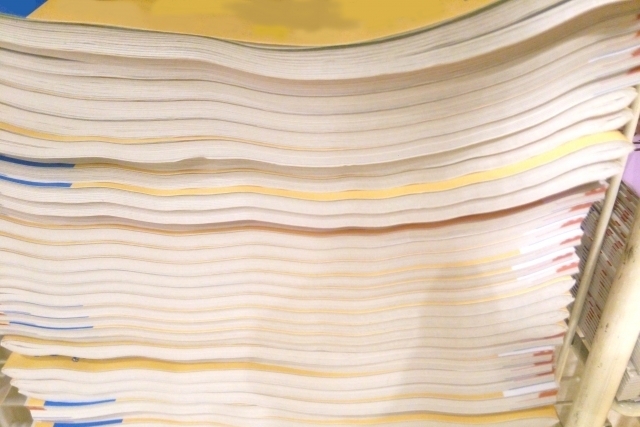
求人情報誌はフリーペーパー、もしくは有料でコンビニなどで配られています。新聞折込は各新聞社が発行する新聞に折り込まれる広告チラシに求人広告を掲載することができます。
紙媒体の特徴としては、特定の地域・年齢層に届きやすいことがあります。希望の人材像に合っている場合には効果が高くなります。
料金形態としては、掲載料金は掲載する求人広告の紙面枠の大きさ、写真の有無、カラーの有無等によって決まっています。また、求人情報誌の場合、配布エリアによっても料金が異なり、地方より都市部の方が掲載料金は高額になっています。新聞折込チラシの場合、料金は求人広告の紙面枠に対する大きさや配送地域に加え、配送日によっても異なります。
ハローワーク

ハローワークは国の支援を受け、各都道府県の労働局が管理している公共職業安定所です。
国が運営していることもあり、ほとんどのサービスが無料で使えます。
ハローワークインターネットサービスを利用すれば、企業はインターネット上にハローワークの求人を掲載することも可能です。
ですが、ハローワークは職業を紹介することを前提としているため、求職者はインターネット上で案件の確認はできますが、応募することはできません。
一度、ハローワークを通してからの応募が必要となります。
こうした従来の求人媒体の他に、近年ではIndeedに代表される検索型の求人サイトの利用が大きくなってきています。
一部の機能は無料でも使うことができますので、選択肢の一つとして考慮すべきでしょう。
indeedの起こした変革

Indeedは検索型の求人広告サイトです。
検索型とは、その名の通り、インターネット上の求人原稿を検索し、一覧にして掲載するサイトです。
つまりA求人広告に掲載しても、B求人広告に掲載しても、検索型のIndeedに表示されるということです。
応募者からすれば、2つのサイトを見なければいけなったものが1つにまとまって、仕事が探しやすいという利点があります。そうした仕事の探しやすさから利用者が増えています。
今、Indeedに利用者が集中することで2つの変化が起きています。
一つ目の変化はあまりにもIndeedに利用者が集中しすぎているため、他求人広告サイトもIndeedに広告を出稿するようになったことです。Indeedの拡大が、求人するならまずIndeedありきという状況を作り出してしまいました。
他求人サイトでもIndeedに検索されるように、求人原稿の文字量を増やしたり、規格をIndeedに対応したものに変更したりと、Indeedの規格が業界の標準となってしまったのです。
もう一つの変化が自社採用サイトの増加です。
Indeedが検索してくれるのであれば、求人広告サイトに広告料を支払い、求人を掲載してもらうよりも、自社の採用サイトを作ってIndeedに掲載をした方が効率的ではないかと考え、自社採用サイトを作成する企業が増えたのです。
indeedのメリット

Indeedのメリットは何といっても利用者が圧倒的に多いことです。
Indeedは世界№1の求人検索サイトと呼ばれており、毎月の閲覧数は2000万を超えます。※合計2000万ページ以上の閲覧があったということです。
リクナビネクスト閲覧数が1000万程度ですので、2倍以上の閲覧です。
ただし掲載されている求人原稿数も他求人サイトと比較すると非常に多いです。
またキーワードの入力欄は自由入力と勤務地のみになっており、登録型のサイトと比べると、こだわりの条件を設定しにくくなっています。
そのため、いかにIndeedの仕組みを理解し上位表示させるかが成否を分けるカギとなるでしょう。
基本は無料でも掲載できますが、広告をかけることも可能で、1クリック15円~999円までで設定できます。
ターゲットの絞り方

求人広告はターゲットに合わせて設定しなければなりません。
川でマグロを探してもいないように、ターゲットが閲覧しない広告であれば効果は出ないのです。
ターゲットの絞り込みは、ターゲットが持っている仕事に対する不安や期待が理解できるまでしっかり行いましょう。
よくターゲットの設定をしましょうというと、20代男性や30代女性というように設定される方がいらっしゃいますが、これでは絞り込めていません。
30代女性ならば、どのようなライフスタイルをおくっていて、どういった仕事観をもっているのか、まで明確にする必要があります。
例えば、「未就学児あるいは児童(小学校1~3年)が1人以上いる母親※片親家庭の場合も含む」というところまで設定する必要があります。
ここまで絞り込めれば、ターゲットが持つ「子供が学校に行っている時間だけ仕事がしたい!」ですとか「仕事に対してブランクがあるので心配」といった仕事に対する考え方が想像できます。想像ができれば、ターゲットに対してぴったりの求人広告を作ることができます。
だからこそ、求人広告のターゲットは、仕事に対する期待や不安が見えるところまで、絞り込む必要があるのです。
予算の立て方
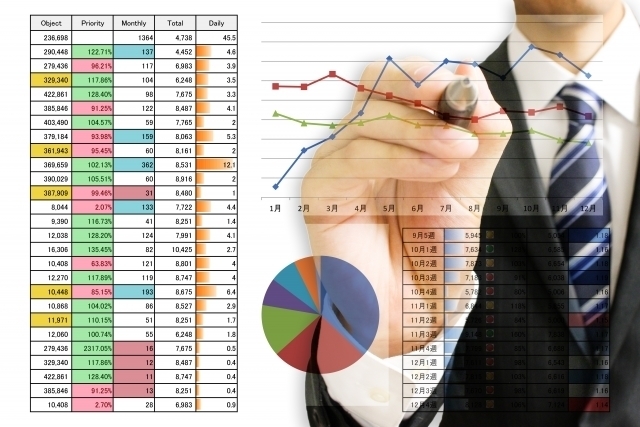
いつ、どのような人材を、何名採用するためにいくらが必要かという採用予算は、経営計画を立てる時点で確保しておくことをおすすめしています。
採用には補充採用と計画採用の2種類の採用方法があります。
補充採用は離職者や休職者が出た場合に採用活動を行いますが、募集する期間も短く、予想もできないため予算が多くかかってしまいます。
私たちがおススメしているのは計画採用です。
経営計画の作成に合わせて、必要な人員と必要な要件を計画にし、期間に余裕をもって採用を行うのです。
計画採用は期間を長くすることによって「いい人がいたら採用する」という採用手法です。
あらかじめ採用の計画を立てることで、補充採用と比べて、費用も安くなり、効率的に採用が行えます。
また期間に余裕があるため、応募者も確保することで、多くの応募者から選べますので、採用のミスマッチも防ぐことができます。
採用の予算の立てるときは、必要な人員の数×必要な要件×期間の3点を考慮し設定することが大切です。
出稿時期

できる限り長い期間で出稿することが重要になります。
確かに応募自体は多い時期と少ない時期はありますが、今はスマートフォンを使い、いつでも求職活動ができる時代です。
休みの日に、応募はしませんが、募集要項などの情報は見られていると思った方がいいでしょう。
事実、厚生労働省労働局が発表している月間有効求職者数を確認してみると、年間を通して仕事を探している人の数は変わりません。
また、これだけ人手不足の時代に、原稿を出稿後、希望の人材からの応募がすぐにあるかといえば、ないと考えるのが自然でしょう。
計画採用ではいつどのような人材が必要なのかを事前に計画しているため、前もって出稿することで期間をできる限り長くし、定置網漁業のように、希望の人材が応募してくるのを待つことができます。
希望の人材像に合った人材を採用するためにはできる限り長く出稿し続けることが重要なのです。
人材像を明確に設定

採用媒体選び最初に行うことは、自社で採用したいと考えている希望の人材像の設定です。
希望の人材像の設定というと、多くの方は「20代男性」や「30代女性」といった風に考えているのではないでしょうか?
ですが、「20代男性」や「30代女性」では人材像を設定したと言えません。
年齢や性別といった大きな分類だけでは、ターゲットとなる人材像が普段どのような行動をしているのかがわからないからです。
例えば、「アパレルに応募をしようとしている30代女性」と「ベーカリーショップで働こうと思っている30代女性」は同じように行動するでしょうか?希望がここまで異なるのであれば、趣味や嗜好、交友関係も違うはずです。普段目にする雑誌や、よくいく場所も異なるのではないでしょうか。
行動が違えば、当然目にする媒体も変わってきます。
ターゲットの行動が見えるまで希望の人材像を具体化することは、採用媒体選びの最初の一歩なのです。
媒体の選び方

採用戦略のプロ・とうかいが、
ターゲットに合わせた媒体をお選びします
繰り返しになりますが、知っているからという理由で採用媒体を選んではいけません。
以前と比較して媒体も非常に多くなっていますし、インターネット検索が主流となった現在では、以前のようなブランド力は低下しています。
以前は、有名なサイトでなければ仕事が見つけにくかったから登録型のサイトを使っていただけなのです。
今の応募者はスマートフォンでの検索を利用し、インターネットの膨大な情報の中から自分に合った仕事を探しています。
応募者にとっての最大のメリットは見つけやすいことなのです。
採用媒体選びは、自社のターゲットの行動に合わせながら、自社の強みを最大限に活かせる媒体を選ぶことが重要になります。
私たちは採用戦略のプロです。
これまで年間100件以上の採用をサポートした経験とノウハウをもとに、ターゲットに合わせた自社の強みを最大限に生かせるターゲットに合わせた媒体を選んでまいります。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」





















