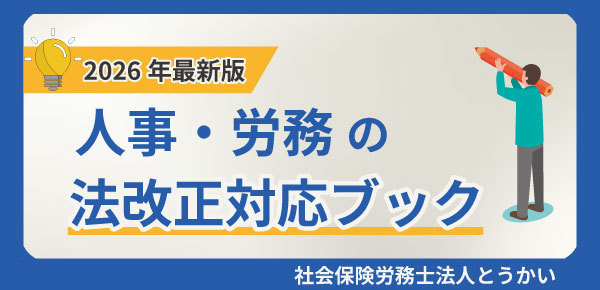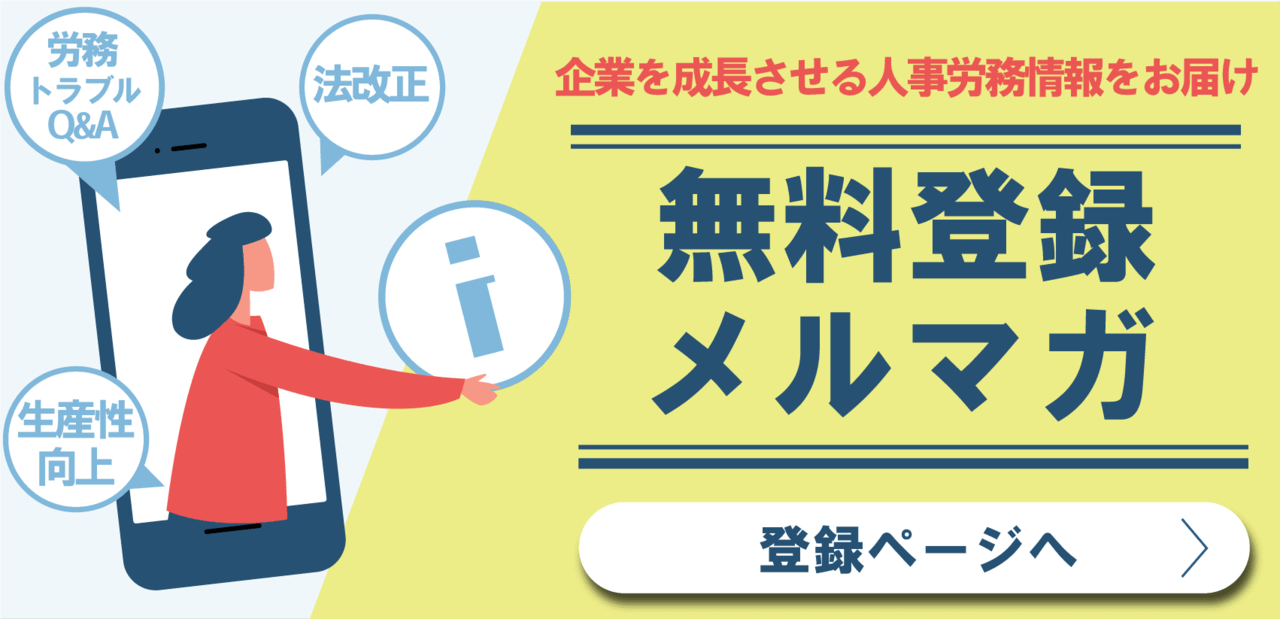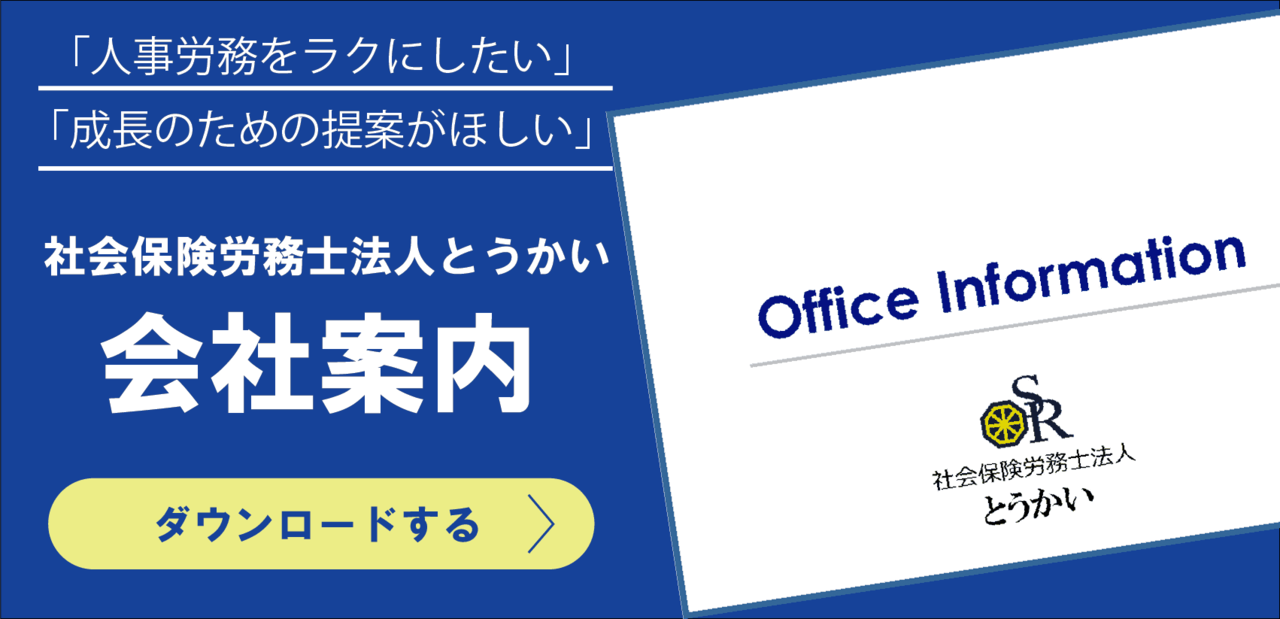どんな罰則があるの?
残業時間の上限規制、企業がとるべき対応とは?

【2019年4月施行】残業時間の上限規制とは?
※中小企業は2020年4月~
さまざまな改革が行われる「働き方改革」
その改革の一環として、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)より、残業時間の上限を超えると罰則が課されることになりました。残業時間は従来においても一定の上限時間が設けられていましたが、今回の法改正によって、今までよりもさらに厳格化、罰則も適用されることになりました。今回は、残業規制の概要と、企業が適切な労働管理を行っていくために、どのような対応をすべきかについてご説明します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

まずは、上限規制のご説明の前に、そもそも残業とは何か、振り返りましょう。
一般的に、会社の終業時刻以降の時間や、会社の休日に働くことなどを、「残業」として一括りにされていることが多いのですが、労働基準法においては、少し違います。まずは労働基準法で定める“労働時間”と“休日”をきちんと押さえておきましょう。
労働基準法においては、原則として「1日8時間」「1週40時間以内」を「法定労働時間」と位置づけています。さらに、休日は、「毎週少なくとも1回」与えるものとし「法定休日」と、定めています。
労働基準法では、法定労働時間を超えた労働時間を残業時間、法定休日の労働時間を休日労働として、定めているのです。つまり、1日で9時間働いた場合は、1時間の残業、1週間で合計48時間働いた場合には、8時間が残業時間、法定休日にあたる日に6時間働いた場合は、6時間が休日労働になるというわけです。
【法定労働時間の例外】
法定労働時間にも以下の例外があります。
① 週44時間特例
10人未満の従業員のいる事業場が対象で、特定の業種(卸売業、小売業、理美容業、映画・演劇業、保健衛生業など)に従事する場合で、就業規則や雇用契約書に定めたとき
② 変形労働時間制
ひと月単位で週あたりの労働時間を40時間以内としたとき
法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、会社は、あらかじめ従業員の過半数を代表する者や労働組合と、「36(サブロク)協定」とよばれる協定を、書面により締結しなければなりません。さらに、「36(サブロク)協定届」
を、所轄の労働基準監督署に届け出ることになっています。
この「36協定届」を届け出ずに、従業員に時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となりますので、注意が必要です。就業規則の作成・届出の場合は、常時10人以上の従業員を使用する使用者に限られているのに対し、36協定は従業員が、1人のみでも法定時間外労働や法定休日労働をさせる場合には、必ず届け出が必要となります。
労働基準法に定める「法定労働時間」に対して、会社の就業規則など独自で定めた「所定労働時間」というものもあります。ここが、間違いしやすい点。会社の所定労働時間が法定労働時間と同じ8時間であれば、とくに気にする必要はありません。しかしながら、会社の就業規則で所定労働時間を7時間など、法定労働時間と異なる定めをしている場合は、注意が必要です。
例えば、所定労働時間を7時間と定めている場合は、7時間労働を超えた時間、つまり所定労働時間外労働が、時間外労働として認識されているからです。
また、休日労働についても、「所定休日」というものもあります。例えば、週休2日制度などで、毎週土曜日・日曜日を休日としている場合で、日曜日を「法定休日」とした場合は、土曜日は「所定休日」となります。
しかし、今回の働き方改革に関連する残業上限規制において、残業の基準に用いられるのは「法定労働外時間」「法定休日」です。「所定労働時間」「所定休日」は該当しませんので、自社の労働時間および休日を、今一度確認しましょう。
今回の働き方改革では、「残業時間の上限規制」とは、労働者の「法定時間外労働」「法定休日労働」に法的な上限が設けられ、規制されることになりました。
前述のように、従業員に残業をさせるには、労使の36協定を締結、労働基準監督署に届ける必要があります。この届け出をしてはじめて、従業員の残業が可能になりますが、残業時間には以下のような1月45時間までと上限が設定されています。45時間の上限時間は、1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、42時間に減少します。特別の事情がなければ、これを超えることはできません。
届け出たとはいえ、企業の業種やサービス内容によっては、残業時間が増える繁忙期があったり、緊急で対応しなければいけない事情が発生したりする場合も。そのような場合は、1年のうち6か月を限度として、36協定の特別条項を活用し、残業を可能にするケースもあります。36協定の書式に「(◯◯の場合には、1か月の時間外労働を80時間まで行わせることができる)といった、文言を追加し、労使で協定をする必要があります。◯◯については、残業をしなければいけない特別な事情を記載する必要があります。
ただ、この特別条項は、1年のうち6か月限定とはいえ、延長時間がそれぞれの企業任せで無制限になってしまうのは問題。今改正では、この特別条項によって延長できる時間に限度が設定し、過重労働の抑止につなげることが目的です。
具体的には、今まで1年のうち6か月を限度として、1か月の残業時間を無制限に設定することができましたが、今回の法改正後は、1か月の残業時間の上限は、100時間に設定されました。特別条項を利用したとしても、月100時間以上は、従業員に残業をさせることはできません。
① 36協定に定められた残業時間の限度は従来のまま。1か月で45時間、1年360時間。
② 特別条項を設ける場合は、1年のうち6か月を限度として、月の残業時間の上限が100時間未満。休日労働の時間も、残業時間に含まれる。
③ 特別条項を利用した場合の残業時間は、1年720時間が限度となる。
④ 特別条項があっても、複数月(2〜6か月)の平均をすべて80時間以内におさめること。
※月の時間外労働と休日労働の合計が、どの2〜6か月の平均を取っても、1か月あたり80時間を超えないこと。
2019年4月以降は、残業時間の上限に関して、さまざまな制限がありますので、自社の残業時間に関する労使協定や就業規則について、今一度、確認をしましょう。これからは残業が厳しく取り締まられるようになります。残業時間が上限を超えている場合は、罰則が科せられることにもなりました。半年以下の懲役か30万円以下の罰金となりますので、残業時間が上限を上回らないように、確実に労働時間を管理し削減していく必要があります。

時間外労働の上限規制の施行に当たっては、すぐに36協定を締結し、届け出をしなくてはならないということではありません。大企業であれば、施行開始の2019年4月以後の期間のみを定めた36協定を締結する時点から、また中小企業であれば、2020年4月以後の期間のみを定めた36協定を締結する時点から、新たに届出を行えばよいという、経過措置が設けられています。
中小企業への上限規制適用に1年間猶予があるのとは別に、残業時間の上限規制そのものに対する除外や猶予の措置がとられている事業があります。残業規制が猶予される、または規制が適用されないのは、以下の事業です。
・土木、建設などの建設事業:2024年3月31日まで規制が適用されません
猶予期間後であっても、災害の復旧や復興の事業に関わる場合は、「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」の規制は摘要されません。
・自動車を運転する業務(タクシー運転手など):2024年3月31日まで規制が適用されません
猶予期間後であっても、「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」「年6回」の規制は摘要されません。また、年間上限が960時間となります。
・病院で働く医師:2024年3月31日まで規制が適用されません
猶予期間後の、上限時間は、今後省令でさだめることになっています。
・鹿児島県、沖縄県における砂糖製造業:2024年3月31日まで、「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」の規制が適用されません
・新技術や新商品などの研究開発業務:上限規制は適用されません
また、一定の年収以上のコンサルタントやアナリスト、研究開発職など高度な職務能力を有している労働者で、「高度プロフェッショナル制度」の適用該当者とされている労働者については、労働基準法の適用外となるため、残業時間の上限規制の適用対象外となります。

把握すべき労働時間は非常に多岐にわたります。
今回の改正にあたって、企業が上限規制への対応として、規制に沿った36協定を締結し、届け出ることはもちろんですが、一番重要になってくるのが、個々の従業員の労働時間の管理を確実に行っていくこと。日々、週、月単位で適時把握していく必要があります。「45時間付近」「80時間付近」「100時間前」などで、アラートがあがる仕組みなどを活用するのもよいでしょう。
労働時間の把握に関しては、2019年4月より管理監督者等も含めた労働者の労働時間の状況を客観的な方法(ICカードやパソコンのログ履歴など)で把握するよう義務付けられていますので、今回の規制内容に即した労働時間の管理が必要となります。とはいえ、そもそも残業が生じないような業務の割り振りや人材体制など、組織の整備の対策を講ずる必要があります。企業においては、さまざまな取り組みが求められます。
上限規制を確実に遵守していくためには、以下のポイントに沿って、日々管理していくことをおすすめします。
時間外労働の上限規制では、「1日」「1か月」「1年」の限度時間を定め、労使で36協定を締結しなくてはなりません。また、休日労働の回数や時間数も定める必要があります。加えて、「1年」の上限について正しく算定するために「起算日」を明記します。この枠組みを超えた労働は違法となります。
特別条項で残業時間の上限を拡大できるのは「年6回」まで。特別条項は、あくまでも繁忙期や緊急時の特別な例外対応というのが大前提です。年間の半分を超えてしまえば、例外にはなりません。
特別条項は、「臨時的な特別の事情がある場合」のみ適用できます。「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」では認められず、必ず具体的な事由を明らかにすることが求められます。
時間外労働と休日労働を合計して、月100時間まで
時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が、すべて1か月当たり80時間まで
時間外労働が年720時間まで
年720時間までといっても、720時間÷12か月=月60時間までOKということではありません。一年のうち6か月は、36協定締結時の時間外労働の限度時間である「1か月45時間」の枠におさめる必要があります。
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、あらかじめ定めておく必要があります。

働き方改革関連法のなかでも最も影響が大きいと言われているのがこの「残業時間の上限規制」です。
経営者の方とお話していると、「中小企業はまだ先」という認識の方がほとんどです。しかし大企業が対応をすれば、その影響は中小企業経営にも影響を与えます。
例えば、「取引」です。大企業は法律により長時間の残業はできなくなりました。残業はできないのにも関わらず、仕事がある状態であれば、仕事を下請けに流していきます。
公正取引委員会は「働き方改革に関連して生じ得る中小企業等に対する不当な行為の事例」を発表。国土交通省も「働き方改革等の推進に向けた受発注者双方の取組について」経済産業省も同様に「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」という文書を発表し、各省庁が横断的に下請けにしわ寄せがいかないように指導を始めています。
そして「採用」です。
働き方改革によって、採用の市場が変わり始めています。大手が自社の残業を抑制しようと採用を強化しています。
採用の強化は労働条件の見直しと採用人数の増加です。
これにより、中小企業の採用難に拍車がかかっています。
このようにすでに中小企業にも影響は出ています。まだ対応できていないのであれば、来年まで待たずに一刻も早く対応すべきでしょう。
そもそも、求職者からすれば、法律を守らなければならない企業と、猶予されているとはいえ、法律が適用になっていない企業であれば、法律を守らなければならない大企業を選ぶからです。
まずは勤怠管理ソフトを導入しましょう。
何事も現状を知ることから始めることから重要です。
勤怠管理ソフトを使えば、出勤・退勤時間の管理はもちろん、残業時間も自動で集計が可能です。
・勤怠管理ソフトの選び方が分からない
・導入をする時間がない
・法律に沿った内容で運用できるか不安
1つでも当てはまる方は弊社にご相談ください。
弊社では勤怠管理ソフトの導入支援を行っています。
現状を把握できていないのであれば、まずはご相談ください。
現状の労働時間の把握を行い、残業時間があまり発生していなければ問題ありませんが、そうでなければ対応が必要です。勤怠管理は徹底してるけど何十時間も残業時間が発生している、という状態では問題を解決したことにはなりません。根本的な解決を行うためには、業務そのものを見直す必要があります。
働き方改革は稼ぎ方改革とも言われています。
・採算は合っているのか
・無駄なことをしていないか
など、業務そのものを見直すことも必要です。
弊社では給与計算、手続き代行サービスや人事評価制度の作成などの支援を行っています。
経営者や幹部が本業に専念するための時間を作るため、アウトソーシングについてもぜひご検討ください。
稼ぎ方改革を一緒に進めていきましょう!

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」