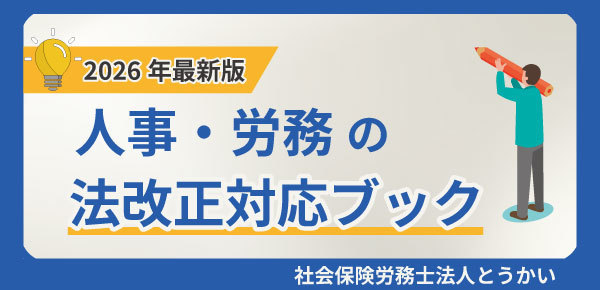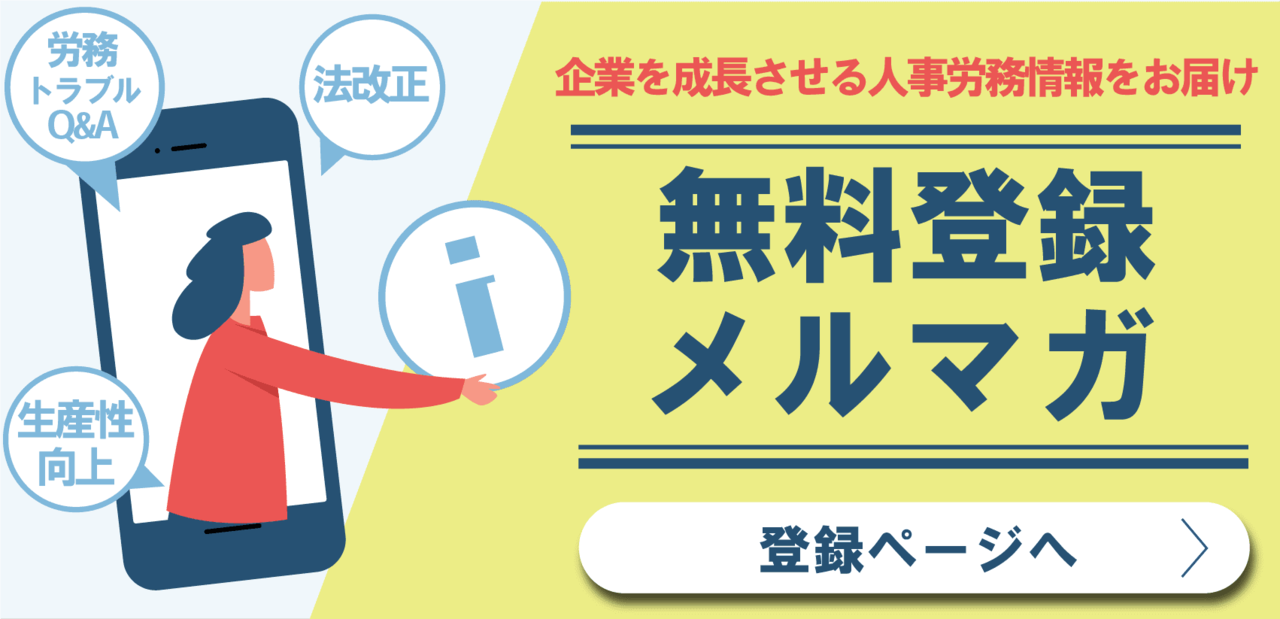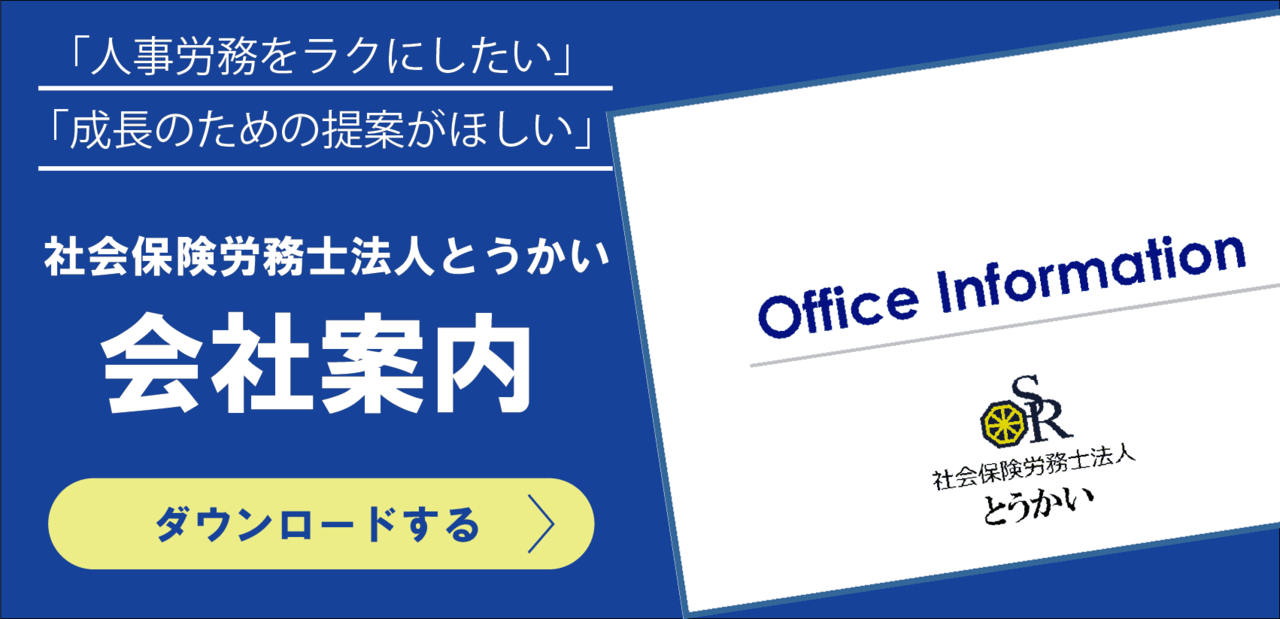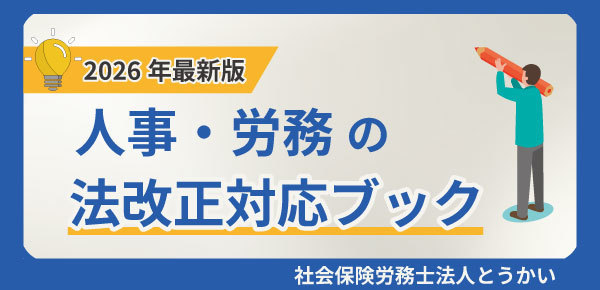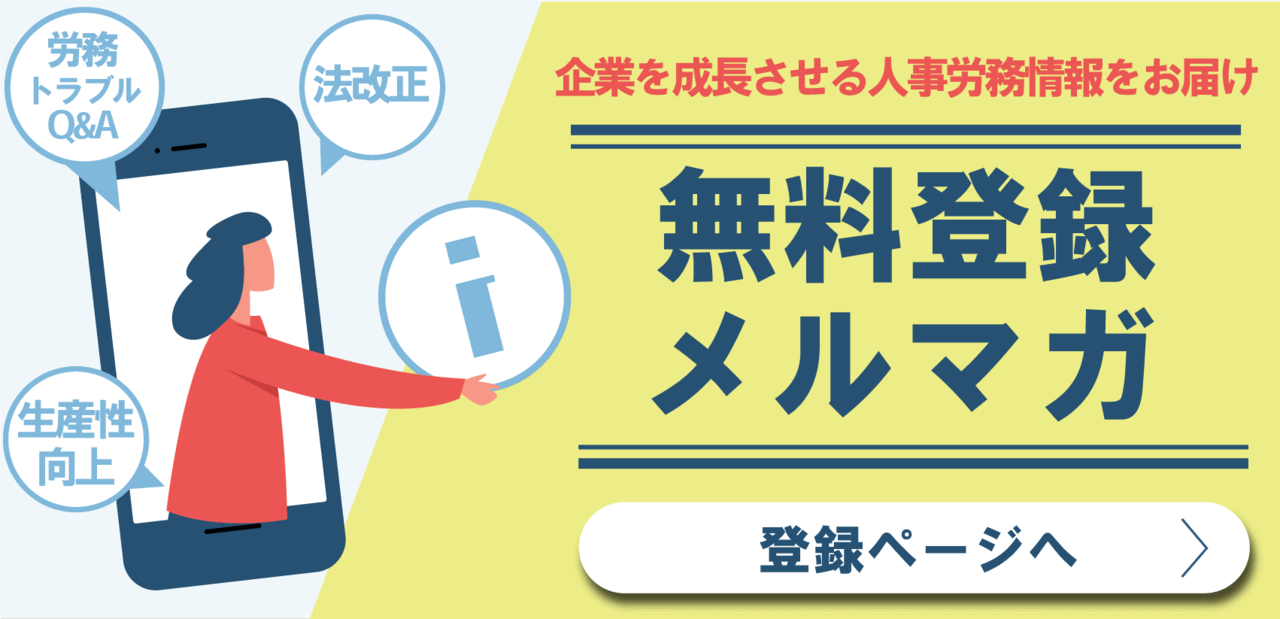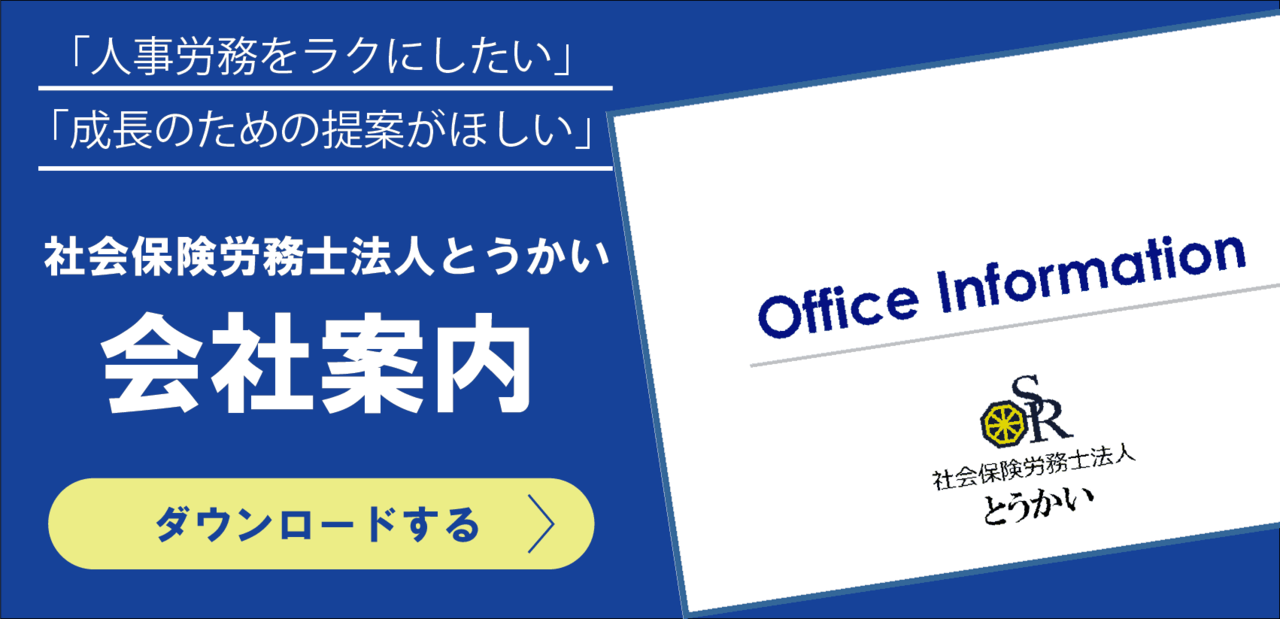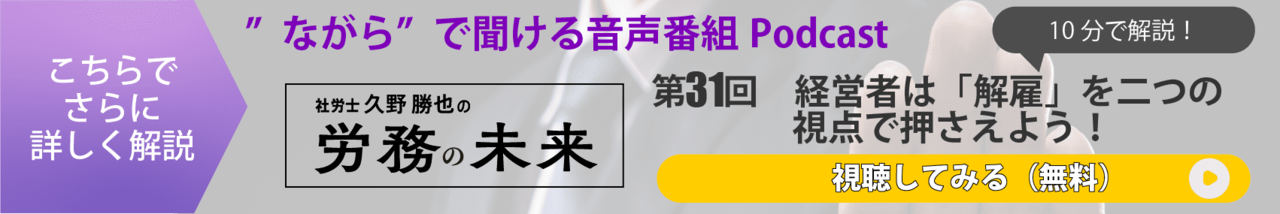就業規則と解雇。解雇について社労士が解説します

会社から解雇を告げられたり、解雇を示唆されたりした場合、多くの人が自身の今後について大きな不安を感じます。
しかし、会社は従業員を自由に解雇できるわけではなく、法律によって厳格なルールが定められています。どのような場合に解雇が認められ、どのようなケースが不当解雇となるのか、その判断基準や対処法について知っておくことは、自身の権利を守るために不可欠です。
この記事では、解雇の種類や法的な規制、不当解雇を疑った際の具体的な対応策について解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、企業活動に多大な影響を及ぼしています。ウイルス感染の終息時期が見えず、通常の事業継続が困難となるなか、解雇や雇い止めなどの人員整理を行う事例が増え始めているようです。とはいえ、業績が悪化したら即人員整理といった単純なものではありません。
まず念頭に置かなければならないのは、解雇は最終手段だということ。ウイルスはいずれ終息する時期が訪れます。安易に解雇を行って人員削減した結果、事業が再開できる時期に適切な人材がいなかったのでは、それこそ事業継続は成り立ちません。役員報酬の減俸や経費の削減など、打てるべき施策を行っているのか、またそもそも解雇などの人員整理を行わなければならない状況と認められるのかといった視点が必要です。そして、それでも人員整理もやむを得ない状況である場合、企業はどのような措置を講じるべきなのか。
この新型コロナウイルスが収束し、企業活動を本格再開するときに成長にドライブをかけられるように、自社にとっての解雇が将来どのような影響を及ぼすのか考えていきましょう。
※2020年4月5日時点での情報に基づき執筆しています。厚生労働省などの最新情報もあわせて確認していただくこともおすすめします。

名古屋の社労士 小栗です。
解雇には厳格なルールがあります。
解雇についての基礎を解説します。
解雇を行うには一定のルールがあり、ルールに反した解雇は「不当解雇」となります。不当解雇は、今回の新型コロナウイルスでの国難とも呼ぶべき事態であっても同様です。慎重に進めなければ、解雇後に従業員から不当解雇を主張され、労働審判や裁判などのトラブルに発展しかねません。ここで、解雇の定義を確認していきましょう。
まず、会社と従業員は、労働契約を締結しています。従業員からの申し出によって、労働契約が終了する場合は退職となります。期間を定めた労働契約が満了した場合も同様です。
一方で、期間を定めていない労働契約や期間を定めている場合であっても、その途中で契約を終了するなど、その労働契約を会社側の意思によって解消することが解雇となります。
ただし、退職勧奨を行った結果、従業員が自主的に退職する場合は解雇にあたりません。

解雇は慎重に判断すべきものです。まずは解雇の定義を押さえておきましょう。
解雇と一言で言っても、いくつかの種類があります。その種類をみていきましょう。
普通解雇とは懲戒解雇・整理解雇以外の解雇のこと。一般的に、会社側と従業員の信頼関係が破綻したことによる労働契約の解除です。例えば、従業員の無断欠勤や遅刻が頻繁にあるなどの勤務状況や勤務態度、職務遂行能力の不足、業務命令違反、病気やけがによる就業不能といった就業規則に規定される従業員の責任を理由に行われる解雇が該当します。とはいえ、就業規則に記載しているからと直ちに解雇が認定されるわけではありません。
過去に能力不足を理由に解雇されたり、病気を理由に解雇されたケースで、元従業員が裁判で解雇の無効を求め、認められたこともあります。就業規則に定めをしていたとしても、本当に解雇が適切か否かは、慎重に判断されるわけです。
わかりやすくイメージすると「リストラ」に該当するのが整理解雇。経営状態の悪化で事業存続のためにやむを得ず人員を削減しなければならない場合に行う解雇です。
今回の新型コロナウイルス感染拡大による経営悪化が原因で、人員削減するといった解雇の場合、整理解雇に該当します。ただし、リストラは本来「restructuring(再構築)」を意味しますので、厳密に言えば、「従業員の解雇(整理解雇)」に留まりません。希望退職者の募集、有期雇用契約の雇止め、不採算部門の整理なども、リストラに含まれますので注意してください。
整理解雇は基本的には従業員に落ち度はありません。いくら経営状態が悪化したとしても、無条件で解雇が認められるわけではありません。以下の4つの要件を満たして初めて認められます。
① 整理解雇の必要性があること
② 解雇回避の努力をしたこと
③ 解雇者の選定が合理的であること
④ 手続きの相当性があること
懲戒解雇とは、解雇の中で最も厳しい措置です。就業規則に規定する懲戒処分のなかで、最も重い処分です。従業員が窃盗や傷害といった犯罪を犯したり、横領や機密情報の漏えいなどといった会社の秩序を著しく乱して、ダメージを与えた際などに科すことができる制裁罰のひとつです。通常、退職金は支払われず、支払われても大幅に減額されます。
懲戒解雇が認められるには、普通解雇より相当悪質である必要があります。普通解雇で足りると判断される場合には、懲戒解雇としては無効と判断されます。
諭旨解雇の「諭旨」とは、理由などをよく説いて知らせ、言い聞かせることの意味があります。つまり、諭旨解雇とは、懲戒解雇相当ではあるものの、会社と従業員が話し合い、諸事情を勘案し、解雇するというもの。前述の最も重い懲戒解雇よりも少し軽い処分です。従業員の反省の意図や、従業員の将来を考慮し、懲戒解雇を避ける温情措置として行われることなどが多いです。


不当解雇とは何か、詳しく解説していきます。
不当解雇とは、法律で定められた解雇の要件を満たさず、法的に無効となる解雇のことです。
会社が従業員を解雇するには、正当な理由と適切な手続きが不可欠であり、これらを欠く解雇は労働者の権利を不当に侵害するものと判断されます。
具体的には、解雇の理由に客観的な合理性がない場合や、理由に対して解雇という処分が重すぎる場合、さらには法律で解雇そのものが禁止されている特定の状況に該当する場合などが、不当解雇と判断される主なケースです。
解雇が有効とされるためには、まず「客観的に合理的な理由」が必要です。
これは、誰が見ても納得できるような、解雇を正当化する具体的な事実が存在することを意味します。
例えば、勤務成績不良を理由とする場合、単に上司の主観的な評価が低いだけでは不十分です。
客観的な指標で成績が著しく劣っており、会社が注意や指導、研修の機会を与えても改善の見込みがないといった事実が求められます。
同様に、協調性の欠如を理由にする場合も、具体的なトラブルの事実や、それによって業務に重大な支障が生じたことなどを証明できなければ、合理的な理由があるとは認められません。
解雇には客観的に合理的な理由があったとしても、「社会通念上相当」でなければ無効となります。
これは、従業員の行為や状態に対して、解雇という処分が重すぎないかというバランスの問題です。
例えば、一度の遅刻や軽微な業務上のミスを理由に即座に解雇することは、通常、社会通念上の相当性を欠くと判断されます。
会社側は、解雇の前に、注意指導や研修、配置転換といった、より軽い処分や解雇を回避するための努力を尽くしたかどうかが問われます。
問題の程度と処分内容を比較し、解雇が最終手段としてやむを得ないといえる場合にのみ、相当性が認められる傾向にあります。
特定の理由や期間における解雇は、労働基準法などの法律によって明確に禁止されています。
例えば、業務上の怪我や病気のために休業している期間と、職場復帰後30日間の解雇は認められません。
同様に、女性労働者の産前産後休業期間と、その後の30日間の解雇も禁止されています。
その他にも、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする差別的な解雇や、労働組合に加入したり正当な組合活動を行ったりしたことを理由とする解雇、育児・介護休業の申出や取得を理由とする解雇も法律で禁じられており、これらの規定に違反した解雇は当然に無効となります。

解雇に関連する労働法を正しく理解することが必要です。
これまでみてきたように、解雇にもさまざまな種類があり、ましてや解雇に至る状況や個別の事情を大きく影響するため、簡単に解雇を行使できません。労働契約法においては、以下のような解雇権濫用の法理を定めています。また、期間の定めのある労働者についても、解雇については、慎重に判断する必要があります。
【労働契約法16条】
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする
【労働契約第17条】
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
解雇は、従業員(労働者)にとっては、突然に収入を断たれるという極めて重大事です。生活が立ち行かなくなることもあるため、会社(使用者)側の判断のみに任せるのではなく、法律により一定の制限が設けられているのです。
さらに、労働者を保護する観点から、労働契約法以外にも、労働基準法などで解雇に制限や規則が設けられています。労働基準法による解雇のルールは大きく分けて以下の4つです。
①解雇の事由(どのような事情で解雇になるか)を入社時に書面で明示すること
②解雇を行うには原則30日前に予告を行うこと
③労災事故によるケガや病気、産前産後の休業中およびその後30日間の解雇はできないこと
④法令違反の申告や、有給休暇を取得をしたことを理由として解雇はできないこと
【労働基準法20条】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

労務チームの島です。やむを得ず解雇を行う場合には、解雇予告が必要です。解雇予告手当の算出方法についてもチェックしておきましょう。
やむを得ない事情があり従業員を解雇したものの、後日、解雇した従業員から訴えを起こされることもあるかもしれません。解雇不当の訴えを起こされないためには、まず、解雇が行われる際に、解雇の予告が行われていることが必要です。労働基準法では、30日前までに労働者に解雇することを通知しなくてはならないとされています。ただし、以下の場合には、例外的に解雇を事前に予告することなく解雇が可能とされています。
①解雇予告期間に代えて30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う。なお、解雇予告に必要な日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することも可能。
②日雇いの労働者で雇用開始後1か月以内に解雇する場合
③使用期間中の労働者で雇用開始後14日以内に解雇する場合
④解雇予告除外認定により認定を受けた場合
解雇予告手当は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
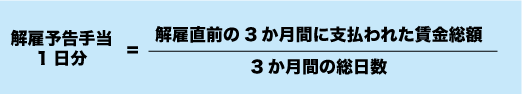
入社からの3か月経過していない場合、
(解雇予告手当1日分)=(入社月から解雇予告日直近の賃金締日までの賃金総額)÷(入社時からの総日数)さらに、解雇予告手当の支払い時期は解雇と同時にされなければなりません。
解雇予告、解雇予告手当の支払いが行われていない解雇は、解雇通知後30日を経過するか解雇予告手当の支払いがなされるまでは無効とされます。
「30日後の○月○日に解雇」といった解雇予告は、口頭でも法的効力は生じます。とはいえ、口頭による解雇予告には「言った・言わない」といった問題が生じやすいものです。解雇が予告されたタイミングも証拠として残すことができません。解雇予告手当の支払いにも影響するものですので、解雇の日付や解雇理由など内容を書面で明示し、通知することをおすすめします。
メールや郵送などの手段の違いによっても、本人に到達するタイムラグが生じる可能性もありますので、解雇予告の日付や解雇予告手当の計算に誤りがないようにする必要があります。送信済みのメールを保管したり、内容証明郵便を利用したりと、証拠が残るようにしておきましょう。
従業員に直接手渡しし、受領書を受け取るのが確実かもしれません。
口頭で解雇を行った場合など、解雇予告を行った従業員から「解雇理由証明書」の請求を求められることがあります。その場合には、会社は「解雇理由証明書」を作成し、従業員に交付しなければなりません。これらは労働基準法第22条により義務づけられており、違反した場合は6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金が科せられることもあります。
【解雇理由証明書に記載すべきこと】
・解雇する人の氏名
・解雇を通知した日付
・発行した日付
・代表者、責任者の氏名(押印)
・解雇理由

不当解雇となるのは、どのようなケースなのでしょうか?
- 従業員を復職させなければならない
解雇ははじめからなかったものとして、労働契約が続いているということになります。会社は従業員を復職させ、給与の支払いを行う必要があります。
- 解雇期間中の給与を遡って支給しなければならない
- 損害賠償(慰謝料)を支払わなければならないケースもある
【クレディ・スイス証券事件(東京地判平成23年3月18日)】
・金融市場の悪化でハイリスクの金融商品の販売事業から撤退した。当該事業に従事していた労働者を解雇したことについて、裁判所は当該解雇を無効としたケース
・会社が販売事業から撤退したことで、解雇の必要性は一応肯定されたが、従業員を自宅待機命令から1年以上経過後に解雇しており、解雇の必要性の程度は高度とはいえない。
・また、当該従業員の解雇後に、従業員の年俸を引き上げたり、4人の退職勧奨を行った直後に新規に4名の採用を行うなど、解雇回避努力が不十分とされた。
【PwCフィナンシャル・アドバイザリー・サービス事件(東京地判平成15年9月25日)】
・マネージャーとして採用した従業員が所属する部門を廃止したため、当該者を解雇したことについて、解雇を無効としたケース。
・部門の不振による損失での廃止は、人員整理の必要性が認められる。
・ただし、従業員の能力不足や人員を削減すること以外施策がないといった具体的根拠を示すものがなく、解雇回避措置をとることが困難とは認められない。
・従業員がマネージャーとしての能力が著しく劣っているとすることは困難であり、整理解雇の対象としたことの合理性は認められない。

不当解雇をされたときの解決策についてご説明します。
会社から解雇を告げられ、その理由に納得できない、あるいは不当だと感じた場合、感情的にならず冷静に対応することが重要です。
まずはその場で安易に同意せず、自身の権利を守るための初動を適切に行う必要があります。具体的には、解雇の意思表示をしないこと、証拠を確保すること、そして専門家への相談を視野に入れながら、会社との交渉や法的な手続きを進めていくことになります。
ここでは、実際に不当解雇の可能性がある場合に取るべき具体的な対応策を段階的に解説します。
解雇を告げられた際に最も重要なことは、その場で解雇に同意するような言動をしないことです。
「わかりました」「承知しました」といった返答は避け、「少し考えさせてください」などと回答を保留する姿勢が賢明です。
特に、会社から退職届や退職合意書の提出を求められた場合は、絶対に応じてはいけません。
これらの書類に署名・捺印してしまうと、自らの意思で退職した「自己都合退職」として扱われ、後から不当解雇を主張することが極めて困難になります。
たとえ「解雇だが、自己都合という形にしてほしい」などと説得されても、決して応じず、まずは専門家に相談することを優先してください。
解雇に同意しない姿勢を明確にした上で、次のステップとして会社との交渉が考えられます。
まずは、解雇を承諾しておらず、今後も働く意思があることを明確に示すため、内容証明郵便で「解雇撤回通知書」などを送付することが有効な手段です。
この通知書の中で、併せて「解雇理由証明書」の交付を請求し、会社側が主張する解雇理由を正式な書面で明らかにさせます。
理由が明らかになれば、それに対する反論を準備し、交渉を進めることができます。
個人での交渉が難しいと感じる場合は、労働組合に加入して団体交渉を申し入れたり、弁護士に代理人として交渉を依頼したりすることも有力な選択肢となります。
不当解雇を争う場合でも、必ずしも職場への復帰を望むわけではないケースも少なくありません。
会社との信頼関係が崩れてしまい、復職しても働き続けるのが難しいと感じる場合、金銭的な解決を目指すという選択肢があります。
これは、解雇の無効を前提としつつ、会社との労働契約を双方合意の上で終了させる代わりに、会社側から解決金を支払ってもらうという方法です。
解決金の額は、解雇期間中に得られたはずの賃金(バックペイ)や慰謝料などを考慮して交渉されます。
この解決方法は、当事者間の交渉のほか、労働審判や裁判上の和解といった法的な手続きを通じて行われることが一般的です。
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大に関連した解雇や雇い止めの見込みが、2020年8月7日時点で4万4,148人と発表しました。1週間前の2020年7月31日時点から2,757人増え、このうちパートや派遣社員などの非正規労働者が1,548人という結果となりました。都道府県労働局の聞き取りや公共職業安定所に寄せられた相談・報告等をもとにした数字であり、実際の解雇や雇い止めの人数はもっと多いとみられています。
業種別では、観光客の減少や外出の自粛の影響を受けた、宿泊業や飲食業が目立つほか、アパレルや製造業など、多くの業界で影響が出ています。もちろん、引き続き業績好調の業種もありますが、新型コロナ関連の影響をまったく受けていない企業のほうが少ないと言えるでしょう。
現状、解雇や雇い止めの影響は、非正規労働者の割合が大きいものですが、今後は予断を許さない状況でしょう。日本経済新聞の大手企業へのアンケートによると、経営者の新型コロナウイルス影響の懸念として、「資金繰り」「取引先の倒産」「売掛債権の回収」を挙げており、大手企業ゆえに内部留保があるとはいえ、先行きを大きく危惧しています。
国内消費が減少し、輸出産業も世界的な需要不足も影響してくれば、現段階で解雇・雇い止めを行っていなくとも、将来の経営を見越して、検討段階に入った企業もあるでしょう。最近では大企業の希望退職募集のニュースが取り上げられることが増えてきました。
一方、新型ウイルスの影響による解雇・雇い止めを防ぐため、注目されているのが「雇用調整助成金」です。制度が拡充され、2020年7月末時点で、申請が66万2,247件に上り、うち支給決定されているのが54万8,462件となっています。厚生労働省は、企業に対し助成金を活用して従業員の雇用を維持するよう呼びかけています。
ここまでご説明してきたとおり、解雇は容易には認められません。それは、コロナの影響があっても同様です。できる限り解雇以外の手段をとる必要があります。とはいえ、整理解雇を実施せざるを得ない状況もあるでしょう。
従業員には、具体的な数値を示したり、選定基準を説明し、できる限り理解を得られるよう丁寧に対応することが重要です。

コンサルタント大矢の経営視点のアドバイス
解雇は「首切り」と言われ、従業員の生活を一変させる行為です。
経営の一時的な不調で判断できる行為ではありません。解雇を行う場合、さまざまな視点から解雇の合理性や社会通念上の正当性を判断されることになります。とはいえ、絶対に解雇できないわけではありません。トラブル社員で頭を悩ませているのであれば、まずは専門家にご相談ください。

一度ご相談ください。状況を整理します。
いかがでしたでしょうか?
今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続けば、整理解雇を行分ければならない企業もでてくることにならざるを得ないと思います。
いくら人間関係ができていたとしても、退職や解雇のこととなるとトラブルがつきものです。今まで同じように、会社のために頑張ってきたとしてもです。残念ながら過去の事例が物語っています。
だからこそ、解雇や退職にかかわる事案に関しては、慎重にすすめなければなりません。該当の方と対話をすることから逃げてはいけません。
企業は対話をし、十分な努力を行いましょう。まずはそこからだと思います。
十分な対話を行ったうえで、法律面のサポートが必要になるケースも多々あります。解雇において同じ状況というのは存在しません。数多くの事例と向き合ってきた私たちが社会保険労務士の立場で支援できることもあると思っています。
「解雇」を思いついたとしても安易に解雇権を行使せず、一度専門家にご相談ください。
お客様の声
企業の成長をリードしてくれる安心して
人事労務をお任せできる社労士事務所です

KRS株式会社
代表取締役 清野光郷 様

KRS株式会社 代表取締役 清野光郷様
岐阜県 鳶工事業 従業員数23名
労務相談の顧問や就業規則の整備をお願いしています。そもそも私自身の考えになりますが、社員の成長と私自身の成長が、会社自体の伸びにつながると考えています。そして、そのためには働くための当たり前の体制が整備された「まともな会社」であることが前提となるでしょう。そこの組織づくり・成長する基盤づくりを進めるにあたっての不安点をよく相談しています。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」