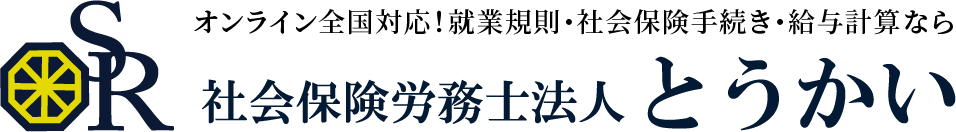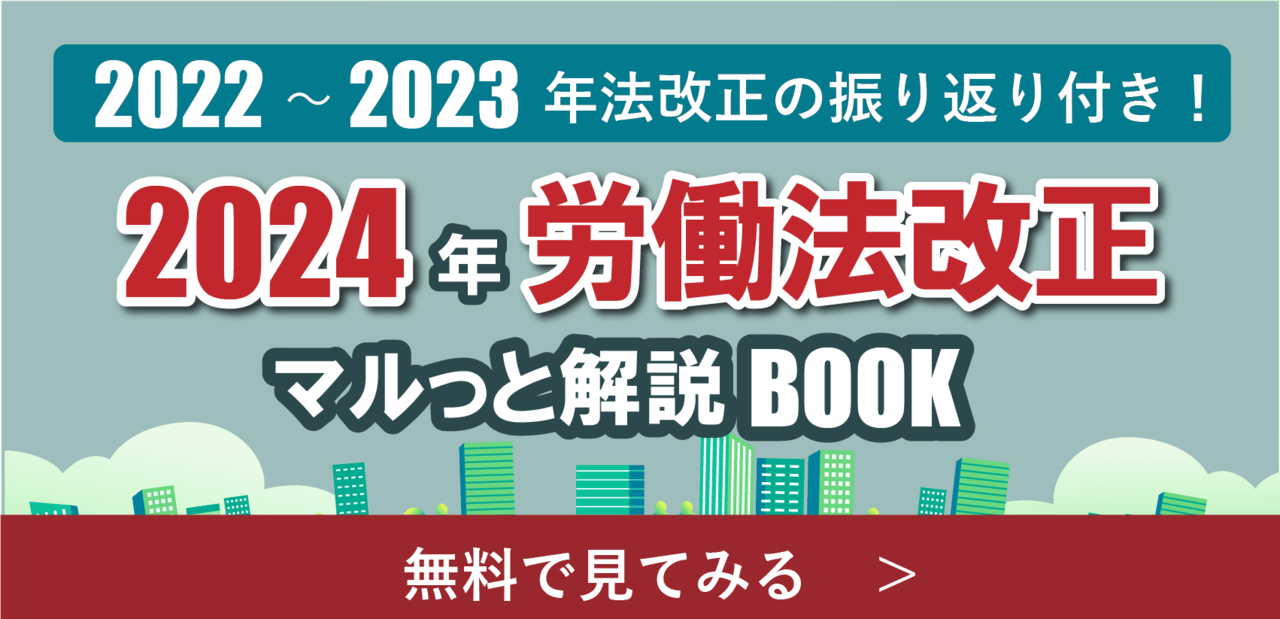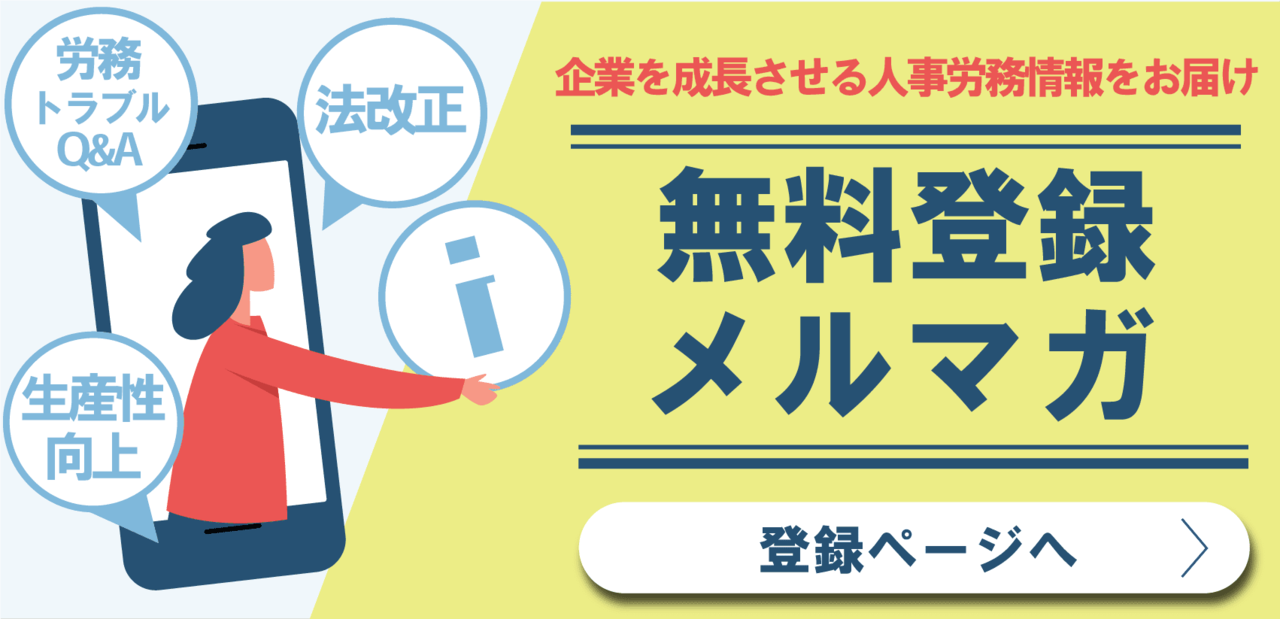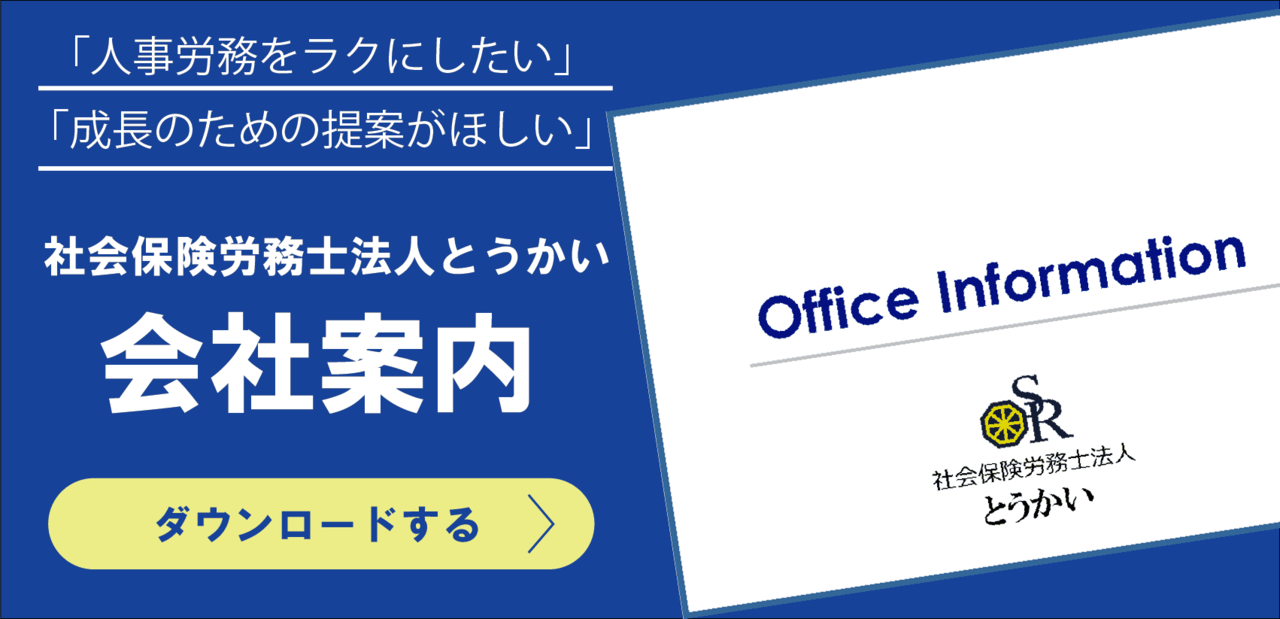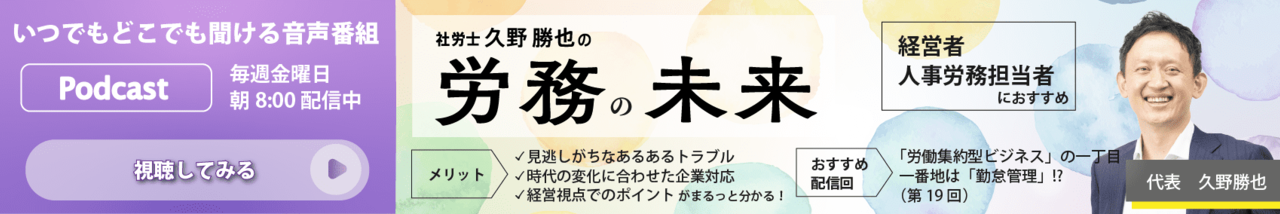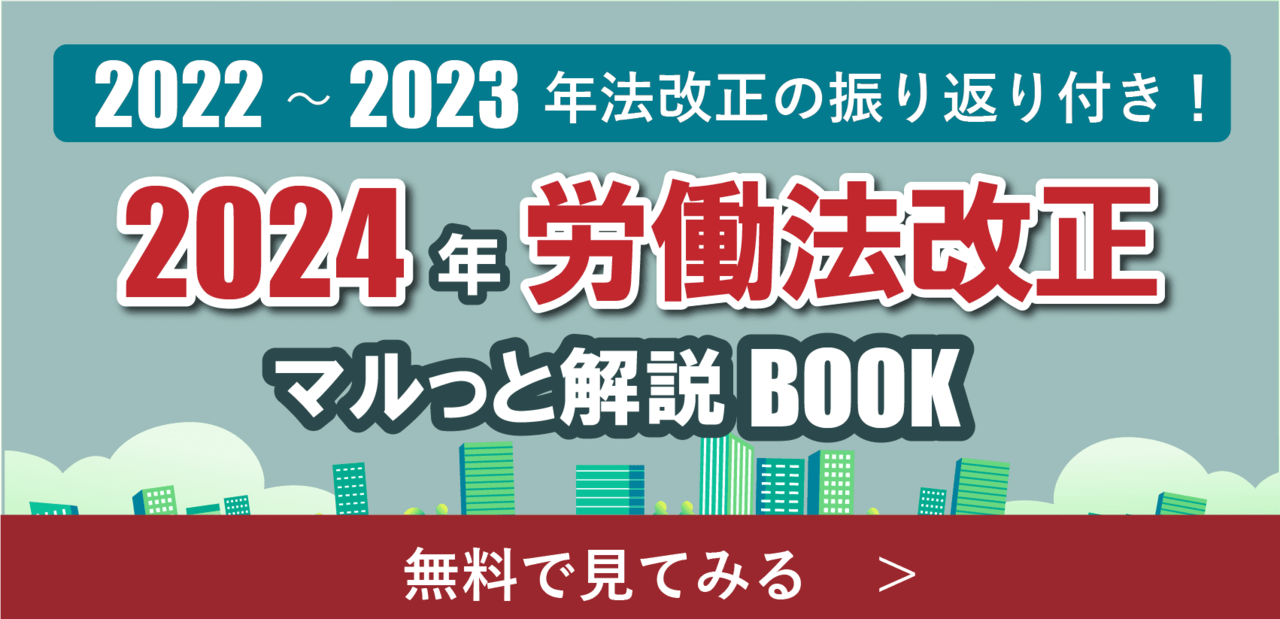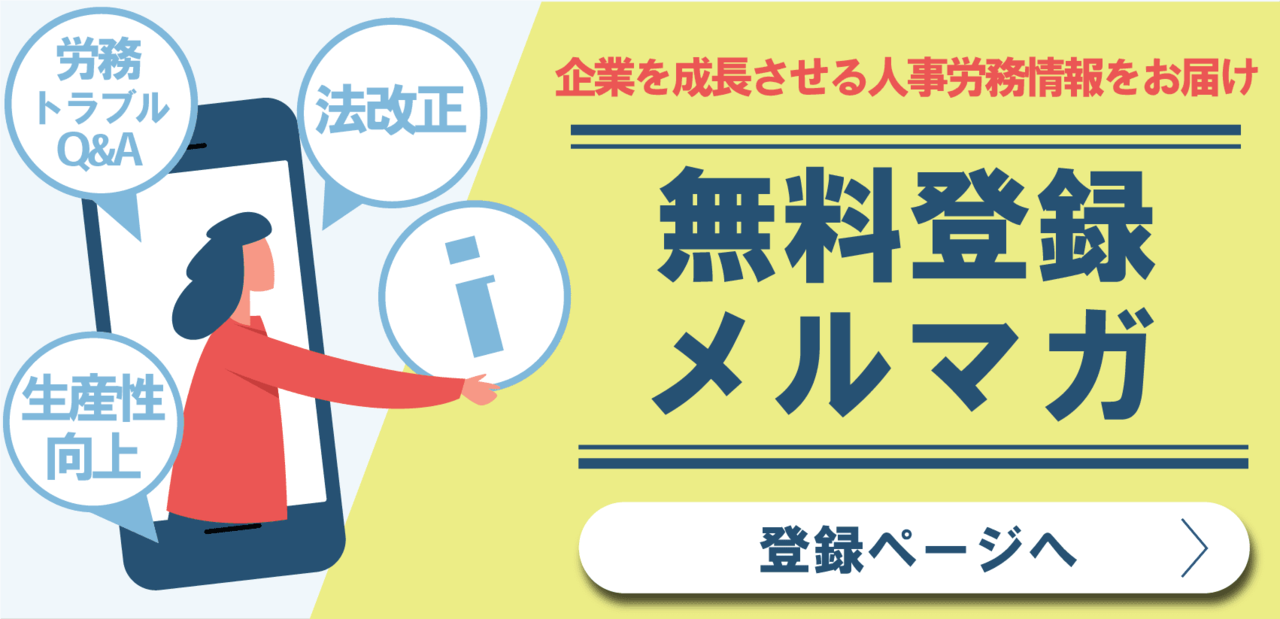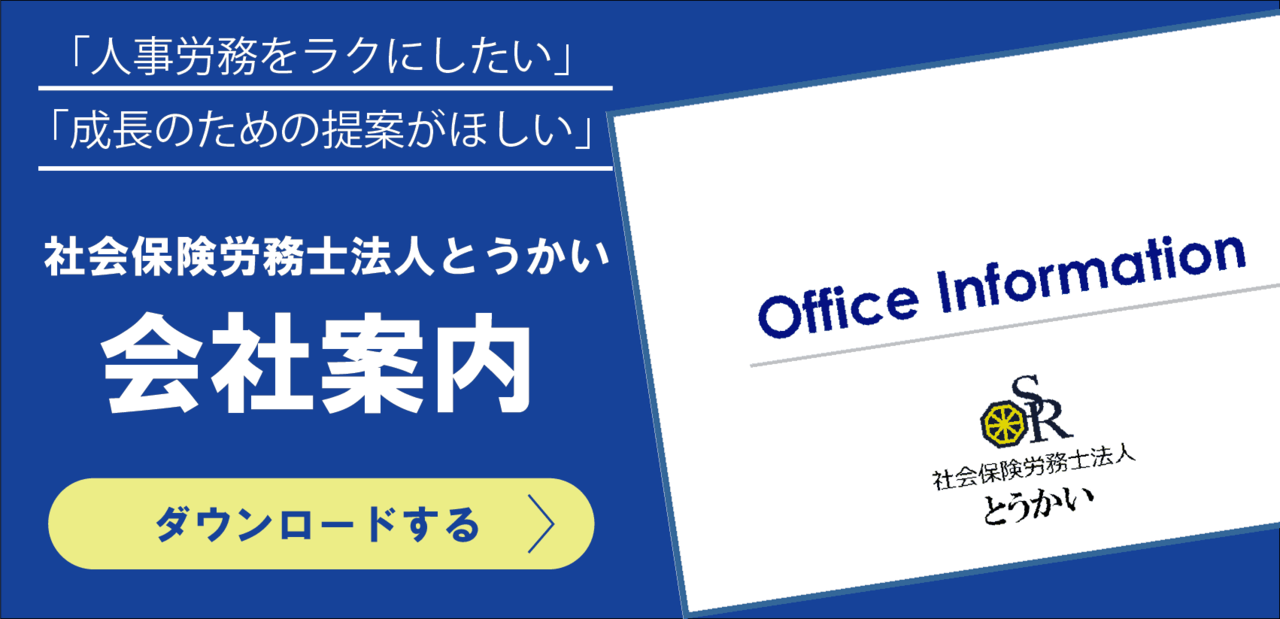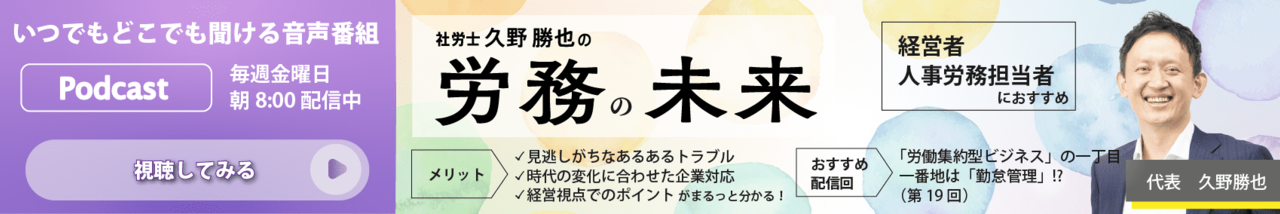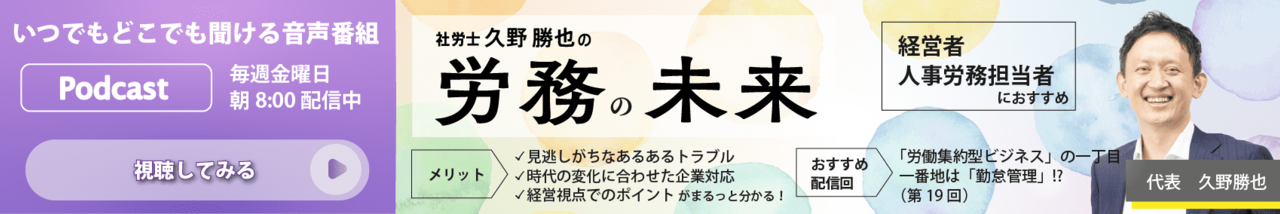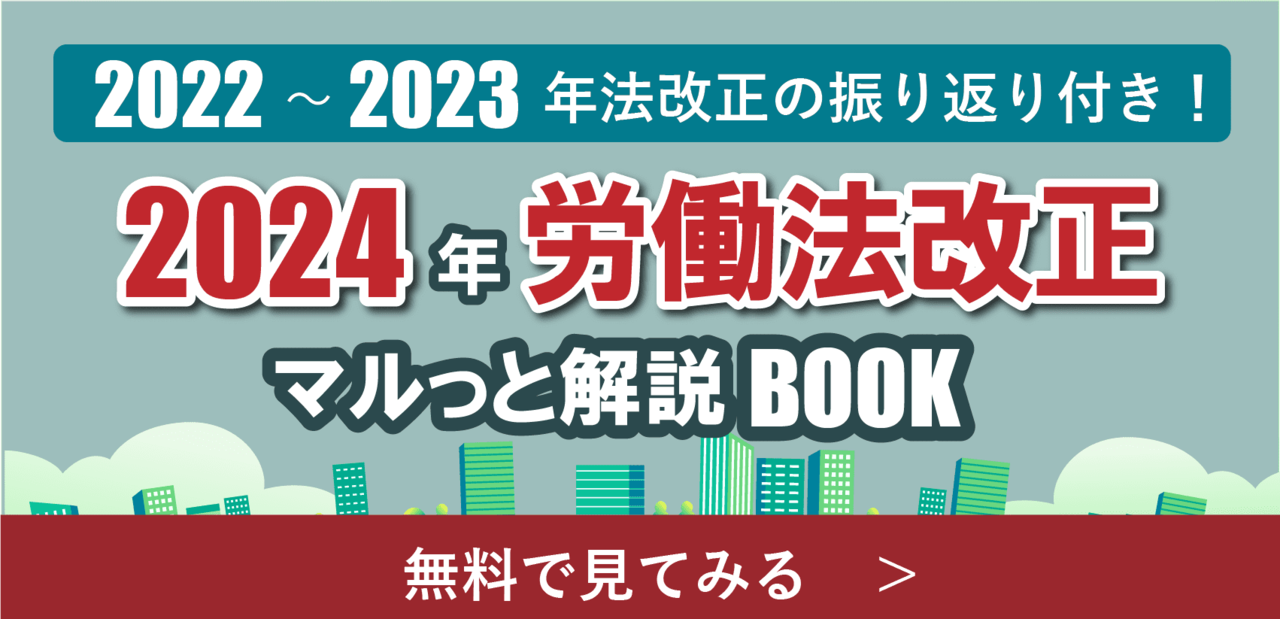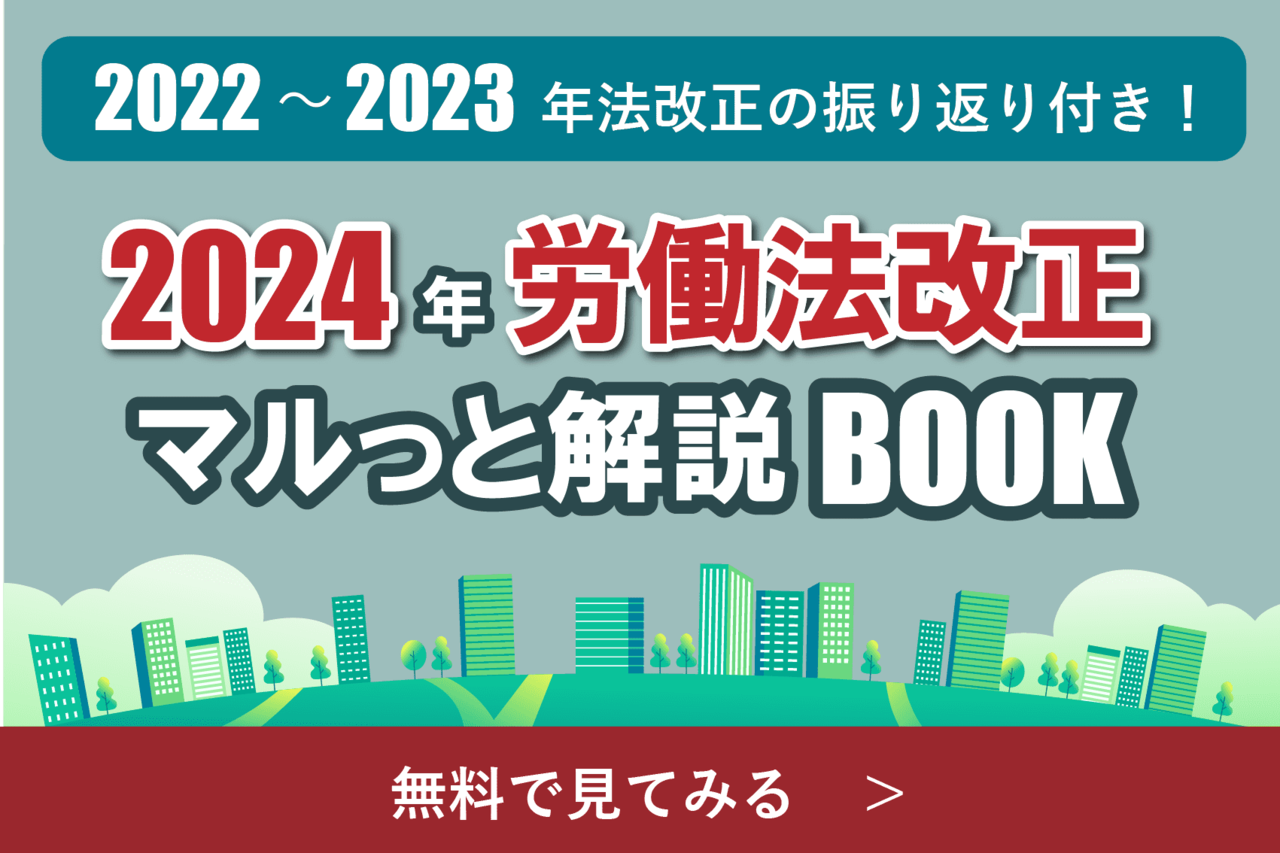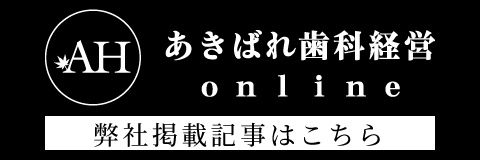同一労働同一賃金とは?
改正後のパートタイム・有期雇用労働法について社労士が解説します。

2019年4月からスタートした「働き方改革関連法」ですが、とくに注目されていることの一つに「同一労働同一賃金」に関わる「パートタイム・有期雇用労働法」や「労働者派遣法」の改正が挙げられます。
現在、日本での非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)は、働く人全体の4割を占めています。非正規雇用労働者の待遇は、正規雇用労働者に比べて大きな差があると言われてきました。同じ企業で働く正規従業員と非正規従業員の間の不合理な待遇の相違を解消することを目的に、法改正がされました。
今回は、「同一労働・同一賃金」の法改正の概要と企業がおさえておきたいポイントを解説していきます。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

中小企業の施行日が迫ってきました。未対応であれば、早急に準備を進めましょう。
同一労働同一賃金とはどのようなものなのでしょうか。また、いつから適用されるのでしょうか。
同一労働同一賃金とは、企業や団体の正規雇用労働者と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。同じ仕事をしているならば、正規従業員であるか非正規従業員であるかを問わず、同一の賃金を支給すべきという考え方です。
不合理な待遇差の解消し、どのような雇用形態であっても納得感のある処遇によって、さまざまな働き方を自由に選択できる社会を目指しています。
同一労働同一賃金に関わる改正法は、すでに2020年4月からスタートしています。
「パートタイム・有期雇用労働法」とは、短時間労働者を対象とした「パートタイム労働法」に、フルタイム有期雇用労働者も対象に加えて名称を変更した法律です。
大企業においては、すでに2020年4月1日から施行スタートし、中小企業については2021年4月1日より施行が予定されています。
中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者」のいずれかが以下の基準を満たしていることとなります。
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他(製造業、建設業、運輸業、その他) | 3億円以下 | 300人以下 |
「労働者派遣法」とは、正規従業員に比べて弱い立場である派遣従業員を守る法律です。派遣従業員を受け入れる企業は、人材不足や業務量調整のための人員補充といった目的で受け入れ、企業の都合で派遣契約期間が終了となることも多いのが実情です。派遣従業員にとっては勤務日数や曜日など働き方を柔軟に決められるというメリットがある半面、賞与などの支給がないために正規従業員に比べて、年収が少ない、福利厚生の恩恵を受けられないといった面があります。
そのため派遣従業員の権利を守ることを目的に制定されたのが「労働者派遣法」です。
そして、この「労働者派遣法」も同一労働同一賃金の適用にあわせ、2020年4月1日より、施行がスタートしました。

同一労働同一賃金のために人事制度の整備を進めるうえで、「均衡待遇」「均等待遇」についての理解は必須です。
「同一労働同一賃金」の主な改正は、以下の3つです。
不合理な待遇さをなくすための規定の整備が必要です。正規従業員と非正規従業員との間で、基本給や賞与などの待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
どのようなことが不合理であるのか判断する基準として「均衡待遇」と「均等待遇」という考え方があります。
均衡待遇とは
均衡待遇とは、以下の3点を考慮して不合理な待遇差を禁止、つまりバランスの取れた待遇にしなければなりません。
① 職務内容
「業務内容」とそれに伴う「責任の程度」のことです。従業員の実態から判断され、最も重要なポイントとなります。「業務内容」は、業務の種類(職種)と個々の業務の中核的業務であるか判断します。
また、「責任の程度」については、業務に伴って与えられている権限の範囲を言います。単独で契約締結可能な金額の範囲や、部下の人数、決裁権限の範囲、業務の成果について求められる役割、トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度によって、判断されます。例えば、正規従業員が繁忙期や急な欠勤者により対応が求められ残業などが増加するのに対し、非正規従業員には対応が求められないとすれば、業務の責任の程度が異なると判断されます。
② 職務内容・配置の変更範囲
転勤や昇進などの人事異動や役割の変化等の有無や範囲など人材活用の仕組み・運用のことをいます。正規従業員が転居を伴う全国転勤があるのに対し、非正規従業員は自宅から通勤できる範囲のみの異動に限られているといった場合は、職務内容・配置の変更範囲が異なると判断されます。
③ その他の事情
その他の事情は、職務の成果・能力・経験をはじめ、合理的な労使慣行、労使交渉の経緯など様々な事情が含まれます。
均等待遇とは
均等待遇とは、以下の2点がまったく同じ場合は、差別的取り扱いを禁止し、すべての待遇について同じ取り扱いにしなければなりません。
① 職務内容
② 職務内容・配置の変更範囲
今後、パートタイマー、有期雇用や派遣などの非正規雇用従業員は、「正規従業員との待遇差の内容や理由」について説明を求めることができるようになります。会社は、非正規雇用従業員からの求めに応じて説明する義務を負うことになります。待遇差の理由を「パートだから」では、説明の義務をはたしていることにはなりません。なぜそのような待遇差が生じているのか、丁寧に説明しなくてはなりません。
また、説明を求めた従業員に対する「不利益取り扱いの禁止」の規定も設けられました。
従業員への説明あたって、どのように説明すべきか、確認しておきます。
誰と比較するか?
誰と比較するか、比較対象を確認します。説明を受けるパートタイム・有期雇用従業員の比較対象となる正規従業員が、誰になるのかを確認する必要があります。
待遇差の内容
待遇差の内容の説明については、比較対象となる正規従業員との間で待遇に関する基準に違いがあるかどうかを説明します。さらに比較対象となる正規従業員とパートタイム・有期雇用従業員などの非正規従業員それぞれの待遇の内容や待遇に関する基準とどのような差があるのかを説明します。
待遇差の理由についても説明しなくてはなりません。「職務内容」「職務内容・配置の変更範囲」「その他の事情」のうち、個々の待遇の性質・目的に照らして説明していきます。成果、能力、経験などによって差が生じているのであれば、その違いを説明します。
どのように説明するか?
どのように説明するかについては、パートタイム・有期雇用従業員などの非正規従業員が、わかりやすいよう、資料(就業規則や給与規程、賃金表など)を活用しながら口頭で丁寧に説明することが基本です。
ただし、説明すべき事項を記載した資料で、わかりやすく理解可能な場合には、その資料を交付する方法でも差し支えありません。
有期雇用の従業員を雇い入れたとき
有期雇用の従業員を雇い入れたときには、本人に雇用管理上の措置の内容、待遇について説明することが義務付けられました。
行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定が整備されています。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象に含まれることになりました。
行政ADRとは、事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。事業主と労働者の間でトラブルが生じた場合、当事者の一方または双方の申し出があれば、都道府県労働局がトラブルの早期解決のための援助を行うというものです。
企業名や内容は非公表であり、調停会議での調停案について、当事者双方に成立した合意は、民法上の和解契約となります。

ガイドラインでは、不合理な待遇差の解消に向け、問題となる例・問題とならない例が解説されていますので、しっかりおさえておきます。
同一労働同一賃金については、ガイドライン(指針)が設けられています。正規従業員と非正規従業員との間で待遇差がある場合、どのような待遇差が不合理か不合理でないかの考え方が示されています。このガイドラインは賃金に限らず、教育訓練や福利厚生などすべての待遇についても求められています。
参照:「同一労働同一賃金ガイドライン」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
基本給の取り扱いは、3つの要素についてそれぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければなりません。
- 労働者の能力または経験に応じて支払うもの
- 業績または成果に応じて支払うもの
- 勤続年数に応じて支払うもの
また、昇給についても、労働者の勤続による能力の向上に応じて行う昇級は、同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を行う必要があります。
賞与の取り扱いは、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、業績等への貢献に違いがあれば、違いに応じた支給を行わなければなりません。賞与は各企業ごとにさまざまな基準があるでしょう。正規従業員には支給するが、非正規従業員は支給なしということがあるかもしれません。その場合には、企業において賞与の性質・目的に照らし、本当に説明がつくものかどうか確認する必要があるでしょう。
企業では、さまざまな各種手当を設けているケースが多いでしょう。こうした各種手当についても、確認していく必要があります。またガイドラインに載っていない退職手当、家族手当、住宅手当などの待遇や、具体例に当てはまらない場合であっても、不合理な待遇差の解消に取り組む必要があるとされています。
① 役職手当
役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければなりません。
② 職務内容と関連のある手当
業務の危険度または作業環境に応じて支給される特殊作業手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、業務の内容が同一の場合の精皆勤手当などは、それぞれの手当の性質・目的を踏まえて、同一の支給を求めることとしています。
③ 職務内容と関連の低い手当
所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で働く労働者に対する補償として支給する地域手当等についても、同一の支給を行わなければなりません。とくに、職務内容と関連の低い通勤手当や食事手当は、同一の支給を求められる可能性が高いと言われます。
①食堂、休憩室、更衣室
福利厚生施設の利用は、正規従業員と同一の利用を認めなければなりません。
② 転勤者用社宅・慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除、有給保障
正規従業員と支給要件が同じ場合は、同一の利用・付与を行わなければならないとされています。有給休暇その他の休暇なども、勤続期間に応じて認めているものについては、同一の勤続期間であれば同一の付与を行わなければなりません。有期雇用の従業員については、更新期間がすべて通算して勤続期間として判断されます。
③ 病気休職
無期雇用の従業員には正規従業員と同一の付与を行わなければなりません。
有期雇用の従業員であっても、労働契約が終了するまでの期間を踏まえ、同一の付与を行わなければなりません。
④ 教育訓練
現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じて実施する必要があります。
同一労働同一賃金のガイドラインは、正規従業員と非正規従業員がともに、共通の賃金の決定基準やルールを用いていることを前提に作成されています。しかしながら、多くの企業では、正規従業員と非正規従業員では異なる賃金決定基準やルールを採用しているケースも多いでしょう。その場合に、「パートだから」「期待する役割が異なる」といった主観的・抽象的な理由では、合理的な待遇差だとは認められません。「職務内容」「職務内容・配置の変更範囲」「その他の事情」の客観的・具体的実態に照らし、不合理でないか確認していくステップが必要となります。
定年後に継続雇用された有期雇用の従業員についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用されます。前述の均衡待遇における「その他の事情」において、定年後に継続雇用された者も考慮され得るとされています。ただ、待遇差が不合理であるかどうかの判断は、総合的に判断されることでもあるので、定年後の継続雇用の従業員と正規従業員に待遇差があったとしても、それだけで不合理ということではありません。

待遇差を解消する対応策については、労使で十分な議論を進めていく必要があります。一方的な対応策は、さらにトラブルに発展する可能性も。
では、非正規従業員との不合理な待遇差があった場合は、どうしたらよいでしょうか。待遇差を解消するにあたっては、留意すべき点が3つあります。
正規従業員と非正規従業員の待遇のバランスをはかろうと、正規従業員の待遇を引き下げることで、待遇差を解消とするのは望ましいものではありません。正規従業員にとっては一律に待遇を下げることは、不利益変更となります。一律に非正規従業員の待遇をアップするといった策も、人件費の増大など企業経営に与える影響は大きいでしょう。いずれにせよ慎重に対応すべき問題です。労使間での十分な話し合いも必要となってきます。
すべての雇用管理区分の正規従業員と非正規従業員との間で、不合理な待遇差の解消が求められます。・雇用管理区分が複数ある場合(総合職、一般職、地域限定正社員など)であっても、すべての雇用管理区分に属する正規従業員との間で不合理な待遇差がないよう解消が求められます。
正規従業員と非正規従業員との間で職務の内容等を分離した場合であっても、不合理な待遇差の解消が求められます。職務内容が異なっていても、内容の違いに応じてバランスの取れた待遇にする必要があります。
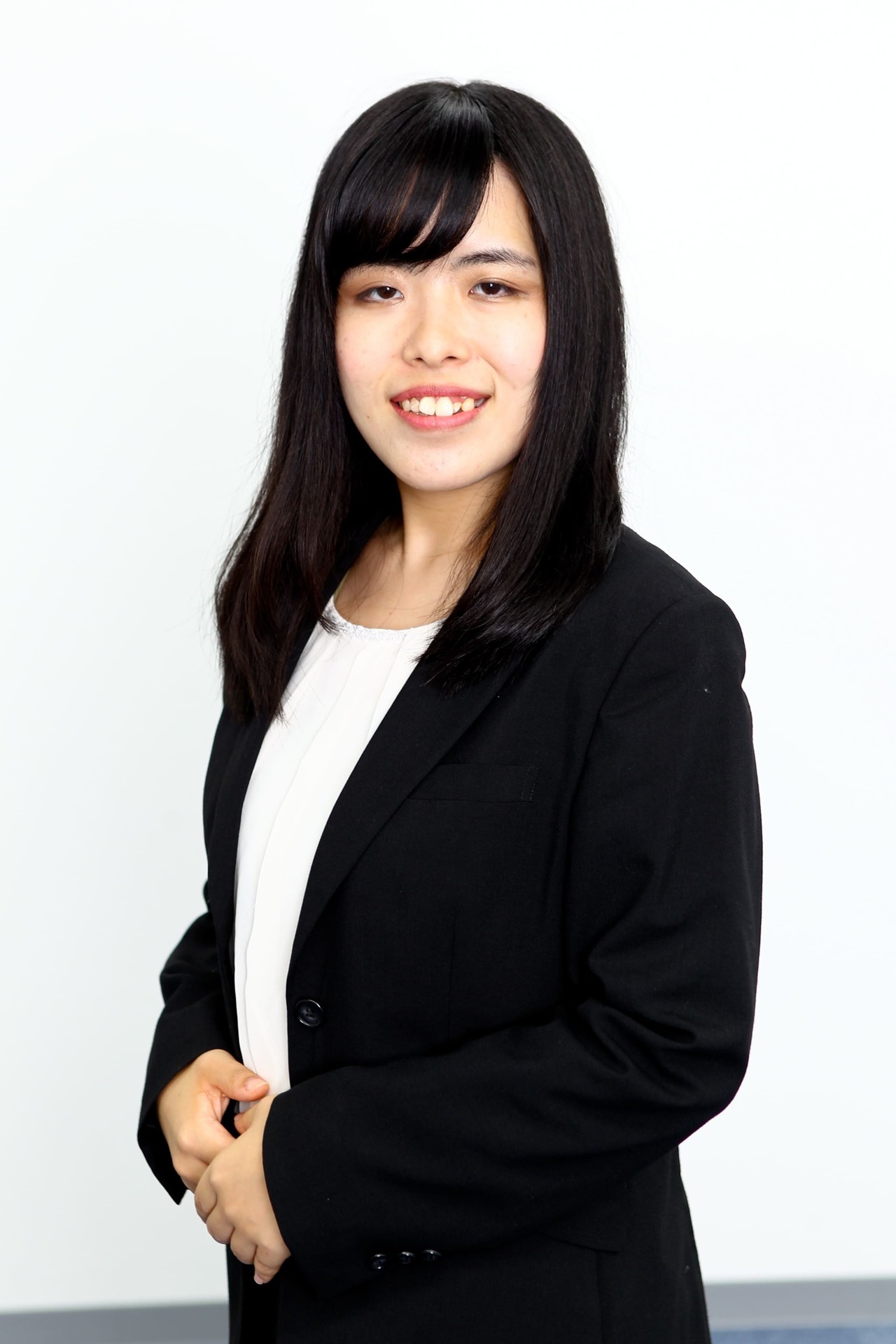
罰則がないからといって、対応しなくてよい、ということではありません。訴訟に発展すれば、経営に影響するほどの事態も引き起こしかねません。
同一労働同一賃金については、関連する法律、影響度も大きいことから、慎重に進めていかなくてはならならいことばかりです。企業の経営者や人事労務担当者にとっては、非常に大きな課題となっているのではないでしょうか?
同一労働同一賃金は、事業主の義務であることから罰則やリスクについても気になっている方も多いでしょう。ただ、現在は罰則の規定はされていません。
ただし、違反したまま事業活動を続けることで、従業員から民事訴訟などに発展する可能性を秘めています。待遇差が違法であるかどうかの最終的な判断は、裁判など司法によることになります。法律違反が認められれば、損害賠償請求をされるケースも出てきます。
また、今後は待遇差についての労使のトラブルも予想されます。明らかに説明のつかない待遇差など法違反の状態は改善していくべきでしょう。
社会が働き方改革を背景に同一労働同一賃金の動きが進むなか、会社が対応していないとなれば、非正規従業員はもとより、正規従業員の離職など、人材流出の原因ともなり得ます。
同一労働同一賃金をめぐる裁判例
同一労働同一賃金における不合理であるかどうかについては、丁寧に労使の話し合いを進めていくことが望まれますが、場合によっては労使の間で解決が図れないケースもあります。その場合には、不合理かどうかについて裁判によって判断されることになります。どのような判例があるのか確認します。
【最高裁判例メトロコマース事件】
駅の売店の有期雇用の契約社員が、正社員との間に不合理な待遇の格差があるとして損害賠償を求めて争い、住宅手当と残業手当の割増率の差については不合理であると判決が下った。ただし、退職金の支給については不合理は認められないとした。
住宅手当と残業手当については不合理であると認められ、退職金については不合理は認められないとの判決でしたが、すべてのケースが退職金の支給に不合理が認められないということではありません。使用者の裁量判断を尊重する余地は比較的大きいが、退職金の性質・支給目的を踏まえて判断されるということが示されました。
【最高裁判例大阪医科大学事件】
秘書業務の有期雇用のアルバイト職員が、賞与等について、正社員との間に不合理な待遇の格差があるとして損害賠償を求めて争った。賞与については不合理ではないという判決が下った。
賞与について不合理ではないという判決ではありましたが、「賞与についても不合理となることがある」と言及されたことは着目したいポイントです。賞与の性質・支給目的を踏まえて判断されるということが示されました。このケースでは賞与の性質が、「算定期間における労務の対価の後払い」であることや「一律の功労報奨」「将来の労働意欲向上」であり、「正職員の職務を遂行し得る人材の確保や定着」を目的としていることから、合理性が認められたということになります。

従業員の待遇に関わる課題は、対応は簡単なことではありません。ぜひ一度ご相談ください。
2021年4月からは、中小企業においても同一労働同一賃金への対応が必要になってきます。実態に即していない、時代に合わない手当などの見直しなどについては、猶予期間を設けたり、新たな手当を設計するなど必要になるかもしれません。不利益変更にならないようにするのはもちろんのこと、労使の十分な話し合いも必要になってきます。それには計画的に取り組んでいかなくてはなりません。
とはいえ、正規・非正規問わず、すべての従業員にとって公平な人事制度を構築することは容易ではありません。待遇差の合理・不合理の判断についても、非常に迷う部分も出てくるはずです。判断に迷った場合には、専門家に相談するなど、早めの対応を行いましょう。

最新セミナー一覧
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」