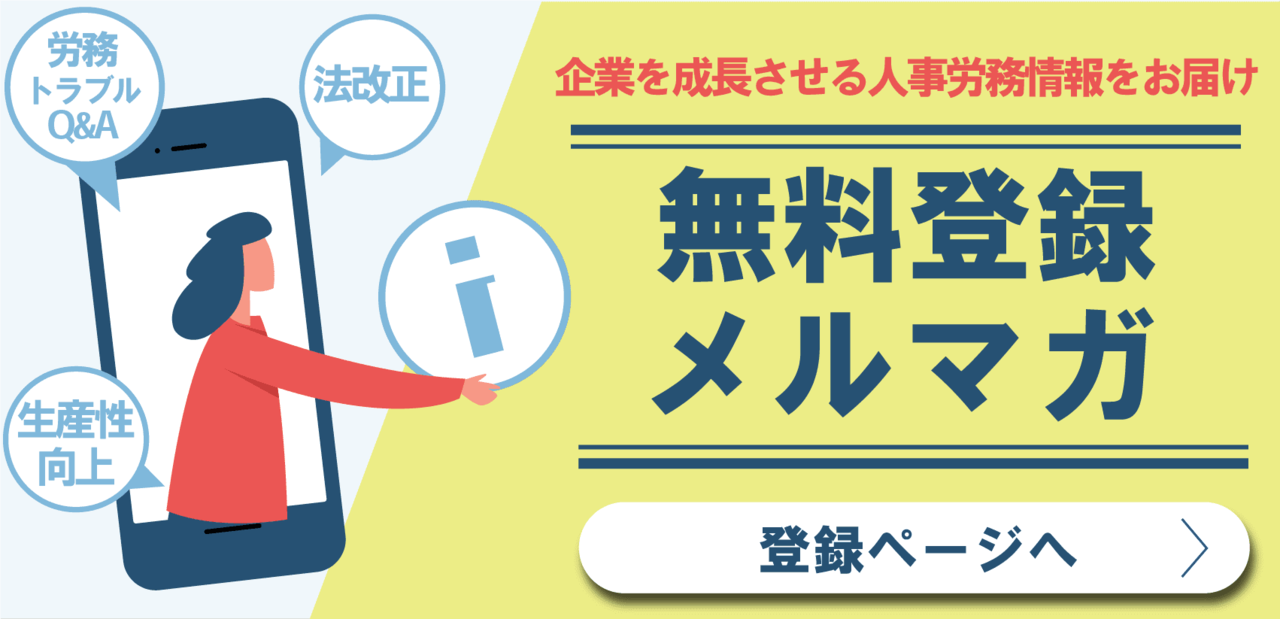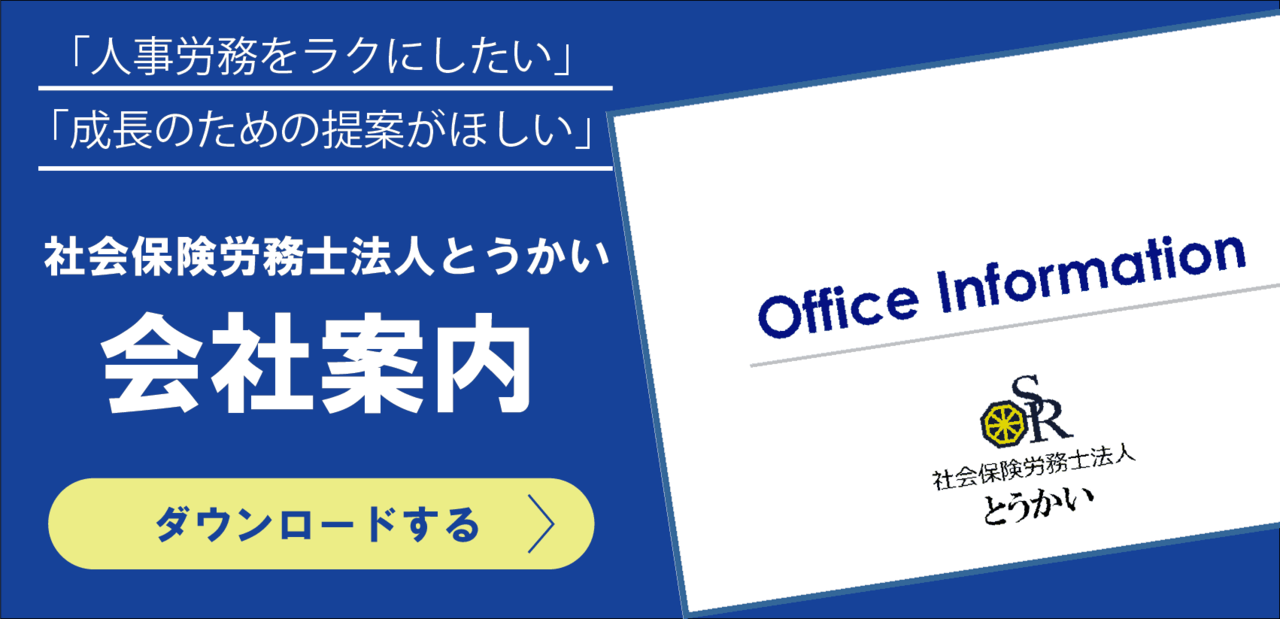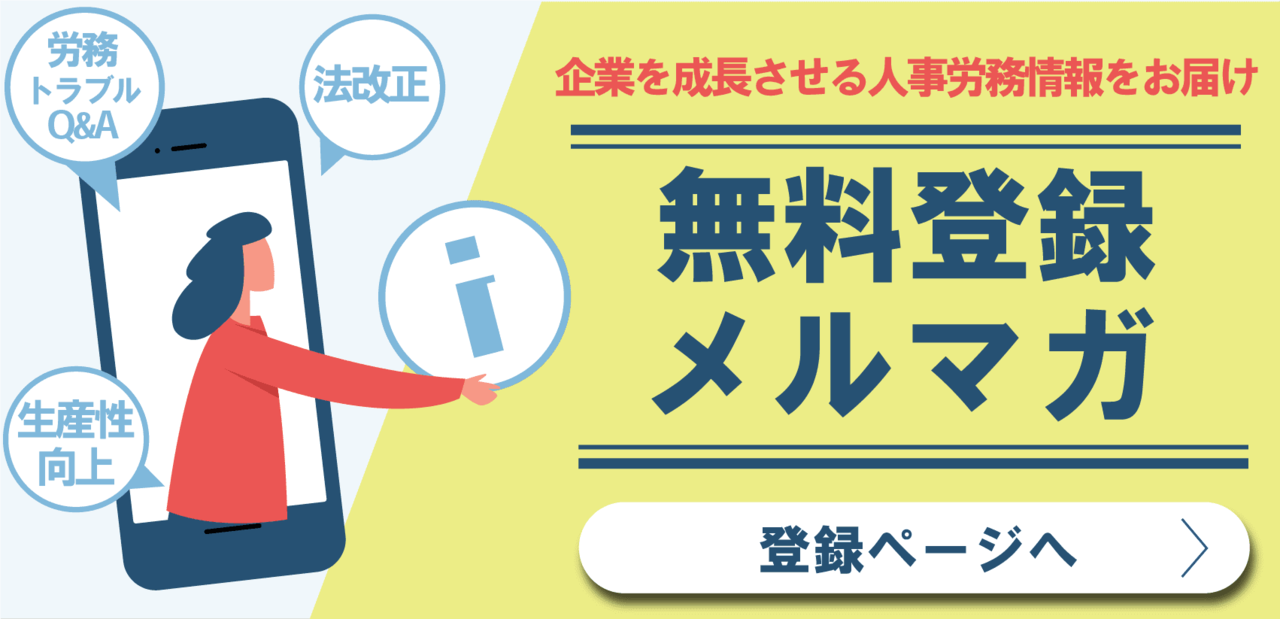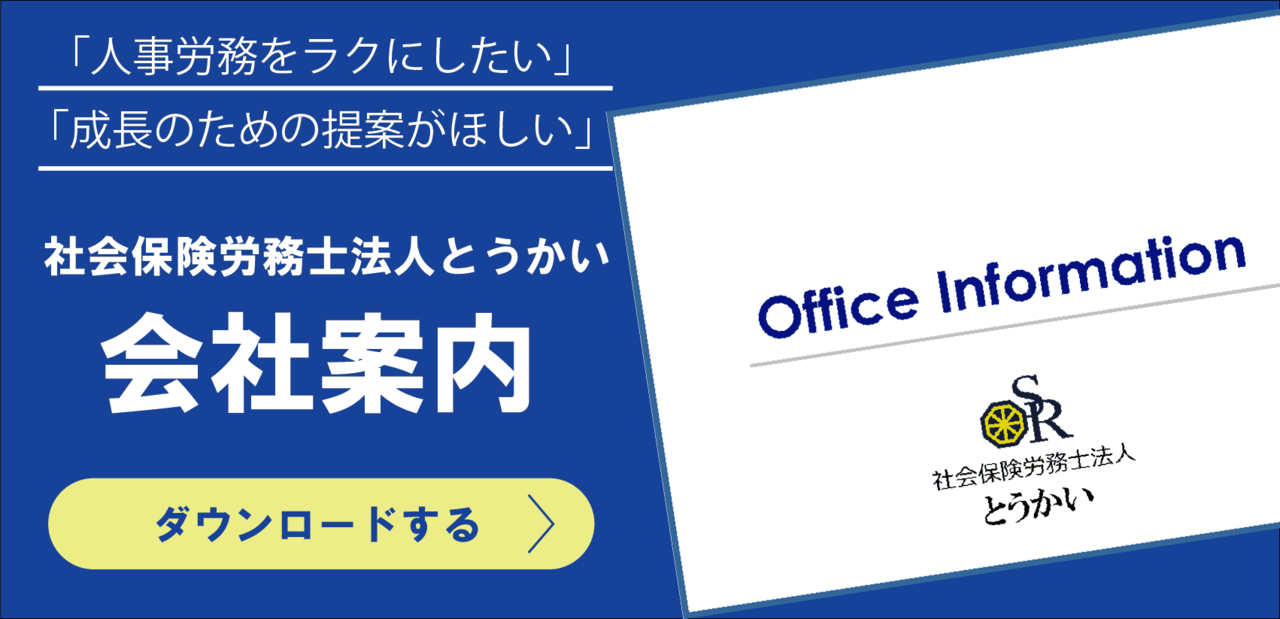自転車配達員とITエンジニアに労災保険適用に。ギグワーカーの特別加入について、
社会保険労務士が解説します。

多様なライフスタイルにあわせ、自由で必要なときに働くギグワークと呼ばれる働き方を選ぶ人がいます。一方でコロナ禍によって、意図せずギグワーカーとして働いている人もいるかもしれません。最近ではUberEatsの配達員やITエンジニアなどフリーランスで働く人も増えてきました。そうした動きを背景に、2021年9月から、Uber Eats配達員を始めとするギグワーカーが労働者災害補償保険(労災保険)に特別加入できるようになりました。
今回は、ギグワーカーの労災保険の特別加入について、社会保険労務士が解説していきます。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
執行役員 社会保険労務士 小栗多喜子
同社、人事戦略グループマネージャーを務め、採用・教育を担当する。商工会議所、銀行、Adeco,マネーフォワードなどセミナーや研修講師も精力的に行っている。労働法のアドバイスだけではなく、どのように法律と向き合い企業を成長させるのかという経営視点でのアドバイスを得意としている。
主な出演メディア
その他、記事の監修や寄稿多数。
取材・寄稿のご相談はこちらから

増加するギグワーカーにも加入ができる労災保険についてご説明します。
労働者災害補償保険(労災保険)は、業務や通勤による労働者の負傷・疾病・障害、死亡に対して保険給付を行う制度です。ほぼすべての労働者に適用されるのが労災です。とはいえ、この労働者の定義は、あくまでも会社に雇用をされ、賃金が支払われているといった人たちが対象となります。働くという意味では同じであっても、個人事業主をはじめとしたフリーランスや事業主などは、基本的に適用対象外となっています。しかし、業務の実態や災害の発生状況を鑑みると、労働者同様であり、保護することがふさわしいであろう、とされる人たちもいます。その場合は、要件を満たす一部職種の個人事業主やフリーランス、中小企業の事業主等は、労災への「特別加入」が認められています。
例えば、中小企業の事業主であっても従業員と同様の業務や作業を行っている、一人で土木や建築業務を行っているような一人親方、個人の配送業者、一定条件の農業作業従事者などがそれに該当します。
特別加入が認められれば、一般の労働者同様、業務災害への保険給付がされることになっています。
労災保険でカバーする補償
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 療養補償給付 | けがや病気の治療に必要な費用や器具を給付 |
| 休業補償給付 | けがや病気のために仕事ができず、賃金がもらえない場合、休業4日目から給付 |
| 傷病補償年金 | けがや病気が療養開始後1年6か月経過しても治っていない場合や障害等級に該当する場合に給付 |
| 障害補償給付 | けがや病気によって障害が残った場合に給付 |
| 遺族補償給付 | 死亡した場合、遺族に給付 |
| 葬祭料 | 死亡した場合、葬祭費用を給付 |
| 介護補償給付 | 障害補償年金または傷病補償年金受給者のうち、障害等級が第1級、第2級の障害で介護を受けている場合に給付 |

労災保険はフリーランスへの間口が広がりました。
労災保険の特別加入制度は、昨今、フリーランスなどで働く人の保護拡大への動きがみられます。2021年4月には、「芸能関係作業従事者」「アニメーション制作作業従事者」「柔道整復師」「創業支援等措置に基づき事業を行う者」といった方に、特別加入の範囲対象が広がりました。
そして2021年9月より、フードデリバリーを行うUberEatsなどの自転車配達員とフリーのITエンジニアなどが、労災保険の特別加入の対象として新たに加わることになりました。
日本フードデリバリーサービス協会によると、現在、フリーランスのフードデリバリーの配達員は約15万7千人、そのうち自転車配達員は約9万人にも上ると推計されています。コロナ禍の影響下でフードデリバリーの需要増や、失業者の受け皿となったこと、比較的参入障壁が低いことから、2020年に大きく増加した自転車配達員。そうした需要が高まるなか、交通事故の増加も社会問題となっていました。加えて、フリーランスとして働く場合には、業務中の交通事故などに対し、十分に補償されないことも問題となっていました。フリーランス協会などが提供する保険もあるものの、給付内容や補償範囲という面では手厚いものではありませんでした。
そこで、今回、自転車配達員などが新たに労災保険の特別加入対象として、加わることとなったのです。
さらに、フリーランスのITエンジニアやウェブデザイナーなども特別加入の対象としています。自転車配達員が交通事故のリスクを抱える一方で、ITエンジニアやウェブデザイナーは、長時間労働の多さが問題とされてきました。フリーランスの良い面ではありますが、労働時間を管理されないので、人によってはかなり長時間労働になってしまう可能性もあります。このような長時間労働によって、脳・心臓疾患などの身体的リスクのほか、メンタル不調などを発症する要因ともなる見過ごせない問題となっていたのです。
もちろんUberEatsだけでなく、デリバリー全般の配達員が対象となります。デリバリーといっても、原付バイク、車、自転車など手段はさまざまにありますが、今回、労災保険の特別加入対象として拡大になったのは、「自転車」を使用してデリバリーを行う人です。もともと原付バイクや車でのデリバリーは、特別加入の対象範囲とされていましたので、今回は「自転車」が追加されたというわけです。
最近、フードデリバリー需要の増加によって配達員に発生しやすい労働災害は、交通事故です。社会問題ともなっています。車を運転する方なら、自動車道の端を速いスピードですり抜けていく自転車にヒヤリとした経験はあるのではないでしょうか。自転車は軽車両であり、基本的に車道を走行のため、自動車との接触事故も起こりやすいと心配されています。
今回、労災保険の特別加入の対象となるのは自転車配達員だけではありません。ITエンジニアもその対象となっています。ITエンジニアとは、フリーランスで「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業」を請け負って行っている人のことを言います。ネットワークやデータベース、組み込み制御システムもその範囲に入りますし、Webデザイナーなどもその範囲に含む幅広いものとなっています。
ITエンジニアとはこんな人
- ITコンサルタント
- プロジェクトマネージャー
- プロジェクトリーダー
- システムエンジニア
- プログラマ
- サーバーエンジニア
- ネットワークエンジニア
- データベースエンジニア
- セキュリティエンジニア
- 運用保守エンジニア
- テストエンジニア
- 社内SE
- 製品開発/研究開発エンジニア
- データサイエンティスト
- アプリケーションエンジニア
- Webデザイナー
- Webディレクター

治療費全額負担。メリットの多い労災保険です。
フリーランスの自転車配達員やITエンジニアに間口の広がった労災保険の特別加入制度ですが、始まったばかりで実際にどれだけの人が加入するのかという点ではわかりません。メリット・デメリットを押さえつつ、自分自身で必要な選択をしていくことになるかと思います。
労災保険 特別加入のメリット
業務中のけが・傷病に対する補償が手厚いことが最大のメリットです。とくに、業務中のけがや傷病などによって、医療機関での治療費は全額労災保険負担となります。自己負担がない、という点は大きいメリットではないでしょうか。また、業務災害によって、休業しなければならなくなった場合には、休業補償も行われます。障害が残った場合や死亡時にも給付されます。
労災保険 特別加入のデメリット
特別加入はメリットが大きく、加入の要件を満たせば、加入しておくほうが間違いありません。デメリットとしてあげるのであれば、特別加入の保険料は自己負担であること、特別加入にあたっては、特別加入団体と呼ばれる労災保険の事務手続きを行ってくれる団体を経由して加入することになります。その特別加入団体の年会費や組合費の支払いの必要が発生します。年会費や組合費等は団体によっても異なります。
「保険料+組合費等」の負担が発生するわけです。
また、労災保険は、あくまで本人の業務災害に補償がされるものですので、事故相手に与えた損害の補償はありません。民間の低額の傷害保険を活用するという方もいるかもしれませんが、これらをメリットととるかデメリットととるかは、環境や収入、働き方の状況によっても変わると思いますので、自分自身にとってなにかベストな選択か検討してみてください。
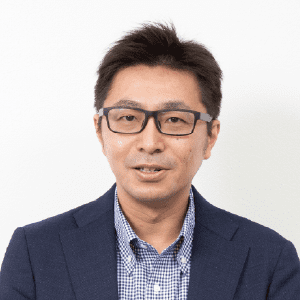
コンサルタント中村のアドバイス
事故相手に与えるリスクに備えるのであれば、損害保険に加入する必要があります。労災の特別加入という選択肢が増えたので、すでに損害保険に加入されている方も特別加入制度と合わせて見直しをすることをおすすめします。

自分の状況に合わせた保険料が選択できます。
労災保険に特別加入をするには、自分自身で保険料を負担する必要があります。特別加入の場合には、「給付基礎額」に応じた保険料を、自分自身で選択して支払うことになります。
まずは、「給付基礎日額」を選択し、保険料の算定基礎額を算出します。
・保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日
・労災保険料=保険料算定基礎額×保険料率
職種によって保険料率が異なります。フードデリバリー配達員については、12/1000、ITエンジニアは3/1000となっています。
■フードデリバリー配達員・ITエンジニアの年間保険料
例)フードデリバリー配達員が給付基礎日額4,000円を選択した場合の年間保険料
4,000円×365日=1,460,000 円
1,460,000 円×12/1000=17,520 円
この保険料に、特別加入団体の組合費を500円/月と仮定すると、
500円✕12か月=6,000円
17,520 円+6,000円=23,520円
※特別加入団体の年会費等は考慮していません。
例)Webデザイナーが給付基礎日額5,000円を選択した場合の年間保険料
5,000円?365日=1,825,000 円
1,825,000 円?3/1000=5,475 円
この保険料に、特別加入団体の組合費を500円/月と仮定すると、
500円?12か月=6,000円
5,475 円+6,000円=11,475円
※特別加入団体の年会費等は考慮していません。
2021年9月から労災保険の特別加入の対象に加わったフードデリバリー配達員やITエンジニア。実際に、特別加入する際にはどのような流れ、手続きとなるのか確認しましょう。
主な加入の流れは以下のとおりです。
① 業種に合った特別加入団体を選択し、団体に加入する
② 特別加入団体で、労災保険の「特別加入申請書」を作成する
(具体的な業務の内容、作業、業務歴、希望する給付基礎日額などを記載)
③ 特別加入団体より「特別加入申請書」が所轄労働基準監督書を経由して、都道府県労働局へ提出される
④ 都道府県労働局長が受理し、承認される
(特別加入の申請に対する労働局長の承認は、申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日)
初めて特別加入を申請する場合には、「特別加入団体」に加入しなくてはなりません。特別加入団体はいくつかあり、業種によって異なります。フードデリバリーを行う自転車配達員の方であれば、貨物運送事業者向けの特別加入団体に加入する必要があります。
ITエンジニアであれば、ITフリーランスの特別加入団体に加入することになります。どの特別加入団体に加入すればよいかわからないといった場合には、都道府県労働局や労働基準監督署に問い合わせてみることをおすすめします。
フードデリバリーなど自転車配達員の特別加入団体
一人親方労災保険組合
厚生労働省
自転車配達員のための特別加入制度チラシ
https://www.mhlw.go.jp/content/000821215.pdf
一人親方その他の自営業者用のしおり
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf
ITエンジニアなどの特別加入団体
ITフリーランス支援機構
https://www.aitf.or.jp/
厚生労働省
ITフリーランスのための特別加入制度チラシ
https://www.mhlw.go.jp/content/000815896.pdf
特定作業従事者用のしおり
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-8.pdf

多様な働き方に関することもご相談ください。
多様な働き方の増加や、コロナの影響下ということもあり、ギグワーカーといったフリーランスなどで働く人は増えています。新たな仕事の担い手としても期待されているところですが、安心して働ける環境には、まだまだ多くの課題が残っています。日本政府としてもフリーランスの働く環境整備のため、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省においてガイドラインを策定しています。フリーランス全般の取引への独占禁止法や下請法の適用、請負契約や準委任契約であっても実態を判断しての労働関連法令の適用など、徐々に議論や整備が進んでいくことが求められています。ギグワーカーの担い手であるフリーランスが安心して働くための環境整備として、今回の労災保険の特別加入の対象拡大に至りました。
当社では、雇用にこだわらない企業と労働者の関わり合い方についてもご提案させていただいております。
詳しくは無料相談にお申込みください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」