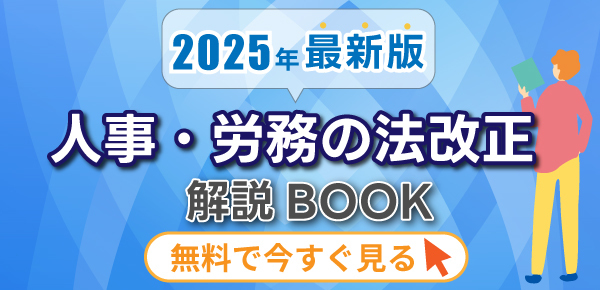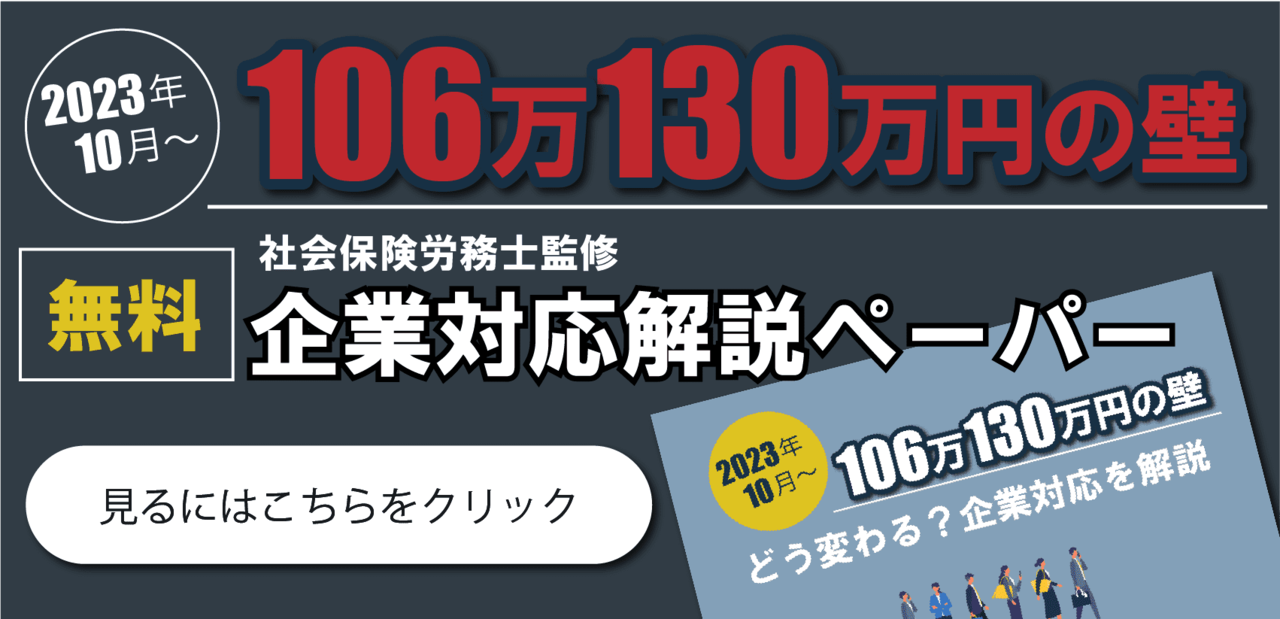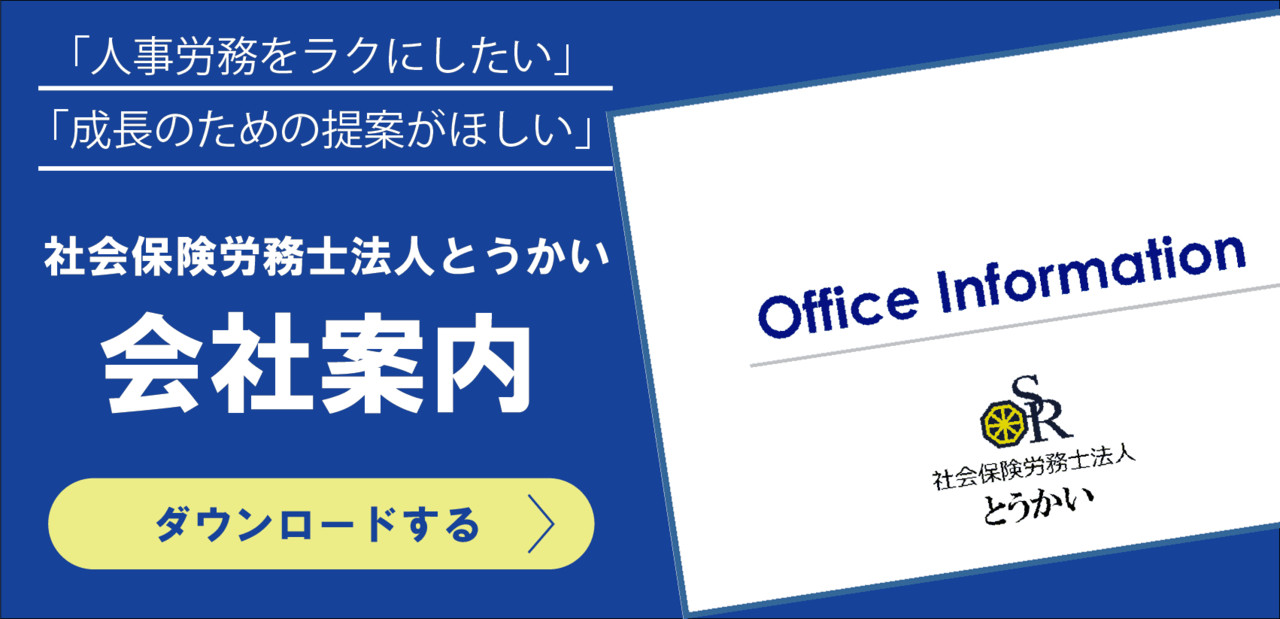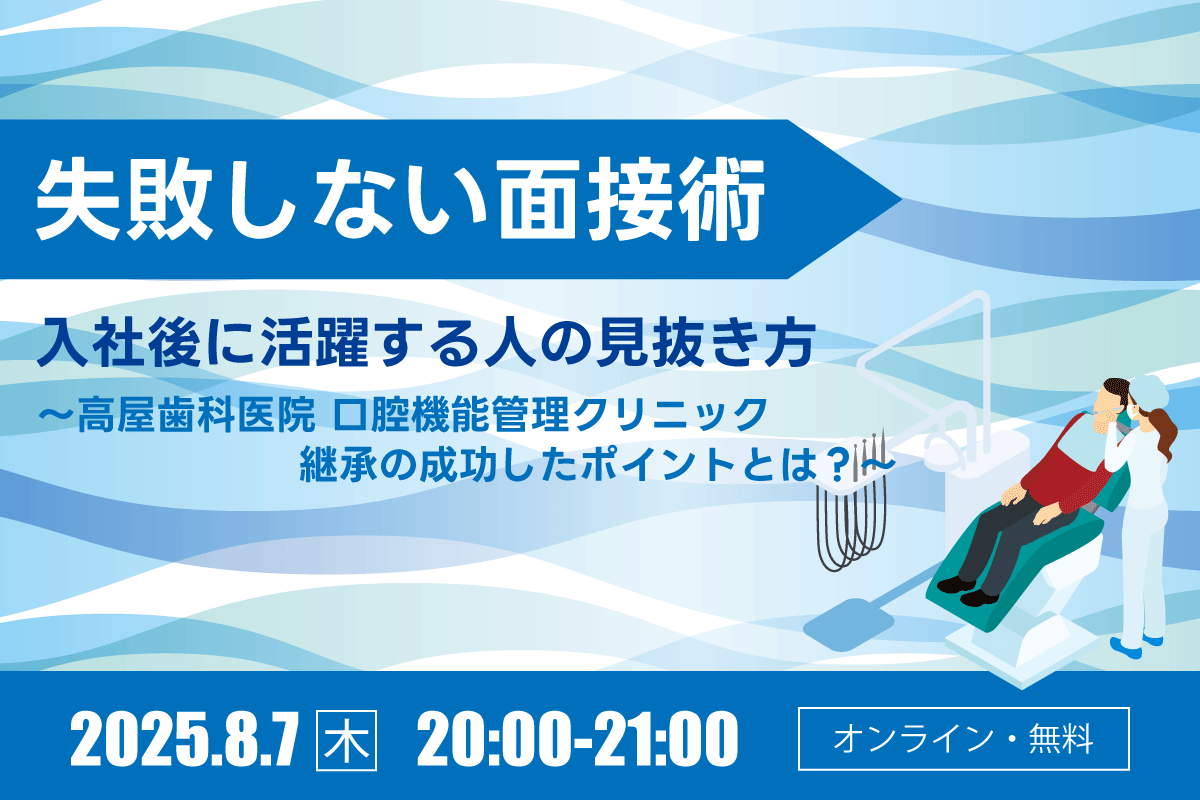安全衛生管理規程は、労働者の安全と健康を確保するために企業が策定する重要な文書です。労働安全衛生法に基づき、厚生労働省の指針等を踏まえて、自社の業種・規模・職場環境に応じた実効性のある規程を整備することが求められます。事業場ごとに異なるリスクに適切に対応するため、具体的な管理措置を講じることが、法令遵守とともに企業の責務となります。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

労働安全衛生法とその関連規則を解説します。
労働安全衛生法は、労働者の安全・健康の確保と快適な職場環境の形成を目的とし、1972年に制定されました。この法律は、すべての事業者に対し、安全配慮義務の具体的内容として、以下のような事項を義務付けています。
• 安全衛生管理体制の整備(安全管理者や産業医の選任等)
• 作業環境のリスクアセスメント
• 定期的な健康診断の実施
• 労働者への安全衛生教育の実施
これらの措置を通じて、職場における労働災害を未然に防止する体制を整える必要があります。
労働安全衛生法に基づいて定められた「労働安全衛生規則」は、企業が具体的に講じるべき安全衛生対策を詳細に規定しています。たとえば、作業場の換気基準、化学物質の取り扱い、熱中症予防対策、VDT作業者に対する措置、産業医による意見聴取など、細かな技術的基準や管理方法が網羅されています。安全衛生管理規程を策定する際は、この規則の内容に沿って構成することが求められます。

安全衛生管理規程の作成手順を紹介します。
規程作成の第一歩は、自社の事業内容や職場環境におけるリスクを洗い出すことです。具体的には、以下のような情報を収集・整理することが重要です。
• 現場の作業内容や危険源の把握
• 過去の労働災害発生状況
• 業界団体や厚生労働省のガイドライン
• 労働者からのヒアリング内容
このような情報をもとに、自社に適した安全衛生対策を検討します。
労働安全衛生法および関係法令に準拠した内容をもとに、次のような項目を明文化します。
• 安全衛生管理体制(安全衛生責任者、安全管理者等の役割)
• 作業環境管理および作業管理の基本方針
• 教育訓練の実施方法と頻度
• 労働災害発生時の対応手順(報告・再発防止策など)
• 健康診断の実施およびフォロー体制
規程に明示することで、組織内での役割分担や対応の一貫性が保たれます。
自社で一から作成するのが難しい場合は、厚生労働省や業界団体が提供している「モデル規程」「テンプレート」を活用する方法も有効です。ただし、そのまま使用するのではなく、自社の業務実態やリスクに即してカスタマイズすることが大前提です。形式的な整合性だけでなく、実務で機能する内容とすることが、法令遵守だけでなく事故防止にも直結します。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」