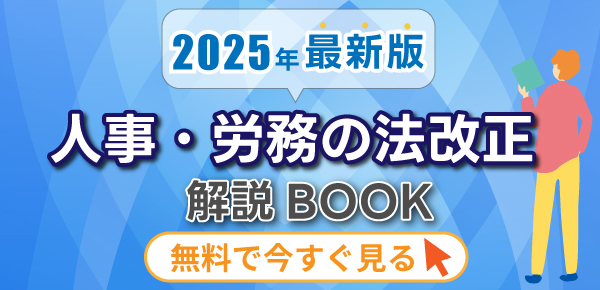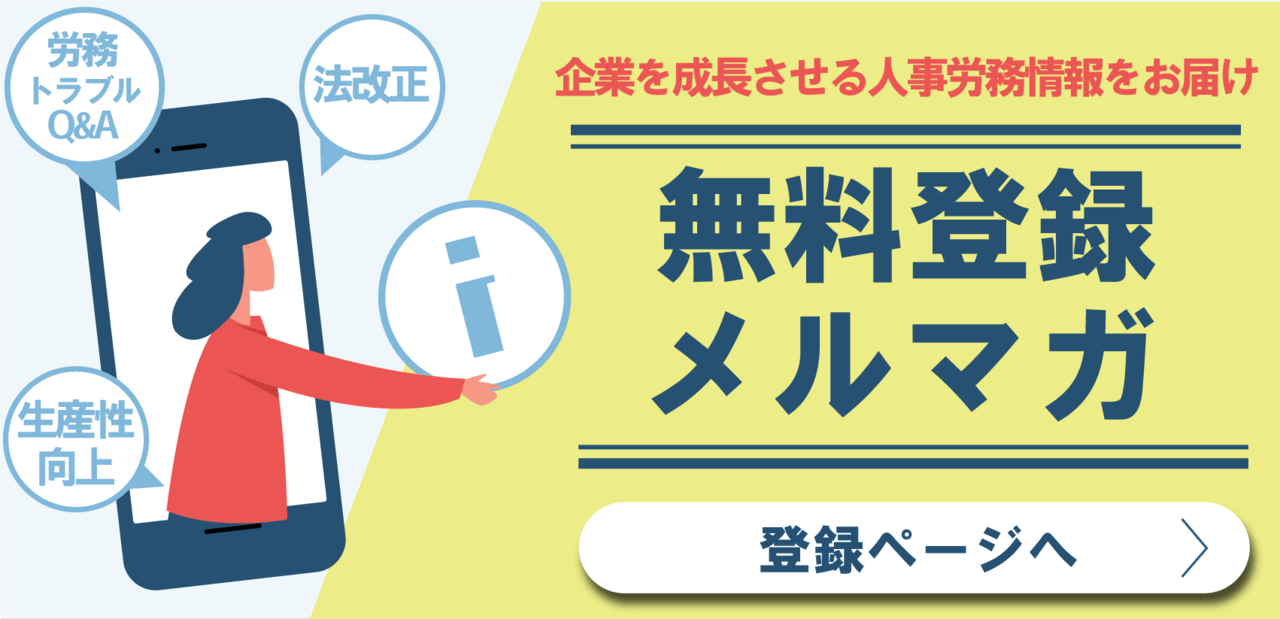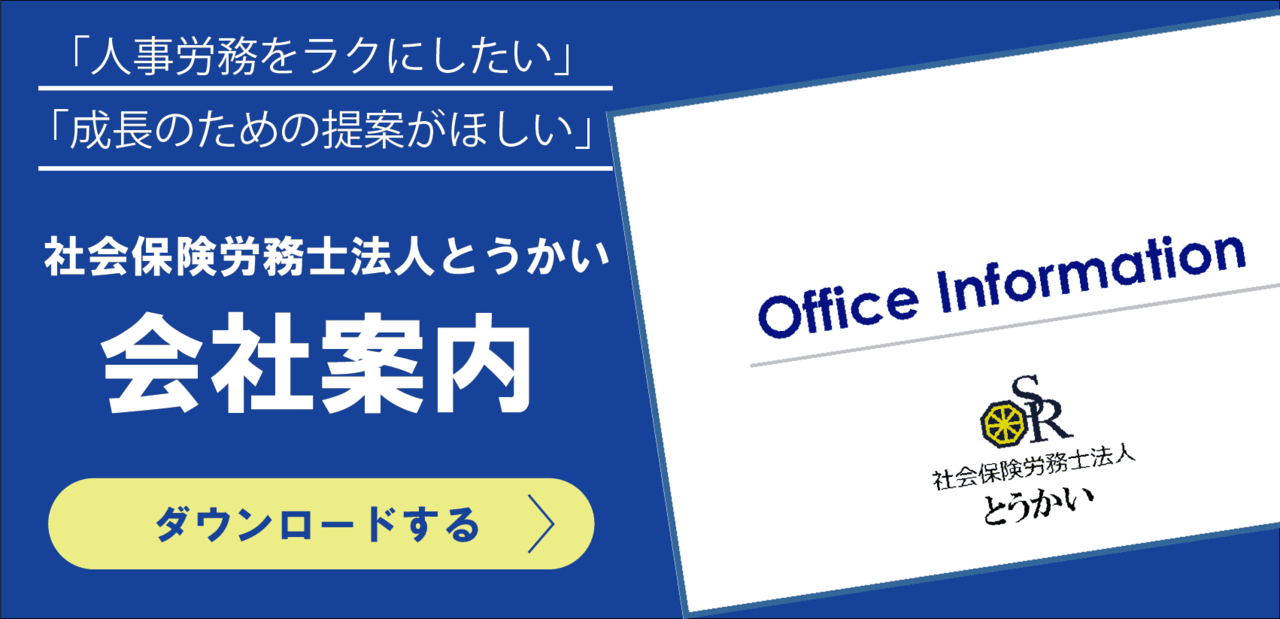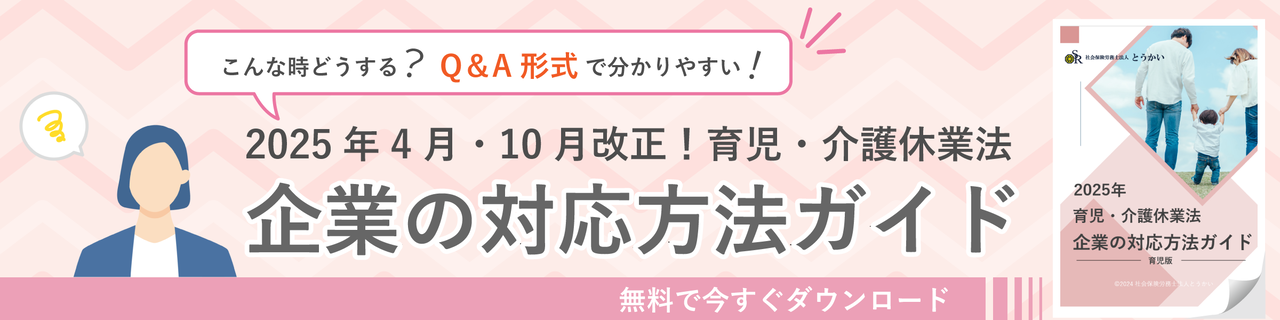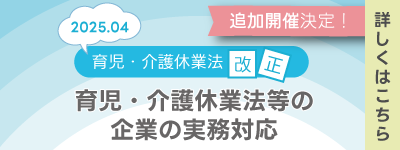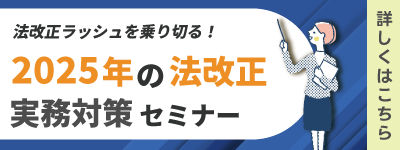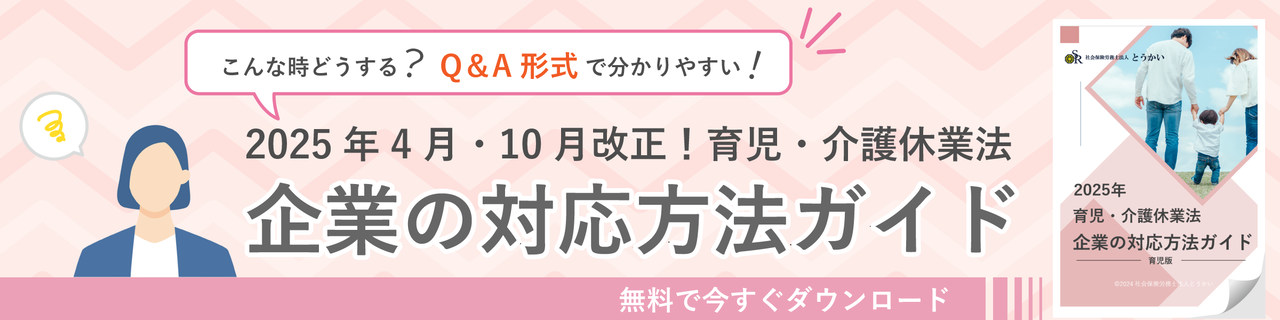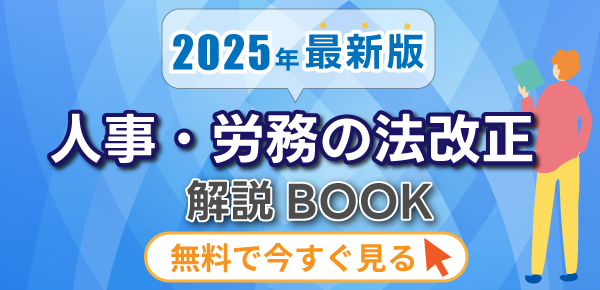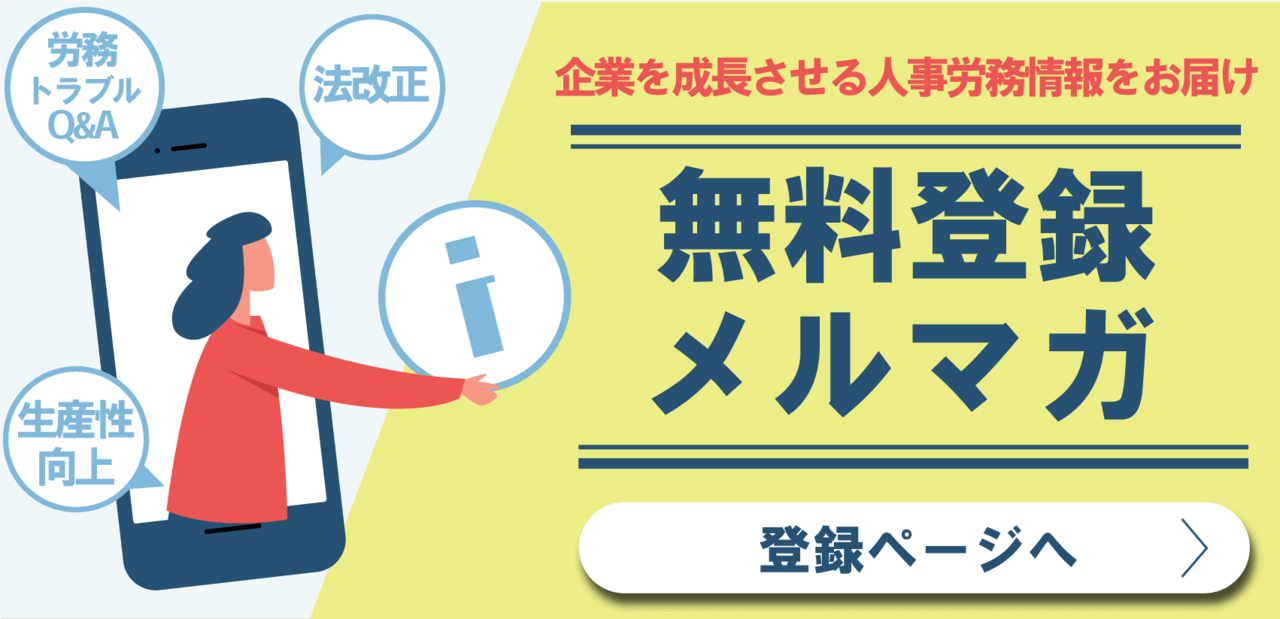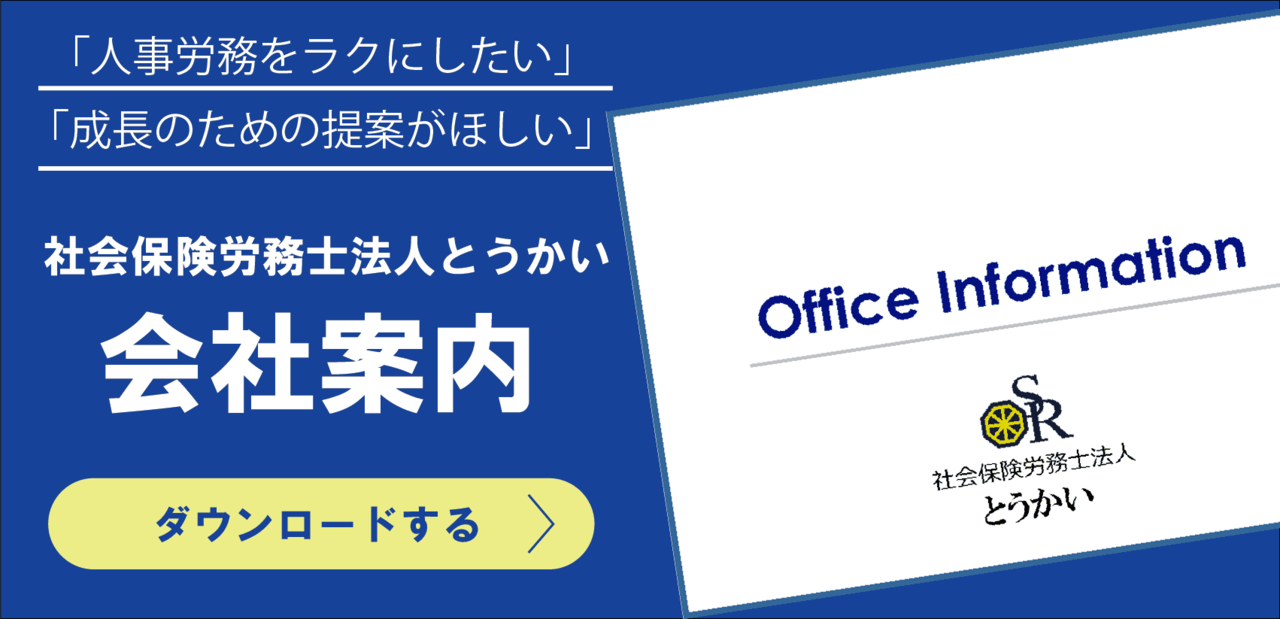セキュリティに強い社労士事務所とは?

セキュリティに強い社労士事務所は、企業や個人事業主が直面する多様なセキュリティリスクに対応するための専門的なスキルと知識を持っています。
昨今はランサムウェアなどサイバー攻撃が原因とされるセキュリティトラブルに敏感な企業も多いことでしょう。多くの企業で、情報セキュリティへの対策が強化されているところです。人事の面から見る情報セキュリティ対策としては、従業員の個人情報の漏洩や不正使用を防ぐことが挙げられます。
そこで、セキュリティリスクに強い社労士事務所では、情報漏洩や個人情報の不正使用を防ぐため、情報セキュリティに重点を置いた厳格な管理体制を構築しています。社労士事務所には、労働関連法令への的確な対応を行える専門知識にプラスして、情報セキュリティ対策に強みを発揮できることが期待されています。情報セキュリティ対策が万全であることは、信頼できるパートナーとして顧客から高く評価されるポイントとなり、持続的な信頼関係を築く礎ともなるのです。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

セキュリティに強い社労士事務所の選び方を詳しく解説します。
社労士事務所を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。企業や個人事業主のニーズに応じたサービスを提供する能力はもちろんのこと、情報セキュリティの観点から信頼できる社労士事務所を選ぶことが重要です。従業員の重要なデータを取り扱うことになりますので、しっかりと情報管理の仕組みが確立され、マイナンバーの取扱いやその他の重要情報を適切に管理しているかどうかを確認しましょう。また、安全な通信手段を利用してデータの処理や交換を行う体制が整っている事務所は、セキュリティ対策に特化していると言えます。そのような体制を持つ事務所は、情報漏えいの防止や顧客データの保護について高い意識を持ち、安心して業務を任せられるパートナーとなるでしょう。
情報漏洩防止は、社労士事務所の情報セキュリティにおいて最も重要な要素の一つです。具体的には、定期的なシステムの更新やパスワード管理の厳格化、従業員へのセキュリティ教育といった基本的な施策が含まれます。さらに、ファイアウォールやアンチウイルスソフトの導入といった技術的な対策も欠かせません。
これらの取り組みによって、意図的な情報漏洩だけでなく、無意識による情報漏洩を防ぐことが可能となります。情報セキュリティの万全な体制を整えることは、社労士事務所が提供するサービスの信頼性向上に欠かせません。企業の人事担当者が、社労士事務所を選定する際には、事務所がどのような具体的な情報セキュリティ対策を実施しているのかを、必ず確認しましょう。セキュリティ事故が起こってからでは、影響も大きく、従業員からの信頼回復にも長い時間がかかることになります。安心して業務の依頼を行うための大切なステップです。
マイナンバーの取扱いは、近年ますます重要性を増しています。社労士事務所を選ぶ際には、マイナンバー制度に基づく情報セキュリティの観点から、どのような管理体制が整備されているか慎重に確認することが重要です。具体的には、適切な本人確認を行い、情報漏洩を防ぐための厳密な運用体制や仕組みが整っているかが評価のポイントとなります。マイナンバーの収集、保管、利用や廃棄まで、どのような体制、運用で行われるのかは確認すべきです。マイナンバーが漏洩した場合のリスクを軽減するためには、法令遵守を徹底し、情報管理に必要な責任を果たしている事務所を選ぶことが賢明です。専用のセキュリティールームを設置しているなど、適切な取扱いを行うことで、安心して業務を依頼できる環境を提供する社労士事務所との信頼関係が築けるでしょう。
企業の人事担当者と社労士事務所との情報のやり取りにおいて、安全なファイル交換サービスの導入は情報セキュリティを確保する上で不可欠です。暗号化された通信経路が提供されるサービスを利用することで、セキュリティリスクを抑えることができます。また、アクセス権限の厳格な管理も情報セキュリティ対策の一環として重要です。指定された関係者だけがアクセスできる環境を整えることで、情報の不正流出やデータの改ざんを防ぐことが可能になります。こうした万全の情報セキュリティ対策を講じている社労士事務所を選ぶことにより、安心して重要な業務を委託できる適切なパートナーを見つけることができるでしょう。

小栗の経営視点のアドバイス
最近は、ビジネスシーンでクラウドサービスを利用する企業が非常に多くなっています。社労士事務所も例外ではありません。依頼の際には、利用するアプリケーションのセキュリティリスクも確認することをおすすめします。多くのSaaSサービスの事業者は、SLA(Service Level Agreement)を明示していることが多いので、自社の情報セキュリティ方針に合致するかの観点での確認も必要でしょう。

セキュリティ対策が優れた社労士事務所の特徴を詳しく解説します。
セキュリティ対策が優れた社労士事務所の強み、選定のポイントとして、特に注目したいのがプライバシーマークやISO27001を取得しているかどうかです。さまざまなリスクや脅威からデータを守るための管理が徹底されており、業務が安全な環境で遂行されています。セキュリティ対策に優れた社労士事務所は、安心で信頼できるパートナーとして選択肢にはいるのではないでしょうか。情報セキュリティを重視する方にとっては、こうした特徴を持つ事務所の利用は非常に有益と言えるでしょう。
プライバシーマークは、個人情報保護に関する厳格な基準をクリアしていることを示すものであり、プライバシーマークを持つ事務所は個人情報保護に関する情報管理の仕組みがしっかりと確立されているため、安心して依頼することができます。プライバシーマーク取得には厳しい審査が求められ、情報管理体制がしっかり整っているかどうかが厳格に評価されるためです。
厳格な審査をクリアした社労士事務所は、クライアントの情報を適切に取り扱うためのプロセスが確立しており、信頼性の高いサービスを提供しているという判断材料となります。
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)に関する国際規格であるISO27001の取得も大きな強みとして評価されます。ISMSは情報の機密性、完全性、可用性を保つための枠組みであり、ISO27001認証を取得することで、社労士事務所は情報セキュリティに対する高い意識を示していることになります。ISO27001を取得している社労士事務所では、情報セキュリティを重要事項として取り組んでおり、リスクアセスメントの実施、定期的な見直しを行うなど、情報資産を保護するために体系的で組織的なアプローチを実施しています。
入退室管理システムを導入している社労士事務所では、物理的なセキュリティの向上とともに、情報セキュリティも大幅に強化されています。入退室管理システムを利用することで、許可された人物のみが特定エリアにアクセスできるよう制限され、重要な機密情報の漏洩リスクを効果的に抑えることが可能です。さらに、誰がいつどの場所にアクセスしたかの履歴を詳細に記録するため、万が一の問題が発生した際にも速やかかつ的確な対応が行える体制を構築できます。そのため、情報セキュリティの観点からも、入退室管理システムの導入は非常に有用と言えるでしょう。
データの安全性を高めるために、外部データセンターを利用する社労士事務所も増えています。外部の専門業者が運営するデータセンターは、最新の情報セキュリティ対策を徹底しており、高い冗長性やバックアップ体制が整えられています。高度な環境でデータを管理することによって、万が一の事故や自然災害から情報を確実に保護することが可能です。最近は地震をはじめ、さまざまな災害リスクにも対応する耐震性、電源設備、セキュリティシステムを保有するデータセンターを利用することで、重要なデータを脅威から守るデータセンターの利用が増えています。企業や社労士事務所側双方が責任を明確化し、セキュリティ管理のクオリティを向上させることが期待されます。
紙媒体を減少させることで、情報漏洩のリスクを減らす取り組みは、現代の企業における重要な責任のひとつです。デジタル化が進むことで、物理的な書類管理が不要になり、紛失や盗難の可能性を大幅に軽減できます。また、電子データはアクセス権限を柔軟に設定できるため、セキュリティが向上し、管理プロセスも効率化されます。情報の安全確保という責任を果たすだけでなく、企業全体の業務効率向上にも寄与するでしょう。
セキュリティ対策が充実した社労士事務所を選ぶ際には、多角的に判断することが求められます。社労士の労働法をはじめとした専門知識や経験はもちろんのこと、情報セキュリティや関連法規に特化した知識を持つ社労士であれば、トラブル予防に役立つ具体的な提案やアドバイスを提供してもらえるでしょう。
また、過去の実績や顧客からの評価も選定の際に欠かせません。信頼性が高いレビューやフィードバックを参考にすることで、その事務所がどれだけ顧客の期待に応え、質の高いサービスを提供しているかの判断ポイントとなります。また、定期的に内部監査を実施し、セキュリティガイドラインの更新を行っている事務所は、常に最新の知識と技術を活用している点で大きな強みと言えます。
これらを踏まえ、セキュリティ対策に特化した事務所を選ぶことで、企業にとって重要な情報を守る第一歩となるだけでなく、長期的な安心を得ることができるでしょう。

鶴見の経営視点のアドバイス
プライバシーマークが個人情報を対象としていることに対し、ISO270001は、個人情報だけでなく技術情報や機密情報なども含む国際規格であることに、より大きな強みがあります。

セキュリティに関連する具体的な対策を見ていきましょう。
セキュリティを強化するためには、さまざまな具体的な対策が必要とされます。PCとサーバーの他、デバイスなどのセキュリティ強化は基本です。最新のアンチウイルスソフトやファイアウォールの導入、ソフトウェアの定期的なアップデートを行い、脆弱性を生かした攻撃から重要なデータを守る取り組みも欠かせません。このような対策は、システム全体の防御を強化する上での大きな強みとなります。
PCとサーバーのセキュリティ強化は、基本中の基本とも言える重要なステップの一つです。セキュリティソフトの導入やパスワードの定期的な変更など、基本的な対策をしっかりと実行することが求められます。加えて、暗号化技術を取り入れることで、個人情報や業務データを含む重要なデータを第三者から安全に保護することが可能です。また、情報セキュリティの観点からは、データのバックアップを定期的かつ適切な場所に保存しておくことも不可欠です。これにより、システム障害やサイバー攻撃などの予期せぬトラブルが発生した場合でも迅速に復旧できるよう備えることができます。デジタル環境の脅威が増加する中で、これらの対策を徹底することが重要です。
PCや社用スマホといったデバイスの遠隔管理も、外部アクセスを制限するためには非常に有効です。遠隔管理ツールを活用し、紛失したデバイスからの情報漏えいリスクを最小限に抑えるだけでなく、管理プロセスの効率化も図ることが可能です。ユーザーが外出時に仕事を行う場合でも、会社のデータや情報が安心して扱える環境を整えることができます。デバイスには企業情報などが保存されているケースも想定して、無関係な第三者へのアクセス制限を講じることも非常に重要でしょう。管理者は、リアルタイムで端末状況を把握し、必要に応じて制限をかけることも容易になります。
セキュリティ技術や仕組みの導入は、企業全体のセキュリティ対策を体系化し、より強固な体制を築く強みとなるでしょう。
資料や書類はクラウドにデータとして保存することで、物理的な脅威や紛失リスクから守られるだけでなく、管理責任の負担を軽減する手段としても有効です。昨今のクラウドサービスでは、高度なセキュリティ対策が施されています。さらに複数のバックアップが確保されることでデータ損失のリスクが大幅に減少するでしょう。また、必要な時に迅速にアクセス可能な環境を提供するため、業務効率向上の観点からも優れています。また、クラウド環境はアクセス権限管理が容易で、特定のユーザーだけが文書にアクセスできるよう設定することが可能であり、物理的な書類管理より、情報漏洩のリスクが低下します。クラウドサービスの活用はセキュリティ面と業務効率の向上において信頼性が高く、責任分担が明確化されるため、現代のビジネスシーンにおいて重要な選択肢となっています。
EDR(エンドポイント検知・対応)やSOC(セキュリティオペレーションセンター)の導入も、被害を未然に防ぐための有効な手段です。大企業のみならず、中小企業であってもサイバー攻撃に対する脅威にさらされている今、EDR、SOCの導入も必要でしょう。EDRはユーザーが利用するパソコンやサーバー(エンドポイント)の挙動を監視し、不審な挙動を検知し、対処する役割を担っています。一方、SOCはセキュリティイベントを集中管理し、リアルタイムでの脅威分析を担当します。これにより、迅速な対応が可能となり、情報の安全性が飛躍的に向上するのです。
アカウントの乗っ取り、不正ログインの防止のため、端末へのログインを2段階認証制にすることも、セキュリティを大きく強化するものです。通常のパスワードだけでなく、二次的な確認としてスマートフォンを使用した認証を取り入れる手法は、多くの大企業でも採用されています。不正アクセスのリスクを大幅に軽減できるため、特に重要な情報を扱う際には必須の対策といえます。
定期的な内部監査は、情報セキュリティを維持・強化するために欠かせません。重要な情報資産を守るため適切な情報セキュリティに関する監査を実施することで、セキュリティ状況の現状を把握し、新たなリスクや潜在的な問題点を早期に特定することが可能になります。さらに、監査結果を検証・評価し適切に活用することで、セキュリティ対策の改善や最適化がスムーズに進められます。
さらに、従業員教育も組織全体の情報セキュリティを高めるうえで重要な役割を果たします。従業員に対して定期的なトレーニングを実施し、最新の脅威や攻撃手法についての知識を提供することで、適切なセキュリティ意識を浸透させることができます。これにより、日常業務においても慎重な行動を徹底し、サイバー攻撃や内部リスクへの耐性を向上することが期待されます。
オフィスの入口における防犯も重要な要素です。訪問者を記録し、管理することで、不審者の侵入を未然に防ぐことが可能です。訪問者名簿や来訪目的を把握することは、セキュリティ対策の一環として非常に効果的です。また、入退室時にIDバッジを利用するなどの手法を取り入れることで、より厳重な管理体制を築くことができます。

セキュリティを重視する際の注意点を見ていきましょう。
セキュリティを重視することは、企業や個人事業主にとって避けて通れない課題です。企業における安全な情報管理と適切なシステム運用は、事業活動を左右するものでもあり、情報セキュリティを強化することは重要な責任と言えます。セキュリティ対策が不十分であれば、セキュリティインシデントリスクが高まり、企業の信頼性にも大きな影響があります。
導入しているセキュリティシステム、ハードウェアが、最新の脅威に対して十分な効果を発揮できるものか詳細を確認することは、全体的な情報セキュリティの強化において重要な責任の一環です。技術や攻撃手法は日々進化しているため、これまでの対策だけでは情報セキュリティにおける責任を果たしきれない場合があります。どのような機能があり、どのように運用されているのかを把握し、組織全体の安全性を向上させるための基盤を構築します。そのため、定期的なシステムの見直しを行い、必要に応じて改善や更新を進めることで、リスクに対する備えを確実なものにしましょう。システムの更新状況やサポート体制について理解しておくことで、緊急時に迅速な対応が可能となります。
高度になるサイバー攻撃など、企業を取り巻く情報セキュリティの脅威は、年々大きな問題となっています。どんなに完璧だと思われる対策も、時間が経てば、抜け道からセキュリティを突破されるというイタチごっこのような状態が続きます。そのため、トラブルは発生するということを前提に、いざトラブルが発生した際のインシデント対応体制についても、事前に確認しておくことが大切です。具体的には、インシデント対応チームが設けられているか、そのメンバーや役割が明確になっているかを確認する必要があります。迅速な対応が求められる中で、誰がどの責任を持つのかをあらかじめ把握しておくことは、冷静かつ的確な行動を取るための助けになります。
さらに、過去のトラブル映像や対処の教訓を元に、対応マニュアルが整備されているかも重要です。トラブル発生時に具体的な対応策を迅速に実行するための指針となり、責任の所在を明確にしながら効率的な対応を可能にします。情報の損失や被害を最小限に抑えることができるでしょう。日頃からの準備が、チーム全体の連携力とセキュリティの強化につながることを念頭に置きましょう。

大矢の経営視点のアドバイス
社労士事務所では、クライアント企業の重要な従業員情報を取り扱うことも多くあります。また、会社に関する機密情報に触れる機会もあるため、情報セキュリティの強化と責任を果たすためには、情報セキュリティに関する専門知識、体制、システムの運用状況ウォッチも重要な役割となります。常に、セキュリティ体制や運営を見直しながら適切な管理を行うとともに、後手に回らない対策に努めています。

セキュリティに強い社労士事務所を選ぶことは、企業や個人事業主にとって非常に重要です。数多くの社労士事務所が存在し、選択肢が多い中で、信頼できるパートナーを見極めるためには、いくつかのポイントを考慮することが求められます。とくに、情報漏洩防止策やマイナンバーの取扱いにおける意識の高さが、情報セキュリティ対策の充実度を示す重要な指標となります。セキュリティ意識が高く、適切な運用を実施している事務所かどうかを確認することをおすすめします。万が一、セキュリティインシデントが発生した場合、迅速かつ適切に対処できる体制や取り組んでいる社労士事務所と、自社のニーズが合致すれば、安心して依頼できるでしょう。とうかいにおいても、安心して業務をご依頼いただけるよう、万全なセキュリティ対策と情報セキュリティ管理を行っておりますので、ご興味をお持ちの方は、お問い合わせください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」