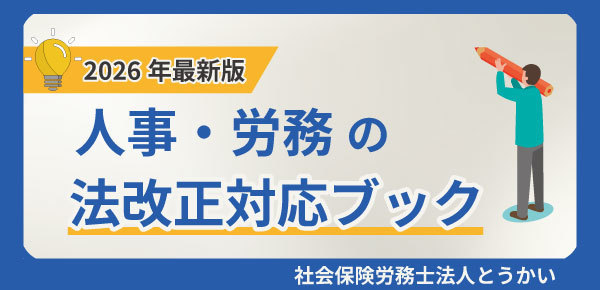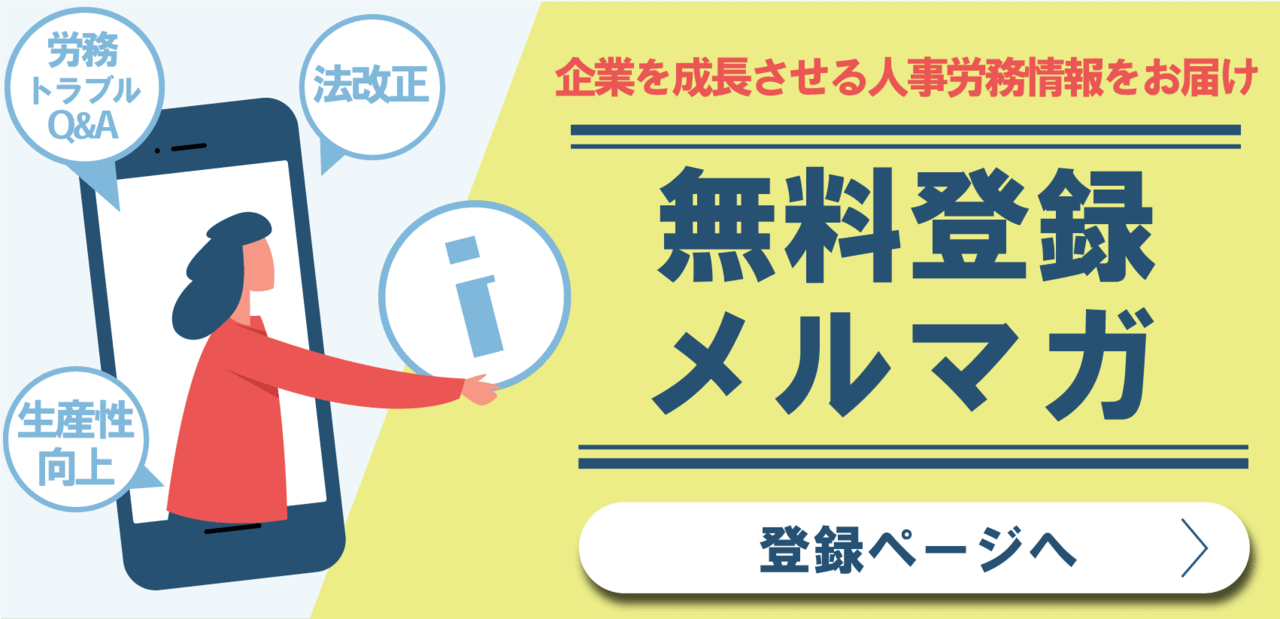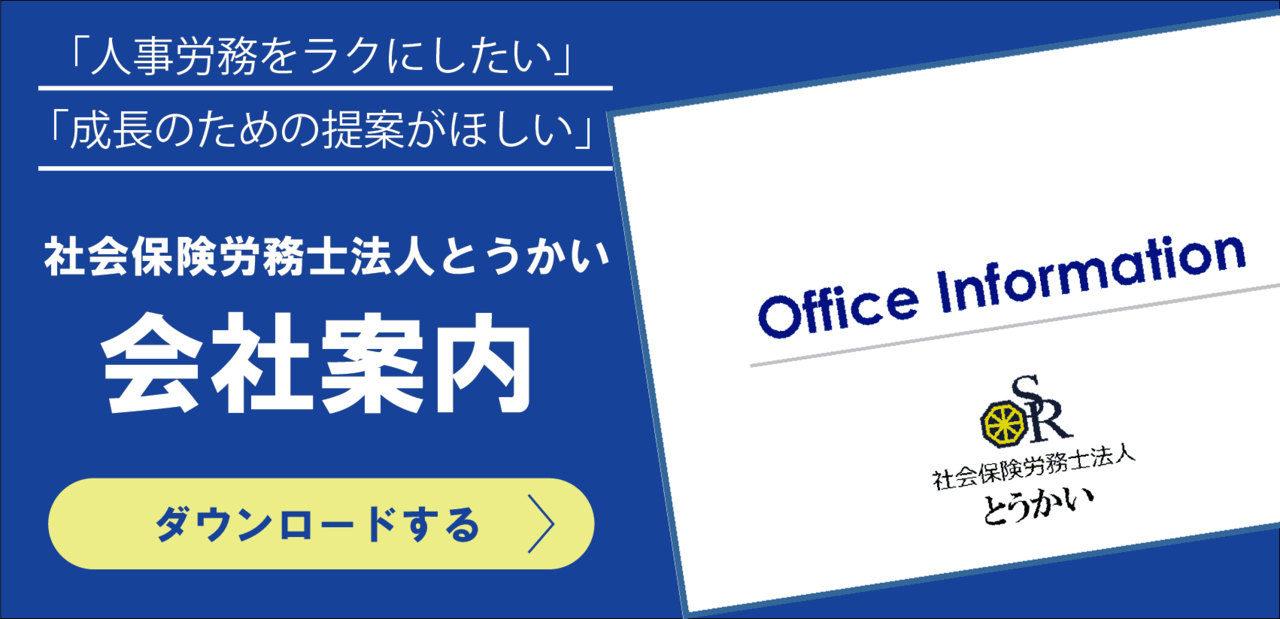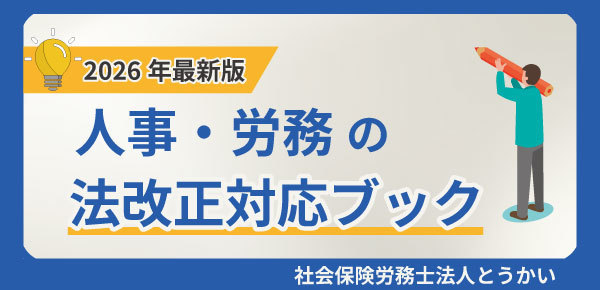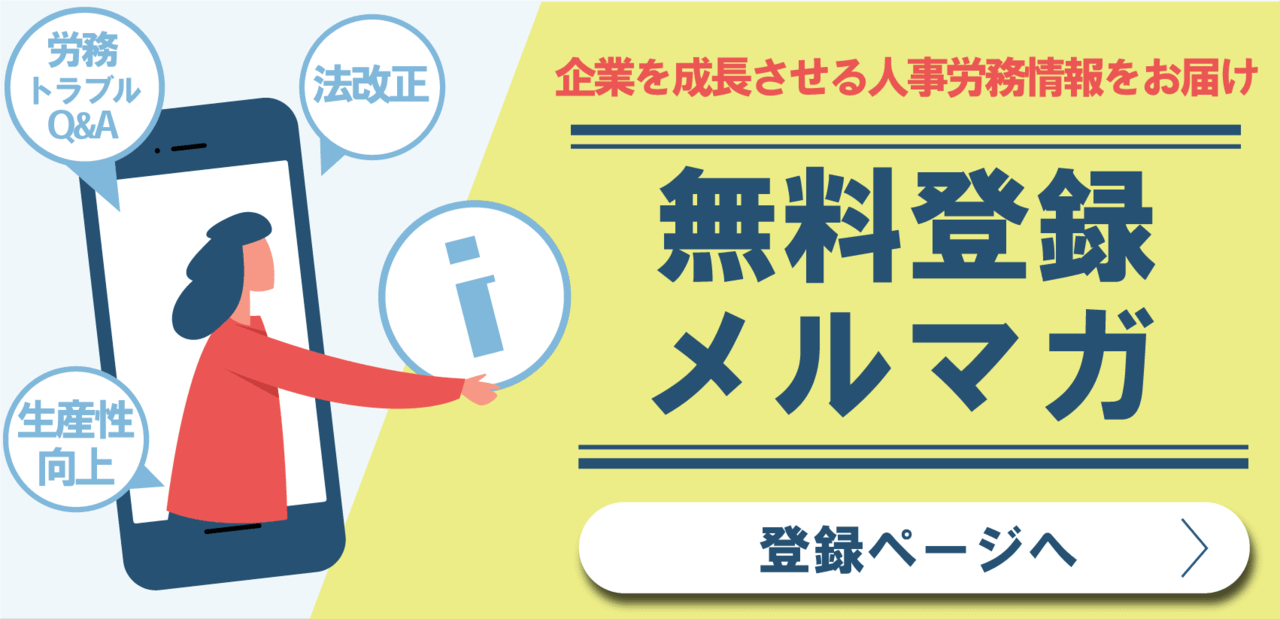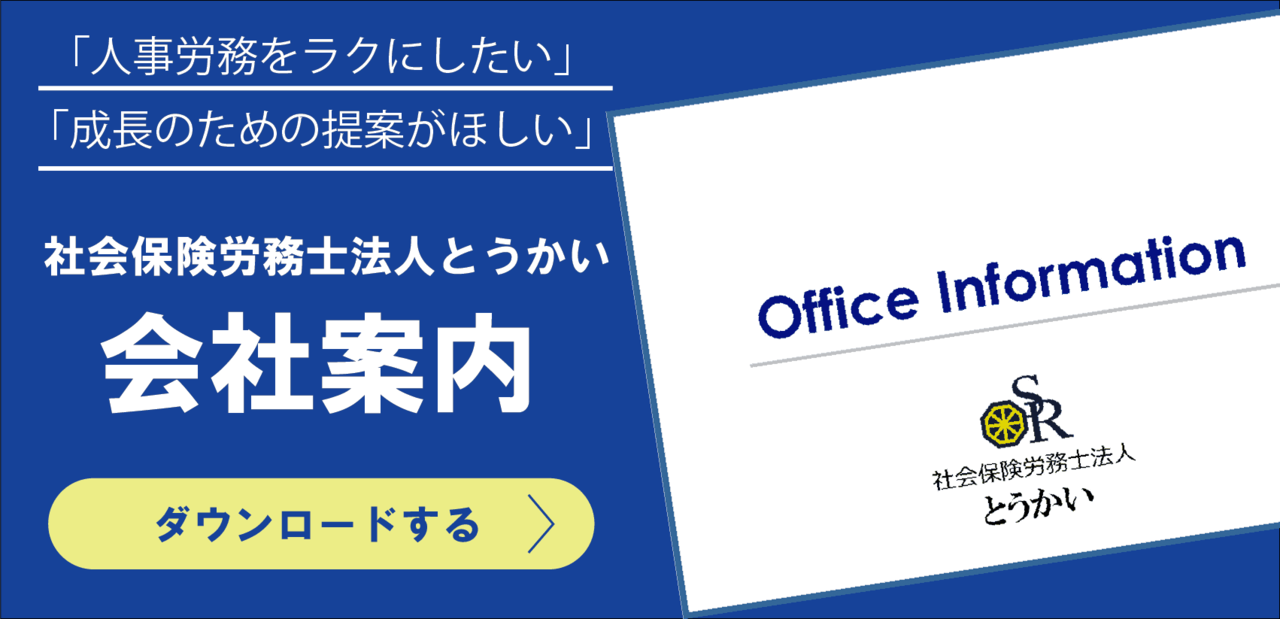2026年4月から【独身税】がスタート!?
「子ども・子育て支援金」はいくら徴収される?

2026年4月から開始される「独身税」。正式には「子供子育て支援金」という制度で、子どもや子育て世代に向けた支援が行われる見込みです。制度の内容や具体的な影響について、多くの人々がその詳細を気にかけています。特に独身者や子育てをする家庭にとって、この新しい制度は一体どのような意味を持つのでしょうか。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

独身税の概要と導入背景について解説します。
独身税は、いわば俗称であり、正確には税金ではありません。少子化対策の一環として2026年4月からスタートする「子ども・子育て支援金」という制度です。端的に言えば、社会保険料の上乗せになります。つまり、独身の人のみが負担するものではなく、健康保険に加入していれば「子ども・子育て支援金」が上乗せされるということです。従来から少子高齢化により社会保障費が増大し、労働人口の減少が経済に悪影響を及ぼす懸念されてきました。そこで、少子化対策の一環として、子育て世帯のための支援や育児インフラの充実に充てることが考えられています。
しかし、この政策には独身者に対する不公平感や経済的な負荷を懸念する声もあり、導入に向けた議論が必要です。政策的観点からは、より包括的かつ持続可能な少子化対策が求められています。
独身税とも呼ばれる子ども・子育て支援金は、公的医療保険に上乗せされる形で徴収される保険料のことです。これは、税金ではなく社会保険料の一部として扱われます。この独身税と言われる所以は、子育てをしない独身者であっても保険料を徴収されることから、独身者に損ではないかということから生まれました。すべての公的医療保険に加入する人々が対象となりますので、独身者だけが負担するわけではありません。したがって、正しい理解が必要です。
少子化が進む中で、国はこれを防ぐための対策を検討しています。この独身税とも呼ばれる子ども・子育て支援金の導入は、少子化問題の解消を目指す政策の一環です。社会保険料に上乗せして徴収される資金は、子育て世代の支援金や育児に関する施策に使われる予定です。つまり、独身税は単なる負担増ではなく、未来の世代を支えるための重要な財源となると位置付けられています。

高谷の経営視点のアドバイス
子ども・子育て支援には、少子化・人口減少のための施策です。2026年4月からスタートすることで、約1兆円程度の原資が確保されると言われています。この原資に別建ての3.6兆円の予算を加えて、子ども・子育てに携わる人々を支援していこうというものです。国をあげて、サポートしましょう、という制度です。

2026年4月から施行される背景と理由を詳しく見ていきましょう。
2026年4月から施行される独身税は、急速に進行する少子高齢化が社会保障制度や経済成長に深刻な影響を与えます。企業においても少子化は、重要な関心事です。労働人口の減少に向かえば人材確保は難しくなるでしょう。この少子化に歯止めをかけるための政策の一環として、独身税つまり子ども・子育て支援金が導入されるものです。独身税の導入によって、企業や家庭における働き手や子供の増加を目指しており、長期的には社会全体の安定を図ることを目的としています。この政策の是非については、多様な意見が交わされていますが、少子化問題に対する切実な解決策として期待される一方で、実効性や公平性に関しても議論が続けられています。
独身税の導入は、少子化が深刻な問題となっていることが大きな要因です。もちろん、独身税に対する反対意見も存在します。負担感を強く感じる人々が多く、実態を考慮した対策が必要との意見もあります。ただ国は、これまで少子化の対策において模索してきましたが、大きな成果にはつながっていません。待ったなしの状況に、一層の真剣な取り組みが求められており、導入に踏み切ったことになります。
2026年4月に独身税が施行される背景には、準備期間を設ける必要があるからです。国は、制度の整備や周知活動を進める時間が求められており、そのためにはしっかりとしたスケジュールが必要です。
加えて、この時期には他の政策とも連携して、より効果的に少子化対策を進める狙いがあります。制度開始から一定の間隔を持つことで、影響を分析しながら調整が行える体制も意図されているでしょう。2026年4月からの実施は、国全体の目標を達成するための重要な一歩とも言えます。

鶴見の経営視点のアドバイス
2026年4月からスタートする子ども・子育て支援金は、社会保険料から徴収されることになります。また、年々負担額も増加していくとのことですから、注目していく必要があるでしょう。社会保険料を労使折半する企業にとっても、無視できない重要な施策です。

子ども・子育て支援金の額と使途を見ていきましょう。
少子化対策である子ども・子育て支援金の具体的な内容を確認していきましょう。独人税とも揶揄される子ども・子育て支援金の財源は、国民の社会保険料の上乗せ分として徴収されることになります。年収に応じて、月額数百円を負担することになります。企業であれば、労使で折半になりますので、企業にも同様の負担が生じることになります。この徴収された資金がどのような形で子ども・子育て支援金として活用されるのか、今後の動向にも注目です。
2026年4月にスタートする独身税は、子ども・子育て支援金の原資となります。その使い途は子どもの出産から大学を卒業するまで、子どもが成長していく過程で発生するさまざまな費用に対しても支援がなされるなど多岐に渡ります。
たとえば、妊娠や出産時の支援強化、出産育児一時金の引き上げ、子育て世帯への住宅支援なども予定されています。従来からある児童手当についても拡充がされていきます。このように、子育て支援金は単なる財政的な支援を超えて、家庭の育児における必要なサポートとなることが期待されています。
2026年4月以降に実施される子ども・子育て支援金は、多くの子育て世代に恩恵をもたらすことが期待されています。例えば、従来の児童手当が拡充され、所得制限が撤廃されたり、支給対象が高校生まで延長されたことが挙げられます。さらに、第三子以降に対して特別支援金が支給されることから、家計に対する助けが強化される方向にあります。子ども1人あたり約206万円から約352万円まで増加することになります。

大矢の経営視点のアドバイス
子ども・子育て支援に関する使い途は、国から出されている「こども未来戦略」に詳しく記載されています。
2025年4月から育児休業給付金が80%に引き上げ!!

制度に対する懸念と課題についてお話しします。
独身税は、独身者への負担を多くする制度として、不満の声があがるなど議論がされています。独身者が経済的負担を感じ、平等性に欠けるとの声もあります。さらに、企業経営者や政策関係者の間では、この制度が経済や社会にどのような影響を与えるかが懸念されています。ただ、少子化対策は、直接的な子育て世代への支援だけではく、子どもたちの育成に社会全体で支えていこうというものです。今後の少子化対策として、バランスの取れたアプローチが求められています。
独身税に対する反対意見は多岐にわたります。まず、独身者のみが負担を強いられることに不公平感を抱いている人々が少なくありません。他の世帯と比較して、独身者が子育てに直接関与していないにもかかわらず、経済的な負担が課せられる点は大きな問題として挙げられます。
また、独身税の効果について懐疑的な見方もあります。実際に、徴収された資金がどのように運用されるのかが不透明であるため、目的が達成される保証がないという声もあります。資金が別の目的に流用されることへの不安もあり、制度が本当に効果的となるかは、社会全体の信頼をどう築いていくかにかかっていると言えます。
このように、独身税に対する反対意見は、制度の本質や運用方法に起因していることが多いでしょう。
独身税が少子化問題に対する有効な解決策であるかどうかには疑問の声が上がっています。少子化の原因は多岐にわたり、経済的な要因だけでなく、社会的な要因や教育環境なども影響を与えています。たとえば、子育てに必要なコストや、子育てを支援するためのインフラの整備が遅れている場合、税金の増額がそのまま解決につながるとは限りません。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
少子化の原因は、確かに独身者の増加という一面はあるものの、その他にも雇用の不安定さ、子育てにかかるお金の問題、仕事と育児の両立の難しさなど、多くの要因があります。これらの一つひとつを紐解き、対応していかなければ少子化対策として十分とは言えないでしょう。

将来の影響と展望を見ていきましょう。
独身税とよばれる子ども・子育て支援金は、結婚や子育てに対するインセンティブを提供し、出生率の向上を図ることです。背景には、労働人口の減少や高齢化社会の進行があり、経済や社会保障制度に深刻な影響を及ぼす懸念が高まっています。この税の導入によって、独身者に限らず一定の経済負担が生じる一方で、家庭を持つことの経済的支援が増えることが期待されています。
独身税の導入は、社会保険料の上乗せ徴収されることから、直接的な経済的負担を強いることになるため、心配の声が上がっています。生活費が圧迫されることが考えられます。特に、生活コストが増加する中での家計管理には、さらなる工夫が求められるでしょう。
また、企業に対しても影響が予測されます。従業員の給与から社会保険料として天引きされるため、手取り収入が減少します。この状況は、従業員のモチベーションや労働環境にも影響を及ぼす可能性があります。企業側としても、給与の見直しや福利厚生の充実が求められる時代になるかもしれません。
少子化が深刻な課題となる中、国が進める子ども・子育て支援金は、期待の声もある一方で、導入するだけでは、根本的な解決にはならないという意見も少なくありません。少子化を解消するためには、結婚や出産を後押しするための包括的な支援策が重要です。人事労務の面から考えれば、従業員の働き方、育児を行う従業員への支援など、子育てに対する金銭面や時間面での支援が考慮されるべきでしょう。たとえば、育児休業の取得促進や、保育施設の充実を図ることで、より多くの人が安心して子どもを持つことができる環境が整えられるでしょう。少子化問題に向けた取り組みは、独身税を含めた多角的なアプローチが求められています。
2025年4月から育児休業給付金が80%に引き上げ!!
よくあるご質問
ここではよくあるご質問をご紹介します。
「独身税」という言葉を聞きますが、正式にはどのような制度ですか?
独身税」は俗称であり、正式名称は「子ども・子育て支援金」制度です。
これは税金ではなく、少子化対策の財源を確保するために、公的医療保険の保険料に上乗せして徴収される社会保険料の一部として位置づけられています。
子ども・子育て支援金はいつから始まりますか?
2026年(令和8年)4月から施行される予定です。
この制度は、急速な少子高齢化への対策として、準備期間を経て開始されます。
この支援金は、独身者だけが負担するのでしょうか?
いいえ、独身者のみが負担するものではありません。
すべての公的医療保険に加入している方が、所得に応じて社会保険料に上乗せされる形で負担します。企業においても労使折半で同様の負担が生じます。
毎月の負担額はどのくらいになる見込みですか?
負担額は年収によって異なりますが、開始当初は年収に応じて月額数百円程度の負担となる見込みです。
また、この負担額は年々増加していくことが示唆されており、今後の動向に注目が必要です。
徴収された子ども・子育て支援金は、具体的に何に使われるのですか?
子どもの出産から大学卒業まで、成長過程で発生するさまざまな費用への支援に使われます。
具体的には、「こども未来戦略」に基づき、妊娠・出産時の支援強化、児童手当の所得制限撤廃や支給対象の高校生までの延長・拡充などが予定されています。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」