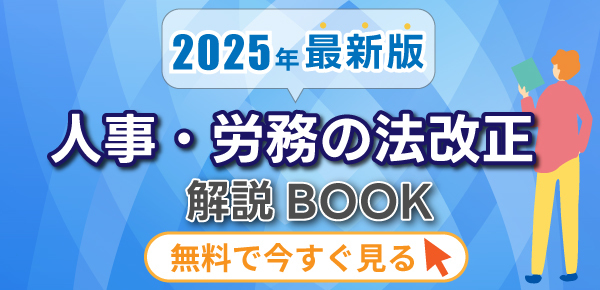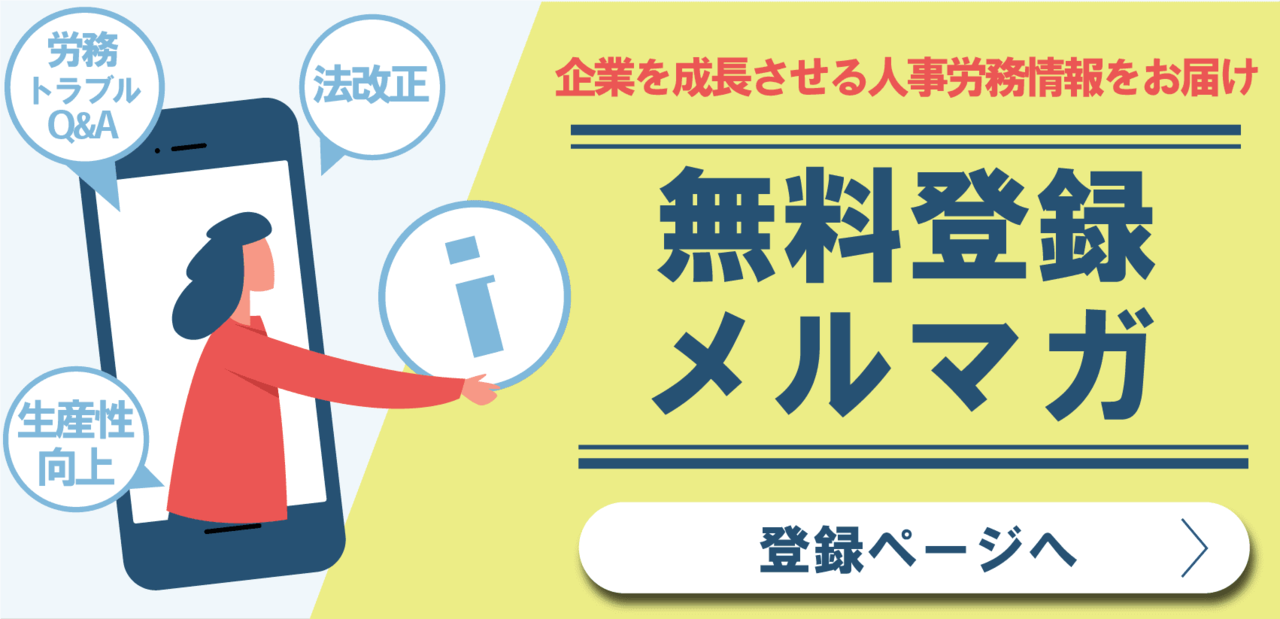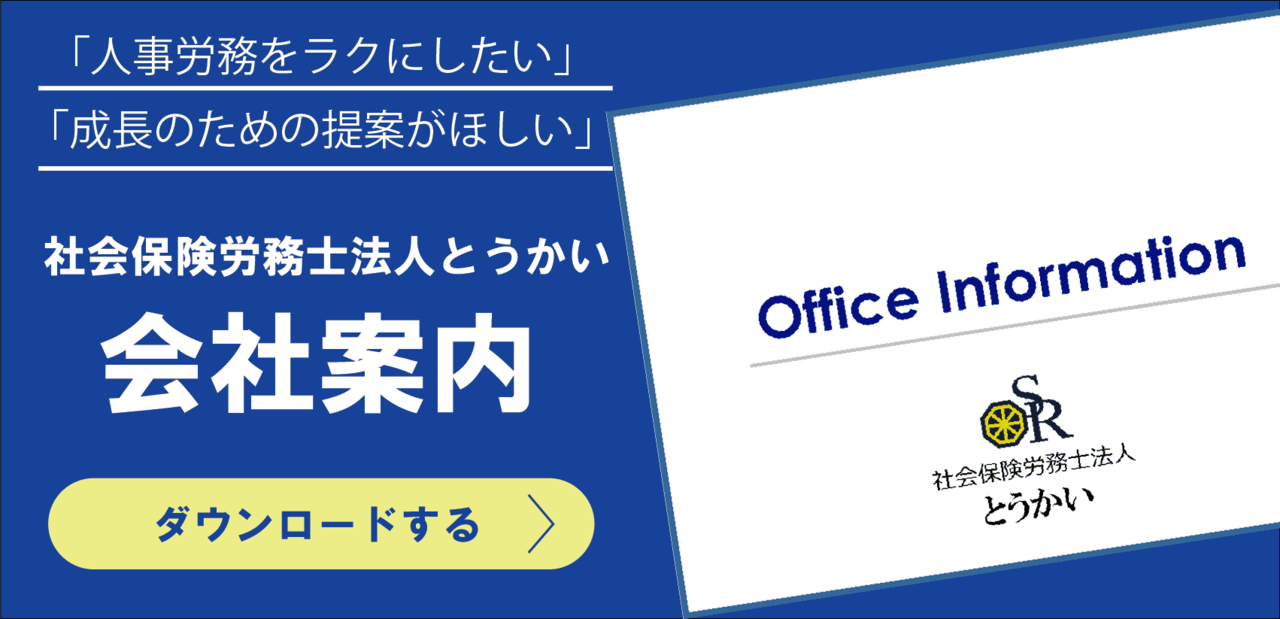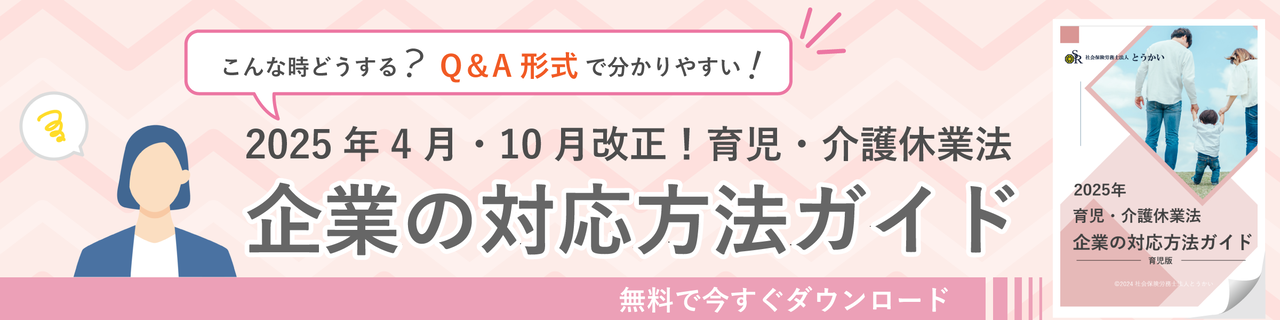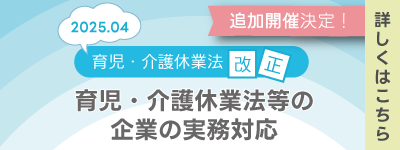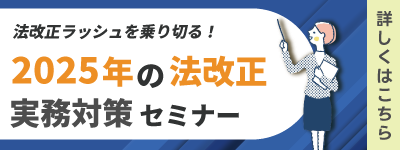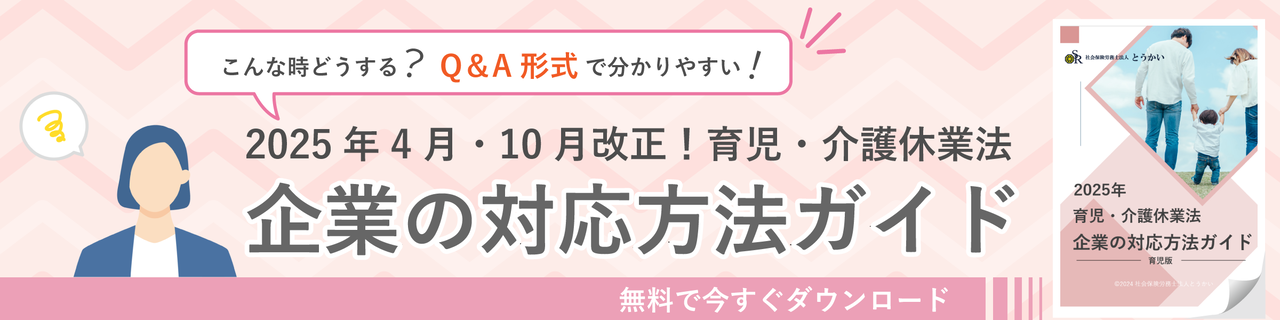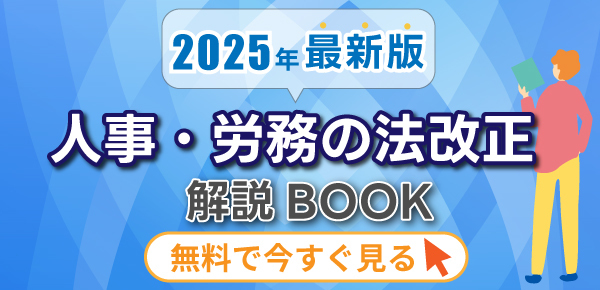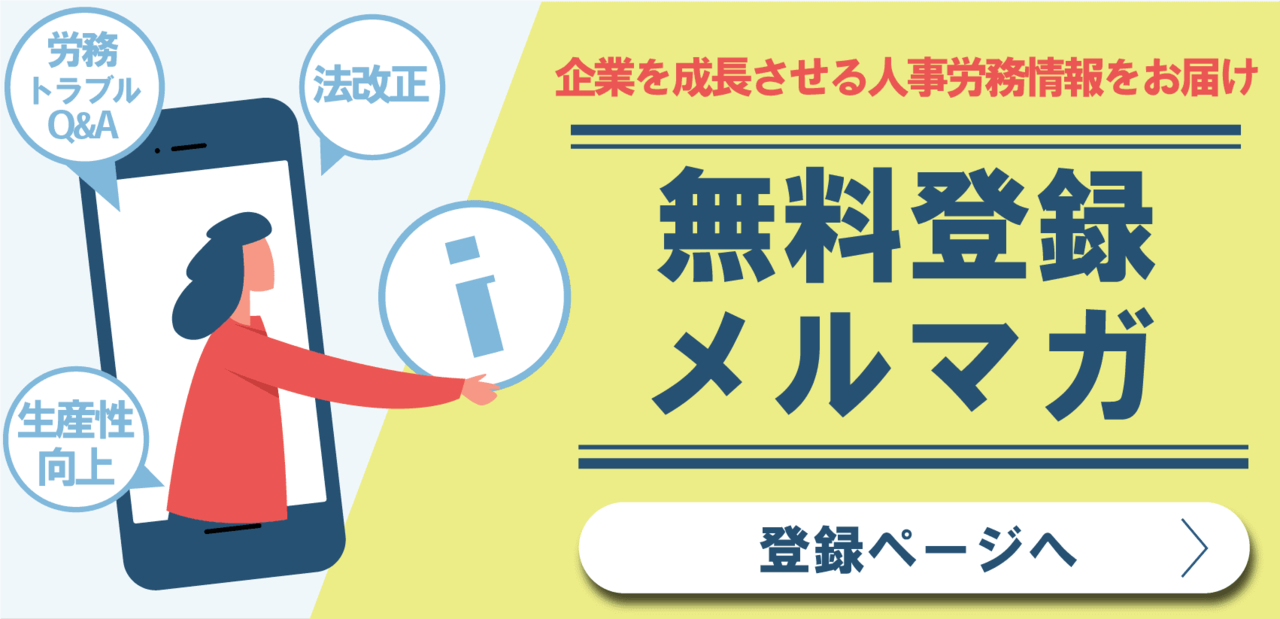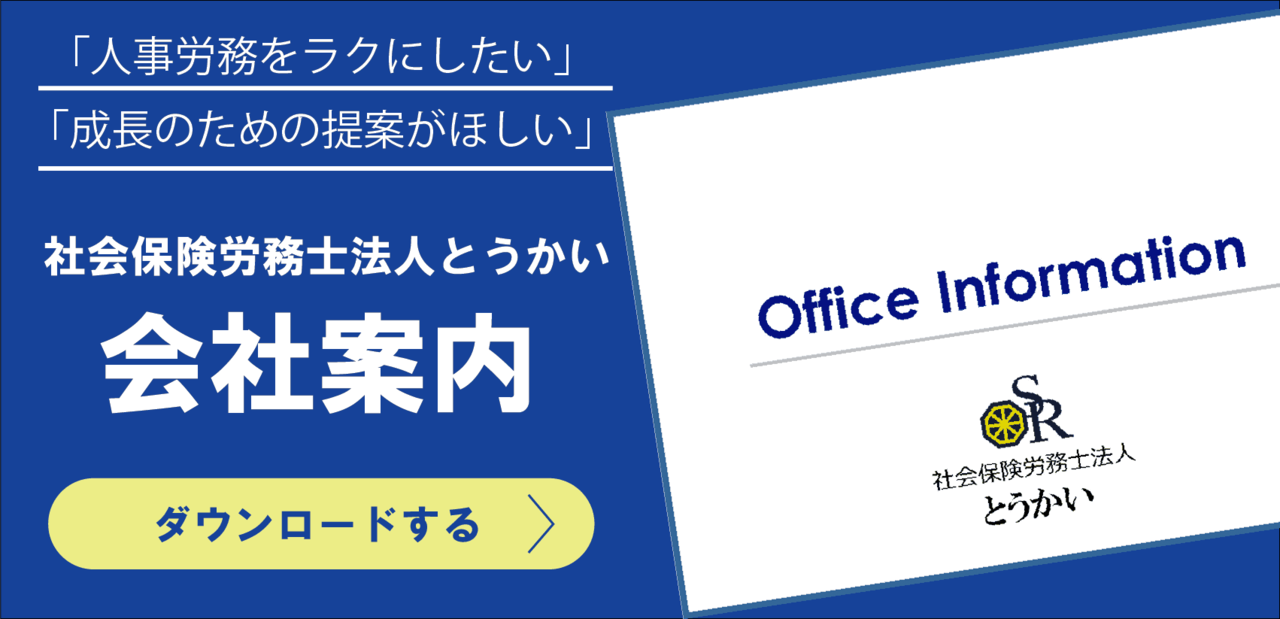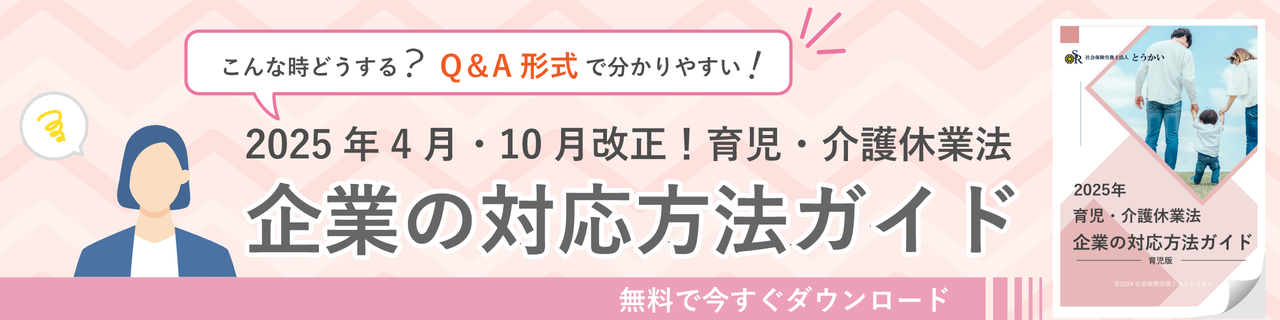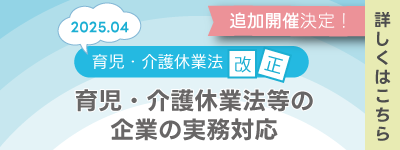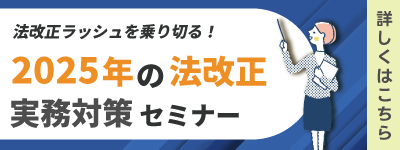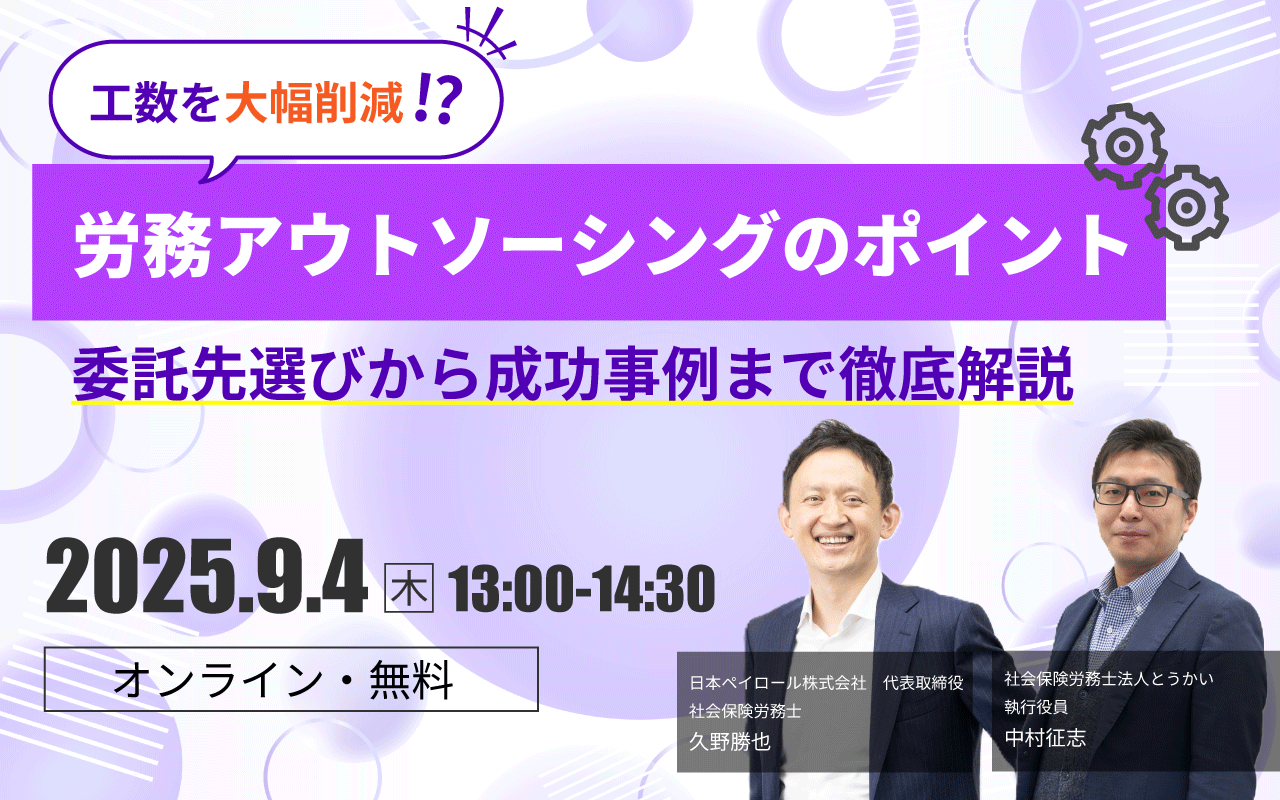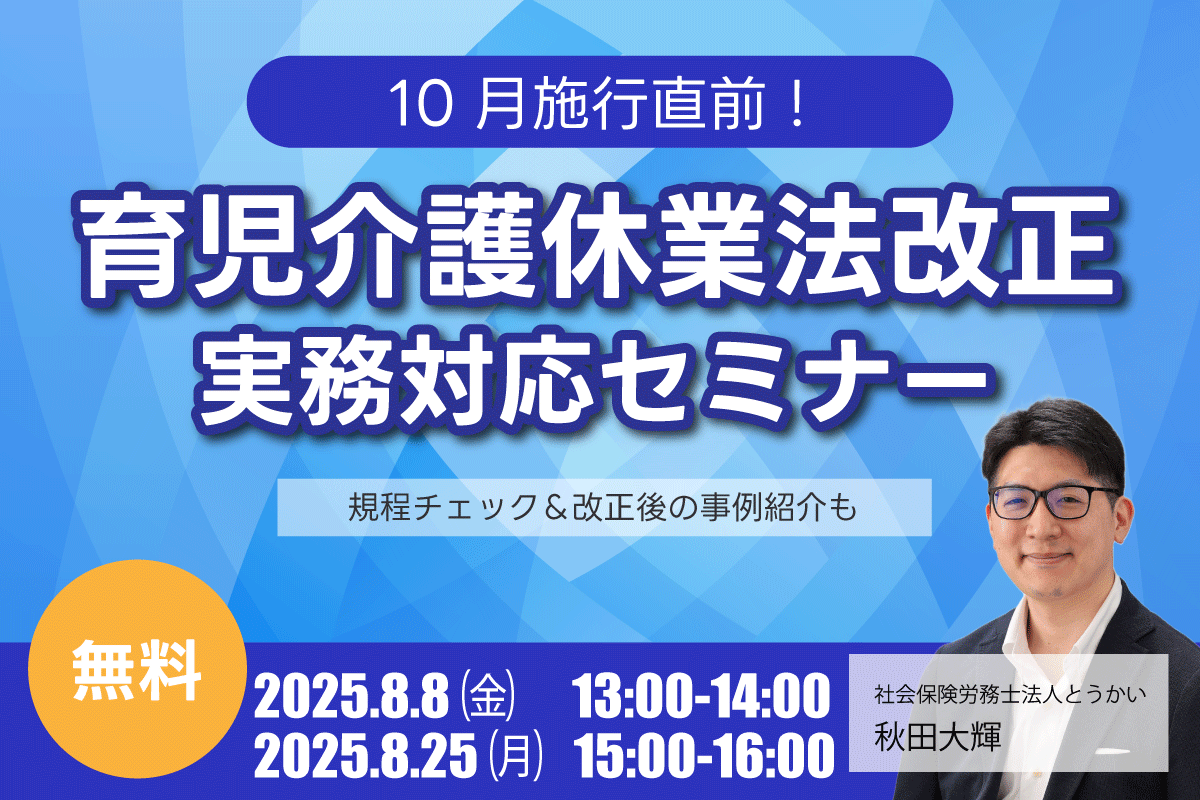育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが厳格化されます!
2025年4月からの変更点と対策

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが厳格化されます!2025年4月からの変更点と対策
2025年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが改正され厳格化されます。この改正は、保育所へ入所できないことを理由に育児休業給付金の延長をする際の手続きが、今より厳密に行われるようになります。具体的には、新たに必要となる書類の追加や、申請者が保育所等への申し込みの正当性を証明するための基準が設けられます。
人事労務担当者、育休を予定・取得する従業員にとっては、重要な改正内容となります。必要な手続きや準備を怠ることがないよう、予め確認、理解しておきましょう。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

支給対象期間延長手続きについて詳しく解説します。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きとは、出産後に原則1歳を満たない子の育児を行う従業員が受け取る給付金を、一定の条件を満たせば2歳となる日の前日まで延長するための手続きです。この延長手続きは、保育所に入所できない場合や、その他の特別な事情によって育児を続ける必要がある場合に適用されます。従業員が育児休業を利用することで、家庭の状況やライフスタイルに合った育児が可能となりますが、延長申請には様々な条件が伴います。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの改正は、手続きを厳格化する背景が存在します。これまでの制度では、延長理由として保育所に入所できなかった理由について、適正であるかどうかの確認が不十分でした。いわば、育休を延長するために、意図的に倍率の高い保育所に申し込みを行う「落選狙い」と呼ばれる事例が増加していました。このような背景を踏まえて、厚生労働省は社会保険制度の健全化を図り、真に保育所利用を希望する従業員を支援し、適正な利用がなされるように、新たなルールが設けられることになりました。
今回の改正は、2025年4月から行われます。子どもが1歳に達する日または1歳6カ月に達する日が2025年4月1日以降の従業員で、育児休業給付金の延長手続きを行う場合に対象となります。また、パパ・ママ育休プラス制度を利用している場合でも、育児休業の終了予定日が子どもの1歳の誕生日後である場合も、対象になりますので、適切な手続きを行う必要があります。人事担当者も対象者である従業員も、事前に手続きが変更されることを理解し、スムーズに申請を進める準備が求められます。
育児休業給付金の支給対象期間を延長するための条件が、2025年4月から厳格化されます。保育所に入れなかったことを理由に育児休業給付金の延長をするためには、保育所などへの利用申し込みが速やかな職場復帰のために行ったと認められることが必要となります。育児休業給付金の延長について不正な申請がされないよう、今回の改正では、ハローワークにおける審査がより詳細になり、保育所への申込状況や入所見込みの有無が厳しくチェックされることとなります。例えば、予め市区町村に対して保育利用の申込をすることになりますが、その申込が自宅や職場から遠すぎる保育所ではない、妥当なものだったかどうかについても判断材料になる点に注意が必要です。加えて、申込の期限や条件を守らない場合、延長が認められないリスクもあります。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きに際して、改定後新たに求められる提出書類があります。まず、現在の制度では市区町村が発行する保育所の利用ができない旨の通知として入所保留通知書が必要でしたが、2025年4月以降は追加で「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と、保育所等の利用申し込み時の申込書の写しも提出することが求められます。これらの書類を用意することで、延長を希望する正当な理由を証明することができ、スムーズな手続きを促進します。準備を整えた上で、必要な書類をしっかりと確認することが重要です。
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書とは、従業員である申請者が育児休業給付金の延長を希望する際に、提出しなければならない重要な書類です。この書類には、保育所等への利用申し込み状況や、速やかな職場復帰を希望している旨が記載されます。具体的には、申請者自身が記入し、保育所に申し込みをした日、利用開始希望日など、条件を詳細に記載します。
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の書き方や提出方法について注意が必要です。育児休業給付金の延長に関して、不正受給が発生しないよう厳格化されることになりましたので、保育所などへの利用申し込み状況を正確に反映しなければなりません。具体的な日付や希望入所日を記載し、提出期限までにハローワークに提出します。書類に不備があると、延長の申請が遅れる可能性があるため、記載内容の確認は慎重に行いましょう。また、提出する書類は必要な場合に追加で求められることもあるため、常に最新の情報をチェックしておくことが役立ちます。
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の提出時には、いくつかの注意点があります。記入内容に誤りがあれば、申請が無効となることがあるため、正確な情報の記載を心がけるべきです。また、利用申し込み先の保育所の通所時間が合理的かどうかも審査の対象となります。自宅までのアクセスや通行方法も考慮し、無理のない範囲の保育所へ申し込みを行うことが求められます。特に、申し込みが落選してしまった理由や、内定辞退の有無により、延長の可否が影響を受ける点にも留意が必要です。
市区町村に保育所等の利用申し込みを行った際の申込書の写しも、今後の手続きでは必須の書類です。この写しは、従業員がどのような保育所に申し込みを行ったのかを証明する重要なデータとなります。申込書のすべてのページを用意し、市区町村に提出したものと同様のものである必要があります。申込内容に変更があった場合は、最新の情報を反映させた写しを提出し、保育所の申し込み状況が正確に分かるように整えなければなりません。
市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知は、入所できなかった理由を証明するために必要です。今回の改正に関わらず、必要な書類です。この通知書は、実際に申し込みをした上で、入所が保留されたり、内定を辞退したことを示す重要な書類です。この通知書が交付されたタイミングにも注意が必要で、子が1歳に達する日の翌日が基準となり、その時期までに保育が実施されっていないことを確認するために、発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2か月前の日以後の日付となっている必要があります。この通知書が正しい情報を反映し、育児休業給付金の支給期間延長に役立つよう、事前にしっかりと確認し、保管しておくことが大切です。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
従業員にとっては、育児休業給付金を延長できるか、できないかは、非常に大きな影響がある大切な手続きになります。いざとなって手続きを忘れていた、遅れていた、というわけにはいきません。早め、早めに準備できるよう、まずは制度をしっかりと理解したうえで、従業員への説明を行うことをおすすめします。

どんな状況が延長の対象になるのかみていきましょう。
育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きには、市区町村が発行する入所保留通知書や、不承諾通知書を用意して、延長の要件が認められなければなりません。
延長が認められるためには、特定の条件が満たされなければならないのです。保育所の申込みの状況や希望入所先について、厳格に確認されます。延長の対象となる事例は、保育所に入所申し込みを行い、その結果入所ができなかった場合です。入所できない理由が、保育所の定員に達していた場合や、入所希望条件が満たされていなかった場合には、延長の可能性が高まります。ただし、単に入所の申し込みを失念していた場合や、保育所への入所希望日を1歳の誕生日以降に設定していたなど条件を満たさなかった時には、延長が認められないことも考えられます。これらの条件を理解していないと、延長申請が認められないことにつながります。
もし保育所への入所申込みを行わなかった場合、その理由にかかわらず育児休業給付金の支給対象期間の延長は非常に厳しいでしょう。保育所を利用することが前提となっているため、申し込みを行うことは不可欠です。たとえ事情があったとしても、公式な申し込みをしていなければ、延長を申し立てる根拠が失われます。これにより、延長を希望する従業員にとっては、事前に計画を立て、保育所への申し込みを済ませることが重要となります。
育児休業給付金の支給対象期間延長を申請する際、保育所への入所希望日を子が1歳に達する日の翌日以降に設定していると、延長が認められません。この場合、保育所に入所する意思が薄いと判断され、申請が却下される可能性があります。従業員は、育児休業期間中に最大限の支援を受けるためには、希望入所日を適切に設定する必要があります。事前に状況を分析し、早めの対応が求められます。
育児休業給付金の支給対象期間延長に関しては、要件に該当しないと、延長は認められませんが、例外的なケースも存在します。
保育所に一次申し込みで内定を受けたものの、その後辞退し、続く二次申し込みで落選した場合にも入所不承諾通知書が通知され、その事実が記載されることになります。その場合、内定を辞退した理由が、やむを得ないと認められれば、延長を認められることになります。この場合、従業員が保育所利用への誠実な意図を持って行動していることを示す必要があります。やむを得ない理由なく、内定辞退をしているケースなどは、延長申請は認められません。内定辞退した理由として、申込時点と内定時点で住所や勤務場所が変わり、内定した保育所への入所が困難な場合などが該当します。
一方で、単に申し込みを失念していた場合には、育児休業給付金の支給期間延長が認められないのが一般的です。これは、申し込みを行わなかったことについての正当な理由がないと捉えられ、意図的に利用の意思が低かったと判断されるからです。持続的に育児休業給付金を利用するためには、申し込みのタイミングを見逃さないことや、期限をしっかりと管理することが求められます。

小栗の経営視点のアドバイス
人事担当者のみなさんにとって、育児休業制度は複雑でわかりにくいという声もよく聞きます。1歳の誕生日、1歳の誕生日の前日、、パパが育休をとる場合、一緒に育休をとる場合、さまざまな基準やケースが複雑に絡み合うので、非常に混乱してしまうのです。しかも、手続きを間違えると大ごとになるので、神経を使うものです。誤りなく、スムーズに手続きを行うためにも、疑問点や不明点があれば、早めにハローワークや顧問社労士に相談して、準備を進めておきましょう。

トラブルを避けるために企業ができることをあげていきます。
育児休業給付金の支給対象期間延長を巡るトラブルを未然に防ぐためには、企業が適切な対応を行うことが重要です。育児休業が必要な従業員に対して、改正された制度内容をしっかりと把握し、適切な情報提供を行いましょう。特に、申請に必要な書類や、提出のタイミングについて丁寧に理解できるよう説明にすることがカギとなります。従業員が必要な手続きを理解できていれば、延長を希望していたが不備で認められなかったという状況を避けることができます。
企業は、育児休業給付金の支給対象期間延長に関連する書類の整備を進めておきましょう。例えば、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書のフォーマットを用意するとともに、それに必要な情報を事前に伝えることでスムーズな申請を促せます。申請者が必要な書類を見落とすことを防ぎ、正しいタイミングでの提出をサポートすることが可能です。
従業員には、育児休業給付金の支給対象期間延長に関する情報を周知させることが重要です。従業員に具体的な手続きや必要書類を明示し、誤解やトラブルのリスクを防ぎましょう。育児休業に関するセミナーなどを通じて、制度の概要、これまでとの変化や申請方法を定期的に伝えることが重要です。特に、育児休業中の従業員には、丁寧に説明を行う配慮が必要です。従業員が申請に関する疑問や不安を解消するためのサポート体制を整え、気軽に相談できる環境にしましょう。それには、人事部門が正確な情報を持ち、具体的なアドバイスを提供することが肝心です。従業員が迷わず手続きを進め、「育児休業給付金、延長できなかった」といったトラブルに直面しないような準備を進めていきましょう。
育児休業給付金の不正延長は厳禁です。育児休業給付金を延長するために、不正に保育所の入所申請を行うケースが増加したことから、今回の改正にもつながっています。本当に保育所を必要としている人の利用機会の妨げにもなりますので、企業として従業員に強く伝える必要があります。雇用保険制度の重要性や、育児休業給付金の適正な利用を理解させることで、従業員が誤った知識にもとづいて行動することを防ぎます。また、不正があった場合のペナルティについても周知しておくと良いでしょう。
実際に、雇用保険の制度に従えば、正当な理由がない限り育児休業給付金の支給対象期間延長は認められません。このような基準を明示し、従業員が覚えておくべきポイントを定期的に再確認することで、制度の遵守を促すことができます。また、企業自身も必要な書類や申請方法に対する正確な理解を深め、法令遵守を徹底することが重要です。

育児休業給付金の支給対象期間延長に関する2025年4月の改正は重要な変更点です。従業員は育児休業給付金支給対象期間延長を行うための具体的な手続き、保育所への入所申込みについて、正確な知識と準備がスムーズな手続きの進行に影響を与えることになります。
企業にとっては、従業員が改正された手続きに困らないよう、十分な周知活動が欠かせません。必要な書類や提出方法についての情報提供が従業員の理解を深め、トラブルを回避する助けとなります。また、不正の防止にも目を向けることで、制度の透明性を維持し、従業員が安心して育児休業を取得できる環境を構築できます。
今後、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きがますます重要なテーマとなることが予想されます。企業は法令に基づいた正しい情報を提供し、従業員が制度を適切に利用できるようにサポートしていく姿勢が求められます。育児を支援する制度の意義を再確認し、家庭と仕事の両立ができる職場環境を整備していきましょう。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」