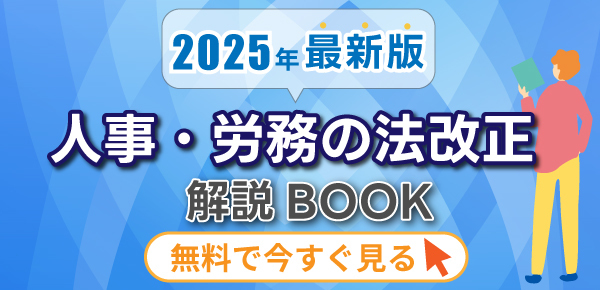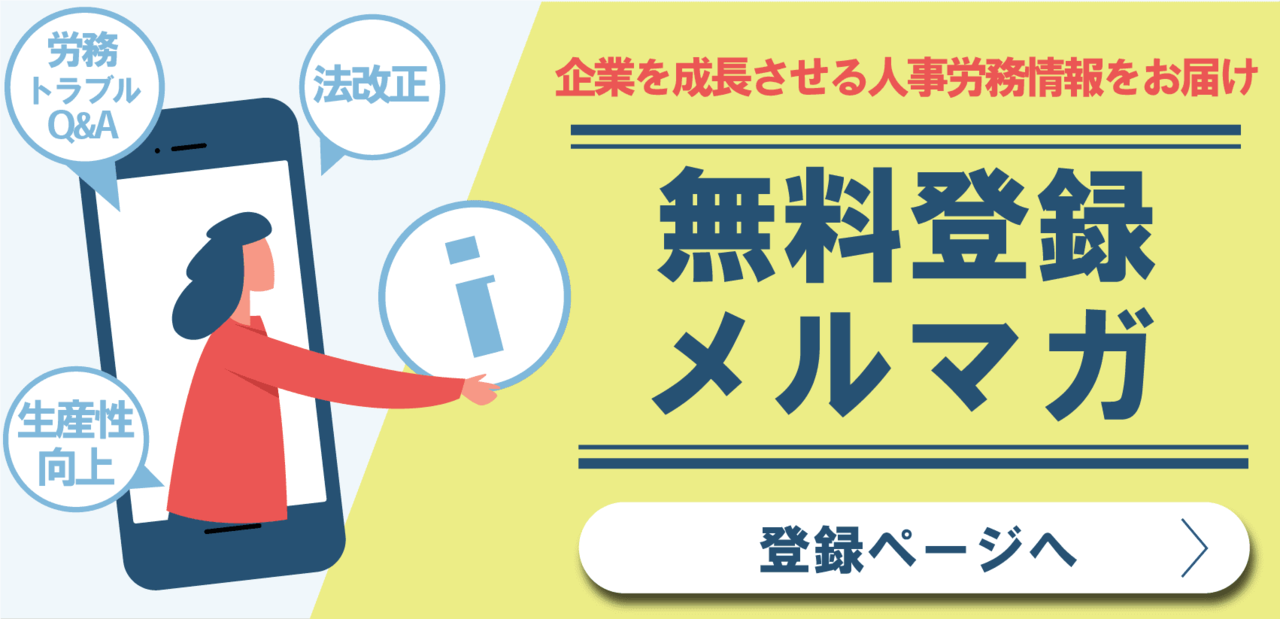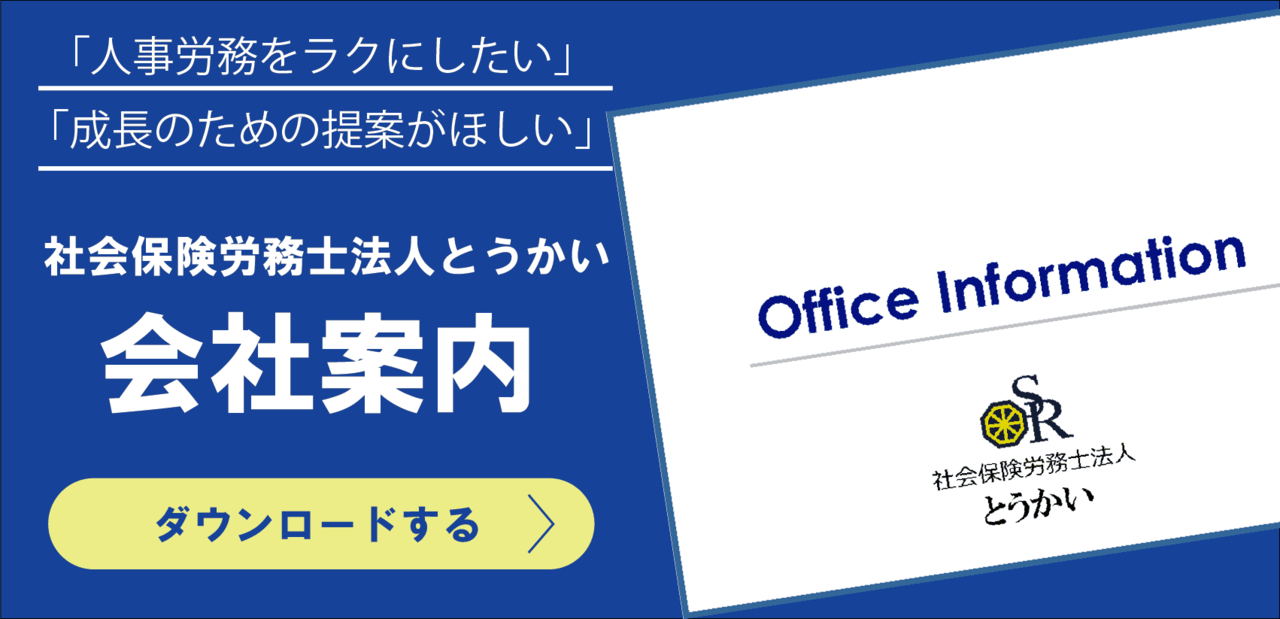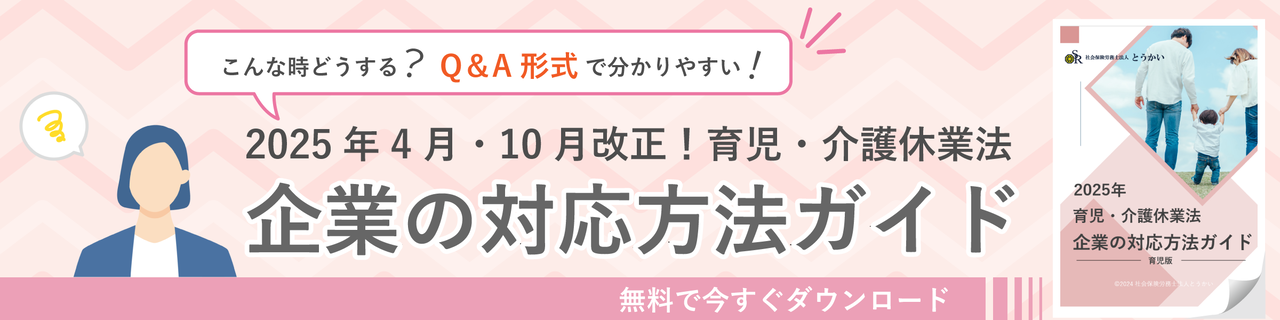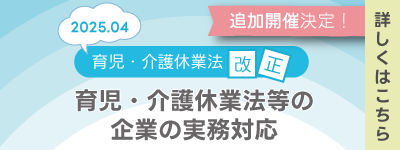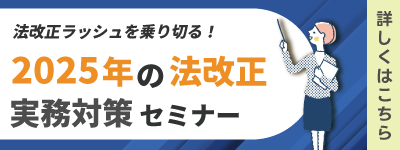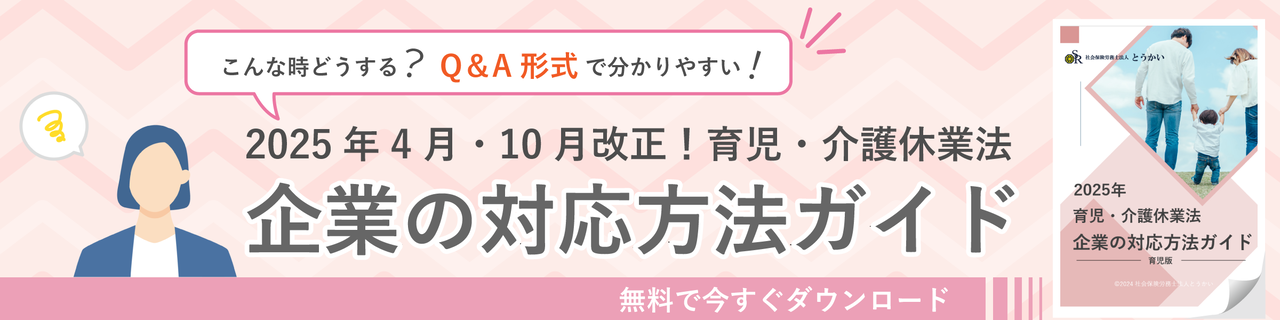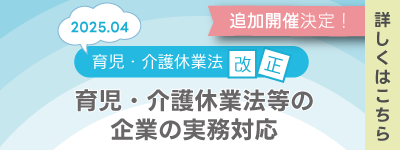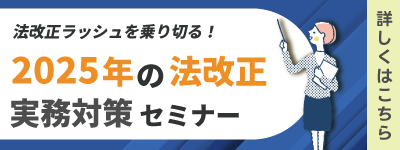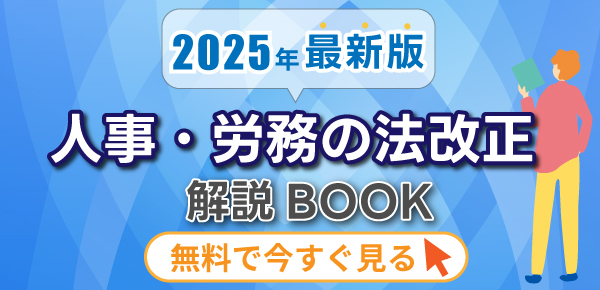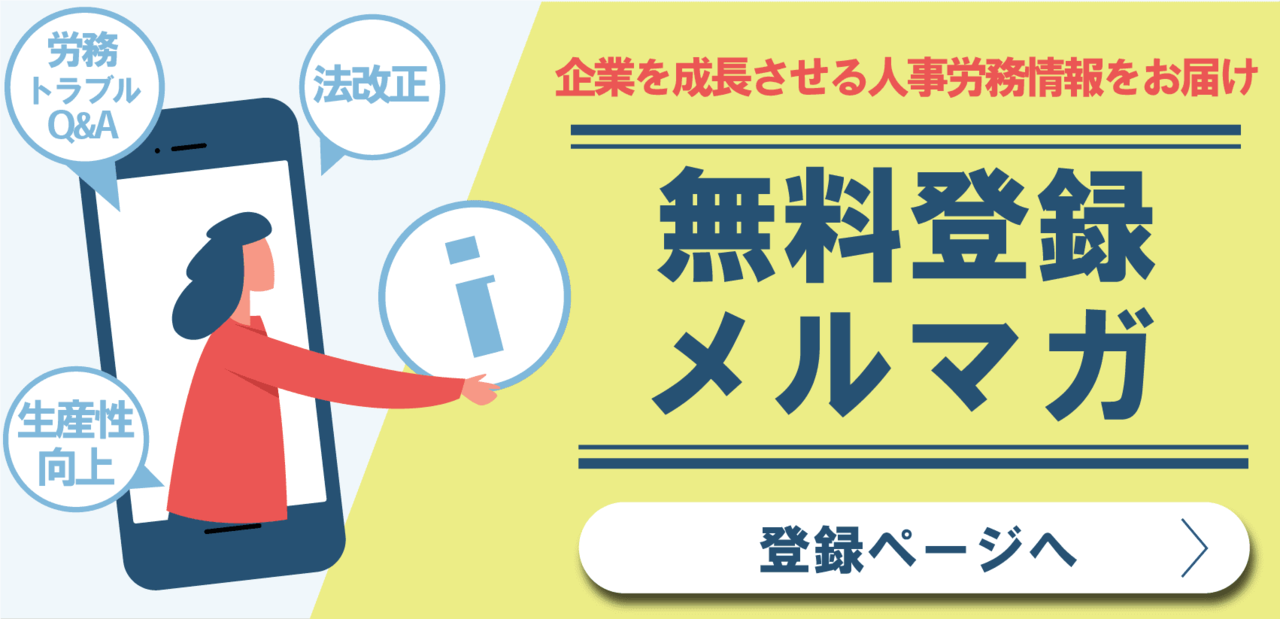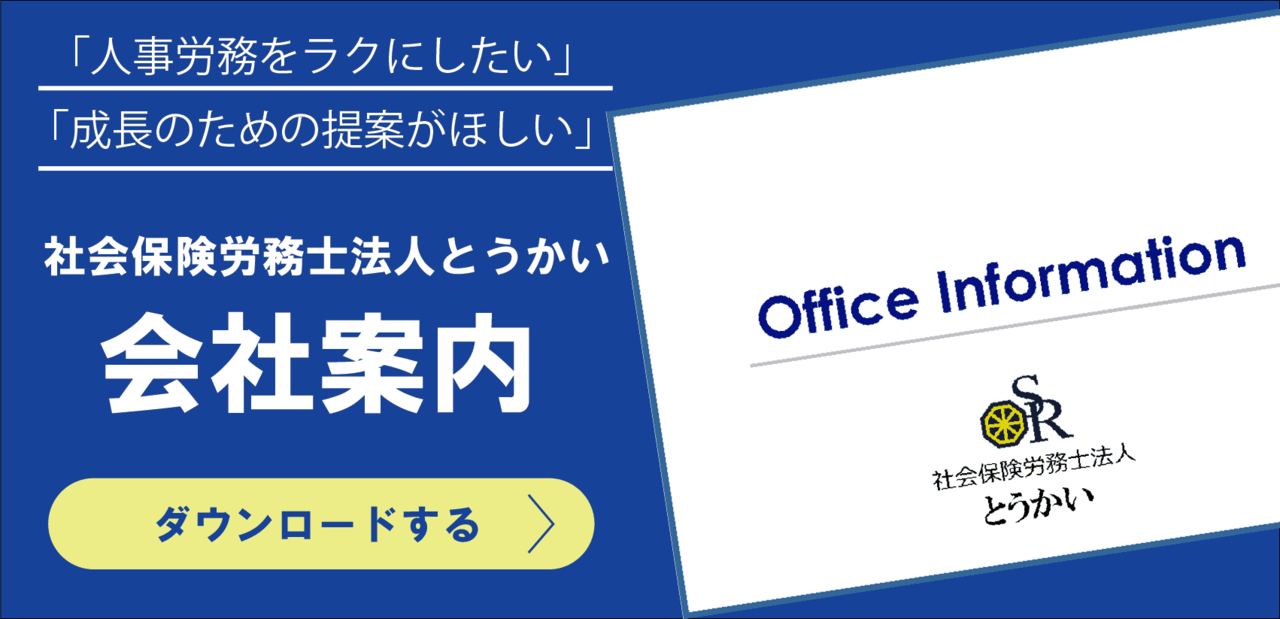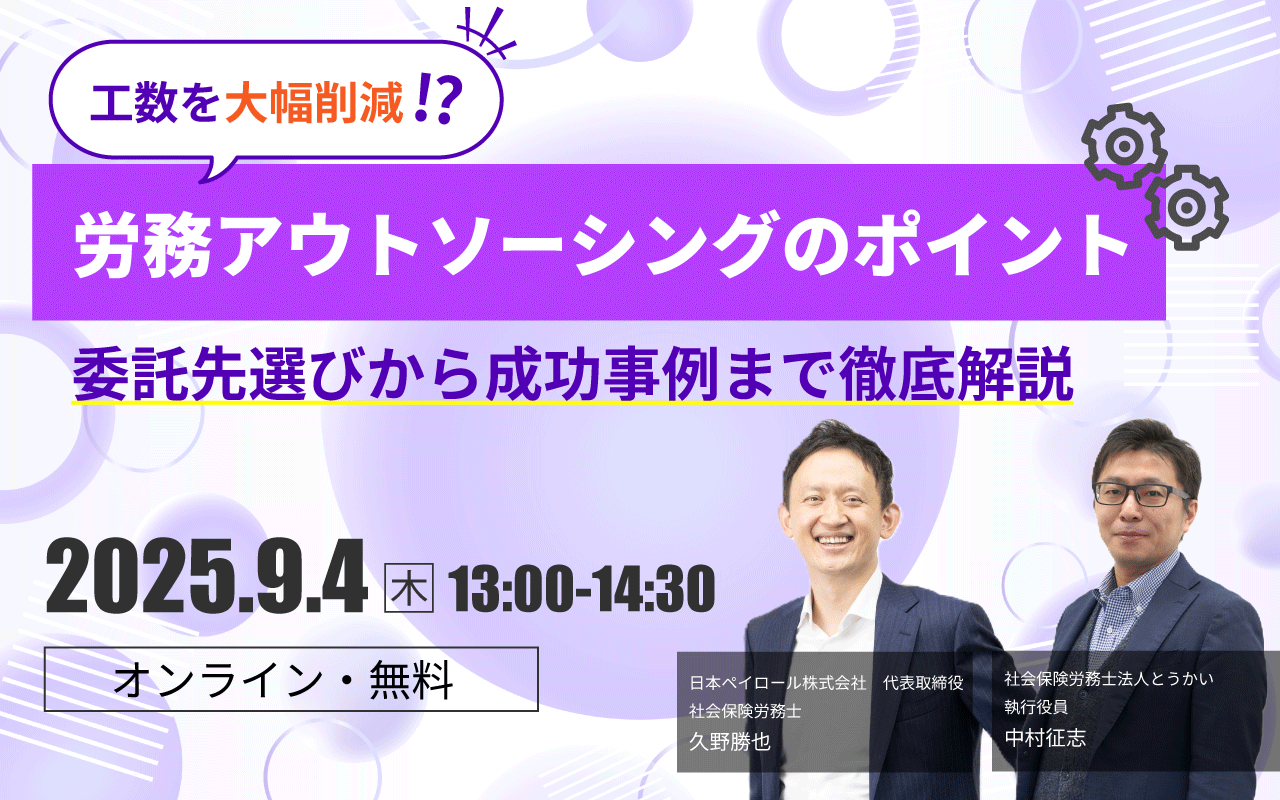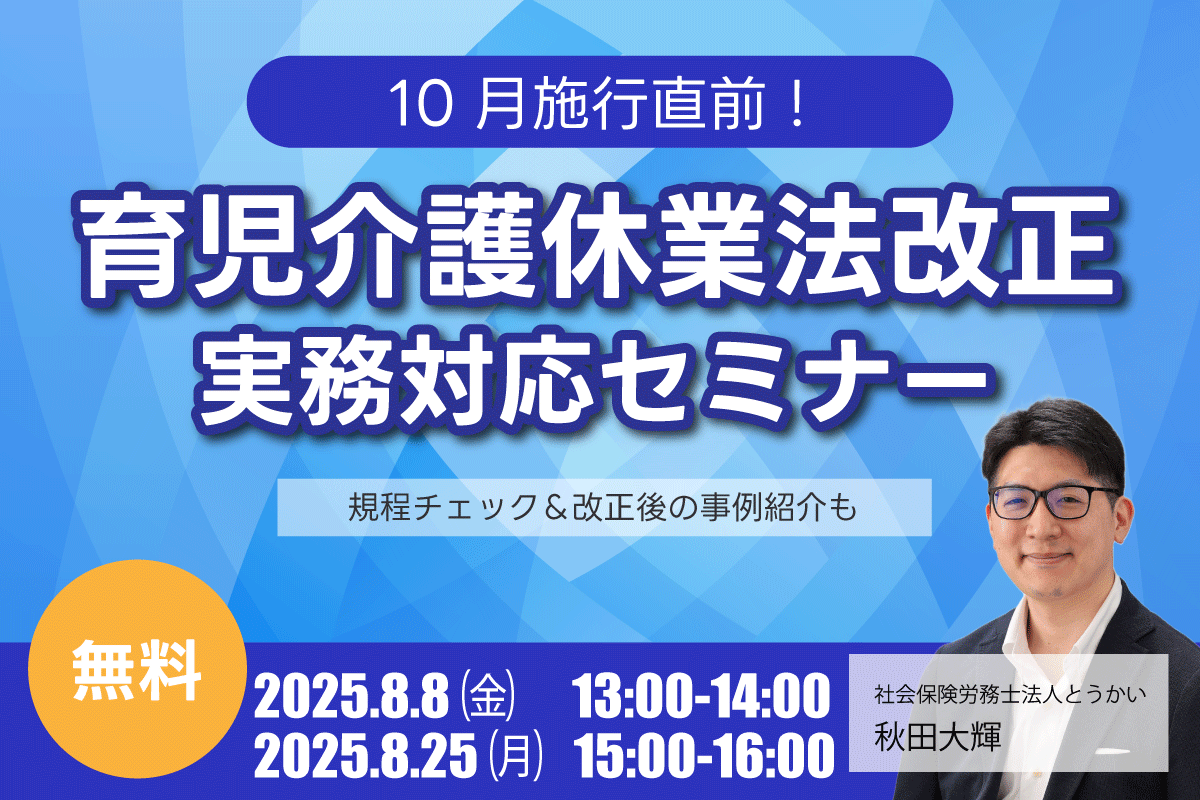【2025年開始】育児時短就業給付とは?背景や条件、支給額について徹底解説

2025年から導入される新たな支援制度である育児時短就業給付。育児をしながら時短勤務で働く従業員に対し、給付金を支給する制度です。この制度は、時短勤務による収入減をサポートすることで共働き家庭の、育児とキャリア形成を両立させるための大きな助けとなります。育児をしながらも職場での成長を目指せる、理想的な働き方を実現する機会が広がっています。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

育児時短就業給付とは何かを詳しく解説します。
育児時短就業給付とは、育児をしながら時短勤務する方々にとって重要なサポート制度です。2歳未満の子どもを育てながら、時短勤務で働く従業員を対象としています。時短勤務中の月の賃金の約10%を給付金として支給し、収入の減少を軽減する目的があります。育児と仕事の両立を目指す環境づくり、社会の実現を目指しているのです。
短時間勤務制度は、従業員が3歳未満の子どもの育児を行うために1日の所定労働時間を1日6時間に短縮する制度です。子育てを行う従業員にとっては、育児と仕事を両立するために、便利な制度ではあるものの、働く時間が短くなることで収入が減少するデメリットもあります。そこで、育児時短就業給付は、短時間勤務による収入減に対して給付金を支給することで、経済的な負担を軽減するのです。従来の短時間勤務制度とは異なり、時短勤務を行う従業員への支援が積極的に行われる点が特徴です。

育児時短就業給付の背景と目的を詳しく解説します。
育児時短就業給付が創設された背景として、日本社会で進行している少子化問題があります。少子化対策が重要な課題とされる中、育児をしながらも安定した収入を得ることができる制度が求められています。育児と仕事を両立し、共働き家庭が育児をしやすい社会を目指すために、育児時短就業給付が導入されることとなります。
育児時短就業給付は、2023年に策定された「こども未来戦略方針」の一環です。子育てしやすい社会の形成が重要視されており、育児に対する支援が強調されています。育児をしながら働くことが自然な形で行えるようにするための施策が、国策として進められています。この方針は日本全体での育児や教育に向けた取り組みの一環として、さまざまな制度改革のきっかけともなるでしょう。育児時短就業給付は、共働き家庭や子育て世帯に寄り添う形で設計されています。さらには、家庭内での役割分担の意識を改善し、育児と仕事の調和を図ることが目指されています。

小栗の経営視点のアドバイス
労働人口の減少により、国としても仕事と育児への施策は、かなり力を入れています。今後も、育児をしながらでも、離職せず仕事を続けていける社会へシフトしていくと思われます。企業においては、そうした人材にも対応できる環境を整えていかければ、よりよい人材の確保は難しい時代となってくるでしょう。
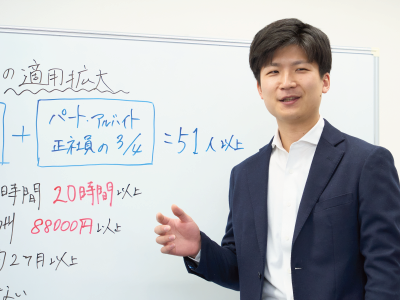
開始時期と支給内容を見ていきましょう。
2025年4月から育児時短就業給付が実施される予定です。日本政府が掲げる少子化対策の一環として、育児をしながら柔軟に働くことを支援するための制度として位置付けられています。対象となる従業員が育児をしながら時短勤務を選択した場合に、収入減を育児時短就業給付によって経済的な支援を行おうというものです。従業員が受け取る給付金は、時短勤務中に得た賃金の一部として支給され、時短勤務を選択した場合であっても、従来の賃金水準を維持することが目的とされています。
育児時短就業給付を受けるためには、いくつかの条件があります。まず、対象となるのは2歳未満の子どもを養育している時短勤務の従業員です。また、時短勤務を開始する日前の2年間において、みなし被保険者期間が12か月以上あることも必要です。性別による制限はないため、男性も女性も等しく支給対象となります。育児を行う際に、柔軟な働き方を選ぶことができる環境が整うことが期待されています。従業員のライフスタイルに合わせた多様な働き方を可能にするため、支給条件は一層柔軟に設計されています。
育児時短就業給付の支給額は、時短勤務中に得た各月の賃金の10%ですが、給付金と賃金の合計が時短勤務前の賃金を超えないように調整がされます。

育児時短就業給付のメリットを見ていきましょう。
育児時短就業給付は、育児中の従業員にとって、仕事と子育てを両立するための働き方においてメリットがあるものです。時短勤務による収入減への支援は、時短勤務制度を取り入れながら働くことの選択肢も広がります。従業員は育児を優先しながらもキャリアを中断せず、ライフスタイルをより柔軟に調整しやすくなります。経済的な支援により、育児における収入面でのストレスが軽減され、心身ともに安定した状態で仕事に取り組むことができます。
育児時短就業給付は、時短勤務制度の利用促進にもつながるでしょう。多くの従業員は、時短勤務を利用したいものの、収入が減ることを気にして短時間勤務を選ばないケースも多くみられました。しかし、給付金により収入の減少を補填する形になれば、時短勤務を選ぶ従業員も増えていくはずです。職場環境における柔軟性を高め、自らのキャリアを築くことと育児を両立するための大きな助けになると期待されています。時短勤務などの利用も進めば、職場全体での育児に対する理解が深まり、より良い労働環境の構築が促進されることが望まれます。
これまで育児を行う人の中には、育児と仕事の両立が難しく、離職してしまう人も少なくありませんでした。時短勤務制度の活用や、収入減を補う制度があれば、育児とキャリア形成の両立が叶ったかもしれません。2025年4月からスタートする育児時短就業給付制度は、働き続けることを前提にしているものです。育児期間中のサポートがあることで、子育てと仕事の両立が容易になります。時短勤務制度を取り入れながら、仕事を継続していくことで、育児にかかる物理的・精神的な負担が軽減されるため、従業員は仕事に集中しやすくなります。将来的には、職場での経験がキャリアを積むうえでプラスに働くことも期待され、大きなメリットとなります。
共働き家庭にとって、育児時短就業給付は大変重要なサポートです。夫婦共に仕事を持つ場合、双方の仕事と子育てを両立させるためには、柔軟な働き方が必要です。どちらかが我慢したり、育児の負担がかかりすぎることなく、両親が協力して家事や育児を分担しやすい環境が整います。家庭内での役割分担が進み、より育児と仕事との両立への理解も深まっていくでしょう。育児に参加することが奨励されるため、育児の負担がより均等に配分され、親子関係の向上にもつながるでしょう。

鶴見の経営視点のアドバイス
育児を担う従業員は、これまで通りのペースで働きたい人もいれば、家庭とのバランスを考えベースダウンしたい人もいます。それぞれが、さまざまなライフプラン、キャリアプランを考えているはずです。会社としては、一人ひとりヒアリングなどを行いながら、希望も考慮しつつ、会社としてどのような対策ができるのか、丁寧な対応が求められるでしょう。

懸念点と課題もしっかり理解していきましょう。
育児時短就業給付には多くのメリットが期待される一方で、いくつかの懸念点や課題も指摘されています。制度の利用の際、従業員間の公平性の問題は、今後改善が求められる重要な課題です。また、制度の導入に伴って発生する事務的な負担も無視できません。これらの課題に対して、具体的な対策が必要とされています。
「マミートラック」とは、女性が育児を理由に本人が望まないにも関わらず、担当業務が変更されたり、部署を異動されるなど、キャリアアップの道から外れることを指します。育児時短就業給付が導入されることで、育児をする親が自由に働ける環境が整う一方で、育児を理由に出世から遠ざけられてしまうのではといったリスクもゼロではありません。育児のために時間を短縮することが、職場での評価にマイナスの影響を与える可能性があります。このような状況が広がると、育児をする従業員のキャリア形成に悪影響を及ぼしかねません。
このような事態を避けるためには、企業文化、風土の改善、育児と仕事の両立ができる環境の醸成が不可欠です。育児をしながらでもキャリアを形成できるような支援体制を整えることが求められます。育児を考慮した評価基準の見直しや、男女ともに育児参加を促す取り組みが必要です。
育児時短就業給付が普及する中で、フルタイム勤務者との公平性、バランスも問題視されます。時短勤務を選んだ場合、給付金を受け取ることで経済的なサポートが得られますが、フルタイムで働き続ける従業員との間に不公平感が生まれる可能性があります。不公平感や格差が職場の士気に影響を及ぼすこともあります。従業員が異なる状況で働いている場合でも、努力や成果が平等に評価されるべきです。育児に対する理解を促進し、職場全体での共感が得られれば、円滑な業務遂行が可能となります。
育児時短就業給付の導入に伴い、新たな事務処理や管理が必要となるため、担当者の事務負担が増加する心配もあります。給付金の申請や管理は職場において新たな業務となるため、それに伴う人員やリソースの確保も重要な課題となります。これが結果として、本来の業務に支障をきたす危険性があります。また、従業員が給付金申請に関する情報を正確に理解し、適切に手続きを行うためのサポート体制も必要です。2025年4月からスタートに合わせ、準備をしておく必要があるでしょう。事務負担を軽減するために、効果的なシステムの導入や、状況に応じて社会保険労務士などの専門家に依頼するなど、対策を講じることで、負担を軽減し、全体の業務効率を向上させることが可能となります。

柔軟な働き方の選択肢を広げられないかと期待されています。
育児時短就業給付が導入されることで、従業員に対する柔軟な働き方の選択肢が大きく広がることが期待されています。育児をする親にとって、仕事と家庭の両立がしやすくなるため、より充実した生活を送ることが可能となります。育児と仕事の両立がしくみとして整っていけば、親自身の今後のキャリア形成にも大きなメリットがあるでしょう。家庭内でのコミュニケーションが向上し、子どもの成長にも好影響を与えられるでしょう。少子化、人材不足を課題としている日本社会において非常に重要なことです。
子どもが3歳を超えると、成長にともなって育児にかかる時間や労力の掛け方が、それまでとは異なってくるでしょう。ただ、この過程においても、柔軟な働き方が引き続き求められることは変わりありません。育児時短勤務制度を活用しながら、働き方を見直すことで、育児と仕事をより効率的に進められるよう、会社としての環境整備が求められます。3歳以降は幼稚園や保育園に通う子どもも増えるため、親の働き方によっては業務に再びフルシフトで対応するケースもあるかもしれません。育児時短就業給付によって充実した育児期間を経験した親が、今度は職場でのさらなる成長を目指すことが可能になります。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
柔軟な働き方が広がることは、会社にとっても従業員にとっても、ゆくゆくは大きな成果を生むことになるでしょう。制度のスタート当初は、社内での環境整備、体制作り、制度を利用していない人との公平感の確保など、テーマは盛りだくさんです。ただし、育児をする人も、しない人もさまざまな人材を受け入れられる企業は、新たな価値を創造できるかもしれません。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」