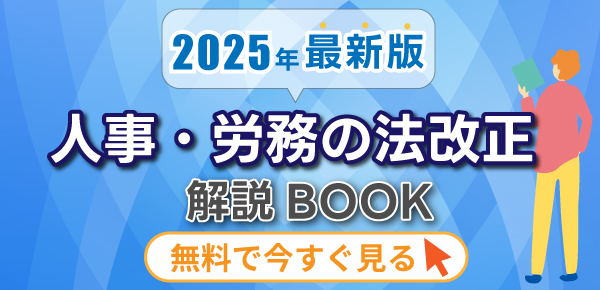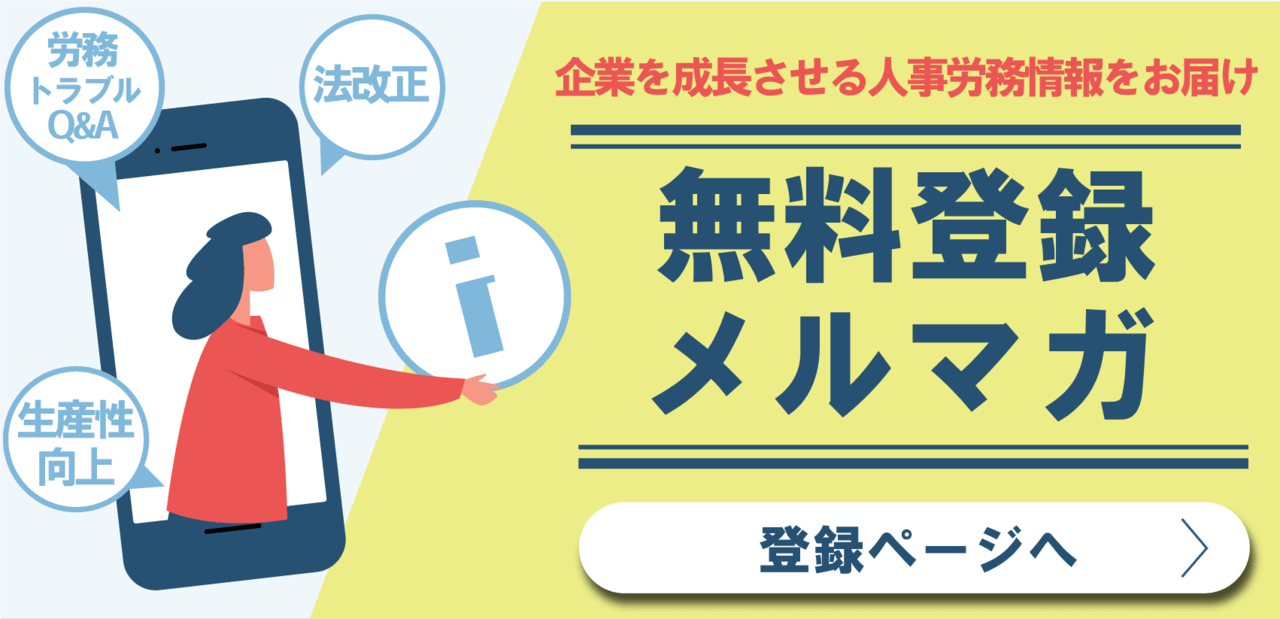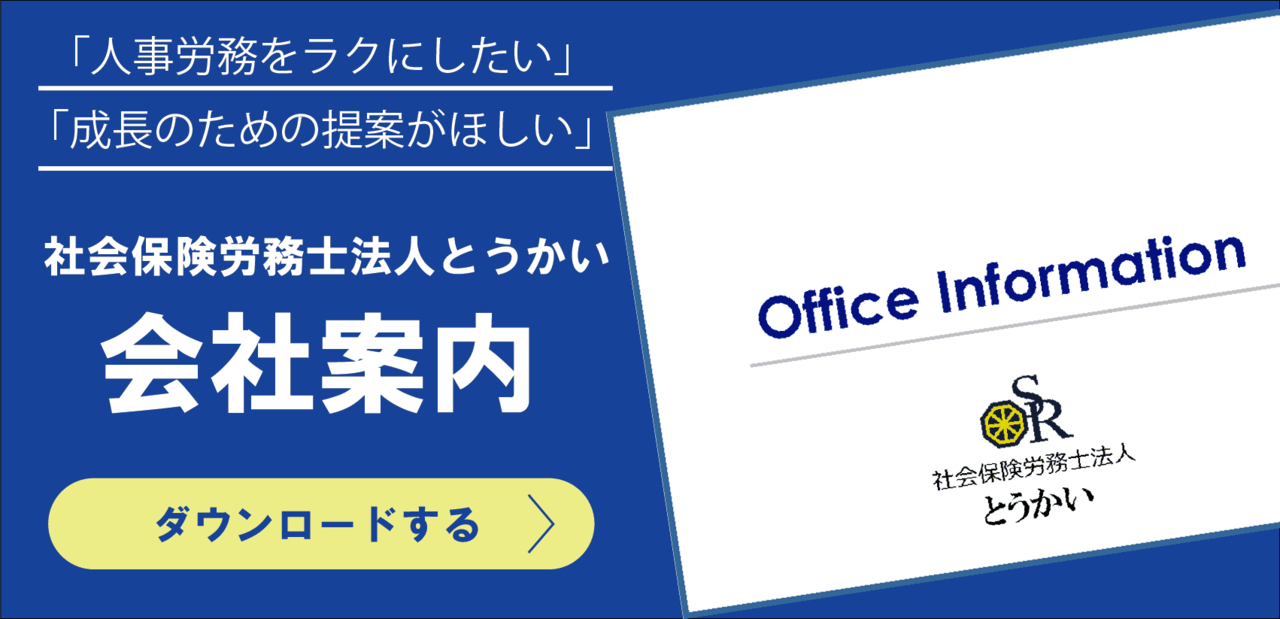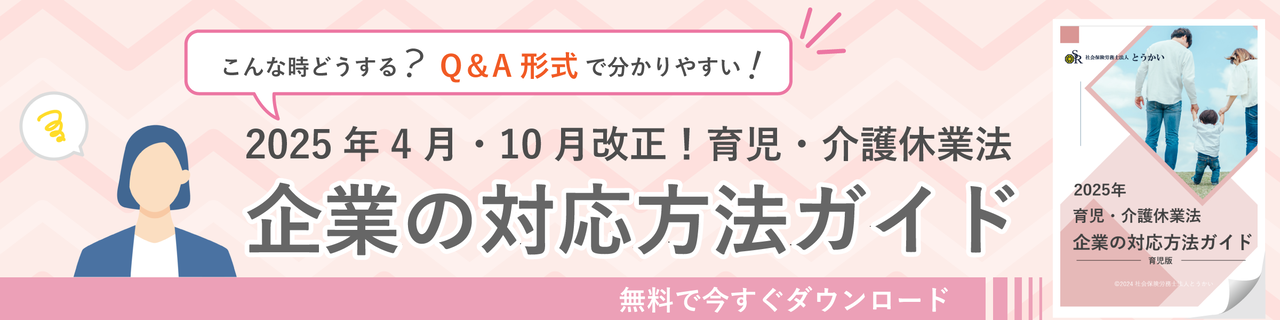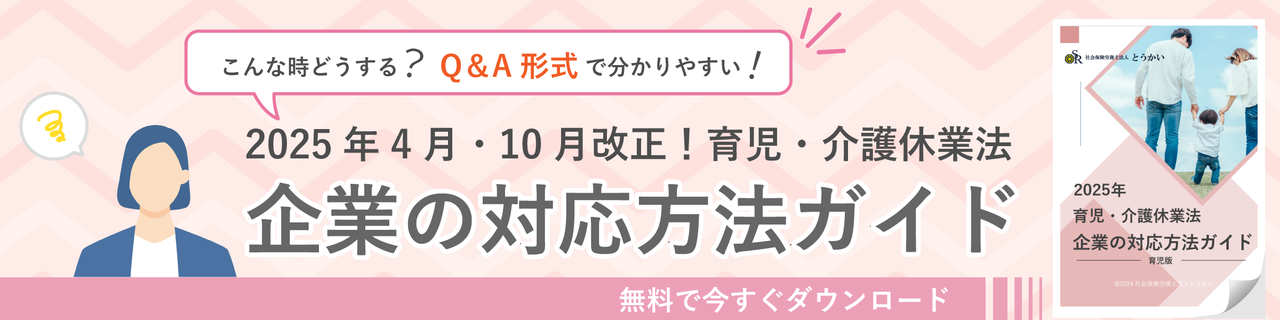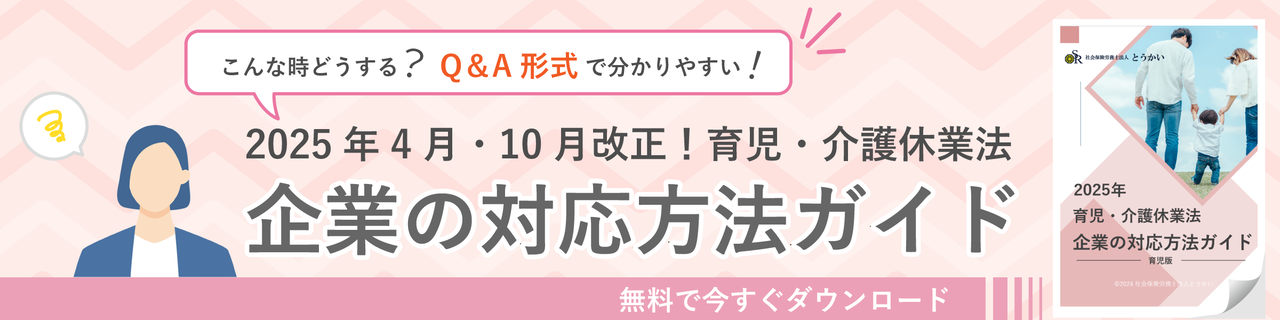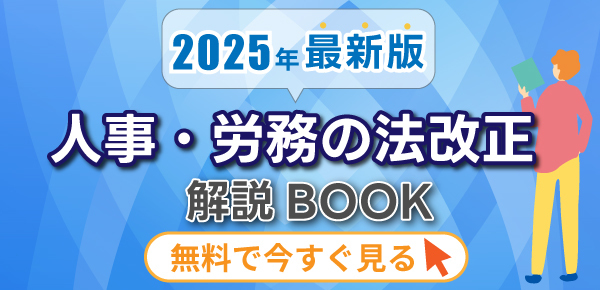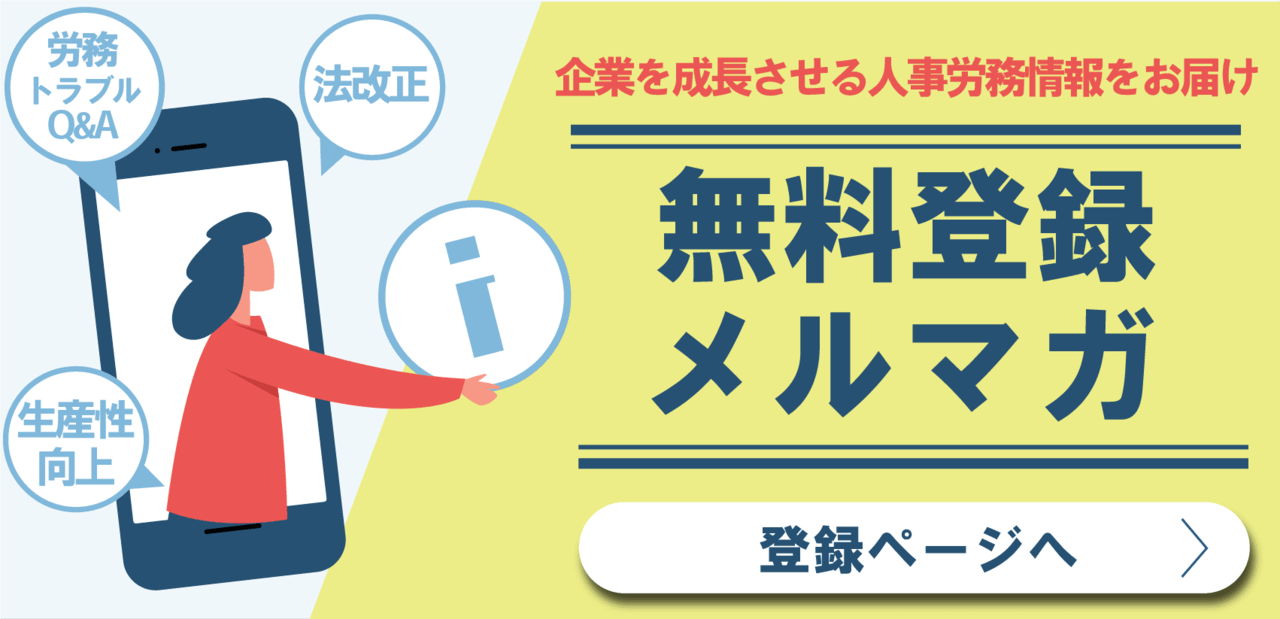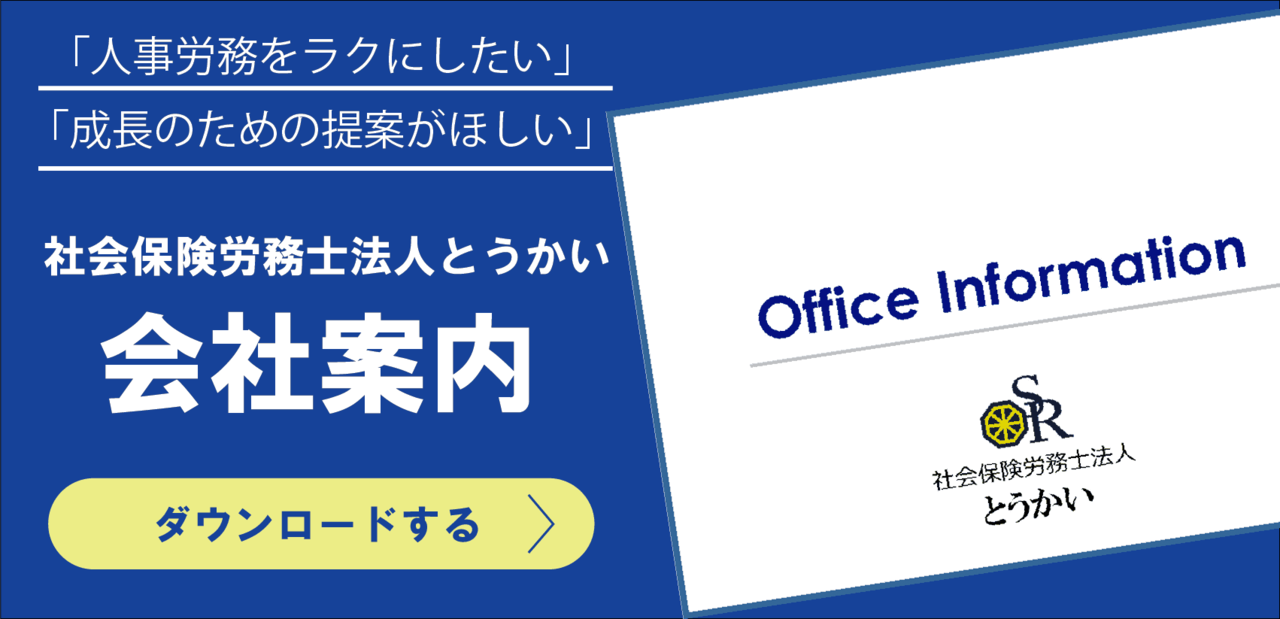育児休業中は社会保険料免除になる?
知らないと損する社会保険の免除要件や手続きの方法

育児休業中は社会保険料の支払いが免除となります。育児休業を取得した月から、終了日の翌月までの期間が免除対象となります。社会保険の免除制度を利用することで、経済的な負担を軽減しながら育児に専念できるでしょう。免除を受けるためには、会社が申し出・届出をすることが必要です。社会保険料の取り扱いを正しく把握し、スムーズに復職できるようにしましょう。従業員が安心して育児に取り組めるよう、企業のサポートが期待されます。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

育休中の社会保険料免除とは?詳しく解説します。
育児休業期間中は、給与から控除される社会保険料が免除されます。通常、社会保険は毎月の給与から健康保険や厚生年金保険などの保険料が控除されます。この社会保険料は、従業員と企業の双方が折半し、保険料を納付することになっています。この従業員と企業の双方が負担する社会保険料が免除される仕組みです。この制度を利用することで、育休中の経済的な負担が軽減されます。
社会保険料が免除されるための条件は、雇用保険の被保険者である従業員が、育児休業を取得する場合に該当します。
育児休業中の給与については、無給として企業が多いでしょう。無給ということで収入がない中で社会保険料を負担をするのは、経済的な負担も大きいので、社会保険料の免除は非常に大きな措置です。
社会保険料の免除期間は、育児休業を取得開始日が属する月から、育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月までが免除の対象期間とされます。
例えば、育児休業を4月15日からスタートした場合、4月分の社会保険料から免除が適用されます。ただし、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までが免除の対象となるため、終了日の扱いには注意が必要です。育児休業が3月30日に終了した場合には、3月31日が翌日となり、その前月までが免除対象となりますので、2月分の社会保険料までが免除となります。一方、3月31日に育休が終了した場合には、翌日4月1日の前月、つまり3月分までが免税対象となります。
また、育休開始日の属する月内に14日以上の育休を取得した場合も、その月の社会保険料が免除されます。
育休中の社会保険料免除については、取得開始・終了日の条件に従って、しっかりと確認することが大切です。

小栗の経営視点のアドバイス
育児休業制度は、過去から見直しが続き、2025年にも育児休業給付金の給付率が一上がるなど、改正が予定されています。これは、今後の日本社会において、子育て支援に力を入れていくアピールでもあるでしょう。働き方の変化と併せて、子育て世代の従業員に、仕事を辞めず活躍してもらうには、法律だけではなく、企業がどのようなサポートをしていくかを考えていかなくてはなりません。

産休・育休期間中の免除に関する詳細を見ていきましょう。
育児休業期間中の社会保険料の免除には、理解しておきたいさまざまなルールが存在しています。特に、産休と育休の切り替えのタイミングや、育休中の状況に応じた免除の条件を理解しておくことが大切です。これにより、経済的な負担を軽減し、安心して育児に専念できる環境を整えることができます。育児休業を取得する際は、事前に詳しい情報を調べ、どのようなケースに該当するのかを確認することが求められます。
育休中の社会保険料の免除取扱いと併せて、産休中の社会保険料の取扱いも確認しておきましょう。産前産後休業(産休)とは、産前42日(多胎妊娠98日)と産後56日のうち、妊娠・出産を理由に仕事を休業していた期間を言います。産休中の社会保険料の免除期間は、産休の開始月から、産休終了予定日の翌日の属する月の前月となります。産休の終了から日を空けずに育休を開始する場合には、引き続き社会保険料が免除されることになりますが、育休開始日によっては、社会保険料の免除の取扱いがされないケースも発生しますので注意が必要です。育休への切り替えの際に重要なのは、育児休業の開始日が正確に設定されていることです。産休が終了した日から育児休業が始まる場合、その日の属する月に育児休業を取得しているとみなされれば、免除の対象となります。このような点を正確に把握し、手続きを進める必要があります。
育児休業中に賞与が支給される場合、社会保険料の扱いにも注意しておきましょう。通常、賞与についても、社会保険料が控除されることになりますが、育休期間中に賞与が支給される場合には、育休の期間が重要になってきます。賞与が支給された月の末日を含む連続した1か月を超える育休を取得した場合、社会保険料が免除されます。ただし、賞与が支給された月に育児休業の対象期間が連続していない場合は、免除が適用されないことになります。十分に注意が必要です。このように、賞与がある際の社会保険料の扱いには複雑な要因が絡むため、事前に確認しておくことをおすすめします。
育児休業中は社会保険料について従業員、企業の双方が免除になります。基本的に育児休業がスタートすれば、連続して勤務を休業することになりますが、場合によっては、育休中に短期間、例えば1日だけの勤務を行うといったケースがあるかもしれません。ただ、臨時的に出勤した場合でも、その後再び育児休業を継続する意図があれば、原則として免除となります。しかし、あえて勤務が予定されていた場合には、一度復職と見なされ、免除が終了します。

高谷の経営視点のアドバイス
育児休業は、基本的に継続して勤務を休業することで、育児に専念することも目的にしています。ただ、労使の合意があれば、一時的・臨時的に勤務することも認められています。この場合には、臨時に出勤したとしても育児休業からの復職として取り扱うことなく、育児休業として認められますので、育休中の社会保険料も免除となります。

男性の育児休業における免除制度を確認しましょう。
最近では、男性の育児休業取得が社会的に奨励されるようになってきました。育児休業を取得することで、ママだけでなく、パパも育児に積極的に参加できる機会が増えつつあります。産後パパ育休なども導入され、男性の育休取得をサポートしています。男性も無理なく育児に専念するため、経済的な負担を軽減するよう、社会保険料の免除も行われます。家庭での役割分担が見直される中で、パパにとっても重要なサポートとなっています。
育児休業を取得する男性が増える中で、社会保険料の免除制度の利用も注目されています。2022年の法改正で導入された産後パパ育休(出生時育児休業)についても、社会保険料は企業と従業員両方の負担分ともに免除されるため、実質的な経済的負担が大幅に軽減されます。
男性が育休を取得する際のインセンティブともなり、より多くのパパが育児に関与するきっかけになります。社会保険料の免除を考慮に入れることで、育休の取得をしやすくする方策が講じられているのです。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
産後パパ育休は、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として取得できる育児休業です。2回にわけて取得することが可能です。通常の育休同様、社会保険料が免除となりますが、その場合には、
・その月の末日が育休中である
・同一月内で育休を取得し、その日数が14日以上である
といった条件があります。

手続きの流れについて見ていきましょう。
育休中の社会保険料の免除を受けるための手続きには、いくつかのステップがあります。まず初めに、従業員は出産や育児休業の予定が決まったら、早めに会社に申し出ることが重要です。免除の申請は、期限が設けられていますので、早めに準備を進めることが望ましいです。必要な書類が整わない場合、免除が受けられないことも考えられるため、慎重に確認することが必要です。
従業員の申し出に基づいて、会社は所轄の年金事務所に申請書を提出します。主な書類としては、育児休業開始届や育児休業給付金の申請書が含まれ、それに加えて会社からの確認書類も求められることが一般的です。
育児休業中の社会保険料免除の計算も確認していきましょう。
健康保険、厚生年金保険いずれも、
標準報酬月額×保険料率÷2
として計算されます。保険料率については、健康保険は都道府県ごとに定められており、厚生年金保険については、一律18.3%となります。
この計算方法を理解することで、無駄な負担を避けることが可能になります。
育児休業から復帰したあとの社会保険料の取り扱いには注意が必要です。復職した月の社会保険料は、原則として通常通り支払う必要があります。しかし、育休復帰後は、出産前と同様に就業スタイルとは限りません。時短勤務などによって、出産前に給与より少なくなることもあるでしょう。復職後、給与が減っているにも関わらず、従前の社会保険料が控除されてしまうと、手取りが大きく減り家計に影響を及ぼす他め、社会保険料を実態に則して控除できるよう、「育休等終了時改定」を行う必要があります。復職時には、保険料の変更や新たな手続きが必要な場合もあるため、確認を怠らないようにしたいところです。正確な情報を把握することで、安心して職場に戻ることができるでしょう。

鶴見の経営視点のアドバイス
育児休業における申請や手続きは、各種の申し出書類や確認書類、申請書など、煩雑でわかりにくいのが現状です。育児休業における手続きは、常時発生するケースとも限らないので、その都度対応するには、担当者が右往左往してしまうという声も聞かれます。そのような場合に、大きな力となるのが、社労士です。人事労務の専門家である社労士は、労働関係に関する法律、法改正の知識、多くの企業のサポートしているケースが多いので、不明点があれば悩まず相談していただくほうが、かえって業務効率が上がるはずです。

終了日と免除終了後の注意点などを見ていきましょう。
育児休業における社会保険料の免除は、育児休業が終了すると終わります。免除が適用される期間をしっかり理解しておくことが大切です。特に、終了日が月末かどうかによって、免除の対象となる保険料が異なる場合があります。
育児休業の終了日がどのように影響するのかは、復帰後の負担を考えるうえでも重要なポイントです。免除が切れるタイミングを把握し、復帰後の具体的な支出計画を立てることが求められます。
育児休業の免除が終了するタイミングは、終了日の扱いによって決まります。具体的には、育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月まで、免除が継続されます。例えば、育児休業が11月30日に終了した場合、11月分の社会保険料までが免除対象となります。この点を把握することは、経済的には大きな違いを生むことになりますので、該当する月の保険料が免除されているかどうかを確認することが必要です。
育児休業から復職した後は、給与が支給されることになりますので、雇用保険料に関しても注意が必要です。復職時には、通常通りの給与が発生するため、その分の雇用保険料を徴収されることになります。
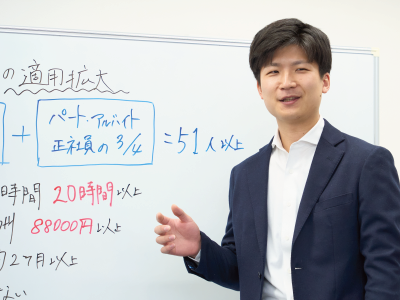
よくある質問に回答していきます。
育児休業については、社会保険料の免除をはじめ、質問が多岐にわたります。様々なケースについて、よくある質問を確認していきましょう。
育児休業における社会保険料の免除は、育児休業を開始した日の属する月から適用されます。たとえば、4月15日に育児休業を取得した場合、4月分の保険料から免除が始まります。
育児休業中においては、給与が支給される収入が減るため、配偶者の扶養に入る検討しているケースもあります。配偶者控除などを利用して、節税できる場合もありますが、扶養が変わると、税法上の扱いにも影響が出るため、手続きや申請を早めに行うことが肝要です。特に免除期間中の所得が低い場合、税金や社会保険の負担が軽減されることがあります。扶養変更に関連した諸手続きに関しては、早めの準備が鼓舞されます。
年金に関する疑問も多く寄せられますが、育児休業中に受けられる社会保険料の免除が直接的に年金に影響を与えることはありません。社会保険料免除がある場合でも、年金加入期間としてカウントされます。免除期間中であっても、保険料を納めたものとして取り扱われますので、将来の年金受給額が減額されるわけではありません。

活用するためのポイントです。
育児休業を取得する際、なるべく多くの制度を活用し、安心して育児に専念するためには、しっかりとした準備が求められます。特に、育児休業中の社会保険料の免除制度について理解を深めることで、経済的な負担を軽減できます。
さらに、育児休業に関する各種手続きや要件についても事前に確認することが重要です。必要な書類や手続きの締め切りを把握することで、スムーズな申請が可能になり、手続きにおけるトラブルを避けられます。
育児休業中は、社会保険料の免除だけでなく、手当や補助金を併用することも可能です。企業によっては、育児を行う従業員への手当を支給していたり、住まいのある地方自治体によっては育児支援金が支給されることもあるでしょう。無理なく育児に専念できる環境が整えるためにも手当や補助金のそれぞれの条件や申請方法を確認し、制度をフル活用することが効果的です。
育児休業の終了後、復職に向けた準備は欠かせません。復帰後は、通常通りの職務に戻るため、どのように業務を進めていくか事前に考えておく必要があります。
また、時短勤務などを行う場合には、復職後の収入や労働条件についてもシミュレーションを行っておくと安心です。特に育休中に経済的な変化があった場合、その影響を事前に把握し、適切な対策や貯蓄計画を立てることが重要です。復職後の不安を軽減し、心身ともに充実した職場復帰を迎えることができます。確実な準備と計画を立てて、育児と仕事の両立をスムーズに進めていくことが肝心です。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」