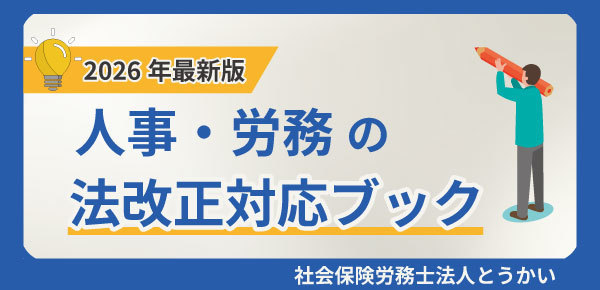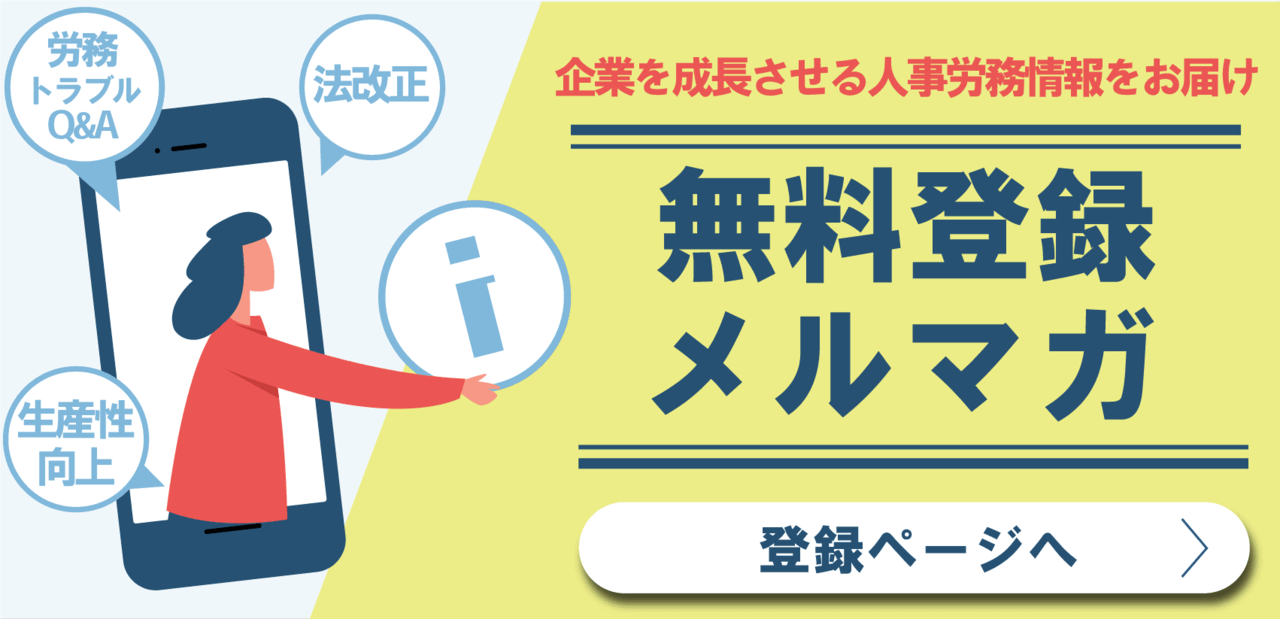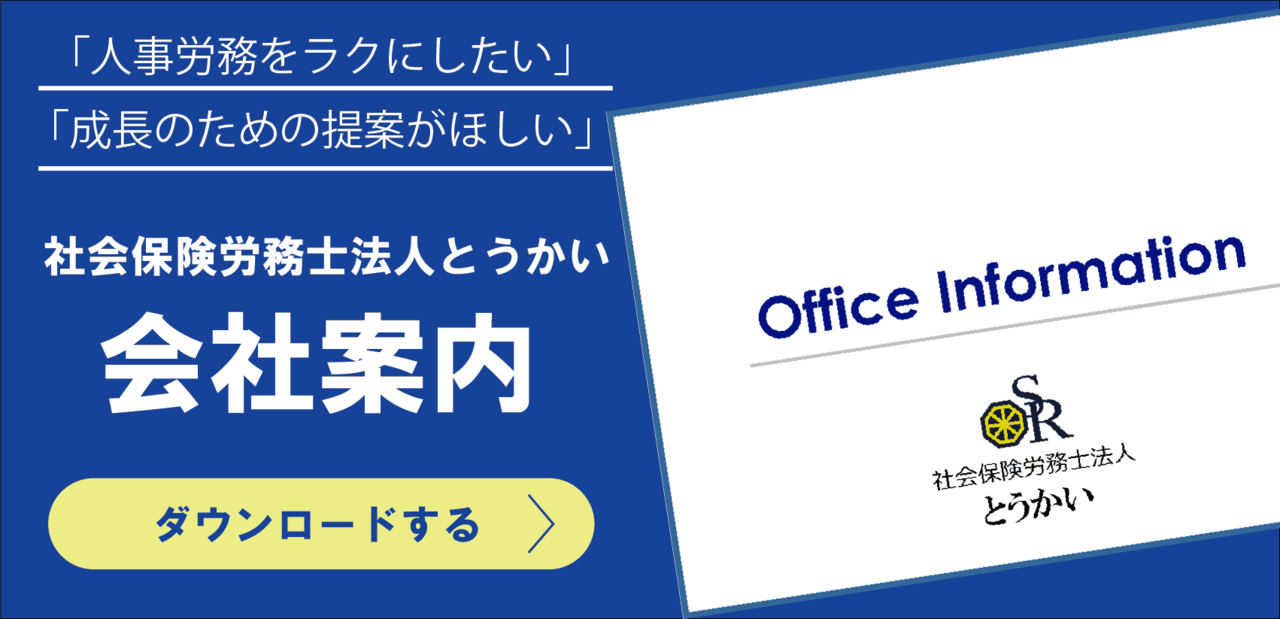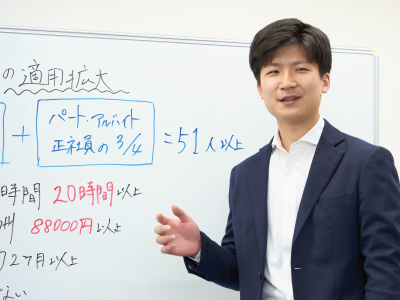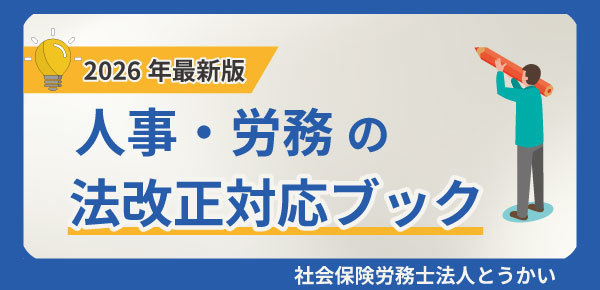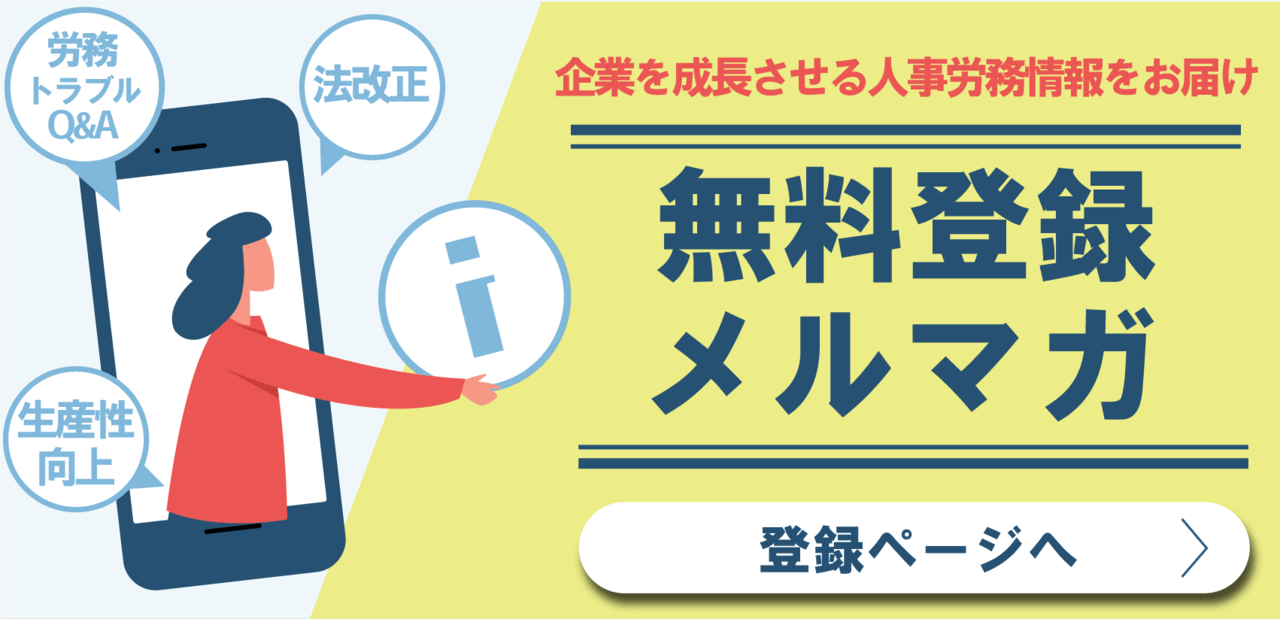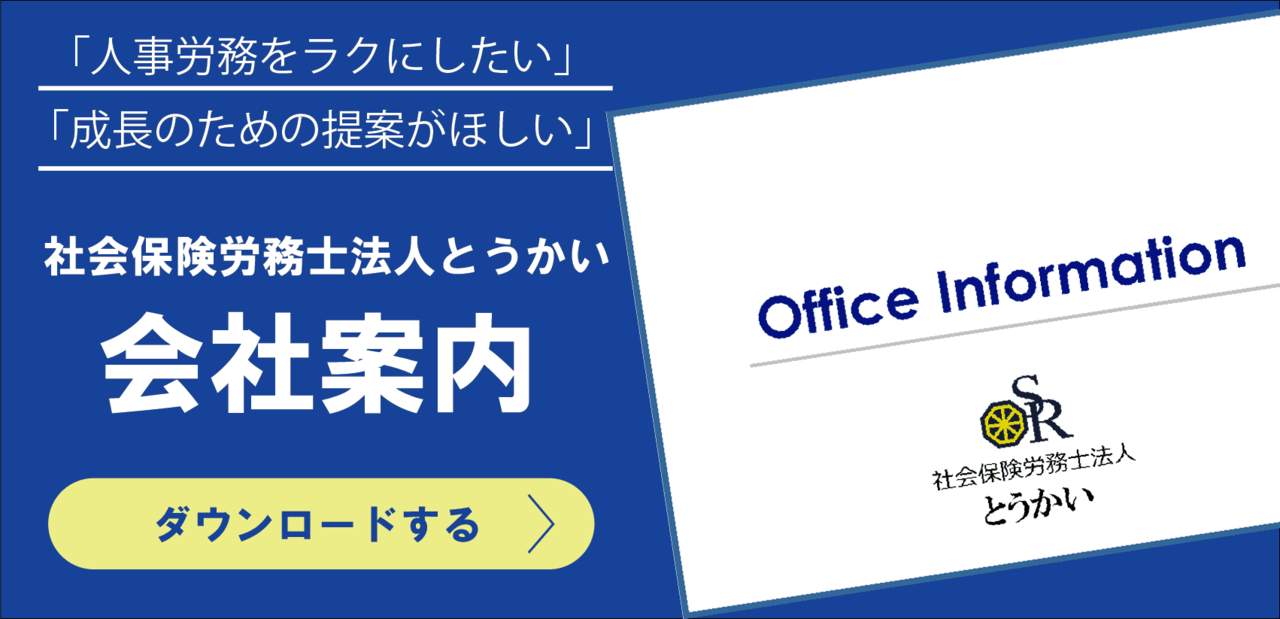企業組合とは?設立のメリットと社会保険手続きの流れを解説

企業組合員は、勤労者としての地位が与えられるため社会保険に加入できます。個人事業主は社会保険に加入できないことを考えると、企業組合員は社会保障が厚いメリットがあります。
企業組合の設立を検討している方は、具体的なメリットや社会保険手続きの流れを把握しておくとよいでしょう。
今回は、企業組合の特徴や設立するメリット、設立手順などを解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

企業組合とは何か?詳しく解説します。
企業組合とは、4人以上が組合員となって資本と労働を持ち寄り、自分たちで働く場を創るための組織です。法人格を有している特徴があります。
組合員になれる人に制限はなく、事業者や勤労者はもちろん、主婦や学生なども加入できます。学歴や年齢、性別を問わず働き方や給料を組合員で決定するため、自由度が高い点も大きな特徴です。
事業を行う分野はさまざまで、専業主婦が合力して保育事業を始めたり、地元特産品の開発や販売を始めたりする実例があります。
近年はソフトウェア開発やネットビジネスをはじめとしたIT関連の企業組合が増えており、時代に適応しながら事業活動を行うことが可能です。

企業組合のメリットについて詳しく見ていきましょう。
企業組合にはさまざまなメリットがあり、独自のノウハウや知識、経験を持つ個人が活躍できる魅力があります。
事業組合が行える事業に制限はなく、あらゆる事業を実施できます。
営利を追求できる組織のため、社会に付加価値を提供して相応の報酬を得ることも可能です。
各組合員が有するアイデアや技能、技術などを活かして事業を行えるため、個人事業主として活動するよりも事業の幅を広げられるでしょう。
事業組合を設立するためには、行政庁からの設立認可書を得たうえで主たる事務所を管轄する法務局に登記の申請を行う必要があります。資本金に関する制限はなく、認可されやすい特徴があります。
また、行政庁の認可を受けているため、対外的な信用力を得られる点も事業組合を設立するメリットです。個人事業を行うケースと比較して、経済的・社会的地位の向上が図りやすいため、事業を展開するうえでも有利でしょう。
企業組合の組合員は、平等な発言権を有しています。
株式会社の場合は大株主が事業に大きな影響を与えますが、企業組合の組合員は出資額に関係なく、議決権・選挙権が平等です。
民主的な組織運営を行えるため、各組合員が自分の考えを主張しやすく、多様な価値観や考え方を受け入れられる環境となっています。
企業組合は加入と脱退が自由で、流動性が高い特徴があります。
つまり、組合に加入したいという意志を有する人は原則として加入でき、組合員として活動できます。将来的に脱退する事情に迫られたとしても、脱退の自由があるため囲い込まれることはありません。
企業組合は、株式会社や合同会社などの法人よりも低コストで設立できます。定款にかかる印紙税や認証手数料などが免除されているため、場合によっては1円もかけずに設立することも可能です。
最低資本金はないため、出資金がいくらでも設立できます。また、個人事業主が各自で行っていた確定申告が不要になり、法人税申告や労働保険・社会保険関係の事務を企業組合でまとめて行えるため、個人の事務的な負担も軽減できます。
企業組合は、中小企業支援センターや中小企業団体中央会などの支援を受けられます。経済的な補助・助成事業や中小企業を支援するための取り組みを受けられるため、事業運営にあたって困ったことがあっても安心です。
企業組合は、全国中小企業団体中央会が行っている「中小企業省力化投資補助金」を利用できる可能性があります。ほかにも、自治体が独自で行っている補助金・助成金を利用できる可能性があり、資金繰りに影響を与えることがあります。
ほかにも、政府系金融機関や都道府県等からの融資を受けられる可能性があるため、個人で事業を行うよりも事業活動の幅が広がるでしょう。
企業組合を、将来的に株式会社に組織変更することも可能です。組織変更する場合でも企業組合を解散する必要はなく、組織の状況に合わせて柔軟に対応できるメリットがあります。
組合が行っている事業を会社形態で行いたい場合や、組合員以外から資金調達を図りつつ事業を拡大したい場合でも、スムーズに組織変更できるでしょう。

企業組合の設立手順を見ていきましょう。
続いて、企業組合を設立する際の手順を解説します。
企業組合を設立するには、4人以上の設立発起人(組合員)が必要です。組合員の中から、最低でも4人を発起人として選定しましょう。
なお、出資者の1/2以上は企業組合の仕事に従事し、従業員の1/3以上は出資者である必要があります。
創立総会に備えるために、設立趣意書や定款の作成を行います。ほかにも、具体的に行う事業計画や収支予算、組合員名簿も作成しなければなりません。
創立総会を開催する2週間以上前までに、創立総会開催案内書の発送も行いましょう。
創立総会で、定款や事業計画、予算などを正式に決定します。また、理事や幹事も創立総会で決定します。
創立総会を開催するためには、総会開催日の当日まで発起人へ設立の同意をした組合員のうち、半数以上の出席が必要です。
創立総会を経て、事業組合の設立認可の申請を行います。
発起人が設立認可申請書類を作成し、添付書類を合わせて所管の行政庁へ提出します。
行政庁より設立の認可を受けたら、発起人から理事へ事務の引き継ぎを行いましょう。具体的には、出資金払込預金口座の開設が挙げられます。
理事へ事務の引き継ぎを行ったら、発起人の役目は終了です。
発起人より事務を引き継いだ理事は、法務局にて設立登記の手続きを行います。出資の払込が完了して2週間以内に、設立登記申請書や代表理事員・組合のゴム印を作成しましょう。
最後に、税務署や県税事務所、市町村へ設立届出を提出すれば一連の設立手続きは完了です。

設立に必要な手続きについて解説します。
健康保険組合に加入するという選択のほかにも、以下の要件を満たす企業組合は健康保険組合を設立できます。
| 企業が単独で設立する場合(単一健保組合) | 事業所で働いている被保険者が常時700人以上 | ||
|---|---|---|---|
| 2以上の事業所または2以上の事業主が共同して設立する場合(総合健保組合) | 合計で被保険者が常時3,000人以上 |
相応の規模が求められますが、要件をクリアしている企業組合は健康保険組合の設立を検討するとよいでしょう。
健保組合を設立する際には、設立しようとしている事業所で働いている被保険者の1/2以上の同意(事業所が2以上の場合、各事業所の2分の1以上の同意)を得る必要があります。
さらに、地方厚生局と相談して設立の作業を行い、厚生労働大臣の認可を受ければ健康保険組合を設立できます。

健康保険組合を設立するメリットをお話します。
健康保険組合を設立することで、組合員が受けられる社会保障給付が充実するメリットが期待できます。
また、健康保険組合の設立には規模の要件が定められているため、設立により組合のステータス向上が期待できるでしょう。対外的な信用度が高まり、事業運営によい影響をもたらしてくれるかもしれません。
加入者の健康の保持・増進に関する、きめ細かいサービスを提供できるようになる点もメリットです。健康保険組合は会社(組合)自体が設立する公法人なので、組織的に協力しやすく、情報伝達もスムーズに行えます。
社会保障給付の充実化を図りつつ、社会保険制度の運営をスムーズに行える点は健康保険組合を設立するメリットといえるでしょう。

企業組合を設立したあとは、組合員を社会保険へ加入させることが可能です。社会保障が手厚くなれば、組合員がより安心して事業活動を行えるメリットが期待できます。
企業組合の設立を検討しているものの、組合員の中に社会保険手続きに詳しい人がいないと、手続きをスムーズに行えません。
手続きが停滞して事業運営に支障が出るようであれば、社会保険制度の専門家である社会保険労務士を頼りましょう。
社会保険労務士法人とうかいでは、規模に関係なく社会保険手続きを代行いたします。煩雑な手続きをアウトソーシングすれば、組合員が生産的な業務に注力できるでしょう。
ITに強い社労士がクラウド導入をサポートするので、業務の効率化も支援いたします。無料相談を承っているので、ぜひお気軽にご相談ください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」