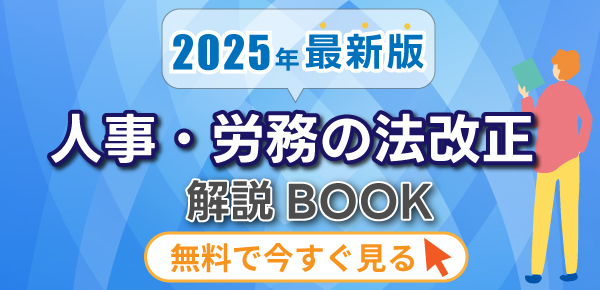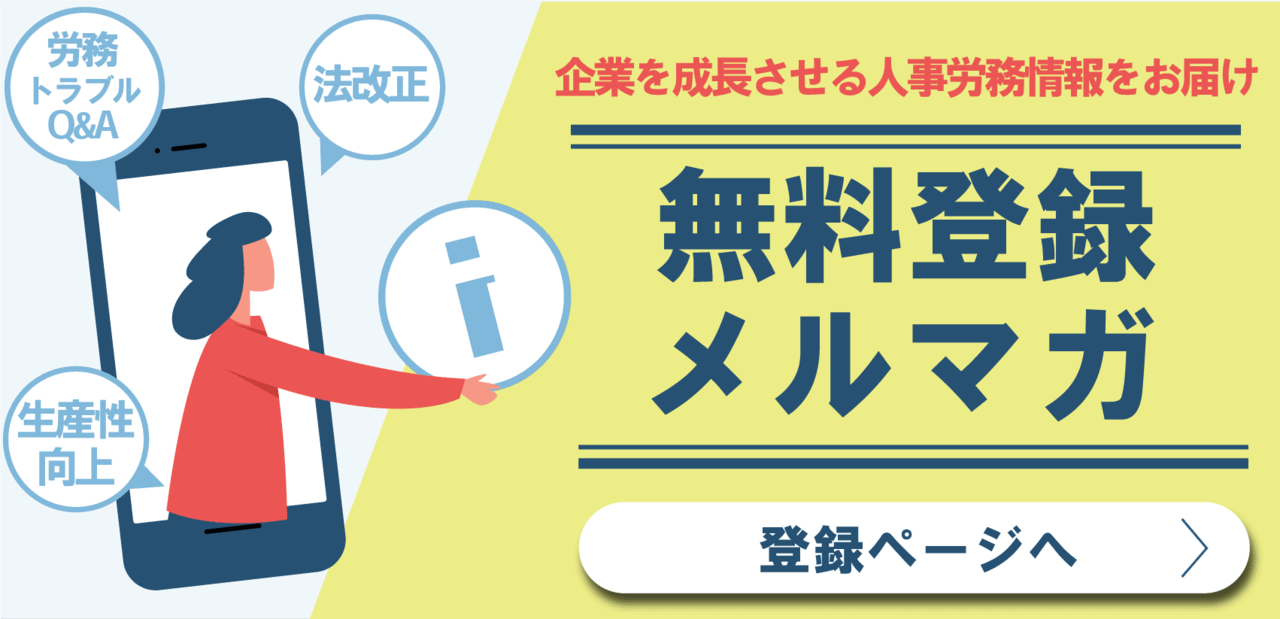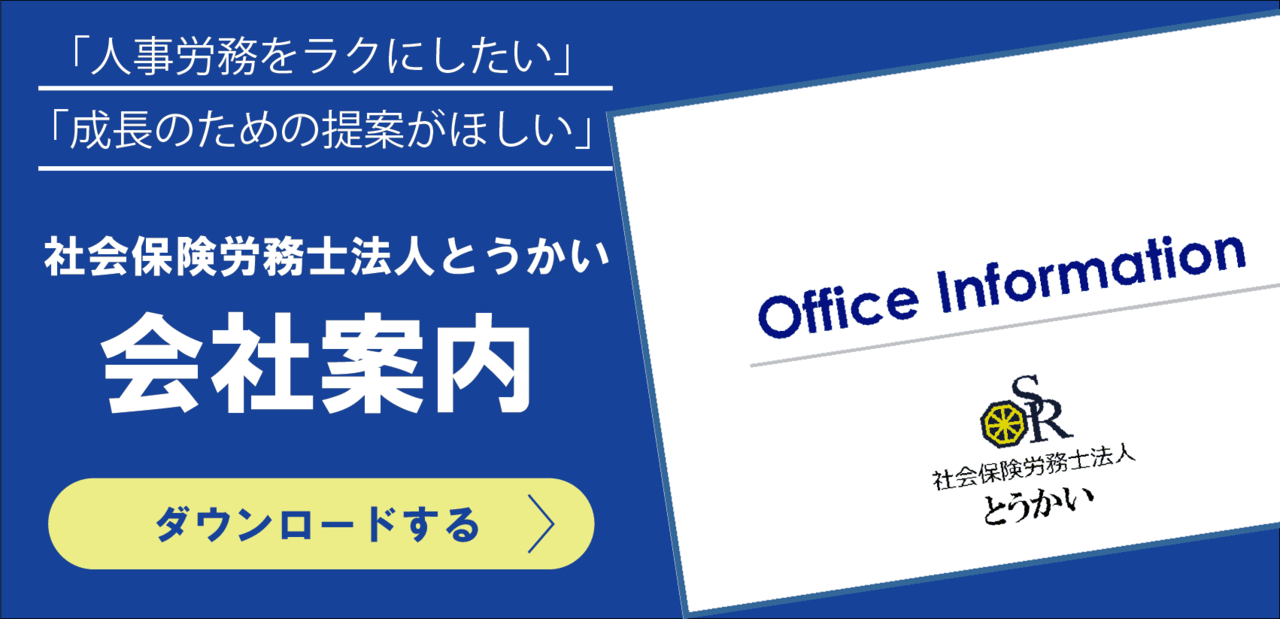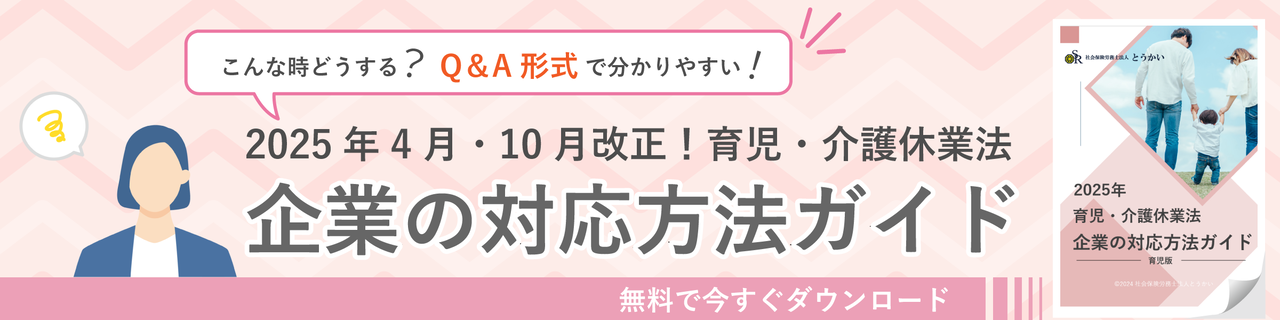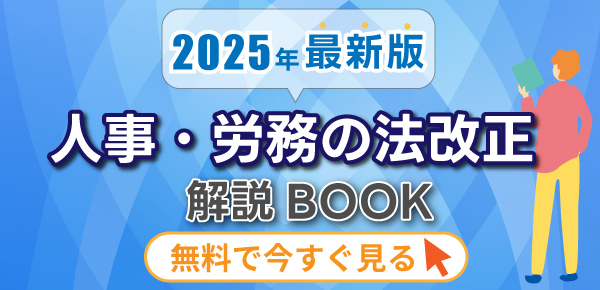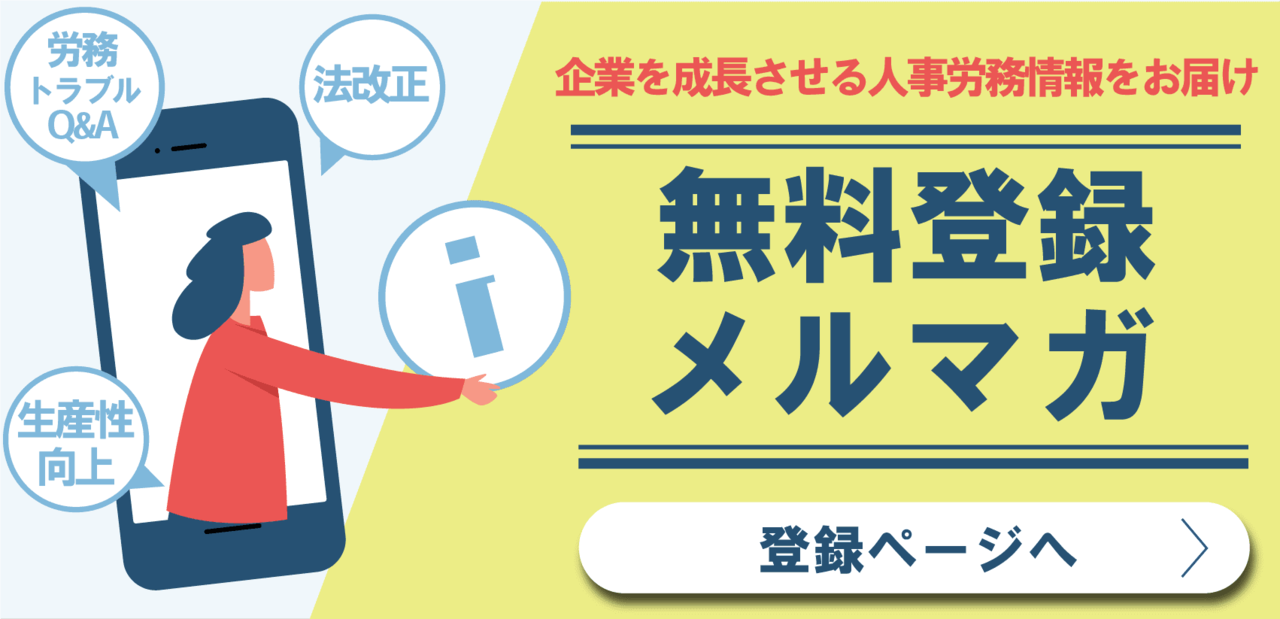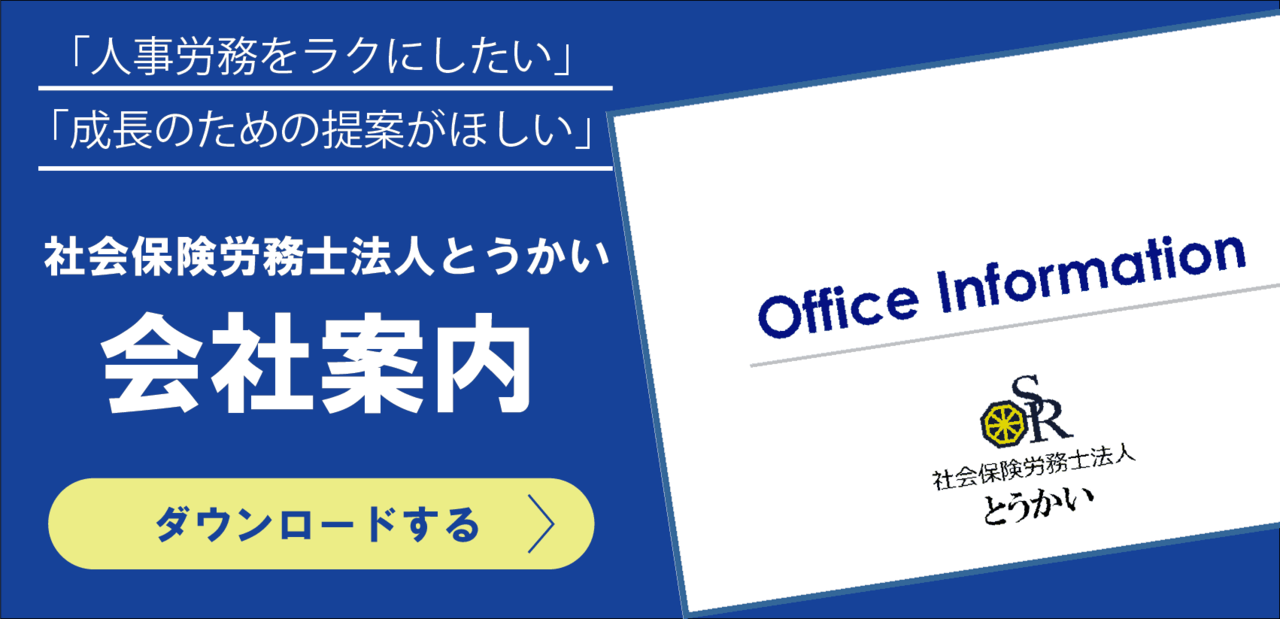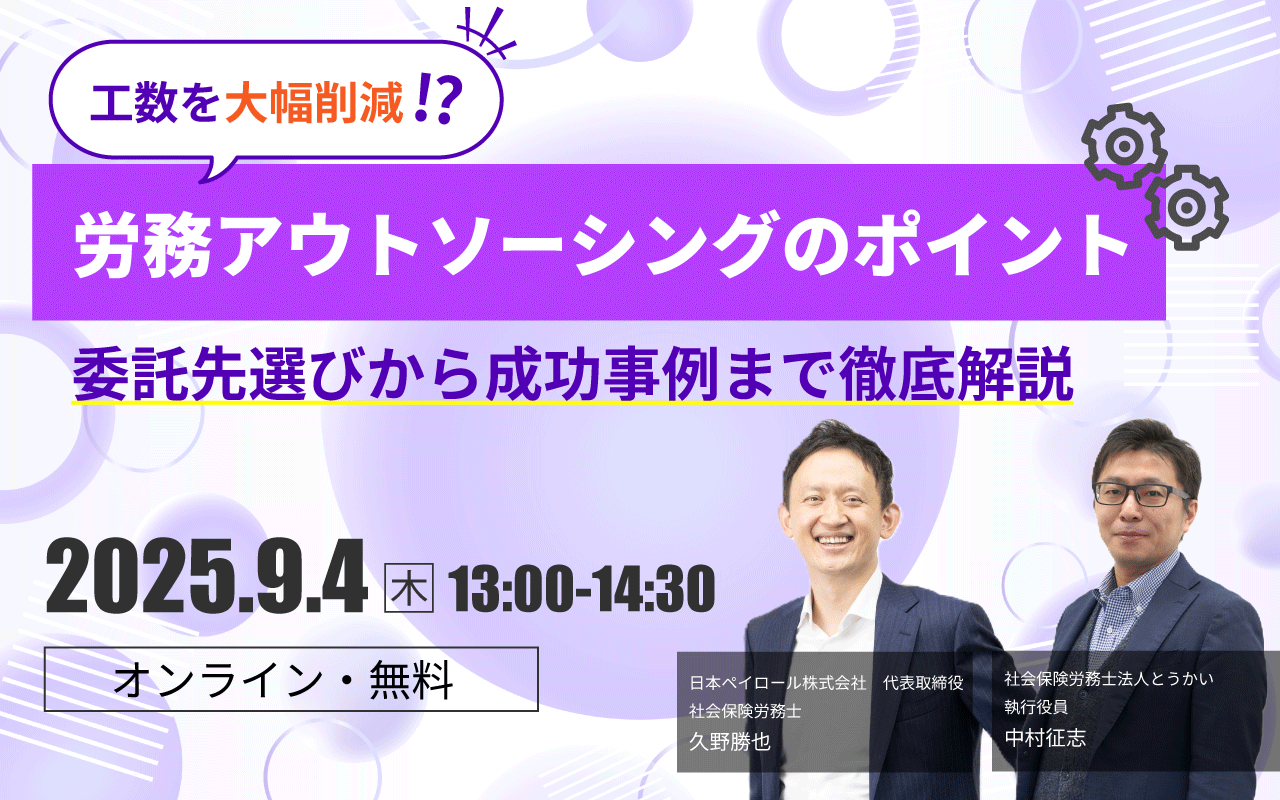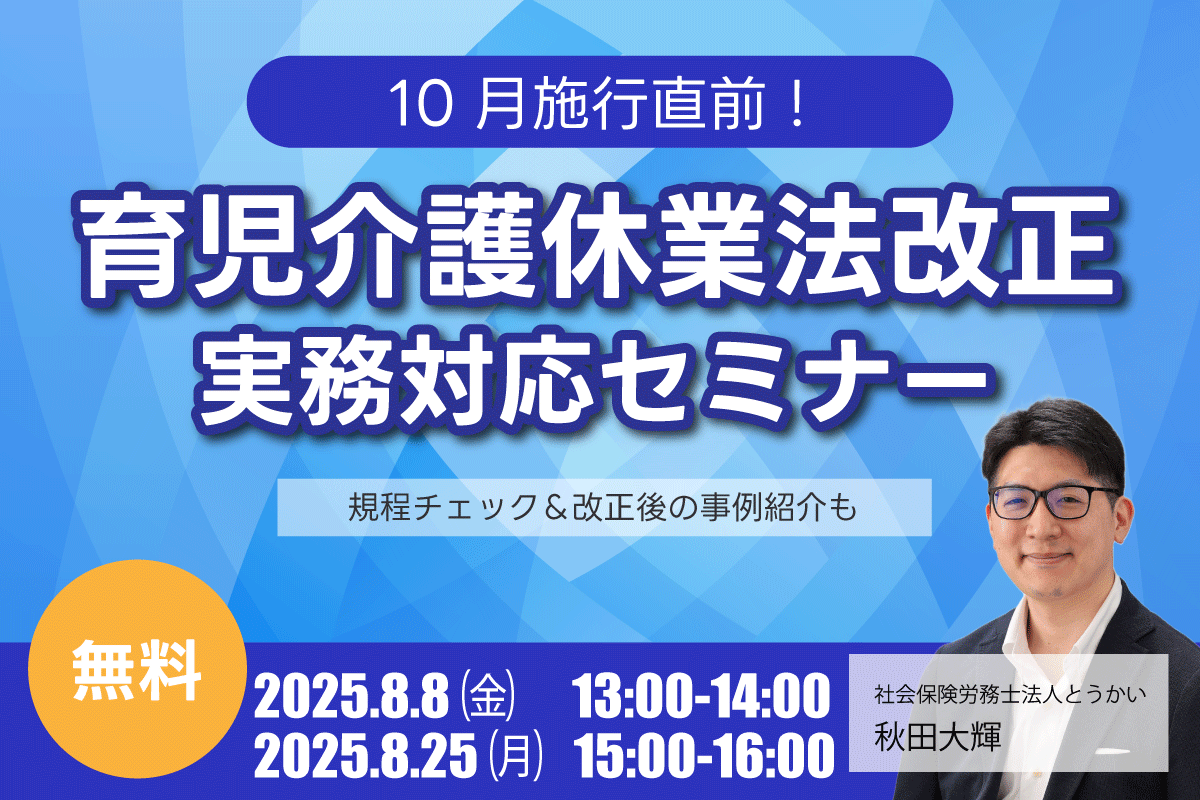「福利厚生」とは?
種類やメリット、企業の導入事例をご紹介

福利厚生とは、企業が従業員のために提供する生活をサポートする制度やサービスです。基本的な給与や賞与といった金銭的報酬とは違い、福利厚生は従業員やその家族の生活の質を向上させ、安全で安心な労働環境をサポートする役割を果たします。福利厚生の充実は企業にとって人事戦略的な意味を持ち、人材の定着や優秀な人材の確保に繋がる重要な要素とされています。近年は、求職者が企業を選ぶ際には、福利厚生の充実度も注目するようになっており、企業はその対策に力を入れるケースが増えています。福利厚生の他社との差別化、企業風土にあった独自性ある制度が求められており、企業競争力の向上に一役を担っています。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

福利厚生の基本知識をわかりやすく解説します。
福利厚生とは、企業が従業員との雇用関係において、給与や賞与といった基本的な労働条件に関わるものとは別に、従業員やその家族のために提供する制度やサービスです。福利厚生は従業員が安心して働ける環境を整えるための取り組みであり、その定義は企業ごとに異なります。社会保険をはじめ、医療や育児、老後の保障など、様々な分野が含まれています。一般的な福利厚生には、健康保険や雇用保険といった法定福利厚生のほか、企業独自に提供される住宅手当や資格取得支援、レクリエーション活動などが挙げられます。
これらの施策を通じて、企業は従業員の働きやすさを高めるだけでなく、従業員の満足度向上や業務効率化を目指すことが重要です。また、福利厚生は企業の内外に対するイメージ形成にも大きく影響し、企業が社会的責任を果たす上でも欠かせない要素となっています。
福利厚生の主な目的は、従業員が安心して安定的に働くための支援を行うことにあります。従業員が仕事に集中できる環境を提供することで、生活の様々な側面をサポートし、従業員満足度の向上を図ることが可能です。福利厚生の充実は、結果として離職率の低下や就業意欲の向上を促し、企業全体の業績向上にもつながります。
さらに、福利厚生の充実は、対外的な企業ブランドの醸成や信頼性を高める点においても大きな効果を発揮します。他社と差別化を図った施策、充実した手厚い制度は、優秀な人材を引き寄せ、企業の競争力を強化することが期待できるでしょう。企業が福利厚生制度を戦略的に導入・改善することは、従業員のモチベーション向上だけでなく、長期的な組織成長をもたらす重要な役割を担うのです。福利厚生制度は企業経営において欠かせない要素と位置づけられるでしょう。
福利厚生には、大きく分けて法定福利厚生と法定外福利厚生の二種類があります。法定福利厚生は、いわゆる社会保険であり、企業が従業員に対して法律で義務付けられている福利厚生を指します。雇用保険、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険が挙げられ、従業員の生活の安定や健康維持を支える重要な制度です。雇用保険は失業中の生活安定をサポートするだけでなく、育児や介護休業の際に、給付金を支給することで休業期間中の収入を支援するなど、ライフステージに応じた支援を行います。健康保険は、病気やケガをした際の医療費負担を補助し、従業員の生活を安定させる役割を果たします。介護保険は、主に高齢者を対象とした介護サービスを支え、厚生年金保険は将来の年金受給により、老後の生活の安定を図ります。労災保険は通勤中の事故、仕事中の事故や病気に備えた保障を行います。社会保険の費用は、企業と従業員の双方が一定の割合で負担します。
これらの法定福利厚生は、従業員にとって欠かせないセーフティネットとして機能し、働きやすい職場環境の構築に大きく貢献しています。そのため、社会保険制度をしっかりと整備することは、企業にとっても従業員からの信頼を高め、充実した福利厚生を構築するための基盤です。保険料の負担が企業と従業員の双方に分配されることで、長期的な働きやすい職場環境づくりにも寄与するでしょう。
一方、法定外福利厚生は、企業の裁量で実施されるものです。企業独自の制度設計も可能で、種類は豊富で多岐にわたります。例えば、住宅手当や育児支援制度、社員旅行などが一般的に知られており、企業ごとの特性や従業員のニーズに応じた柔軟な提供が可能です。他社と差別化を図り、より従業員に響くのは、この法定外福利厚生の充実の如何にかかっているでしょう。従業員満足度向上や優秀な人材の確保につながるため、企業にとっても重要な施策として捉える向きもあります。企業は福利厚生の種類を適切に整備し、独自の価値を提供することで、他社との差別化が期待されます。
法定外福利厚生は、企業によってバリエーションもさまざまです。正社員だけでなくパートタイマーやアルバイト従業員にも適用されることがあります。住宅手当、家賃補助や通勤手当、健康診断の補助、社員食堂の利用や食事補助などといったものがあります。例えば、家賃補助であれば、東京都のような住宅費が高い都市部においては、家賃補助の導入は従業員にとって大きな経済的支援となり、家計の負担を軽減するだけでなく、生活の安定にも寄与します。健康診断の補助では、従業員の健康意識が向上し、病気の早期発見や予防につながります。それにより、健康リスクを減らし、長期的には医療費の削減や生産性向上など、企業にもプラスの影響をもたらします。
さらに、従業員の結婚や出産、親族の死亡といった慶弔関連支援や産前産後休業、育児休業など、従業員のライフステージに応じた制度も豊富です。近年では、社員のストレスマネジメントを目的としたメンタルヘルス支援や、リモートワークを進めるための環境整備に関する制度が注目を集めています。従業員がリフレッシュできる機会として旅行補助制度を含むレジャー関連のサポートも人気があります。従業員のニーズに応じた取り組みにより、企業は従業員の生活の質を向上させると同時に、企業全体の魅力を高めることを目指しています。

鶴見の経営視点のアドバイス
福利厚生制度の利用でよくあるのが、限定された人たちのみしか使えないケースです。福利厚生制度の基本は、誰もが利用できる制度です。もちろん、正社員・非正社員との区分で利用を分けることも可能ではあるのですが、同一労働同一賃金に反しないような運用としなくてはなりません。

福利厚生によって得られるメリットを確認しましょう。
福利厚生の充実は、会社にさまざまなメリットをもたらします。従業員にとって働きやすい環境を整えることで、会社への満足度が向上し、長期的に勤務してもらえる可能性が高まります。福利厚生は従業員が仕事に対する意欲を高め、結果として業務のパフォーマンス向上やチームワークやエンゲージメントの強化に期待が寄せられています。安心して働ける環境があることで、仕事に積極的に取り組むことにつながり、会社全体の業績向上にも貢献されるでしょう。福利厚生は従業員と会社双方にプラスの効果をもたらす、企業の重要な施策です。
福利厚生は、従業員のモチベーション向上に大きく関係します。従業員が感じる待遇やサポートの充実は、仕事に対する意欲や熱意を高めるだけでなく、業務の生産性向上にもつながる大切な要因です。安心して楽しく働ける会社としての魅力を高めることも可能です。健康診断の充実やリフレッシュ休暇、社員旅行などの取り組みは、従業員に心身ともにいい充実感を与えるのではないでしょうか。従業員のモチベーションが高まれば、業務への取り組み姿勢も前向きになり、会社全体の雰囲気やチームワークが改善されるきっかけともなり得ます。
充実した福利厚生のある会社には、非常に良い企業イメージを持つのではないでしょうか。就職活動を行う求職者にとって、働きやすい環境と充実した待遇のある企業は、魅力的に映るでしょう。近年、求職者が就職先を選ぶ選択肢の一つには、福利厚生があります。とくに若手層の人材は、福利厚生の充実を重視する傾向が強まっており、手厚い制度を設けている会社は注目を集めるでしょう。優秀な人材を引き寄せることができれば、結果として採用力の強化につながるわけです。人材獲得競争が激しくなる中で、求職者にとって魅力のある企業と認識されることは、会社の持続的な成長を支える重要な要因です。
福利厚生費は企業の重要な経費の一部です。福利厚生制度を充実させれば、当然ながらこの費用の負担も大きくなるわけです。とはいえ、福利厚生費には、従業員の生活や健康を向上させるための多くの施策が含まれており、企業としての社会的責任を果たすための重要なコストでもあります。福利厚生費を適切な科目として管理し、効果的な施策を導入することは、従業員のモチベーションを高めるだけでなく、企業全体のパフォーマンスの向上にも寄与します。そのため、福利厚生費は単なる経費ではなく、長期的な視点での重要な投資の視点も必要といえるでしょう。
福利厚生に関する費用については、経費として認められていれば節税効果も期待されますので、コスト負担は大きくとも、法人税の節税効果は果たすというわけです。福利厚生費用を経費として計上し利益が減少することで、結果として法人税の負担を軽減することが可能です。税制上の優遇措置をうまく活用することで、企業は効率的にコストを管理することができます。
さらに、従業員のニーズにマッチした福利厚生の効果により、従業員の満足度を高め、人材定着率を向上させることができれば、人材流出を防ぐことが可能となるでしょう。通常、人材が流出すれば、新たに人材を採用し教育するなど、人件費や教育にかかる余分なコストが発生するものです。新たなコスト発生の抑制にも繋がることになります。従業員の定着を支えるための投資が企業の長期的な成長に寄与する重要な要素となります。
多くの企業で導入しているのが従業員の健康に関連する福利厚生制度です。従業員の健康維持・向上のため、健康診断の実施をしていることが多いでしょう。充実した健康診断の実施は、疾病の早期発見や予防に役立ち、安心して働ける環境をサポートします。さらに、メンタルヘルスの支援やフィットネスプログラムの提供も、心身の健康をサポートする上で重要です。従業員が心身ともに健康で働くことができれば、仕事の効率も自然と向上し、結果として生産性の向上も期待できます。健康的な職場環境の構築は、従業員満足度を向上させるだけでなく、企業全体の業績や競争力の向上にもつながります。

高谷の経営視点のアドバイス
福利厚生制度活用の難しさは、全従業員を公平に満足させることにあります。矛盾なく、公平・公正に利用が可能で、全従業員が満足する制度を設計し、運用していくことは非常に労力のいることです。また、時代や社会の変化によっても、制度の見直しや刷新が必要になってくる面もあるでしょう。自社にマッチする福利厚生制度の導入にお悩みの担当者は、ぜひご相談ください。

福利厚生の企業導入事例と運用形態を確認しましょう。
福利厚生は企業の文化や方針によって多種多様な形で実施されています。最近は、従業員のニーズやライフスタイルの変化に対応した制度の導入に注目が集まっています。いくつかの導入事例を通じて、自社の状況に合わせた福利厚生の検討、運用を学ぶ際の参考材料としましょう。
大手IT企業の社員サービスとして、リモートワーク環境を整備とフレックスタイム制度の導入があります。従業員が柔軟に働ける体制を積極的に整えています。また、子育て中の従業員向けに、保育施設を設置したり、ベビーシッター利用の補助を行うなど、育児中の従業員を最大限にサポートすることで、仕事と家庭の両立を支援しています。
充実した福利厚生を利用することで、従業員は子育てにより離職することなく、安心して働くことができます。
さらに、定期的に従業員同士が交流できるイベントや、スキルアップを目的とした自己啓発セミナーの開催により、従業員間のつながりを深めながら、スキルアップ、キャリアの成長をサポートする取り組みも行われています。これらの支援は、従業員満足度を高めることに直結し、企業全体の生産性向上にも寄与しています。
企業は従業員のワークライフバランスの向上を目指し、各種休暇の取得や有給休暇の取得促進に力を入れる動きが活発化しています。
例えば、ある製造業の企業では、有給休暇の取得率向上を目的に“休暇奨励日”を設定し、従業員が積極的に休暇を取れる環境作りに取り組んでいます。年間を通じて計画的に休暇を取得することで、従業員がリフレッシュし、仕事への意欲を高める機会とする狙いがあります。その結果、従業員の満足度が向上し、業務効率や生産性の向上といったポジティブな効果が表れています。このように、各種休暇や有給休暇に関する取り組みは、従業員だけでなく企業全体にとってもメリットのある重要な要素となっています。
リロクラブやベネフィット・ワンといった福利厚生サービスの活用も注目されています。これらのサービスは、充実した福利厚生サービスを自社で設計することなく導入することができます。リロクラブであれば、提供するレジャー施設の割引サービスや、ベネフィット・ワンであれば、健康診断無料提供プログラムなど、従業員のライフスタイルに沿った多彩なオプションも利用可能です。また、資格取得支援や育児サポートといったスキルアップや生活支援のプログラムもあり、それぞれのニーズに合わせて選択することができます。
企業はリロクラブやベネフィットワンなどのトータルで福利厚生をサポートを支援するサービスを効率よく活用することで、コストを抑えつつ、従業員にとって魅力的で効果的な福利厚生を実現することができます。

大矢の経営視点のアドバイス
最近では、低コストで優秀な福利厚生サービスも多くあります。トレンドにも敏感にさまざまサービスラインアップがありますので、なかなか人事担当者で手が回らないといった場合には、サービスの利用も検討材料の一つではないでしょうか。

福利厚生を充実させるためのポイントを見ていきましょう。
福利厚生を充実させることは企業にとって重要な課題の一つです。適切な福利厚生制度を導入することで、従業員の満足度を向上させ、定着率の改善や優秀な人材の確保にもつながります。充実した福利厚生を実現するには、明確な目的・方針、目標設定や制度設計の見直しが重要です。また、従業員のニーズや、福利厚生を利用したうえでのフィードバックを受け入れる姿勢を持つことも大切なポイントです。制度の効果を高められるだけでなく、企業文化の向上も期待できます。
よりよい福利厚生制度を目指すには、まずはその目的を明確にすることが、成功を左右する重要な要素です。企業が福利厚生制度を導入する場合、その目的として、従業員の健康維持やワークライフバランスの向上なのか、モチベーションの向上なのか、働きやすい職場環境なのか、目的を明確にしたうえで、目標を設定することになります。制度の目的を・方針を明確にすることで、どのような福利厚生の具体策、手法が必要かを判断できるでしょう。目標を定量的な指標で示すことで、制度の導入効果を測定できるようになりますので、定量・定性の目標をしっかりと設定することをおすすめします。従業員のニーズに沿った的確な施策を講じるための基盤を築くためには、これらの要件を抑えることが大切なのです。
従業員のニーズの把握は、効果的な制度設計において不可欠です。企業内のアンケート調査やヒアリングを通じて、従業員が会社に求める福利厚生の内容を把握しましょう。子育て世代の従業員が多い企業であれば育児支援に関するニーズが多いこともあるでしょう。一方で、介護に関わる世代の従業員が多い場合などは、介護と仕事の両立ができるような勤務制度にニーズが集まることがあるかもしれません。
ライフステージに応じたニーズに対応することが重要です。また、同様のニーズを持つ社員を対象にしたグループ化も効率的です。ニーズに即した制度を整えることで、組織全体のエンゲージメントを高めることに繋がります。
制度を運用する上での注意点は多々存在します。まず、しっかりとした運用体制を整えることが必須です。福利厚生制度が効果的に機能するためには、運用ルールの明確化や透明性が必要です。定期的に制度の評価を行い、結果を基にした改善策を講じることも重要です。これにより、制度の魅力を維持しつつ、常に従業員の期待に応える形での仕組みを提供することが可能です。こうした改善サイクルを確立することで、長期的な満足度向上が実現できるでしょう。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」