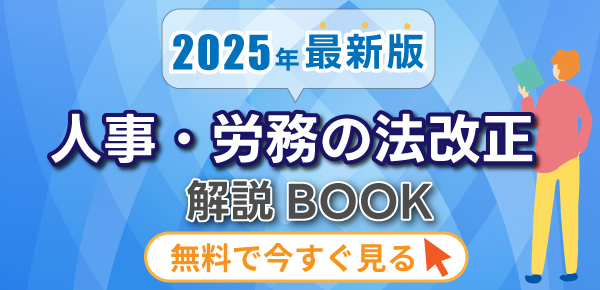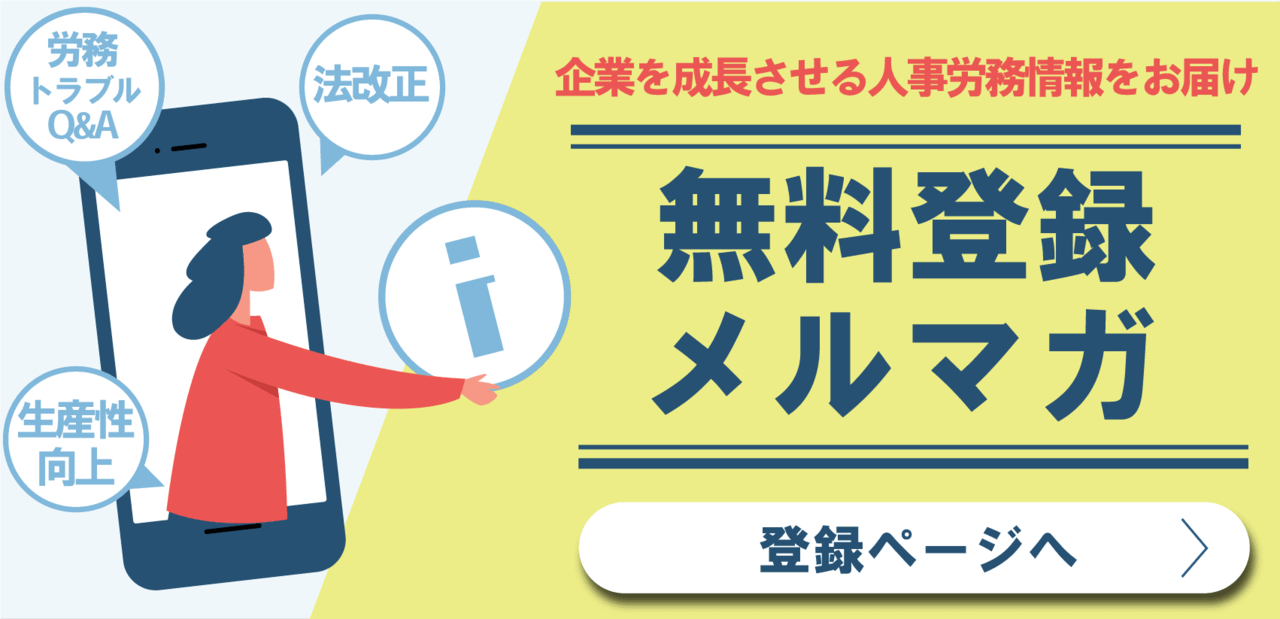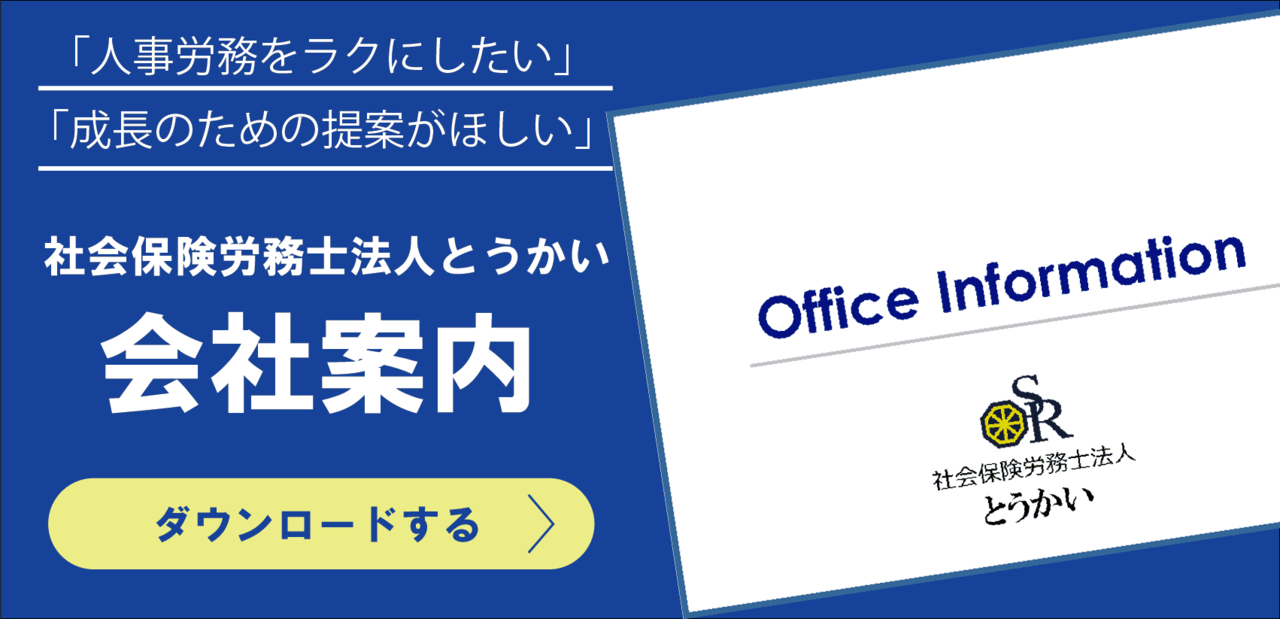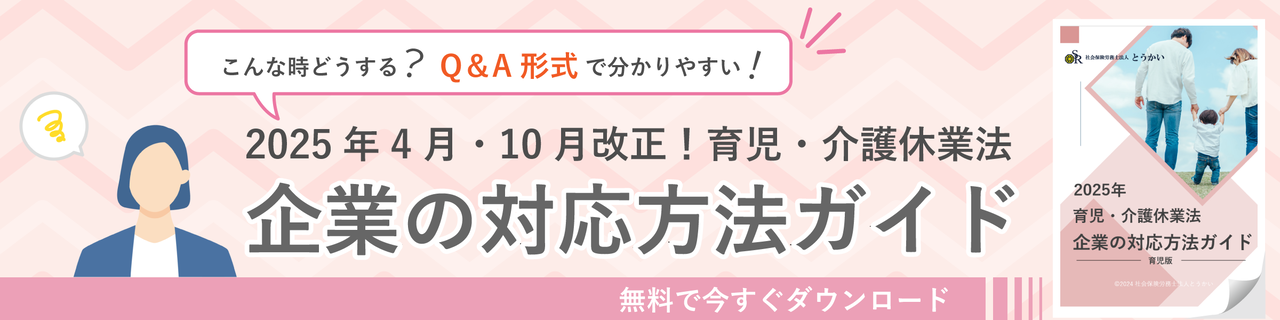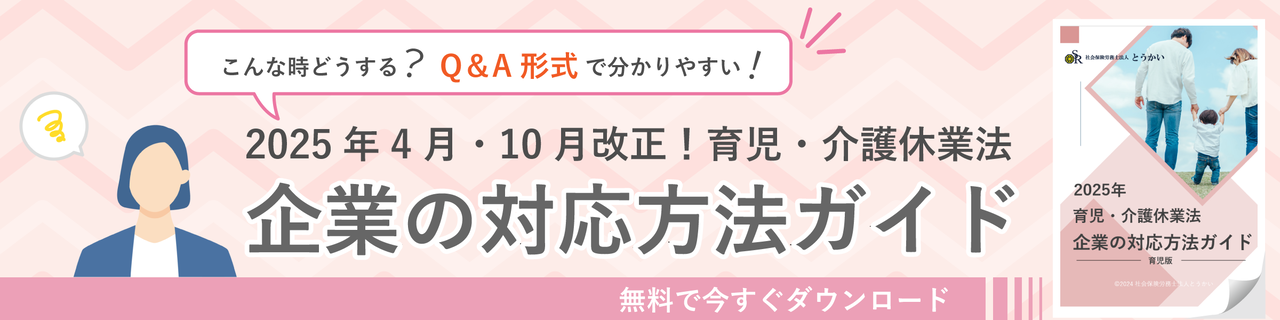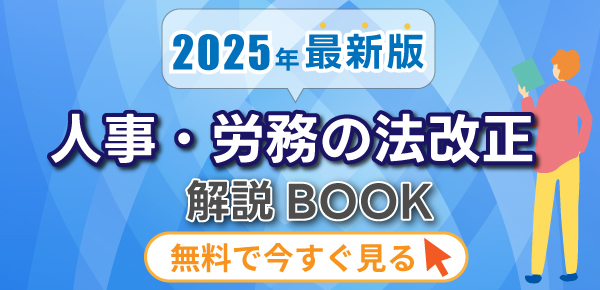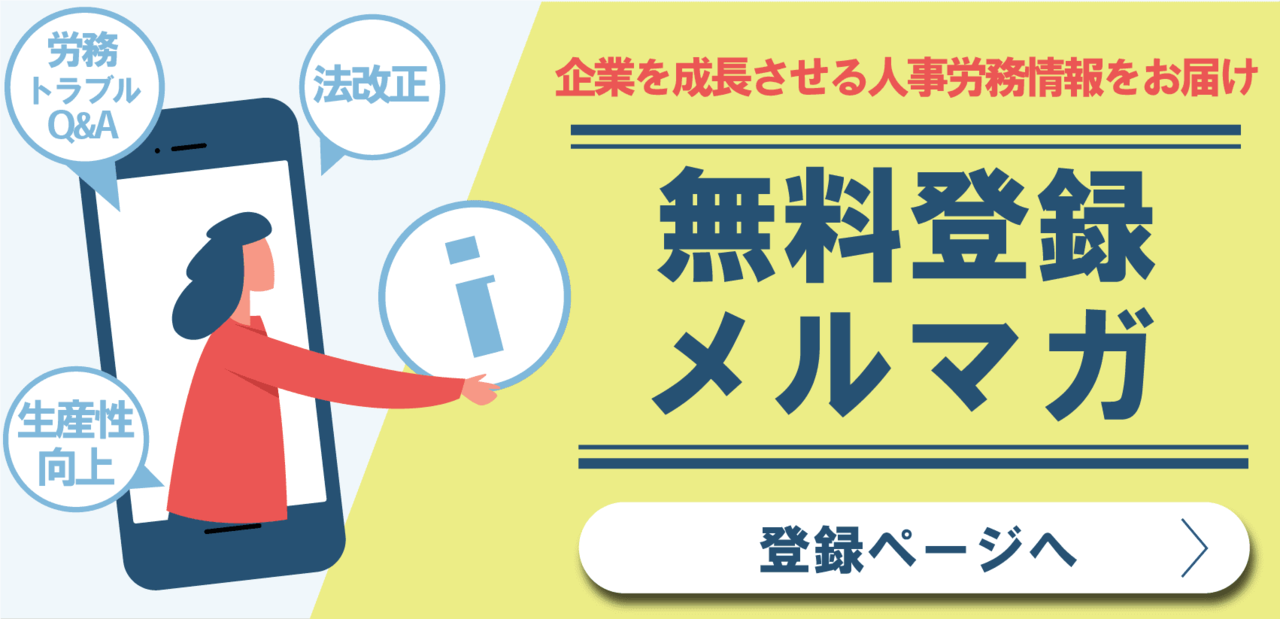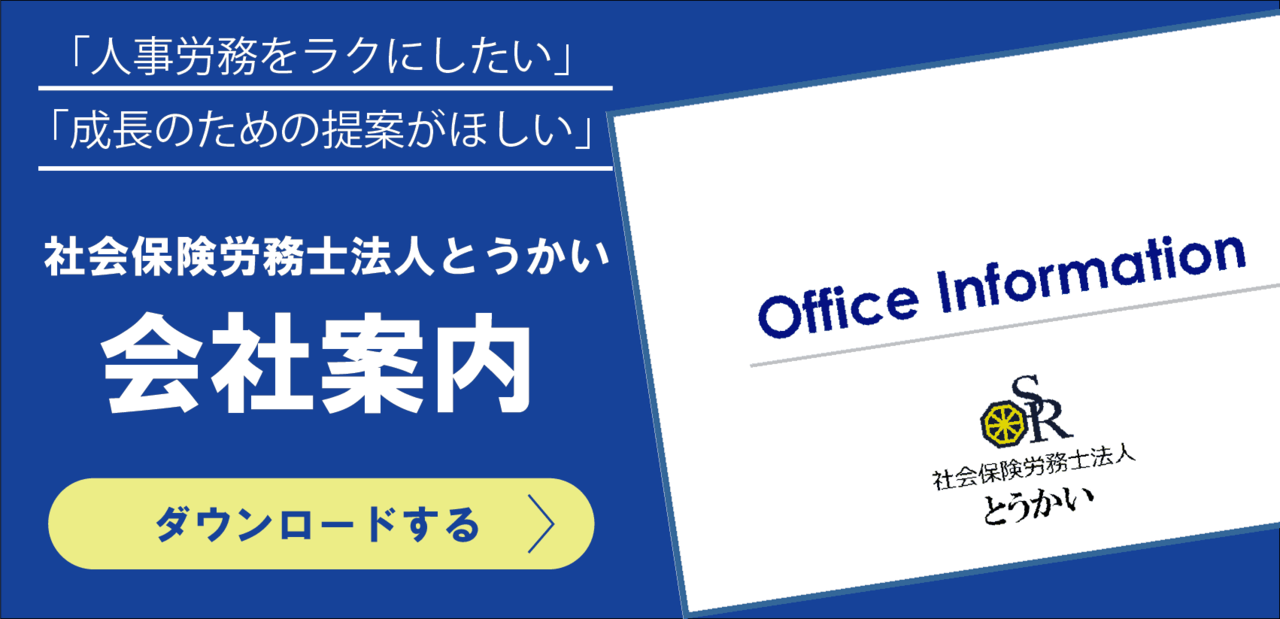「金融所得課税」とは?社会保険料と新NISAの積み立てへの影響を解説

金融所得課税の2025年スタートにより、投資信託や株式投資から得られる利益にどのように影響を与えるのかが注目されています。新NISAとともに投資を始める人も増えたとあって、金融所得課税は税負担に変化をもたらすとも言われています。投資家は自身のポートフォリオを見直し、税利得の最大化を図る必要が生じるかもしれません。合理的な資産運用のために、金融所得課税の動向を把握しておきましょう。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

金融所得課税とは何か?詳しく解説します。
金融所得課税とは、株式や投資信託、預金などから得た利益(所得)に対して課される税金を指します。配当金や譲渡時の利益、預金の利子など金融機関を通じた投資収益に対し、一定の所得税を適用する仕組みです。このように金融所得は課税の対象になるものですが、個人投資を促進するため非課税としたのが、新NISAということです。本来、金融所得課税は、申告分離課税、総合課税、申告不要の3種類の課税方式があります。利益に対して課税される税率は、所得税15%と住民税5%を合わせた20%に復興特別所得税0.315%を加算した20.315%です。金融所得税は、個々の投資家が得る収益に対して、公平な負担をもたらすことが意図されています。税制の透明化や公平性を促進するために導入されており、とくに高額所得者への影響が問われるポイントとなります。
金融所得課税として高額所得者・富裕層の金融所得課税の引き上げがされます。国の税収を安定させるための重要な政策として位置づけられ、国民の所得格差の是正と財政再建を目的としています。近年の金融市場の変化や、国民生活の多様化に伴い、投資による資産形成が注目されています。多くの国民が資産運用を始める中、問題となっているのは、公平な税負担の実現です。そこで、富の集中や税逃れの防止も踏まえ、資産所得に関する課税を見直し、高所得者層より多くの税収を確保することで、社会的な合意形成を図ろうとしています。
金融所得課税は、そもそも高額所得者との所得格差を是正するという目的があります。金融所得税は、高額所得者であっても一般的な所得者層であっても、一律に20.315%の課税がされることになり、富裕層が得する制度となっているため、是正しようというものです。ミニマムタックス、富裕層ミニマム税などと呼ばれています。
こうした金融所得に対する課税がスタートする一方で、社会保険制度にも同様の議論がされてきました。背景には、多数の高所得高齢者の医療費と社会保険料の適正について議論されてきたのです。金融資産の多い高齢者の世帯からは社会保険料の負担を増やすべきだとの議論です。金融所得や金融資産の多い世帯には、社会保険料の算定に金融所得が反映されるかどうかが重要な焦点となっています。
さらに、給与所得者世代にも金融資産所得の反映をするかどうかも話題となっています。給与所得を基にした社会保険料計算は、金融所得は反映されていません。つまり、所得の種類による社会保険料の取扱いに違いが生じるため、経済状況に応じた公平な負担が確保されることが期待されています。税制の見直しと社会保険制度の整合性を強化することにより、税負担の軽減が実現され、安定的な社会保障が可能となるというわけです。制度の改正が進む中で、さらなる議論が求められる時期に差し掛かっています。

新NISAにも影響するのかを見ていきましょう。
社会保険料にも金融所得を反映させるべきか議論されていますが、気になるのが新NISA制度です。2024年からスタートした新NISA制度は、非課税で投資・運用ができる個人投資家にとって魅力的な税制です。その利益が社会保険料にどのように影響を及ぼすかについての注目が集まっています。新NISAを通じて得られる利益は、非課税とされていますが、社会保険料に関連する制度は異なるため、影響がゼロとは言えません。金融所得や投資信託の収益に対する課税の変化が、今後の社会保険料に及ぼす影響については、引き続き観察する必要があります。
もしも投資で得た利益が社会保険料の算定に加算されることとなった場合、どのような影響があるでしょうか。投資で得た利益は、確定申告によって反映されることが基本です。特に、1年後の社会保険料には、前年の所得金額が大きな影響を与えます。たとえば、金融資産を運用し、株式や投資信託から利益を上げた場合、それが確定申告で報告されれば、社会保険料の算定に影響を及ぼす可能性があります。実際には、金融所得の増加が前年の所得に加算され、結果的に保険料が引き上げられることも考えられます。投資家にとっては、短期的な利益追求が将来的な負担増を招くリスクを内包していると言えます。
金融所得を社会保険料の算定に反映させるかについては、現段階でNISAなどの非課税所得は賦課対象としない方向性です。ただ、引き続き動向には注目しておくべきでしょう。新NISAでは、投資信託や株式投資に対する税の優遇が魅力ですが、利用する際にはいくつかの注意点が存在します。まず、投資信託を選ぶ際に、その運用方針や手数料、リスクを十分に理解しておくことが大切です。新NISA口座の非課税制度を利用しても、将来的に金融所得が社会保険料に反映される可能性があるため、長期的な視点での資産運用を考慮する必要があります。新NISAの利点を最大限に活用するためにも、これらの点をしっかりと確認し、投資判断を行うことが求められます。

大矢の経営視点のアドバイス
現時点では金融所得課税がNISAに影響することはないようですが、引き続き注目しておくことが必要でしょう。昨今では、年収の壁議論、社会保険の負担、iDeCoの改正など、税や投資、保険料などについての話題が多くあります。自分自身で金融リテラシーをあげていくことも重要です。
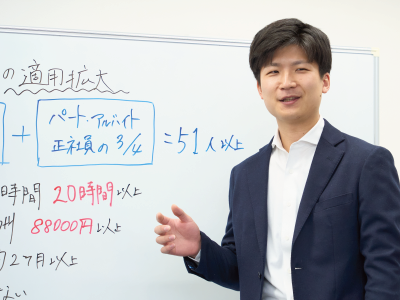
「扶養」や「世帯」にどのような影響があるのかを確認しましょう。
金融所得に関する税制、社会保険料など、注目すべき事項がありますが、議論途中の部分もあり、動向は引き続きチェックしておく必要があるでしょう。また、扶養や世帯といった扶養の仕組みも、相関関係がありますので、注意が必要です。
社会保障制度において非常に重要な役割を果たします。扶養される側の所得が一定の限度を超えると、扶養から外れることになります。特に、金融所得などの利益が増加すると、扶養の資格に影響を及ぼす可能性が高まります。これにより、扶養者が負担する社会保険料の変化や、家計全体の支出に影響が出ることもあります。
60代は、退職後の生活を考える重要な時期となります。定年で退職するのか、引き続き働き続けるのか、年金を受け取りつつ、ペースダウンして働くのか、さまざまなケースが考えられます。この年齢層において、社会保険料の負担が特に注目されています。年金受給者の場合、年金だけで生活を支えることが難しいケースが増え、金融所得、特に株式や投資信託を利用することが多くなります。ところが、この金融所得が扶養の資格や社会保険料の増減に直接的な影響を与えることがあります。従って、60代の個人投資家は、投資の利益がどのように役割を果たすか、深く理解することが重要です。
扶養に入っている人が投資を行っている場合には、場合によっては扶養から外れるケースもありますので、注意が必要です。扶養から外れずに投資を行っていくには、「特定口座」で投資をしなければなりません。もしも「一般口座」で投資を行う場合には、投資による利益によって左右されることがあります。たとえば、投資信託や株式で得た利益が一定の金額を超えることで、扶養の条件を満たさなくなることがあります。特に、家族内での収入の変動が大きい場合、扶養されている人の所得状況を適宜見直す必要が生じます。投資家にとっては、扶養の範囲内で得た利益を管理することが肝要となります。このように、扶養の外れるタイミングやその理由は、具体的な利益の状況に依存するため、注意を払いながら投資戦略を考えることが求められます。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」