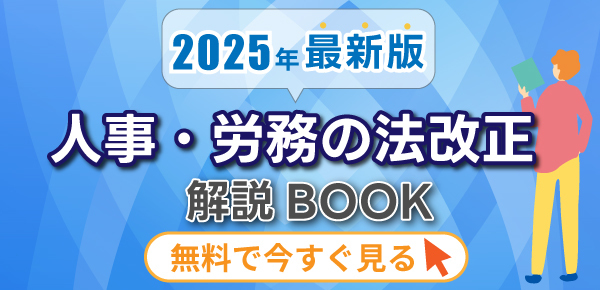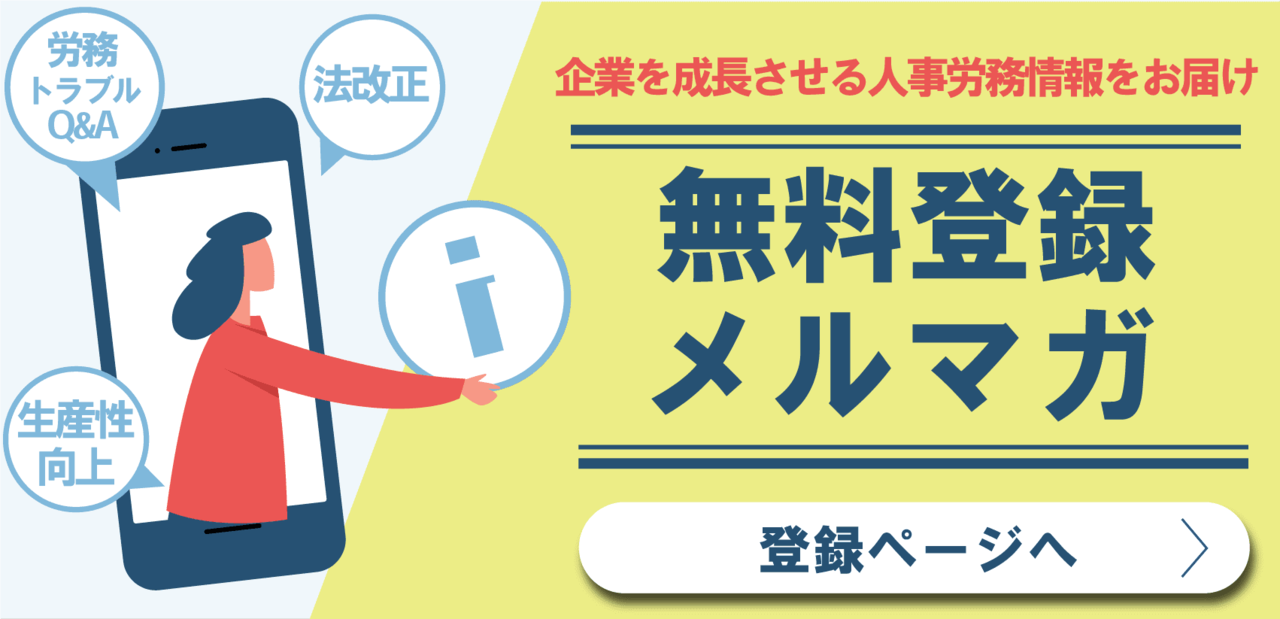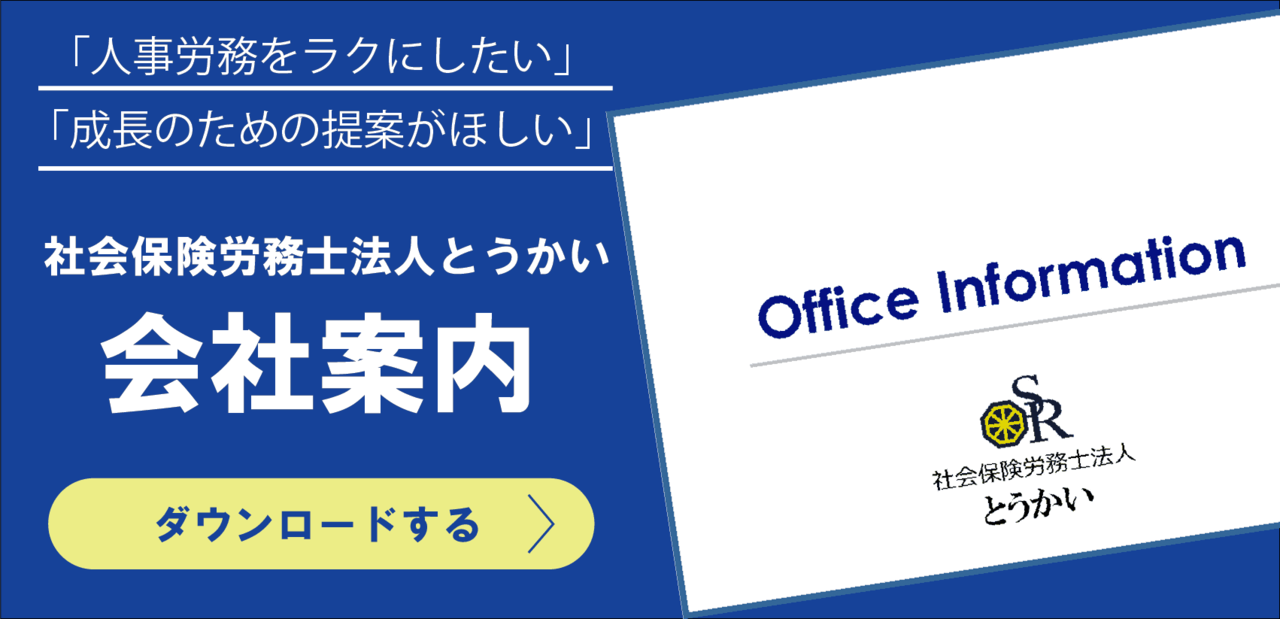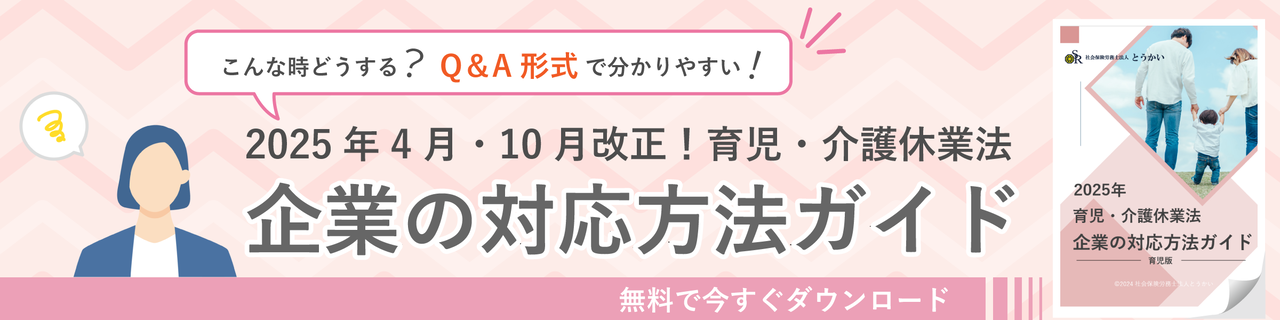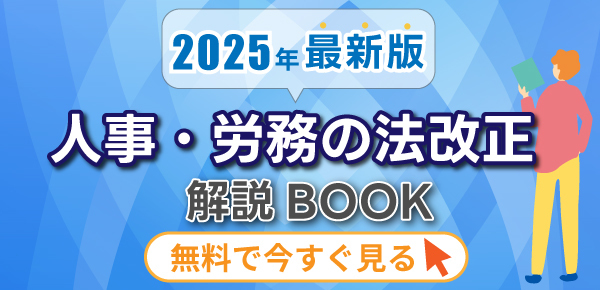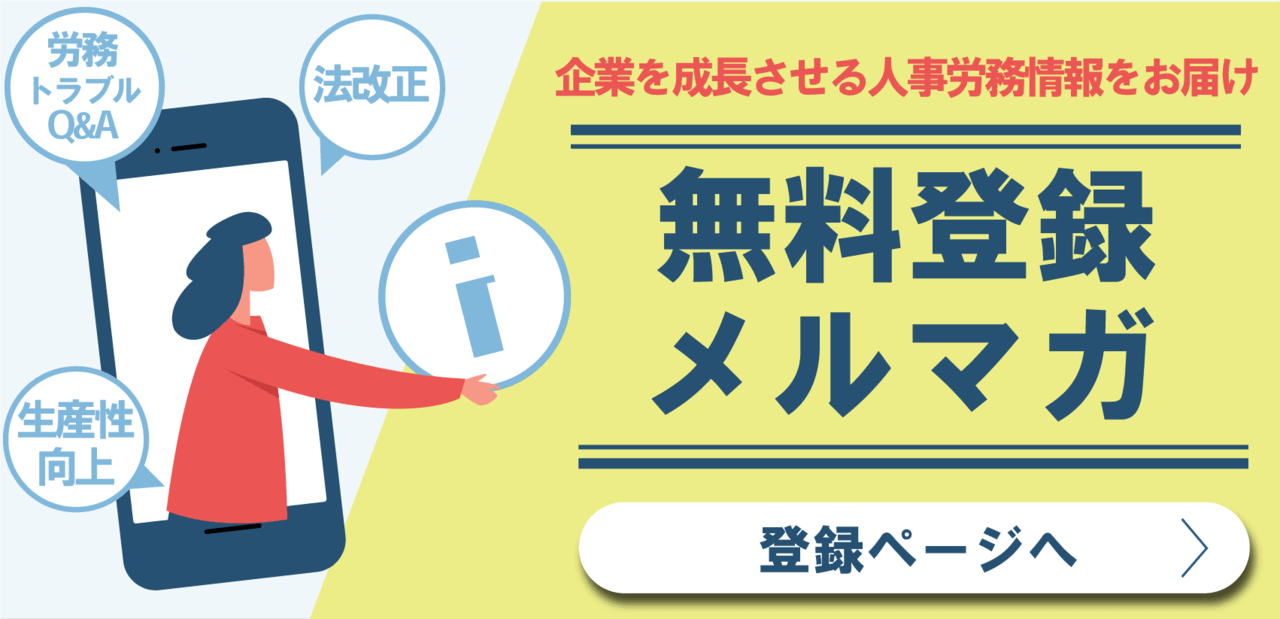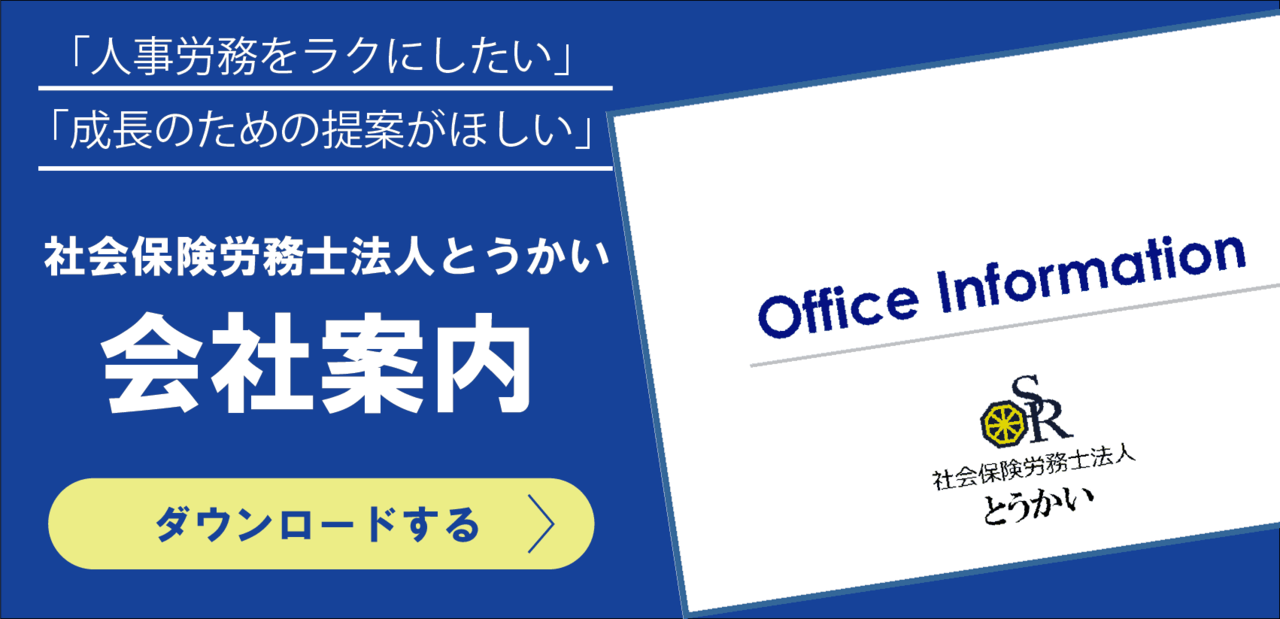【2025年最新】ハラスメントの種類と定義とは?
ハラスメントを予防するために会社でできること

職場でのハラスメントが重要な課題となっている現代、企業や組織において意識的に取り組む必要性が高まっています。特に、最新のハラスメントの種類や新しい定義が次々と登場しており、これらに適切に対応することが従業員の安心で働きやすい環境を整える上で不可欠です。各種ハラスメントがもたらす影響は多様であるため、正確な理解を深めることと、実効的な予防策を講じることが重要です。ハラスメントによっては、法律で防止するための措置を義務付けられているものもあります。
企業が最新の情報に基づいた取り組みを進めることで、働く人々の安全で安心できる職場環境の実現が期待されています。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

ハラスメントの基本と定義を詳しく解説します。
ハラスメントとは、他者に対する不当な態度や言動が原因で、相手に不快感や心理的苦痛を与える行為を指します。法律上の定義があるものもあれば、社会的な背景から生まれた新しい概念も存在し、その種類は多岐にわたります。企業は、これらの違いや具体的な行動を理解することで、職場でのハラスメントを効果的に防止するための手段を講じることが可能になります。
社会や組織で一般的に考えられるハラスメントは、人間関係における嫌がらせの形態です。状況や環境によって、さまざまなケースのハラスメントが発生する可能性があります。とくに職場では、人間関係の質が問われており、従業員一人ひとりの権利や気持ちに対する配慮が重要です。このような姿勢は、健全な組織の成長を支える基盤となり、ハラスメントを未然に防ぐための新しい取り組みや意識改革にもつながります。
どのような言動・行動がハラスメントに該当するのか、詳しく理解しておかなければなりません。ハラスメントの種類や状況によっても異なります。例えば、特定の個人に対して無礼または不適切な発言を繰り返す行為や、身体的な接触を含む行動、さらに職場や学校などの権限を利用して不当な要求を行うといった言動・行為は、一般的にハラスメントとして認識されます。また、無視や冷たい態度といった精神的な攻撃も含まれ、被害者が苦痛を感じる場合でも、これらがハラスメントに該当する可能性があります。近年では「新しいハラスメント」として認識されるものも増えており、例としてオンライン上の嫌がらせや、過剰な監視が挙げられます。ハラスメントの形態は多様化しつつあり、それが無意識に行われる場合であっても、その影響を十分に理解し、慎重に行動することが求められます。

鶴見の経営視点のアドバイス
厚生労働省では職場におけるハラスメントについて、「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」の3つを満たすものと定義しています。

代表的なハラスメントの種類と具体例をご紹介します。
職場環境において、ハラスメントは様々な問題や深刻な事態を引き起こす要因となります。その中でよく見られるハラスメントは、多くの人に影響を与える可能性もあるため、正確な理解が必要です。
代表的なものとしてパワハラ(パワーハラスメント)、セクハラ(セクシャルハラスメント)、マタハラ(マタニティハラスメント)、ケアハラ(ケアギバーハラスメント)、モラハラ(モラルハラスメント)などが挙げられますが、これに加えて最新のハラスメントとして、「テクハラ」や「リモハラ」などの新たな形態も注目されています。たとえばテクハラ(テクノロジーハラスメント)は、ITツールの使用や運用の強制、技術的な知識欠如を責める行為を指し、リモハラ(リモートハラスメント)は在宅勤務やオンライン会議におけるハラスメント行為を含みます。これらの問題は職場環境だけでなく、従業員のメンタルヘルスにも影響を与えるため、迅速な対策が求められます。
パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場における上下関係を利用して、相手に嫌がらせやいじめ、不当な言動行為です。主に職務上の権限を持つ上司や管理職がその立場を利用して部下や同僚に嫌がらせをする場面で見られることが多いです。例えば、威圧的な態度や不必要で過大な業務を強制する、業務に関連しない暴言や物理的な攻撃などが典型的な例として挙げられます。また、業務の場面において無能扱いや個人的な攻撃を受けることで、従業員の仕事へのモチベーションが著しく低下する可能性があります。具体的には、「こんなこともできないのか」と侮辱的な言葉で攻撃される、仕事の報告をした際にわざと大声で怒鳴られるといったケースなどです。これらの行動は、被害者に深刻な精神的苦痛を与える場合があり、職場環境にも悪影響を及ぼします。状況が放置されれば、心的なダメージが長期間にわたり続き、メンタルヘルスに深刻な影響を及ぼすことが少なくありません。これらの問題を防ぐためには、労働環境の改善とともに早期対応が重要です。

小栗の経営視点のアドバイス
厚生労働省のパワハラ定義によると、「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」を挙げています。優越的な関係を背景として行われるこれらの言動や行為は、深刻なトラブルを招くことになります。
セクハラ(セクシュアルハラスメント)は、性的な意味合いを持つ嫌がらせや不快と感じさせる言動・行動です。セクハラ行為は、身体的な接触や言動だけでなく、無言の圧力や暗黙の了解を装った行動を伴う場合も少なくありません。性的な言動によって相手が拒否した際に不利益を与える行為や、相手を精神的に傷つける行動もセクハラに該当します。職場内の性的な関係を強要する、または繰り返し性的な発言を行うことで相手に強い不快感を与える行為は、被害者の心身の健康はもちろん、職場全体の環境にまで及ぶことがあります。このような問題は、深刻に受け止め適切に対応しなければさらなるトラブルに発展する可能性もあります。
例えば、飲み会の席で異性に対して不適切に体に接触をすることや、私生活に関して過剰に突っ込んだ質問を行うケースが考えられます。これらは、職場や日常生活で生じる問題の一部に過ぎません。また、性的な関係を拒否した場合に部署を異動させるといった不当な扱いが行われることも、セクハラと捉えます。
マタハラ(マタニティハラスメント)は、妊娠や出産に関連する嫌がらせであり、特に女性従業員にとって深刻な問題です。妊娠や出産に伴う身体的・精神的な負担に加えて、職場での不適切な対応や理解不足が引き金となりやすいでしょう。例えば、妊娠中の女性に対し、「休業中は仕事をしない方がいい」といった発言を行ったり、「子育てをしながらの仕事は無理だろう」といった差別的な発言も見受けられます。こうした言動は、妊婦や育児中の母親に対する社会的な偏見を反映したものです。このような発言が繰り返されることで、妊婦や育児中の従業員に精神的な負担を与えるだけでなく、職場全体の環境や雰囲気にも悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、育児休業を取得したことを理由に降格させるといった待遇の悪化や昇進の妨げが挙げられます。マタハラ行為は女性従業員のキャリアや職場環境を損なうだけでなく、職場での公平性が失われる要因ともなり得ます。
マタハラ行為を放置したり、職場でのサポートが不十分であると、出産後の復帰をためらわせるだけでなく、働く意欲そのものを削ぐ結果を招く可能性があります。こうした状況を改善するためには、偏見の解消を目指した啓発活動や管理職を含む従業員全体への教育企業や職場全体でこの問題に対する適切な対応が求められています。
ケアハラ(ケアハラスメント)は、近年注目される新しいハラスメントの一つです。働きながら介護を担っている従業員に対し、嫌がらせをするなどの行為です。さらに、会社の介護に関連する制度を利用させないなどの不利益な行為をいいます。例えば、介護休業を申請すると、上司から「その分、他にしわ寄せが来る」といった心無い言葉が投げかけられることがあります。
多くの企業では介護休業制度が設けられているものの、実際には職場の雰囲気や業務の圧力などから利用しづらい状況があり、従業員は深刻な悩みを抱えることが少なくありません。特に、介護に携わる従業員に対する理解や配慮が不足している場合、ケアハラが発生することがあります。ケアハラにより過度な精神的ストレスを引き起こすことがしばしばです。従業員の辞職や長期的なメンタルヘルス問題に繋がることも少なくありません。本人のみならず、職場の雰囲気が悪化する要因ともなるでしょう。このような状況を防ぐためにも、職場全体で介護への理解を深め、柔軟な対応策を講じることが求められます。
モラハラ(モラルハラスメント)は、言葉や態度を通じて相手に精神的な苦痛を与える行為です。身体的な攻撃が伴わないために外部からの判断が難しく、被害者自身もハラスメントを受けていると気づきにくい場合も多いでしょう。具体的には、「お前はいつもダメだ」といった否定的な言葉を日常的に受け続ける状況や、自分の意見に対して一切の配慮がない扱いを受けることが、モラハラ(モラルハラスメント)の一例として挙げられます。心理的な負担を被害者に強いる行為が問題視されています。また、周囲の人間関係を利用して孤立させるようなケースもあります。例えば、仲間内で意図的に仲間外れにする行為や他者との連携を妨害する行動は、加害者が被害者に対して優位性を保つための典型的な手段です。さらに、嫌悪的な発言や態度、無視することで、相手の精神的な健康を著しく損なう結果に繋がります。これらの行為は心理的負担を積み重ね、トラウマを引き起こすことさえもあります。
日常的に行われるモラハラは、被害者の心の健康に深刻な影響を与えます。その人の仕事や日常生活におけるモチベーションが著しく低下し、被害者の自尊心や社会的関係にも深刻な影響を及ぼします。そのため、早期に対策を講じることが重要です。
最近では、新しい形態のハラスメントとして、ジェンハラ(ジェンダーハラスメント)、ロジハラ(ロジカルハラスメント)、テクハラ(テクノロジーハラスメント)、スメハラ(スメルハラスメント)などが知られるようになりました。これらは、特定の状況や社会的背景、新しい価値観やライフスタイルの変化により生まれたものであり、それぞれの問題に対して細やかな配慮が求められます。これらのハラスメントの形態は、被害者の心身に深刻な影響を与えることがあり、早期に適切な対策を講じることが重要です。
例えば、ジェンハラは性別や性的指向を理由とした偏見や差別的な言動を指し、職場での平等を妨げる深刻な要因の一つとして挙げられます。ロジハラは正論を突きつけて相手を追い詰めることによって、心理的負担を与える行為です。テクハラでは、IT技術や知識の不足が問題視され、上司や同僚からの過度な指摘や支援不足が要因となります。一方、スメハラは体臭や香水などをはじめ、臭いによる不快感に起因し、職場内の人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。このようにハラスメントの種類や内容も細分化されており、ハラスメント対策が非常に難しいとも言えるでしょう。ただ、新しいハラスメントも現代の職場において無視することのできない重要な問題であり、組織全体でその特性や影響について理解を深めることが求められます。それぞれの種類に応じた適切な対応策を講じることが、快適で健全な職場環境の実現に欠かせない要素となります。

大矢の経営視点のアドバイス
2020年には改正パワハラ防止法が施行、2022年からは企業においてハラスメント防止のための適切な措置を講じるよう義務付けられています。ただ、ハラスメントにはさまざまなケースや、指導とパワハラの境界線、本当にハラスメントにあたるのかといったケースも多々あり、人事担当者もお悩みかもしれません。自社の状況・環境で起こりやすいハラスメントを理解し、適切な予防策を検討していきましょう。

ハラスメントの影響とリスクを確認しましょう。
ハラスメントの問題は、加害者・被害者の両者の問題だけでなく、企業全体にも深刻な影響を及ぼすことが少なくありません。ハラスメントが常態化すれば、職場環境の悪化が従業員のメンタルヘルスに直接的な影響を与え、士気が低下するでしょう。最新のハラスメントについて正しく理解し、早期に適切な対策を講じることが、企業全体のパフォーマンスを維持するためには欠かせない要素といえます。
ハラスメントを受けた従業員は、精神的な苦痛が蓄積され、メンタルヘルス不調を訴えることがあります。業務パフォーマンスの低下や職場での人間関係が悪化につながることにもなるでしょう。被害者の心的ストレスは、自己評価の低下やうつ病などの深刻な健康問題から、長期的には休職や離職の増加といった企業に大きく影響を及ぼす事態を招きます。休職者・退職者による人材補充など、人事計画にも影響を及ぼします。
企業にとってハラスメント問題は多大なリスクを伴います。ハラスメント問題が放置されていたり、対応に誤りがあれば、労働基準監督署からの指導や是正命令を受ける可能性もあるでしょう。トラブルが発展すれば、訴訟リスクも生じます。昨今は従業員が不当な扱いを受けたと訴えるケースが増加しています。これらの問題が裁判に発展することで、企業は金銭的な損害賠償を求められるだけでなく、その過程で多大な時間とリソースを費やすことになります。このような法的手続きへの対応は、企業の戦略的な業務運営に悪影響を与えるだけでなく、企業の信頼性やブランドイメージへのダメージにもつながります。
さらに、ハラスメント問題は、生産性低下も招きかねません。例えば、ハラスメントが発生することで社内のコミュニケーションが希薄化し、業務を円滑に進めるために必要なチームワークが大きく損なわれることがあります。また、職場環境の悪化により、従業員が日々ストレスを抱えて働く状況が生まれると、全体的な業務効率の低下が避けられません。このような影響が積み重なることで、最終的には企業の業績や競争力にも大きな打撃を与える可能性があります。
職場での最新のハラスメントの問題は、全体的な士気に大きな悪影響を及ぼします。ハラスメントの発生が周囲に与える影響は、一見目に見えにくいものですが、従業員同士の信頼関係を損ないます。職場に恐怖や不安感が蔓延し、従業員が自由に意見を述べることが難しくなることで、組織全体の創造性やイニシアティブが大幅に低下するリスクが高まります。このような環境では、従業員のモチベーションの維持が困難となり、生産性にも悪影響を及ぼします。
また、ハラスメントなどに関する問題が外部に広まり、企業の評判にも大きな打撃を与える可能性があります。特にハラスメントの対応が不十分であると認識されると、求職者はその企業での就職を敬遠し、優秀な人材の確保が難しくなるでしょう。
企業はブランドイメージや評判、いわゆる「reputational damage(評判リスク)」に見舞われ、顧客や取引先からの信頼が低下するリスクが高まります。上場企業であれば、株価に影響することもありますし、ステークホルダーからの厳しい目にもさらされることになります。顧客や取引先からの信頼を損失することで、事業機会を逃してしまう危険性もあります。現代のビジネス環境では、職場環境の良さが競合他社との差別化要素として非常に重要視されるため、企業はこれらの問題を他人事とせず、適切な対策を急ぐことが求められます。
企業がハラスメントへの早急な対応や予防策を講じることは、従業員の安全と働きやすい環境を守るだけでなく、持続可能な企業運営においても不可欠であると言えます。

ハラスメントを防止するために会社が行うべき対策を見ていきましょう。
ハラスメントの防止は企業にとって重要な課題です。職場内でのハラスメントは、従業員のメンタルヘルスに悪影響を与えるだけでなく、企業全体の生産性低下やイメージダウンといった深刻な結果を招く可能性があります。特に近年では、最新のハラスメントの形態も問題視されており、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントだけでなく、オンラインを通じたハラスメントなど、新たな問題も発生しています。そのため、企業はこれらに迅速に対応できる体制を整える必要があります。
ハラスメント防止に向けて、まずは明確な社内方針を策定することが不可欠です。方針には、従来のハラスメントだけでなく、新しいハラスメントにも対応できるよう、ハラスメントの定義や該当する具体的な行為が詳細に示されている必要があります。従業員全体にこの方針をしっかりと周知し、理解を深めてもらうことが重要です。
明確なポリシーやガイドラインを策定し、従業員全体に周知徹底することで、防止意識を高めることが求められます。
さらに、ハラスメントへの理解を深め、職場全体で意識を共有するために、定期的な教育や研修の実施が有効です。この教育では、新しいハラスメントのケースも取り上げ、職場でどのような影響をもたらすのかを具体的に認識させることが求められます。ケーススタディを取り入れることで具体例に基づいた考察の場を提供でき、実際の行動指針を得る助けになるでしょう。従業員一人ひとりが職場の健全性を保つ重要性を理解し、ハラスメントが決して容認されない環境を作り上げることが目標です。
ただ、一旦掲げた方針や制度も、想定外の状況に十分対応できない場合もあるため、企業は柔軟かつ継続的に政策やマニュアルを見直しながら、より効果的な対策を模索する姿勢を持つことが重要です。
ハラスメント対策には、相談窓口の設置が重要です。相談窓口は、従業員が安心して利用できる環境、サポート体制を築くことが求められます。匿名で相談できる仕組みを整えることで、従業員はプライバシーを心配することなく気軽に相談を行うことが可能になります。
また、相談窓口での対応を円滑に進めるために、対応マニュアルの作成が必須です。マニュアルには、最新のハラスメント事例やトレンドを反映し、迅速かつ適切なサポートを提供できる指針を明確にする必要があります。マニュアル作成にあたっては専門のカウンセラーや人事部門との連携を強化し、場合によっては外部機関との協力体制も含む包括的な方針を組み込むことが理想です。これにより、従業員が安心して相談できる体制の構築が実現します。
ハラスメントの問題が発生した際は、迅速かつ適切な対応が不可欠です。問題が確認された場合は、直ちに調査を開始し、事実確認を徹底する必要があります。この調査では、被害者、加害者、目撃者などからのヒアリングを含め、客観的かつ公正に実施することが求められ、これによって確実かつ透明性の高い判断を下すことが可能となります。
調査結果を基に、企業は適切な処分や再発防止策を迅速に講じましょう。企業としての責任を果たすと同時に信頼回復へ繋げることが重要です。

ハラスメントを防止するために個人ができることを確認しましょう。
職場でのハラスメント防止において、従業員個人の意識や行動が非常に重要な役割を果たします。各自が積極的に取り組むことで、より安全で快適な職場環境を実現することができます。会社任せでなく、ハラスメントに関する知識を習得し、状況に柔軟に対応する意識を持つことが重要です。ハラスメントの兆候をいち早く感知し、適切かつ迅速に行動をとることが求められます。こうした個々の取り組みが、職場全体の健全な環境づくりに繋がります。
ハラスメントなどが発生せず、安心・安全に働くことのできる職場環境は、従業員にとって働くベースとなるものです。ハラスメントが発生しない職場環境を維持するためには、周囲で起こる微妙な変化や言動に敏感といったハラスメントの兆候を見逃さないことが重要です。リアルなやりとりの中での言葉や態度によるものだけでなく、オンライン上での行動や無視、意図的な情報の遮断など、多岐にわたるケースがあります。ハラスメントが疑われる兆候として、従業員同士の言動や態度の変化、不適切な発言、否定的なコメントの増加などが挙げられます。こうしたサインを早期に察知すれば、問題がさらに深刻化するのを防ぎ、迅速な対処が可能となります。
安全で快適な職場環境を作るためには、従業員自身が積極的に行動を起こすことが必要です。まず、従業員が被害者・加害者にならないためにも、それぞれがハラスメントに関する知識を持ち、意識を高めることが必要不可欠です。特に新しいハラスメントとされるような言動や態度を理解し、注意することが重要です。冷静に状況を観察し、働く仲間の行動や感情の変化に注意を向けることで、問題を未然に防ぐ力が養われます。互いを気遣い助け合う姿勢は、職場全体の信頼関係を強固にするためにも重要です。時代に応じて変化するハラスメントのリスクを認識し、適切な対応を取ることが求められています。
新しいハラスメントの中には、周囲の人々が気づきにくい形で精神的な負荷を与えてしまう行動や無意識の偏見による発言なども増えています。このような行動をしないよう意識し、常に他者を尊重する姿勢を持つことで、職場内で信頼と良好な関係性を築くことが可能となります。
また、自主的に教育や研修へ参加することで、ハラスメント全般の知識はもちろん、新しいハラスメントに対する理解を深めることも効果的です。セミナーやワークショップに参加することで、多様な状況や視点について他者と意見交換を行い、自らの行動を振り返る貴重な機会となります。そのうえで、仲間と共に予防活動や改善策に取り組む姿勢を持つことが、チーム全体の意識向上や職場環境の改善に繋がることでしょう。

高谷の経営視点のアドバイス
ハラスメントの防止にあたっては、会社・人事部が主体となって進めていくことはもちろんですが、これらの取り組みを行なっていくのは、従業員自身です。従業員一人ひとりが、具体的にどのような発言・行動がハラスメントに該当するのか、しっかり理解してもらわなければなりません。ただ単に、業務で強く指摘されたとしても、必ずしもハラスメントに該当するわけではありません。変にハラスメントを危惧して、指摘すべきこと、教育すべきことを発言したり、行動できなくなっては、企業として業績活動するうえで、問題です。安全で信頼性の高い職場文化の構築のためにも、しっかりと従業員個人にハラスメントの正しい理解をしてもらうための活動が必要でしょう。

職場でのハラスメント問題は、組織全体に深刻な影響を与える可能性があります。各種ハラスメントの種類や具体例を理解し、企業側の対策を講じることが要求される状況が続いています。従業員個人それぞれがハラスメントを防止する意識を持ち、行動を起こすことも欠かせません。自身や周囲の人々の言動に注意を払い、ハラスメントの兆候を見逃さないように心がけましょう。企業と個人の双方が協力して、健全な職場環境の構築に向けて努力し、快適な職場が実現されることによって、業務の効率が向上し、全体の士気も高まります。
ハラスメントの防止に向けた取り組みにお悩みの会社、人事担当者の方は、ぜひご相談ください。人事労務の専門家が、御社のハラスメント対策について、しっかりとアドバイスさせていただきます。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」