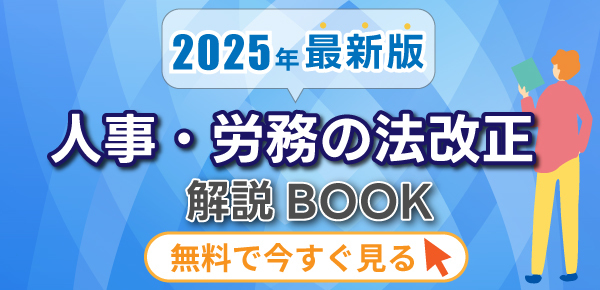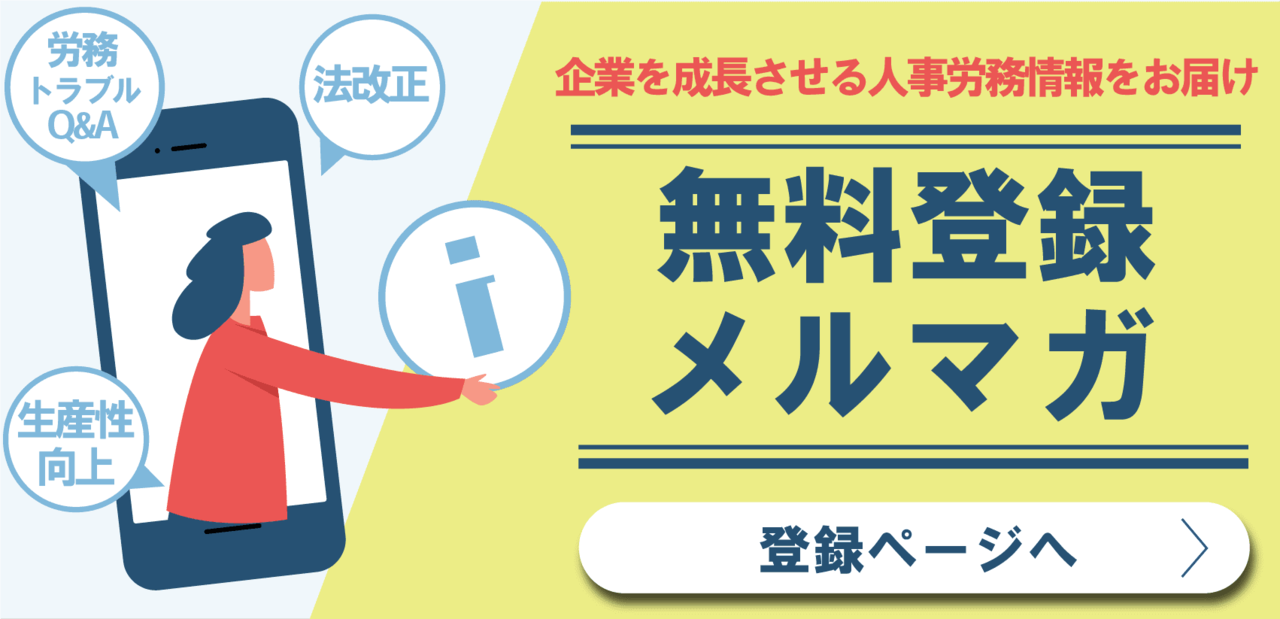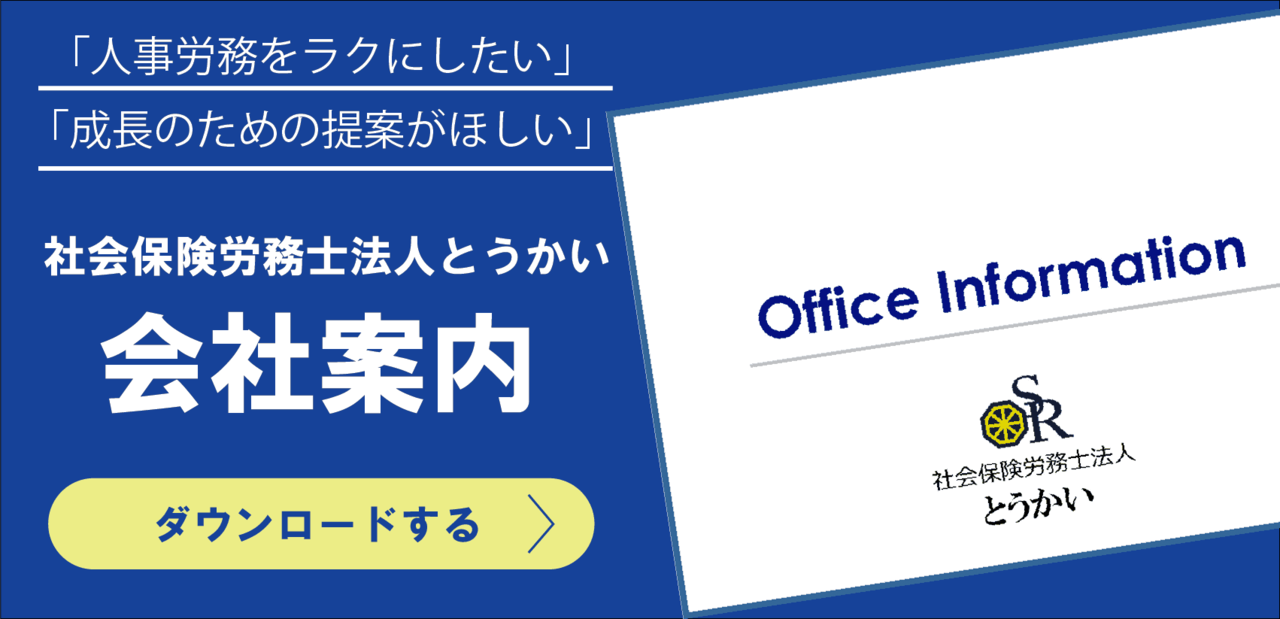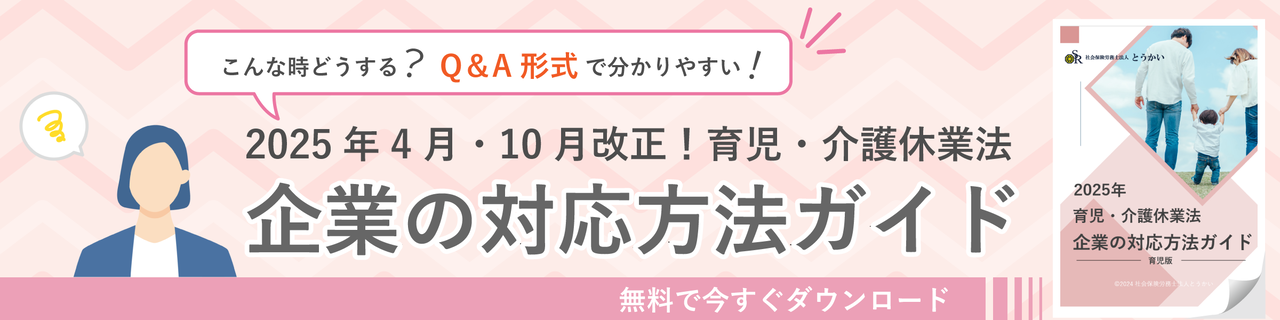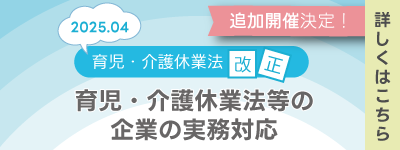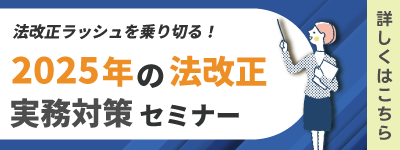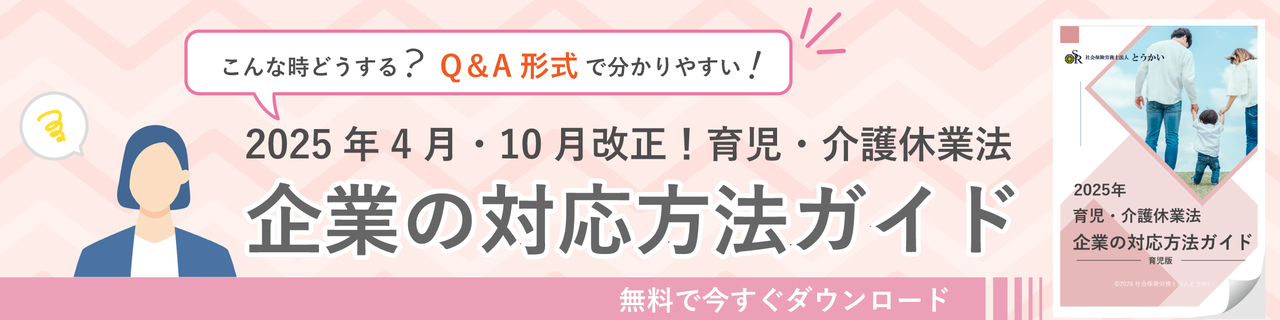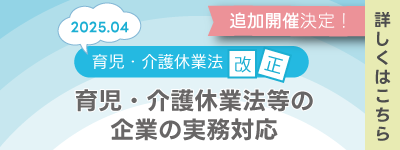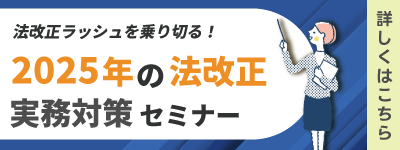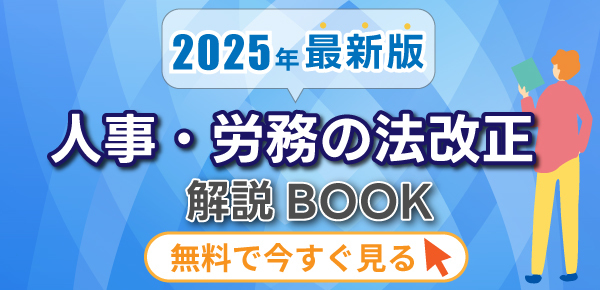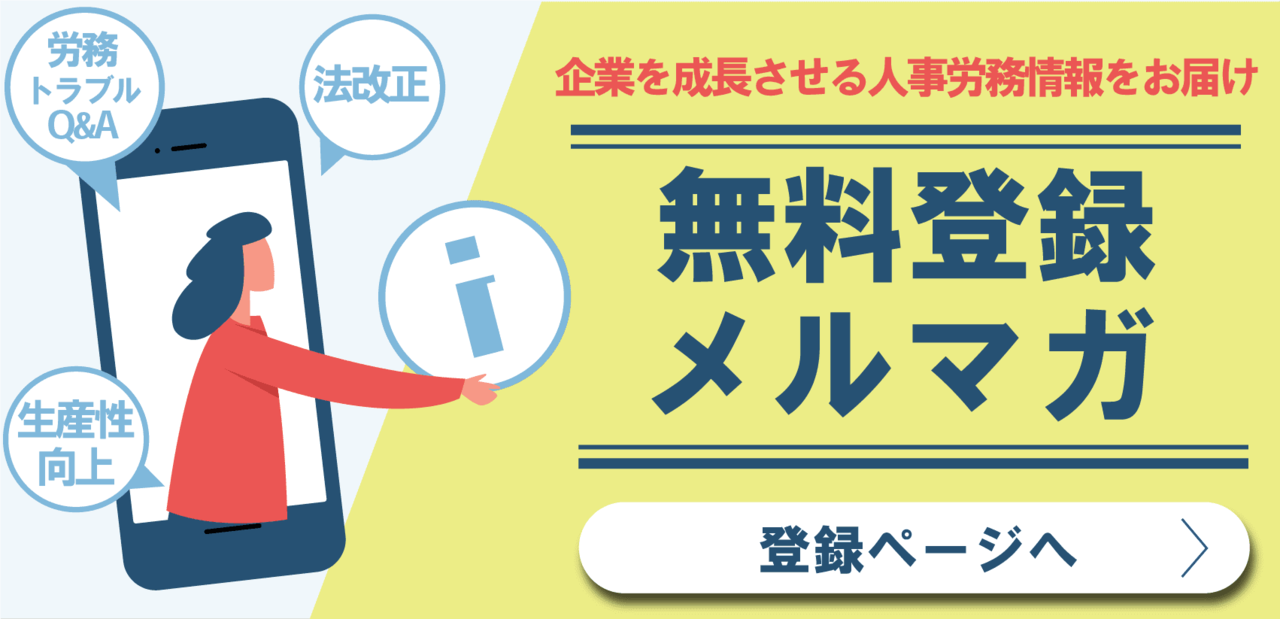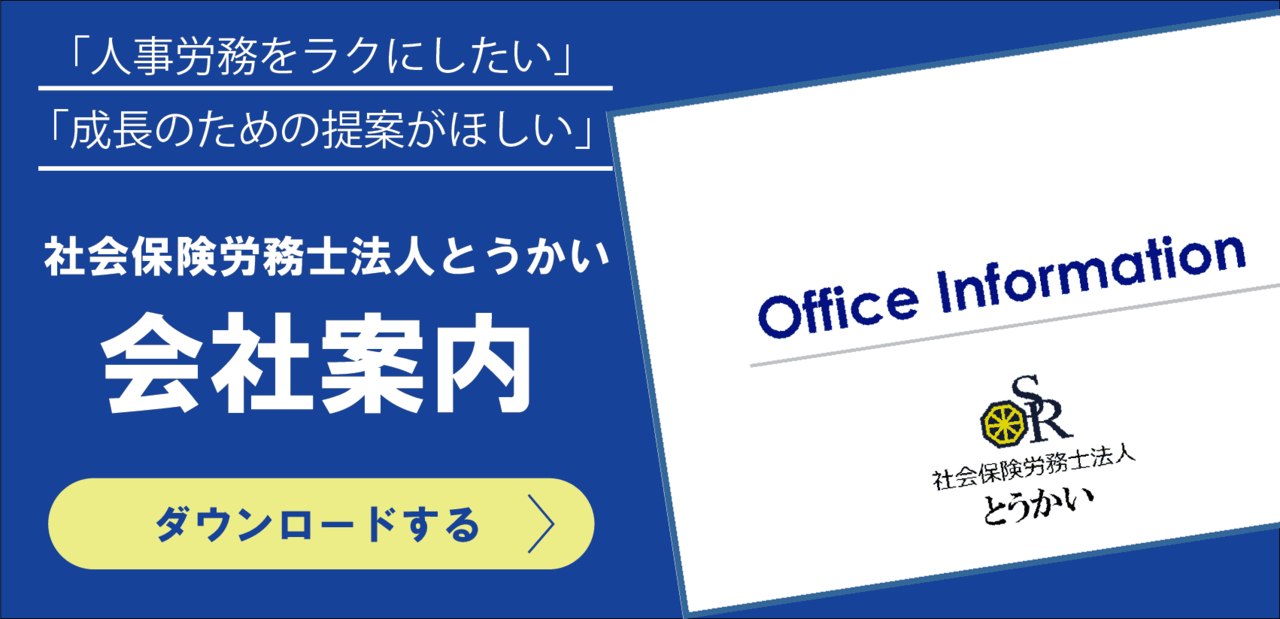年収103万の壁見直し“123万円に引き上げ” 2025年度税制改正大綱が決定

2025年度の税制改正大綱において、「年収103万円の壁」の見直しが正式に発表され、控除額が123万円に引き上げられることが決定しました。この新たな方針は、2024年12月の自民党と公明党の両党は、国民民主党の協議のもと決定されたものです。扶養控除を受ける家庭やパートタイムで働く人々の家計に直接的な恩恵をもたらすとの期待から、当初、国民民主党が求めた178万円への引き上げまでには至りませんでした。年収103万円の壁が長年にわたって課題とされてきた中、この改正により、多くの労働者が働き方の選択肢を拡大できる可能性があるのか、注目すべきニュースです。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

103万円の壁について解説します。
103万円の壁とは、働き控えなど勤務時間を調整したり、制限することを、“壁”として表現されています。所得税や住民税の観点から年収が103万円を超えると、扶養控除の対象から外れます。具体的には、配偶者や扶養家族の年収が103万円を超えると、所得税が課されるようになり、さらに住民税の負担も増加します。これにより、家庭全体の手取り収入が減少する可能性があるため、結果的に「103万円の壁」を気にする家庭が増えているのが現状です。
手取りの収入が減ることを心配して、多くの家庭で税金の負担を最小限に抑えるために、特にパートタイムやアルバイトで働く人たちにとって大きな影響を与えています。この影響で、多くの人々が働き方を制限せざるを得ない状況も見られます。たとえば、労働時間を減らしたり、収入を調整するためにパートタイムにとどめたりといった行動が取られることがあります。これにより、家庭の生活費や教育費などの支出が捻出しづらくなり、労働市場全体にも影響を及ぼしています。

高谷の経営視点のアドバイス
103万円の壁は、長らく扶養者である配偶者や学生に大きな影響があったものです。今回の123万円への引き上げは、減税効果としては大きな期待ができないとの声も多く聞かれます。今後も議論が続くことが予想され、来年の通常国会で、どのような結論が見られるのか、注目し続けるニュースです。

123万円へ引き上げ決定の背景についてご説明します。
年収の壁を103万円から123万円へ引き上げる決定に至った背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。まず日本における人材不足や女性の社会進出促進への対応策としての一面、加えて社会全体で生活費や子育てにかかる家計への経済的負担が増している現状があります。とくに、昨今の物価の上昇は、多くの家庭が生活の厳しさを感じる結果となっています。
日本社会が抱える課題の解決を狙って、年収の壁の議論が巻き起こりました。もともとは国民民主党が提起した178万円の壁を皮切りに、与党と野党の協議が続き、与党側も103万円からの引き上げに前向きな姿勢を示しました。12月の税制改正のタイミングで、年収の壁を引き上げる決定は、多くの家庭が直面している年収103万円の壁という制約を緩和する目的を持っています。この控除額の引き上げは、家庭内の負担を軽減し、幅広い層に経済的な余裕をもたらすことが期待されたものの、与党の決定は123万円であり、国民民主党の要求とは開きのある水準となりました。この改正が経済や労働市場にもたらす影響は見逃せません。控除額を上げることで、働く意欲を持つ人々の収入を支え、消費を促進させるのか、将来的な経済成長を見据えた重要な政策となるのか注目すべきところです。

控除額を上げることで、どのような影響が出るのでしょうか。
年収の壁が103万円から123万円に引き上げによって、多くの家庭への影響が期待されています。とくに扶養控除を受けている家庭では、生活費の負担が軽減され、経済的な余裕が生まれるのかが期待されます。低所得者層やパートタイムで働く労働者にとっても大きなメリットになると言われています。年収がこの控除枠に収まることで税負担が軽減し、より多くの収入を手元に残すことが可能になります。ただし、103万円から123万円への引き上げ効果は、大きな減税とまでは言えないとの試算もあり、経済全体の成長を促進し、好循環を生み出す、労働市場にもポジティブな効果をもたらすまでの効果があるのかは、不透明です。しかしながら、こうした年収の壁の議論、税制改正がどのような形で社会全体に影響を及ぼしていくのか、その経済的な波及効果にも注目が集まります。

引き上げ後の課題と今後の展望を見ていきましょう。
年収の壁が103万円から123万円に引き上げられたことで、多くの恩恵が期待されていますが、一方で新たな課題も見えてきています。例えば、引き上げ後も一定の収入の壁が存在しており、パートタイムで働く人々や扶養控除に依存している家庭は、依然として年収を意識せざるを得ない状況にあります。この壁を完全に解消することはできておらず、家庭の収入計画に影響を与えています。また、一部ではさらに引き上げを求める意見があり、収入制限の柔軟化が議論の焦点になることが想定されます。
さらに、年収の壁を超えた際に発生する税負担の増加も懸念されています。これにより、労働者が収入を意識的に抑える現象が続く可能性が指摘されています。特に、控除範囲を超えた場合の急激な負担の増加が労働意欲を損ない、社会全体での生産性の低下につながるリスクがあるため、より緩やかな調整が求められています。
今後の展望としては、制度のさらなる見直しや柔軟な改善が重要となるでしょう。特に、年収の範囲や制限の引き下げ、またはその見直しについて、政策的な意義を踏まえた議論がより深まる必要があります。将来的には収入制限の考え方をより緩和し、多様な働き方を支援する柔軟な制度づくりが求められるとの意見が主流になる可能性が高いと考えられます。このような取り組みにより、働く意欲を高める環境が整い、経済成長を促すきっかけが生まれることが期待されます。

大矢の経営視点のアドバイス
所得税に対する年収の壁以外にも、社会保険の壁も存在します。働くパート・アルバイトの方にとっては、所得税の年収の壁同様、重要な関心事でしょう。所得税の議論に終始せず、働く意欲を高める環境整備として、社会保険に関する議論も進めていかなければなりません。
年収の壁が123万円に控除額が引き上げられたばかりですが、さらなる引き上げの議論は続いていく見込みです。そもそも国民民主党の要求である178万円とは大きな開きがあり、税制大綱では178万円を目指して来年から引き上げることで合意されています。今後の議論次第では新たな政策提案が生まれる可能性があります。ただし、財源確保や税収をどうバランスさせるかも重要な課題として浮上しています。控除額の引き上げは、多くの家庭や個人にとって税負担の軽減につながるものの、一方で財政への影響を無視することはできません。今後の政策運営において、こうした課題に対処するための柔軟かつ公平な制度設計が求められるでしょう。政治的な議論を通じて、社会のニーズに応える形でのさらなる見直しが進む可能性があります。このような議論は、NHKを含めた各メディアでも取り上げられることが多く、国民の注目を集めています。
年収の壁の引き上げに伴い、税収が減少することで、財政面での影響がますます顕在化すると考えられます。とくに地方税の減収は、約4兆円に上るとされ公共サービスや社会保障の質を低下させる可能性があるとして、地方税収の減少も話題となりました。しかしながら、総務相試算によれば、地方税である住民税の減収は最大1000億円に留まり、当初の約4兆円より大きく圧縮された結果となっています。
一方、賃金への影響についても無視することはできません。労働市場における賃金水準の上昇が伴わない場合、政策本来の狙いが十分に達成されないリスクがあります。この点については、労働力の供給と需要のバランスを適切に保ちながら、政策を進行させることが重要です。特に1200万円以上の高所得層に対する控除額引き下げが議論される中、高所得者層の行動やマクロ経済への影響についても一層の分析が求められます。
年収の壁をテーマとして、税制の動向には税収、公共サービス、社会全体への影響といった多岐にわたる課題が伴います。今後、引き下げや引き上げに限らず、多岐にわたる変数を考慮した政策の調整が不可欠であり、全体的な経済状況や社会の変動に柔軟に対応する議論が成功の鍵を握るでしょう。

2025年度税制改正での注目ポイントを見ていきましょう。
2025年度の税制改正には、数々の注目ポイントが存在します。その中でも、「年収103万円の壁」の見直しが大きな話題となっています。この壁が123万円に引き上げられる予定です。この改正は、働く人々や扶養家族を抱える家庭にとって大きな経済的影響をもたらすと考えられています。これにより、パートタイムやアルバイトで働く人々の就労意欲が向上していくのかに期待と注目が集まっています。
さらに、住宅ローン減税や特定扶養控除の改正なども国民の関心事です。住宅購入や高校生などを扶養する親の負担の軽減といった支援の拡充は家計にとって、重要な制度の一つです。生活設計を見直し、より効率的な資産形成を進めるための材料となるでしょう。税制改正によるメリットを正しく把握するためにも、動向を注意深く確認することが重要です。
2025年度の税制改正において、住宅ローン減税や扶養控除の変更が注目を集めています。経済環境や生活様式の多様化に対応するため、これらの控除の見直しが家庭の経済状況に与える影響は大きく、特にその調整内容は、多くの家庭に直接関係してきます。
住宅ローン減税については、子育て世代などに対する優遇措置は、1年間の延長が盛り込まれています。初めて住宅を購入する人々を含め、住宅購入へのハードルを下げることが期待されています。住宅市場の活性化も期待され、経済全体への波及効果が見込まれます。
また、高校生などの扶養控除の見直しは、子どもを持つ家庭にとって重要です。例えば特定扶養控除の対象が上がることで、支援対象が増えるような政策が実施されれば、教育費や生活費の補助が強化される可能性があります。このような変更が家庭の安定や子どもたちの将来に寄与する形で作用することが期待され、生活の質向上にもつながるでしょう。今回の税制改正においては、結論が来年以降に先送りされました。
こうした税制の変更が家庭経済にどのように影響するのかをしっかりと検討し、今後の生活設計に役立てることが重要です。それぞれの改正点を十分に理解し、適切に備えることで家計への負担を軽減する可能性が高まります。
税制改正においては、各党の意見が大きな影響をもたらします。与党税制改正対抗においては、各党の方向性の違いも見られます。自民党や公明両党は、年収の壁を103万円から123万円に引き上げる税制措置を盛り込みましたが、国民民主党とは合意に至らず、来年度予算の成立に雲がかかった状態です。また、学生を含む幅広い層が恩恵を受けられる政策を進めるべきだとの指摘もあり、これが具体的な対策にどう反映されるか注目されています。
一方、野党側からは、さらなる負担軽減を求めていくでしょう。特に所得格差を縮小するための対策を強調する声が多いのが特徴です。また、NHK受信料の見直しや負担削減に関連する提案を通じて、市民生活全般の負担を軽減する動きも見られます。これに対して、少数与党としては、税収の確保と社会保障の安定性を維持するためのバランスを取る必要があるとされています。
税政策の方向性に関する議論は、県レベルでも重要であり、多くの市民や学生にとって関心の高い問題です。このため、今後の各党の対応や意見の違いが、どのように税制改正に影響を与えるのか注意深く観察することが求められます。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」