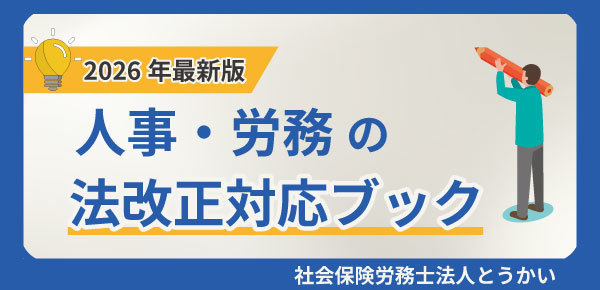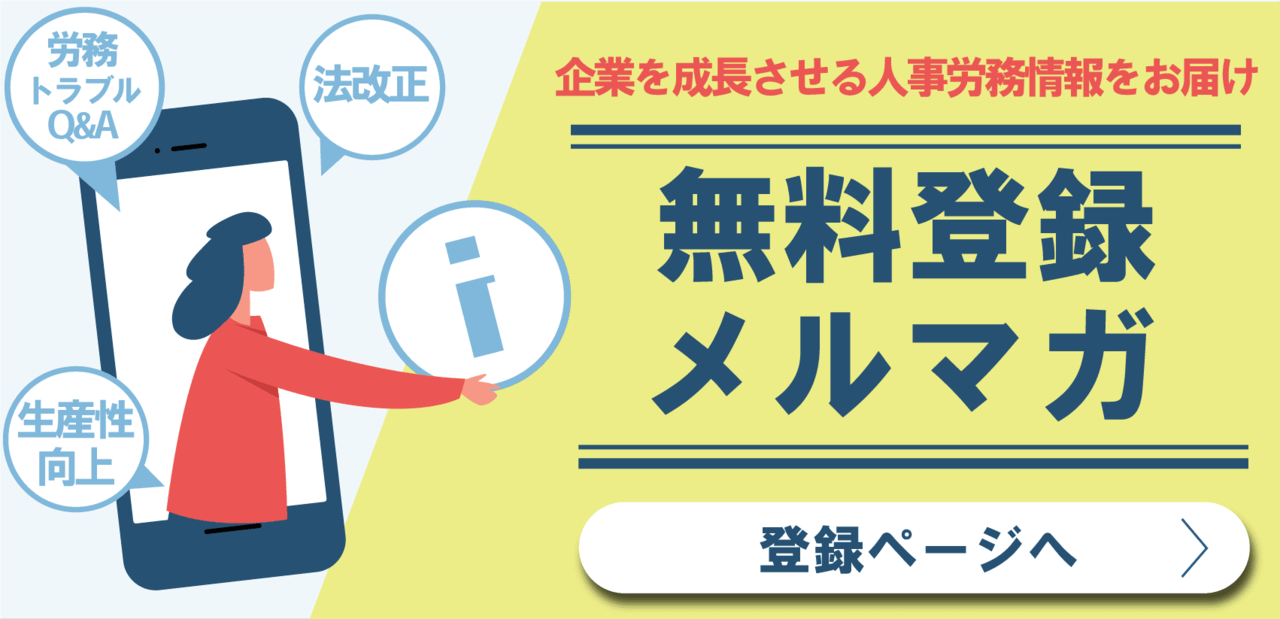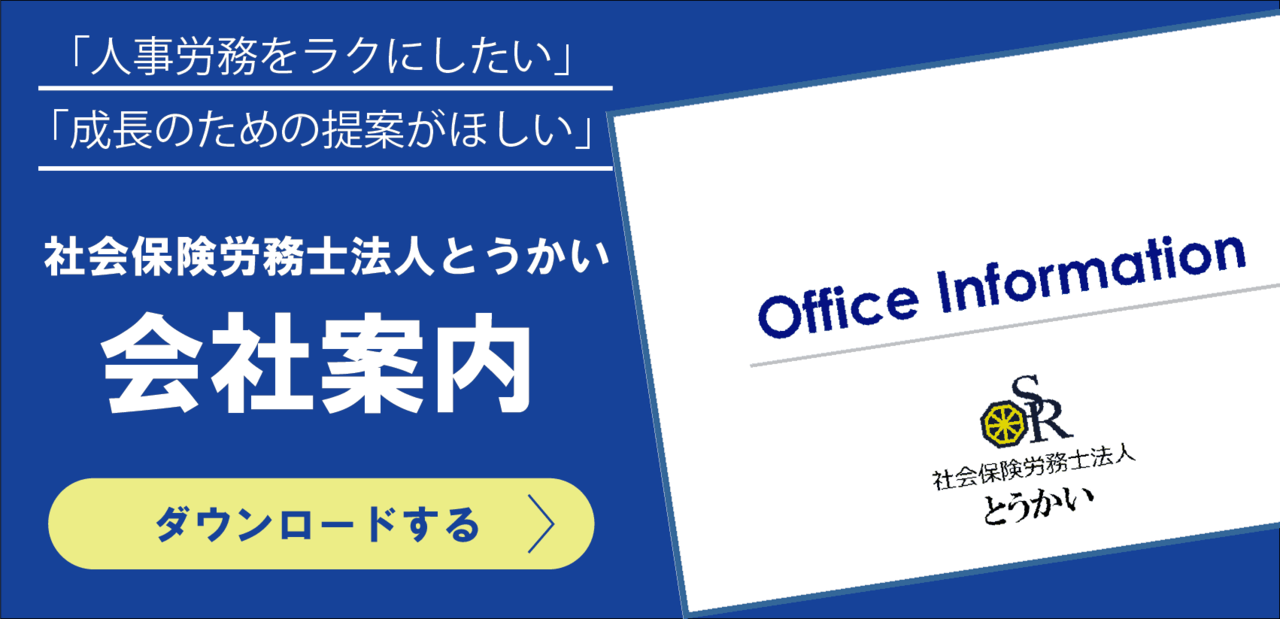【テンプレート付き】採用活動で欠かせない「内定通知書」とは?
その役割・注意点を徹底解説

企業が採用活動を進め、ようやく自社にマッチした人材に出会えたとき、必ず発行するのが「内定通知書」です。この書類は、企業と求職者双方にとって非常に重要な意味を持っています。単に採用の意思を伝えるだけでなく、今後の労働契約の前提となる内容を明記し、トラブルを防ぐ役割も担っています。
とはいえ、中小企業の人事担当者の中には「内定通知書って何をどこまで書くべき?」「内定承諾書とはどう違うの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。今回はそんな方に向けて、内定通知書の基礎知識から記載内容、注意点、法的効力、トラブル事例まで、幅広く解説していきます。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから


似た書面の違いについて解説します。
ここでよく混同されがちなのが「内定通知書」と「内定承諾書」の違いです。
内定通知書は企業側が発行する書類で、内定承諾書は求職者側が内定を承諾する意思を示して返送する書類です。つまり、通知と承諾という関係性にあります。
内定通知書を受け取った求職者が、内容を確認し問題がなければ、署名・捺印した内定承諾書を企業へ返送することで、採用に関する合意が成立する流れです。
この2つをしっかり区別せずに運用してしまうと、入社前のトラブルを招く可能性が高まります。例えば、内定通知書に「○月○日付で正式に採用する」と書いた場合、その時点で労働契約が成立したとみなされることもあるため、通知文面には細心の注意が必要です。
| 書類名 | 目的 | タイミング |
| 採用通知書 | 採用試験の合格を知らせる | 採用試験後、内定決定前 |
| 内定通知書 | 採用の意思を正式に通知する | 内定決定後、なるべく早く |
| 労働条件通知書 | 労働条件を正式に明記し通知する | 雇用契約締結時(法律上必須) |
それぞれ目的と役割が異なるため、混同せず、適切に用いることが重要です。
内定通知書は、単なる採用決定の連絡ではありません。文書として交付することで、企業と求職者の間で採用の条件や今後の予定を明確にし、認識のズレを防ぐ重要な役割を果たします。
採用活動では、面接の場でさまざまな条件提示や説明が行われますが、口頭だけのやり取りだと誤解が生まれることも少なくありません。例えば、「勤務地は名古屋」と口頭で伝えたつもりでも、求職者は「将来は東京勤務もあるかもしれない」と勝手に解釈しているケースもあるのです。
こうした行き違いを防ぐためにも、内定通知書には「勤務地」「労働条件」「入社予定日」「試用期間の有無と条件」などを明記し、事前にしっかり共有しておくことが大切です。

高谷の経営視点のアドバイス
採用競争が激しい現在、内定通知のスピードは採用成功の鍵です。条件の検討を終えたら、なるべく早く内定通知書を作成し、速やかに発送・説明を行うことをおすすめします。

内定通知書の法的効力についてです。
内定通知書は、労働契約成立の前段階ではありますが、その内容や表現によっては法的効力を持つ場合があります。実際、過去の判例でも「企業が内定を通知し、求職者が承諾した時点で労働契約が成立した」と認められた事例があります。
仮に求職者が内定通知書を受け取り、内定承諾書を提出した後に、企業側が一方的に内定を取り消した場合、不当解雇にあたる可能性もあります。この場合、企業側には損害賠償責任が発生することもあるため、「内定の取消しはやむを得ない場合のみ」と慎重に運用することが重要です。
特に以下のような理由による内定取消しは、基本的に認められないと考えられています。
● 経営状況の悪化による採用計画の見直し
● 社内事情による採用枠の削減
●社長や役員の方針変更
一方で、以下のような場合には内定取消しが認められることもあります。
● 健康状態に重大な問題が判明した場合
● 経歴詐称が発覚した場合
●犯罪行為など社会的信用を著しく損なう行為があった場合
いずれにしても、内定通知書の内容次第でトラブルの発生リスクは大きく変わるため、記載内容は非常に重要です。

大矢の経営視点のアドバイス
内定取り消しの事由は、なるべく具体的に記載しておくことが重要です。曖昧にすると、取り消し時の正当性が問われる恐れがあります。また、労働条件もなるべく具体的に記載し、労基法違反にならない内容で整えておくことが大切です。
実務上、内定通知書に関するトラブルも少なくありません。例えば、内定通知書に「正式採用とする」と明記してしまい、内定承諾後に取り消しができなくなったケース。企業側の一方的な都合で取り消そうとしたところ、求職者から訴えられ、裁判で不当解雇と認定された事例もあります。
また、「労働条件について面接時の説明と通知書の内容が違う」というトラブルもよくあります。給与額や勤務地、残業の有無など、些細なズレでも求職者の信頼を損ね、採用辞退やトラブルの原因になりかねません。
このような問題を防ぐためにも、内定通知書の文言は法的な観点からも慎重に作成することが重要です。可能であれば社労士や弁護士など、労務・法律の専門家のチェックを受けることをおすすめします。

小栗の経営視点のアドバイス
内定取り消しの判断は、労働法の観点から非常にデリケートです。内定取り消しを検討する場合は、必ず社労士や弁護士など専門家に相談し、客観的な証拠と合理的理由を揃えたうえで進めましょう。

規程を作成する際のご相談はお任せください。
内定通知書は、採用活動における大切な書類です。単に「採用が決まったことを伝えるためのもの」ではなく、求職者との間で労働条件や今後の流れを明確にし、双方の安心と信頼を築く役割を担っています。
作成にあたっては、曖昧な表現や誤解を招く表現を避け、記載内容の正確性と法的リスクの回避を意識することが重要です。特に、内定取り消しや労働条件の説明不足によるトラブルは、企業イメージの悪化にも直結します。
企業の採用力を高め、良い人材とのご縁をしっかり繋げていくためにも、内定通知書の作成と運用を丁寧に行うことが、今後ますます重要になっていくでしょう。


最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」