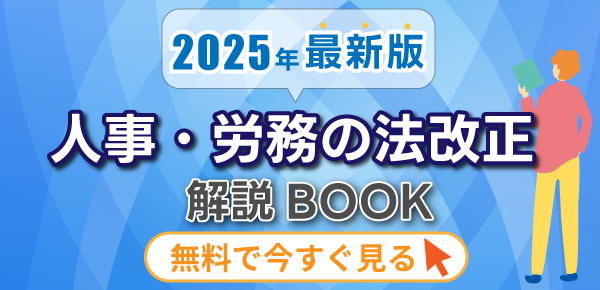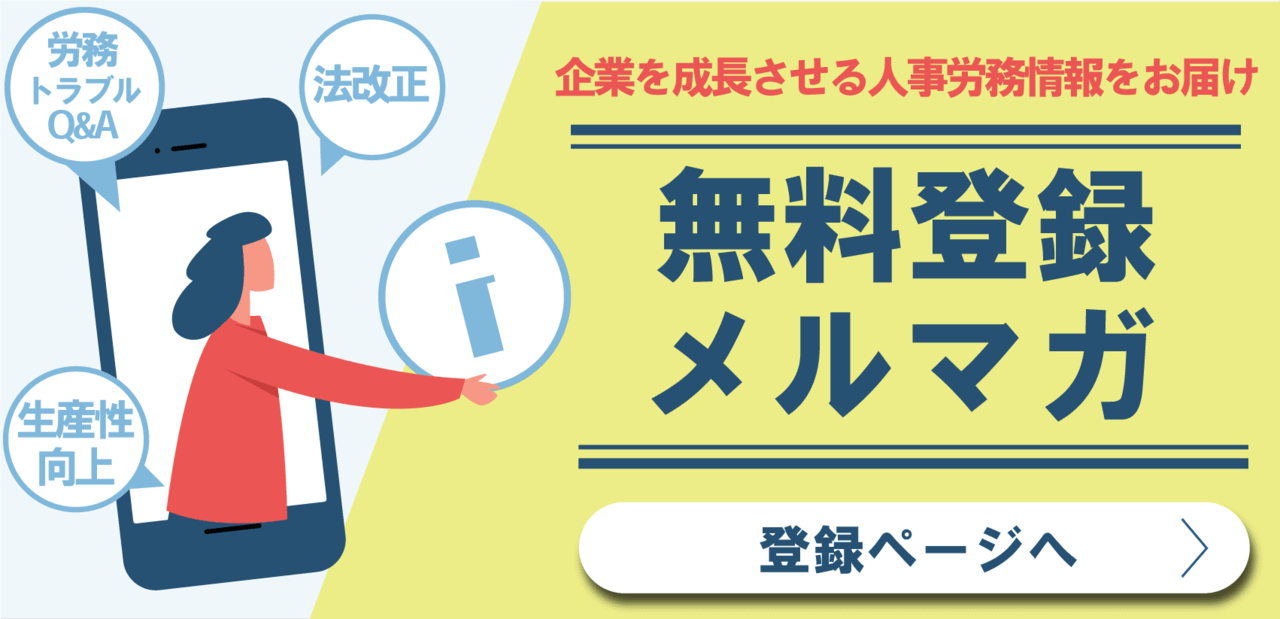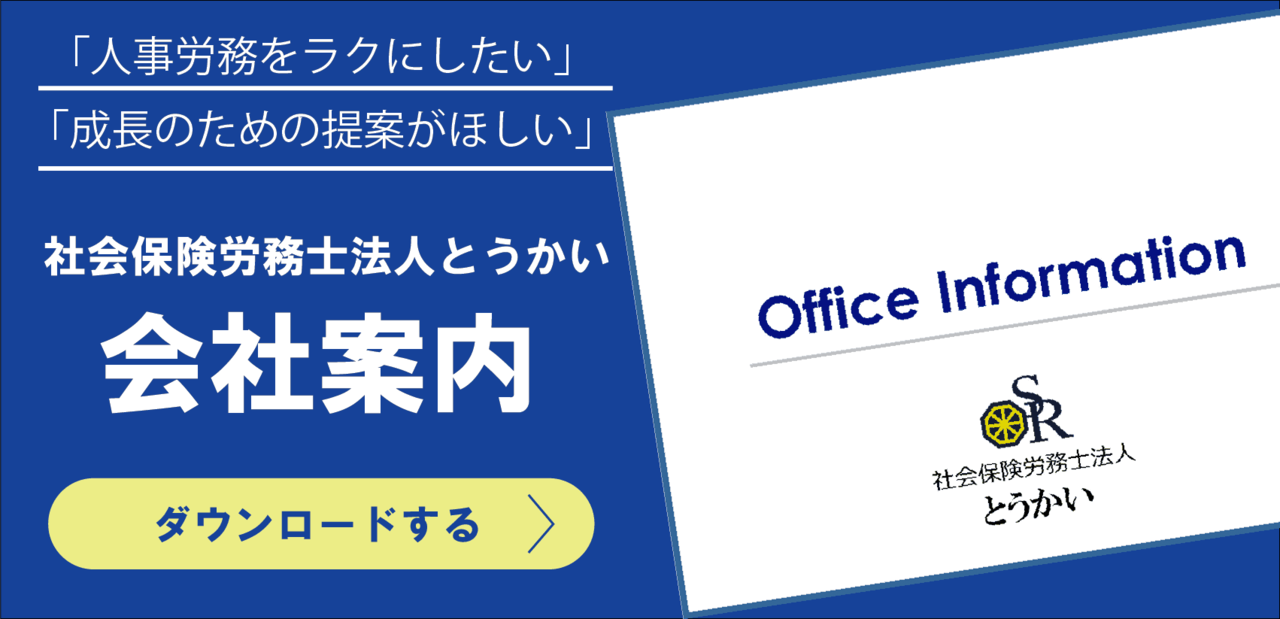従業員の遅刻・早退時の給与は? 給与控除額の計算方法について

従業員が遅刻や早退をしたときの給与控除計算方法にはいくつかのポイントがあります。まず第一には遅刻や早退の時間を正確に把握することが重要です。続いて、一般的には控除額の計算の基となる時間単価を算出し、遅刻や早退の時間を掛け合わせて控除額を計算することになります。控除の計算方法は、労働基準法に基づく適正な方法で行わなくてはなりません。それには正確な労働時間の管理が大切で、遅刻・早退時間に対して過度な控除が発生しないよう注意が必要です。誤った控除額の計算は、従業員との不要なトラブルにも発展するリスクがあります。従業員に対する説明や理解を得ることも実務上重要なプロセスです。給与計算の透明性を保つことで従業員の信頼を維持し、トラブルを回避するために、正しい給与控除額の計算方法を理解しておきましょう。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

遅刻・早退控除の基本概要を確認していきましょう。
遅刻や早退が発生した際に、従業員の給与からその時間に相当する金額を控除することが遅刻・早退控除です。働いていない分の給与は支払わないという考えに基づき、遅刻や早退をすれば、その分の給与は支払わなくてもよいということです。
経営者や人事労務担当者は、遅刻や早退が発生すれば、正確な給与控除計算を行うことが不可欠です。また従業員の遅刻や早退が頻繁な場合には、勤務態度や仕事の進捗に大きな影響を与える可能性があるため、適切な労務管理も重要でしょう。
ノーワーク・ノーペイの原則とは、働かなければ賃金を支払わないという基本的な考え方で、労働契約法第6条や民法第624条に基づいたものです。会社にとっては労働を提供しなかった時間に対する賃金支払義務が免除されます。これが遅刻や早退にも適用され、具体的には、遅刻や早退で実労働時間が所定労働時間に満たない場合、その不足分を給与から控除することができます。経営者や労務・人事担当者は、この原則を理解し、適切な給与計算方法を実務で確実に実行することが重要です。ただし、会社は就業規則や労働契約書で遅刻や早退の際の給与控除に関する規定を明示しておく必要があります。
労働契約書や就業規則で定められた労働時間を守ることは、企業と従業員の双方にとって重要な責務です。遅刻・早退控除の給与計算は、この所定の労働時間に基づいて行われます。この遅刻・早退時間分を超えての控除は認められません。企業の経費管理の観点からも、遅刻・早退控除は必要です。正確な勤務時間の把握により、企業の運営コストを適切に管理することが可能となります。さらに、遅刻や早退を行った社員に対して、規律を促す効果も期待できます。これにより、全体の業務効率を向上させることができます
一方で、従業員の勤怠状況が著しく不良で、労働契約書や就業規則に違反した場合などについては、ペナルティとして減給の懲戒処分を課すこともあります。ただし、これは遅刻・早退に対する給与控除ではなく、あくまで懲戒処分になります。減給の懲戒処分を課す場合には、就業規則等に減給の制裁を定める場合の規定をしっかりと明記しておくことも忘れてはなりません。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
ノーワークノーペイは法律に基づいた考え方です。ただし、遅刻や早退の控除に関する給与計算方法自体については、法律に定められてはいません。必ず会社の就業規則等で明確にして、従業員への周知や理解を得ておきましょう。

遅刻・早退控除の計算方法を解説します。
遅刻・早退控除の適切な給与計算を行うためには、明確な計算方法を設定する必要があります。就業規則にこれらの計算方法を明記し、従業員全体に理解させることも欠かせません。給与計算の透明性を保つことで従業員の信頼を維持し、トラブルを回避できます。
具体的には、遅刻や早退した時間に該当する分の控除額を算出することになります。計算にあたっての注意すべきポイントを確認していきましょう
遅刻や早退による控除額は、以下の計算式で算出することが一般的です。
遅刻・早退控除額 =基本給 ÷ 月の所定労働時間 × 遅刻・早退時間
基本給は、1か月あたりに支払う給与額です。企業によって、この月給与の範囲は、本給のみとする場合や、役職手当などを含めた月次の給与とするかなど、異なってくるでしょう。そのためにも、遅刻・早退控除を計算するための月給の定義を就業規則等に明記しておく必要があるのです。
また、月の所定労働時間とは、労働契約や就業規則等で定めたその月の勤務時間を意味します。
例えば、月給が30万円、月の所定労働時間が160時間の従業員が、10分の遅刻をした場合の控除額の計算例を確認しましょう。
遅刻控除額 = 30万円 ÷ 160時間 × 0.167(10分)=313円
つまり、この313円を給与から差し引くことになります。
遅刻・早退控除額を計算する際には、1分単位で計算しなくてはなりません。例えば、8分の遅刻をした場合に、10分単位に切り上げて、計算することなどはできません。過剰に控除してしまうことになり、労基法違反ともなりますので注意しましょう。給与計算にあたっては、労働時間を一律で切り捨てるなどの処理は、労働者にとって不利益な扱いになりますので、できません。
1分単位で計算するためには、従業員の勤怠を正確に記録し、適切な給与管理体制を整えることが重要です。それが労使双方の信頼関係を築くことにつながります。

小栗の経営視点のアドバイス
遅刻や早退をした際の給与計算には、1分単位で計算するといった原則の他にも、計算結果の端数切り上げなど端数処理にもルールがあります。自社の控除計算方法がルールに違反していないかなどご不安がある場合には、お気軽に社労士にご相談ください。

従業員の勤怠の注意点と管理方法を解説します。
従業員の遅刻・早退に伴う給与計算方法は、企業の労務管理において非常に重要です。それには労働基準法をはじめとした関連法令に基づき、適切な勤怠管理と給与計算方法を導入することで、労使間のトラブルを未然に防げます。
具体的には、遅刻・早退の記録を正確に管理し、そのデータを基に給与を計算することが重要です。例えば、タイムカードの精査や労働時間の勤怠管理システムの導入をにより、計算ミスを防ぐことも可能です。
労務担当者や人事担当者は、これらの実務上の注意点をしっかりと理解し、適切な管理方法を確立することで、企業全体の労務管理がスムーズに行えるでしょう。
遅刻・早退控除は、原則、基本給を対象として行われます。役職手当などを含む月給を基礎とする場合には、その旨を就業規則等に定めておくべきでしょう。住宅手当や通勤手当などの諸手当は、勤務実態に大きな影響がない限り控除の対象とならないことが一般的です。ただし、労使間で異なる合意がなされている場合、その合意に基づく就業規則に従うことが必要です。この際、就業規則は法令に矛盾しない範囲で行われることが求められます。労務担当者や人事担当者は、給与計算時にこれらの法律的根拠や実務上の注意点を正確に把握することが重要です。
遅刻・早退が生じても、給与形態によっては控除できないケースもあります。従業員の給与形態が完全月給制や年俸制である場合、遅刻や早退による給与控除がされません。完全月給制では、一定の給与額をあらかじめ定めていますし、年俸制においても年間の総支給額が固定されているため、遅刻・早退による控除はされません。こうした場合には、給与計算における法律的根拠や実務上の注意点を把握しつつ、就業規則や労働契約で具体的かつ明確に定義することが重要です。
フレックスタイム制は、総労働時間を満たしていれば遅刻・早退の控除は発生しません。フレックスタイム制の特徴でもあり、コアタイムに遅刻や早退をしても、総労働時間を満たしていれば、給与計算において遅刻・早退の控除を考慮しないことが一般的です。ただし、総労働時間を満たしていなければ、直接影響を与えるため、その満たしていない分は適切に控除する必要があります。
従業員が遅刻・早退を繰り返すなど勤怠の状況が悪い場合には、懲戒といったペナルティを課すことは可能です。ただし、労働基準法第91条では、違反行為に対する減給の制裁が厳格に定められています。具体的には、減給の制裁は1日分の平均賃金の半額を超えてはならない、減給総額が一賃金支払い期間における賃金の1/10を超えてはならないという制約があります。
労働基準法に基づいた給与計算方法を理解し、就業規則にその詳細を明記することが必要です。さらに、従業員に対してもこの規則を周知徹底することが求められます。これにより、遅刻早退控除の実務が法律に抵触することなく適切に運営できるでしょう。
遅刻・早退による控除分を、残業時間で相殺することはできません。変形労働時間制を導入していたり、遅刻・早退した日の労働時間が8時間を超えないケースでは、従業員との合意があれば、相殺が可能な場合もありますが、原則は相殺禁止です。
労働時間は独立した概念であるため、遅刻・早退による控除と残業時間は別々に扱う必要があります。そのため、遅刻早退控除の給与計算方法を厳守し、法的根拠に基づいた適切な管理が不可欠です。
時短勤務が導入されている従業員に対しては、契約上の労働時間に基づいて給与計算を行う必要があります。例えば、1日6時間の時短勤務が設定されている従業員が早退した場合、その早退分の時間を基本給から控除することが求められます。

高谷の経営視点のアドバイス
時短勤務の場合には、そもそも会社所定の労働時間を短縮する取り扱いとなりますので、減額した基本給を設定するのか、基本給は時短勤務前を変わらず、短縮した時間分を控除するのかによっても、給与計算の方法が異なります。時短勤務者が発生する際には、基本給、手当などの計算方法がどのように変わるのか、遅刻や早退をした場合の控除計算などについても、しっかりと従業員に説明しておく必要があるでしょう。

本記事では、遅刻・早退に関する給与計算の注意点、計算方法などについて詳細に解説しました。適切な給与計算は、従業員と企業双方にとって信頼関係を築く重要な要素です。適切な対応をすることで、労務管理のトラブルを未然に防ぎ、働きやすい職場環境を作る一助となるはずです。
とうかいでは、従業員の勤怠管理や給与計算でお悩みの経営者、人事労務担当者のみなさまに、わかりやすいアドバイスを行なっています。遅刻・早退などの給与計算は、考え方の誤解やミスが多く発生しやすいこともありますので、自社の給与計算などにご不安がある場合には、ぜひご相談ください。
この記事が、給与計算や労務管理において皆様のお役に立つことを願っています。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」