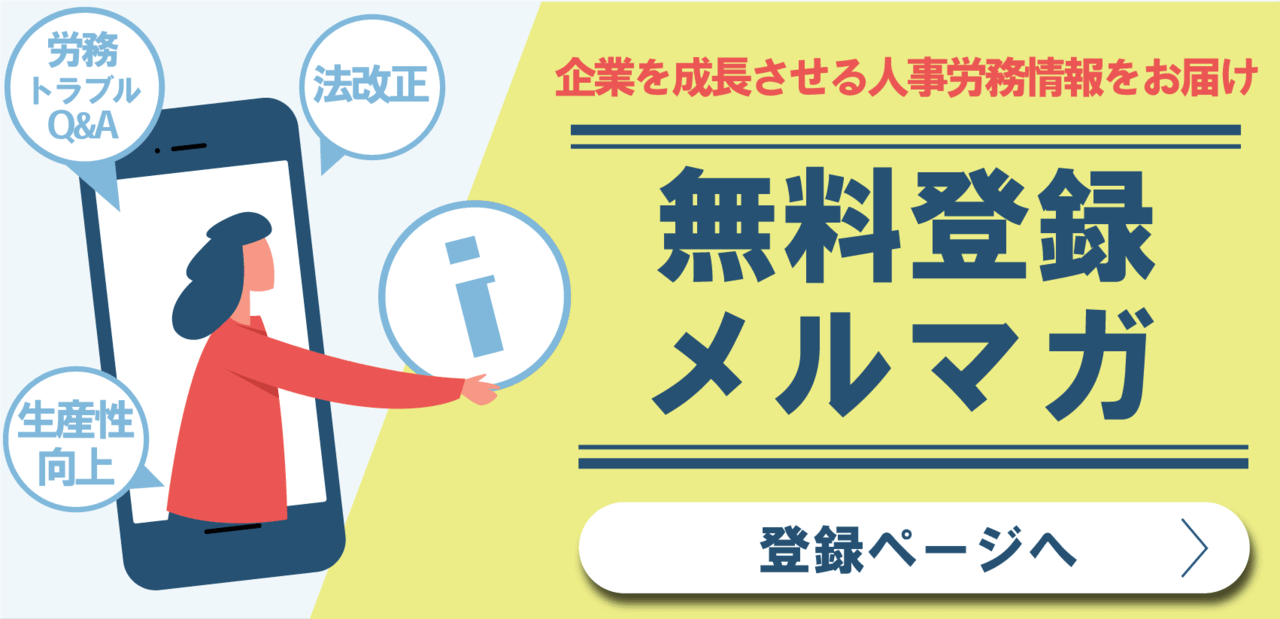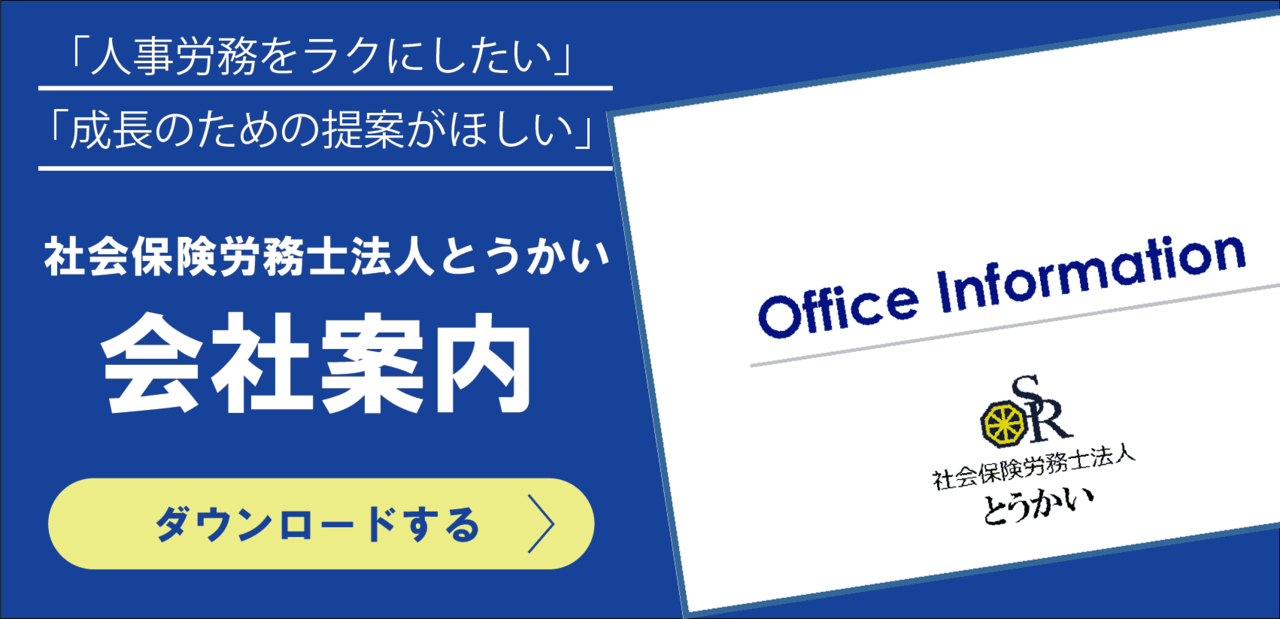給与計算の端数処理の方法は?注意すべきポイントもあわせて解説!


今回は、給与計算の端数処理の方法について、詳しく解説します。
給与計算は、企業の人事や経理担当者にとって重要な業務であり、法的な観点と会社の就業規則や給与規程を正確に理解することが必要です。なかでも、計算時に発生する1円未満の端数の処理方法まで理解しておく必要があることをご存知でしょうか?
端数処理の方法が給与総額にどのように影響するか、その方法が従業員にメリットをもたらすか、反対に不利益をもたらすかなど、どのような端数処理方法を選択するかを理解しておかなければなりません。適切な方法を選び透明性を持って処理することで、従業員との信頼関係を損なうことなく業務を進めることになるでしょう。今回は、給与計算の端数処理の方法について、詳しく解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

端数処理と労働基準法について解説します。
給与計算時の端数処理は、労基法を遵守する、そして会社の就業規則や給与規程に沿った処理をする上で欠かせない要素です。給与計算を行う際は必ず端数が発生するもので、その処理を適切に処理する必要があります。従業員の給与に関するものですから、1円未満であっても一定のルールに基づいて計算する必要があるのです。そのうえで、端数処理への理解は欠かせません。
具体的には、計算結果に対し「切り捨て」「切り上げ」などといった端数処理を行うことになりますが、どのタイミングで端数をどのように扱うかを労基法や会社の就業規則等に沿って行うことになります。ただし、原則として企業に都合のより処理ではなく、従業員が不利益を被らないよう処理を行うこととなります。どの方法を採用するかは事前に就業規則や給与規程に明記することが望ましいです。適切に規定することで従業員からの信頼を確保し、法令遵守にも努めることができます。端数処理の基準を設定し、継続的に見直すことが給与計算の精度を高め、企業運営の正確性を保つためには必要です。
労働基準法は給与計算で生じる端数処理のルールを定めており、これに従うことは企業にとって重要です。端数処理については、給与金額に対する処理と、労働時間に対する処理など、いくつかの種類、端数処理を実施するタイミングがあります。まずは給与計算を開始するタイミングで理解しておきたいのが、労働時間計算時の端数処理方法です。
労働時間は1分単位で計算されますが、残業時間を1か月の合計時間として計算する際、労働時間に1時間未満の端数が生じた際には、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることが認められています。ここで注意したいのは、1か月の合計時間に対して波数処理が可能という点です。1日単位の時間の端数処理ではありません。例えば、1日に2時間18分の残業を行なった場合に、18分を切り捨て可能ということではありません。月の残業時間の合計が20時間14分だった場合には、端数である14分の切り捨てが可能になるというわけです。
ただし、労基法で認められていますが、労働者の権利を尊重するために従業員に利益になるような端数処理を採用する企業も増えています。人事部や経理部の皆様は正確かつ公平な給与計算を実施するため、これらの基準をしっかりと把握し適切に処理することが求められます。
給与の端数処理は、法律に基づき処理するのが原則です。労基法上で認められている端数処理は、
・割増賃金
① 1時間あたりの賃金および割増賃金に円未満の端数が生じた場合、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げ。
② 1か月間の割増賃金の総額に1円未満が生じた場合、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げ。
・平均賃金の計算
賃金総額を総暦日数で除した場合、銭未満は切り捨て
・1か月の賃金計算
① 1か月の賃金に100円未満の端数が生じた場合は、50円未満の端数切り捨て、50円以上切り上げ
② 1か月の賃金に1000円未満の端数がある場合、端数を翌月の賃金支払日に繰越が可能。
労働基準法をはじめとする規制では、明確な端数の取り扱いが定められており、通常は切り捨てられます。しかし、実際の運用では従業員の権利保護を理由に、就業規則や給与規程で、労基法を下回らない、かつ従業員にメリットのある選択する企業も少なくありません。また、労働契約や給与規定に特定の処理方法が記載されている場合は、それに従う必要があります。人事部や経理部の担当者は、これらの法的要件及び企業内規則を熟知し、適切な端数処理を実施することが求められます。
欠勤控除における端数処理は法的な観点から細心の注意を払う必要があります。欠勤控除の端数処理は、原則、「切り捨て」を用います。欠勤控除を計算する際には、給与の日割り計算を行い給与日額を算出することになりますが、その際に端数を「切り上げ」てしまうと、従業員が不利益を被る可能性があるからです。企業は透明性を保ちながらこの処理を行い、労働者からの信頼を損なわないよう努める必要があります。具体的には、給与計算の方法を明確にし、適切な説明責任を果たすことが不可欠です。

鶴見の経営視点のアドバイス
従業員への給与は、労働時間に対して全額支払うのが鉄則です。小数点以下の端数であっても、従業員が不利になるような計算は認められていません。自社の給与計算における端数処理について、今一度確認しておきましょう。

給与計算での端数処理タイミングと計算方法を説明します。
給与計算を行う際、端数処理は避けて通れない重要なステップです。この処理を適切に行うことで、正確かつ公正な給与支払いが保証されます。ただし、給与計算時の端数処理は、処理を行うべきタイミングについての理解が必要です。適切なタイミングで処理を行わなければ、従業員が不利益を被ることになりかねませんので、注意しましょう。
給与計算で端数処理が発生するケースの多くが、残業代を計算するときです。端数処理として適用される方法は、企業ごとに設定された就業規則や給与規定によって異なりますので、まずは会社のルールを理解しておきましょう。そのうえで、残業代を計算するときの端数処理のタイミングを確認します。どのタイミングで端数処理を行うのかを明確にしておくことになりますが、1時間単価を計算するとき、次に割増単価を計算するとき、そして最終的に月の残業代を計算するときがタイミングとなります。
これは法的に定められた端数処理を下回る処理でなければ、各企業のポリシーに基づいて選択可能です。したがって、人事部や経理部の担当者は、自社の規定を確認し、適切な端数処理方法を選択することが求められます。正確な給与処理を行うことは従業員への信頼を保つためにも極めて重要です。
具体的な計算例を用いて、端数処理の理解を深めましょう。
例)月給250,000円(1日の所定労働時間7時間30分、1か月平均所定労働日数22日)の従業員が月12時間の残業をした場合
①1か月あたりの平均所定労働時間を算出する
7時間30分 × 22日 = 165時間
② 1時間あたりの賃金単価を算出する
月給250,000円 ÷ 165時間 = 1,515.151円
50銭未満の端数を切り捨て 1,515円
③ 1時間あたりの残業単価(25%割増)を算出する
1,515円 × 1.25 = 1,893.750円
50銭未満の端数を切り上げ 1,894円
④ 12時間分の残業手当を算出する
1,894円 × 12時間 = 22,728円
これらの計算を理解し、法規制に則った適切な端数処理方法を選択する必要があります。この方法によって従業員への支払いが適切に管理され、企業の信頼性が保たれます。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
従業員への給与は、労働時間に対して全額支払うのが鉄則です。小数点以下の端数であっても、従業員が不利になるような計算は認められていません。自社の給与計算における端数処理について、今一度確認しておきましょう。
よくあるご質問
ここではよくあるご質問をご紹介します。
給与計算における「端数処理」とは何ですか?
給与計算の過程で発生する1円未満の数値(端数)を、法律や会社の規定に従って「切り捨て」や「切り上げ」などで処理することです。
給与計算では、時給単価の算出や残業代の計算などで、1円未満の細かな数値が発生します。労働基準法では、従業員が不利益を被らないよう、特定の計算項目について端数処理のルールが定められています。企業は、この労基法のルールを下回らない範囲で、就業規則や給与規程に沿った適切な処理を行う必要があります。
労働基準法で認められている、給与計算の端数処理の主なルールは何ですか?
割増賃金や平均賃金、1か月の賃金総額について、特定のタイミングで「50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ」などの処理が認められています。
労働基準法で認められている主な端数処理のルールは以下の通りです。
-
割増賃金(1時間あたり):円未満の端数について、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げ。
-
割増賃金(1か月の総額):1円未満の端数について、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げ。
-
平均賃金:銭未満は切り捨て。
-
1か月の賃金:
-
100円未満の端数が生じた場合、50円未満は切り捨て、50円以上は切り上げ。
-
1000円未満の端数がある場合、翌月の賃金支払日に繰越が可能。
-
【企業の担当者が必要な対応】 これらの処理は、労基法上の特例として認められているものです。企業の担当者は、自社の就業規則や給与規程にこれらの処理方法を明記し、全従業員に透明性を持って適用する必要があります。
労働時間の計算における端数処理のルールはどうなっていますか?
労働時間は原則1分単位で計算しますが、残業時間など1か月の合計時間として計算する際に限り、「30分未満切り捨て、30分以上1時間に切り上げ」が認められています。
労働時間の計算では、1日単位ではなく、1か月の合計時間に対してのみ端数処理が認められています。例えば、1か月の残業時間の合計が20時間14分だった場合、14分(30分未満)は切り捨てが可能です。逆に、20時間35分だった場合は、35分(30分以上)は1時間に切り上げて21時間として処理できます。ただし、これはあくまで例外的な措置であり、従業員の不利益にならないよう、1分単位で計算する企業も増えています。
残業代を計算する際の端数処理は、どのタイミングで行うのが適切ですか?
残業代の計算は、主に「1時間あたりの賃金単価」「割増単価」「月の残業代総額」を算出する3つのタイミングで端数処理が発生する可能性があります。
残業代の計算は、以下のステップで端数処理のタイミングがあります。
-
1時間あたりの賃金単価を算出する時:月給を月平均所定労働時間で割った単価の円未満の処理。
-
1時間あたりの割増単価を算出する時:賃金単価に割増率(例:1.25)をかけた後の円未満の処理。
-
1か月の残業手当の総額を算出する時:最終的な残業手当総額の1円未満の処理。
【企業の担当者が必要な対応】 どのタイミングでどのような端数処理を行うかは、就業規則や給与規程で明確に定めておく必要があります。また、計算処理は必ず従業員が不利益を被らない方法を選択し、一貫性を保って運用することが、従業員からの信頼を確保するために重要です。
欠勤控除をする際の端数処理で、特に注意すべきことはありますか?
欠勤控除の端数処理は、従業員が不利益を被るのを避けるため、原則として「切り捨て」を用いる必要があります。
欠勤控除は、給与から控除(差し引く)処理であるため、日割り計算などで発生した端数を「切り上げ」てしまうと、控除額が増えて従業員が本来もらうべき給与額が減る(不利益を被る)ことになります。労働基準法の「賃金の全額払い」の原則からも、従業員の不利益になるような計算は認められていません。そのため、欠勤控除においては、端数は原則「切り捨て」で処理します。
端数処理の方法が、従業員との信頼関係に影響するのはなぜですか?
給与計算は従業員の生活に関わるため、端数処理であっても不透明な処理や従業員に不利益となる処理を行うと、企業への不信感につながるからです。
給与は、従業員にとって最も重要な労働の対価です。1円未満の端数であっても、それが「切り捨て」によって常に企業側に有利になるように処理されていると、従業員は不公正さを感じやすくなります。企業は、労働基準法を遵守することはもちろん、従業員の権利を尊重し、端数処理の方法を就業規則や給与規程に明記するなど、透明性を持って運用することが、信頼関係を維持するために不可欠です。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」