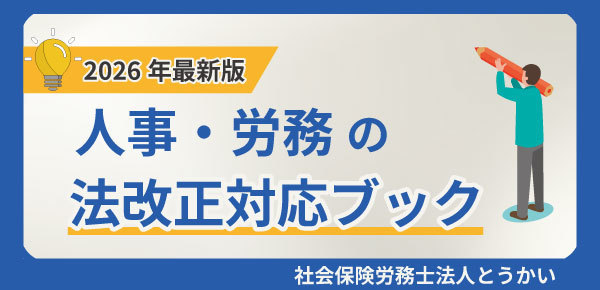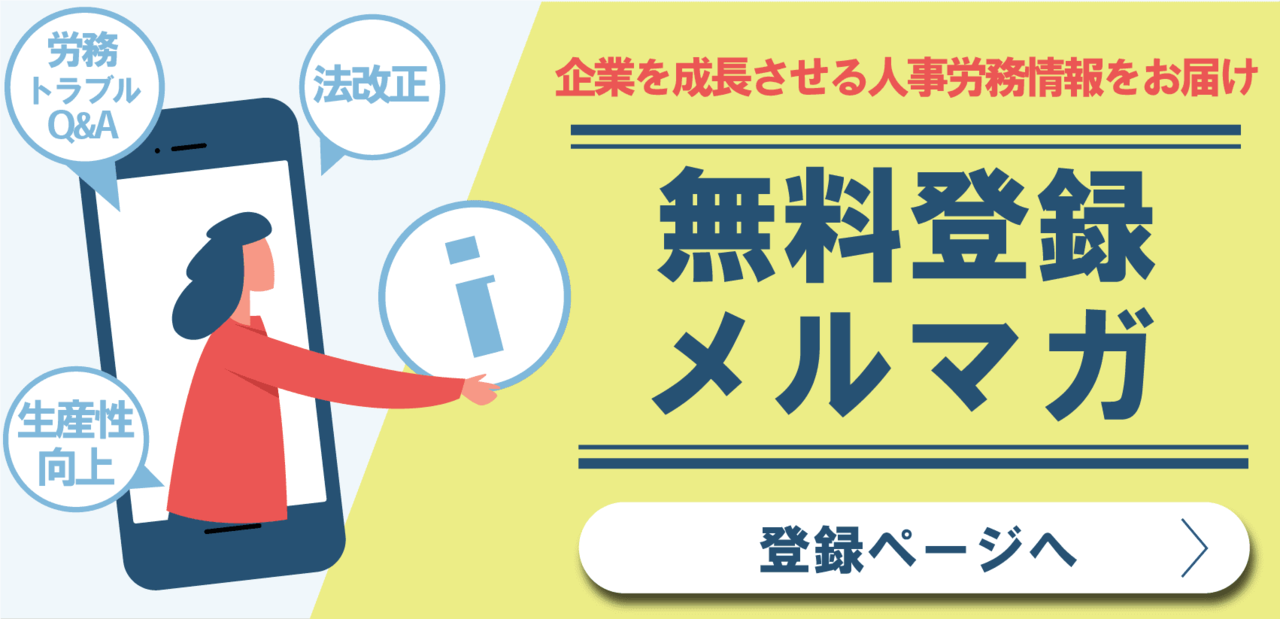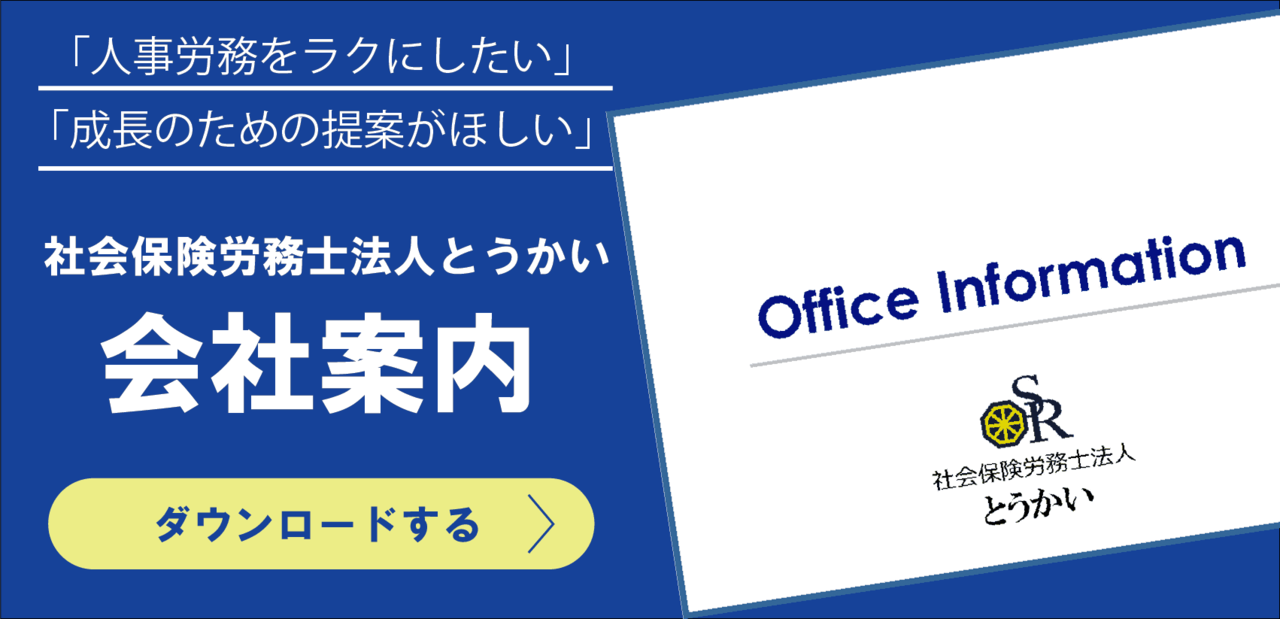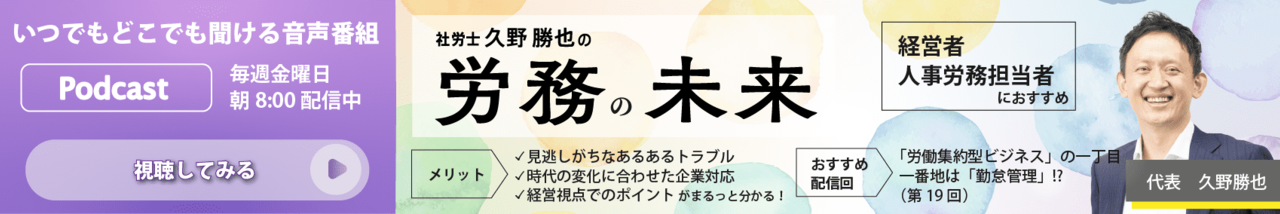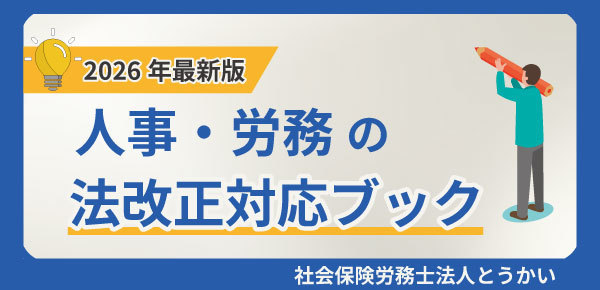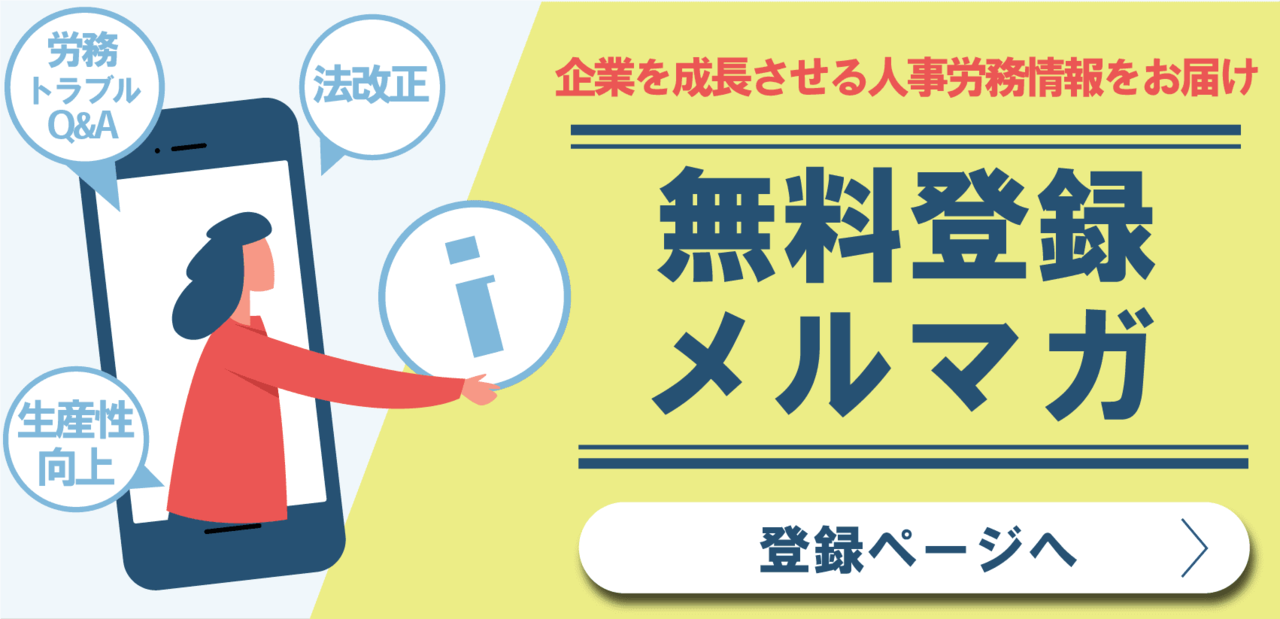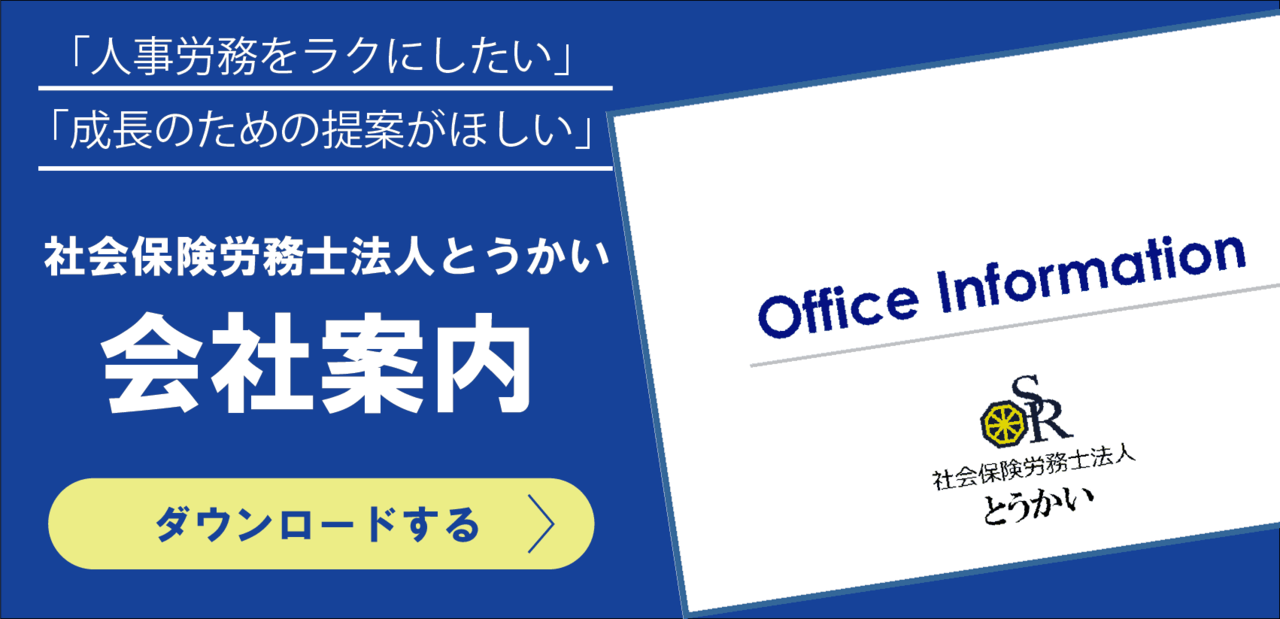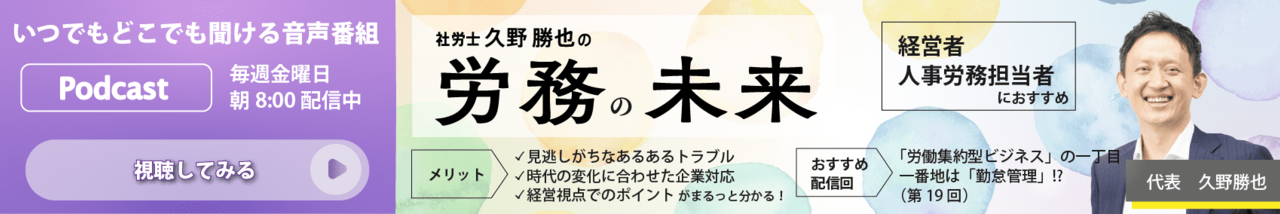昇給とは?6種類の昇給制度とその機能について解説

労働者が勤める企業を選ぶ際に重要視するもののひとつとして「給与」があげられます。
勤続年数や職務遂行能力の変化に伴い、基本給が引き上がることを「昇給」といいます。
当たり前の制度である昇給ですが、実は6種類あるのをご存知でしょうか。
ここでは6種類の昇給制度をはじめ、企業における昇給の機能や、日本企業の一般的な昇給額と昇給率について詳しく解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

勤続年数、実績などの変化に応じて行われる基本給の引き上げを「昇給」といいます。
昇給の方法は様々で、日本で一般的なのは毎年定期的に昇給していく「定期昇給」です。
似た言葉に「昇格」や「昇進」といったものがありますが、それぞれ意味は異なっています。
昇格(しょうかく)とは、社内での等級が上がることです。
「総合職◯級」「一般職△級」など、級数が増えることをいい、業務上の権限やそれに伴う責任が大きくなっていきます。
昇格時にはあわせて昇給も行われることが多いでしょう。
昇格はあくまで「社内評価」であることがポイントです。
昇進(しょうしん)とは、役職(職位)が上がることです。
「課長」や「部長」といった肩書がつき、より責任のある職務を課されるようになります。名刺などに役職が表記されることから、昇格が社内評価であるのに対し、昇進は対外的に社内での地位を示すという特徴があります。
昇進も昇格と同様に、多くの場合は昇給を伴います。
昇給(しょうきゅう)とは、給与が上がることです。
給与が上がるタイミングは様々ですが、日本では勤続年数に応じて毎年安定して給与が上がる定期昇給が主流となっています。
昇格、昇進にあわせて昇給することもあります。
定期昇給が労働の質と直結しないのに対し、欧米諸国では職務遂行能力を重視した昇給制度が広く採用されています。

昇給制度は主に次の6種類です。
それぞれの昇給機会や昇給額、昇給率などは企業ごとに異なり、企業の給与規定に基づいています。
臨時昇給は時期を特に定めない昇給制度です。
企業の業績が好調な場合などに臨時で行われる昇給を指します。
一部の社員の実績や功労に対して給与を上方改定するものであれば特別昇給となり、全社員の給与を一律で上方改定するものであればベースアップとなります。
年齢や勤続年数など、自動的に生じる変化を基準とするのが自動昇給です。
実績や能力に関係なく、全従業員が一律で対象となります。
実績や勤務態度などへの評価(考課)を基準とした昇給制度です。
考査昇給または査定昇給といいます。
企業によって昇給率は異なり、定期昇給と同タイミングで考課昇給の査定が行われることもあります。
日常の業務が給与に関わるため、従業員の仕事に対するモチベーションアップにも繋がりますが、企業側からすると査定作業に時間とコストがかかるといったデメリットもあります。
技能や職務遂行能力の向上などを理由とした昇給が普通昇給です。
特殊な職務への従事、特別な功労など、普通昇給の範囲外となる特別な理由に基づく昇給を特別昇給といいます。
時期を決めて定期的に行われる昇給のことを定期昇給といいます。
日本ではこの定期昇給が主流であり、一般的に毎年1、2回実施する企業が多いようです。
業績によって定期昇給を実施するか否かを決める企業もあります。企業によってルールは様々なため、従業員は自社の給与規定をきちんと把握しておくべきでしょう。
定期昇給の対となるのが、時期を特に決めない臨時昇給です。
定期昇給は無限に昇給が続くわけではなく、ある程度の年齢に達すると昇給はストップする仕組みです。
定期昇給制度のある企業のうち、平均的な昇給停止年齢は48.9歳とされています。
昇給停止年齢は企業の規模によって差があり、中規模企業では30代後半、小規模企業では50代が多いようです。
従業員にとっては決まったタイミングで安定的に給与がアップすることが定期昇給制度のメリットでしょう。
昇給の比率やタイミングが定まっている企業の場合、将来的な収入を見通せるため、住宅購入などライフプランに合わせた資金計画が立てやすくなります。
企業側も従業員の生涯年収をおおよそ予測することができるため、経営計画において給与という固定費を計算しやすくなります。
定期昇給制度では実績に関わらず安定して昇給するため、社員の働く意欲が上がりにくい、人件費が高騰しやすいという点がデメリットといえるでしょう。
実績と勤続年数にギャップが生まれる可能性もあります。
実績が低いのに勤続年数が長いため給与が高いという状況を、不公平だと感じる従業員もいるかもしれません。
チームワークが円滑に行われず、業績に悪影響を及ぼすリスクもあります。
トヨタ自動車、日産自動車、ホンダ、日立製作所などが定期昇給制度を廃止しています。
トヨタ自動車は2021年1月より一律的な昇給制度をやめ、個人の能力を重視する評価制度に一本化しました。
従来からある職位による「職能基準給」と、個人の評価に基づく「職能個人給」の2つを統合して基本給を決定します。
昇給制度には上記で解説した6種類以外に「ベースアップ」という仕組みがあります。
昇給が個々の労働者を対象とするのに対し、従業員全体の給与水準を一斉に引き上げる方法がベースアップ(略してベア)です。
例えば、「ベースアップ3%」が採用される場合、勤続年数や役職に関わらず、基本給が20万円の社員は20万6,000円に、30万円の社員は30万9,000円に引き上げられます。
社会の物価上昇などに合わせて一律で給与アップできるので、企業としては利益を従業員全員へ分配できるメリットがあります。
しかし、企業としては固定費の大幅上昇であり、一度改定した給与は簡単に引き下げることができないため、将来的なリスクも含んでいます。

大矢の経営視点のアドバイス
厚生労働省から公表された「令和5年度労働経済の分析」においては、今後「年齢」「勤務年数」に基づく昇給制度から、「成績」「職務」に基づく給与体系に変える企業が多い健康にあります。弊社ではこれまで全国360社以上、数名企業から2,000名以上の企業をサポートしてきたため、豊富な事例ふまえてご提案することが可能です。ぜひご相談ください。

企業は労働の対価として従業員へ給与を支払いますが、その給与をアップさせる昇給にはどのような機能や意味合いがあるのでしょうか。

昨今の社会情勢や経済環境、多様化する働き方によって、昇給の現状はどのようになっているのでしょうか。
ここでは業種別、規模別に企業の昇給額と昇給率の傾向をみていきましょう。
日本経済団体連合会の調査「2021年春季労使交渉における中小企業業種別妥結結果(加重平均)および2021年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果(加重平均)」によると、2021年の日本企業における昇給金額は次のような結果になりました。
大手企業のアップ率を更に詳しくみていくと、鉄鋼(1.27)、私鉄(1.06)、貨物運送(1.32)と1%前半の業種もあれば、繊維(2.00)、機械金属(2.00)、自動車(2.05)、建設(2.43)、商業(2.11)と2%以上の業種もあり、ばらつきがあります。
同様に中小企業では繊維(1.47)、運輸・通信(1.37)、が1%前半にとどまり、2%以上は金融(2.03)のみと、業種によってアップ率はまちまちという結果でした。
製造業平均
| 2021年度 | 2020年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | アップ率 | 平均 | アップ率 | |
| 中小企業 | 4,633円 | 1.75% | 4,716円 | 1.81% |
| 大手企業 | 6,153円 | 1.87% | 6,842円 | 2.09% |
非製造業平均
| 2021年度 | 2020年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | アップ率 | 平均 | アップ率 | |
| 中小企業 | 3,971円 | 1.57% | 3,844円 | 1.52% |
| 大手企業 | 5,959円 | 1.87% | 8,397円 | 2.24% |
中小企業においては前年とほぼ同水準の総平均4,376円、アップ率1.68%となりました。
大手企業においては総平均6,124円、アップ率1.84%と、前年度と比べるとマイナス972円、アップ率マイナス0.28%となっています。
| 2021年度 | 2020年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | アップ率 | 平均 | アップ率 | |
| 中小企業 | 4,376円 | 1.68% | 4,371円 | 1.70% |
| 大手企業 | 6,124円 | 1.84% | 7,096円 | 2.12% |
※中小企業は従業員数500人未満の17業種754社を対象に実施
※大手企業は原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手256社を対象に実施
厚生労働省の「令和元年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」によると、令和元年中に管理職の定期昇給を「行った・行う」企業は71.2%(前年69.7%)、「行わなかった・行わない」企業は6.2%(前年8.1%)となっています。
また、一般職においては、「行った・行う」は80.4%(前年80.1%)、「行わなかった・行わない」は3.0%(前年4.5%)という結果になりました。
管理職に比べ、一般職での昇給実施率が高い傾向にあるようです。
| 管理職 | 一般職 | |
|---|---|---|
| 行った・行う | 71.2%(前年69.7%) | 80.4%(前年80.1%) |
| 行わなかった・行わない | 6.2%(前年8.1%) | 3.0%(前年4.5%) |
業種別に実施率をみていくと、建設業(管理職84.7%・一般職93.4%)や製造業(管理職79.6%・一般職89.0%)の実施率がおよそ8割を超えているのに対し、宿泊業・飲食サービス業(管理職48.2%・一般職59.8%)の実施率が低いのが目立っています。
業種別の実施状況を以下に一覧で紹介します。
定期昇給の実施状況「行った・行う」
| 業種 | 管理職 | 一般職 |
|---|---|---|
| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 66.7% | 88.9% |
| 建設業 | 84.7% | 93.4% |
| 製造業 | 79.6% | 89.0% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 72.9% | 100.0% |
| 情報通信業 | 78.6% | 85.3% |
| 運輸業・郵便業 | 57.7% | 71.9% |
| 卸売業・小売業 | 69.6% | 78.9% |
| 金融業・保険業 | 69.4% | 79.2% |
| 不動産業・物品賃貸業 | 76.6% | 84.5% |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 76.9% | 91.6% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 48.2% | 59.8% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 69.3% | 75.4% |
| 教育・学習支援業 | 66.6% | 76.3% |
| 医療・福祉 | 71.7% | 75.8% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 65.4% | 69.0% |
規模別にみると、管理職も一般職でも1,000~4,999人の大規模企業での昇給実施率が高いことがわかりました。
対して、100~299人の小規模企業では管理職、一般職どちらも実施率は8割以下という結果になっています。
企業規模別の実施状況を以下に一覧で紹介します。
定期昇給の実施状況「行った・行う」
| 規模 | 管理職 | 一般職 |
|---|---|---|
| 5,000人以上 | 67.5% | 89.1% |
| 1,000~4,999人 | 76.0% | 90.0% |
| 300~999人 | 72.9% | 81.9% |
| 100~299人 | 70.3% | 79.0% |
実際の昇給制度はどのようなものなのでしょうか。
ある企業の具体例をみていきましょう。
- 職責等級制度のもと、社員の等級が分かれている
- 等級ごとにレンジやレートが設定されている(レンジは賃率の範囲を指すもの)
- レンジは4区分されており、2回分の半期成績の累積ポイントで昇給額が設定されている
- 昇級による昇給とともに、同一等級内でも年単位の昇給がある
- 成績評価次第で昇給とならない場合もある
- 自動昇給制度はない
- レンジに上限があり、昇級しない場合昇給とならない
この企業では、昇級することで同一等級内での昇給も可能です。
しかし、自動昇給制度を採用していないため、成績評価次第では給与に変動がない場合もあります。
このように実際の昇給制度は複雑になる場合が多いため、企業は新卒者や転職希望者が昇給制度をきちんと把握できるように給与規定を明確にしておく必要があるといえます。
学歴による昇給額に差はあるのでしょうか。
2006年の時点では、大卒者の平均昇給率は男性「約2.9%」、女性「約3.3%」。
高卒者の平均昇給率は、男性「2.32%」、女性「約2.02%」でした。
昇給率は男女ともに大卒者が高卒者を上回っています。
長期的にみていくと収入にも差がでるため、最終学歴は昇給額だけでなく生涯年収にも影響するといえるでしょう。

昇給に関するよくある疑問に回答します。
昇給通知とは、企業が従業員に対して昇給したことを通知することです。
賃金規定で定期昇給が定められている場合が多いですが、昇給通知を行う法的義務はありません。
そのため、給与明細が昇給通知を兼ねる場合もあります。
しかし、少額の昇給や査定のタイミングによっては昇給したこと自体に気が付かない場合もあります。
社員のモチベーションアップのためにも、企業は昇給通知を行うべきだといえるでしょう。
社員を昇給させる場合、昇給理由を明確にすることが重要です。
経営が好調なためのベースアップであれば、会社への信頼度の上昇が見込めるでしょう。
また、昇格によるものであれば、職務遂行能力が認められたことによる労働意欲の向上も期待できるかもしれません。
昇級理由を明確に伝えることは、社員の働くためのモチベーションやライフプランに大きく影響するのです。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」