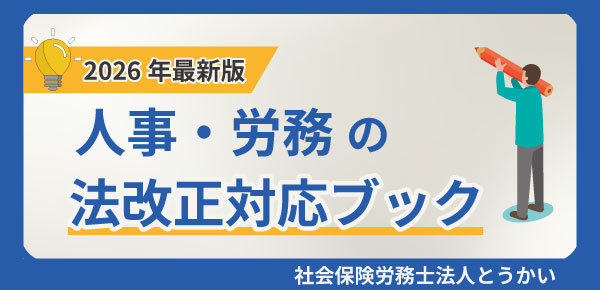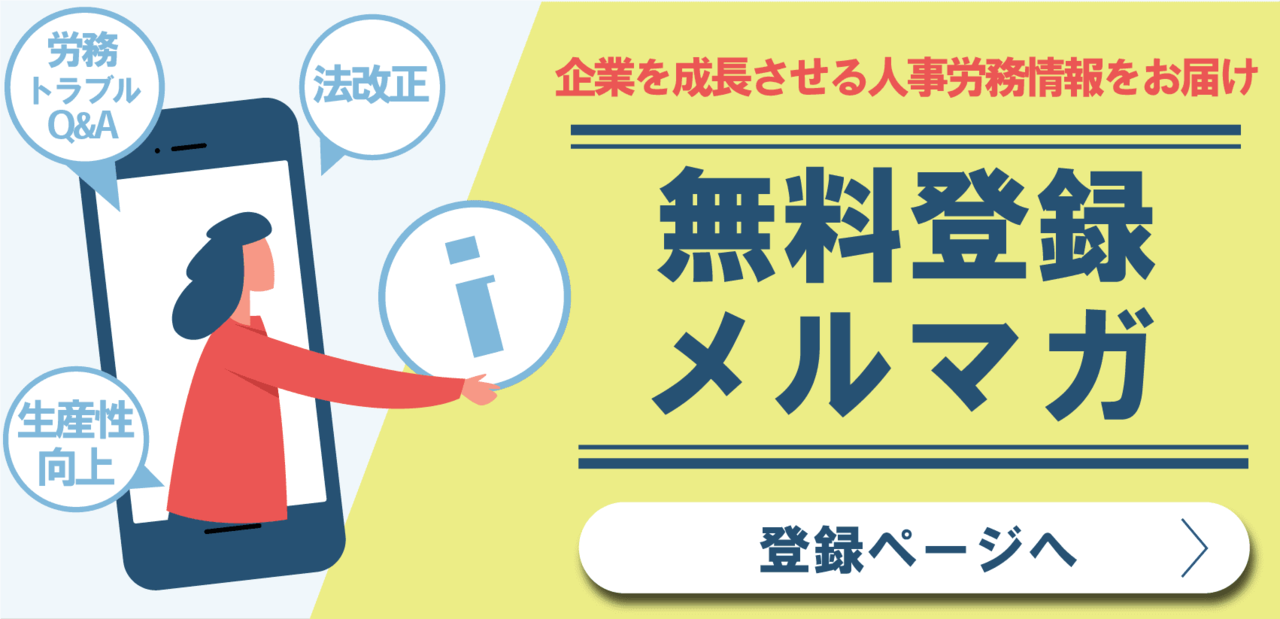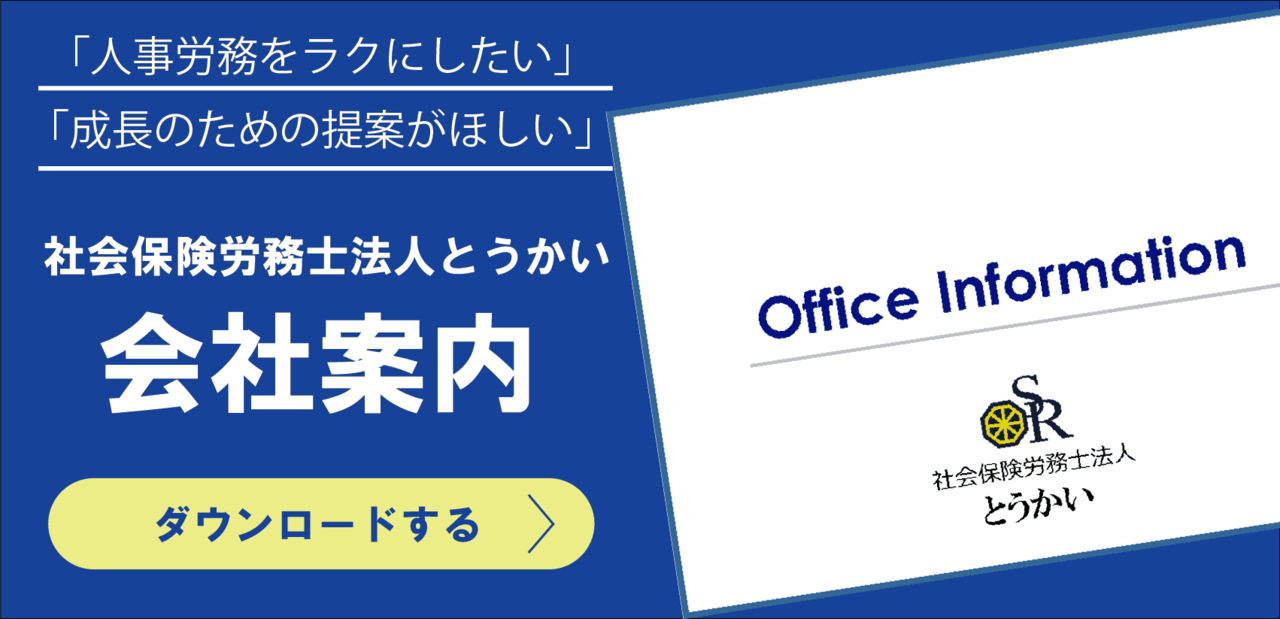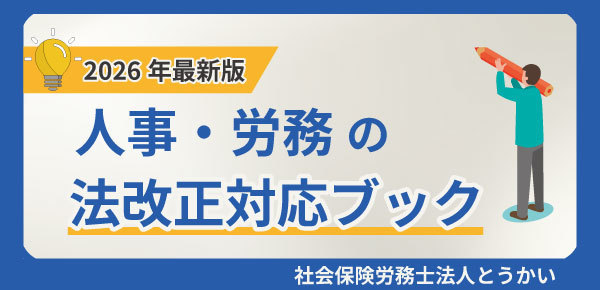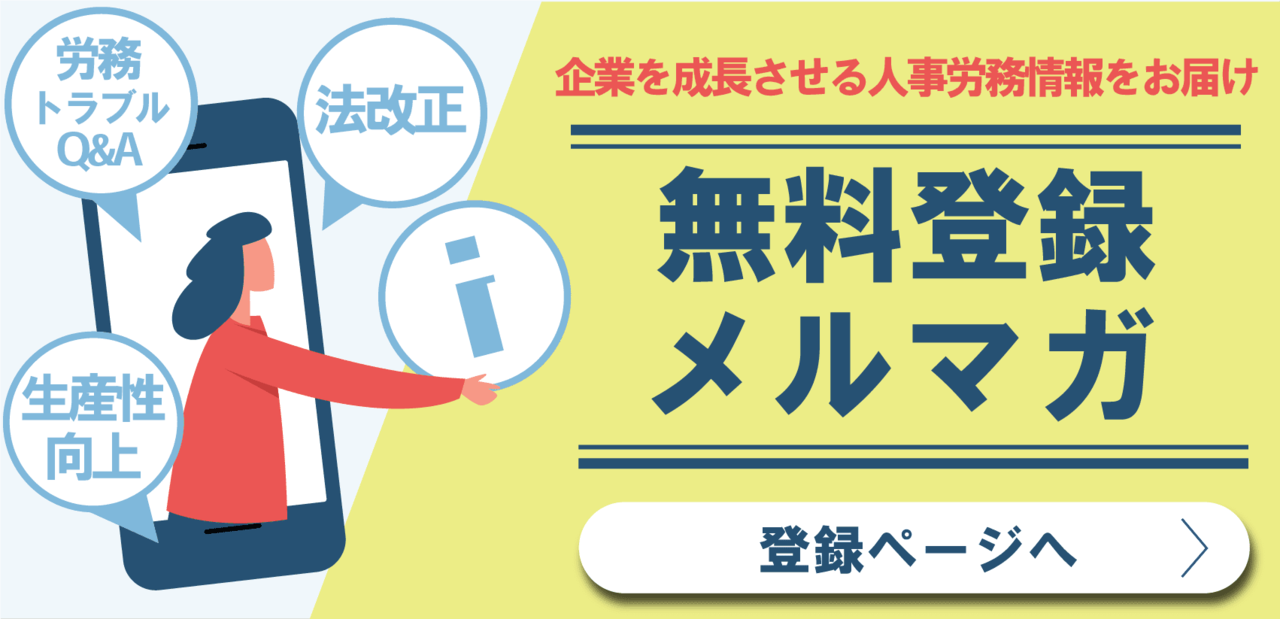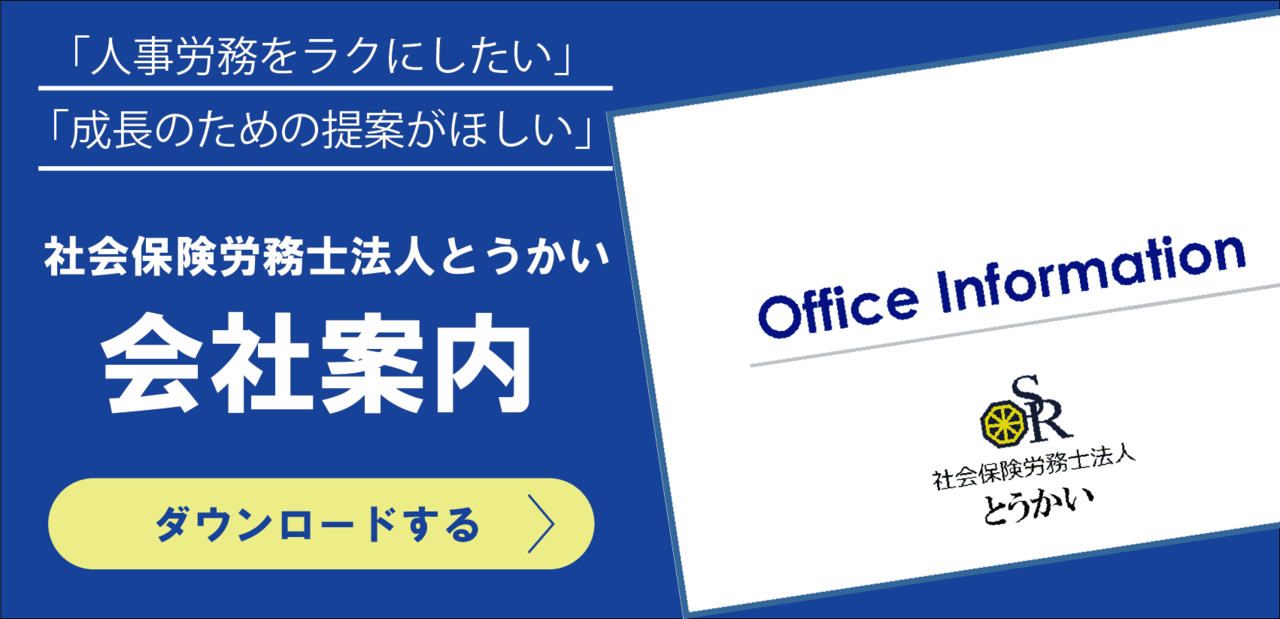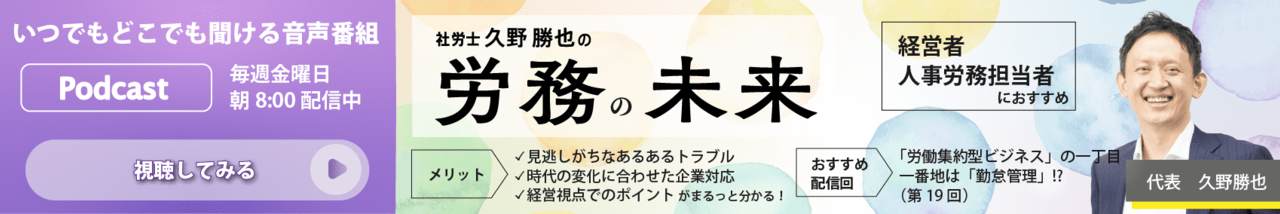『弥生給与』とは? 給与計算ソフトウェア選びにお悩みの担当者向けに、ITに強い社労士が詳しく解説します。

『弥生給与』とは、数多ある給与計算ソフトウェアの中でも、かなり昔から利用されているシステムのひとつです。会計や販売といった弥生シリーズのうちでも、利用企業の多いソフトウェアになります。シンプルでわかりやすい画面表示で、給与業務初心者にも比較的簡単に利用できるのが「弥生給与」です。
今回は、この『弥生給与』に注目し、給与計算ソフトウェアの基本と、どのような会社におすすめなのかを、ITに強い社労士が詳しく解説します。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
執行役員 社会保険労務士 小栗多喜子
同社、人事戦略グループマネージャーを務め、採用・教育を担当する。商工会議所、銀行、Adeco,マネーフォワードなどセミナーや研修講師も精力的に行っている。労働法のアドバイスだけではなく、どのように法律と向き合い企業を成長させるのかという経営視点でのアドバイスを得意としている。
主な出演メディア
その他、記事の監修や寄稿多数。
取材・寄稿のご相談はこちらから
バックオフィス系の業務を担っている人であれば、一度は「弥生」という名前は聞いたことがあるのではないでしょうか? 小規模企業から中規模企業をメインターゲットに、会計や給与といったバックオフィス業務を支援するソフトウェアなどがラインアップされています。ソフトウェアの提供方法については、従来型のオンプレミス型タイプ、クラウドサービスタイプなどにわかれています。
○弥生シリーズのラインアップ一例
| 業務の目的 | ソフトウェア・サービス | 提供タイプ |
| 経理・会計 | 弥生会計オンライン | クラウド |
| 弥生会計23 | デスクトップ | |
| 申告 | やよいの青色申告オンライン | クラウド |
| やよいの青色申告23 | デスクトップ | |
| やよいの白色申告オンライン | クラウド | |
| 給与 | 弥生給与23 | デスクトップ |
| やよいの給与計算23 | デスクトップ | |
| やよいの給与明細オンライン | クラウド | |
| 請求 | MISOCA | クラウド |
| 見積納品請求書23 | デスクトップ | |
| 顧客管理 | やよいの顧客管理23 | デスクトップ |

『弥生給与』とはどのような
ものでしょうか。
『弥生給与』とは、弥生シリーズの給与計算ソフトウェアです。給与計算に必要なさまざまな機能をサポートし、メインとなる給与・賞与計算、社会保険、年末調整業務まで、スムーズに行うことができると人気のソフトウェアです。給与計算業務は、労働基準法をはじめ、社会保険や所得税といった業務を行う上で必須の知識が数多くあります。ましてや従業員の給与計算はミスなく正確に行わなければなりません。さまざまな法律や就業規則に沿って、運用するには担当者にとってとても負担の大きいものです。『弥生給与』は、これらの業務を効率化し、ミスや漏れを防ぐことで、ルールに則った給与支払額を算出するための工夫がされています。シンプルでわかりやすい画面構成で、給与計算業務の経験が浅い担当者であっても、比較的簡単に設定が可能であり、計算業務も画面に沿って入力すれば完結できるのが魅力です。また、法改正に伴う制度変更なども定期的にアップデートされるため、最新の法律・制度に対応することができます。
①従業員規模
『弥生給与』は従業員100名くらいの規模感の会社におすすめです。もちろん複数事業所がある場合や部門管理も可能です。
②デスクトップタイプ
ここ最近はクラウドタイプの給与計算ソフトウェアが主流になってきた中、『弥生給与』はデスクトップタイプとなっています。OSはWindows10、11に対応していますので、Windowsユーザーであれば、とくに問題なく利用できるでしょう。デスクトップタイプとはいえ、定期的にアップデートが行われますし最新の法律や規制に対応しますので安心です。
③簡単設定
給与計算業務の肝は、導入時の環境設定です。通常、給与計算ソフトウェアは、労基法、税法、社会保険といった各種法律や、会社独自の就業規則や給与規程に沿った設定が必要です。『弥生給与』の場合は、設定の仕方や使い方を解説した動画もあり、初めての方でも比較的簡単に設定が可能でしょう。ナビゲーションに沿って順番に設定していけば、概ね完了できます。
④シンプル画面
『弥生給与』は、使いやすいインターフェースが特徴で、給与計算業務に不慣れな初心者であっても取り組みやすいとされています。
⑤サポートプラン
『弥生給与』はサポート体制も充実しています。サポートプラン別のサービスメニューが用意されています。例えば、パソコンのトラブル対応、操作質問などをはじめ、業務支援のサービスといった充実したトータルプランや、最小限のサポートでOKの場合であればセルフプランといったサポートプランがあります。自社の状況や、実務担当者のレベルに応じて選択が可能です。
*『弥生給与』あんしん保守サポート(年間価格)
| セルフプラン | ベーシックプラン | トータルプラン |
| 41,500円 | 54,200円 | 75,000円 |

『弥生給与』と『やよいの給与計算』の2種類の違いを詳しく解説します。
「弥生」シリーズのうち、給与計算を行うことができるソフトウェアは、『弥生給与』と『やよいの給与計算』の2種類があります。
この2つの違いは、対応する従業員規模です。『弥生給与』は、従業員100人くらいまでの中小企業をメインターゲットにしているのに対し、『やよいの給与計算』については、従業員30人以下の小規模企業を対象としています。従業員規模が30人以下といった企業は、専任の給与計算担当者がいないケースも多くあります。しかしながら給与実務には専門知識が必要な場面が多く、複雑なシステムは使いこなせないという問題があります。そもそも複雑な機能が必要ないということもあるでしょう。そこで『やよいの給与計算』では、少人数の企業に合わせ、より機能がシンプルで操作しやすい、そして専門知識がない初心者であっても使いこなせるソフトウェアとなっています。従業員100人くらいを対象としている『弥生給与』も、シンプルで操作がしやすいソフトウェアでありますが、『やよいの給与計算』は、よりシンプルで使いやすいものとなっています。『弥生給与』と『やよいの給与計算』は、従業員数規模に応じて、適切に機能が設定されているのです。
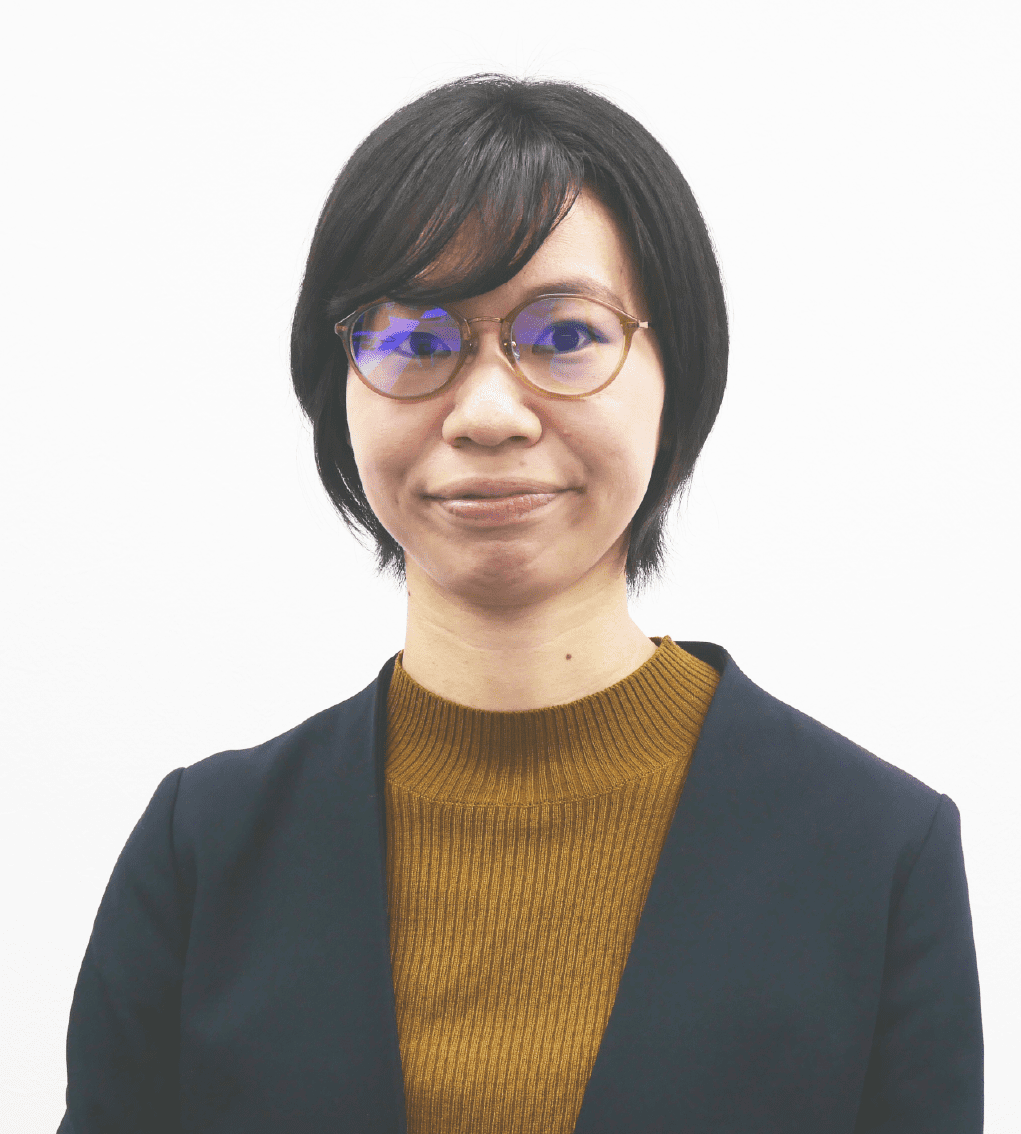
弥生給与の使い方はシンプルで簡単、おすすめの理由のひとつです。
『弥生給与』を使うにあたっては、シンプルでわかりやすい、設定もしやすいのがメリットです。給与計算の実務に慣れていない担当者であっても、導入時のスタートアップガイドも用意されていますし、設定ウィザードに沿って進めていけば、概ね完了できるでしょう。弥生のオフィシャルサイトには、導入設定の動画なども用意されているので、悩まず設定することが可能です。給与計算担当者の頭を悩ませる年末調整業務も、年末調整ナビも用意されていますので、比較的簡単に作業が完了するはずです。
不安な場合には、まずは体験版で試してみることをおすすめします。
◾️『弥生給与』『やよいの給与計算』スタートアップガイド
https://www.yayoi-kk.co.jp/startupguide/payroll/

デスクトップ型のソフトウェアで不便がないのか、しっかり説明します。
『弥生給与』は、デスクトップ型のソフトウェアです。1つのPCにインストールして利用します。クラウドが主流になりつつあるなか、デスクトップ型のソフトウェアで不便がないのか気になるものではないでしょうか?
給与計算業務において、クラウドが生きる場面は、給与明細書の発行や配布です。拠点が複数ある場合などは、紙の給与明細書を印刷して送付するといった手間を効率化したいという担当者は多いはずです。その点クラウドサービスであればメール配信やダウンロードが可能です。『弥生給与』はデスクトップ型であっても、クラウドサービスとの連携が可能です。『やよいの給与明細オンライン』を利用すれば、給与明細書の発行がWeb配信や印刷やメール添付のための明細書のダウンロードが可能となります。
また、その他にも『弥生給与』と連携できるクラウドサービスは豊富にあります。
【勤怠管理】
TimeP@ck
CLOUZA
Foucus U タイムレコーダー
KING OF TIME
【明細書】
Web給金帳Cloud
Foucus U 給与明細 for 弥生

デスクトップ型のソフトウェアのメリット・デメリットをご紹介します。
『弥生給与』は、デスクトップ型のソフトウェアです。1台のPCに、1つのライセンスが紐づいて利用することが可能です。1つのライセンスを複数のPCで共有することはできません。ただし、同時利用でなければ、1ライセンスに1台のみ追加インストールが可能です。要は、2台のPCにインストールはできるものの、2台同時にはソフトウェアを利用できないということになります。
その他、給与担当者が複数いる場合もあるでしょう。その場合には、すべての担当者に管理者権限を与え1台のPCで複数のログオンユーザーが利用することもできます。

少しでもご不安やご不明な点があれば、サポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお問合せください。
給与計算業務は、どのようなソフトウェア・システムを選ぶかは非常に重要です。従業員規模、業種、労働時間制など、自社の就業規則や給与規程にフィットできる機能を持つソフトウェアを選択しなければなりません。まずは企業の具体的なニーズや要件を整理することが欠かせないでしょう。最近の給与計算のソフトウェアは、優れた機能を持つものも多いのですが、会社の規模、予算、業務の複雑さなどを考慮して比較検討し、最適なソフトウェアを選択することをおすすめします。無料トライアルやデモを利用して実際に操作してみることも大切でしょう。
ソフトウェア選びに時間をかけたくない、担当者のパワーが割けないといった場合には、労務管理のプロである社会保険労務士への相談も検討してみてください。専門家の視点で会社に合ったソフトウェア選びを行うことで、導入までの期間が短縮できますし、いざ運用がスタートしても大きなトラブルなく進めることが期待できます。
当社では人事労務の専門知識はもちろんですが、昨今のIT知識に長けた社労士が揃っています。少しでもご不安やご不明な点があれば、サポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお問合せください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」