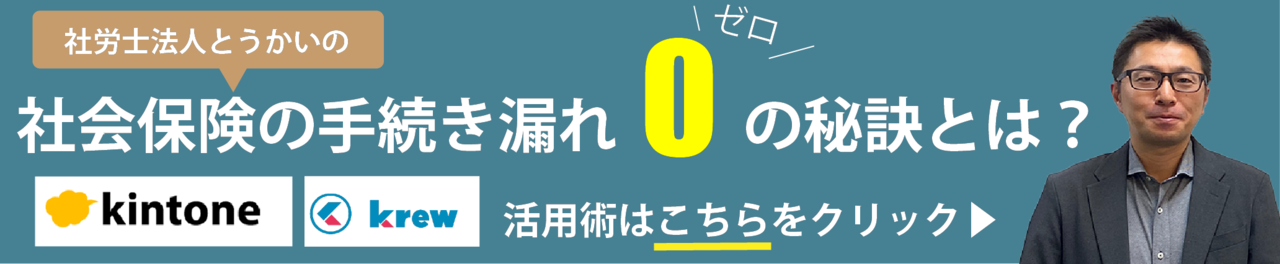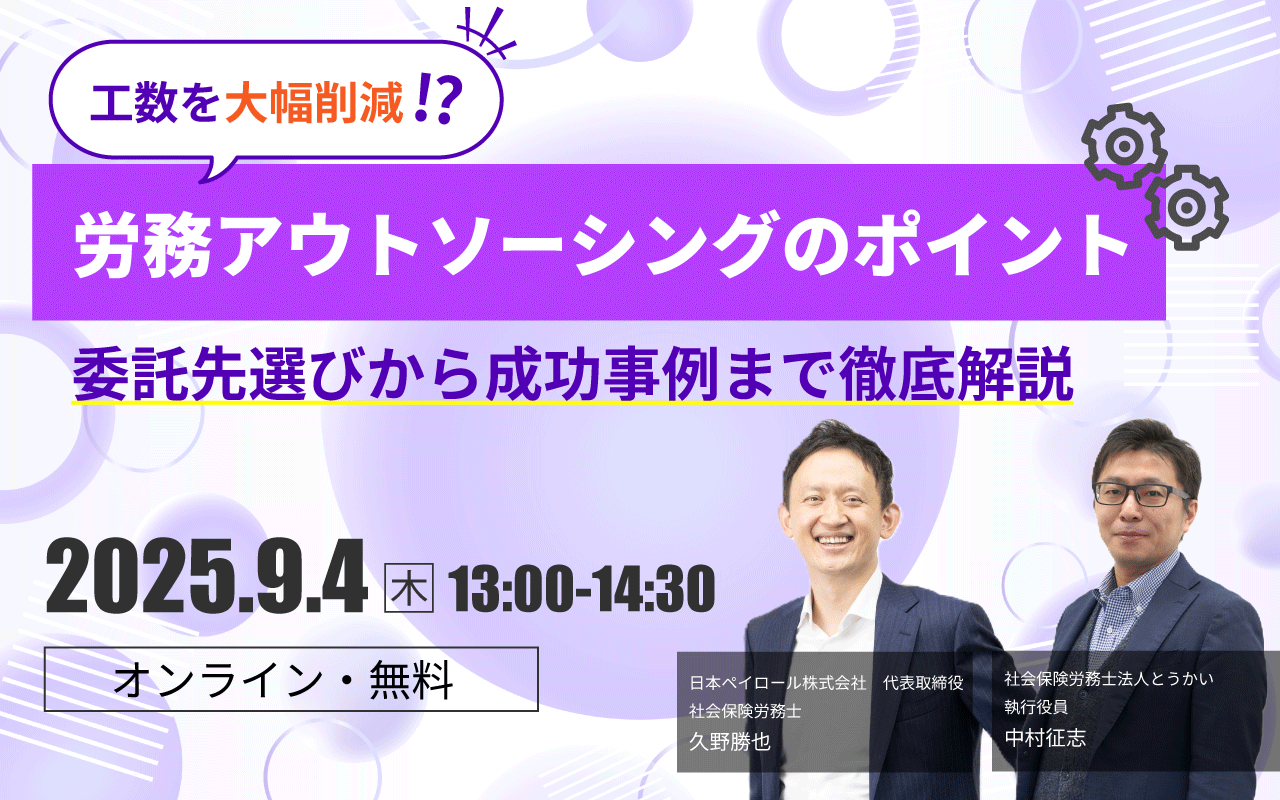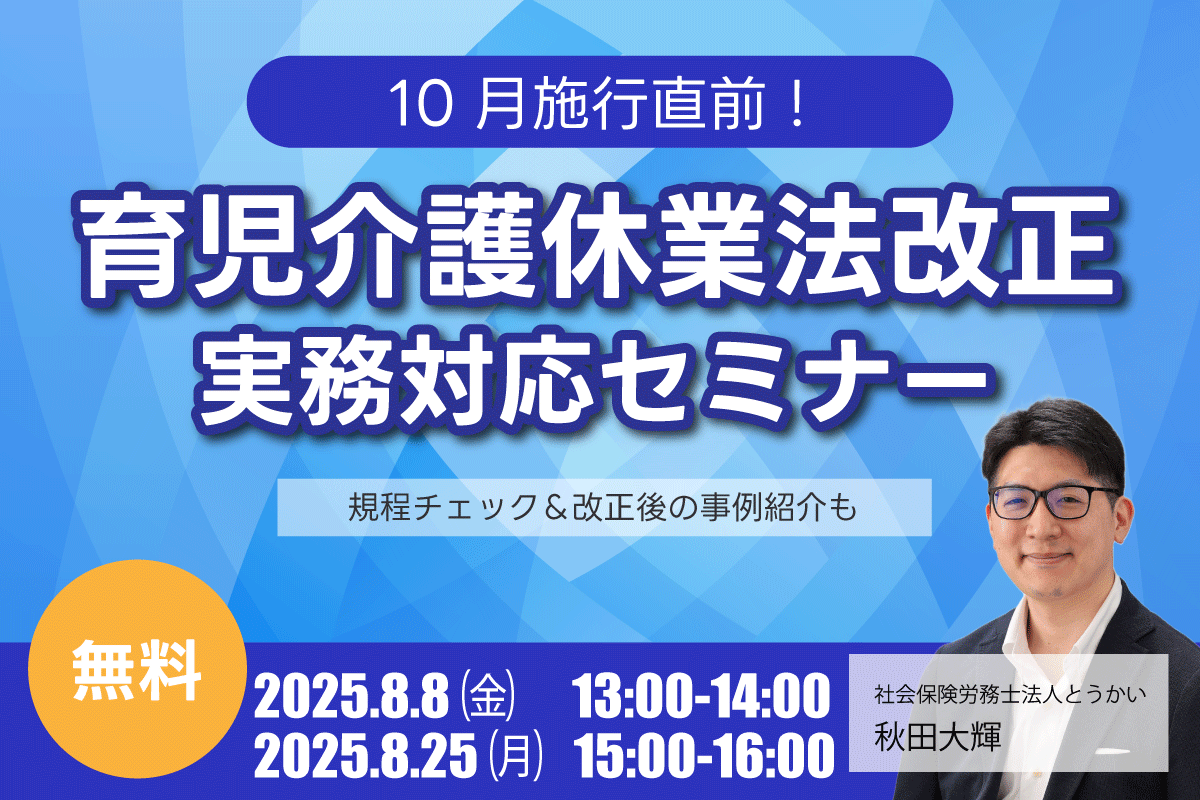社労士が引退や事業継承をするには。
円滑なリタイア方法を事業承継に詳しい社労士が解説します。
- ホーム
- ご退任・承継先をお探しの社労士の方
- 社労士が引退や事業継承をするには。 円滑なリタイア方法を事業承継に詳しい社労士が解説します。


社労士の引退や事業継承について詳しく解説していきます
「高齢なのでそろそろリタイアを考えている」
「引退したいが後継者がおらず、職員の雇用に悩んでいる」
「顧問先に迷惑をかけたくない」
「事業承継の具体的方法がわからない」
「どのくらいの価格で事業譲渡が可能なのか知りたい」
さまざまな理由によって、引退や事業承継にお悩みの社会保険労務士の方々がいらっしゃいます。今回は、引退や事業承継を視野に入れている社会保険労務士のみなさまのサポートとなるよう、M&Aに詳しい社労士が、知っておきたい事業承継のイロハをお伝えします。

事業継承とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
詳しく解説していきます。
そもそも事業承継とは、一般的に事業の経営を後継者に引き継ぐことを言い、その目的、手法などはさまざまです。ただ、単に次の後継者を誰にするか、という問題だけではなく、ヒト・モノ・カネといった経営資源を第三者含め誰に引き継ぐのかも含まれます。事業承継後に、後継者が安心して経営を行い、さらに成長させていくために、どのような事業承継がベストであるのか、経営者が頭を悩ませる経営課題でもあります。最近は、経営者の高齢化が進み、後継者不在による廃業も深刻になっています。廃業により雇用が失われることも大きな問題です。そのためには、早い段階から事業承継について考え、アクションを取ることが重要となってきます。
① 親族内承継
現在の経営者の親族に承継するかたちです。相続による財産や株式の移転がされます。所有権と経営の承継がされることになります。
② 親族外(従業員)承継
親族以外から、経営者を選び承継されることになります。役員(MBO)や従業員(EBO)を次の後継者として育成していくといったことも考えられます。
③ M&A
社外の第三者へ、株式を譲渡したり、事業を譲渡することで、承継します。後継者がいない場合などは、このケースが取られることが多いでしょう。
④ IPO
中小企業では一般的ではありませんが、会社を上場させることで価値を高め、広く後継者を募ることが可能です。
| メリット | デメリット | |
| ① 親族内承継 | ・社内外から受け入れられやすい ・後継者を早めに決定でき、準備期間もある | ・経営能力のある後継者とは限らない ・親族候補者が多くいる場合、争いに 発展する場合もある |
| ② 親族外承継 | ・社内外から広く後継者を選択できる ・役員や従業員への後継であれば、事業や業務に 精通しており、社内外から理解を得やすい | ・後継者が株式を取得する場合に、多くの 資金が必要になる場合がある ・債務保証の引き継ぎが難しい |
| ③ M&A | ・承継先を幅広く選択できる ・承継先との事業シナジーを期待できる ・雇用維持 ・株式の売却益を獲得できる | ・承継先を見つけることに時間や手間、 コストがかかる ・これまでの会社風土の承継が困難 |
| ④ IPO | ・資金調達が可能となり、事業の成長が期待できる ・知名度アップ | ・時間やコストが大きな負担となる ・これまでの会社風土の承継が困難 |
・経営権/経営理念
・株式
・事業用の資産(設備や不動産など)
・資金
・従業員
・事業ノウハウ
・取引先との人脈や口座
・顧客情報
・知的財産権や許認可など

社労士と株式会社の事業承継
にはどのような違いがある
のでしょうか
近年、多くの企業において経営者の事業承継について話題に上がることが増えてきました。経営者の高齢化をはじめ、目まぐるしく変わる経営環境において、事業継続や雇用維持の選択肢として、事業承継を決断するケースもあります。一般企業に限らず、社会保険労務士業界においても同様に、事業承継の問題は避けて通れません。
昔であれば、社労士資格を取得した子が後継者として、親の社労士事務所を引き継ぐケースも多くありました。ただ今は、親の家業を継ぐといったものが主流であった時代と異なり、親の仕事を子供が引き継ぐケースも減っています。
とくに社労士事務所の事業承継の場合、一般企業とは異なる社労士事務所ならではの問題もあります。そもそも「社会保険労務士資格」が大前提であることも要因の一つでしょう。加えて社労士事務所の規模感も影響しています。社労士事務所の多くは小規模であり、事務所所長である社労士と数人の事務スタッフの従業員という構成が多いのが実情です。唯一の有資格者である所長が引退したくとも、後継者となる従業員がいない、という場合も多いのです。
さらに、後継者不在以外にも社労士業界を取り巻く事業環境の変化も、事業承継を行う要因ともなっています。近年の社労士業界は、DX推進によって社会保険をはじめとした手続業務や給与計算の低価格が進み、価格競争の一面が否定できません。給与計算業務などでいえば、低価格でアウトソーシング業務を請け負うITベンダーも存在します。加えて企業は、ITツールを使いこなし、スピード感を持って、レベルの高いサービスを期待します。こうした競合先の多い業務の中で、数人規模の社労士事務所が生き残っていくには至難の業です。
手続き業務以外に活路を見出し、人事制度コンサルティングや助成金・補助金業務に注力していくにも、一足飛びに顧問契約を獲得できるわけではありません。多くのサービスが混在するなか、企業側もシビアに選択するようにもなってきました。何十年も付き合ってきた顧問社労士だからといって、この先企業にメリットあるサービスの提供がなければ、別の顧問先、別のサービスを選択することにもなるでしょう。
こうした状況下で、社労士事務所は新たな経営戦略、どのように事業継続・展開していくかといった視点が欠かせません。そのために、事業承継(M&A)といった選択肢を視野に入れるケースが増えています。
社会保険労務士の事業承継で増えているM&Aで、そのプロセスを確認していきましょう。まず社会保険労務士事務所の事業承継(M&A)は、事業を承継してくれる先を探したい「売りたい」のか、事業規模を広げていくために「買いたい」のかによって、それぞれステップを踏んでいくことになります。ここでは、売り手としてのプロセス・方法をみていきます。
事業承継(M&A)を決断し、いざ売りたいと思っても、やみくもに売り先を探しても始まりません。事業承継(M&A)をスムーズに短期間で成功させるためには、どのようなM&Aアドバイザリーを選ぶかが非常に重要になってきます。M&Aアドバイザリーといっても、銀行やM&A仲介サービス会社などがあり、M&Aの目的に応じた依頼先を選ぶことになります。M&Aのアドバイザリーは、売り先探しや交渉、条件の取り決め、価値算定、各種書類の作成といった多岐に渡るプロセスをサポートしてくれる役割です。信頼して任せることができるのかしっかり判断しなくてはなりません。
M&Aのアドバイザリーを決めたら、アドバイザリーの契約を締結し、いよいよ本格的にM&Aに向けてのスタートです。
① 譲渡する社会保険労務士事務所の概要など資料作成
売り先に打診し検討してもらうためには、社会保険労務士事務所の概要や希望する条件といった資料が必要になります。いわばお見合いの釣り書きのようなものになります。
② 価値算定
どのくらいの価値がつくのかの算定を行います。年間の顧問報酬や営業利益をベースに相場を検討されることになります。
③ 売り先の紹介や選定
希望条件などに合致した売り先候補を選出し、紹介します。
④ 面談や交渉/デューディリジェンス
面談や交渉を進めながら、双方の合意で基本合意を締結し、デューディリジェンスを行います。譲受後にリスクがあるのかどうか、逆にメリットとなる部分、シナジーは何かなど明らかにしていきます。デューデリジェンスを行い、
売り手としては、
・どのくらいの価格で売却できるのか
・従業員の雇用は維持できるのか
・その後の事業経営はどのようになるのか
といった検討をしていくでしょう。
一方、買い手であれば、
・事務所を買うことで、紐づく顧客の獲得はどのくらいになるのか
・事業成長の見込みやサービス領域の拡大はできるか
・雇い入れる従業員のスキルセットはどの程度か
などといった、検討をしていくことでしょう。
⑤ M&Aの成約
さまざまなステップを経て、お互いの合意が叶えばM&Aの成約となります。
一般企業に限らず、社会保険労務士事務所においても、事業承継の検討を始めるのであれば、早いうちに越したことはありません。今現在は健康でバリバリ働けていても、突然に事業承継が必要な場面がやってくることもあります。焦って事業承継を進めた結果、交渉が不利に働いたり、残る従業員に影響がでたり、さらには売却価格に影響が出てしまうこともありえます。より好条件で事業承継を進めていくためにも、思い立った時点から動きだしましょう。
社会保険労務士事務所を事業承継(M&A)するとき、なるべくなら高く売却し、ハッピーリタイアが理想です。ただ、やみくもに希望価格を提示しても、話はまとまらないでしょう。ある程度の相場価格をチェックしておく必要があります。社会保険労務士事務所を売却する場合の相場としては、一般的に年間の顧問報酬や営業利益の2〜3年分をベースに算定されると言われています。一般企業と異なり、士業の企業価値算定にあたっては企業の純資産価格は移動しないと考えられるため、概ね営業利益の2〜3年ということになっています。もちろん、これはあくまで相場価格です。売却時には単に経営成績のみで判断されるわけではありません。これまでの業務内容、顧問先、従業員の雇用状況など総合的に判断し、価格が決定されます。
事業承継(M&A)を検討する際に、気をつけたいのが職員や顧問先などへの情報漏洩です。重要な一大イベントですから、誰かに相談したいといっても、無闇に相談するわけにはいきません。まだ心が決まっていない、何の話も進んでいない段階から、職員や顧問先に情報がもれることで、いらぬ不安感・不信感を招きかねません。
・顧客離れにつながらないように注意
M&Aにおいて、買い手として重要なポイントの一つは、どのような顧客を持っているかです。タイミング悪く情報漏洩などがあることで、顧客が離れることになるようなリスクは避けなければなりません。希望価格での成約が難しくなることに加え、交渉が決裂することもあります。
・従業員の離職に注意
自分の勤めている職場が、売られてしまうかもしれない、となれば、そのことがきっかけで離職してしまう従業員がいるかもしれません。買い手とすれば、実務経験豊富な従業員も含めて買収動機になっているケースも多いものです。不安感などを与えるような不用意な情報漏洩には気をつけましょう。
そのためには、M&Aアドバイザリーや専門知識を持った相談者に、早い段階から相談することが重要です。

事業継承にまつわるお悩みは
とうかいにお任せください。
どんな業界、会社であっても、事業承継については、大きな経営課題となっています。社労士業界も同様で、高齢のために引退を考えているが、「後継者がいない」「従業員の引受先をどうしたら」「今の顧問先に迷惑をかけたくない」といったお悩みを抱えている社労士事務所の所長も多くいらっしゃいます。長年、心血を注いで運営してきた事務所を譲るとき、顧客に迷惑をかけず、従業員も安心できる、そして自分自身もハッピーリタイアできることが理想でしょう。
社会保険労務士法人とうかいでは、社労士事務所の規模を問わず、事業承継にお困りの所長をサポートしています。今すぐ事業承継を行いたい方、そろそろ考え始めようと思っている方も、今後の方向性にお悩みであれば、実績を踏まえながらサポートしていきます。事業承継にお悩みの方は、社会保険労務士法人とうかいと一緒に進めてみませんか? ぜひお気軽にお問合せください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」