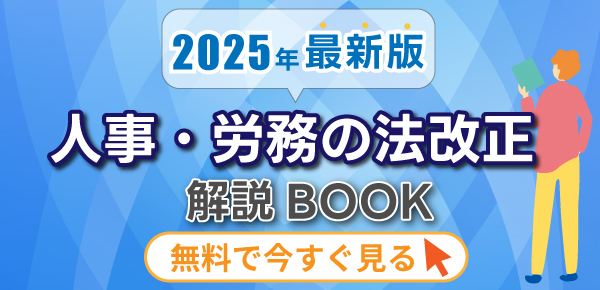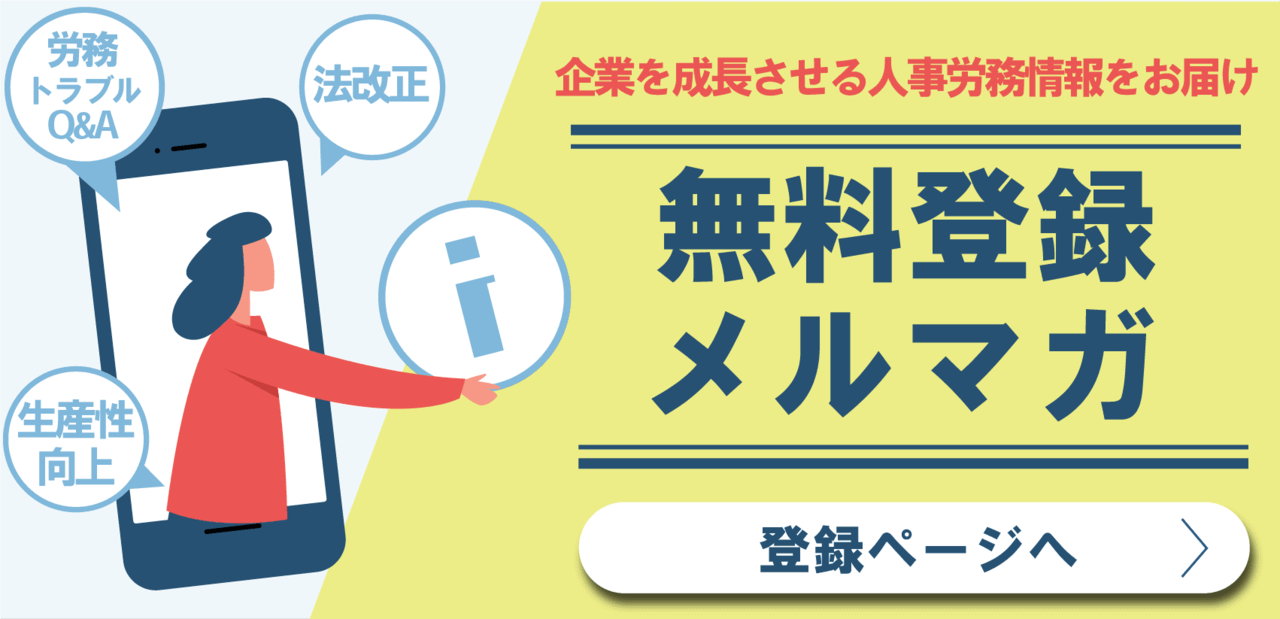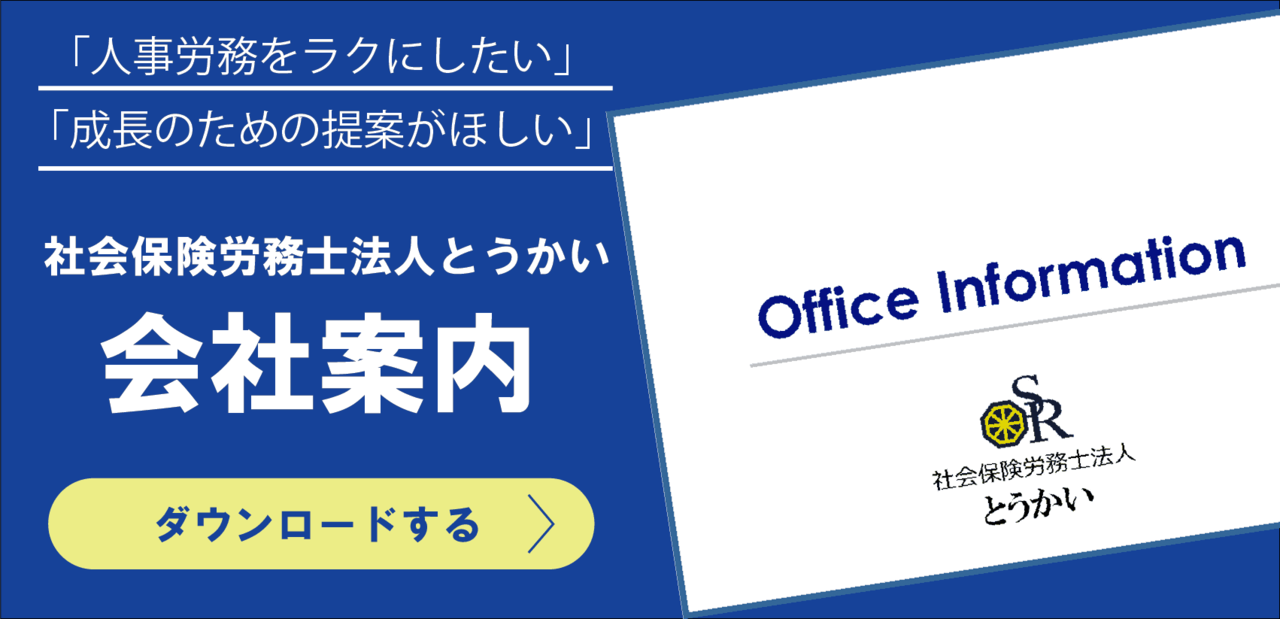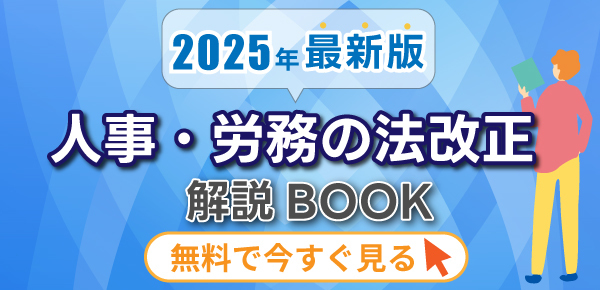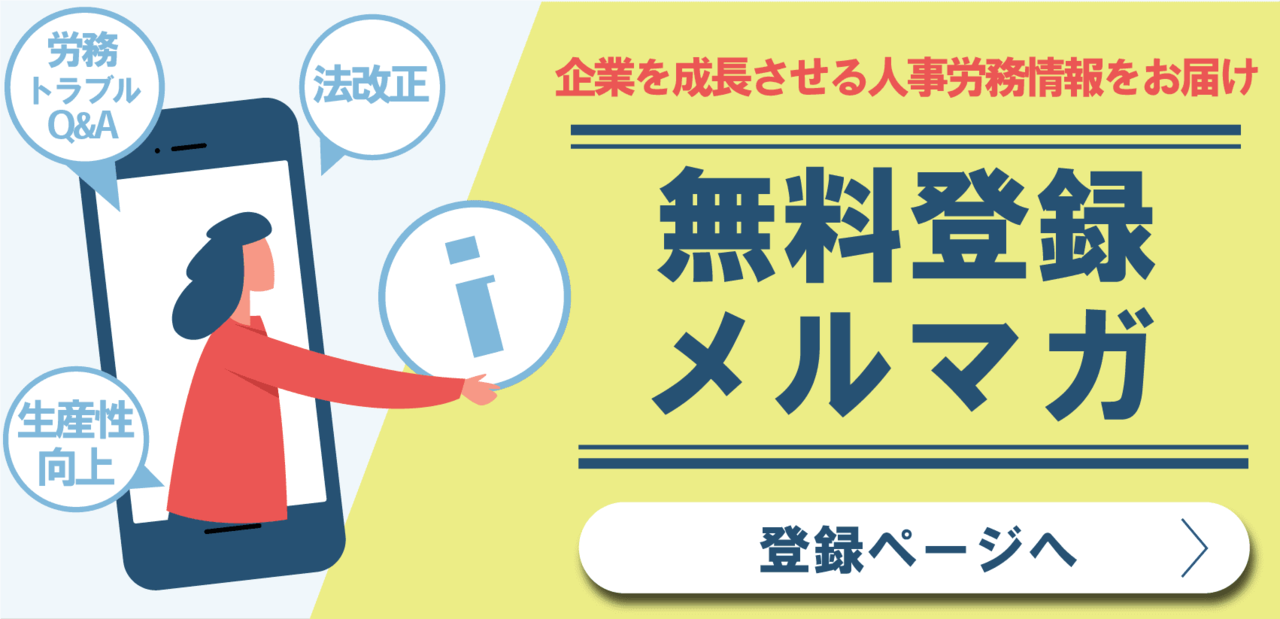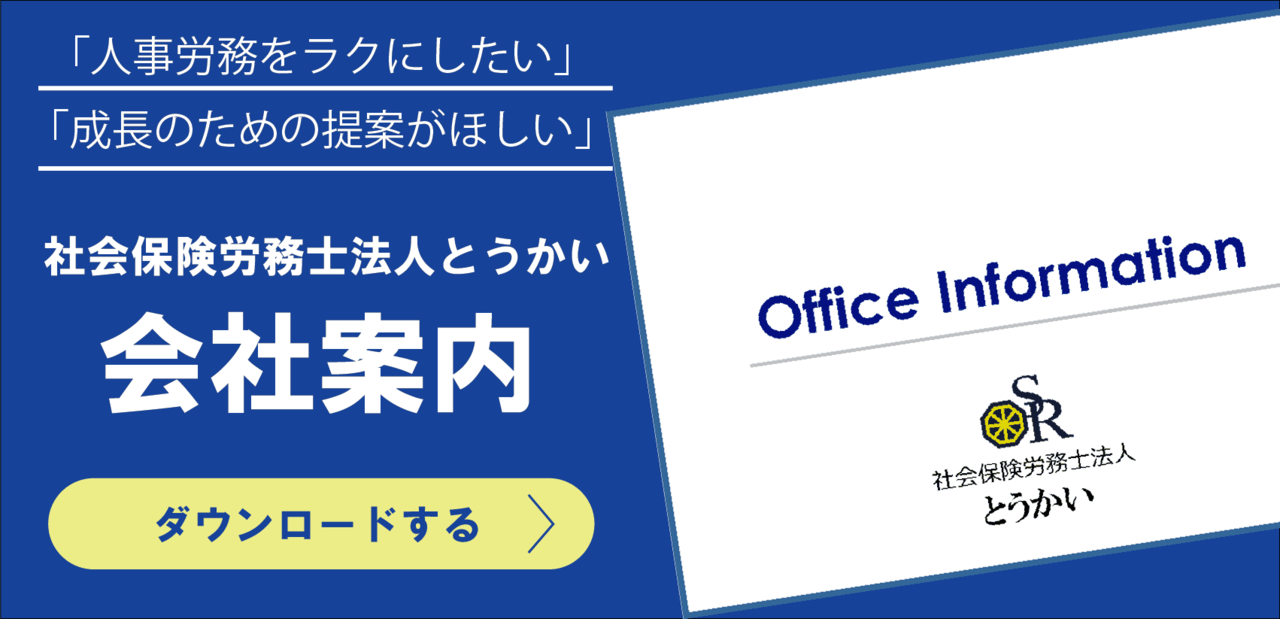業務委託とは?間違えやすい雇用契約との違いや注意点などを解説

業務委託契約は、企業が外部の個人や法人に特定の業務を依頼する形態の契約です。主に、企業が社内で行えない業務を外部に任せることで、専門性を活かし、効率的に業務を進めることが可能となります。併せてコスト削減を図る目的もあるでしょう。ただ、業務委託を活用する一方で、雇用契約との違いを正しく認識・理解していないことから、思わぬトラブルになるケースも少なくありません。業務委託契約は、雇用契約と異なるため、注意が必要です。雇用契約は労働基準法の保護を受ける労働者と企業の主従関係を規定していますが、業務委託契約にはそのような主従関係が存在しません。このため、契約内容や業務の遂行方法などについても、異なる基準が適用されます。雇用契約では、給与や労働条件に関する法律が重要な役割を果たしますが、業務委託契約の場合は契約書に明記される内容が優先され、法的な責任は双方の合意に基づいて決まる点も留意すべきでしょう。
今回は、業務委託契約と雇用契約との違い、注意すべきポイントなどについて解説していきます。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

雇用契約と業務委託契約について解説します。
雇用契約と業務委託契約は、それぞれ企業と労働者または外部業者との関係を構築するための重要な契約形態です。雇用契約は従業員として雇用されることで、企業の指示の下で労働を提供し、対価として賃金を受け取る契約です。この契約に基づいて、労働者は労働基準法をはじめとした法律上の保護を受ける権利があります。一方、業務委託契約は、外部の専門家や企業に特定の業務を依頼するものであり、主として成果物や業務の提供を期待する契約形式です。業務委託契約では、法律上の雇用関係は存在せず、保護も受けません。企業には、業務の成果や納期について明確な取り決めが求められるため契約書が重要になります。
雇用契約とは、企業が労働者を雇い、業務を提供し、労働者が労働に従事する、その労働に対し報酬を支払う約束をするという契約関係です。労働者が企業の指示に従い、決められた勤務時間や場所で働くことで対価として賃金を受け取る仕組みです。雇用契約により、労働者は労働基準法をはじめとした法律に基づき、給与や時間外労働、有給休暇、社会保険など、一定の権利が保障されます。労基法に沿った雇用契約を結ぶことで、労務上のトラブル回避やリスク管理が可能となります。雇用契約を締結する際は、労働条件や仕事内容を明確にし、労働者との契約書を用意しておくことがすすめられます。
業務委託契約とは、自社で対応できない業務や専門性の高い業務を外部の個人や法人に依頼する形態の契約です。業務委託契約は、請負契約や委任(準委任)契約などが含まれます。発注者である企業が求める成果物や業務内容に基づいて、報酬などの条件が設定され、具体的な業務の遂行方法については委託先に委ねられるため、契約を結ぶ際には詳細な取り決めが必要です。業務委託契約においては、報酬は契約書に基づいて支払われ、業務提供の結果により報酬が変動することはありません。雇用契約とは異なり、労働者ではないため、労働基準法などの保護は受けられず、業務遂行に対しての自由度が高い点が特徴です。業務の内容や条件を明確に取り決め、双方の合意のもとで進めることが重要です。

大矢の経営視点のアドバイス
雇用契約と業務委託契約は、本来、明確に異なる契約のはずです。しかしながら、業務委託契約を締結しながらも、従業員のような働き方をしているケースも少なくありません。このようなケースは、後々、大きなトラブルにつながりかねませんので、契約を改めて見直してみましょう。

雇用契約と業務委託契約の違いについてご説明します。
雇用契約と業務委託契約は、働く側と依頼する側との関係性において、明確な違いが存在します。雇用契約は、企業が労働者を雇用し、その労働に対して賃金を支払うという形式をとっています。この契約により、労働者は企業からの指揮命令のもとで働くことになります。一方で、業務委託契約は、特定の業務を外部の個人や法人に委託する契約であり、主従関係はありません。業務委託契約では、依頼者が求める成果や業務の達成を重視し、遂行方法は依頼先に委ねられます。このため、双方が各契約形態の理解を深めることは、トラブルや誤解を避けるためにも重要です。
雇用契約と業務委託契約の違いを理解するうえで、重要な要素が「使用従属性」です。「使用従属性」とは、労働基準法第9条において、労働者に該当する者として①使用者(企業:雇用主)の指揮命令の下で労働を提供すること、②労務の代償として報酬を支払われる、ことと定義されていることによります。雇用契約においては、労働者は企業による指揮命令のもとで働き、出勤時間や勤務場所に対する制約が存在します。また、賃金は労務提供に対して直接支払われるものであり、労働基準法や労働契約法の適用を受けます。これに対し、業務委託契約では、業務遂行に対する企業からの指揮命令は一切なく、委託先の自由度が高まります。つまり、依頼された業務の成果が求められ、その達成のための具体的な方法は委託先が決定します。したがって、業務委託契約は、独立した事業者としての関係が前提となるのです。
業務委託契約には、請負契約や委任(準委任)契約といった2つの分類の契約形式があります。請負契約は、依頼者が指定した仕事の成果物を納品することを目的とする契約です。定めた納期と業務の完成に対して報酬支払われることになります。完成した成果物を納めなければ報酬は支払われないことが一般的です。
一方、委任契約は、最終的な成果だけでなく、業務の遂行そのものに重点が置かれています。業務の進め方にも裁量が与えられます。したがって、委任契約においては、結果に関係なく報酬が支払われることが多いのです。このように、請負契約と委任契約にはそれぞれの特性があり、適切な契約の選択がビジネスの成否に影響を与えることがあります。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
契約形態については、イメージがしにくい部分もあるでしょう。例えば、請負契約であれば、WebクリエイターにWebサイトのデザインを依頼し、サイトデザイン完成が成果物として、報酬を支払うといった具合です。一方、委任契約であれば、弁護士に依頼する場合などをイメージしてみるとよいでしょう。業務を遂行すること自体に対して報酬が支払われることになります。仕事の成果に相当した報酬も支払われますが、成果とは関係なく報酬が発生することになるからです。

業務委託契約と雇用契約のメリット・デメリットを見ていきましょう。
業務委託契約と雇用契約は、それぞれの特性があるように、それぞれのメリットとデメリットがあります。
雇用契約の大きなメリットの一つは、労働者にとっては、安定した賃金を受け取ることができ、生活の基盤を確保できる点でしょう。雇用をされていることで、社会保険の適用をはじめ、定期昇給があったり、福利厚生の充実、退職金制度が存在している企業も多く、長期的な視点からも利益を得やすい特長があります。
また、労働者は労働基準法をはじめとした労働関連法に守られていることで、解雇や不当な待遇から保護される権利があります。
一方でデメリットもあります。企業側にとっては、雇用契約を通じて労働者に対して法的な責任を持つため、雇用契約に伴う事務手続きやコストが企業の負担となる場合もあります。労働者の労働時間や勤務場所の管理が必要となり、労務トラブルが生じるリスクも抱えている面があります。とくに、解雇や残業に関する問題が発生すると、その解決までの時間やコストがかかることになり、経営への影響が少なくありません。このようなリスクがあるため、企業には慎重な雇用管理が求められます。
業務委託契約は、企業が特定の業務を外部に依頼することになるので、多様なメリットがあります。まず、専門的なスキルを持ったフリーランスや他社に業務を委託することで、質の高い成果物を期待できる点が挙げられます。また、必要な時だけ業務を発注することができるため、業務の柔軟性が高まり、コストの最適化につながるでしょう。
しかし、デメリットも存在します。業務委託を依頼するには信頼できるパートナーでなければなりません。自社にマッチする委託先を見つける必要があるため、契約内容の交渉や取り決めに手間がかかる一面もあります。また、指揮命令系統があるわけではないので、業務の進行状況を正確に把握しづらい点も問題視されています。成果物が納期内に提供されない場合には、企業の業務に直接的な影響を与える可能性も高くなるでしょう。業務委託契約を利用する場合には、リスクを十分に理解した上で適切な契約を結ぶことが求められます。
雇用契約と業務委託契約には、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。しかし、企業がこれら契約形態ごとのメリットデメリットを理解し活用することで、より効果的な人材配置や業務遂行が可能になります。例えば、従業員を雇用契約で雇い入れ安定した業務を提供しつつ、特定の専門的な業務を業務委託契約で外部に任せることによって、柔軟性を持った運営が実現します。
トラブルを避けるためには、双方の契約における条件を明確にし、業務内容や責任範囲をしっかりと記載することが重要です。これにより、企業はより効率的かつ効果的な人材活用やリソース管理が可能になることが期待できるでしょう。

雇用契約と業務委託契約の同時契約について解説します。
雇用契約と業務委託契約を同時に結ぶことは、企業にとって柔軟な人材管理の手段となります。雇用契約を結んだ従業員が、同時に外部の業務を委託される場合、通常、その業務は本業以外の役割となることが多いです。この形態を利用することで、企業は必要な専門知識やスキルを持った人材をその都度確保できるメリットがあります。
一方で、業務委託契約を結ぶ際には、労働者の権利と企業の義務がどう分かれるのかが重要なポイントになります。明確な業務範囲や報酬条件を設定し、誤解を避けるための契約書を用意することが必要です。また、雇用契約による労働法上の規制が適用される場合があるため、業務委託契約が雇用契約とみなされないように配慮が求められます。
自営型のテレワークにおいては、業務委託契約が特に重要な役割を果たします。自宅で働く環境を持ちながら、企業から特定の業務を受託することが可能です。例えば、翻訳やデザイン業務など、成果物が明確に定義されている場合、アウトソーシングの形で効率的に業務を進められます。
テレワークを活用することで、場所にとらわれない働き方が実現し、企業側はオフィスコストを削減することが期待されます。ただし、業務委託契約においても権利が保障されていることを意識する必要があります。契約内容や条件が不明確な場合、後にトラブルに発展する可能性があるため、事前の取り決めや合意をしっかりと行っておくことが大切です。

鶴見の経営視点のアドバイス
雇用している従業員と、特定の業務範囲において業務委託契約を結ぶケースもあります。いわば雇用契約と業務委託契約を同時に締結することになりますが、業務範囲に重複する部分があれば、雇用の延長とみなされてしまいます。明確な線引きができるか慎重に判断してください。

直接雇用と業務委託の判断基準についてお話しします。
直接雇用と業務委託の判断基準にはいくつかの重要な要素があります。雇用契約と業務委託契約は、この判断基準に基づいて契約形態が決まります。もっとも基本的な判断基準が「使用従属性」です。業務を遂行する者が企業の指示や管理にどの程度従う関係にあるかを示しており、業務を行う際の自由度が直接雇用と業務委託の選定に影響を与えます。よって、作業場所、時間、方法に対する支配権が大きいほど、使用従属性が強くなり、雇用契約と見なされる可能性が高まります。最近では、あたかも従業員のように働いているものの、実は契約としては業務委託契約として扱われ、労働者としての法律上の保護を受けられていないケースも問題となっています。
使用従属性を判断する際には、いくつかの具体的な要素が考慮されます。まず、業務を遂行する際の指示の有無やその内容が重要です。企業が業務の進行方法について詳細に指示を出している場合、使用従属性が認められる可能性があります。
次に、勤務時間や勤務場所に対する制約が関わってきます。特定の時間に出勤し、決められた場所で業務を行う義務がある場合、雇用契約に基づく関係が成立します。さらに、報酬の支払基準や、業務内容に対する代替性や変更の自由度も使用従属性の判断に影響を与える要素として重要です。
直接雇用と業務委託の契約形態によって、報酬の基準も大きく異なります。雇用契約においては、賃金が時間単位や月額で支払われるのが一般的で、労働時間に基づいて変動します。残業代を支払っている、欠勤すれば給与から控除されるなど、賃金として扱われている場合には雇用されていると判断されるでしょう。雇用契約は、労働基準法に基づいた最低賃金や残業手当が適用され、労働者は法律により保護されます。
対して、業務委託契約では、業務の成果に対して報酬が支払われることが一般的です。請負契約の場合、業務を完了し納品した時点で報酬が発生し、作業の内容や成果によって金額が決まります。これにより、業務の遂行方法や使用する手段に対して自由度が増す一方で、労働者としての法律による保護はないため、リスクを考慮した適切な契約が求められます。

:業務委託契約が雇用契約と判断された場合のリスクを見ていきましょう。
業務委託契約が、実際は雇用契約であると判断される場合、さまざまなリスクが発生します。まず、雇用契約と認定されれば、企業側は労働基準法に基づく法的義務を果たさなければなりません。例えば、社会保険や労働保険の加入、年次有給休暇の付与などが求められ、これに対応する事務負担やコストが発生します。
また、契約内容に関しても注意が必要です。業務委託契約書を取り交わしているにもかかわらず、使用従属性が認められた場合、契約書に記載された条件や業務の範囲が適用されなくなります。労働者側が不当な扱いを受けたと訴えた際、企業は契約上の責任を果たさなければならず、その結果、企業の評判や信頼性が損なわれる恐れもあります。さらに、雇用契約と見なされれば、解雇や労働条件の変更に関する法律が適用されることになり、企業はその対応に多くの時間と労力を割く必要が生じます。これにより、業務の効率が低下し、経営に対する影響も無視できないものとなります。したがって、契約締結時から、適切な契約形態を選ぶことが極めて重要です。

副業における雇用契約と業務委託契約について解説します。
副業を行う際には、雇用契約と業務委託契約のどちらを選択するかが重要なポイントとなります。最近では副業を行う、本業とは別に仕事を持つ機会も増えてきました。副業を行う際にも、どのような契約形態を選択するのか理解しておく必要があるでしょう。そもそも雇用契約を結んでいる本業の企業の他に、副業として雇用契約を結ぶ場合、本業である主たる雇用先に副業を報告することになるでしょう。会社の規定によっては、副業について制約を設けていることがあるため、副業を行う場合にはあらかじめ確認しておくことが求められます。
対して、業務委託契約の場合は、特定の業務を外部に依頼する形態であり、働き方に対する自由度が高くなります。実績に基づいて報酬が支払われるため、成果次第で一定の収入を得ることができる可能性があります。しかし、法的な保護が薄いため、労働基準法に基づく保障は受けられません。この点を考慮すると、業務委託契約を選んだ場合、自身の業務内容や報酬の取り決めを明確にしておくことが重要です。
副業をする場合は、働き方や契約形態によって法的なリスクや収入の安定性が異なります。自分に合った形を選び、事前にしっかりと準備を整えることで、円滑な副業ライフを実現できます。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」