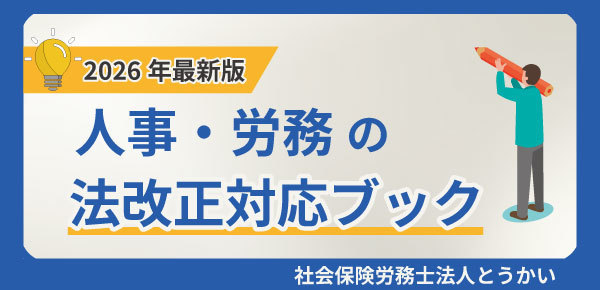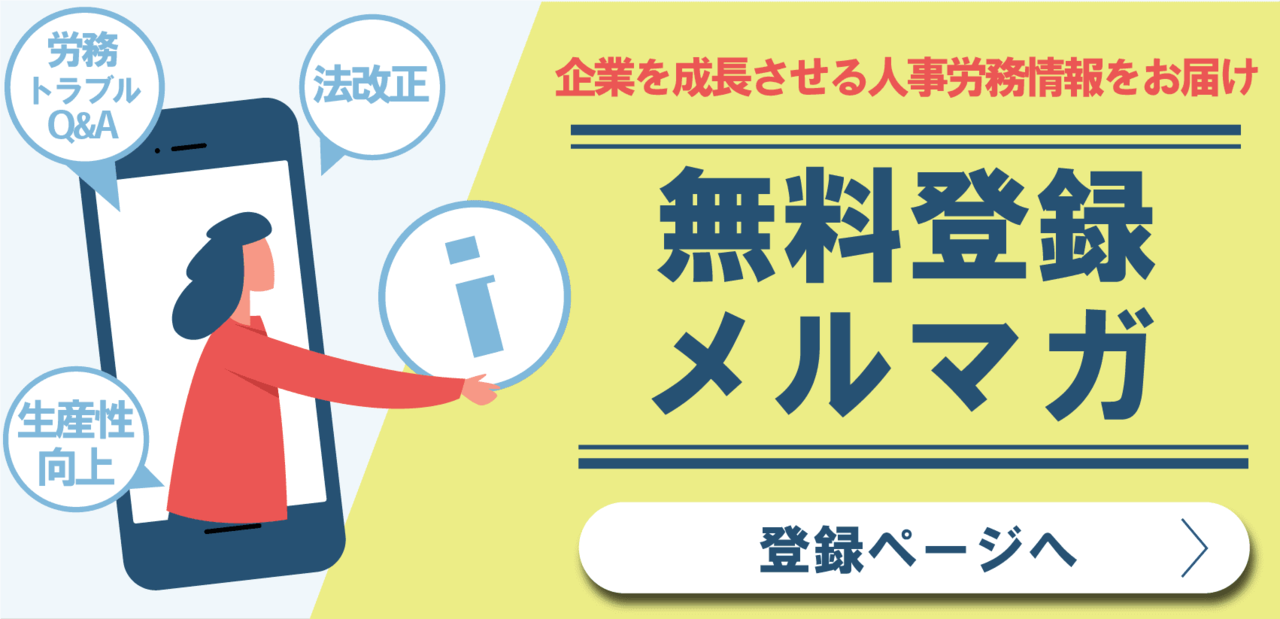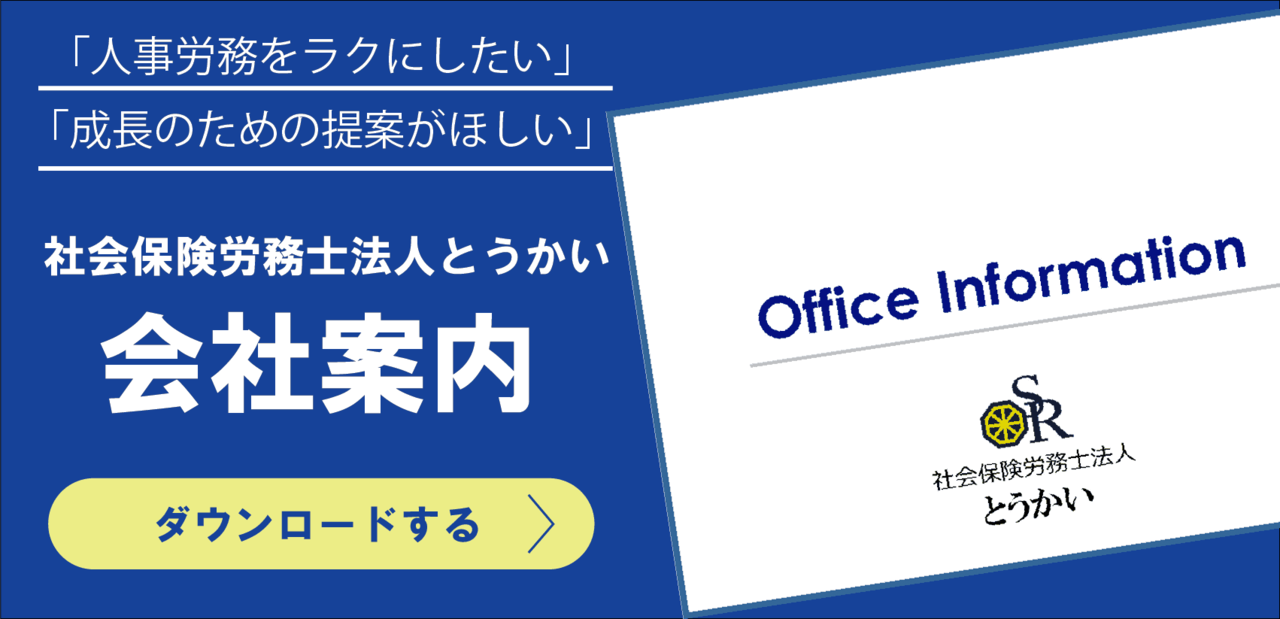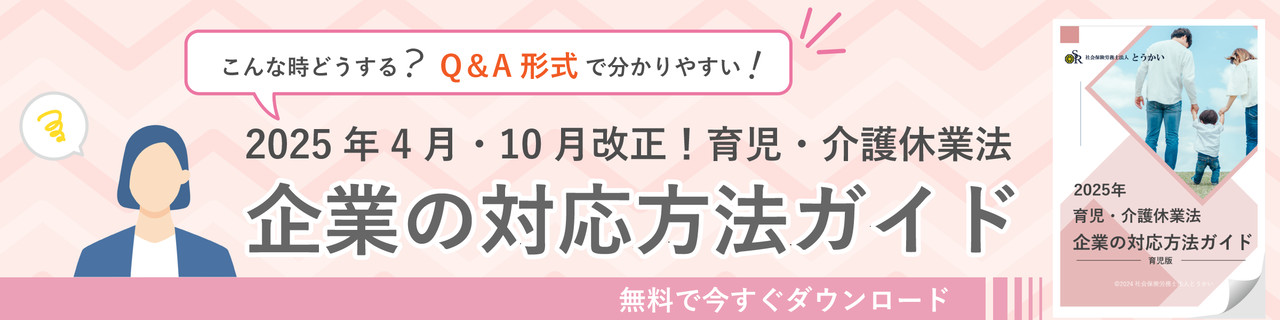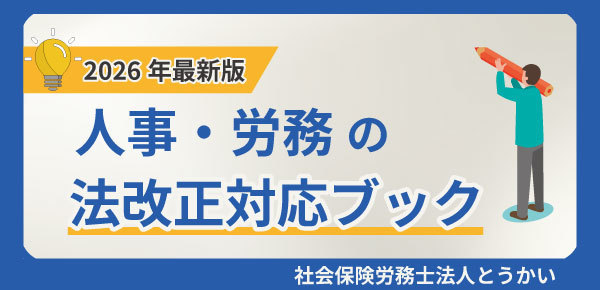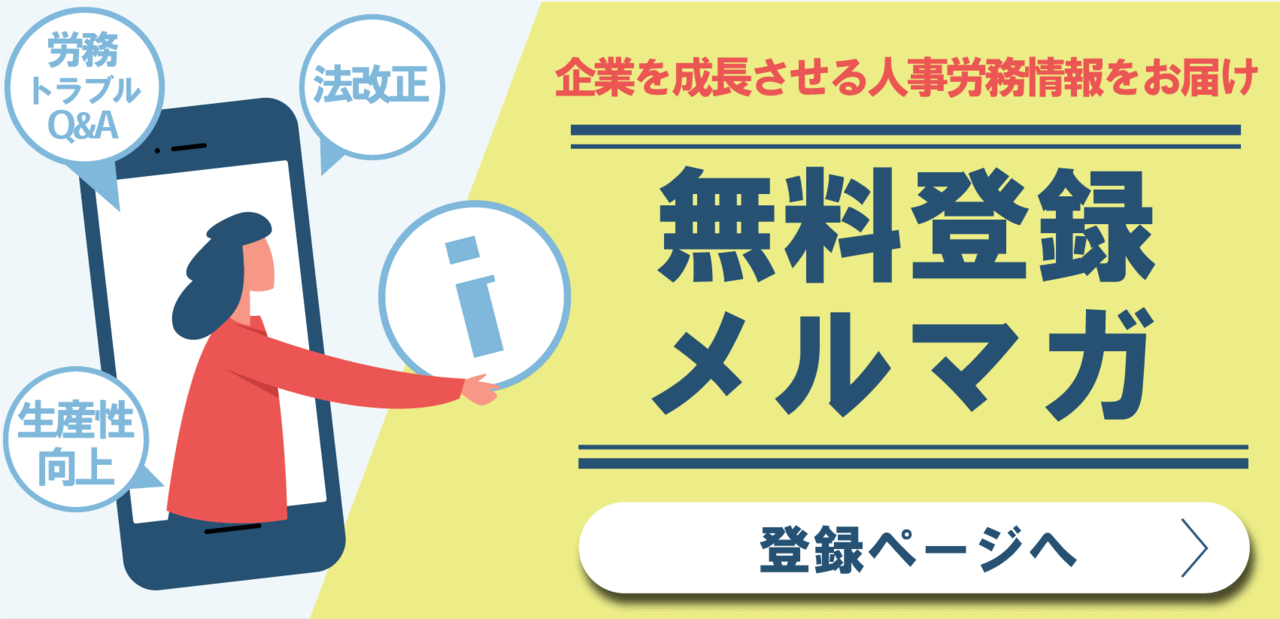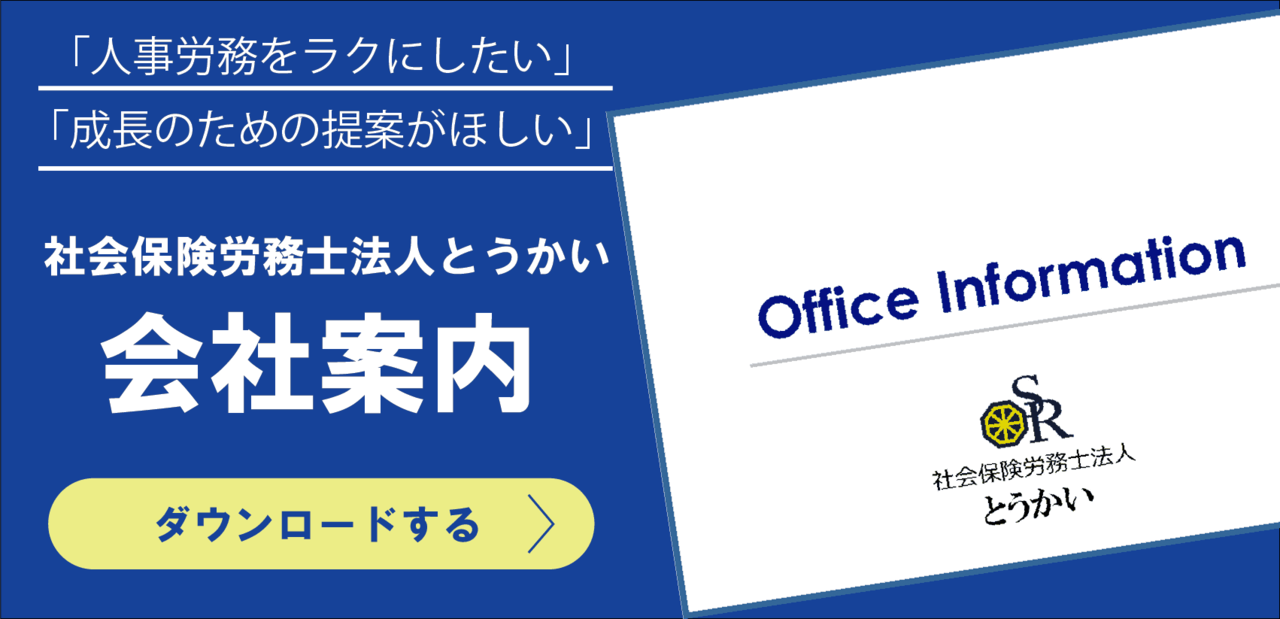社会保険適用促進手当とは?
「年収の壁」対策の概要と条件、課税への影響を解説

社会保険適用促進手当とは、短時間労働者を支援し、働きやすい環境を整えるために設けられた制度です。いわゆる「年収の壁」、すなわち106万円や130万円を超えた際に生じる社会保険料負担の増加によって、短時間労働者が就業調整を行い、結果、労働力の不足が生じていると問題視されています。そこで、従業員が新たに社会保険に加入する際の負担を軽減し、保険料を支払いながらも手取り収入を確保できるような配慮として、社会保険適用促進手当があります。
社会保険適用促進手当は、短時間労働者にとっての働くメリットを高めると同時に、長期的な社会保険加入を促進する重要な制度と言われています。短時間で勤務する従業員を多く抱える企業については、従業員の安定した働き方と生活水準の向上に向け、制度内容を理解しておきましょう。
この記事の監修
社会保険労務士法人とうかい
社会保険労務士 小栗多喜子
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
・NHK「あさイチ」
・中日新聞
・船井総研のYouTubeチャンネル「Funai online」
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから

社会保険適用促進手当の基本概要を詳しく解説します。
社会保険適用促進手当は、年収の壁を意識せずに働ける環境を整えることを目的に設けられた制度です。短時間労働者の社会保険加入を妨げる要因となる保険料負担の増加を緩和する役割を担っています。短時間労働者の多くは、年収の壁を超えると社会保険料に加入することとなり、社会保険料の負担増が手取り収入の減少につながるため、働く意欲や時間を制限する要因となりかねません。そこで、短時間労働者の就業調整課題を解消するため、事業主が新たに社会保険に加入した従業員に対して、社会保険適用促進手当を支給します。社会保険適用促進手当を支給することで、従業員の手取り収入の減少を抑えることができるようになります。これまで就業調整を行なっていた短時間労働者にとって働きやすい環境が整備され、社会保険加入の拡大が期待されているのです。労働環境の合理的な見直しにもつながり、短時間労働者の権利保護や長期的な生活の安定化にも貢献できるか期待が寄せられています。
社会保険適用促進手当は、短時間労働者である従業員が、新たに社会保険に加入した場合に、社会保険料の負担を軽減するための取り組みの一つです。社会保険適用促進手当の支給によって、従業員が新たに加入した社会保険に伴う社会保険料の一部を事業主が実質的に代わりに負担する形となります。本来従業員が負担する社会保険料を事業主が負担することで、従業員の手取り収入減少を抑えることができるのです。結果として従業員は安心して働き続けることができます。社会保険加入により、手取り減少に対する懸念を払拭し、従業員の働く意欲を高めるとともに、働き控えによる人材不足の解消に期待が寄せられています。

大矢の経営視点のアドバイス
社会保険適用促進手当を支給する場合には、就業規則等に規定する必要があります。記載の方法など、疑問があれば、社労士などにご相談ください。

「年収の壁」とは何かを詳しく解説します。
「年収の壁」とは、パートやアルバイトなど短時間労働者の年収が、一定のボーダーラインを超えると、所得税や社会保険料の負担が発生することとなり、手取り収入が減少することから表現されています。この年収の壁は103万円、106万円、130万円などがあり、所得税に関わる壁が103万円、その他社会保険に関わる壁が106万円、130万円の2つ存在します。これら年収の壁は、手取り収入への影響があることから、短時間労働者の働き控えなどが生じ、自由で柔軟な働き方を阻む一因とされています。
106万円の壁と130万円の壁は、社会保険上のボーダーラインです。
まず、106万円の壁は、従業員が51人以上の勤務先で働く場合、年収がこの額を超えると社会保険への加入が求められます。パートやアルバイトとして働く方も社会保険に加入し、被保険者として取り扱われることになります。厚生年金保険や健康保険、介護保険などの加入が義務付けられます。給与から社会保険料が控除されるため、結果として手取り収入が減少する可能性があります。そのため、多くの短時間労働者が収入と労働時間を慎重に調整する状況が見られます。106万円を意識し働き方を調整する大きな理由となっています。
次に130万円の壁では、勤務先が50人以下であっても、年収がこの水準を超えると勤務先の社会保険に加入する必要が生じます。社会保険料の負担が増加するという経済的な影響に加え、貯蓄や将来の計画にも影響を及ぼす可能性があります。とくに扶養控除の適用を受けている家庭においては、扶養から外れることで社会保険や税制面での両方の待遇が変わり、家計全体の収支に影響を及ぼす場合があります。
これらの壁は、働き方や収入調整に際して労働者にとって重要な意思決定の要素となっており、その選択が生活や将来設計に直結する問題となることが注意すべき点です。
被扶養者で仕事をする人にとって、年収の壁は非常に重要なテーマです。とくに106万円の壁を超える場合、所得税法上の扶養から外れることにより税負担が増えること、社会保険の加入が必要になることから、社会保険料を負担することになります。年収の壁ギリギリのラインで働いている人にとっては、手取り収入が大きく減ることにもなりかねません。このため、扶養を維持したい被扶養者は、収入を増やしたい気持ちがあっても、生活費負担を懸念し労働時間や給与を制限するジレンマに直面することがよくあります。厚生年金保険の加入においては、将来の年金受給額が増加するメリットがあるものの、短期的な生活費の負担を考えると、就業調整をするといった選択をするケースが多いのです。こうした状況は、働き方やキャリア選択にも影響を与える要因となります。将来的な年金の受け取り額や老後の生活設計にまで影響を及ぼします。

大矢の経営視点のアドバイス
103万〜130万円まで、さまざまな年収の壁があることで、最近のニュースでも議論を呼びました。数字のからくりの議論ではなく、働きたい人が、制度のうえで働き損にならないしくみ作りを目指したいものです。

社会保険適用促進手当の対象者と条件を確認しましょう。
社会保険適用促進手当は、短時間労働者を対象とした支援策として設けられており、適用基準が定められています。
手当の恩恵を最大限に活用するためには、自身の賃金や雇用条件を十分に確認し、制度が定める基準を正確に理解することが重要です。
社会保険適用促進手当の対象者は、新たに社会保険に加入した従業員であり、標準報酬月額が10.4万円以下に限定されています。
標準報酬月額が11万円以上の場合には、保険料負担増によって手取り収入が減少しても手取り年収は106万円を超えるため、適用対象外となります。
社会保険適用促進手当は、新たに発生した従業員本人負担分の社会保険料相当額を上限として支給されます。また、支給される期間は、最大2年間となっています。
短時間労働者を含む働き手が安心して働ける環境が整備され、雇用の安定と仕事への意欲を向上させる効果が期待されています。この仕組みが事業所規模を問わず広がることで、多くの働く人々が支えられています。

社会保険適用促進手当のメリットを見ていきましょう。
社会保険適用促進手当は、従業員だけでなく、企業側にも一定のメリットが期待できる制度です。短時間労働者にとっては、手取り収入の減少を抑え、働く意欲を高める大きな支援策となっています。従業員は社会保険料の負担が軽減され、経済的な安定を図りやすくなります。
一方、企業側にとっても、人材の流出の防止や、新たな人材確保が容易になり、職場環境の改善につながります。人材不足に悩んでいる業界では、従業員が安心して働ける環境を整えることが競争力の強化にもつながります。社会保険適用促進手当は、従業員と企業の両者にとって有益な制度として評価されています。
社会保険適用促進手当は、社会保険料への直接的な影響があります。従業員が新たに負担する社会保険料を、代わって社会保険適用促進手当として事業主が負担することで、従業員の手取り額の減少を軽減することが可能になります。従業員は社会保険適用促進手当が支給されたとしても、社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額や標準賞与額の算定対象には含みません。つまり、会社側も従業員側も社会保険料の負担を軽減できるというわけです。ただし、手当が算定基礎に含まれないとはいえ、他の収入に関連する税負担は依然として残るため、注意が必要です。手取り収入が一時的に維持されても、保険料の負担軽減以外に課せられる税金を考慮する必要があります。最終的な収入と支出のバランスを把握し、自身の収入状況を見直しながら最適な就労計画を立てることが重要です。
短時間労働者への就労促進も、社会保険適用促進手当の大きなメリットです。一定条件を満たした短時間労働者にとっては、社会保険料負担を軽減する大きな助けとなります。これにより、短時間労働者が安心して働ける環境が整い、仕事に対する積極的な姿勢を育む効果が期待されます。この手当を受けることで、短時間勤務の制限や負担が軽減されるため、働き方を見直し、より多くの時間を仕事に割くことも可能になります。結果として企業にも恩恵をもたらします。企業側は必要な人材を確実に確保でき、業務のスムーズな遂行が可能となるため、組織としての持続的な成長が促進されます。このような循環こそが、個人と企業、さらには社会全体の活性化を実現する鍵といえるでしょう。

社会保険適用拡大による課税への影響を確認しましょう。
2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大され、これまで対象外だった短時間労働者も社会保険の加入対象となることが増加しました。ただし、社会保険の適用拡大は、年収の壁にも関係して、税制面にもさまざまな影響があります。社会保険に新たに加入することによって所得税や住民税に与える影響が注目されています。社会保険に加入すると、その分所得が増えることになりますが、年収の上昇に伴い、税負担も増加することが一般的です。
これにより、中長期的には手取りの収入が減少する可能性があり、労働者にとって不安要素があることは否定できません。特に、年収が106万円や130万円の壁を超えると、税額に変動が生じ、経済的な負担が増えることが懸念されています。このため、適用拡大による課税の影響をしっかりと考えておくことが求められます。
所得税と住民税は、年収に基づいて課税されるため、社会保険の適用拡大がこの二つの税にどう影響するのかが重要なポイントです。従業員は雇用契約の内容や勤務時間をしっかり管理しなければならなくなります。従業員にとっては働き方の選択が重要であり、自身の経済状況や税負担について理解を深める必要が生じてきます。

コンサルタント中村の経営視点のアドバイス
社会保険の適用拡大により、パートやアルバイトを掛け持ちや、副業などを行なっている人は二重加入になってしまうケースもありますので、注意が必要です。社会保険は、将来の年金にも関わりますので、疑問点があれば早めに勤務先に相談するなど解決しておきましょう。

社会保険適用促進手当は、短時間労働者にとって非常に重要な制度です。手当の支給期間は最大2年間ということもあり、どれだけの効果を発揮するのか引き続き注目すべきところではありますが、昨今の物価上昇などに伴い、働く意欲のある人が増えるなか、短時間労働者の経済的な不安軽減や、安定した生活基盤を築く手助けとなればと期待されています。短時間労働者の働き方には、税負担、社会保険の適用など、年収に応じた変化を理解し、しっかりと対策を練ることが求められます。ただ、実際には、複雑に影響し合っている部分も多く、わかりにくいといった現状もあります。パート・アルバイト従業員を多く抱える企業担当者の方で、制度の疑問、不安に感じていることなどありましたらお気軽にご相談ください。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」