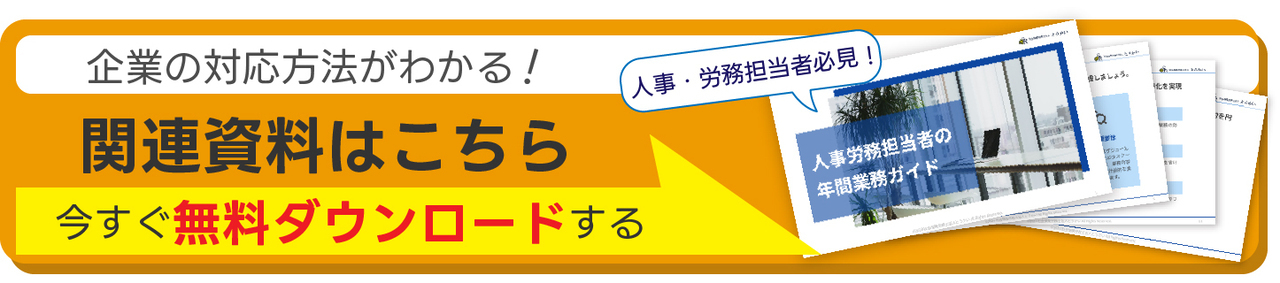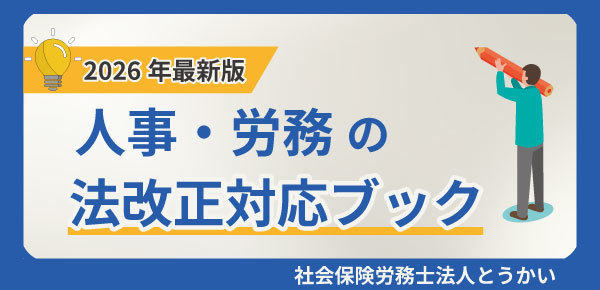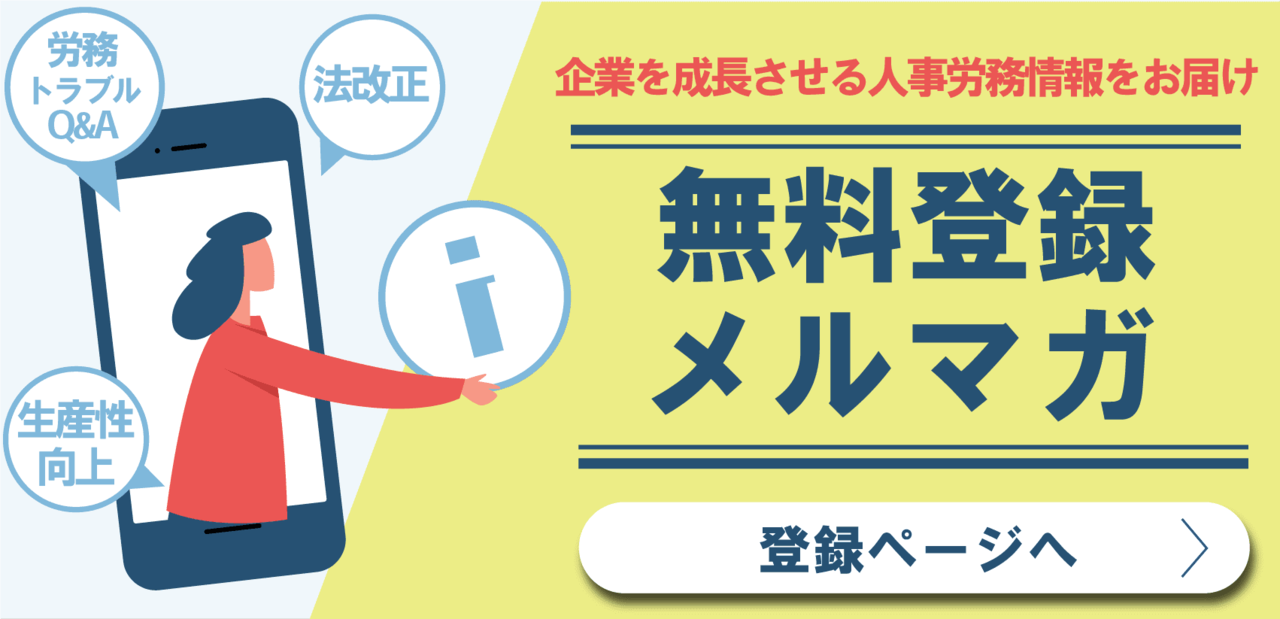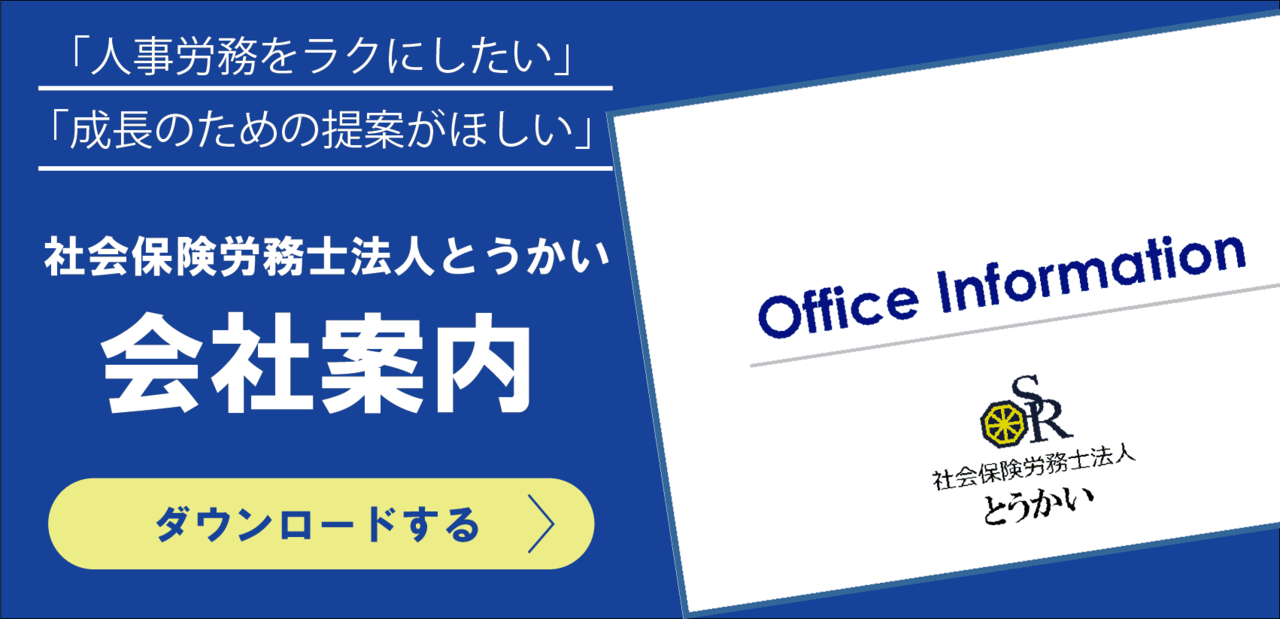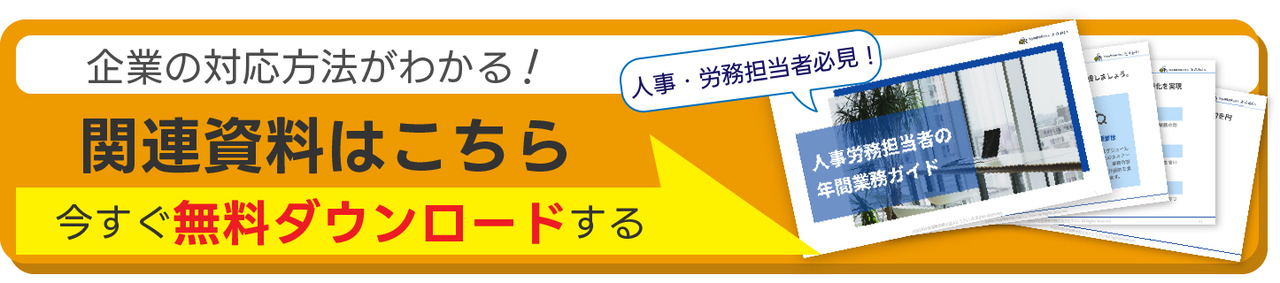就業規則とは?社会保険労務士が分かりやすく解説します。

就業規則とは、事業場ごとに作成される、雇用主と労働者の間の雇用に関するルールを定めたものです。労働基準法89条より、常時10人以上の労働者を使用する雇用主は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。法律上では、労働者の数が10人未満であれば作成義務や提出義務はありません。
しかし、労働者が安心して働ける職場を作ることは事業規模や業種を問わず、企業を成長させるためには、すべての事業場にとって重要なことです。そのためには、予め就業規則で労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。しかし、会社の規模や業態、経営状態によって定めるべきルールは異なります。会社を成長させるためには、それぞれの会社に合った就業規則の作成が必要です。
就業規則の専門家である社労士が作成から運用までのポイントを徹底的に解説します。
目次
- 就業規則とは?就業規則の基礎知識
- 就業規則の作成義務と就業規則を作成するメリット
- 就業規則と労働契約の違いは?その関係性について分かりやすく解説します。
- 就業規則と労働協約の関係は?労働組合がある場合の対応方法
- 就業規則における労働時間。労働時間について社会保険労務士が分かりやすく解説します。
- 就業規則のテンプレート大活用!社会保険労務士が就業規則のひな形やテンプレートのカスタマイズの仕方について解説します。
- 就業規則の周知の方法。労働者代表の選出の仕方はどうすればいい?
- 就業規則の作成方法と相場について。失敗しない就業規則の作成について解説します。
- 就業規則の不利益変更。トラブルになりにくい不利益変更の仕方について解説します。
- 固定残業制度と就業規則。固定残業制度を導入する際の就業規則の注意点。
- 就業規則と残業申請制。残業申請制を取り入れる際の注意点について社会保険労務士が分かりやすく解説します。
- 就業規則への副業の規定の仕方を社会保険労務士が解説します。
- 就業規則の退職・解雇の規程の作り方。労務トラブルを回避する規程の作成方法とは?
- ストレスチェックと就業規則。就業規則の変更方法について社労士が解説します。
- 知らないとこわい同一労働同一賃金。労務トラブルを防ぐ就業規則の規程方法について社労士が解説します。
- 就業規則とパワハラ防止法 2020年4月施行(予定)を前に社労士が解説します
- 外国人雇用のためにまず整備すべき就業規則。外国人雇用に対応した就業規則の作成方法を社労士が解説します。
- 就業規則とテレワーク。テレワーク制度導入のための注意点について社労士がわかりやすく解説します。
就業規則はなぜ必要なのか?

就業規則の目的
「従業員の数が増えてきたので、就業規則をそろそろ作りたい」当社にもこのようなご相談がよくあります。しかし、就業規則は会社と従業員のルールです。会社として従業員に対してどのように働いてほしいのか?を就業規則の中で表現しなければ、ルールそのものが形骸化してしまいます。就業規則は法的な拘束力を持ちますので、意思のない就業規則の作成はトラブルを引き起こしてしまうのです。
そして就業規則は、経営者が従業員に対してどのように働いてほしいのか?のメッセージが込められているだけではなく、コンプライアンスの観点からも法的に対応したものでなければなりません。
就業規則は経営者と従業員のルールブックです。よく経営者のための就業規則や従業員のための就業規則というフレーズを聞きますが、就業規則は経営者・従業員・法律の3つの視点からどうすれば会社が成長するのかを考えて作成するべきなのです。
経営者のメリット
就業規則は会社から従業員への「どのように働いてほしいか?」というメッセージです。
会社のルールを定めることは会社の価値観を従業員と共有することです。テンプレートやひな形でも法律的な作成、届出の義務は満たされるかもしれませんが、経営者の意思の入っていない就業規則では、従業員が楽しく働き、企業を成長に導けるとはいいがたいでしょう。
従業員に対するメッセージをこめることで、企業を成長に導けるのです。
また、就業規則が存在することで、使用者と従業員の間のトラブル防止にも繋がります。
例えば、従業員が業務上、不誠実な行いをした場合でも、懲戒免職や減給の定めが就業規則にないと、懲戒解雇をすることができません。
就業規則に定めらているルールがあるからこそ、事前にトラブルを防げるのです。
従業員のメリット
就業規則は労働条件や賃金その他について包括的にまとめた会社のルールです。
就業規則がなければ、同じ会社にも関わらず、一人ひとり適用される労働条件が異なってしまうことがあります。少人数であれば、経営者が一人ひとりに合わせて労働条件を設定することもできるでしょうが、組織を成長させるためにはルールが必要です。基準を設定することで従業員は安心して働くことができるのです。
法的な視点
労働基準法89条より、常時10人以上の労働者を使用する雇用主は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。法律上では、労働者の数が10人未満であれば作成義務や提出義務はありません。
ですが、昨今はハローワークでの新卒求人を行う際に、就業規則、賃金規程の有無を確認されるなど、法的な義務ではありませんが、10名未満でも届出を行っておくべきであるでしょう。
会社を成長させる就業規則とは?

ひな形は規模に関わらず作成されています。もし、一度有効な就業規則として作成してしまうと、あとで困ったとしても、不利益変更等に該当する場合は変更が難しくなります。
企業独自の就業規則が大切
就業規則は、経営者と従業員の約束事です。そこにはどのように働いてほしいかという思いと従業員のどのように働きたいという2つの思いが詰まったものでなければなりません。
よく中小企業で、インターネットからひな形をダウンロードしたものをそのまま使っているケースがあります。もちろん法的な知識のもと正しく作成されていれば問題はありませんが、何も考えずに、とりあえず作成しているのであれば直ちに改定すべきでしょう。
会社は人の集合体です。そのルールに意思は入っていないのであれば、会社は成長しないでしょう。経営者の意思と従業員の意思の2つの意思を就業規則にこめるからこそ会社は成長するのです。意思のはいった自社独自の就業規則を作成しましょう。
時代に合った規則を作成することが大切
就業規則は一度作って終わりではなく、その時代に合わせて改定を続ける必要があります。労働関係法令の改正に対応することも必要ですが、それに加えて、組織の在り方や従業員の考え方など時代に合わせて人事戦略そのものが変わります。その都度改定を行う必要はありませんが、大きな法改正や会社のステージが変わったとき、事業承継の発生などでは改定を行うべきでしょう。
2019年4月から働き方改革関連法が順次施行されます。この改正は労働関連法70年ぶりの大改正と言われており、就業規則の改定を行った方がいいケースが多いです。時代に合わせて人は変化します。だからこそ就業規則も時代に合わせて変化させていくべきなのです。
就業規則の作成義務と義務を履行しない場合のリスク。また、10名未満の場合でも就業規則を作成するメリットについてわかりやすく解説します。
就業規則に書いてある労働時間と雇用契約に書いてある労働時間が違う?こんなときはどちらを信じたらいいの?本来あってはならないことですが、こういったケースは多くみられます。就業規則と労働契約書の関係性について社会保険労務士が分かりやすく解説します。
就業規則が会社・従業員ともに、きちんと運用されていくには、お互いの取り決めや合意形成が必要となってきます。そのために、重要なのが、使用者と労働組合が取り決める「労働協約」、労働組合がない場合は、会社と労働者の過半数代表者との取り決めである「労使協定」です。
今回は、この「労働協約」と「労使協定」の違いに着目して、解説していきます。
「就業規則」を作成するうえで、押さえておくべき重要な事項が、「労働時間」。とくに、2019年4月より「働き方改革」が施行が始まり、企業の労働時間の把握が義務化されるなど、労働時間の把握がより厳密に求められることになりました。今回は、「労働時間」について、詳しく説明していきます。
「就業規則」は会社と従業員の約束事です。就業規則はさまざまなルールが記載されている大切なものです。
今回は、就業規則の作成後、従業員への「周知」に着目し、周知の方法や注意すべきポイントについて解説します。
就業規則のひな形はどう使えばいいの?テンプレートがインターネットでダウンロードできるけどどう使えばいいの?など、テンプレートやひな形、最近では、選択肢にこたえると就業規則ができあがるものまであります。それらの活用方法を社会保険労務士が専門家の目線で解説します。
就業規則はどれも同じではありません。専門家に頼む場合、ひな形を使う場合などさまざな方法が考えられます。それぞれのメリットとデメリットなど費用との関係も含めて解説します。
- 9
就業規則の不利益変更 トラブルになりにくい不利益変更の仕方について解説します。
就業規則の不利益変更は原則として禁止です。不利益変更は行わないにこしたことはありませんが、経営上仕方なく行わざる得ない場合もあります。
今回は、一方的な不利益変更や従業員の同意が得られない不利益変更が理由で、大きなトラブルにならないよう、不利益変更の基本的な知識を解説し、正しい方法で不利益変更を進めていただくヒントにしていただけたらと思います。
固定残業制度は残業時間削減にもつながる制度ですが、労務トラブルが多い制度であることも事実です。固定残業制度をどうすれば円滑に運用できるのか?社会保険労務士が分かりやすく解説します。
「働き方改革」の中で、重要テーマとして挙げられる長時間労働の削減。そのための施策として、従業員が残業を予め事前に申請し、それに対して上司(会社)が承認した場合にのみ残業を行うという「残業申請制」の仕組みを取り入れている会社もあります。今回は残業申請制について、導入する際の注意点などについて解説していきます。
大手が副業解禁をしているからと深く考えずに副業を解禁することは危険です。副業解禁に伴うメリットやデメリットを社会保険労務士が分かりやすく解説します。
労働は生活と密接に関係しているため、解雇や退職に関しては多くの労務トラブルが発生しています。すべてではありませんが、就業規則に規程しておくことで防げるトラブルもあります。トラブルの事案も交えながら社会保険労務士が分かりやすく解説します。
50名以上の事業場に関してはストレスチェックの実施が義務付けられています。厚生労働省のモデル就業規則にも規定例は記載されています。就業規則の規定例を社会保険労務士が分かりやすく解説します。
同一労働同一賃金は社会に対して大きな影響を与えると考えられています。今後求められる対応と就業規則や賃金規程などの規程の見直し方法について社会保険労務士が分かりやすく解説します。
初めて法制化された「パワハラ防止法」について具体的にどのような対処が必要なのか、この機会にハラスメントの基準を確認し、対策への準備をすすめましょう。
外国人雇用に関するトラブルは年々増してきています。その一つの原因に外国人労働者のための就業規則が未整備であることが挙げられます。日本独自の商習慣など、国が違えば常識も変わります。外国人雇用を行う前に整備しておきたい外国人雇用のための就業規則に関して社会保険労務士が分かりやすく解説します。
柔軟な働き方を実現する働き方改革。事務系の仕事では在宅勤務を認める会社も増えてきています。一方、それにともったトラブルも発生しています。雇用の専門家である社会保険労務士が在宅勤務の導入について解説します。

最新セミナー
お役立ちコラム「人事労務のお悩み相談所」